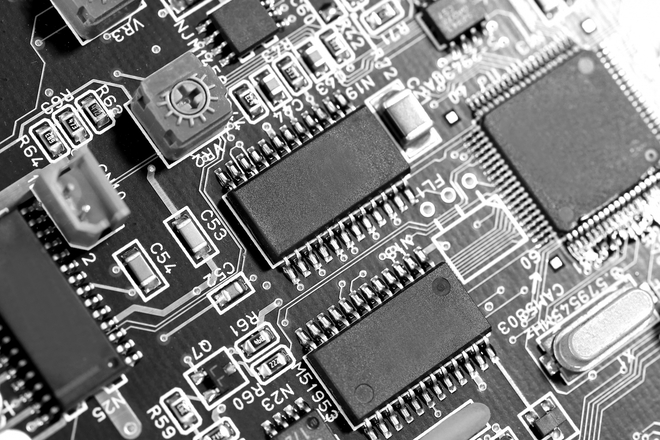設備工事のM&A事例10選|業界動向やメリット・デメリットを徹底解説

自社の事業領域拡大や新規事業への参入を目指し、設備工事会社のM&Aを検討している担当者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、専門性が高い業界のため、「買収候補の企業価値をどう評価すれば良いのか」「技術的なリスクを見抜けるだろうか」といった不安を感じることもあるでしょう。
M&Aは、成功すれば大きなシナジー効果を生み出しますが、そのためには業界への深い理解と、適切なパートナー選びが不可欠です。
この記事では、設備工事業界のM&Aに関する最新の市場動向から、実際のM&A事例、売り手・買い手双方のメリット・デメリットまで詳しく解説します。
さらに、専門外の担当者でも買収候補企業のリスクを見極めるための具体的なチェックポイントも紹介します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
【2025年最新】設備工事業界のM&A事例10選

まずは、近年の設備工事業界でどのようなM&Aが行われているのか、具体的なイメージをつかんでいきましょう。
ここでは、事業承継や事業エリア拡大、新規技術の獲得など、さまざまな目的で行われた最新のM&A事例を10件紹介します。
1. 北陸電気工事株式会社 × 株式会社日建
2023年11月、北陸電気工事株式会社は神奈川県を拠点とする株式会社日建の全株式を取得し、子会社化しました。
北陸電気工事は電気・管工事を中心としたインフラ関連事業を展開する北陸地域基盤の企業で、日建は空調や給排水設備などの管工事に強みを持つ首都圏企業です。
本件M&Aにより、北陸電気工事は関東エリアへの本格進出を果たし、商圏拡大と中期経営計画の目標達成に向けた成長基盤の強化を図っています。
参考:北陸電気工事株式会社『株式取得(子会社化)に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ』
| 譲渡企業 | 株式会社日建 |
| 譲受企業 | 北陸電気工事株式会社 |
| 目的 | 関東エリアへの本格進出と商圏拡大 |
| 概要 | ・北陸地盤の北陸電気工事が、首都圏で管工事に強みを持つ日建を子会社化
・関東エリアでの営業力と施工体制を強化し、中期経営計画の達成を目指す |
2.交換できるくん × 株式会社IMI
2025年6月、住宅設備ECサイトを運営する交換できるくんは、住宅設備保証事業を手がけるIMIの全株式を取得し、子会社化することを発表しました。
このM&Aの目的は、交換できるくんの主力である住宅設備の交換・修理事業に、IMIが持つ保証サービスのノウハウを組み合わせることです。
これにより、住宅設備のライフサイクル全体をカバーする包括的なサービスを提供し、顧客満足度の向上と事業領域の拡大を図ります。
参考:株式会社交換できるくん『交換できるくん、住宅設備保証事業に本格参入』
| 譲渡企業 | 株式会社IMI |
| 譲受企業 | 株式会社交換できるくん |
| 目的 | 住宅設備保証事業への参入と、既存事業とのシナジー創出 |
| 概要 | ・住宅設備ECサイト運営の交換できるくんが、住宅設備保証事業のIMIを子会社化
・交換・修理から保証まで、住宅設備のライフサイクル全体をカバーするサービス体制を構築 |
3. 株式会社四電工 × ベルテック
2021年12月、四国電力グループの四電工は、岡山県で電気設備工事を手がけるベルテックを子会社化しました。このM&Aは、四電工が中期経営指針で掲げる成長戦略の一環です。
ベルテックが岡山・香川地域で築いてきた事業基盤と、在籍する多数の若手技術者を獲得します。
結果、当該エリアでの営業力と施工体制を強化し、収益力の向上を目指すことが可能です。
参考:株式会社四電工『株式会社ベルテックの株式取得(子会社化)に関するお知らせ』
| 譲渡企業 | 株式会社ベルテック |
| 譲受企業 | 株式会社四電工 |
| 目的 | 岡山・香川地域における営業・施工体制の強化 |
| 概要 | ・四国を地盤とする四電工が、岡山県で電気設備工事を手がけるベルテックを子会社化
・ベルテックの持つ地域基盤と若手技術者を活かし、収益力向上を目指す |
4. 株式会社九電工× 中央理化工業
2021年8月、九州を地盤とする総合設備工事会社の九電工は、消防・防災設備の設計・施工・保守を専門とする中央理化工業を子会社化しました。
このM&Aの目的は、九電工グループの事業ポートフォリオに、専門性の高い消防・防災分野を加えることにあります。
中央理化工業が持つ100年以上の歴史で培われた技術力と顧客基盤を活かすことが可能です。
そして、グループ全体のサービス提供能力と企業価値の向上を図ることができます。
参考:福岡証券取引所『中央理化工業株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ』
| 譲渡企業 | 中央理化工業株式会社 |
| 譲受企業 | 株式会社九電工 |
| 目的 | 消防・防災設備分野への事業拡大とグループのサービス強化 |
| 概要 | ・九州最大手の九電工が、100年以上の歴史を持つ消防・防災設備の専門企業である中央理化工業を子会社化
・九電工グループの営業網と技術力を融合させ、事業拡大を図る |
5. 株式会社四電工 × 横山工業
2021年4月、四電工は栃木県で空調・管工事を手がける横山工業の全株式を取得し、子会社化しました。
このM&Aは、四電工の首都圏における事業基盤強化を目的としています。
創業50年を超える歴史を持つ横山工業をグループに迎えることで、首都圏近郊エリアでの営業・施工体制を強化し、総合設備企業としての競争力を高める狙いがあります。
参考:株式会社四電工『横山工業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ』
| 譲渡企業 | 横山工業株式会社 |
| 譲受企業 | 株式会社四電工 |
| 目的 | 首都圏近傍エリアにおける総合設備企業としての収益基盤拡充 |
| 概要 | ・四電工が、栃木県を拠点に空調・管工事を手がける横山工業を子会社化
・首都圏での体制を強化し、総合設備企業としての競争力を高める |
6. 株式会社きんでん× 株式会社フジクラエンジニアリング
2021年6月、電気設備工事大手のきんでんは、フジクラの子会社であるフジクラエンジニアリングの全株式を取得し、子会社化しました。
このM&Aは、再生可能エネルギーや次世代情報通信といった成長市場への対応力強化を目的としています。
両社が持つ技術や経営資源を相互に活用し、社会インフラを支える企業としての持続的な成長と、環境配慮型社会の実現への貢献を目指します。
参考:株式会社きんでん『株式会社フジクラエンジニアリングの株式取得(子会社化)に関するお知らせ』
| 譲渡企業 | 株式会社フジクラエンジニアリング |
| 譲受企業 | 株式会社きんでん |
| 目的 | 再生可能エネルギー、次世代情報通信分野での事業強化 |
| 概要 | ・電気設備工事大手のきんでんが、情報通信やプラント設備に強みを持つフジクラエンジニアリングを子会社化
・両社の技術を融合し、社会インフラ分野での持続的成長を目指す |
7. 燦キャピタルマネージメント × 高山エンジニアリング
2023年6月、投資事業を手がける燦キャピタルマネージメントは、再生可能エネルギー関連の設備工事を行う高山エンジニアリングの株式51%を取得し、子会社化しました。
このM&Aの主な目的は、燦キャピタルマネージメントがクリーンエネルギー分野へ本格的に進出することです。
また、高山エンジニアリングが持つ特定建設業許可を早期に活用することで、事業展開を加速させる狙いもあります。
参考:燦キャピタルマネージメント株式会社『当社による事業会社の株式の一部取得(子会社化)完了、商号変更及び 本店移転に関するお知らせ(開示事項の経過)』
| 譲渡企業 | 高山エンジニアリング株式会社 |
| 譲受企業 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 |
| 目的 | クリーンエネルギー分野への進出および特定建設業許可の取得 |
| 概要 | ・投資事業会社の燦キャピタルマネージメントが、再エネ設備工事を手がける高山エンジニアリングを子会社化
・成長分野への参入と事業ポートフォリオの多角化を図る |
8. 北陸電気工事株式会社 × スカルト
2022年9月、北陸電気工事は福井県を拠点とする総合設備業者のスカルトを子会社化しました。
このM&Aは、北陸電気工事の主力エリアである北陸地域での事業基盤をさらに強固にすることを目的としています。
電気工事から土木、通信工事まで幅広く手がけるスカルトをグループに加えることで、商圏のさらなる拡大と地域内での総合的なサービス提供能力の向上を図っています。
参考:北陸電気工事株式会社『株式取得(子会社化)に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ(株式会社スカルト)』
| 譲渡企業 | 株式会社スカルト |
| 譲受企業 | 北陸電気工事株式会社 |
| 目的 | 北陸地域における商圏のさらなる拡大と事業基盤強化 |
| 概要 | ・北陸電気工事が、福井県を拠点とする総合設備業者のスカルトを子会社化
・主力エリアである北陸での対応力を強化し、グループ全体の企業価値向上を目指す |
9. 中央電機工事株式会社の株式取得に関するお知らせ
LPガスや情報通信サービスなどを展開するTOKAIホールディングスが、電気設備工事を手がける中央電機工事を買収した事例です。
このM&Aは、異業種からの参入により事業の多角化を図る典型的なケースといえます。
TOKAIホールディングスは、既存の生活インフラ関連事業と電気設備工事事業とのシナジーを創出しています。
参考:株式会社TOKAIホールディングス『中央電機工事株式会社の株式取得に関するお知らせ』
| 譲渡企業 | 中央電機工事株式会社 |
| 譲受企業 | 株式会社TOKAIホールディングス |
| 目的 | 総合生活インフラ企業としての事業領域拡大 |
| 概要 | ・LPガスや情報通信などを手掛けるTOKAIホールディングスが、電気設備工事会社を買収
・既存事業とのシナジーを創出し、顧客へより幅広い生活インフラサービスを提供することを目指す |
10. オリックス×株式会社HEXEL Works
金融サービスを主軸に多角的な事業を展開するオリックスが、電気設備工事・保守を行う株式会社HEXEL Works(ヘクセルワークス)を買収しました。
このM&Aの目的は、オリックスグループが展開するビルメンテナンス事業との連携強化にあります。
ヘクセルワークスの専門的な技術力と施工能力をグループ内に取り込むことで、建物管理におけるサービスの品質向上と運営の効率化を図り、不動産関連事業の競争力を高めています。
参考:オリックス株式会社『マンション、米軍関連施設でトップシェアを誇る電気設備工事会社。事業承継を実現し、オリックスと歩む第二創業とは
』
| 譲渡企業 | 株式会社HEXEL Works |
| 譲受企業 | オリックス株式会社 |
| 目的 | ビルメンテナンス事業との連携強化 |
| 概要 | ・多角的な金融サービスを展開するオリックスが、電気設備工事・保守を手がけるヘクセルワークスを買収
・自社グループのビルメンテナンス事業と連携し、建物管理におけるサービス品質の向上と効率化を図る |
設備工事業界のM&Aの現状と市場規模

設備工事業界は2025年現在、堅調な市場成長を背景にM&Aが活発化しており、業界全体の構造変化が進んでいます。
ここでは、業界の基本概要から最新の市場動向まで詳しく解説します。
設備工事とは?4つの主要な工事分野
設備工事は建物や施設に必要なライフラインを構築・維持する専門工事で、主に以下の4つの分野に分類されます。
- 電気設備工事:受変電設備、照明設備、火災報知器などの電気系統全般
- 空調設備工事:空調機器、換気設備、冷暖房システムの設置・メンテナンス
- 給排水設備工事:上下水道配管、衛生設備、消防設備の施工
- ガス設備工事:都市ガス配管、LPガス設備の設置・保守
空調と給排水の工事については同一企業が一括して手掛けるケースが多く、M&Aによる事業統合で大きなシナジー効果が期待できる領域です。
一方、ガス設備工事は各地域のガス供給会社やその関連企業が担当するパターンが一般的となっています。
このように設備工事にはさまざまな分野がありますが、特に電気工事は市場規模も大きく、M&Aが活発な領域です。
電気工事会社のM&Aに特化した動向や成功のポイントについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください。
設備工事業界の市場規模
国土交通省の最新調査(令和7年4月分速報)によれば、設備工事業(主要20社)の受注総額は4,710億円に達し、前年同月比で5.3%の増加となりました。
特に、主要な工事分野である電気工事と管工事は共に堅調な伸びを示しています。この市場の拡大傾向は、M&A市場における設備工事企業の価値評価にも好影響を与えます。
また、年度単位で見ても業界の好調さは続いています。同資料によれば、電気工事業界(主要20社)の令和5年度(2023年度)の受注高は、前年度比14.9%増の2兆2,597億円に達し、4年連続の増加を記録しました。
この継続的な成長は、脱炭素化に向けた省エネ設備の更新需要や企業の積極的な設備投資意欲が背景にあります。
| 工事分野 | 受注高(億円) | 前年同月比増加率 |
| 管工事 | 2,077 | +8.3% |
| 電気工事 | 2,540 | +8.8% |
| 合計 | 4,710 | +5.3% |
参考:国土交通省『設備工事業に係る受注高調査結果(令和7年4月分速報)』
設備工事M&Aの今後の動向
設備工事業界のM&A市場は、以下の3つのトレンドが今後も継続すると予測されます。
大手企業による中小設備工事会社の買収拡大
即戦力となる技術者確保と地域密着型の営業基盤獲得といった二重のメリットを狙った動きが活発化しています。
建設業許可維持に必要な資格保有者を一括して獲得できる点が、長期的な人材育成コストの大幅削減につながっています。
垂直統合型M&Aの増加
電気設備、空調設備、給排水設備など専門分野に特化した工種を統合し、ワンストップサービス体制の構築を目指す企業が増えています。
顧客が複数の業者と個別に契約する煩雑さを解消し、総合的な価値提供が可能になる点が評価されています。
技術獲得型の異業種M&Aが注目
IoT技術やAIを活用したスマート設備への市場需要拡大を受け、ビルディングオートメーションや電気設備のIoT化、空調設備の遠隔監視制御システムなど、従来の設備工事とデジタル技術を組み合わせた事業展開が模索されています。
このような動向は、設備工事と密接に関連するリフォーム業界でも同様に見られます。住宅やビルのリフォームにおいても設備工事は不可欠であり、両業界のM&Aには共通点も多くあります。
関連性の高いリフォーム業界のM&A市場動向にご興味のある方は、こちらの記事もあわせてお読みください。
設備工事業界でM&Aが増加している3つの背景
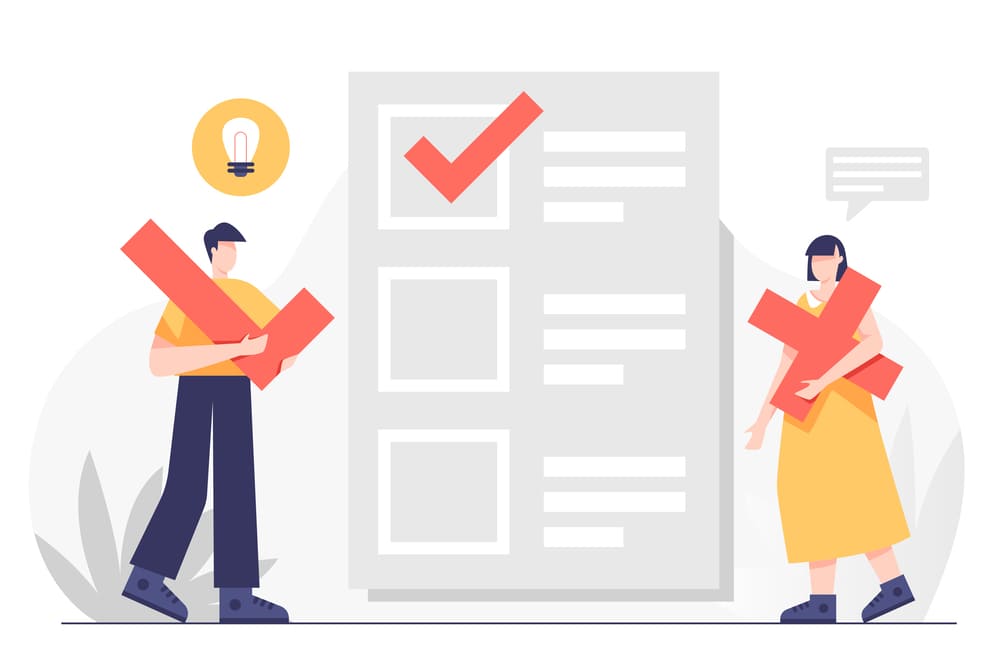
なぜ今、設備工事業界でM&Aが活発化しているのでしょうか。その背景には、個々の企業の事情だけでなく、業界全体が直面する構造的な課題が存在します。
ここでは、M&Aを後押しする3つの主要な背景について掘り下げていきます。
背景①:後継者不足と経営者の高齢化
設備工事業界では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。
2024年11月発表の帝国データバンク調査によると、設備工事業の後継者不在率は60.1%に達しており、業界全体の6割以上の企業で事業承継問題が発生している状況です。
多くの設備工事会社は中小企業であり、創業者やその家族が経営を担ってきましたが、次世代への承継が困難なケースが増加しています。
親族内承継や従業員承継が実現できない場合、M&Aが唯一の選択肢となり、会社の存続と従業員の雇用維持を図る重要な手段として位置づけられています。
特に地方の設備工事会社では、若年層の都市部流出により後継者候補の確保がより困難となっており、M&Aによる事業承継のニーズが高まっています。
背景②:深刻化する人手不足と技術者の採用難
設備工事業界は技術力に依存する業界であり、有資格者や熟練技術者の確保が事業継続の生命線となっています。
しかし、少子高齢化の進行により新規入職者の確保が困難になっており、既存技術者の高齢化も進んでいます。
建設業許可の維持には、電気工事士や管工事施工管理技士などの国家資格保有者の配置が必要ですが、これらの人材確保には長期間の育成期間と高いコストが必要です。
M&Aにより他社を買収することで、即戦力となる技術者と有資格者を一括して獲得できるため、人材不足解消の効果的な手段として活用されています。
また、建設現場のDX化が進む中で、従来の技術に加えてデジタル技術への対応が求められており、多様なスキルを持つ人材の確保がより重要になっています。
背景③:DX化への対応と競争の激化
設備工事業界では、IoT技術やAIを活用したスマート設備への需要拡大により、従来の施工技術に加えてデジタル技術への対応が必要になっています。
経済産業省が指摘する「2025年の崖」問題により、ITシステムの老朽化や人材不足が企業経営に深刻な影響を与える可能性があります。
建設業従事者の6割以上が「2025年の崖」について認識しておらず、約半数の企業が対策を講じていない現状があります。
しかし、2025年度の建設現場DX市場は586億円と推計されており、BIM技術、IoTセンサー、AI活用による現場管理の効率化が競争優位性の確保に直結します。
大手企業との競争激化も背景にあり、中小企業が単独で最新技術への投資や人材育成を行うことは困難です。
M&Aにより技術力のある企業と統合することで、DX化への対応力を短期間で向上させることが可能になります。
設備工事会社のM&A売却メリット【売り手視点】

自社を譲渡することは、経営者にとって大きな決断です。
しかし、M&Aは単なる事業の売却ではなく、会社と従業員の未来を守り、経営者自身の新たな人生を切り拓くためのポジティブな選択肢となり得ます。
ここでは、売り手側が得られる5つの主要なメリットを解説します。
後継者問題の解決と事業存続
M&Aの最大のメリットは、後継者不足問題を根本的に解決できることです。設備工事業界の後継者不在率は60.1%に達しており、多くの企業で事業承継が困難な状況となっています。
親族内承継や従業員承継が実現できない場合でも、M&Aにより適切な買い手企業を見つけることで、長年培ってきた事業を存続させることが可能です。
特に地方の設備工事会社では、技術継承や地域密着型の営業ノウハウを次世代に引き継ぐことが地域社会への貢献にもつながります。
廃業による技術の消失を防ぎ、地域インフラの維持に重要な役割を果たすことができます。
大手企業傘下による経営基盤の安定
大手企業の傘下に入ることで、買収先企業の設備や資源を活用できるようになり、経営基盤の安定化を図れます。
買収企業からの資金調達により、経営に難を抱えていても事業基盤を再び安定させることが可能です。
また、新しいノウハウや技術を手に入れることで事業の成長が期待でき、単独では困難だった大型案件への参入や新規事業領域への展開も実現できます。
特に建設DXへの対応や最新設備への投資において、大手企業のリソースを活用できる点は大きなメリットです。
従業員の雇用の維持
M&Aにより、従業員の雇用と取引先との関係を維持できることも重要なメリットです。廃業を選択した場合、従業員は転職を余儀なくされ、長年築いてきた顧客との関係も失われてしまいます。
M&Aでは、買い手企業が既存従業員の雇用を継続するケースが一般的であり、従業員にとっても安定した雇用環境の確保と、大手企業での新たなキャリア形成の機会が得られます。
特に技術者や有資格者は、より大きな組織での活躍機会を得ることができます。
創業者利益の獲得と個人保証からの解放
M&Aによる株式譲渡により、創業者は保有株式の売却対価として創業者利潤を確保でき、引退資金に充当することが可能です。
長年の事業運営に対する対価を適正に評価してもらえることで、経済的な安心感を得ることができます。
また、多くの中小企業では経営者が会社の借入金に対して個人保証を行っていますが、M&Aにより個人保証からの解放も実現できます。
経営者の個人的なリスクを軽減し、老後の生活設計を安定させることが可能です。
長年築いた取引先との関係性の継承
設備工事業界では、地域密着型の営業により長年築いてきた取引先との信頼関係が重要な経営資源となっています。
M&Aにより、これらの貴重な取引先との関係性を買い手企業に継承することで、地域社会への継続的な貢献が可能です。
買い手企業にとっても、既存の顧客基盤を一括して獲得できるメリットがあり、双方にとって価値のある取引となります。
特に地方市場では、新規参入が困難な場合が多く、既存の関係性は非常に高い価値を持ちます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
設備工事会社買収のメリット【買い手視点】

異業種から設備工事業界へ参入する、あるいは既存の事業を強化する上で、M&Aは非常に有効な戦略です。
ゼロから事業を立ち上げるのに比べて、時間、コスト、リスクを大幅に圧縮できます。ここでは、買い手企業が享受できる3つの大きなメリットを見ていきましょう。
事業エリアの拡大と新規顧客の獲得
M&Aによる最も直接的なメリットは、短期間での事業エリア拡大と新規顧客基盤の獲得です。
設備工事業界は地域密着型の営業が重要であり、新規地域への参入には長期間の営業活動と信頼関係の構築が必要です。
例えば、北陸電気工事による株式会社日建の買収では、北陸地域基盤の企業が首都圏市場に本格進出を果たし、商圏拡大を実現しました。
このように、M&Aにより既存の営業基盤を一括して獲得することで、新規エリアでの事業立ち上げコストと時間を大幅に削減できます。
地方から都市部への進出だけでなく、都市部企業による地方市場への参入においても、地域特有の商慣習や取引先ネットワークを理解した企業を買収することで、効率的な市場開拓が可能です。
即戦力となる技術者・有資格者の確保
設備工事業界では、電気工事士や管工事施工管理技士などの国家資格保有者が事業継続の要となっています。
これらの人材育成には数年の期間と高いコストが必要ですが、M&Aにより即戦力となる技術者と有資格者を一括して獲得できます。
建設業許可の維持に必要な資格保有者を確保できることで、長期的な人材育成コストを大幅に削減できる点は大きなメリットです。
また、熟練技術者が持つ専門知識やノウハウは、自社の技術力向上にも寄与します。
特に人手不足が深刻化する現在の市場環境では、優秀な人材を確保することが競争優位性の源泉となっており、M&Aによる人材獲得の戦略的価値は極めて高いものがあります。
隣接業種取り込みによる事業多角化
設備工事業界では、電気設備、空調設備、給排水設備など専門分野に特化した企業が多く存在しますが、M&Aにより隣接業種を取り込むことで事業多角化を実現できます。
垂直統合型M&Aにより、顧客に対してワンストップサービスを提供できる体制を構築することで、複数の業者と個別に契約する顧客の煩雑さを解消し、総合的な価値提供が可能です。
これにより、単価の向上と継続的な受注の確保が期待できます。また、IoT技術やAIを活用したスマート設備への需要拡大を受け、従来の設備工事にデジタル技術を融合させた新たな事業領域への展開も可能です。
技術獲得型の異業種M&Aにより、ビルディングオートメーションや遠隔監視制御システムなどの高付加価値サービスを提供できる体制を構築することができます。
そして、設備工事と親和性の高い代表的な業界がビルメンテナンスです。ビルメンテナンス事業との連携強化を目的としたM&Aは、大きなシナジー効果が期待できます。
ビルメンテナンス業界のM&A動向や、より具体的な連携事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。
設備工事業界M&Aのデメリットと注意点

M&Aには多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。特に、文化や価値観の異なる組織が一つになる過程では、予期せぬ問題が発生する可能性があります。
ここでは、売り手・買い手双方の視点から、事前に把握しておくべきリスクを解説します。
【売り手側】企業文化・経営方針の変更リスク
M&A後に最も懸念されるのが、買い手企業の経営方針による企業文化の変化です。
特に地域密着型の設備工事会社では、長年培ってきた独自の企業風土や価値観が重要な経営資源となっているケースが多くあります。
買い手企業が効率性や収益性を重視する経営スタイルを導入した場合、従来の丁寧な顧客対応や地域社会との結びつきが軽視される可能性があります。
このような変化は、既存顧客との関係悪化や従業員のモチベーション低下を招くリスクがあります。
また、意思決定プロセスの変更により、現場の判断で迅速に対応していた案件が、本社承認を要するようになるなど、業務効率の低下が生じる場合もあります。
売り手企業は、M&A交渉において企業文化の継承について十分に協議し、重要な価値観の維持を条件に含めることが重要です。
【売り手側】従業員の退職・技術流出懸念
M&A発表後に従業員が不安を感じ、退職が相次ぐケースがあります。設備工事業界では、熟練技術者や有資格者の存在が事業価値の核心部分を占めているため、キーパーソンの流出は企業価値の大幅な低下につながります。
特に現場責任者クラスの技術者が競合他社に転職した場合、顧客との関係も同時に失われる可能性があり、売上減少の要因となります。
また、長年蓄積された施工ノウハウや顧客情報などの技術的資産が流出するリスクも考慮する必要があります。
このような事態を防ぐため、M&A発表時には従業員への丁寧な説明と不安解消に努め、キーパーソンに対する処遇改善や継続雇用の確約を買い手企業と事前に協議しておくことが重要です。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
【買い手側】統合コストと管理負担の増加
買収後の統合プロセスには、システム統合、業務標準化、組織再編などで相当なコストと時間が必要です。
設備工事業界では、施工管理システムや顧客管理システムが各社固有のものを使用しているケースが多く、統合作業が複雑化する傾向があります。
また、複数の拠点を持つ企業を買収した場合、管理負担が大幅に増加し、本業に集中できない状況が生じる可能性があります。
地方の設備工事会社では、現地の商慣習や規制に精通した管理者の配置が必要となり、人材確保と育成にも追加コストが発生します。
さらに、買収企業の業績が期待を下回った場合、のれんの減損処理により財務面でのマイナス影響を受けるリスクもあります。
【買い手側】簿外債務・コンプライアンスリスク
設備工事業界では、工事完成保証や労働災害に関する潜在債務、下請業者との未解決の紛争など、財務諸表に表れない簿外債務が存在する可能性があります。
これらの債務が買収後に判明した場合、予想以上の財務負担を強いられることになります。
また、建設業法や労働安全衛生法などの業界特有の法規制に関するコンプライアンス違反が発覚するリスクもあります。
特に下請業者への代金支払い遅延、労働者の安全管理不備、建設業許可の適正な維持管理などに問題がある場合、買収後に行政処分を受ける可能性があります。
これらのリスクを回避するため、M&A実行前にデューデリジェンスを徹底的に実施し、法務・財務・税務面での詳細な調査を行うことが不可欠です。特に設備工事業界に精通した専門家によるチェックが重要です。
設備工事のM&Aを有利に進めるための3つのポイント

設備工事業界のM&Aを成功に導くためには、事前準備から交渉、統合まで戦略的なアプローチが必要です。
業界特性を踏まえた重要なポイントを3つの段階に分けて詳しく解説します。
ポイント①:自社の強みを整理し、企業価値を正しく把握する
M&Aを有利にさせる第一歩は、自社の強みと企業価値を客観的に把握することです。設備工事業界では、売上高や利益だけでは測れない無形資産が企業価値の大部分を占めているケースが多くあります
まずは、自社の強みと弱みを客観的に分析し、企業価値を正しく評価することがスタートラインです。
- 保有する許認可・資格: どのような建設業許可を持っているか? 1級施工管理技士などの有資格者は何名在籍しているか?
- 工事実績と顧客基盤: 公共工事の実績はあるか? 安定した取引を続けている優良顧客はいるか?
- 技術力とノウハウ: 他社にはない独自の技術やノウハウはあるか?
- 財務状況: 収益性や成長性はどうか?
これらの情報を整理し、「自社が買い手にとってどのような魅力を持つのか」を明確にすることが、交渉を有利に進める鍵となります。
ポイント②:M&Aの目的を明確にし、譲れない条件を決める
M&Aの成功には、明確な目的設定と優先順位の決定が不可欠です。
売り手企業は事業承継、従業員の雇用維持、企業文化の継承など、買い手企業は事業拡大、技術力強化、人材確保など、それぞれの目的を明確にし、譲れない条件を事前に整理しておくことが重要です。
売り手企業の主要な検討項目は以下の通りです。
- 従業員の処遇:雇用継続、待遇改善の条件
- 事業の継続性:主要事業の維持、発展方針
- 企業文化の維持:経営方針、品質基準の継承
- 売却価格:企業価値に見合った適正な対価
- 統合後の役割:経営陣の処遇、関与度合い
買い手企業においても、投資回収期間、シナジー効果の実現時期、統合コストの上限など、具体的な成功指標を設定し、M&A後の統合計画を詳細に策定することが成功の要因です。
双方の目的と条件をすり合わせ、Win-Winの関係を構築することで、円滑なM&A実行と統合後の成功を実現しましょう。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ポイント③:実績豊富なM&Aの専門家に相談する
M&Aのプロセスは非常に専門的で、法務、税務、財務など多岐にわたる知識が求められます。自社だけで全てを進めるのは現実的ではありません。
業界の動向に精通し、豊富な実績を持つM&Aの専門家に相談することが、成功への近道です。
専門家は、客観的な視点から企業価値を算定し、最適なパートナー候補を見つけ出し、複雑な交渉を円滑に進めるための力強い味方となります。
設備工事のM&Aは、未来を託すための重要な経営戦略

設備工事業界のM&Aは、単なる事業売却や買収ではなく、業界の未来を形作る重要な経営戦略です。後継者不足、人手不足、DX化への対応といった構造的課題を克服し、持続可能な成長を実現するための有効な手段です。
2025年の市場動向を見ると、設備工事業界は受注高の大幅増加により好調な成長を続けており、M&A市場においても企業価値の向上が期待できる環境が整っています。
大手企業による中小企業の買収、垂直統合型M&A、技術獲得型の異業種M&Aなど、さまざまな形態のM&Aが活発化しており、各企業の戦略に応じた最適な選択肢が広がっています。
しかし、M&Aを成功に導くためには、業界特有の慣行や価値評価を深く理解した、専門的な知見が不可欠です。
そこで私たちM&Aフォースでは、設備工事業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
設備工事会社のM&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)