家具業界のM&A完全ガイド|2025年最新動向と売却相場・事例を徹底解説

家具業界のM&Aは、後継者不在や価格競争の激化、設備投資負担の大きさに悩む家具製造や販売を行う企業の経営者にとって、事業を守りながら次世代につなぐ有効な手段です。
本記事では、家具業界の市場規模や最新動向、事例、売却相場、実際に利用される手法までを詳細に解説します。
家具業界とは

家具業界とは、家具の製造・流通・小売までを含む幅広い産業を指します。住宅やオフィス環境に密接にかかわる産業であり、ライフスタイルの変化や不動産市場の動向によって業績が左右されやすい特徴があります。
例えば、新築住宅の需要増加は家具需要を押し上げ、逆に景気低迷時には大きな打撃を受けやすい構造です。
また、近年ではインテリア性だけでなく、機能性や環境配慮型の商品も重視されています。
サステナブル素材を使用した家具やIoTを取り入れたスマート家具など、新しいトレンドも登場しています。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
家具業界の現状と市場規模

家具業界の現状を把握するには、市場規模や需要動向を理解しておくことが重要です。
国内市場は横ばい傾向が続いており、価格競争の影響で収益性が下がりやすい一方で、EC化の進展や生活スタイルの多様化によって新たな需要が生まれています。
本コラムでは、国内市場の推移、EC化率拡大の影響、コロナ禍による構造変化について解説します。
国内家具市場の推移と現在の規模
株式会社矢野経済研究所における、2022年国内における家庭用・オフィス用家具の調査では、家具市場の規模は 1兆1,330億円 でした。これは前年比103.8%の微増となります。
- 家庭用家具: 7,090億円(前年比103.7%)
- オフィス用家具: 4,240億円(前年比103.9%)
参考:株式会社矢野経済研究所『家庭用・オフィス用家具市場に関する調査を実施(2023年)』
こうした市場の動きは、消費者の動向とも連動しています。内閣府の消費動向調査では、家具を含む耐久消費財に対する消費者の買い替え意欲などが示されており、景気やライフスタイルの変化が市場に与える影響を読み取ることができます。
参考:内閣府『消費動向調査』
また、政府統計の総合窓口であるe-Statの家計調査によれば、一世帯あたりの家具への年間支出金額の推移も確認でき、長期的な需要の変動を把握する上で重要な指標となります。
EC化率の急速な拡大とその影響
大手ECプラットフォームの台頭により、価格の透明性が増し、家具のオンライン販売(EC)市場は成長を続けています。
令和5年度 電子商取引に関する市場調査報告書によれば、生活雑貨・家具・インテリア分野のEC市場規模は2023年時点で2兆4,721億円に達し、EC化率は31.54%と伸長しました。
AR(拡張現実)技術を使って家具を室内に試し置きできるサービスなど、オンラインと相性の良い販売手法が市場の成長を後押ししています。
参考:経済産業省『令和5年度 電子商取引に関する市場調査報告書』
コロナ禍による市場構造の変化
2020年には、新型コロナウイルスの影響による「巣ごもり需要」で家庭用家具の需要が拡大しました。
一方で、オフィスの改装や移転が停滞したため、市場全体としては微減の1兆373億円となりました。
2022年には、在宅勤務の定着など、コロナ禍に対応した住環境の見直し需要が高まり、家庭用・オフィス用ともに市場は回復基調を示しました。
消費者の「居住空間を快適にしたい」という意識は定着しており、今後も在宅需要を取り込む新たな製品開発やサービス展開が求められています。
業界全体としては、市場環境が大きく変わる中でM&Aを活用した事業再編の動きが強まっています。
家具業界の今後の課題|売り手が直面する課題とは

家具業界の企業が直面している課題は多岐にわたり、特に中小企業にとっては経営存続に関わる深刻な問題となっています。
事業承継問題から競争環境の変化まで、売り手企業が抱える主要な課題を詳しく解説します。
後継者不在による事業承継問題
家具業界の多くの企業は、創業から数十年を経ており、代表者の高齢化が進んでいます。
経営者が引退を考える中で、親族や従業員に後継者が見つからず、廃業のリスクが高まっているのが現状です。
中小企業庁の統計によれば、中小企業の約3分の1が後継者未定の状態にあります。後継者不在の主な要因は以下の通りです。
- 子どもの他業種への就職:製造業離れや都市部への人口流出
- 業界の将来性への不安:市場縮小や競争激化への懸念
- 承継準備の不足:計画的な承継準備を行っていない企業が多数
- 経営スキルの複雑化:デジタル化対応など新たなスキルの必要性
なかでも、創業50年を超える家具メーカーでは、創業者の高齢化が進む中、事業の継続方法について早急な決断が求められています。
参考:中小企業庁『中小企業実態基本調査』
大手ECプラットフォームとの価格競争
家具業界の競争環境を厳しくしている最大の要因の一つが、大手ECプラットフォームの存在です。
Amazonや楽天市場などの大手モールでは、大量仕入れによる低コスト販売が可能であり、価格基準が市場全体に影響を与えています。
結果として、中小メーカーは独自のデザインや地域密着型サービスを強みとしなければ生き残りが難しくなりました。価格競争の影響をまとめると以下の通りです。
- 利益率が低下し、販管費や人件費の確保が困難化
- ブランド力が弱い企業は値下げ以外の戦略がなくなる
- 長期的には資金繰りが悪化し、廃業またはM&A検討へ
このように、価格競争は単なる事業戦略の問題ではなく、経営継続を左右する重大なリスクとなっています。
原材料費高騰と人手不足の深刻化
木材や鉄材、布などの家具原材料は、国際的な需給バランスや為替変動によって価格が変動します。
特にウッドショックと呼ばれる木材価格の急騰は、家具メーカーの原価率を大幅に押し上げました。また、人手不足は地方企業に顕著であり、熟練工の高齢化に加え、新規採用の難航が続いています。
この二重苦によって、利益を圧迫される企業が増えています。
設備投資負担と技術革新への対応
家具業界では、生産ラインの効率化や最新のCAD・CAM技術導入、自動化ロボットの採用など、継続的な設備投資が求められています。
しかし、中小企業にとって数千万円規模の投資は資金繰りを圧迫し、成長を阻害します。さらに、持続可能性を重視する市場トレンドに沿い、環境対応型の製品開発を進めるには追加投資が欠かせません。
この結果、成長機会をつかむどころか競争力を喪失する企業もあり、M&Aによって大手企業の技術や設備を活用しようとする動きが加速しています。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
【2025年版】家具業界におけるM&Aの最新動向

ここまで見てきたように、家具業界は後継者問題や価格競争、原材料費高騰など構造的な課題を抱えています。
こうした状況を打開する手段の一つとして、M&Aの活用が広がっています。2025年現在では、大手による積極的な買収から中小企業の事業承継型まで、多様な動きが見られるのが特徴です。
ここでは、家具業界のM&A最新動向を具体的に解説します。
M&A件数の推移と活発化の背景
近年、家具業界におけるM&Aの件数は増加傾向にあります。
この背景には、前述の後継者不足や市場競争の激化に加え、デジタル化への対応やグローバル展開の必要性が高まっていることがあります。
M&Aは、これらの経営課題を迅速に解決するための有効な手段として、多くの企業に認識されています。
| 年 | 主なM&Aの目的 | 背景 |
| 2020-2021年 | EC強化、巣ごもり需要対応 | コロナ禍によるライフスタイルの変化 |
| 2022-2023年 | 事業承継、サプライチェーン強化 | 後継者不足の深刻化、原材料価格の高騰 |
| 2024-2025年(予測) | DX推進、海外展開、ESG対応 | デジタル技術の進化、グローバル競争の激化 |
大手企業による積極的な買収戦略
大手の家具メーカーや小売業者は、シェア拡大や新規分野参入を目的に積極的な買収を行っています。
特に注目されるのは、以下のような動きです。
- 高級家具ブランドの買収によるブランド力強化
- 海外市場展開を目的とした現地企業の買収
- EC事業に強みを持つ企業との統合
大企業がM&Aを主導することで、業界全体の構造再編が進んでおり、中小企業にとっても買収対象としての需要が高まっています。
中小企業の事業承継型M&Aの増加
家具業界の中小企業は、経営者の高齢化と後継者不在という課題を背景に、廃業回避のためM&Aを選択するケースが増えています。
買い手企業が持つ資本力や販路を活用することで、存続と成長を両立できるメリットがあるためです。
地方の家具メーカーや販売会社が、地域内での承継や首都圏の企業との統合によって、新たな成長機会を得る例も増えています。
異業種からの参入動向
2025年現在、家具業界には家電メーカーや不動産関連企業、さらには外資系企業など異業種からの参入が活発化しています。
理由は、以下の通りです。
- 住宅販売やリフォーム事業との親和性が高いため
- ECプラットフォームを持つ企業にとって、家具は販売拡大に有効な商材となるため
- サステナブル需要の拡大に伴い、エコ素材家具を扱う新規事業として注目されているため
異業種参入は競争激化を招く一方で、M&Aによる異業種企業との連携が、新しいビジネスモデルを生み出すきっかけにもなっています。
売り手企業が得られるM&Aのメリット

家具業界の経営者にとって、M&Aは単なる売却手段ではなく、事業の存続と成長を実現する重要な選択肢です。
特に後継者不在や競争激化の状況にある中小企業にとって、M&Aを活用することで事業を次世代につなぎ、従業員や取引先を守れる可能性があります。
ここでは、売り手企業が享受できる主なメリットを紹介します。
事業承継問題の根本的解決
後継者がいない企業にとって、M&Aは事業承継を可能にする最も現実的な方法です。
親族承継や従業員承継では限界がある場合でも、外部の買い手に経営権を引き継ぐことで、事業を継続させる道が開けます。
地域に根差した家具製造技術や取引基盤が途絶えることなく守られる点は、廃業とは大きな違いです。
創業者利益の確保と資金調達
M&Aでは、売却によってまとまった資金を得られるため、創業者利益を確保できます。
これにより、引退後の生活資金を確保できるほか、新規事業や不動産投資など別分野への挑戦も可能です。
さらに、一部株式を売却する形であれば、経営に関与しつつ資金調達を行うといった柔軟な選択もできます。
従業員の雇用継続と待遇改善
廃業の場合、従業員は職を失うリスクに直面します。しかしM&Aを選択すれば、買い手企業が従業員を引き継ぐことが一般的です。
特に資本力を持つ企業による買収では、福利厚生や待遇の改善が期待でき、従業員の将来を守る手段にもなります。
経営者にとっては、従業員を安心させられる点が大きな魅力です。
買い手の経営資源活用による事業拡大
M&Aによって買い手企業の販売網や物流ネットワーク、ブランド力を活用できるため、売り手企業はこれまで以上に事業拡大のチャンスを得られます。
例えば、首都圏の販路に乏しい地方家具メーカーが、大手流通グループに買収された結果、全国展開を実現するケースもあります。
単独で難しかった戦略をスピーディに実現できる点は大きな魅力です。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
家具業界M&Aで活用される主要な手法

家具業界のM&Aには、複数の手法が存在します。代表的なのは「株式譲渡」「事業譲渡」「資本業務提携」の3つであり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
売り手企業がどのような目的でM&Aを実施するかによって、最適な手法を選択する必要があります。
株式譲渡による完全買収
株式譲渡は、企業の発行済株式のすべて、あるいは一部を譲渡することにより、経営権を移転する方式です。
家具業界でも、オーナーが保有する株式を売却して買い手に事業を引き継ぐケースが多く、会社そのものを承継できる点が利点です。
既存の取引先や従業員との契約もそのまま維持されるため、事業継続性が高い形態といえます。
事業譲渡による部分的な売却
事業譲渡は、会社の特定事業や資産のみを譲渡する方式です。
例えば、家具の製造部門は売却するが、小売店舗事業は残すといった柔軟な対応が可能です。
これにより、収益が悪化している部門だけを切り離すことができ、売り手企業の経営リスクを軽減できます。
ただし、契約や従業員の引き継ぎに手続きが必要となるため、株式譲渡に比べて時間とコストがかかる点が課題です。
資本業務提携による戦略的連携
資本業務提携は、株式を一部取得し出資関係を築くと同時に、業務上の協力を行う形態です。
完全に経営を譲渡するわけではないため、売り手企業の独立性を一定程度維持できます。
家具業界においては、製造企業と小売企業が販路拡大を目的に提携するケースや、異業種との提携による商品開発が進んでいます。
各手法のメリット・デメリット比較
以下の表は、代表的な3手法の特徴を整理したものです。参考にしてみてください。
| 手法 | メリット | デメリット | 向いているケース |
| 株式譲渡 | 契約そのまま承継、現場の混乱が少ない | 創業者が完全に経営から離れる | 会社そのものを承継したい場合 |
| 事業譲渡 | 不採算事業のみ切り離せる | 契約移行に手続きコストが増える | 部分売却や選択的承継を希望する場合 |
| 資本業務提携 | 独立性を保ちつつ協力できる | 完全譲渡に比べて経営権移転効果は弱い | 成長資金や販路拡大を狙う場合 |
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
家具業界M&Aの売却相場

家具業界のM&A売却相場は、企業の規模や収益性、保有資産によって大きく異なります。
一般的に中小家具メーカーの場合、売却価格は年間利益(営業利益)の2倍〜5倍程度で算定されるケースが多いとされています。また、不動産やブランド価値を保有している場合、上乗せ評価が行われる場合があります。
【相場に影響する主な要素】
- 年間売上と利益率(収益力)
- 自社ブランド力や技術力
- 保有する不動産や工場、設備の資産価値
- 買い手企業にとってのシナジー効果(販路・商品拡大)
中でも、従業員の熟練技術やデザイン力は大きな付加価値と評価される傾向が強く、同業他社だけでなく異業種企業からも注目されやすい要素です。
家具M&A価格の算定方法
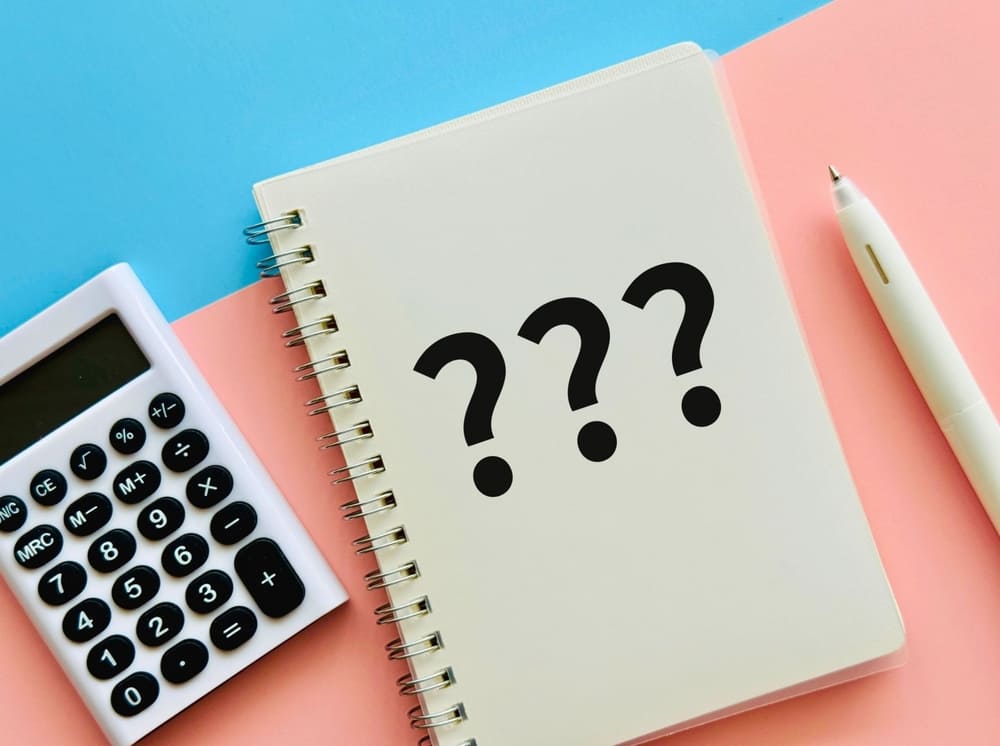
企業価値評価(バリュエーション)には複数のアプローチがあり、対象企業の特性に応じて複数の方法を組み合わせて総合的に判断するのが一般的です。
ここでは、代表的な3つのアプローチについて、その基本的な考え方を解説します。
コストアプローチ
コストアプローチとは、企業が保有している純資産(資産-負債)を基準にして企業価値を評価する方法です。
家具業界の場合、工場、倉庫、土地、設備、在庫などの資産が評価対象になります。
利益が安定していない企業でも算定しやすい点がメリットですが、将来性やブランド力などの無形価値が反映されにくいデメリットがあります。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、将来的に企業が生み出すキャッシュフローを現在価値に割引して評価する方法です。
家具業界では、過去の売上推移や今後の市場成長性、買い手企業とのシナジーを考慮に入れるため、強みを持つ会社では高い評価が付きやすい算定方法です。
ただし、予測精度が重要となり、業績変動の大きな企業では算定が難しくなる場合もあります。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、同業他社のM&A事例や株式市場における類似企業の株価をもとに、自社の価値を評価する方法です。
家具業界でも、過去の家具メーカーや販売会社の売却実績をベースに参考値が算出されます。
市場の実態に即している点が強みですが、直近に類似事例がないと活用が難しくなることもあります。
家具業界の代表的なM&A事例

家具業界では、中小企業の事業承継型M&Aから、大手企業による成長戦略としての買収まで多様な事例が見られます。
ここでは、代表的な4つの類型に分けて代表的なM&A事例を紹介します。
製造業者同士の統合事例
(事例)カリモク家具 × 旭川家具メーカーとの提携・協業強化
国内大手のカリモク家具は、北海道旭川地区の家具メーカーと包括的な連携を進め、製品ラインアップ拡充や物流効率の改善を図っています。
これはM&Aによる統合というよりも、業務提携に近い形ですが、地域産業の存続や販路拡大を目的とした重要な取り組みです。
地方メーカーの事業承継を補完する動きとして注目を集めています。
| 事例概要 | 内容 |
| 売り手/協業側 | 北海道旭川地区の家具メーカー |
| 買い手/連携側 | カリモク家具株式会社 |
| 目的 | 製品ライン拡充、地域産業振興 |
| ポイント | 業務提携を通じて、将来のM&Aに発展する可能性を持つ戦略的関係 |
参考:カリモク家具株式会社『プレスリリース』
小売・ECプラットフォームによる買収事例
(事例)島忠とニトリホールディングスによる買収
2020年には家具小売大手「島忠」を巡って、ニトリホールディングスとDCMホールディングスが争奪戦を繰り広げ、最終的にニトリが島忠を子会社化しました。
総合的な売上規模拡大とホームセンター業態とのシナジー創出を目的とした事例であり、日本の家具業界における大型M&Aの代表例です。
| 事例概要 | 内容 |
| 売り手 | 島忠株式会社 |
| 買い手 | 株式会社ニトリホールディングス |
| 目的 | 小売網の拡大、ホームセンターとのシナジー強化 |
| ポイント | 業界最大級の買収案件となり、規模の経済を重視した統合 |
参考:ニトリホールディングス『株式会社島忠(8184)に対する公開買付けの開始 及び 同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ』
異業種からの参入事例
(事例)良品計画(無印良品)によるリノベーション・家具関連事業強化
無印良品を展開する良品計画は、家具販売に加えてリノベーションや不動産分野に進出しており、関連会社との資本提携を進めています。
異業種連携によって、家具だけでなく住空間全体をトータルで提供する戦略の一環と位置付けられます。
M&Aというよりも資本業務提携型の事例ですが、今後の業界再編を示唆する動きです。
| 事例概要 | 内容 |
| 売り手 | リノベーション関連企業 |
| 買い手 | 株式会社良品計画 |
| 目的 | 家具と住生活サービスを統合した新しい事業展開 |
| ポイント | 異業種融合で多角化を図り、家具販売の付加価値を高める |
参考:Airbnb Japan株式会社『良品計画とAirbnb、包括連携協定を締結』
海外展開を目的とした事例
(事例)IDC大塚家具と中国企業グループによる資本業務提携
大塚家具は中国資本と連携し、アジア市場への展開を進めています。
国内市場が縮小する中、海外マーケットでの成長を狙った動きで、中国の販路や購買層の取り込みを目指しています。
国内市場の競争激化に対応するため、海外展開を強化するM&A事例の一つです。
| 事例概要 | 内容 |
| 売り手/提携側 | IDC大塚家具株式会社 |
| 買い手/提携先 | 中国企業グループ(公式リリースに基づく) |
| 目的 | 中国市場を中心とした海外展開 |
| ポイント | 国内需要減少に対応し、海外販路拡大を狙った国際的な取り組み |
参考:IDC大塚家具株式会社『大塚家具 中国市場への参入の一環として北京国際家居展に出展 提携先獲得へ』
家具業界M&Aで押さえるべき重要なポイント

家具業界でM&Aを成功させるには、単に買い手が見つかればよいわけではありません。
売却価格や条件設定だけでなく、売却のタイミングや企業価値を高めるための準備、買い手企業との相性、従業員への対応が大きく影響します。
この章では、M&Aを進める際に注意すべき重要なポイントを解説します。
売却タイミング
M&Aでは売却のタイミングが結果を大きく左右します。
家具業界は景気や住宅市場の影響を受けやすいため、好景気で需要が高まり、業績が安定している時期に交渉を始めるのが理想です。
逆に赤字や需要低迷のタイミングで売却を急ぐと不利な条件で取引が成立するリスクが高まります。
数年先を見据え、余裕を持って準備を始めることが重要です。
企業価値向上のための事前準備
高い売却価格を得るためには、M&A交渉前に財務基盤や経営体制を整える準備が欠かせません。
具体的には以下の取り組みが有効です。
- 不要な在庫や不採算事業の整理
- 財務諸表の透明性確保(粉飾や不明瞭な会計の改善)
- 新規顧客や販路開拓による売上基盤の強化
- 主力製品や技術の競争力を高める施策
これらにより、買い手から見た企業の魅力が増し、交渉が有利に働く可能性があります。
買い手企業との相性評価
M&Aが成立しても、買い手と売り手の経営方針に大きな隔たりがあると、従業員や取引先に不安が生じます。
そのため、価格条件だけでなく経営理念や事業方針がどの程度一致するかを見極めることが重要です。
特に家具業界では、地域に根差したブランドや製造スタイルの違いがあるため、買い手がそれを受け入れられるかどうかが成功の鍵となります。
従業員への配慮と情報管理
M&Aの過程で従業員への説明や情報開示を誤ると、不安から離職につながる可能性があります。
従業員は家具製造や販売のノウハウを担う重要な戦力であり、その流出は企業価値を下げる要因となります。
そのため、交渉段階では情報管理を徹底し、正式契約後に適切なタイミングで従業員に説明することが不可欠です。
従業員の雇用維持や待遇改善が見込まれる場合には、それを丁寧に伝えることで信頼を維持できます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
家具業界M&Aの主な専門相談先

家具業界でM&Aを進める際には、自社だけで判断するのではなく、専門的な知識と経験を持つ外部機関に相談することが不可欠です。
M&Aは法務・税務・財務・人事など幅広い領域をカバーする必要があり、適切なパートナーを選ぶことで成功に近づきます。
ここでは、家具業界の経営者が利用しやすい代表的な相談先を解説します。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、売り手と買い手をマッチングし、条件交渉から契約成立までを全面的にサポートします。
家具業界は地域に根差した中小企業が多く、業界特化型の仲介会社の存在も増えています。
仲介会社を利用するメリットは、幅広い買い手候補にアクセスできる点と、専門的な価格査定やスキーム設計を任せられる点です。
一方で、仲介手数料が発生するため、費用と効果のバランスを見極める必要があります。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
金融機関
銀行や信用金庫などの金融機関も、M&A相談の重要な窓口です。
長年にわたり地元企業と関係を築いてきた金融機関は、売り手企業と同地域の買い手候補を把握している場合が多く、信頼性の高いマッチングが期待できます。
また融資や資金繰りの相談と合わせて進められる点も特徴です。
ただし、金融機関がM&Aの専門家として関与する範囲は限定的なため、詳細なスキーム構築や交渉は別途専門家の協力が必要になります。
顧問税理士・公認会計士
顧問税理士や公認会計士は、財務状況の整理から企業価値算定、税務対策まで幅広いサポートを担います。
家具業界の企業は在庫資産や設備投資が多く、こうした資産評価の妥当性を確認することが売却価格に直結するため、税理士・会計士の知見は不可欠です。
M&A後の税務リスク軽減やオーナーの相続対策など、中長期的な視点でのアドバイスが期待できます。
財務数値に基づく客観的な判断を得たい場合には最適な相談先です。
事業承継・引継ぎ支援センター
中小企業庁が各都道府県に設置している「事業承継・引継ぎ支援センター」も心強い窓口です。
公的機関が運営しているため、初期相談は無料で受けられ、専門家による基本的な助言やマッチング支援を提供しています。
家具業界で後継者不足に悩む経営者にとって、民間仲介会社に依頼する前のファーストステップとして有効です。
ただし、仲介業務を直接担うわけではなく、あくまでサポートや助言が中心となる点は理解しておく必要があります。
家具業界M&Aで企業価値を高めよう

後継者不在や競争激化、原材料高騰など、家具業界が抱える課題は深刻化しており、M&Aは事業存続や販路拡大を実現する有効な手段です。
株式譲渡や事業譲渡といった手法があり、早期から財務改善などの準備を進め、適切なタイミングで実行することで企業価値を高められます。
M&Aは事業の「終わり」ではなく、新たな成長への「始まり」です。
専門家の支援を受けながら自社に最適なM&Aを検討し、厳しい市場を乗り越える競争力を手に入れましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










