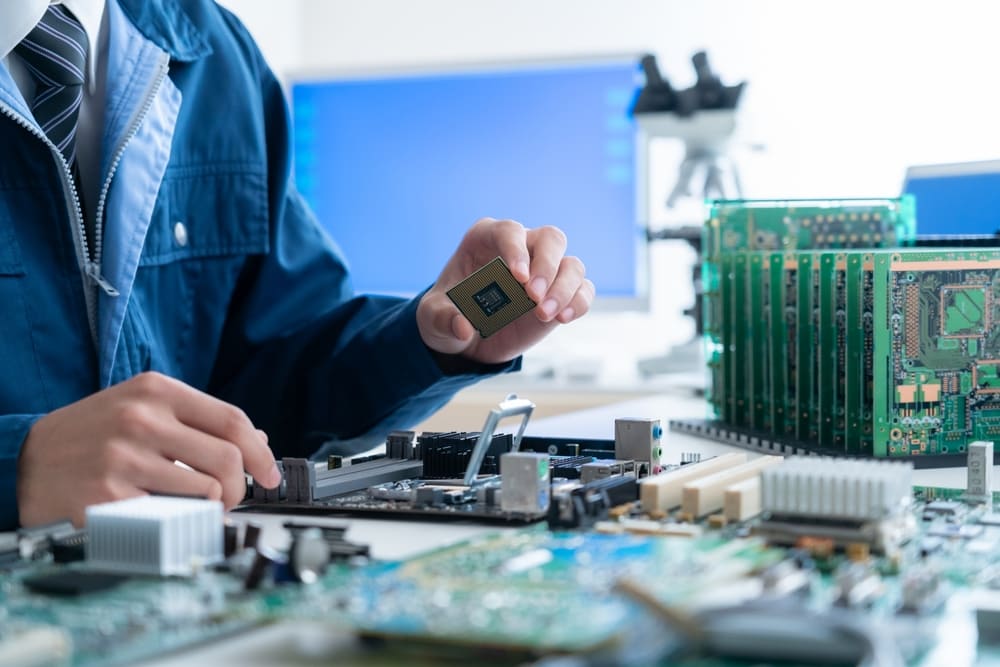温泉施設のM&A|最新動向と成功のポイント・メリットと事例を徹底解説

温泉施設のM&Aは、後継者不足や施設の老朽化、そして変化する観光需要といった課題に直面する業界において、事業承継や新たな成長戦略を実現する有効な手段として注目されています。
現在、この流れを背景にM&Aは一層活発化していますが、その一方で温泉・温浴施設ならではの特有の留意点も多く、成功には正しい知識と準備が欠かせません。
本記事では、2025年最新の市場動向を踏まえつつ、売り手・買い手それぞれのメリットとデメリット、目的別に参考となる事例7選、そしてM&Aを成功に導くための5つの重要ポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説していきます。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
温泉・温浴施設業界の現状と市場動向

温泉施設のM&Aを検討する場合、まずは業界全体の現状と市場の動きを正しく理解することが不可欠です。
ここでは、温泉施設の基本的なビジネスモデルから近年のトレンド、市場動向を解説します。
温泉施設とは?主なビジネスモデルと業界の特色
温泉施設とは、温泉法で定められた温泉を利用した公衆浴場や宿泊施設などを指します。
そのビジネスモデルは、大きく2つのタイプに分けられます。
- 宿泊型施設(旅館・ホテル)
宿泊サービスを主軸とし、温泉入浴に加えて食事や宴会・リラクゼーションなどを提供します。客単価が高く、観光地としてのブランド力が収益を大きく左右するのが特徴です。 - 日帰り型施設(スーパー銭湯・健康ランドなど)
入浴をメインサービスとし、食事処や休憩スペース・マッサージなどを併設して滞在時間を延ばす工夫をしています。地域住民の日常的な利用が多く、リピーターの確保が経営の鍵となります。
また、温泉施設業界は、地域経済への貢献度が高く、多額の初期投資が必要な装置産業であるという特色も持っています。
温泉市場はコロナ禍から回復し新たなトレンドを生み出している
新型コロナウイルスの影響で一時的に大きな打撃を受けた温泉・温浴施設業界ですが、現在は国内旅行需要の回復や行動制限の緩和により、市場は回復基調にあります。
特に、円安を背景としたインバウンド(訪日外国人観光客)の急増は、観光地の温泉施設にとって大きな追い風となっています。日本の温泉文化は海外でも人気が高く、インバウンド需要の取り込みが今後の成長の重要な要素です。
さらに、近年では以下のような新たなトレンドも生まれています。
- サウナブームの高まり
若者を中心に巻き起こったサウナブームにより、本格的なロウリュサウナや充実した外気浴スペース(ととのいスペース)などを導入し、施設の付加価値を高める動きが活発です。 - 多様なニーズへの対応
ワーケーションやグランピングといった新しい旅のスタイルと温泉を組み合わせたサービスも登場し、顧客層の拡大が進んでいます。
施設の老朽化・後継者不足などの業界課題からM&Aが加速
市場が回復し、新たなトレンドが生まれる一方で、温泉・温浴施設業界は構造的な課題を数多く抱えています。そして、これらの課題こそがM&Aを加速させる主な要因となっています。
- 施設の老朽化と修繕費の増大:
高度経済成長期に建てられた施設が多く、築数十年が経過し、大規模な修繕や改修が必要な時期を迎えていますが、多額の投資が経営の大きな負担となっています。 - 後継者不足と経営者の高齢化:
経営者の高齢化が進む中、子どもや親族に事業を引き継ぐ親族内承継が困難なケースが増加しています。長年地域で愛されてきた施設であっても、後継者が見つからず廃業の危機に瀕する例は少なくありません。 - 人手不足と労働環境:
少子高齢化により、全産業で人手不足が深刻化していますが、特に宿泊業はその傾向が顕著です。従業員の確保・定着のためには、労働環境の改善やDX化が急務です。 - 燃料費の高騰:
温泉を維持するための燃料費(ガス・重油など)は、近年の世界情勢の影響で高騰を続けています。コスト増加分を価格に転嫁することが難しく、収益を圧迫する大きな要因となっています。
これらの課題は個々の経営努力だけでは解決が難しく、M&Aによる事業の再編や承継が有効な解決策として注目されています。
温泉業界におけるM&Aの最新動向

業界特有の課題を背景に、温泉・温浴施設業界ではM&Aが活発に行われています。その動向は、単なる後継者問題の解決策に留まらず、企業の成長戦略としても重要な位置を占めるようになっています。
ここでは、近年の主要な3つのトレンドを解説します。
事業承継を目的としたM&Aの増加
最も顕著なトレンドが、後継者不在に悩む中小規模の施設オーナーが、第三者へ事業を譲渡する事業承継型M&Aです。
これまで大切に育ててきた事業や屋号、そして従業員の雇用を守りたいという思いから、廃業ではなくM&Aを選択する経営者が増えています。
買い手にとっても、地域に根差したブランドや固定客を持つ優良な施設を引き継げるメリットがあり、双方のニーズが合致しやすいのが特徴です。
特に、地方の歴史ある老舗旅館などがこの形で存続するケースが目立っています。
大手ホテルチェーンや異業種による事業拡大を目的としたM&A
大手資本によるM&Aも活発です。買い手の目的は主に事業の拡大や多角化にあります。
- 大手ホテルチェーン
全国展開を加速させるため、あるいは「高級旅館」「湯治宿」「カジュアルなリゾートホテル」といった異なる価格帯やコンセプトの施設をポートフォリオに加えるため、戦略的にM&Aを活用しています。ゼロから施設を建設するよりもスピーディーに事業を拡大できる点が大きな魅力です。 - 異業種からの参入
不動産会社やIT企業、飲食業など、これまで温泉事業と直接的な関わりのなかった企業による参入も増えています。地域創生への貢献や、自社の既存事業(例:不動産開発ノウハウ・Webマーケティング技術)とのシナジー効果を狙った動きであり、業界に新たな風を吹き込んでいます。
インバウンド需要を見据えた外資系ファンドによる買収
日本の「温泉(ONSEN)」文化は、国際的にも高いブランド価値を持っています。円安も追い風となり、日本の温泉施設は海外の投資ファンドにとって非常に魅力的な投資対象となっています。
これらのファンドは、将来性の高い日本の観光資源に投資し、大規模なリノベーションや運営の効率化によって施設の価値を最大限まで高めた後、再売却することで利益を得ることを目的としています。
特に、国際的な知名度が高い観光地の大型施設が主なターゲットとなっており、今後もこの買収の動きは続くと予想されます。
温泉M&Aのメリット【売り手・買い手別】

M&Aは、売り手と買い手の双方にとって、単なる事業の売買に留まらない多くのメリットをもたらす戦略的な選択肢です。それぞれの立場から、具体的にどのような利点があるのかを見ていきましょう。
売り手のメリット
後継者不足や経営の将来に不安を抱えるオーナーにとって、M&Aは事業と関係者の未来を守るための有効な手段となります。主なメリットは以下の通りです。
- 後継者問題の解決と事業の存続:
後継者がいない場合でも、意欲のある第三者に事業を引き継いでもらうことで、長年守ってきた屋号や地域での役割を未来へつなげられます。廃業というつらい選択を避けられる点は、経営者にとって最大のメリットと言えるでしょう。 - 従業員の雇用の維持:
廃業すれば従業員は職を失ってしまいますが、M&Aであれば、新たなオーナーのもとで雇用が継続される可能性が非常に高まります。大切な従業員の生活を守れることは、経営者にとって大きな安心材料となります。 - 創業者利益の獲得と個人保証の解除:
事業を現金化することで、オーナーはリタイア後の生活資金や新たな事業への投資資金となる「創業者利益」を確保できます。また、多くの場合、金融機関からの借入金に対する経営者の個人保証からも解放され、長年の経営の重圧から解放されます。 - 施設の維持・活性化:
自社の資金力だけでは難しかった大規模な修繕やリニューアルも、資金力のある買い手の傘下に入れば実現可能です。これにより、施設の魅力が向上し、さらなる発展が期待できます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
買い手のメリット
新規参入や事業拡大を目指す企業にとって、M&Aは時間とコストを大幅に削減できる、極めて効率的な成長戦略です。
- スピーディーな事業展開:
土地の確保や煩雑な許認可(特に温泉権の取得)の手続き、施設の建設などをゼロから行う必要がなく、買収後すぐに事業を開始・拡大できます。市場の変化に迅速に対応できる点は、競争上の大きな強みです。 - 有形・無形資産の一括承継:
土地や建物といった有形資産だけでなく、長年の運営で培われたオペレーションノウハウ、熟練した従業員、地域でのブランドイメージ、そして何より大切な常連客といった価値ある無形資産をまとめて引き継ぐことが可能です。 - 既存事業とのシナジー効果(相乗効果):
例えば、旅行会社が温泉旅館を買収すれば、自社のツアーに組み込むことで安定した集客が見込めます。また、Webマーケティングに強い企業が運営ノウハウを提供することで集客力を向上させるなど、双方の強みを活かした相乗効果が期待できます。 - 新規参入リスクの低減:
すでに運営実績と顧客基盤のある施設を引き継ぐため、全くのゼロから事業を立ち上げる場合に比べて、集客や運営面での失敗リスクを大幅に抑えられます。
温泉M&Aのデメリットと注意点【売り手・買い手別】

M&Aは多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべきリスクも存在します。事前にこれらを理解し、対策を講じておくことが、M&Aを成功させるための重要な鍵となります。
売り手のデメリット・注意点
希望通りの条件でM&Aを成立させ、円満な形で事業を引き継ぐためには、いくつかの注意点があります。特に、従業員や取引先への配慮は非常に重要です。
- 希望価格で売却できない可能性がある:
施設の老朽化が激しい場合や収益性が低い場合、期待していた価格での売却が難しいことがあります。 - 従業員の離職リスク:
経営者が変わることへの不安から、長年勤めてくれた従業員が離職してしまう可能性があります。 - 情報漏洩による事業価値の低下:
M&Aの交渉が外部に漏れると、従業員の動揺や取引先の不安を招き、事業価値が損なわれる恐れがあります。 - 最適な相手が見つからない:
自社の文化や従業員を大切にしてくれるような、理念の合う買い手企業がすぐに見つかるとは限りません。
買い手のデメリット・注意点
買い手側は、主に財務面や組織統合に関するリスクを想定しておく必要があります。事前の徹底した調査が何よりも重要です。
- 簿外債務のリスク:
決算書には表れない未払いの残業代や訴訟リスクなど、予期せぬ負債を引き継いでしまう可能性があります。 - 想定以上の修繕・投資費用:
事前の調査では分からなかった建物の欠陥や設備の不具合が見つかり、多額の追加投資が必要になることがあります。 - 従業員との関係構築:
新しい経営方針に対して従業員の理解が得られず、反発を招いたり、キーパーソンが離職してしまったりするリスクがあります。 - 既存顧客の離反:
経営者が変わったことで、これまで施設を支えてきた常連客が離れてしまう可能性があります。
【目的別】温泉・温浴施設のM&A・事業承継の事例7選

理論だけでなく、実際の事例を知ることはM&Aを検討する上で非常に重要です。
ここでは、M&Aの「目的」に焦点を当て、参考となる7つの成功事例を紹介します。
【事業承継】ビジョンが後継者不在の「こしかの温泉」を子会社化し事業を継続
- 買い手:株式会社ビジョン(グローバルWiFi事業など)
- 売り手:株式会社こしかの温泉
100年以上の歴史を持つ鹿児島県の「こしかの温泉」は、後継者不在という課題を抱えていました。そこで、2021年、地方創生事業に力を入れるビジョン社が完全子会社化により事業を継承しました。
歴史ある温泉宿のブランドと従業員の雇用を守りつつ、ビジョン社が持つWebマーケティングやDX(デジタルトランスフォーメーション)のノウハウを活かし、施設の新たな価値創造と活性化を目指しています。後継者問題に悩む地方の老舗施設にとって、代表的な成功モデルの一つです。
(情報引用元:株式会社ビジョン「こしかの温泉株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」)
【事業拡大】穴吹興産が「祖谷温泉」「祖谷渓温泉観光」をM&Aし観光事業を強化
- 買い手:穴吹興産株式会社(不動産事業)
- 売り手:有限会社祖谷温泉・祖谷渓温泉観光株式会社
西日本を中心に不動産事業を展開する穴吹興産は、観光事業の強化を目的として、徳島県の名勝・祖谷渓にある「祖谷温泉」などを子会社化しました。これにより、同エリアでの観光事業におけるドミナント(地域集中)戦略を加速させました。
不動産開発で培ったノウハウを施設の価値向上に活かし、グループ全体の事業ポートフォリオを拡充する狙いがあります。
(情報引用元:穴吹興産株式会社「祖谷渓温泉観光株式会社」「有限会社祖谷温泉」の株式譲受(子会社化)に関するお知らせ)
【グループ強化】極楽湯HDが温浴事業を手掛ける「エオネックス」「利水社」を子会社化
- 買い手:株式会社極楽湯ホールディングス(温浴施設運営大手)
- 売り手:株式会社エオネックス・株式会社利水社(温浴施設運営)
温浴施設の運営で国内最大手の極楽湯ホールディングスは、同業であるエオネックスと利水社を子会社化しました。これは、同業他社を買収することで、店舗網を一気に拡大し、市場におけるシェアをさらに高めるための戦略です。
規模の経済性を活かし、仕入れコストの削減や人材交流による運営ノウハウの向上など、グループ全体の経営効率化を図っています。
(情報引用元:株式会社利水社「親会社変更に関するお知らせ」)
【異業種参入】アルファクス・フード・システムが「ナチュラルグリーンパークホテル」の温泉事業を譲受
- 買い手:株式会社アルファクス・フード・システム(飲食店向けシステム開発)
- 売り手:ナチュラルグリーンリゾート株式会社
飲食店向けにオーダーシステムなどを開発するアルファクス・フード・システムは、事業の多角化を目的に、ナチュラルグリーンリゾート株式会社の宿泊部門と天然温泉に関する事業を譲り受けました。
自社開発の配膳AIロボットなどを導入してホテル運営の省人化モデルを構築し、その成功事例を本業に活かすという、強力なシナジー効果を狙った異業種参入の好例です。
(情報引用元:株式会社アルファクス・フード・システム「ホテル運営事業の譲受に関するお知らせ」)
【ブランド再生】大江戸温泉物語が「タラサ志摩ホテル&リゾート」をM&A
- 買い手:大江戸温泉物語グループ株式会社
- 売り手:TSCホリスティック株式会社(タラサ志摩ホテル&リゾート)
全国で温泉リゾートを展開する大江戸温泉物語グループは、三重県のTSCホリスティック株式会社より、同社が所有するタラサ志摩ホテル&リゾートを買収しました。
同社は、既存の施設を買収し、「大江戸温泉物語」ブランドとしてリニューアルオープンさせることで再生を図るビジネスモデルを得意としています。高いブランド力と集客力を活かして施設の収益性を劇的に改善させる、典型的なブランド再生型のM&Aです。
(情報引用元:大江戸温泉物語グループ「当社子会社における事業譲受に係る契約締結のお知らせ」)
【不動産活用】サンフロンティア不動産が「ホテル大佐渡」を買収し再生へ
- 買い手:サンフロンティア不動産株式会社
- 売り手:株式会社ホテル大佐渡
不動産再生事業を手掛けるサンフロンティア不動産は、新潟県佐渡島で自家源泉を持つ温泉宿「ホテル大佐渡」を買収しました。同社は、建物の持つポテンシャルを最大限に引き出す不動産活用のプロフェッショナルです。
温泉という強力なコンテンツを持つ施設の価値を、大規模リニューアルによってさらに高め、収益性を向上させることを目的としています。
自社の専門性を活かして事業価値を高める、不動産業界ならではのM&A戦略です。
(情報引用元:サンフロンティア不動産株式会社「株式会社ホテル大佐渡の株式譲受に関するお知らせ」)
【歴史・ブランドの承継】メモリードが創業300年の「雲仙湯元ホテル」の歴史を継ぐ
- 買い手:株式会社メモリード(冠婚葬祭・ホテル事業など)
- 売り手:株式会社雲仙湯元ホテル
長崎県で創業300年超の歴史を誇る名門「雲仙湯元ホテル」は、後継者不在と施設の老朽化という課題に直面していました。
オーナーは従業員の雇用維持と地域経済への貢献を願い、長崎県内の企業への譲渡を希望します。その想いに応えたのが、同じく長崎に本社を置き、冠婚葬祭事業を中核にホテル・リゾート事業も展開する有力企業のメモリードでした。
同社はホテルの歴史的価値を高く評価し、既存のホテル事業で培った運営ノウハウや集客力を活かして事業を承継しました。
300年の伝統と雇用を守りつつ、新たな発展を目指す、地域を愛する企業同士の理想的なM&Aとなりました。
(情報引用元:事業引き継ぎ支援センター「〈事例3〉雲仙湯元ホテル|第三者承継の事例紹介」)
温泉施設のM&Aを成功に導く5つのポイント

温泉施設のM&Aは、業界特有の専門的な知識が必要であり、成功のためには慎重な準備が欠かせません。
ここでは、M&Aを成功へと導くために特に重要な5つのポイントを解説します。
M&Aの目的を明確にし、具体的な戦略を立てる
まず最初にすべきことは、「なぜM&Aを行うのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、交渉の軸がぶれてしまい、最適な相手を見つけることができません。
- 売り手の場合:後継者不在の解決が最優先か、従業員の雇用維持か、それとも少しでも高い価格での売却を目指すのか。
- 買い手の場合:事業エリアの拡大か、既存事業とのシナジー創出か、あるいは新規事業への足掛かりとしたいのか。
目的によって、どのような相手を探すべきか、どのような条件を優先すべきかが変わってきます。この最初の軸設定が、M&A全体の成否を左右します。
自社の強みと課題を整理し、企業価値を正しく把握する
次に、自社(または買収対象企業)の価値を客観的に評価することが重要です。これは適正な売買価格を算定する土台となります。
評価すべきは、財務諸表に現れる数字だけではありません。温泉施設ならではの「無形の資産」もしっかりと洗い出しましょう。
- 強みの例:源泉かけ流しであること、特定の泉質が持つ効能、眺望の良い露天風呂、地元の食材を活かした料理、長年勤める優秀な料理長や仲居、リピート率の高い顧客基盤、地域でのブランドイメージなど。
- 課題の例:修繕が必要な箇所、耐震基準への対応、特定の従業員に業務が依存している状況など。
これらの強みと課題を整理することで、自社の本当の価値を理解し、交渉を有利に進められます。
「温泉権」や許認可、不動産の権利関係を事前に確認する
これは温泉施設M&Aにおいて最も専門的かつ重要なポイントです。温泉を利用する権利である「温泉権」は、法律上の権利関係が非常に複雑です。
- 温泉権の確認:
温泉権は誰が所有しているのか(自社所有か、借用か)、権利の期限はいつまでか、そして最も重要な「M&Aによって権利の承継が可能か」を必ず確認する必要があります。これを怠ると、買収したのに温泉が使えないという最悪の事態になりかねません。 - 許認可の確認:
旅館業法に基づく営業許可はもちろん、消防法や食品衛生法など、運営に必要な許認可が適正に取得・更新されているかを確認します。 - 不動産の権利関係:
土地や建物の所有権は誰にあるのか、抵当権は設定されていないかなど、不動産の登記情報も詳細に調査します。
これらの法的な確認は専門知識を要するため、必ず弁護士などの専門家のサポートを受けましょう。
自社とのシナジー効果が期待できる最適なパートナーを選定する
M&Aの相手選びは、単に「高く買ってくれる」「安く売ってくれる」という価格だけで決めるべきではありません。事業を譲渡した後、あるいは引き継いだ後に、双方が成長できる関係性を築けるかという視点が不可欠です。
- 企業文化や経営理念への共感:
従業員を大切にする文化や、地域貢献への考え方など、基本的な価値観が近い相手ほど、M&A後の統合はスムーズに進みます。 - 事業上のシナジー:
事例で見たように、買い手の持つWebマーケティング力やホテル運営ノウハウが、売り手の施設の魅力をさらに高めるような、具体的な相乗効果が見込めるかを見極めましょう。
お互いの強みを活かし合えるパートナーこそが、M&Aを真の成功に導きます。
M&A後の統合計画(PMI)まで見据えて準備を進める
M&Aは、株式譲渡や事業譲渡の契約を締結したら終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。
買収後の経営統合プロセスを指す、PMI(Post Merger Integration)の準備を、交渉段階から進めておくことが成功の鍵となります。
- 従業員への丁寧な説明とケア:
経営者が変わることへの不安を払拭し、モチベーションを維持するためのコミュニケーション計画を立てます。 - 運営方針のすり合わせ:
予約システムや経理システム・仕入れ先・サービス内容など、具体的な運営方針をどのように統合していくかを事前にシミュレーションします。
PMIがうまくいかなければ、従業員の大量離職や顧客離れを招き、期待したシナジー効果も得られません。契約前からM&A後の姿を具体的に描いておくことが重要です。
温泉施設のM&A・売却を進める際の一般的な流れ

温泉施設のM&Aは、専門的な知識と慎重な手続きが求められる複雑なプロセスです。
ここでは、専門家への相談から最終的な契約締結までの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:M&A仲介会社など専門家への相談・依頼
M&Aを成功させるためには、豊富な知識と経験を持つ専門家の協力が不可欠です。まずは、M&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)、事業承継に強い金融機関などに相談することから始めます。
この段階で、自社の状況やM&Aの目的、希望条件などを伝え、信頼できるパートナーを選定します。
専門家とは秘密保持契約を結んだ上で相談を進めるため、情報が外部に漏れる心配はありません。
ステップ2:企業価値評価と売却先の探索
相談した専門家が、財務状況や将来性・無形資産などを総合的に分析し、企業の客観的な価値(企業価値)を算定します。この企業価値評価が、売却価格を交渉する上での重要な土台となります。
並行して、売り手の希望条件に基づき、買い手候補となる企業のリストアップ(ロングリスト・ショートリストの作成)が行われます。
この時点では、売り手企業が特定されないよう、匿名化された資料(ノンネームシート)を用いて買い手候補に打診を進めるのが一般的です。
ステップ3:トップ面談と基本合意契約の締結
買い手候補の中から関心を示した企業が見つかると、秘密保持契約を締結した上で行われるのが、より詳細な企業情報を記載した企業概要書(インフォメーション・メモランダム)の開示です。
その後、売り手と買い手の経営者同士が直接会って、経営理念や事業への想い・M&A後のビジョンなどを共有するトップ面談が行われます。
ここで双方の相性を確認し、M&Aを進める意思が固まると、譲渡価格やスケジュール、独占交渉権といった主要な条件を定めた基本合意契約書(MOU/LOI)を締結します。
ステップ4:デューデリジェンス(買収監査)の実施
基本合意後、M&Aのプロセスで最も重要な段階であるデューデリジェンス(DD)が行われます。これは、買い手が弁護士や公認会計士などの専門家チームを組織し、売り手企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセスです。
調査は、財務・税務・法務・事業など多岐にわたります。特に温泉施設の場合は、温泉権の法的な有効性や、施設の老朽化具合、必要な許認可の状況などが厳しくチェックされます。
売り手側は、要求された資料を迅速に提出するなど、デューデリジェンスに誠実に対応することが重要です。
ステップ5:最終契約の締結とクロージング
デューデリジェンスで大きな問題が見つからなければ、その調査結果を踏まえて最終的な条件交渉に進みます。
双方がすべての条件に合意すると、法的拘束力を持つ最終契約書(株式譲渡契約書や事業譲渡契約書など)を締結する流れです。
その後、契約書に定められた日に株式や事業資産の引き渡しと売買代金の決済を実施します。これらの最終的な手続きをクロージングと呼び、これをもってM&Aの一連のプロセスが完了となります。
温泉M&Aの動向とポイントを理解し、自社に最適な選択をしよう

本記事では、温泉・温浴施設業界の現状から、M&Aの最新動向、具体的なメリット・デメリット、成功のポイント、そして事例までを網羅的に解説しました。
後継者不足や施設の老朽化といった深刻な課題を抱える一方で、インバウンド需要の回復という大きなチャンスも到来しています。
このような状況下で、M&Aは事業の存続と成長を実現するための極めて有効な戦略的選択肢です。
しかし、温泉施設のM&Aは専門性が高く、成功のためには信頼できるパートナーの存在が不可欠です。個々の施設の状況やオーナー様の想いは千差万別であり、最適な解決策も一つではありません。
まずは自社の現状を客観的に把握し、将来の可能性を探るためにも、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)