事業承継の流れと策定方法とは|必要書類や手順を徹底解説

中小企業経営者の高齢化が進み、後継者不在による事業継続の困難は大きな社会問題となっています。事業承継は後継者不足の課題を解決する有効な手段の1つです。
一方で「事業承継の流れがわからない」「計画策定が複雑で進められない」などの不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、事業承継の流れを理解し、具体的な計画策定を進めたい経営者の方に向け、実践的な作成手順を9つのステップに分けて詳しく解説します。
適切な事業承継計画の策定を行って、企業価値を維持した円滑な事業承継を実現しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業承継とは

事業承継は経営者が築き上げてきた事業を次世代に引き継ぐ包括的なプロセスです。本章では、事業承継の基本的な考え方について以下の2つの観点から解説します。
- 事業承継の定義
- 事業譲渡との違い
事業承継の定義
事業承継とは、会社の経営権とこれまで培ってきた有形・無形の資産すべてを後継者へ引き継ぐ一連のプロセスを指し、単に会社の代表者が交代することではありません。
具体的には、株式などの「資産」、経営理念や技術・ノウハウの「知的資産」、そして最も重要な「経営権」の3つの要素の円滑な承継が目的です。
近年、経営者の高齢化が深刻化し、後継者が見つからずに廃業を選択する中小企業が増えています。
大切な会社と社員、取引先を守るために、事業承継の事前準備は不可欠です。
事業譲渡と事業承継の違い
| 種類 | 目的 | 範囲 |
| 事業譲渡 | 売却対価の獲得 | 会社の事業の一部または全部 |
| 事業承継 | 会社を継続的に発展させること | 経営権と事業に関わるすべての要素 |
事業譲渡と事業承継は混同されがちですが、その目的と範囲が大きく異なります。
事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を他社に売却する取引を指します。
一方、事業承継は経営権と事業に関わるすべての要素を後継者に引き継ぎ、会社を継続的に発展させることを目的とした取り組みです
事業譲渡では売却対価の獲得が主目的ですが、事業承継では企業理念の継承や社員の雇用維持、取引先との関係継続など、より広範囲な要素を考慮する必要があります。
事業承継の手続きの流れ
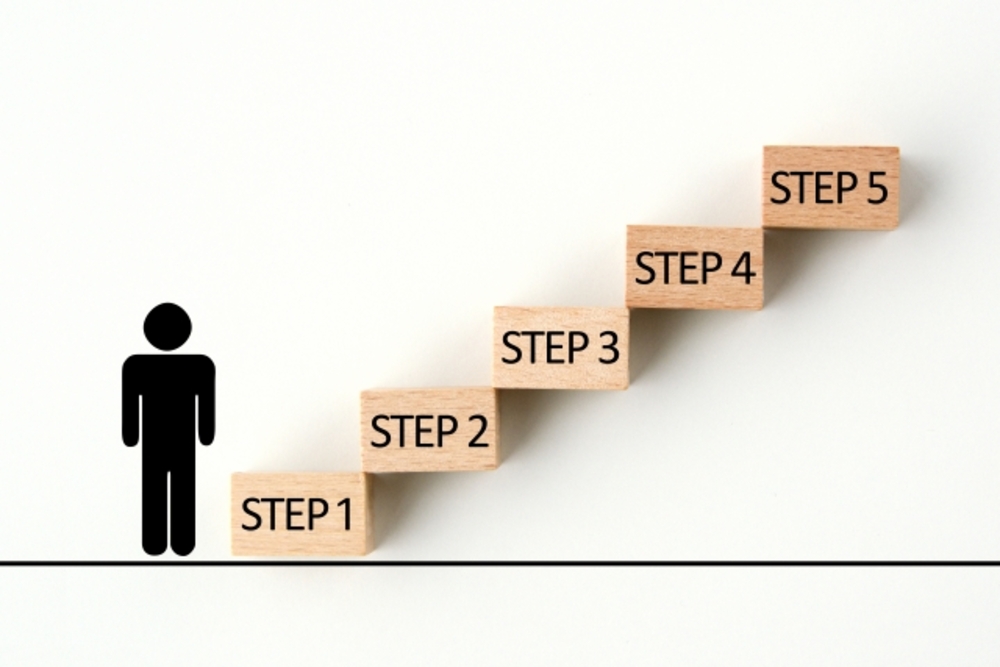
事業承継を具体的に進めるためには、どのようなステップを踏むのでしょうか。
本章では、専門家へ相談してからクロージング(取引の完了)までの一般的な流れを解説します。
- ステップ1:相談
- ステップ2:現状のヒアリングと提案
- ステップ3:契約
- ステップ4:企業概要書の作成
- ステップ5:マッチングトップ面談
- ステップ6:基本合意契約の締結
- ステップ7:買収監査(デューデリジェンス)
- ステップ8:最終契約書の締結
- ステップ9:クロージング(決済)
各ステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:相談
事業承継を考え始めたら、まずは専門家へ相談しましょう。
M&A仲介会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)、税理士、弁護士、あるいは公的機関である事業承継・引継ぎ支援センターなどが主な相談先として挙げられます。
特にM&Aによる第三者への事業売却を検討する場合、豊富な実績と専門知識を持つM&A仲介会社が心強いパートナーです。
相談時は自社の現状や事業承継に対する希望、不安などを率直に伝えることが重要です。
専門家は、ヒアリングした内容を基に、考えられる選択肢や今後の進め方について的確なアドバイスを提供します。
ステップ2:現状のヒアリングと提案
次のステップでは、専門家が会社の詳細なヒアリングを実施します。
- 財務状況
- 事業内容
- 組織体制
- 強みや弱み
など、多角的な視点から会社の現状を深く理解するためです。
ヒアリングに基づき、専門家は企業の価値評価の概算を行い、想定される譲渡価格や最適なM&Aスキーム、考えられる買い手候補のタイプなどを提案します。
経営者はこの提案内容を吟味し、事業承継を本格的に進めるかどうかを判断します。この段階で、自社の市場価値や可能性を客観的に知ることが可能です。
ステップ3:契約
専門家からの提案内容に納得し、M&Aによる事業承継を本格的に進める意思が固まったら、M&A仲介会社などの専門家とアドバイザリー契約、または仲介契約を締結します。
本契約には、提供されるサービスの内容、業務範囲、手数料体系、契約期間などが明記されています。
契約書の内容は専門的で複雑な場合があるため、不明な点は必ず確認し、十分に理解した上での署名が重要です。特に、料金体系は会社によって大きく異なるため注意が必要です。
ステップ4:企業概要書の作成
アドバイザリー契約締結後、M&A仲介会社は譲渡対象企業の詳細な資料を作成します。
まず、企業名を特定されない形に匿名化した「ノンネームシート」を作成し、潜在的な買い手候補に打診します。
ノンネームシートで興味を示した企業とは秘密保持契約(NDA)を締結した上で、より詳細な企業情報が記載された「企業概要書(インフォメーション・メモランダム)」を開示します。
企業概要書は、買い手企業がM&Aを本格的に検討するための重要な判断材料です。自社の魅力が最大限に伝わるよう、正確かつ魅力的な作成が求められます。
ステップ5:マッチング・トップ面談
複数の買い手候補の中から、条件やビジョンが合致する企業を選定し、経営者同士のトップ面談を実施します。
トップ面談はお互いの経営理念や将来のビジョン、企業文化などを直接確認し、信頼関係を築くための非常に重要なプロセスです。
面談では事業への想いや社員の将来など、定性的な側面についても話し合います。
トップ面談を通じて、数字だけでは分からない「相性」を確認し、最終的なパートナー候補を絞り込んでいきます。
ステップ6:基本合意契約の締結
トップ面談を経て、双方のM&Aに対する意思が固まった段階で基本合意書を締結します。
基本合意書には、現時点での譲渡価格やスキーム、今後のスケジュール、独占交渉権の付与、デューデリジェンスへの協力義務などが盛り込まれています。
通常、基本合意書に法的拘束力はありませんが、交渉内容を文書で確認し、その後のプロセスを円滑に進めるための重要な意思確認書としての役割を果たします。
この合意をもって、買い手は本格的な買収調査であるデューデリジェンスへと進みます。
ステップ7:買収監査(デューデリジェンス)
基本合意締結後、買い手企業は弁護士や公認会計士などの専門家を起用し、売り手企業に対して詳細調査(デューデリジェンス)を実施します。
調査範囲は、財務、税務、法務、人事、事業、ITなど多岐にわたります。
デューデリジェンスの目的は、これまでの交渉で提示された情報に誤りがないかを確認し、帳簿に現れない「簿外債務」や「偶発債務」などの潜在的リスクを洗い出すことです。
売り手側は、要求された資料を迅速かつ正確に提出し、誠実な対応を心がけましょう。
ステップ8:最終契約書の締結
交渉がまとまれば、M&Aの最終的な合意内容を記した「最終契約書(DA)」を締結します。
株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」、事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」を締結します。
最終契約書に記載されるのは、以下の内容です。
- 取引の前提条件
- 譲渡価格
- 支払方法
- 双方の表明保証
- 遵守事項
- 解除条件
最終契約書は、法的効力のある正式な契約書で、取引の詳細な内容が記載されています。
専門家によるリーガルチェックを受け、内容を十分に理解した上で契約締結しましょう。
ステップ9:クロージング(決済)
最終契約書で定められた条件がすべて満たされた後、株式の引き渡しと譲渡代金の決済を行う「クロージング」を実施します。具体的には、売り手は株券や印鑑証明書などを引き渡し、買い手は対価を支払う流れです。
また、クロージングと同時に株主名簿の書き換えや役員変更の登記申請など、経営権の移転に必要な法的手続きも行われます。
クロージングをもって、M&Aの手続きは法的に完了し、会社の経営権は正式に買い手へと移転します。
【承継方法別】事業承継の手続きと必要書類

事業承継の手続きや必要書類は、誰に事業を引き継ぐかによって異なります。本章では、承継方法別の具体的な手続きについて解説します。
- 親族内承継の手続きと書類
- 社員承継の具体的な流れ
- M&A承継における契約関係
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
親族内承継の手続き
親族内承継は、経営者の子どもなどの親族に事業を引き継ぐ方法です。
主に「相続」または「生前贈与」によって経営権の要である自社株式を後継者に集中させます。相続の場合は、他の相続人とのトラブルを避けるため、後継者に株式を集中させる旨を明記した「遺言書」の作成が不可欠です。
遺言書がないと、株式が法定相続分に応じて分散し、経営が不安定になるリスクがあります。
生前贈与の場合は、「贈与契約書」を作成し、計画的に株式を移転していきます。どちらの場合も、後継者の税負担を考慮した対策が重要です。
| 必要書類: 遺言書、贈与契約書、遺産分割協議書など |
社員承継の手続き
役員や社員に事業を引き継ぐ場合、後継者が経営者から株式を買い取ることが一般的です。
多くの非上場会社では株式に譲渡制限が付いているため、会社法に基づき、株主総会または取締役会での「株式譲渡承認請求」と「承認決議」の手続きが必要です。
その後、現経営者と後継者の間で「株式譲渡契約書」を締結し、株式の対価を支払います。
手続き完了後は、会社に対して「株主名簿書換請求」を行い、株主名簿の更新により、後継者が正式な株主として認められます。
| 必要書類: 株式譲渡承認請求書、株主総会議事録、株式譲渡契約書、株主名簿書換請求書など |
M&A承継の手続き
M&Aによる第三者への承継では、買い手企業との間でさまざまな契約書や書類の取り交わしが必要です。
まず、本格的な交渉に入る前に、情報漏洩を防ぐための秘密保持契約書(NDA)を締結します。交渉が進み、大筋で条件が合意されると、独占交渉権などを定めた基本合意書(LOI)を結びます。
買収監査(デューデリジェンス)を経て、最終的な条件が固まったら、法的な拘束力を持つ最終契約書(株式譲渡契約書など)を締結し、取引は完了です。
| 必要書類: 秘密保持契約書、基本合意書、株式譲渡契約書(または事業譲渡契約書など) |
承継方法共通で必要な手続き
承継方法にかかわらず、法人の場合は経営者の交代に伴い、法務局で役員変更の登記手続きが必要です。代表取締役の交代はもちろん、他の役員の退任や就任がある場合も同様です。
また、不動産などの資産を会社名義ではなく個人名義で所有している場合は、その名義変更手続きも別途発生します。
個人事業主の場合は、現経営者が「個人事業の廃業届出書」を提出し、後継者が「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出すれば、実質的な経営の引継ぎが完了します。
事業承継にかかる費用

事業承継を進める上では、さまざまな費用が発生します。本章では、承継方法ごとの費用や税金について解説します。
- 親族内承継の費用と税金対策
- 社員承継における資金調達
- M&A承継の費用構造と専門家報酬
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
親族内承継の費用相場
親族内承継では、主に税金が大きなコストです。
生前に株式や事業用資産を譲る場合は「贈与税」、経営者の死後に引き継ぐ場合は「相続税」が後継者に課されます。
非上場株式の評価額は高額になることも多く、納税資金の準備が大きな課題です。
税負担を軽減するためには、暦年贈与の活用や、相続時精算課税制度、事業承継税制の特例措置など計画的な利用が不可欠です。
これらの制度は要件が複雑なため、税理士などの専門家への相談費用も発生します。
社員承継の費用相場
社員承継の場合、後継者にとって最大の負担は「株式の買取資金」です。
会社の規模や業績によっては、株式評価額が数千万円から数億円に上ることもあり、個人の資金力だけでは準備が困難なケースも少なくありません。
そのため、日本政策金融公庫などの政府系金融機関や民間金融機関からの融資の利用が一般的です。
この場合、融資にかかる金利や保証料が費用です。また、現経営者側は、株式の譲渡によって得た利益(譲渡所得)に対して所得税・住民税が課税されます。
M&A承継の費用相場
M&Aによる第三者承継では、売り手経営者の株式譲渡所得に対して20.315%の税金が課されます。
これは譲渡価格から取得費や手数料を差し引いた金額に、所得税・住民税・復興特別所得税を合算した税率です。
ただし2025年1月から、年間所得3.3億円超の部分には最大27.5%の税率が適用されています。
一般的なM&A案件では従来通り20.315%の税率ですが、大型案件では税負担が増加する可能性があります。
専門家報酬の費用相場
事業承継の手続きは複雑で専門的な知識を要するため、弁護士、税理士、M&A仲介会社などの専門家への依頼が重要です。また、仲介会社に支払う報酬も重要なコストです。
特にM&A仲介会社の手数料は、会社や案件規模によってさまざまです。一般的に「レーマン方式」の成功報酬体系が採用されており、取引金額に応じて一定の料率が適用されます。
会社によっては着手金や中間金が必要な場合もありますが、着手金・中間金が無料で、成約時にのみ費用が発生する「完全成功報酬制」の会社を選ぶことで、初期コストを抑えられます。
事業承継をスムーズに行うためのポイント

事業承継は単なる手続きの実行だけでなく、多くの関係者の理解と協力があって初めて成功します。
本章では、承継プロセスを円滑に進めるために押さえておくべき重要なポイントを解説します。
- 個人事業主と法人の違いを理解する
- 後継者の選定・育成を行う
- 相続・贈与の対策を行う
- 相談窓口を活用する
具体的な取り組み方を見ていきましょう。
個人事業主と法人の違いを理解する
事業承継の手続きは、個人事業主と法人で大きく異なります。
法人の承継は、主に会社の「株式」を後継者に移転することで経営権を引き継ぎます。
一方、個人事業主には株式の概念がありません。そのため、事業で使っている店舗や設備、在庫といった資産一つひとつを個別に譲渡または賃貸借する手続きが必要です。
また、許認可が必要な事業の場合、法人では会社が許可を保有していますが、個人事業主の場合は個人に対して許可が与えられているため、後継者が新たに取得し直す必要があります。
後継者の選定・育成を行う
事業承継の成否は、後継者選びにかかっていると言っても過言ではありません。
後継者には経営能力やリーダーシップはもちろん、事業に対する熱意やビジョンが求められます。
親族、社員、第三者の中から最適な候補者を選定したら、それで終わりではありません。 経営者としての知識や経験、そして最も重要な経営理念や判断基準、リーダーシップなど、経営の本質的な部分を時間をかけて伝授していく必要があります。
現経営者と一緒に業務を行い、取引先や金融機関へ同行させるなど、計画的な育成期間を設けることが不可欠です。
相続・贈与の対策を行う
特に親族内承継において、相続税や贈与税の対策は避けて通れない課題です。
対策を怠ると、後継者が高額な納税資金が準備できず、事業継続が困難になるケースもあります。
国の「事業承継税制」を活用すれば、一定の要件のもとで納税が猶予・免除されます。また、計画的な生前贈与や生命保険の活用など、方法は多岐にわたります。
上記の対策は、実行までに時間がかかるものも多いため、経営者が元気なうちから専門家と相談し、早期に着手しましょう。
相談窓口を活用する
事業承継は、経営者一人で抱え込まずに専門家の力を借りることが成功への近道です。
国や地方自治体も中小企業の事業承継を後押ししており、無料で相談する窓口が設置されています。
代表的なのが、各都道府県にある「事業承継・引継ぎ支援センター」です。支援センターでは、事業承継に関するあらゆる相談に専門家が対応してくれます。
また、M&Aを視野に入れる場合は、M&A仲介会社が強力なパートナーです。
豊富な経験とネットワークを活かし、自社に最適な相手を見つけ、交渉から契約までをサポートしてくれます。
【法人の場合のみ】株式の整理をする
法人の事業承継において、経営権の承継はすなわち株式の承継を意味します。
後継者が安定した経営を行うためには、議決権の過半数、理想的には3分の2以上を後継者に集中させることが重要です。
過去の経緯から株式が親族や社員などに分散している場合は、承継のタイミングで買い集めるなどの整理が必要です。
株式が分散していると、重要な経営判断が迅速に行えなかったり、株主間の対立で経営が混乱したりするリスクがあります。
計画的に株式を後継者に集約させる準備を進めましょう。
【法人の場合のみ】事業用財産の整理をする
中小企業では、会社の事業所や工場などの不動産を経営者個人が所有し、会社に貸しているケースが見られます。
この場合、事業承継の際に不動産も後継者に引き継ぐ必要がありますが、他の相続人から遺留分(法律で保障された最低限の相続分)を主張されると、事業に必要な資産が分散してしまう恐れがあります。
上記の事態を避けるため、生前に後継者へ贈与したり、遺言書で明確に指定したりするなどの対策が必要です。
また、「遺留分に関する民法の特例」を活用し、他の相続人の合意を得て事業用資産を遺留分の対象から除外するのも有効な手段です。
事業承継計画の策定方法|実践的な作成手順

事業承継を成功に導くためには、羅針盤となる「事業承継計画」の策定が不可欠です。本章では、実践的な計画の立て方を解説します。
- 現状分析と将来ビジョンの明確化
- 承継方法の選択
- 具体的なスケジュール作成
3つの手順を詳しく見ていきましょう。
現状分析と将来ビジョンの明確化
計画策定の第一歩は、現状の正確な把握です。
財務状況(資産、負債、収益性)、事業内容(強み、弱み、市場での立ち位置)、組織体制(社員のスキル、後継者候補の有無)などを客観的に分析します。
その上で、経営者として会社を今後どうしていきたいのか、後継者に何を託したいのかといった将来ビジョンを明確にします。
現状と理想のギャップを埋めるための道筋が、事業承継計画の骨子です。
承継方法の選択
現状分析と将来ビジョンを踏まえ、誰に、どの方法で事業を引き継ぐかを具体的に決定します。
選択肢は主に「親族内承継」「社員承継」「第三者承継(M&A)」の3つです。
それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自社の状況に最も合った方法を選びます。
例えば、親族に適任者がいれば親族内承継、長年貢献してくれた信頼される役員がいれば社員承継、後継者不在だが事業の成長を願うならM&A、といった形で最適な選択肢を検討します。
承継方法選択の段階で、選んだ方法に伴う課題(税金、資金、法的手続きなど)も洗い出しましょう。
具体的なスケジュール作成
承継方法が決まったら、実行に向けた具体的なスケジュールを作成します。これは、5年から10年先を見据えた長期的なロードマップです。
「いつまでに後継者教育を終えるか」「いつ株式の移転を開始するか」「いつ代表取締役を交代するか」といったマイルストーンを時系列で設定します。
各タスクの担当者と期限の明確化により、計画が具体性を帯び、進捗管理がしやすいです。
スケジュールは、関係者全員で共有し、認識を合わせておくことが重要です。
リスク対策と代替プランの準備
事業承継には、経営者の急な体調不良や後継者候補の心変わり、相続トラブルなど、予期せぬリスクが伴います。
計画通りに進まなかった場合に備え、想定されるリスクを洗い出し、それぞれの対応策をあらかじめ検討しておくことが肝要です。
例えば、「親族内承継が難しくなった場合は、社員承継に切り替える」「M&Aの交渉が不調に終わった場合に備え、別の候補先もリストアップしておく」など、代替プランを用意しておくことで、不測の事態にも冷静かつ迅速に対応可能です。
事業承継の成功の3つのポイント
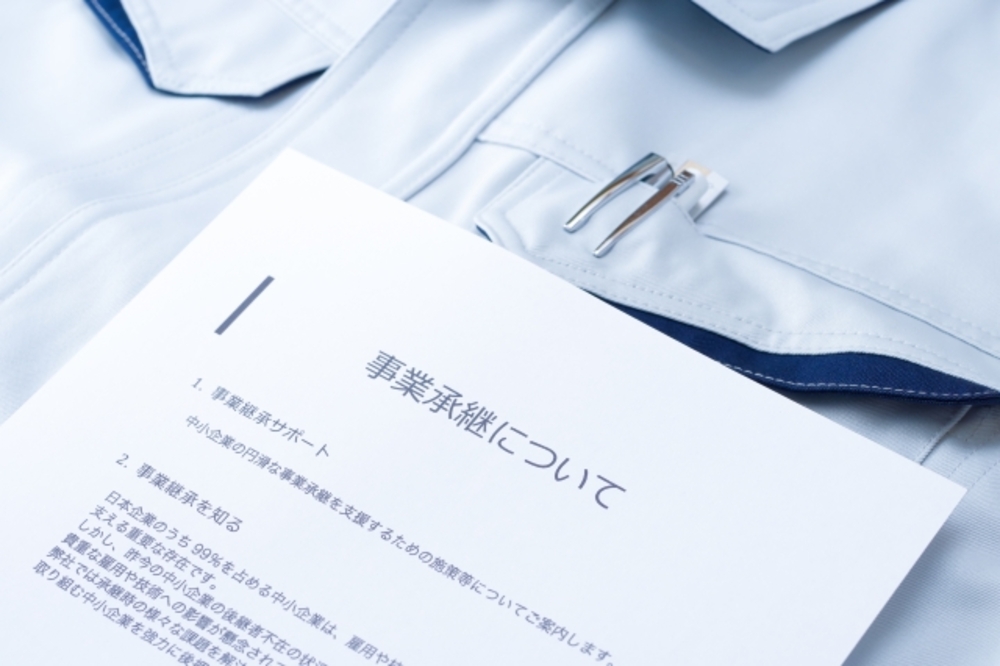
長期間にわたる事業承継を成功させるためには、計画性と戦略性が求められます。本章では、特に重要となる3つの成功ポイントを解説します。
- 早めに準備を行う
- 後継者の育成に力を入れる
- 税務・法務リスクの事前対策を立てる
それぞれを詳しく見ていきましょう。
早めに準備を行う
事業承継の成功は、準備期間の長さに比例するといっても過言ではありません。
経営者の引退が現実的になってから慌てて準備を始めても、最適な後継者を見つけられなかったり、十分な税金対策ができなかったりと、多くの問題に直面します。
理想は経営者が50代後半~60代前半のうちに準備を開始し、5年から10年かけてじっくりと取り組むことです。
早期の着手により、会社の強みをさらに伸ばす「磨き上げ」の時間も確保でき、より良い条件での承継が可能です。
後継者の育成に力を入れる
後継者を誰にするか決めることと同じくらい重要なのが、その後の育成です。会社の経営は、すぐに身につくものではありません。
現経営者は、自らが持つ経営ノウハウ、業界知識、人脈、そして何よりも「経営者としての心構え」を、時間をかけて後継者に伝えていく必要があります。
OJT(現場での実務研修)だけでなく、経営セミナーへの参加などOFF-JTの機会も設け、体系的な知識と実践的な経験の両方を積ませることが、次世代の経営者を育てる上で不可欠です。
税務・法務リスクの事前対策を立てる
事業承継には、相続税や贈与税などの税務リスク、そして株式の分散や遺留分を巡るトラブルなどの法務リスクが常に伴います。これらのリスクは、事前に対策を講じることで大幅に軽減可能です。
例えば、税務面では「事業承継税制」の活用が有効です。法務面では、遺言書の作成や、株式の譲渡制限規定を定款に設けるなどの対策が挙げられます。
専門的な対策は、自社だけで判断せず、税理士や弁護士といった専門家と連携し、計画的に進めることが成功の鍵を握ります。
事業承継の手続きの注意点

事業承継のプロセスには、思わぬ落とし穴が潜んでいることもあります。本章では、多くの経営者が直面しがちな注意点を解説します。
- 後継者を慎重に選ぶ
- 時間に余裕を持って取り組む
失敗を未然に防ぐための心構えを見ていきましょう。
後継者を慎重に選ぶ
後継者の選定は、事業承継の成否を決定づける重要な要素です。
単に血縁者であるから、あるいは勤続年数が長いからといった理由だけで安易に選んではいけません。
事業に対する情熱、リーダーシップ、経営判断能力、そして誠実な人柄など、次期経営者としてふさわしい資質を多角的に見極める必要があります。
特にM&Aで第三者に会社を託す場合は、相手企業の経営理念や文化が自社と合うか、社員を大切にしてくれるかなどの慎重な判断が、円満な承継に不可欠です。
時間に余裕を持って取り組む
事業承継は、一朝一夕には完了しない長期的なプロジェクトです。
現状の把握から後継者教育、株式や資産の移転、関係者への周知など、やるべきことは山積しています。
これらのプロセスには、一般的に5年から10年といった長い時間が必要です。
準備期間が短いと、後継者教育が不十分になったり、十分な税金対策が打てなかったり、相続トラブルに発展したりするリスクが高まります。
経営者が元気で判断力が確かなうちに、準備を開始することが、成功への最大の秘訣です。
事業承継の流れを把握してスムーズな手続きを実現しよう

事業承継は、誰に引き継ぐかによって流れや準備が大きく異なります。
最も重要なことは、早期に準備を開始し、計画的に進めることです。親族内承継では相続税対策、社員承継では資金調達、M&Aでは信頼されるパートナー選びが成功の鍵です。
複雑な法務・税務手続きが伴うため、専門家のサポートは不可欠です。まずはお気軽にご相談ください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)






