事業承継の失敗を防ぐ|失敗事例10選・要因・対策を法人経営者向けに解説

事業承継の失敗は、単に経営者が交代するだけでなく、最悪の場合、会社の廃業や倒産を招きかねない深刻な問題です。
「後継者が見つからない」「社内の混乱で業績が悪化する」「多額の税金で資金繰りが立ち行かなくなる」など、そのリスクはさまざまです。
しかし、なぜ事業承継は失敗してしまうのでしょうか。
この記事では、事業承継を検討中の経営者様が抱える不安を解消するため、具体的な失敗事例10選とその背景にある要因を解説します。
さらに、失敗を未然に防ぐための実践的な対策や、悩みに応じた専門相談先まで網羅的に解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業承継の失敗とは?

事業承継の失敗とは、経営のバトンタッチが円滑に進まず、結果的に企業の存続や成長が脅かされる状態を指します。
具体的には、後継者が経営を軌道に乗せられず業績が悪化するケース、相続争いから親族関係や従業員との関係が悪化するケース、最終的に廃業や倒産に至るケースなどが挙げられます。
重要なのは、会社が存続しているからといって、事業承継が成功したとは限らない点です。
承継後に企業価値が大きく毀損したり、従業員の大量離職を招いたりした場合も、実質的には失敗と捉えるべきです。
経営者にとって事業承継は、単なる株式や代表権の移譲ではありません。
これまで築き上げてきた企業文化や従業員の雇用、取引先との信頼関係といった目に見えない資産を次世代へ引き継ぐことが重要な経営課題です。
事業承継の失敗|企業への影響とは?

事業承継がうまくいかないと、企業はさまざまな深刻な影響を受けます。その影響は複合的に絡み合い、最終的には企業の存続そのものを脅かすことになります。
具体的にどのような事態が起こりうるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
廃業・倒産
事業承継の失敗がもたらす最も深刻な結末が、企業の廃業や倒産です。後継者が見つからない、あるいは後継者の能力不足によって経営が立ち行かなくなるケースが典型です。
また、株式の承継に伴う多額の相続税が払えずに資金繰りがショートしたり、相続人間でのトラブルが訴訟に発展し、経営どころではなくなったりする事態も想定されます。
長年かけて築き上げた会社が、事業承継がうまくいかないだけで、一瞬にして消滅してしまうリスクがあるのが廃業・倒産です。
業績の悪化
経営者が交代した直後は、業績が悪化しやすい危険な時期です。先代経営者のようなリーダーシップを後継者が発揮できず、経営判断が遅れたり、誤った方向に進んだりするケースが少なくありません。
さらに、新体制への反発から古参の役員や従業員が非協力的になり、組織が一体として機能しなくなることもあります。
その結果、売上の減少や利益率の低下を招き、企業の競争力が著しく低下してしまうケースもあります。
退職者の増加と人材流出
事業承継は、従業員にとっても大きな変化であり、不安を感じやすいタイミングです。
新しい経営方針についていけない、後継者との人間関係がうまくいかない、会社の将来性に疑問を感じるなどの理由から、退職者が続出するリスクがあります。
特に、会社の事業を支えてきた中核人材や、重要な技術を持つベテランが流出してしまった場合、その損失は計り知れません。
人材の流出は、残った従業員の負担増にもつながり、さらなる離職を招く悪循環に陥る危険性があります。
資金繰りの悪化
事業承継は、資金繰りの面でも大きなリスクを伴います。
特に親族内承継では、後継者が自社株を買い取るための資金や、相続税・贈与税の納税資金として、多額の現金が必要になる場合があります。
これを準備できなければ、承継そのものが頓挫しかねません。
また、金融機関が後継者の経営手腕を疑問視し、先代経営者の個人保証の解除や新規融資に難色を示すケースもあります。
これにより、運転資金や設備投資の調達が困難になり、事業の継続や成長が阻害される事態に発展します。
| 失敗がもたらす影響 | 主な内容 |
| 廃業・倒産 | 経営の混乱が資金繰りの悪化を招き、事業継続が不可能になる |
| 業績の悪化 | 経営方針の迷走や顧客離れにより、売上や利益が大幅に減少する |
| 退職者の増加と人材流出 | 新体制への不信感から優秀な人材が離れ、組織力が低下する |
| 資金繰りの悪化 | 相続税等の納税資金が不足し、事業に必要な運転資金が枯渇する |
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
【承継方法別】事業承継の失敗事例10選

事業承継の失敗は、どのような承継方法を選択しても起こり得ます。
ここでは、「親族内承継」「従業員承継」「M&Aによる第三者承継」のそれぞれで実際に起きた失敗事例を10個紹介します。
自社の状況と照らし合わせながら、潜んでいるリスクを事前に把握しましょう。
【親族内承継の失敗事例】
長年、中小企業の主流であった親族内承継ですが、身内ならではの感情的な問題や準備不足が失敗を招くケースが後を絶ちません。
ここでは、親族内承継の3つの典型的な失敗事例を解説します。
事例1:【大塚家具】経営方針の対立で父娘が対立し、ブランド価値が毀損
「高品質な商品を、専門知識を持つ社員が丁寧な接客で販売する」というビジネスモデルを一代で築いた大塚家具。
創業者である父・大塚勝久氏から長女・久美子氏へ経営のバトンが渡された後、深刻な経営権争いが勃発しました。
会員制で高価格帯の家具をコンサルティング営業する父のやり方に対し、久美子氏は「入りやすく、見やすい」オープンな店舗で、よりカジュアルな価格帯の商品も扱う方針を打ち出しました。
この経営方針の根本的な違いが、委任状争奪戦(プロキシーファイト)にまで発展。
結果的に久美子氏が勝利したものの、一連の「お家騒動」はブランドイメージを大きく傷つけ、顧客離れと業績悪化を招きました。
最終的に、大塚家具は家電量販大手ヤマダ電機(現ヤマダホールディングス)の傘下に入り、2021年8月27日をもって上場廃止。創業家の経営方針を巡る対立が、一つの有名ブランドを終焉に導いた象徴的な事例です。
| 企業名 | 株式会社大塚家具 |
| 業界 | 家具・インテリア小売業 |
| 承継方法 | 親族内承継 |
| 失敗要因 | ・先代と後継者の経営方針を巡る対立
・委任状争奪戦によるブランドイメージの毀損 ・旧来のビジネスモデルからの転換の失敗 |
| 結果 | ・深刻な業績悪化と赤字経営
・第三者(ヤマダ電機)への身売り、のちに上場廃止 |
事例2:【ロッテホールディングス】兄弟間の後継者争いが「お家騒動」に発展
菓子・アイスクリーム製造大手のロッテグループでも、創業者の長男と次男による壮絶な後継者争いが繰り広げられました。
創業者である重光武雄氏の後継者として、長男の宏之氏が日本のロッテグループ、次男の昭夫氏が韓国のロッテグループをそれぞれ率いる体制が続いていました。
しかし、2015年に父・武雄氏が長男・宏之氏をグループの役職から解任したことをきっかけに対立が表面化。
兄弟間での経営権を巡る訴訟合戦や株主総会での委任状争奪戦が泥沼化し、その様子は「お家騒動」として大々的に報じられました。
最終的には次男・昭夫氏が日韓ロッテグループの経営権を掌握しましたが、創業家内の根深い対立はグループのガバナンス体制の不透明さを露呈する結果となりました。
| 企業名 | 株式会社ロッテホールディングス |
| 業界 | 食品製造業 |
| 承継方法 | 親族内承継 |
| 失敗要因 | ・後継者指名が不明確だったことによる兄弟間の対立
・複雑な株主構成 ・経営権を巡る長期の訴訟合戦 |
| 結果 | ・創業家内の深刻な対立と親族関係の悪化
・企業の社会的イメージの低下 |
事例3:【一般企業】相続税の支払いで経営が圧迫されたケース
後継者不在の問題は、特に中小企業において深刻化しています。
東京商工リサーチの調査によると、2024年には後継者不在が原因で倒産した企業が過去最多の462件に達しました。
その主な要因の一つが、代表者の「死亡」による突然の事業承継です。
遺言により後継者である長男が会社の全株式を相続したものの、ここで大きな問題が発生します。
会社の業績が好調だったため、非上場株式である自社株の評価額が想定以上に高騰しており、数億円単位の莫大な相続税が課されることになるケースです。
結果として、金融機関からの借入や保有資産の売却でなんとか納税したものの、会社は多額の負債を抱え、その後の設備投資や事業展開が大きく制限されることになります。
相続に関する事前の納税対策を怠ったことが、会社の成長の足かせとなってしまう事例です。
| 企業名 | (非公表・中小企業の典型例) |
| 業界 | 製造業など |
| 承継方法 | 親族内承継(相続) |
| 失敗要因 | ・自社株評価額の想定の甘さ
・相続税の納税資金準備不足 ・生前の相続対策の欠如 |
| 結果 | ・多額の借入による財務状況の悪化
・事業継続はできたものの、成長投資が困難に |
参考:東京商工リサーチ『2024年の「後継者難」倒産 過去最多の462件 建設業、サービス業他など労働集約型が上位に』
【従業員承継(EBO)の失敗事例】
親族以外で会社のことを最もよく理解している役員や従業員への承継は、有力な選択肢です。しかし、資金面や経営者としての資質の問題が壁となることがあります。
ここでは、従業員承継の3つの典型的な失敗事例を解説します。
事例4:【ユニゾホールディングス】EBO(従業員買収)が経営破綻の引き金に
不動産事業を展開し、東証1部に上場していた優良企業、ユニゾホールディングス。2019年に大手旅行会社HISによる敵対的買収を仕掛けられたことを発端に、複数のファンドを巻き込んだ争奪戦に発展しました。
最終的に同社は、従業員と米投資ファンドが設立した会社によるEBO(従業員による企業買収)を選択し、2020年6月に上場を廃止しました。
しかし、このEBOに要した2,000億円超という巨額の買収資金が、その後の経営を大きく圧迫します。
資金繰りが悪化し、資産の切り売りを余儀なくされ、最終的に2023年4月、約1,262億円の負債を抱えて民事再生法の適用を申請するに至りました。
従業員の雇用を守るためとされたEBOが、結果的に会社を破綻に追い込んだ皮肉な事例です。
| 企業名 | ユニゾホールディングス株式会社 |
| 業界 | 不動産業 |
| 承継方法 | 従業員承継(EBO) |
| 失敗要因 | ・EBOのための過大な資金調達(2,000億円超の借入)
・買収後の財務悪化と資金繰りの失敗 |
| 結果 | ・民事再生法の適用を申請し、経営破綻 |
参考:東京商工リサーチ『「社債償還」が注目されるユニゾホールディングス』
事例5:【一般企業】先代経営者が引退後も経営に介入し、新体制が機能不全に
長年会社を支えてきた専務に事業を承継し、自身は会長に就任した創業社長。
しかし、引退後もご意見番として毎日出社し、新社長の経営方針や意思決定にことごとく口を挟みました。
「そのやり方はうちの会社には合わない」「俺の代ではそんなことはしなかった」と会議の場で新社長の決定を覆すこともあり、従業員は「本当の社長は誰なのか」と混乱。
新社長もリーダーシップを発揮できず、改革は進みません。
結果として、旧体制のまま市場の変化に対応できず、業績が徐々に低迷していくことになりました。
経営権の委譲と同時に、権限の委譲を明確にしなかったことが失敗の原因となった事例です。
| 企業名 | (非公表・中小企業の典型例) |
| 業界 | (全業種) |
| 承継方法 | 従業員承継(EBO) |
| 失敗要因 | ・先代経営者の過度な経営介入
・新旧経営者の役割分担の曖昧さ ・後継者のリーダーシップ発揮の阻害 |
| 結果 | ・従業員の混乱と意思決定の遅延
・経営改革の停滞と業績悪化 |
事例6:【一般企業】後継者の個人保証を引き継げず、資金調達が難航
運送会社で、社長の右腕だった常務が後継者となり、株式譲渡も完了しました。
しかし、金融機関からの借入金に対して設定されていた、先代経営者の個人保証を後継者に引き継ぐ段階で問題が発生しました。
金融機関は、後継者個人の資産背景や経営者としての実績が不十分であると判断し、保証の引き継ぎを認めませんでした。
これにより、既存の融資の条件が厳しくなったり、新たな設備投資のための追加融資が受けられなくなったりして、資金繰りが悪化。事業の成長機会を逃す結果となりました。
経営者保証に依存した資金調達構造からの脱却を計画的に進めなかったことが原因です。
| 企業名 | (非公表・中小企業の典型例) |
| 業界 | 運送業など |
| 承継方法 | 従業員承継(EBO) |
| 失敗要因 | ・後継者の個人保証の引き継ぎ失敗
・金融機関からの信用力の低下 ・「経営者保証に関するガイドライン」の活用不足 |
| 結果 | ・新規の資金調達の難航
・設備投資の遅延による事業への悪影響 |
参考:中小企業庁『経営者保証に関するガイドライン』
【M&Aによる第三者承継の失敗事例】
後継者不在問題を解決する有効な手段としてM&Aが増加していますが、買い手を見つければすべてが解決するわけではありません。安易なM&Aは、新たな問題を生む可能性があります。
ここでは、第三者承継の3つの典型的な失敗事例を解説します。
事例7:【マイクロソフト】事業環境を見誤り、巨額の減損損失を計上
2014年、米マイクロソフトは、かつて携帯電話市場を席巻したフィンランドのノキアの携帯端末事業を約72億ドルで買収しました。
狙いは、自社のOS「Windows Phone」を搭載したスマートフォンで、AppleのiOSやGoogleのAndroidが支配する市場に切り込むことでした。
しかし、買収のタイミングはすでに遅く、市場の牙城を崩すことはできませんでした。
期待したシナジーは生まれず、買収からわずか1年後には、買収額を上回る約76億ドルの減損損失を計上し、大規模なリストラを余儀なくされました。
M&A対象事業の将来性や市場環境の分析を見誤ったことが、巨額の損失につながった代表的な失敗事例です。
| 企業名 | マイクロソフト コーポレーション |
| 業界 | ソフトウェア・ITサービス |
| 承継方法 | M&Aによる第三者承継 |
| 失敗要因 | ・M&A対象事業の市場環境と将来性の見誤り
・期待した事業シナジーの欠如 |
| 結果 | ・約76億ドルの巨額の減損損失を計上
・携帯電話事業からの事実上の撤退 |
参考:Microsoft『マイクロソフト、携帯電話ハードウェア事業の再編を発表』
事例8:【LIXIL】デューデリジェンス不足で、買収先の子会社の不正会計が発覚
住宅設備大手のLIXILは、2013年にドイツの水栓金具大手グローエを買収しました。しかしその2年後、グローエの子会社であった中国のJoyou(中宇)で大規模な不正会計が発覚。LIXILは多額の特別損失を計上する事態に見舞われました。
この失敗の最大の原因は、買収前のデューデリジェンス(買収監査)が不十分であったことだと指摘されています。
Joyouの財務状況やガバナンス体制のリスクを正確に把握できていなかったために、巨額の「簿外債務」を抱え込むことになりました。
M&Aにおいて、専門家による徹底したデューデリジェンスがいかに重要かを示す教訓的な事例です。
| 企業名 | 株式会社LIXIL |
| 業界 | 住宅設備機器 |
| 承継方法 | M&Aによる第三者承継 |
| 失敗要因 | ・デューデリジェンス(買収監査)の不備
・買収先の子会社におけるガバナンス体制の欠陥 |
| 結果 | ・子会社の不正会計発覚による多額の損失計上
・株主からの訴訟リスクなど |
参考:株式会社LIXIL『GROHE Groupの株式取得完了について』
事例9:不利な契約条件に気づかず、売却後に後悔
高齢を理由に引退を決意したオーナー社長が、知人の紹介で買い手候補を見つけ、M&A仲介などの専門家を介さずに直接交渉を進めました。
「早く楽になりたい」という一心で契約書にサインしましたが、売却後に改めて内容を確認すると、以下のような自社に著しく不利な条件が多数含まれていることに気づきました。
- 想定より遥かに低い譲渡価格
- 過度に厳しい競業避止義務(長期間、広範囲での同業種への関与禁止)
- 予期せぬ債務の個人保証
契約後のため覆すことは難しく、長年かけて育てた会社を安値で手放しただけでなく、引退後の自身のキャリアまで縛られる結果となりました。
専門家による客観的な視点や契約内容のチェックを怠ったことが原因です。
| 企業名 | (非公表・中小企業の典型例) |
| 業界 | (全業種) |
| 承継方法 | M&Aによる第三者承継 |
| 失敗要因 | ・専門家を介さない直接交渉
・契約内容の確認不足と理解不足 ・売却を急ぐあまりの安易な意思決定 |
| 結果 | ・不当に低い価格での会社売却
・オーナーの経済的損失と引退後の活動制限 |
事例10:M&A仲介会社選びの失敗で、時間と費用を浪費
後継者不在に悩む食品メーカーが、M&Aによる事業承継を決意し、あるM&A仲介会社と専任媒介契約を結びました。
しかし、その仲介会社は手数料の獲得を優先するあまり、売り手の希望や企業文化を無視した買い手候補ばかりを紹介。
さらに、売り手企業の事業の強みを深く理解せずに交渉を進めたため、企業価値を正当に評価してもらえませんでした。
結局、満足のいく相手が見つからずにM&Aは不成立に終わりましたが、契約に基づき高額な着手金や月額報酬は返金されず、時間と費用だけを無駄にしてしまいました。
東京商工リサーチの調査でも、M&A仲介を巡るトラブルやリスクが指摘されており、仲介会社の選定がいかに重要かを示しています。
| 企業名 | (非公表・中小企業の典型例) |
| 業界 | (全業種) |
| 承継方法 | M&Aによる第三者承継 |
| 失敗要因 | ・自社に合わないM&A仲介会社の選定
・仲介会社とのコミュニケーション不足 ・料金体系(特に着手金・月額報酬)の確認不足 |
| 結果 | ・M&A不成立による時間と費用の浪費
・事業承継の機会損失と遅延 |
参考:東京商工リサーチ『M&A仲介の意義とリスクチェック強化の取り組み』
なぜ事業承継は失敗するのか?根本にある4つの共通要因
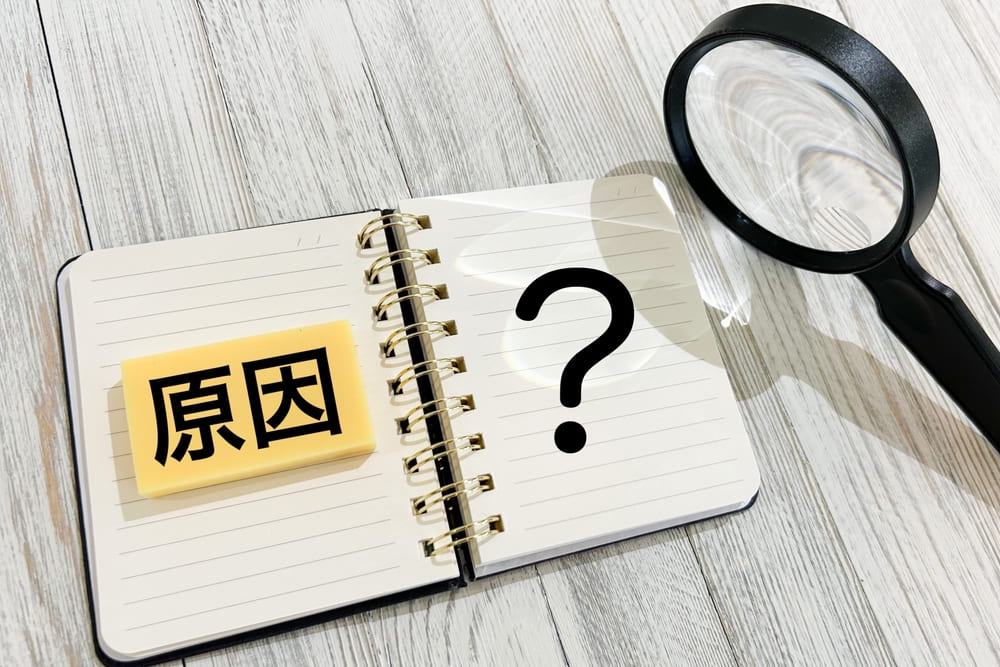
これまで見てきた失敗事例の背景には、いくつかの共通する要因が存在します。
承継方法にかかわらず、多くの失敗はこれらの要因が複雑に絡み合って引き起こされています。
自社の状況に当てはまるものがないか、確認してみましょう。
要因1:準備不足(後継者選定・育成の遅れ)
事業承継の失敗要因として最も多いのが、準備不足です。特に、後継者の選定や育成に着手するのが遅すぎることが問題です。
多くの経営者が「まだ自分は元気だから大丈夫」と考え、事業承継を先送りにしがちです。しかし、一般的に、後継者が経営者として一人前になるには、長い期間が必要とされています。
いざという時に慌てて後継者を決めても、経営ノウハウやリーダーシップ、従業員との信頼関係などを十分に引き継ぐ時間がなく、結果として経営を軌道に乗せられずに失敗してしまうのです。
要因2:コミュニケーション不足(経営者・後継者・従業員間の断絶)
事業承継は、経営者と後継者だけでなく、他の親族や従業員、取引先、金融機関など、多くのステークホルダーが関わります。
これらの関係者とのコミュニケーションが不足すると、さまざまな誤解や対立が生じます。
例えば、経営者が後継者だけに事業承継の話を進め、他の従業員に情報共有しなかったために社内に不信感が広がるケースです。
また、後継者が自分の考えを従業員に十分に説明しないまま改革を進め、反発を招くケースなどです。
丁寧な対話を怠ることが、組織の一体感を失わせ、承継の失敗につながります。
要因3:現状把握の甘さ(自社の強み・弱み・財務状況の軽視)
事業承継を成功させるには、自社の現状を客観的かつ正確に把握することが不可欠です。
しかし、長年経営に携わってきた経営者ほど、自社のことを分かっているつもりになり、現状把握を怠る傾向があります。
例えば、財務諸表に現れない簿外債務や、特定の従業員に依存した属人化した業務、自社の本当の強みや弱みなど、客観的な視点で見ないとわからない問題は少なくありません。
こうした現状把握の甘さが、M&Aの交渉破談や、承継後の予期せぬトラブルを引き起こす原因となります。
要因4:専門知識の欠如(税務・法務リスクの軽視)
事業承継には、株式の譲渡や相続に伴う税務、会社法などの法務といった専門的な知識が不可欠です。
例えば、自社株の評価額を正確に算定できていないと、後継者は想定外に高額な贈与税や相続税に苦しむことになります。
また、遺言書の作成や遺産分割協議の進め方に不備があると、親族間での相続争いに発展しかねません。
こうした専門知識の欠如から生じる税務・法務リスクを軽視した結果、承継プロセスそのものが頓挫したり、後継者に大きな負債を残してしまったりする失敗は後を絶ちません。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業承継に失敗しやすい企業が持つ5つの特徴

事業承継がうまくいかない企業には、組織文化や経営体質に共通する特徴が見られます。
ここでは、特に注意すべき5つの特徴を挙げます。これらの特徴に心当たりがある場合は、早期の改善が必要です。
特徴1:経営者のワンマン体質が強い
創業社長やカリスマ経営者に多く見られるのが、強力なリーダーシップで会社を引っ張ってきたワンマン体質の企業です。
こうした企業では、すべての意思決定が社長一人に集中しており、他の役員や従業員は指示待ちの状態になりがちです。
その結果、社長が引退した途端に会社が機能不全に陥るリスクがあります。
また、後継者が自分の色を出そうとしても、先代のやり方が絶対的な基準となり、自由な経営判断ができないという問題も生じやすくなります。
特徴2:経営状況や業務内容がブラックボックス化している
経営者が会社の財務状況や重要な取引先との関係、業務のノウハウなどを誰にも共有せず、自分一人の頭の中にしか持っていない状態です。
経理担当者でさえ、会社の全体的な資金繰りを把握していないケースもあります。
このようなブラックボックス化された経営は、後継者への引き継ぎを著しく困難にします。
いざ承継しようとしても、会社の全体像が見えないため、後継者は何から手をつけて良いかわからず、経営の舵取りに窮することになります。
特徴3:特定の人物に業務が依存している(属人化)
「この業務はAさんしかできない」「あの取引先のことはBさんしか知らない」といったように、特定の従業員のスキルや経験に業務が依存している状態を属人化と呼びます。
中小企業では、こうした職人気質のベテラン社員が事業の中核を支えていることも少なくありません。
しかし、事業承継の観点からは非常に大きなリスクです。そのキーパーソンが退職してしまえば、事業そのものが成り立たなくなる可能性があるからです。
業務が標準化・マニュアル化されていないため、後継者や他の従業員への引き継ぎも困難を極めます。
特徴4:企業理念やビジョンが明確にされていない
企業理念やビジョンは、会社が進むべき方向を示す羅針盤であり、従業員の求心力を高めるための重要な要素です。
これが明確に言語化され、社内で共有されていない企業は、経営者が変わるタイミングで組織が大きく揺らぎやすくなります。
先代経営者の暗黙の想いのようなものは、後継者や新しい従業員には伝わりません。
共通の価値観や目指すべきゴールがないため、新体制下で組織がバラバラになり、一体感のある経営ができなくなってしまいます。
特徴5:「まだ先のこと」と問題を先送りにしている
多くの経営者が、日々の業務に追われ、「事業承継はまだ先のこと」と問題を先送りにしがちです。
特に、業績が好調な時ほど、その傾向は強くなります。「後継者の話は縁起が悪い」「自分が引退するイメージがわかない」といった感情的な理由も、先送りの一因です。
しかし、事業承継の準備には長い年月がかかります。
問題を直視せず、準備を怠っている間に経営者の健康状態が悪化したり、外部環境が急変したりして、いざという時に手遅れになってしまうケースが非常に多いのです。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業承継の失敗を回避する!今日から始めるべき5つの対策

事業承継の失敗は、決して他人事ではありません。しかし、適切な対策を早期に講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。
ここでは、企業の未来を守るために、経営者が今日からでも始められる5つの具体的な対策を解説します。
対策1:早期に事業承継計画を策定し、ロードマップを明確化する
最も重要な対策は、できる限り早い段階で事業承継計画の策定に着手することです。
事業承継には5年から10年かかると言われています。まずは会社の現状分析から始め、誰に、いつ、どのように引き継ぐのかという大枠の方向性を決めます。
その上で、後継者の育成、株式や資産の移転、関係者への告知など、具体的なタスクとスケジュールを盛り込んだロードマップを作成しましょう。
計画を文書として見える化することで、やるべきことが明確になり、計画的に準備を進められます。
対策2:経営の見える化を進め、誰でも状況を把握できるようにする
磨き上げとも呼ばれますが、後継者がスムーズに経営を引き継げるよう、ブラックボックス化された経営からの脱却を図ります。
具体的には、以下の取り組みが挙げられます。
| 見える化のポイント | 具体的な取り組み内容 |
| 経営状況の可視化 | ・月次決算の体制を構築し、リアルタイムで業績を把握できるようにする
・資金繰り表を作成し、キャッシュの流れを明確にする |
| 業務の標準化 | ・業務マニュアルや手順書を作成し、属人化を解消する
・社内情報を共有するためのITツール(グループウェアなど)を導入する |
| 組織構造の整備 | ・組織図や役割分担表を明確にする
・定期的な会議体を設け、情報共有の場を作る |
これらの取り組みは、後継者のためだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながり、企業価値を高める効果があります。
対策3:後継者候補の育成プログラムを導入する
後継者を誰にするか決めたら、次は計画的な育成が必要です。単に業務を教えるだけでなく、経営者としての視点や判断力を養うための経験を積ませることが重要です。
例えば、以下のような機会を提供することが考えられます。
- ジョブローテーション:営業、製造、経理など、社内のさまざまな部門を経験させ、事業全体を理解させる。
- 権限委譲:最初は小さな部門の責任者から始め、徐々に大きな裁量権を与えて意思決定の経験を積ませる。
- 外部研修の活用:中小企業大学校などの公的機関や、民間の研修プログラムに参加させ、経営に関する体系的な知識を学ばせる。
重要なのは、先代経営者がOJT(On-the-Job Training)を通じて伴走し、成功も失敗も含めて経験させながら、フィードバックを与え続けることです。
対策4:社内外のステークホルダーと丁寧に対話する場を設ける
事業承継は、経営者と後継者だけで完結するものではありません。従業員、取引先、金融機関といったステークホルダーの理解と協力が不可欠です。
後継者が決まったら、できるだけ早い段階で関係者に紹介し、経営者の交代が企業の成長にとってプラスであることを丁寧に説明しましょう。
特に従業員に対しては、承継後の経営方針や処遇について誠実に伝え、不安を取り除く努力が求められます。
こうした対話を通じて、後継者が周囲からの信頼を獲得し、円滑にリーダーシップを発揮できる土壌を整えることが重要です。
対策5:信頼できる専門家に早期から相談し、客観的な意見を取り入れる
事業承継には、税務、法務、M&Aなど、高度な専門知識が要求される場面が多々あります。経営者一人で抱え込まず、早い段階から信頼できる専門家のサポートを得ることが成功への鍵です。
専門家は、自社の状況を客観的に分析し、潜在的なリスクを指摘してくれるだけでなく、最適な承継方法の選択や具体的な計画策定を手伝ってくれます。
また、M&A仲介会社や金融機関など、必要なネットワークを紹介してくれる役割も担います。相談費用はかかりますが、失敗による損失を考えれば、必要不可欠な投資と言えるでしょう。
| 対策ステップ | 具体的なアクション | 目的 |
| 対策1 | 事業承継計画書の作成に着手する | ゴールとスケジュールを明確にし、関係者と共有する |
| 対策2 | 経営状況の見える化を行う | 財務状況や業務フローを整理し、誰でも把握できる状態にする |
| 対策3 | 後継者育成プログラムを開始する | OJTや外部研修を通じて、計画的に経営者としての能力を高める |
| 対策4 | 定期的な対話の場を設ける | 家族会議や経営会議で、事業承継についてオープンに議論する |
| 対策5 | 専門家に初回相談を申し込む | 客観的な視点と専門知識を取り入れ、最適なプランを検討する |
【悩み別】事業承継の相談先はどこがベスト?4つの専門機関を徹底比較

事業承継の準備を始めようと思っても、「一体どこに相談すれば良いのか」と悩む経営者は少なくありません。
相談先にはそれぞれ特徴があり、自社の状況や悩みに合わせて最適なパートナーを選ぶことが重要です。
ここでは、代表的な4つの相談先を比較解説します。
M&A仲介会社:M&Aによる承継を検討している場合に最適
企業売却や買収による第三者承継を希望する場合は、M&A仲介会社の活用が有効です。
条件交渉や企業マッチング、契約書作成まで一貫したサポートを受けられます。
仲介会社選定時は過去の実績や手数料体系を慎重に検討し、自社に合うパートナーを選びましょう。
事業承継・引継ぎ支援センター:公的機関で中立的なアドバイスが欲しい場合
中立的な立場で事業承継を支援する公的機関として、事業承継・引継ぎ支援センターがあります。
各都道府県で無料相談や登録企業の紹介、セミナー開催などを行っており、専門家とも連携しながら支援体制が整っています。
資金調達や税務相談を含めた幅広いアドバイスが得られます。
金融機関(銀行・信用金庫):資金調達とセットで相談したい場合
事業承継には納税資金や買収資金など大きな資金が必要となります。
銀行や信用金庫は、資金計画やファイナンス面のサポートが得意分野です。
事業内容や承継プランに合わせて、資金調達の方法や利率交渉など経済的な視点から支援が受けられます。
士業専門家(税理士・弁護士):税務や法務の専門的な助言が欲しい場合
顧問税理士や弁護士は、事業承継における税務・法務の専門家です。
相続税や贈与税のシミュレーションと対策、遺言書の作成、株主間契約といった法的な手続きにおいて、的確なアドバイスを提供してくれます。
ただし、彼らの専門はあくまで税務・法務であり、経営戦略やM&Aの相手探しといった分野は専門外となる点に注意が必要です。
| 相談先 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
| M&A仲介会社 | M&Aによる第三者承継を専門に支援する | ・豊富な買い手候補ネットワークを持つ
・企業価値評価から交渉、契約まで一貫してサポート |
・着手金や成功報酬など費用が高額になる場合がある
・仲介会社によって質にばらつきがある |
・後継者不在でM&Aを具体的に検討している
・できるだけ高く会社を売却したい |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 国が設置する公的な相談窓口 | ・無料で相談できる
・中立的な立場でアドバイスをもらえる ・後継者不在企業と起業家をマッチングする後継者バンクがある |
・直接的な交渉や契約手続きは行わない
・最終的には他の専門家への橋渡しが中心 |
・何から始めればよいかわからない
・まず中立的な意見を聞きたい |
| 金融機関(銀行・信用金庫) | 融資取引のあるメインバンクなど | ・自社の経営状況をよく理解している
・資金調達(融資)とセットで相談できる ・M&A情報を保有している場合がある |
・事業承継の専門性が高いとは限らない
・融資先の都合を優先される可能性がある |
・承継に伴う資金調達の相談がしたい
・長年の付き合いがあり信頼できる |
| 士業専門家(税理士・弁護士) | 顧問税理士や弁護士など | ・税務や法務のリスクについて専門的な助言が得られる
・会社の内部事情に精通している場合が多い |
・M&Aの相手探しや交渉のノウハウは持っていない
・分野が限定的で、承継全体のサポートは難しい |
・親族内承継で相続税対策が必要
・契約書のリーガルチェックを依頼したい |
これらの相談先は、どれか一つを選べばよいというものではありません。
事業承継のフェーズや課題に応じて、複数の専門家と連携しながら進めていくのが一般的です。
まずは無料で相談できる事業承継・引継ぎ支援センターや日頃から付き合いのある顧問税理士に最初の相談をしてみるのが良いでしょう。
事業承継失敗を回避し、企業価値を最大化させましょう

事業承継は、企業にとって避けられない大きな転換期です。失敗すれば、長年かけて築き上げたすべてを失いかねない一方で、成功すれば企業は新たな成長ステージへと飛躍できます。
重要なのは、失敗事例から学び、問題を先送りにせず、早期に計画的な準備を始めることです。そして、経営者一人で、あるいは家族だけで抱え込まず、信頼できる専門家の力を借りることです。
企業の未来を守り、その価値を最大化させるために、まずは相談という形で第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)






