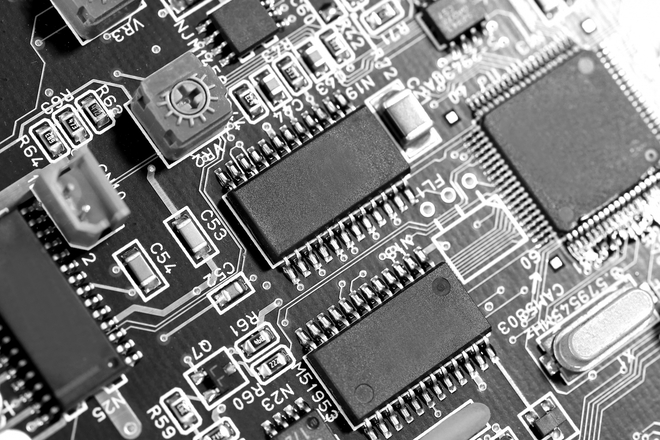製造業のM&A完全ガイド|現状・動向・メリット・事例まで徹底解説
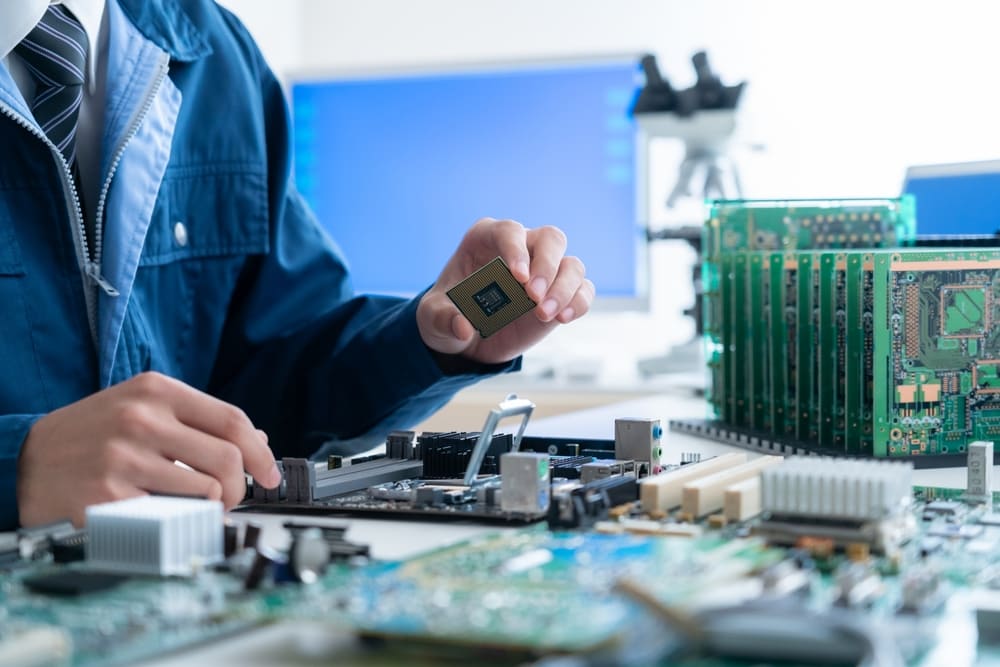
近年、製造業界を取り巻く環境が変化している中、でM&A(企業の合併・買収)を検討・実行する企業が増加しています。しかし、その具体的な内容や意義、さらには進行方法について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、製造業のM&Aについて全面的に解説します。製造業の現状や課題、M&Aの最新動向、メリット、さらには成功に導くステップや事例まで、詳しく解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
製造業とは?

製造業とは、原材料に加工や組み立てなどの工程を加え、新たな製品を作り出す産業のことです。私たちの生活に欠かせないさまざまな製品は、製造業によって生み出されています。ここでは、製造業の分類と市場規模について解説します。
製造業の分類
製造業は、製品の種類や製造方法によって多岐に分類されます。代表的な分類として、以下のものが挙げられます。
| 分類 | 概要 | 代表的な製品 |
| 機械工業 | 金属加工機械、産業機械、工作機械などを製造する産業 | 自動車、航空機、ロボット、建設機械 |
| 金属工業 | 鉄、アルミニウム、銅などの金属材料を製造する産業 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品 |
| 電気機械工業 | 電気機器、電子機器、情報通信機器などを製造する産業 | パソコン、スマートフォン、家電製品 |
| 化学工業 | 化学製品、医薬品、化粧品などを製造する産業 | プラスチック、合成繊維、医薬品、農薬 |
| 食品工業 | 食料品、飲料などを製造する産業 | 加工食品、飲料、菓子 |
これらの分類はあくまで一例です。実際にはさらに細かく分類されます。また、近年では、AIやIoTなどの技術を活用した新たな製造業も登場しており、その分類はますます多様化しています。
食品製造業のM&A|事例でわかる価格相場と成功のポイント【2025年最新版】
製造業界の市場規模
製造業は、日本経済を支える重要な産業の一つです。「日本のGDP(国内総生産)」において、製造業は約2割を占めています。
2021年時点で日本のGDPの約2割(約113兆円)を占め、日本経済を支える中心的な産業としての役割を果たしています。しかし、近年では、グローバル競争の激化や国内市場の縮小などにより、日本の製造業は厳しい状況に置かれているのが現状です。
このような状況の中、製造業界でM&Aを積極的に活用することで、事業の再編や効率化を図り、競争力を高めようとする動きが加速しています。
なぜ今、製造業でM&Aが活発なのか?製造業界の現状と課題

ここでは、M&Aが活発な理由を、製造業界の現状と課題に焦点を当てて解説します。
後継者不足と高齢化問題
日本の製造業は、経営者の高齢化と深刻な後継者不足といった大きな課題に直面しています。
帝国データバンクの全国「社長年齢」分析調査(2024年)によると、製造業の経営者の平均年齢は61.6歳と過去最高水準になっています。
多くの中小製造業でこの問題は顕著です。経営者の平均年齢は年々上昇を続けており、2023年には60.5歳に達しました。
しかし、経営者の高齢化が加速する一方で、次世代の経営者が不足している後継者問題も深刻化しています。
後継者が見つからない場合、長年培ってきた貴重な技術やノウハウの承継が困難になるだけでなく、従業員の雇用維持も難しくなり、地域経済への影響も懸念されます。
経営が順調でも、後継者不在のためにやむを得ず廃業する企業も少なくありません。
このような状況から、事業を次世代へ引き継ぎ、企業の存続と従業員の雇用を守るための有効な選択肢として、第三者への事業承継、すなわちM&Aへの関心が高まっています。
中小企業M&Aとは?|動向や価格の決め方・事例をわかりやすく解説
事業承継型M&Aとは?メリット・デメリット・成功のポイントを解説
国内市場の縮小
国内市場の縮小は、多くの製造業企業にとって深刻な課題です。日本の製造業は国際的な競争力を落としており、IMDの「世界競争力年鑑」によれば、2024年の日本の順位は67カ国・地域中38位に下落しています。
この背景には、少子高齢化による人口減少や国内需要の減少があり、多くの企業の収益性低下につながっています。特に、中国景気の減速や中国企業との競争激化も日本企業の業績に影響を与えている要因です。
このような厳しい環境下で、M&Aは有効な打開策の一つです。M&Aを通じて他社の技術や販路を獲得し、事業規模を拡大できます。
また、海外市場など新たな成長市場へアクセスすることで、国内市場縮小の影響を乗り越え、持続的な成長を目指す企業の増加が期待できます。
グローバル競争の激化
製造業界では、国境を越えた競争が年々激しさを増しています。2025年に向けて、特に中国やインドなどのアジア諸国からの競合企業が技術力を高め、コスト競争力を武器に市場シェアを拡大する傾向です。
中国は「Asia Manufacturing Index 2025」で首位を維持しており、インドも「Make in India」などの政策で競争力を高めています。この状況下で、国内企業におけるM&Aは、海外市場への迅速な進出や競争力強化のための重要な戦略です。
M&Aを通じて、技術やノウハウを持つ企業を買収することで、自社だけでは数年かかる開発期間を大幅に短縮でき、競合企業の俊敏な動きに対抗できます。
さらに、AI、IoT、ロボティクスなどの先端技術を持つ企業とのM&Aを通じて、製造プロセスの効率化やコスト削減を実現し、グローバル市場での競争優位性を確立できます。
技術革新への対応
製造業において、AI、IoT、ロボティクスに代表される急速な技術革新への対応は、競争力維持・向上のための喫緊の課題です。M&Aは、これらの先端技術を迅速に獲得し、自社に取り込む有効な戦略として注目を集めています。
その理由は、自社単独での研究開発には莫大な時間とコスト、専門人材が必要となり、市場のスピードに対応できないリスクがあるためです。
M&Aを通じて、すでに高度な技術やノウハウを持つ企業をグループに迎え入れることで、開発期間の大幅な短縮、コスト削減、そして即戦力となる専門人材の確保が実現します。
具体例として、スマートファクトリーの構築に必要なIoT基盤やセンサー技術、AIを活用した予知保全システムや品質管理、生産ラインの自動化を加速させるロボティクス、サプライチェーン効率化に貢献するクラウド技術などを有する企業がM&Aの対象として活発に検討されています。
技術革新が加速する製造業界において、M&Aは変化に適応し、持続的な成長を達成するための重要な経営判断です。特に大手企業を中心に、将来の競争優位性を確立する目的で、AIやクラウド関連など先端技術を持つ企業の買収が増加しています。
人材確保の難しさ
製造業全体で、人材確保は深刻な経営課題であり、特に、スキルを持つ専門人材の不足が顕著です。少子高齢化による労働人口の減少に加え、AIやIoTといった技術革新に対応できる人材への需要が高まっていることが背景にあります。
日本の労働市場は、終身雇用の文化が根強く残っており、経験豊富な人材の流動性が低い傾向にあります。特に地方の中小企業では、この問題がより深刻です。人手不足は効率性を損なう要因となっており、製造業全体に影響を与えています。
このような状況下で、M&Aは必要なスキルや経験を持つ人材を迅速かつ確実に獲得するための有効な戦略です。
外部から優秀な人材を取り込むことで、人材不足の解消だけでなく、組織全体の能力向上や技術革新への対応力強化を図る手段として、M&Aの重要性が高まっています。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
製造業M&Aの最新動向

製造業におけるM&Aは、事業承継、技術革新、グローバル展開など、多岐にわたる目的で活発化しています。ここでは、製造業M&Aの最新動向を4つのポイントに絞って解説します。
大手と中小企業間のM&A増加
大手企業が、特定の技術やノウハウを持つ中小企業を買収する動きが活発です。これは、大手にとっては迅速な技術獲得や市場アクセス、中小企業にとっては経営基盤の安定化や販路拡大につながるためです。
特に、部品メーカーなどを買収し、開発から製造までの工程をグループ内で一貫して行う内製化・垂直統合を目指す動きが見られます。
海外進出を意図したM&A
国内市場の縮小やグローバル競争の激化を背景に、海外市場への進出やシェア獲得を目的としたクロスボーダーM&Aが増加しています。
現地企業を買収することで、その地域の商習慣や法規制への対応、販路やネットワークの獲得が容易になり、海外進出に伴うリスクを低減できるためです。
後継者不在のため、M&Aが事業承継の解決策として注目
後継者不足は多くの中小製造業にとって深刻な課題であり、M&Aを事業承継の手段として活用するケースが増えています。
2023年の製造業におけるM&A件数は過去最高を記録するなど、第三者への事業譲渡し、技術や雇用の維持、事業の継続を図る動きが顕著です。
技術革新を目的として、大手企業がAIやクラウド関連の買収が増加
AI、IoT、ロボティクスといった先端技術への対応は、製造業の競争力を左右する重要な要素です。
自社開発には時間とコストがかかるため、これらの技術を持つ企業(特にIT関連企業など)をM&Aによって獲得し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させる動きが活発化しています。
自動化技術やロボット関連企業の買収、生産効率向上やコスト削減を目的としたITベンチャーの買収などがその例です。
参考:内閣府ホームページ『ロボット関連分野の産業化と 日本が取るべき戦略』
【売り手】製造業のM&Aのメリット

製造業のM&Aは、買い手だけでなく、売り手にも大きなメリットをもたらします。特に、後継者不足や経営者の高齢化が進む製造業においては、M&Aは事業の継続と成長を実現するための有効な手段です。
ここでは、売り手側の視点から、M&Aのメリットを詳しく解説します。
事業承継問題の解決
製造業、特に中小企業において、経営者の高齢化に伴う後継者不足は事業継続を脅かす深刻な課題です。親族や社内に適切な後継者が見つからず、廃業を選択せざるを得ないケースも少なくありません。
このような状況下で、M&Aは事業承継問題を解決するための有効な手段として注目されています。M&Aを活用して事業を意欲ある第三者へ譲渡することで、会社の存続が可能になるためです。M&Aによる事業承継は、株式譲渡や事業譲渡といった手法を用いて行われます。
この方法は、単に会社を残すだけでなく、長年培ってきた貴重な技術やノウハウ、そして最も重要な従業員の雇用を守ることも可能です。取引先との関係維持も期待でき、地域経済への影響も最小限に抑えられます。
創業者利益の獲得
M&Aによる会社売却は、長年企業経営に携わってきた創業者にとって、多額の創業者利益を得る絶好の機会です。創業者利益とは、会社の「資本+株式資本」と「売却額」との差額であり、経営努力の結晶といえます。
この利益は、新規事業への再投資、セミリタイア後の生活資金、あるいは家族への資産承継など、さまざまな形で活用できます。特に製造業では、事業承継の課題を抱える経営者が多く、M&Aによる創業者利益の獲得は、長年の経営努力に対する正当な報酬です。
また、資金繰りが悪化している場合でも、M&Aにより得た資金で負債を整理し、心理的な負担から解放されるメリットもあります。さらに、従業員の雇用や取引先との関係を守りながら、自身は経済的自由を手に入れられる点も大きな魅力です。
従業員の雇用維持
M&Aは、廃業とは異なり従業員の雇用を継続できる大きな利点があります。特に製造業では、長年培った技術やノウハウを持つ従業員は会社の重要な資産であり、その雇用を守ることは経営者の重要な責務です。
一般的に、中小企業のM&Aでは従業員の雇用が継続されることが多く、買い手企業にとっても技術者や熟練工の人材確保が大きな目的の一つです。そのため、多くの場合、雇用条件は維持または改善されます。
労働条件の維持については、契約書に明記することで、より確実に従業員の立場を守ることが可能です。M&Aによる事業継続は、従業員の生活を守るだけでなく、地域経済への貢献や取引先との関係維持にもつながります。
経営者として「自分がいなくなった後も従業員が安心して働ける環境を残したい」といった思いを実現できる点が、売り手側にとってのM&Aの大きなメリットです。
経営基盤の強化
M&Aは、売り手企業の経営基盤を強化する有効な手段です。資金力や経営資源が豊富な企業グループに加わることで、単独では解決が難しかった経営課題への対応力が向上します。
具体的には、買い手企業の資金力を背景とした大規模な設備投資や積極的な研究開発の推進が可能です。また、双方の販路や顧客基盤を相互活用することで売上拡大が期待でき、企業の信用力向上は資金調達の円滑化にもつながります。
さらに、スケールメリットによるコスト削減や経営ノウハウ・人材の交流による組織力の底上げ、事業リスクの分散なども実現しやすいです。このように、M&Aを通じて経営基盤を強化することは、事業の安定化と持続的な成長の実現に貢献します。
技術導入による事業成長
M&Aを通じた技術導入は、製造業の事業成長に大きな役割を果たします。特に中小企業が持つ独自技術やノウハウは、大手企業にとって魅力的な資源です。M&Aによって、これらの技術が広く活用されることで、新たな製品開発や市場拡大が加速されます。
例えば、ITスタートアップ企業が老舗メーカーと統合することで、IoTシステムや工場管理ソフトを実際の工場で試験運用し、成功モデルをパッケージ化することが可能です。
この統合によって、従来はIT単独での販売が難しかった製品が実際の工場での事例を示せると全国展開が実現します。
さらに、統合後のDXパッケージ化により、従来の製品品質も向上し、クレーム率の大幅な減少につながります。
このように、M&Aを通じた技術導入は、単なる技術の獲得にとどまらず、新たなビジネスモデルや市場展開の可能性を広げる重要な戦略です。
工場売却はM&Aでも可能!売却方法と手続き手順・必要書類を解説
【買り手】製造業のM&Aのメリット

製造業におけるM&Aは、買い手企業にとっても大きなメリットをもたらします。ここでは、主なメリットを5つ紹介します。
新規事業への参入
M&Aは、自社が未経験の分野へ迅速に参入するための有効な手段です。特に製造業では、異分野の技術やノウハウを持つ企業を買収することで、新たな製品ラインナップの拡充や新市場への進出を加速できます。
通常、新規事業を立ち上げるには、市場調査、技術開発、人材育成など、多くの時間とコストがかかりますが、M&Aを活用することでこれらのプロセスを大幅に短縮し、競争の激しい市場で優位に立つことが可能です。
技術やノウハウの獲得
独自の技術やノウハウを持つ企業を買収することは、自社の技術力向上に直結します。特に、高度な技術や特殊なノウハウは、自社で開発するには長い年月と多大な投資が必要となる場合があります。
M&Aによって、これらの貴重な資産を効率的に獲得し、自社の製品やサービスの品質向上、競争力強化につなげることが可能です。
また、買収先の企業が持つ特許や知的財産権なども同時に獲得できるため、技術的な優位性を確立する上で大きなアドバンテージとなります。
シェア拡大と競争力強化
同業の企業を買収することで、市場シェアを拡大し、競争力を高められます。市場シェアの拡大は、価格交渉力の向上や販売チャネルの強化につながり、収益性の向上に貢献します。
また、競合他社を買収することで、市場における競争を緩和し、より安定した経営環境を築くことが可能です。
さらに、買収先の顧客基盤やブランド力を活用することで、新たな顧客層を開拓し、事業の成長を加速させられます。
人材の獲得
M&Aは、即戦力となる優秀な人材を獲得する手段としても有効です。特に、技術者や研究開発者など、特定のスキルを持つ人材は、採用市場での獲得競争が激しく、採用が難しい場合があります。
M&Aによって、これらの貴重な人材をまとめて獲得し、自社の技術力や開発力を強化できます。また、買収先の経営陣や従業員のノウハウを吸収することで、組織全体の能力向上にもつながります。
シナジー効果による企業価値向上
M&Aによって、複数の企業が統合されることで、さまざまなシナジー効果が生まれます。例えば、技術、ノウハウ、顧客基盤、販売チャネルなどの経営資源を相互に活用することで、単独では実現できなかった新たな価値を創造することが可能です。
また、重複する部門の統合や規模の経済性を追求することで、コスト削減効果も期待できます。これらのシナジー効果によって、収益性の向上、競争力強化、そして企業価値の最大化を実現することが可能です。
製造業におけるM&Aは、買い手企業にとって、新規事業への参入、技術・ノウハウの獲得、シェア拡大、人材獲得、そしてシナジー効果による企業価値向上など、多くのメリットをもたらします。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
製造業のM&Aの相場

製造業のM&Aに関心をお持ちの皆様にとって、最も気になる情報の一つが「相場」ではないでしょうか。M&Aの価格は、企業の規模、業績、業界の動向など、さまざまな要因によって大きく変動します。
ここでは、製造業M&Aの相場について、M&A価格の計算方法と企業価値評価の方法の2つの側面から解説します。
M&A価格の計算方法
M&A価格は、売り手と買い手の交渉によって決定されますが、その交渉のベースとなるのが企業価値評価です。企業価値評価とは、企業の資産や収益力などを総合的に評価し、その企業の価値を金額で示すものです。
M&A価格は、この企業価値評価額を参考に、最終的な交渉によって決定されます。M&A価格の計算方法には、さまざまなものがありますが、代表的なものとして以下の3つが挙げられます。
| 評価方法 | 概要 | メリット | デメリット | 製造業への適用性 |
| 純資産法(コストアプローチ法) |
貸借対照表の純資産額を基に評価 | 客観性が高い、計算が容易 | 将来性や収益性を反映しない | 安定した資産を持つ企業に適している |
| 類似会社比較法(マルチプル法) | 類似上場企業の株価指標を参考に評価 | 市場の評価を反映、比較的容易 | 類似企業がない場合、市場の歪みの影響を受ける | 同業種で上場企業がある場合に有効 |
| DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法) | 将来のキャッシュフローを予測し、現在価値に割り引いて評価 | 将来性を反映、詳細な分析が可能 | 将来予測の不確実性が高い、主観が入りやすい | 成長性の高い企業や、事業計画が明確な場合に有効 |
それぞれの評価方法には、メリットとデメリットがあり、企業の特性や状況によって適切な評価方法の選択が必要です。製造業の場合、有形固定資産の割合が高い企業が多いため、純資産法が有効な場合があります。
一方で、技術力やブランド力が高い企業では、DCF法を用いて将来の収益力を評価することが重要です。また、M&A取引時には、企業価値の評価が重要なファクターとなります。
M&Aを成功させるためには、専門家(M&A仲介会社、FA(ファイナンシャルアドバイザー)、弁護士、公認会計士、税理士など)に相談し、適切な企業価値評価を行うことが不可欠です。専門家は、企業の財務状況や業界の動向を分析し、客観的な視点から企業価値を評価できます。
製造業M&Aを成功させるためのポイント

製造業のM&Aは、企業の成長戦略や事業承継の有効な手段となりえますが、成功させるためにはいくつかの重要な注意点があります。これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることで、M&Aの成功率を高めましょう。
明確な戦略と目標設定
M&Aを検討する際には、まず明確な戦略と目標を設定することが不可欠です。M&Aによって何を達成したいのか、どのようなシナジー効果を期待するのかを具体的に定義する必要があります。
例えば、技術力の強化、市場シェアの拡大、新規顧客の獲得など、具体的な目標を設定することです。M&Aの方向性が明確になり、その後のプロセスを円滑に進められます。
適切なパートナー選定
M&Aの成功は、最適なパートナー企業を選定できるかどうかに大きく依存します。候補企業の財務状況や技術力だけでなく、自社の長期的な戦略目標と相手企業の事業が合致しているか(戦略的適合性)を見極めることが不可欠です。
単に条件が良いだけでなく、その提携が自社の成長にどう貢献するのか、具体的なシナジー効果を描ける相手を選ぶ必要があります。加えて、企業文化の相性も極めて重要です。
価値観や働き方が大きく異なる企業同士が統合すると、従業員の混乱やモチベーション低下を招き、期待した成果を得られないリスクがあります。事前に相手企業の文化を理解し、統合後の円滑な運営が可能かどうか慎重に判断すべきです。
パートナー選定においては、自社のネットワークや既存の知識だけに頼らず、広い視野で候補を探すことが求められます。客観的な評価のためには、M&Aアドバイザーなどの専門家の意見を参考にすることも有効な手段です。
統合後の経営管理
統合後の経営管理(PMI)は、M&Aの成功にとって非常に重要です。PMIでは、組織文化の融合、業務プロセスの統合、情報システムの統一が重要です。効果的なPMIを実施することで、シナジー効果を最大化し、経営効率を高めることができます。
成功のカギは、明確な統合計画と迅速な実行です。初期段階で重点的に取り組むべき項目を特定し、優先順位をつけて実行することが重要です。
また、従業員のモチベーション維持や顧客との関係強化にも注力しましょう。定期的な進捗確認と柔軟な計画の見直しを行い、想定外の課題にも迅速に対応できる体制を整えることが、PMIの成功につながります。
デューデリジェンスの実施
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&Aの対象となる企業の価値やリスクを詳細に調査することです。財務、法務、税務、労務だけでなく、製造業特有の生産設備や技術資産、サプライチェーン、環境リスクなどを徹底的に調査しましょう。
製造業では、製造設備の老朽化や知的財産権の評価、環境規制への対応状況が重要な調査ポイントです。不十分なデューデリジェンスは、M&Aの失敗要因としてしばしば指摘されています。
具体的な数字については、信頼できる調査結果を参照することが推奨されます。拙速な調査は高額な追加コストや想定外の法的リスクを招くため、専門家の支援を受けながら計画的に進めることが重要です。
デューデリジェンスは単なる手続きではなく、M&A後の統合計画を立てる貴重な機会でもあります。
専門家への相談
M&Aは高度な専門知識と経験が求められる複雑なプロセスです。専門家への相談は、M&Aを成功させるための重要なステップです。
M&Aアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士など、各分野の専門家は、企業の財務状況や業界の動向を分析し、客観的な視点から企業価値を評価します。
専門家のサポートにより、法的リスクの回避、財務分析、交渉サポートなど、M&A全体のプロセスが円滑に進められます。特に、デューデリジェンスや契約交渉においては、専門家のアドバイスが不可欠です。
彼らは、潜在的なリスクを早期に発見し、適切な価格での取引を実現する手助けをします。さらに、統合後の経営管理(PMI)においても、専門家の指導が重要です。
組織文化の融合や業務プロセスの統合を支援し、M&Aのシナジー効果を最大化するための戦略を提案してくれます。
M&A実行の8つのステップ

M&Aは複雑なプロセスを経て実行されます。ここでは、M&Aを成功に導くための主要な8つのステップを解説します。各ステップを理解し、着実に実行していくことが重要です。
1.M&A戦略の策定
M&Aを成功させるためには、まず明確な戦略を策定することが不可欠です。M&Aの目的、買収後の経営方針、期待されるシナジー効果などを具体的に定義します。
この戦略が、その後のプロセス全体の指針となります。例えば、新規事業への参入、技術獲得、市場シェア拡大など、具体的な目標を設定しましょう。
2.M&A仲介会社への相談・選定
M&Aのプロセスは専門的な知識を要するため、M&A仲介会社への相談を検討しましょう。M&A仲介会社は、M&A戦略の策定から交渉、契約締結まで、一連のプロセスをサポートしてくれます。
複数の仲介会社を比較検討し、自社のニーズに合った最適なパートナーを選定することが重要です。仲介会社のビジネスモデルや手数料体系、実績などを確認し、信頼できる会社を選びましょう。
3.M&A候補先の選定
M&A戦略に基づいて、具体的な買収候補先を選定します。候補先の財務状況、技術力、市場におけるポジションなどを分析し、自社の戦略目標に合致するかどうかを評価します。
M&A仲介会社のサポートを受けながら、候補先リストを作成し、優先順位をつけて交渉に臨みましょう。
4.トップ面談
買収候補先の経営陣と直接会って、M&Aに対する考え方や企業文化、将来のビジョンなどを共有します。トップ面談は、相互理解を深め、友好的な関係を築くための重要な機会です。
事前に候補先の情報を十分に調査し、質問事項を準備しておくことが大切です。
5.基本合意契約を締結
トップ面談を経て、M&Aの基本的な条件(買収価格、スケジュール、秘密保持など)について合意が得られたら、基本合意契約を締結します。
基本合意契約は、一部を除き法的拘束力を持つものではありませんが、その後の交渉を円滑に進めるための重要なステップです。
6.デューデリジェンス
買収候補先の詳細な調査(デューデリジェンス)を実施します。財務、法務、税務、ビジネスなど、多岐にわたる側面から企業価値を評価し、リスクを洗い出しましょう。
デューデリジェンスの結果は、買収価格の調整や契約条件の見直しに影響を与える可能性があります。
7.最終契約の締結
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な買収条件を決定し、最終契約を締結します。
最終契約には、買収価格、支払い方法、クロージング条件、表明保証などが詳細に記載されます。契約内容を十分に理解し、慎重に交渉を進めることが重要です。
8.クロージング
最終契約に定められた条件がすべて満たされると、クロージング(取引完了)となります。株式譲渡、資産の移転、経営権の移行などが行われ、M&Aが正式に完了します。
クロージング後も、統合プロセス(PMI)を着実に実行し、シナジー効果を最大化することが重要です。
製造業M&Aの事例

製造業におけるM&Aは、企業の成長戦略、技術革新、事業承継など、多岐にわたる目的で活用されています。ここでは、M&Aによって新たな未来を切り拓いた3つの事例を紹介します。
廃業を決めた業歴75年の塗装店が存続と成長を同時に手にした事例
神奈川県で75年の歴史を持つ地域密着型の有限会社青竜社塗装店は、住宅塗装を手掛けてきました。従業員への事業承継後、営業力不足から業績が悪化し、一時は廃業も検討する状況に追い込まれました。
しかし、顧問税理士からの提案を受け、M&Aによる事業継続の道を探ります。複数の候補の中から、同じ神奈川県内で船舶の製造・修理や電気工事など、異なる事業を展開するエス・プランニング株式会社とのM&Aが成立しました。
青竜社塗装店は、エス・プランニングの持つ営業力に事業再建の期待を寄せ、一方のエス・プランニングは、青竜社塗装店の持つ塗装技術や実績を獲得することで、事業領域の拡大とシナジー効果を見込んでのM&Aです。
この異業種間のM&Aにより、青竜社塗装店は廃業の危機を乗り越え、75年続いた事業と従業員の雇用を守ることに成功しました。譲受企業の社長が従業員一人ひとりに直接説明を行うなど、丁寧なコミュニケーションによって円滑な統合が進められています。
この事例は、M&Aが深刻な経営課題を抱える企業の存続と、譲受企業の成長戦略実現を同時に達成しうることを示しています。
参考:日本M&Aセンター『廃業を決めた業歴75年の塗装店が、存続と成長を同時に手にした異業種M&A』
技術も事業も異なる製造業2社が手を組み他社にない強みを得た事例
株式会社ハリガイ工業(茨城県)と株式会社ケー・アイ・ピー(千葉県)のM&A事例は、異なる技術と事業を持つ2つの製造業企業が手を組み、新たな強みを得た例です。
ハリガイ工業は、ゴム成型や産業機器の加工組立を主力事業としており、新規顧客開拓が課題でした。一方、ケー・アイ・ピーはプラスチック製品の製造・販売を手掛け、大手衣料メーカーのプラスチック製品加工が主力事業でした。
このM&Aにより、ハリガイ工業は新たな材料技術を獲得し、顧客層の拡大に成功しています。特に、プラスチック加工技術の導入により、金属やゴム以外の材料を扱えるようになり、提案の幅が広がりました。
さらに、両社の技術と顧客基盤を活用することで、新たな製品開発や市場拡大が加速されました。社員全員への迅速なコミュニケーションも成功要因で、M&A後に社員の離職はなく、両社の役員が合同で経営会議を進めることで、シナジー効果を最大化しています。
参考:日本M&Aセンター『技術も事業も異なる製造業2社が手を組み 他社にない強みを得て顧客拡大を目指す』
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
製造業M&Aで新たな未来を切り拓く

製造業を取り巻く環境が変化する中、M&Aは事業承継、技術獲得、海外展開、人材確保といった多様な課題を解決し、成長を加速させる有効な手段です。
製造業が直面する後継者不足、国内市場縮小、グローバル競争激化などの課題に対し、M&Aは効果的な解決策となります。売り手にとっては事業承継問題の解決や従業員の雇用維持、買い手にとっては技術獲得や市場拡大といったメリットがあります。
M&Aは企業の未来を左右する重要な決断であり、リスクも伴うため、実施には明確な戦略と専門家への相談が不可欠です。ぜひ、本記事で得た知識を活かし、貴社にとって最適なM&A戦略を検討してみてください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)