旅行代理店のM&A動向|メリット・相場・最新事例10選を徹底解説

旅行代理店業界で、事業承継や再編を目的としたM&Aが加速しています。
コロナ禍を経て旅行需要は回復しつつも、オンライン化の波や後継者不足といった課題は依然として深刻です。「事業の将来が不安だ」「どう生き残れば良いか」と悩む経営者の方も多いのではないでしょうか。
こうした状況を打開する有効な選択肢がM&Aであり、大手による業界再編やDX化を目的とした買収など、その動きはますます活発化しています。
本記事では、旅行代理店業界の最新M&A動向から、買い手・売り手双方のメリット、価格相場、そしてHISやエアトリなど具体的な事例10選を徹底解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
旅行代理店業界の現状と抱える課題

旅行代理店業界は、今大きな転換期を迎えています。アフターコロナで旅行需要が回復する明るい兆しがある一方で、古くからの構造的な問題も浮き彫りになっています。
M&Aがなぜこれほど活発化しているのか、その背景にある業界の現状と課題から詳しく見ていきましょう。
市場環境の変化:コロナ禍からの回復と不安定な経営基盤
新型コロナウイルスの5類移行に伴い、国内旅行やインバウンド(訪日外国人旅行)の需要は急速に回復しています。観光地が賑わいを取り戻し、業界全体としては明るい未来が見え始めています。
しかし、その裏で多くの旅行代理店が不安定な経営基盤に悩まされているのが実情です。
- コロナ禍の財務的ダメージ:数年にわたる需要の低迷期を乗り切るために受けた融資の返済負担が、本格的に始まっています。
- 収益性の圧迫:燃油サーチャージの高騰や円安が、特に海外旅行を取り扱う代理店の収益性を圧迫しています。
- 景気への依存:旅行業界は景気変動の影響を受けやすく、先行きが不透明な経済状況は経営の不安定さに直結します。
回復基調にある今だからこそ、体力のある大手企業の傘下に入ることで経営を安定させたい、あるいは不採算事業を整理したいというニーズが高まっており、M&Aがその有効な手段として選ばれているのです。
構造的な課題:深刻化する後継者不足とデジタル化の遅れ
現在の市場環境の変化に加え、旅行代理店業界には以前から根深い構造的な課題が存在します。
その代表格が後継者不足です。特に地域に密着して長年経営を続けてきた中小の旅行代理店では、経営者の高齢化が進む一方で、親族や従業員の中に適任の後継者が見つからないケースが少なくありません。
事業への愛着や従業員の生活を守りたくても、後継者がいなければ廃業を選択せざるを得ないという厳しい現実に直面しています。
さらに、デジタル化の遅れも深刻な課題です。楽天トラベルやじゃらんnetといったオンライン旅行代理店(OTA)が台頭し、消費者がWebで手軽に旅行を予約するスタイルが一般化しました。
しかし、多くの中小代理店では、オンライン予約システムの導入やWebマーケティングへの投資が追いついていません。
この後継者問題とデジタル化の遅れという2つの大きな課題を同時に解決する手段として、第三者への事業承継、すなわちM&Aが極めて有効な選択肢となっているのです。
旅行代理店業界におけるM&Aの最新動向

業界が抱える課題を背景に、旅行代理店業界では生き残りと成長をかけたM&Aが活発に行われています。
ここでは、最新のM&A動向を2つのポイントから解説します。
デジタル領域の強化を目的としたM&Aの活発化
OTAとの競争が激化する中、従来の旅行代理店にとってデジタル技術の活用は避けて通れない経営課題です。自社でシステムを開発するには莫大なコストと時間がかかるため、スピーディーにデジタル対応を進める手段としてM&Aが選ばれています。
具体的な動きとしては、以下のようなケースが見られます。
- 既存の旅行代理店によるIT企業の買収:オンライン予約システムや顧客管理システム(CRM)のノウハウを持つIT企業を買収し、自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)を一気に加速させる動きです。
- IT企業による旅行代理店の買収:Webマーケティングやプラットフォーム運営に強みを持つIT企業が、旅行という巨大市場に参入するため、許認可や業界ノウハウを持つ旅行代理店を買収するケースも増えています。
大手による業界再編と地域特化型企業の買収
コロナ禍を経て、体力のある大手旅行代理店が事業規模の拡大やサービス多角化を目指し、M&Aを仕掛ける動きも目立っています。
特に注目されるのが、特定の地域や特定の分野に強みを持つ「地域特化型」や「専門特化型」の中小代理店の買収です。
大手企業にとって、こうしたM&Aには以下のような狙いがあります。
- 仕入力の強化:グループ全体の規模を拡大し、ホテルや交通機関に対する価格交渉力を高める。
- サービスの多様化:インバウンド向け、富裕層向け、アドベンチャーツーリズムなど、自社にはない専門的なノウハウを持つ企業を取り込み、新たな顧客層を開拓する。
- エリアの補完:自社が手薄だった地域の顧客基盤やネットワークを獲得する。
買収される中小企業側にとっても、大手のブランド力や資本力を活用できるメリットは大きく、双方のニーズが一致しやすいことから、業界再編の動きは今後も続くと見られています。
旅行代理店M&Aのメリット

M&Aは、売り手と買い手の双方にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。
この章では、それぞれの立場から見た主なメリットを整理します。
売り手のメリット:事業承継・雇用の維持・売却益の獲得
会社の譲渡を検討する売り手(譲渡企業)にとって、M&Aは廃業以外の未来を切り拓くための有力な手段となります。
主なメリットは以下の3つです。
- 後継者問題の解決と事業の存続
最大のメリットは、後継者がいなくても事業を存続させられる点です。長年かけて築き上げてきた会社名、顧客や取引先との信頼関係、そして地域でのブランドイメージを、買い手企業に引き継いでもらうことができます。 - 従業員の雇用の維持
廃業を選んだ場合、従業員は職を失うことになります。M&Aであれば、従業員の雇用は原則として買い手企業に引き継がれます。従業員は生活の基盤を失うことなく、より大きな企業の安定した環境のもとで働き続けられる可能性が生まれます。経営者として、従業員の将来を守れることは大きな安心材料となるでしょう。 - 創業者利益(売却益)の獲得
会社を譲渡することで、創業者・オーナーはまとまった売却益を得ることができます。この資金は、引退後の豊かな生活(ハッピーリタイア)を送るための資金や、新たな事業を始めるための元手として活用できます。廃業時にかかる清算コストを考えれば、金銭的なメリットは非常に大きいと言えます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
買い手のメリット:事業拡大・新規参入・ノウハウの獲得
会社を譲り受ける買い手(譲受企業)にとって、M&Aは時間とコストを大幅に削減し、一気に成長を加速させるための有効な戦略です。
- スピーディーな事業拡大
M&Aによって、売り手企業が持つ顧客基盤や営業拠点、仕入ネットワークなどをまとめて手に入れることができます。自社で一から開拓する場合に比べて圧倒的に短い時間で事業規模を拡大し、市場での競争力を高めることが可能です。 - 低リスクでの新規参入
旅行業を始めるには、第一種や第二種といった複雑な許認可の取得が必要です。M&Aであれば、許認可を持つ企業を譲り受けることで、この手続きにかかる時間と手間を大幅にショートカットできます。インバウンドや特定のテーマ旅行など、新たな分野へ迅速かつ低リスクで参入できるのは大きな魅力です。 - 専門人材・ノウハウの獲得
M&Aで得られるのは、目に見える資産だけではありません。売り手企業が長年培ってきた独自のツアー企画力、地域との強固なコネクション、経験豊富なベテラン従業員といった、目に見えない貴重なノウハウや人材もまとめて獲得できます。これらは、買い手企業にとって新たな価値創造の源泉となります。
旅行代理店のM&Aにおける価格相場
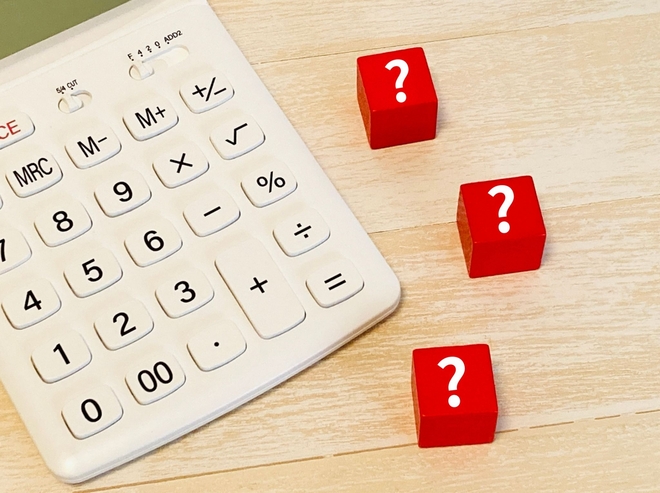
M&Aを検討する上で、最も気になる点の一つが、自社はいくらで売れるのか、買収にはいくらかかるのかという価格の問題ではないでしょうか。
ここからは、その相場観と評価方法の基本を解説します。
相場の目安は「営業利益の3~5年分 + 純資産額」
M&Aの価格に絶対的な正解はありませんが、中小企業のM&Aでは広く使われている簡易的な計算式があります。それが以下の式です。
企業価値 = 営業利益 × 3~5年分 + 時価純資産額
この計算式の内訳は、以下のようになります。
- 営業利益 × 3~5年分
これはのれん(営業権)と呼ばれる部分で、会社の「将来稼ぐ力」を評価したものです。安定した顧客基盤、独自のツアー企画力、地域でのブランド力といった、貸借対照表には載らない無形の価値がここに反映されます。旅行代理店の場合、リピート顧客の多さや特定の分野での専門性などが評価され、倍率が変動します。 - 時価純資産額
これは会社の解散価値とも言える部分です。会社が保有する資産(現金、不動産、車両など)を現在の価値(時価)で評価し直し、そこから負債(借入金など)を差し引いた金額です。帳簿上の価格ではなく、実態に近い価格で評価されるのがポイントです。
例えば、年間の営業利益が1,000万円、時価純資産額が3,000万円の会社であれば、1,000万円 × 3〜5年 + 3,000万円で、6,000万円〜8,000万円が一つの相場の目安となります。
相場を左右する企業価値の主な評価方法
実際のM&Aでは、より精緻な企業価値評価(バリュエーション)が行われます。
評価方法は、企業の特性や状況に応じて使い分けられますが、主に以下の3つのアプローチがあります。
| 評価アプローチ | 概要 | 旅行代理店への適用時の注意点 |
| コストアプローチ | 企業の純資産(資産-負債)を基準に評価する方法。 | 資産が少ない傾向にあるため、ブランド価値などの無形資産が評価されにくい。 |
| マーケットアプローチ | 類似する上場企業やM&A事例の株価や取引価格を参考に評価する方法。 | 事業内容や規模、地域性が完全に一致する類似企業の選定が難しい場合がある。 |
| インカムアプローチ | 企業が将来生み出すと予測される収益やキャッシュフローを基準に評価する方法(DCF法など)。 | 将来予測の精度や、リスクを反映する割引率の設定が評価額を大きく左右する。 |
旅行代理店の価値は、顧客リストや地域での評判、優秀な添乗員といった目に見えない資産に支えられていることが多いです。
そのため、どの評価方法を用いるにせよ、こうした無形資産をいかに適切に評価に反映させるかが重要なポイントとなります。
旅行代理店業界のM&A・事業承継の事例10選

近年、旅行代理店業界ではさまざまな目的でM&Aが実施されています。
ここでは、業界の動向を理解する上で参考となる10の事例をピックアップし、その目的や背景を解説します。
これらの成功事例から、自社のM&A戦略のヒントを探ってみましょう。
H.I.S. × デベロップ|大手による事業領域の拡大
2024年、大手旅行代理店のエイチ・アイ・エス(H.I.S.)は、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard」を運営する株式会社デベロップの株式20%を取得しました。
これは、従来の旅行事業に加え、成長が見込まれるホテル事業への投資を強化し、事業ポートフォリオを多角化する戦略の一環です。
大手企業がM&Aを通じて非旅行事業へ進出し、経営の安定化を図る代表的な事例と言えます。
(情報引用元:H.I.S.「株式会社デベロップの株式取得 (持分法適用会社化) に関するお知らせ」)
エアトリ × GROWTH|オンライン事業の強化
オンライン旅行事業を展開する株式会社エアトリは、2024年にWebマーケティング会社の株式会社GROWTHを買収しました。
エアトリの持つ旅行コンテンツと、GROWTH社の持つWeb広告運用のノウハウを組み合わせることで、デジタル領域での集客力を大幅に強化する狙いがあります。
オンラインでの競争が激化する中で、デジタルマーケティングの専門知識を取り込むための戦略的なM&Aです。
(情報引用元:株式会社GROWTH「株式会社エアトリへグループイン_事業体制の強化へ 」)
令和トラベル × Aloha7|海外展開の加速
新興の海外旅行専門代理店である株式会社令和トラベルは、2023年にハワイ専門の老舗旅行会社Aloha7 Inc.を買収しました。
これにより、令和トラベルはハワイという人気デスティネーションにおける強固な基盤と専門知識を獲得しました。
スタートアップ企業がM&Aを活用し、特定の地域への展開をスピーディーに加速させている好例です。
(情報引用元:株式会社令和トラベル「Aloha7 Inc.の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」)
西友HD × 奥ジャパン|異業種からのインバウンド事業参入
スーパーマーケット大手の西友ホールディングスは、2025年にインバウンド向けツアーに強みを持つ奥ジャパン株式会社を買収しました。
これは、小売業で培った顧客基盤や店舗網を活用し、成長が見込まれるインバウンド市場へ本格参入するための足がかりです。
異業種企業が、旅行業界の専門知識とネットワークを持つ企業を買収することで、新規事業を迅速に立ち上げる典型的な事例と言えます。
(情報引用元:エンデバー・ユナイテッド株式会社「奥ジャパン株式会社の株式譲渡に関するお知らせ」)
アジャイルメディア × インプレストラベル|DX推進
SNSマーケティング支援を行うアジャイルメディア・ネットワークは、旅行メディアを運営するインプレストラベルを買収しました。
目的は、インプレストラベルが持つコンテンツ制作力と旅行業界でのネットワークを獲得し、自社のデジタルマーケティング事業と融合させることです。
旅行コンテンツを活用した新たな広告商品の開発や、旅行業界のDX推進を支援するサービス展開を目指しています。
(情報引用元:アジャイルメディア・ネットワーク株式会社「(開示事項の経過)当社連結子会社株式会社インプレストラベルの第3種旅行業登録に関するお知らせ」)
アソビュー × そとあそび|アクティビティ領域の強化
レジャー・遊びの予約サイトを運営するアソビューは、アウトドア・アクティビティに特化した予約サイト「そとあそび」の事業を譲り受けました。
類似サービスを統合することで、掲載する体験プランの数を増やし、顧客基盤を拡大させることが目的です。
市場でのシェアを拡大し、プラットフォームとしての競争力を高めるための水平型M&Aの好例です。
(情報引用元:アソビュー株式会社「アソビュー、アウトドア予約そとあそび社の全株式取得。ニューノーマルでの遊び方提案を強化」)
IBJによるかもめの全株式譲渡|ノンコア事業の売却と事業存続
2021年、婚活サービス大手の株式会社IBJは、完全子会社で海外旅行事業を手掛ける株式会社かもめの全株式を、旅行業界で豊富な実績を持つ個人経営者へ譲渡しました。
当初、IBJはハネムーン需要など中核の婚活事業とのシナジーを期待していましたが、コロナ禍で海外旅行事業の収益回復が困難になりました。
そこで事業を廃止するのではなく、旅行業界のプロフェッショナルに経営を委ねることで、かもめの事業価値と従業員の雇用を守る道を選びました。
異業種からM&Aで参入した事業が、市場環境の変化に応じてノンコア(非中核)事業となった際に、最適な専門家へ売却するという、合理的な経営判断の好例と言えるでしょう。
(情報引用元:株式会社IBJ「連結子会社 2社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ」)
AZITO → エスクリ|ノンコア事業の譲渡
オリジナルウェディング事業などを手掛けるAZITO株式会社は、2021年にリゾートウェディング事業の一部を、ブライダル大手の株式会社エスクリへ事業譲渡しました。
これは、自社の経営資源をコア事業に集中させるための選択と集中戦略の一環であり、ノンコア事業を売却することで経営の効率化を図る事例です。
(情報引用元:株式会社エスクリ「エスクリ 旅行事業をスタート!ハネムーン・ゲスト移動手配、法人出張・個人旅行を LINE で完結!」)
阪急交通社グループ|子会社合併による経営効率化
2023年、大手旅行代理店の阪急交通社は、100%子会社である阪急阪神ビジネストラベルと阪神トラベル・インターナショナルの2社を合併させました。
このM&Aは、コロナ禍を経て多くの企業が取り組む経営効率化を目的とした、グループ内再編の典型的な事例です。両社は共に業務渡航(BTM)を主たる事業としており、事業内容が重複していました。
今回の合併により、重複していた管理部門などを一本化し、経営資源を最適化。これによりコストを削減し、激化する市場での競争力を強化する狙いがあります。
大手グループが、経営の無駄をなくし、より効率的な組織を作るためにM&Aを活用している好例と言えるでしょう。
(情報引用元:株式会社阪急交通社「子会社2社の合併に関するお知らせ」)
KNT-CT HD|第三者割当増資による経営再建
近畿日本ツーリストなどを傘下に持つKNT-CTホールディングスは、コロナ禍で悪化した財務状況を改善するため、第三者割当増資を実施しました。
これは厳密にはM&Aとは異なりますが、外部資本を受け入れて経営再建を図るという点で関連性の高い動きです。
新たな株主からの資金調達により、事業の立て直しと将来の成長に向けた投資原資を確保しました。
(情報引用元:KNT-CTホールディングス株式会社「債務超過解消に向けた計画について」)
旅行代理店のM&Aを成功に導くための3つのポイント
M&Aは複雑なプロセスであり、成功させるためには慎重な準備と計画が不可欠です。
この章では、旅行代理店のM&Aを成功に導くために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。
M&Aの目的を明確にし、具体的なシナジー効果を描く
なぜM&Aを行うのか?という目的を明確にすることが、全ての始まりです。
売り手であれば「後継者問題の解決」「創業者利益の確保」「従業員の雇用維持」など、何を最優先にしたいのかを整理しましょう。
買い手であれば、どのエリアに進出したいのか、どのような専門ノウハウが欲しいのか、どれくらいの事業規模拡大を目指すのかといった目的を具体化します。
その上で、相手企業と一緒になることで、どのような相乗効果(シナジー)が生まれるのかを具体的に描くことが重要です。
例えば、「当社の顧客基盤と、相手企業のツアー企画力を組み合わせれば、新しい顧客層にアプローチできる」といった具体的なビジョンがあれば、交渉もスムーズに進み、M&A後の成功確率も格段に高まります。
企業文化の統合(PMI)を見据えた計画をする
M&Aのプロセスは、契約が完了したら終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。
M&A後の統合プロセスはPMI(Post Merger Integration)と呼ばれ、その成否がM&A全体の成功を左右すると言っても過言ではありません。
特に重要なのが企業文化の統合です。長年培われてきた仕事の進め方、価値観、従業員同士のコミュニケーションの取り方といった文化は、会社ごとに大きく異なります。
これを無視して無理に一方のやり方を押し付ければ、従業員のモチベーション低下や離職を招きかねません。
契約前から、お互いの企業文化を尊重し、どのように融合させていくかを計画しておくことが大切です。給与体系や人事評価制度といった具体的な制度のすり合わせはもちろん、両社の従業員が円滑にコミュニケーションを取れるような交流の場を設けるといった配慮も、PMIを成功させる鍵となります。
専門家へ早期に相談する
M&Aには、企業価値評価、法務、税務、会計といった高度な専門知識が不可欠です。経営者が本業の傍ら、これら全てを独力で進めるのは現実的ではありません。
有利な条件で交渉を進め、潜在的なリスクを回避するためにも、早い段階で信頼できるM&Aの専門家(M&A仲介会社やアドバイザーなど)に相談することが成功への近道です。
専門家は、豊富な経験とネットワークを活かして、自社に最適な相手企業を探してくれるだけでなく、複雑な交渉や手続きの進行をサポートしてくれます。何より、客観的な第三者の視点から冷静なアドバイスをもらえることは、感情的になりがちなM&Aのプロセスにおいて大きな助けとなるでしょう。相談先の選定も、M&Aの重要なプロセスの一つです。
旅行代理店のM&A・事業承継の相談先

いざM&Aを検討しようと思っても、「一体どこに相談すれば良いのか?」と悩む経営者は少なくありません。M&Aの相談先にはそれぞれ特徴があり、自社の状況や目的に合わせて最適なパートナーを選ぶことが重要です。
ここからは、代表的な3つの相談先をご紹介します。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立ち、中立的な立場でM&Aの成立を支援する専門家です。
豊富な案件情報と専門知識を持ち、相手探しから条件交渉、契約書の作成、クロージングまで、プロセス全体をサポートします。
特に中小企業のM&Aに強く、全国的なネットワークを持つ会社が多いのが特徴です。
手数料は成功報酬型が一般的で、M&Aが成立するまで費用が発生しないケースが多いです。
金融機関(銀行・証券会社)
銀行や証券会社も、取引先企業向けにM&Aの仲介サービスを提供しています。
長年の取引で企業の財務状況や内情をよく理解しているため、信頼関係を築きやすいのがメリットです。
また、M&Aに伴う資金調達(ローンなど)の相談も同時に行える利便性があります。
ただし、M&A専門の部署を持たない支店では、対応できる案件の規模や種類に限りがある場合もあります。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、国が各都道府県に設置している公的な相談窓口です。
後継者不在に悩む中小企業の事業承継を支援することを主な目的としており、無料で相談に乗ってくれます。
地域の商工会議所や金融機関と連携し、後継者探しやM&Aのマッチングをサポートします。
ただし、あくまで中立的な立場での情報提供やマッチングが中心であり、具体的な交渉や手続きの代行は行いません。
| 相談先 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
| M&A仲介会社 | ・専門性が高い ・豊富な案件情報とネットワーク ・プロセス全体をサポート | ・仲介手数料が発生する | ・初めてM&Aを検討する企業 ・最適な相手を広く探したい企業 |
| 金融機関 | ・信頼関係がある ・資金調達の相談も可能 | ・M&A専門の担当者がいない場合がある ・取引金融機関の系列内で話が進みがち | ・メインバンクとの関係が良好な企業 ・M&Aと融資をセットで考えたい企業 |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | ・無料で相談できる ・公的な機関としての安心感がある | ・具体的な交渉や手続きの代行はしない ・大規模な案件には不向きな場合がある | ・まずは情報収集から始めたい企業 ・事業承継を主目的に考える小規模事業者 |
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aを有効な選択肢とし、旅行代理店の未来を拓く

コロナ禍からの回復という明るい兆しが見える一方で、後継者不足やデジタル化の波といった構造的な課題は、多くの旅行代理店にとって待ったなしの状況です。このような変化の激しい時代において、M&Aはもはや他人事ではなく、自社の未来を切り拓くための極めて有効で現実的な経営戦略の一つとなっています。
売り手にとっては長年育ててきた事業と従業員の雇用を守る道となり、買い手にとっては時間とコストをかけずに事業を拡大するチャンスとなるM&Aは、双方にとって明るい未来を実現する可能性を秘めているのです。
もちろん、M&Aを成功させるためには、目的を明確にし、自社に最適なパートナーを見つけ、専門家の力を借りながら慎重にプロセスを進めることが不可欠です。
まずは自社の価値を改めて見つめ直し、未来を切り拓く選択肢としてM&Aを具体的に検討していきましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










