会社売却マニュアル|失敗しないための流れと必要な知識を解説

会社売却の流れや手順がわからず、「何から手をつければ良いのだろう」とお悩みの経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「後継者が見つからない」「会社の将来を考えると、M&Aも選択肢かもしれない」とお悩みの経営者にとって、会社売却は、長年尽くしてくれた従業員の雇用や大切な取引先との関係を守りながら、事業を未来へつなぐための有効な手段となり得ます。
しかし、そのプロセスは複雑で、何から手をつければ良いかわからないという声も少なくありません。
本記事では、会社売却の基本から流れ、メリット・デメリット、価格の算出方法や税金、実際の事例まで、経営者が知っておくべき全知識をわかりやすく解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
そもそも会社売却(M&A)とは? 目的や手法を解説

会社売却は、経営権や事業を第三者に譲渡し、対価を得るプロセスです。
特に中小企業では、後継者問題や成長戦略の一環としてM&Aが注目されています。
ここでは、会社売却の主な目的や手法について解説します。
会社売却の主な目的
会社売却を決断する理由は、経営者の年齢や会社の状況によってさまざまです。主な目的として、以下の点が挙げられます。
| 目的の種別 | 具体的な内容 |
| 事業承継型 | ・後継者が見つからず、親族や社内にも適任者がいない
・廃業を避け、会社と従業員の雇用を守りたい |
| 成長戦略型 | ・大手企業の傘下に入り、資金力やブランド力、販路を活用して事業をさらに成長させたい
・自社だけでは難しい、新たな分野への進出や技術開発を実現したい |
| 創業者利益獲得型 | ・会社を売却してまとまった資金を得て、引退後の生活を豊かにしたい(ハッピーリタイア)
・新規事業を立ち上げるための資金を確保したい |
主な会社売却の手法を紹介
会社売却には複数の手法があり、それぞれ特徴や手続きが異なります。
どの手法を選択するかは、売却の目的や会社の状況によって変わるため、専門家と相談しながら慎重に決定する必要があります。
代表的な手法は以下の通りです。
株式譲渡
株式譲渡は、会社のオーナー経営者が保有する株式を買い手企業に売却することで、会社の経営権を移転させる手法です。
売り手企業の法人格はそのまま存続し、株主が変わるだけなので、事業に関する許認可や従業員との雇用契約、取引先との契約なども原則としてそのまま引き継がれます。
そのため、手続きが比較的簡潔で、中小企業のM&Aにおいて最も一般的に利用されています。
事業譲渡
事業譲渡は、会社そのものではなく、会社が営む事業の一部または全部を買い手企業に売却する手法です。
例えば、複数の事業を持つ会社が、特定の事業だけを切り離して売却するケースなどがこれに当たります。
会社は手元に残したまま、不採算事業の整理や主力事業への集中を図りたい場合に有効です。
ただし、譲渡する資産や負債、契約などを個別に選別して移転させるため、手続きが複雑になる傾向があります。
会社分割
会社分割とは、会社が営む事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に承継させる組織再編行為です。
既存の会社に承継させる「吸収分割」と、新しく設立する会社に承継させる「新設分割」の2種類があります。
特定の事業を切り離して、より大きな企業グループに統合させたい場合などに用いられます。
合併
合併は、複数の会社を一つの会社に統合する手法です。
一つの会社が他の会社を吸収する「吸収合併」と、全ての会社が解散して新しい会社を設立する「新設合併」があります。
合併により、組織やブランドが完全に一つになるため、強力なシナジー効果が期待できますが、手続きは非常に複雑です。
| 手法 | 概要 | 特徴 |
| 株式譲渡 | 売り手企業の株主が保有する株式を買い手企業に譲渡し、経営権を移転させる最も一般的な手法 | ・手続きが比較的簡便
・会社はそのまま存続するため、従業員の雇用や取引先との契約関係を維持しやすい ・包括的に承継するため、簿外債務なども引き継ぐリスクがある |
| 事業譲渡 | 会社の事業の一部またはすべてを買い手企業に譲渡する手法 | ・売りたい事業だけを選択して売却できる
・譲渡する資産や負債を個別に選べるため、買い手は偶発債務などを引き継ぐリスクを避けやすい ・資産や契約の移転手続きが個別に必要となり、手間がかかる場合がある |
| 会社分割 | 会社の事業の一部またはすべてを分割し、新会社または既存の別会社に承継させる手法 | ・事業譲渡と同様に、特定の事業のみを切り離せる
・対価を株式で支払うことも可能 ・手続きが複雑になる傾向がある |
| 合併 | 2つ以上の会社を一つの会社に統合する手法 | ・複数の会社が一体となることで、強力なシナジー効果が期待できる
・すべての権利義務を包括的に承継する ・統合作業(PMI)に多大な労力が必要となる |
【売り手側】会社売却によって得られる5つのメリット
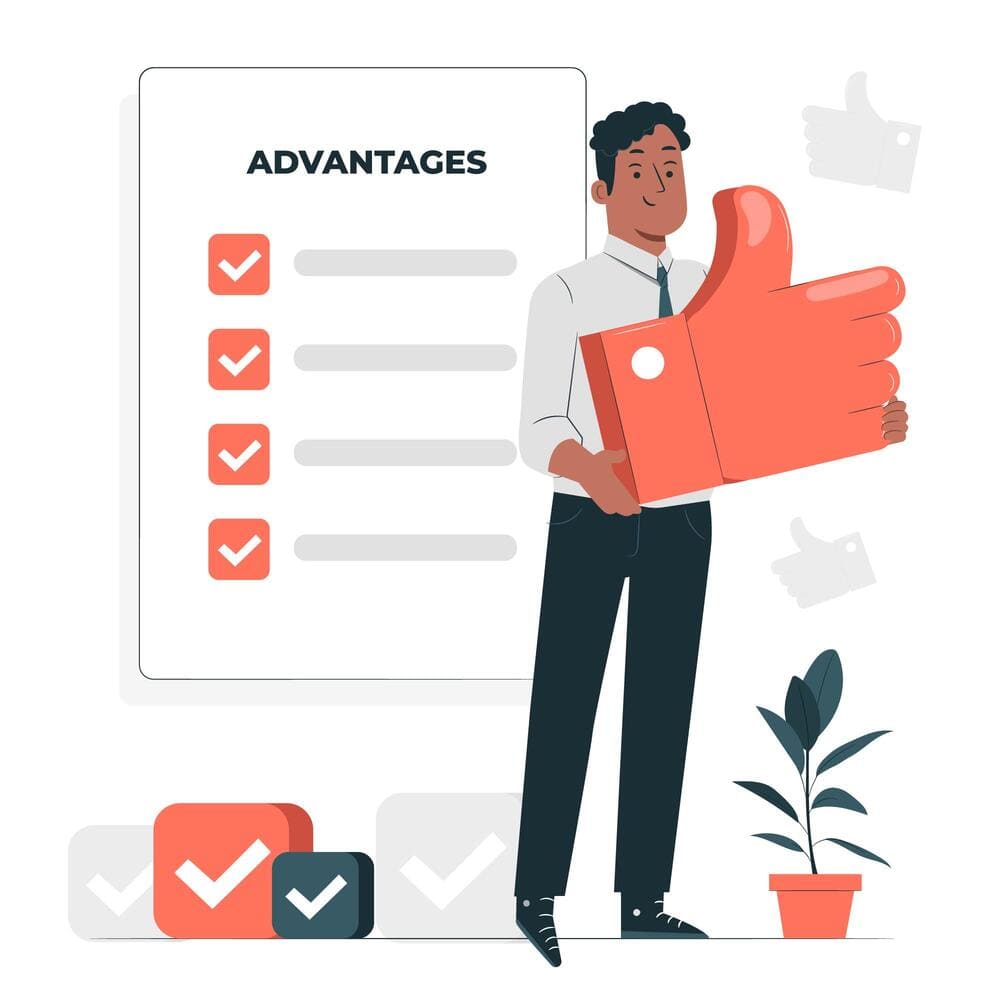
会社売却は、経営者、従業員、そして会社そのものに多くのメリットをもたらす可能性があります。
ここでは、売り手側が得られる代表的な5つのメリットを解説します。
後継者問題を解決できる
売り手側が得られるメリットのひとつは、後継者不在の問題を解決できる点です。
子どもが別の道に進んでいたり、社内に経営を引き継いでくれる人材がいなかったりする場合でも、M&Aによって意欲のある第三者に事業を託せます。
これにより、長年かけて築き上げた会社が存続し、その技術やブランドが未来へと受け継がれていきます。
廃業を選択した場合に失われてしまうものを守れるのは、経営者にとって大きな安心材料です。
創業者利益を獲得できる
会社を売却することで、オーナー経営者は「創業者利益」としてまとまった資金を得られます。
これは、長年の経営努力によって高めてきた企業価値が、現金という形で還元されるものです。
この資金は、引退後の豊かな生活を送るための基盤となるだけでなく、新たな事業を立ち上げるための元手や、個人資産の形成にも活用できます。
会社の価値が正当に評価されれば、多額の売却益を得ることも可能です。
従業員の雇用先を確保できる
廃業を選んだ場合、長年会社を支えてくれた従業員を解雇せざるを得ません。これは経営者にとって非常に辛い決断です。
しかし、会社売却であれば、従業員の雇用は買い手企業に引き継がれるのが一般的です。
従業員は生活の基盤を失うことなく働き続けることができ、経営者は従業員に対する責任を果たせます。
むしろ、大手企業の傘下に入ることで、待遇や福利厚生が改善され、従業員にとってより良い労働環境が実現するケースも少なくありません。
取引先との関係を継続できる
会社が存続することで、これまで信頼関係を築いてきた取引先との関係も継続できます。
廃業となれば取引先に迷惑をかけてしまう可能性がありますが、会社売却であれば事業が継続されるため、取引をそのまま続けられる場合がほとんどです。
サプライチェーンの維持は、地域経済にとっても重要な意味を持ちます。
長年の取引関係を守れることは、経営者としての社会的信用を維持することにもつながります。
大手傘下での事業成長が期待できる
自社だけでは限界があった事業展開も、資金力や販売網を持つ大手企業の傘下に入ることで、大きく飛躍する可能性があります。
新たな設備投資や研究開発、海外展開など、これまで実現できなかった成長戦略を描けるようになります。
自らが育てた事業が、新たな環境でさらに大きく成長していく姿を見届けられることは、創業者にとって大きな喜びとなるでしょう。
| 対象者 | メリット |
| 経営者 | ・後継者不在の問題を解決できる
・創業者利益(売却益)を得られる ・借入金の個人保証や連帯保証から解放される |
| 従業員 | ・廃業を回避し、雇用が維持される
・買い手企業の安定した基盤のもとで、待遇が改善される可能性がある |
| 会社・事業 | ・買い手企業の資金力や販路を活用し、事業が成長できる
・シナジー効果により、企業価値が向上する |
| 取引先 | 安定した取引関係を継続できる |
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
【売り手側】会社売却で注意すべき4つのデメリット

会社売却は多くのメリットをもたらす一方で、当然ながらデメリットやリスクも存在します。
これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、後悔のないM&Aを実現するために不可欠です。
ここでは、特に売り手側が注意すべき4つのデメリットについて、具体的に解説します。
希望の買い手が見つからず、時間がかかる恐れがある
会社売却は、相手があって初めて成立する取引です。
自社の強みや将来性を評価し、かつ従業員や企業文化を大切にしてくれる理想の買い手がすぐに見つかるとは限りません。
交渉が長期化する可能性も念頭に置き、余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。
経営方針の転換により、従業員のモチベーションが低下するリスクがある
経営者が変わることで、社内の雰囲気やルール、評価制度などが変わる可能性があります。
新しい環境に馴染めず、従業員のモチベーションが下がったり、最悪の場合、離職につながったりするリスクもゼロではありません。
従業員の不安を払拭するための丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
希望通りの条件で売却できない場合がある
売り手が希望する売却価格と、買い手が評価する企業価値には、しばしばギャップが生じます。
交渉の結果、希望額を下回る価格での合意となるケースも少なくありません。
価格だけでなく、従業員の雇用維持など、何を最も優先するのか、条件の優先順位をあらかじめ決めておくことが重要です。
取引先や顧客との関係が悪化する恐れがある
経営体制の変更を理由に、長年の取引先や顧客が離れてしまうリスクも考慮すべきです。
特に、前経営者の個人的な信頼関係で成り立っていた取引は、引き継ぎが難しい場合があります。
売却後も円滑な関係が続くよう、買い手と共に丁寧な説明を行う必要があります。
| 注意点 | 具体的な内容 |
| 交渉の長期化 | ・希望の条件に合う買い手がすぐに見つからない場合がある
・交渉が長引き、経営に支障をきたす可能性がある |
| 従業員の動揺 | ・会社売却の情報が漏れると、従業員が不安になり、モチベーション低下や離職につながるリスクがある |
| 条件の不一致 | ・必ずしも希望通りの価格や条件で売却できるとは限らない |
| 経営の自由度 | ・売却後は買い手企業の経営方針に従う必要がある
・一定期間、競合する事業を行えない「競業避止義務」が課されることが多い |
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
【買い手側】会社買収によって得られる5つのメリット

売り手だけでなく、買い手側にも会社買収(M&A)を行う大きなメリットがあります。
買い手の動機を理解することは、自社をより魅力的に見せ、有利な交渉を進めるうえで役立ちます。
以降では、買い手が得られる主なメリットを見ていきましょう。
時間とコストを大幅に削減できる
新規事業をゼロから立ち上げるには、多くの時間とコスト、そして労力がかかります。
人材の採用や教育、技術開発、顧客開拓など、事業が軌道に乗るまでには数年単位の時間が必要です。
M&Aによって既存の会社を買収すれば、これらの経営資源をすべて一度に手に入れることができます。
事業立ち上げにかかる時間とコストを大幅に削減し、迅速に市場へ参入できる点は、買い手にとって最大の魅力の一つです。
事業規模と市場シェアを拡大できる
同業他社を買収することで、買い手は一気に事業規模を拡大し、市場におけるシェアを高めることができます。
スケールメリットを活かして、仕入れコストの削減や生産性の向上を図ることが可能です。
また、これまで進出できていなかった地域への足がかりを得たり、新たな顧客層を獲得したりと、事業領域の拡大にもつながります。
シナジー効果による企業価値の向上が期待できる
シナジー効果(相乗効果)とは、複数の企業が統合されることで、「1+1」が2以上になる効果を生み出すことです。
具体的には、以下のような効果が期待できます。
- 販売シナジー:互いの販売チャネルを相互活用し、売上を伸ばす
- 生産シナジー:生産設備を共有・集約し、コストを削減する
- 技術シナジー:双方の技術やノウハウを組み合わせ、新製品や新サービスを開発する
これらのシナジー効果を最大化することで、企業全体の価値を飛躍的に高めることが可能です。
人材・技術・ノウハウを獲得できる
事業は「人」で成り立っています。
M&Aは、設備や資産だけでなく、その事業を支える優秀な人材や、長年培われた独自の技術、業務ノウハウを獲得する有効な手段です。
特に、専門性の高い業界では、人材獲得を主目的としたM&Aも少なくありません。
サプライチェーンを強化できる
製造業などにおいて、原材料の供給元や製品の販売先を買収することで、サプライチェーン全体を強化できます。
これにより、原材料の安定確保、物流の効率化、顧客ニーズの直接的な把握などが可能です。
川上から川下までの一貫した体制を築くことで、経営の安定化と収益性の向上が期待できます。
| メリットの種別 | 具体的な内容 |
| 時間・コストの削減 | 新規事業をゼロから立ち上げるよりも、既存の会社を買収する方が早く、低コストで市場に参入できる。 |
| 事業規模の拡大 | 同業他社を買収することで、一気に市場シェアを拡大できる(スケールメリット)。 |
| シナジー効果 | 互いの強み(技術、販路、顧客基盤など)を組み合わせることで、1+1が2以上になる相乗効果が期待できる。 |
| 人材・技術の獲得 | 買収を通じて、優秀な人材や独自の技術、ノウハウ、特許などをまとめて獲得できる。 |
| サプライチェーン強化 | 仕入先や販売先を買収することで、原材料の安定確保や販路の強化につなげられる。 |
【買い手側】会社買収によって得られる5つのデメリット

買い手側にも、M&Aに伴うデメリットやリスクは存在します。
売り手としては、これらの買い手の懸念点をあらかじめ理解し、不安を解消するための情報を提供することが、交渉を円滑に進める鍵となります。
買い手側が直面する可能性のある主なデメリットは以下の通りです。
従業員間の価値観や仕事の進め方が衝突し、摩擦が生じる可能性がある
長年異なる環境で働いてきた従業員同士が、すぐに一つのチームとして機能するとは限りません。
企業文化や価値観、仕事の進め方の違いから、現場で混乱や対立が生じる可能性があります。
M&Aの成否は、こうした「人と組織」の統合をいかにスムーズに進めるかにかかっています。
複雑な手続きが必要になる
会社売却は、単なる売買契約ではありません。法律、会計、税務など、多岐にわたる専門知識が必要です。
特に、相手企業の価値やリスクを精査する「デューデリジェンス」は非常に重要なプロセスです。
専門家の知見なくして、適切なM&Aを実行することは困難です。
期待したシナジー効果が得られない可能性がある
M&Aの計画段階で期待したシナジー効果が、必ずしも実現するとは限りません。
市場環境の変化や、統合プロセスの失敗などが原因で、想定したほどの成果が上がらないケースもあります。
「こんなはずではなかった」という事態を避けるため、事前の慎重な分析と実現可能な計画の策定が求められます。
簿外債務・偶発債務を承継する恐れがある
買い手にとって最も怖いリスクの一つが、買収後に予期せぬ債務が発覚することです。
例えば、未払いの残業代や将来発生する可能性のある損害賠償など、決算書には表れない「簿外債務」や「偶発債務」を引き継いでしまう恐れがあります。
デューデリジェンスによって、これらの隠れたリスクを徹底的に洗い出すことが重要になります。
| デメリット | 具体的な内容 |
| 組織文化の衝突 | 異なる企業文化を持つ従業員同士がうまく融合できず、社内に摩擦が生じる可能性がある。 |
| 手続きの複雑さ | デューデリジェンス(買収監査)や契約手続きが複雑で、専門家のサポートが不可欠。 |
| シナジーの不発 | 期待していたほどのシナジー効果が得られず、投資に見合ったリターンを得られないリスク。 |
| 偶発債務のリスク | 買収後に、帳簿には載っていなかった債務(簿外債務)や訴訟リスクが発覚する可能性がある。 |
会社売却の一般的な流れ・手順を9ステップで徹底解説

会社売却は、思い立ってすぐにできるものではありません。
専門家への相談から最終的な引き渡しまで、多くのステップを踏む必要があり、通常は半年から1年以上の期間を要します。
ここでは、M&A仲介会社などの専門家のサポートを受けながら進める場合の、一般的な9つのステップを順を追って解説します。
| フェーズ | ステップ | 主な内容 |
| 準備段階 | 1. 専門家への相談 | M&Aの目的や希望を整理し、仲介会社などの専門家に相談する。 |
| 2. 最適なプランの提案 | 専門家によるヒアリングと分析に基づき、売却戦略の提案を受ける。 | |
| 3. アドバイザリー契約の締結 | 信頼できる専門家と、仲介や助言に関する契約を結ぶ。 | |
| 4. 企業概要書の作成 | 自社の魅力を伝えるための詳細な資料を作成する。 | |
| 交渉段階 | 5. マッチングとトップ面談 | 買い手候補を探し、経営者同士の面談を行う。 |
| 6. 基本合意契約の締結 | 主要な条件について、法的拘束力のない形で合意する。 | |
| 最終段階 | 7. 買収監査(デューデリジェンス) | 買い手が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査する。 |
| 8. 最終契約書の締結 | 最終的な条件を確定し、法的な契約を結ぶ。 | |
| 9. クロージング | 株式の引き渡しと代金の決済を行い、全ての手続きが完了する。 |
ステップ1:専門家への相談
会社売却を考え始めたら、最初のステップとしてM&Aの専門家に相談します。
相談先には、M&A仲介会社、金融機関、事業引継ぎ支援センター、公認会計士、税理士などがあります。
この段階では、自社の現状や売却を考える理由、希望条件などを伝え、会社売却の実現可能性やおおまかな流れについてアドバイスを受けます。
多くの専門機関が無料相談を実施しているため、複数の機関に相談し、比較検討しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
ステップ2:現状のヒアリングと最適なプランの提案
専門家は、経営者との面談を通じて、会社の財務状況、事業内容、強みや弱みなどを詳細にヒアリングします。
この情報をもとに、どのような売却スキーム(株式譲渡、事業譲渡など)が最適か、想定される売却価格はどのくらいか、どのような買い手候補が考えられるか、といった具体的なプランの提案を受けます。
この段階で、売却への意思を固めていきます。
ステップ3:アドバイザリー契約の締結
相談した専門家の中から、信頼できるパートナーを選び、「アドバイザリー契約」または「仲介契約」を締結します。
この契約には、専門家に支払う手数料の体系や金額、業務の範囲、契約期間、秘密保持義務などが定められています。
契約内容を十分に理解し、納得したうえで署名することが重要です。この契約締結をもって、本格的な売却活動がスタートします。
ステップ4:企業概要書の作成
契約後、買い手候補に自社の魅力を伝えるための資料「企業概要書(インフォメーション・メモランダム)」を作成します。
企業概要書は、会社の沿革、事業内容、組織体制、財務状況、事業計画などが詳細に記載された資料です。
企業価値を正しく伝え、買い手の関心を引くための非常に重要な資料であり、専門家と協力しながら慎重に作成を進めます。
ステップ5:マッチングとトップ面談
専門家は、ノンネームシート(社名が特定されない匿名の企業概要)を使って、買い手候補を探します。
関心を示した買い手候補とは秘密保持契約(NDA)を締結したうえで、詳細な企業概要書を開示します。
双方がさらに交渉を進めたいとなれば、経営者同士が直接会って話をする「トップ面談」が設定されます。
ここでは、お互いの経営理念やビジョン、企業文化などを確認し、信頼関係を築くことが目的です。
ステップ6:基本合意契約の締結
トップ面談を経て、双方がM&Aに前向きな意思を持つと確認できたら、主要な条件をまとめた「基本合意書(LOI)」を締結します。
基本合意書には、売却価格、スケジュール、デューデリジェンスの実施、独占交渉権の付与などが盛り込まれています。
一部の条項を除き、法的な拘束力はありませんが、交渉の方向性を固めるための重要な合意です。
ステップ7:買収監査(デューデリジェンス)の実施
基本合意後、買い手は売り手企業に対して「デューデリジェンス(DD)」と呼ばれる詳細な調査を実施します。
弁護士や公認会計士などの専門家チームが、財務、税務、法務、事業など、あらゆる側面から企業の実態を調査し、潜在的なリスクを洗い出します。
売り手は、この調査に誠実かつ迅速に協力する必要があります。ここで大きな問題が発見されると、条件の見直しや交渉の破談につながることもあります。
ステップ8:最終契約書の締結
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な条件交渉を行います。
売却価格や従業員の処遇、引き継ぎの段取りなど、細部にわたる条件を詰め、双方が合意に至れば、「最終契約書(DA)」を締結します。
株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」、事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」がこれにあたります。
共に法的な拘束力を持ち、契約後のM&Aの実行を確約するものです。
ステップ9:クロージング(決済と引き渡し)
最終契約書に定められた条件に基づき、会社の引き渡しと代金の決済を行います。
これを「クロージング」と呼びます。具体的には、株式の譲渡手続きや株主名簿の書き換え、売却代金の振り込みなどが行われます。
クロージングをもって、会社売却に関するすべての手続きが完了し、経営権が正式に買い手に移転します。
会社売却価格はいくら?企業価値評価の基本的な算出方法

経営者にとって最大の関心事の一つが「自分の会社はいくらで売れるのか」という点です。
M&Aにおける価格は、決まった定価があるわけではなく、最終的には当事者間の交渉で決まります。
しかし、その交渉の土台となる企業価値評価の基本的な考え方を知っておくことが大切です。
コストアプローチ
貸借対照表(バランスシート)上の純資産を基準に企業価値を評価する方法です。
帳簿上の資産と負債の差額で計算する「簿価純資産法」と、資産を現在の時価で評価し直して計算する「時価純資産法」があります。
計算がシンプルで分かりやすい反面、会社の将来性やブランド価値といった無形の資産が評価されないという欠点があります。
インカムアプローチ
将来、会社がどれだけの利益(キャッシュフロー)を生み出すかを予測し、それを現在の価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。
代表的な手法に「DCF(Discounted Cash Flow)法」があります。
成長性が高い企業や、独自の技術を持つ企業の価値を評価するのに適していますが、将来予測の精度に結果が大きく依存します。
マーケットアプローチ
事業内容や企業規模が似ている上場企業の株価や、類似のM&A事例での取引価格を参考に、企業価値を類推する方法です。
「類似会社比較法(マルチプル法)」などが代表的です。
市場での客観的な評価を反映できる点がメリットですが、比較対象として適切な会社が見つからない非上場の中小企業には適用が難しい場合があります。
| アプローチ | 考え方 | メリット | デメリット |
| コストアプローチ | 会社の純資産(資産-負債)を基準に価値を算出する。 | 客観性が高く、計算が比較的容易。 | 会社の将来の収益力や無形の価値(ブランド、技術など)が反映されない。 |
| インカムアプローチ | 会社が将来生み出すと期待される収益(キャッシュフロー)を基準に価値を算出する。 | 会社の将来性や成長性を評価に含めることができる。 | 事業計画の精度に評価額が大きく左右され、客観性に欠ける場合がある。 |
| マーケットアプローチ | 類似する上場企業や、過去のM&A事例と比較して価値を算出する。 | 市場の評価が反映されるため、客観性が高い。 | 比較対象となる適切な企業や事例が見つからない場合がある。 |
M&Aの相場は利益の何倍?価格算定方法から高値売却の5つのコツまで徹底解説
会社売却に必要な税金とは

会社を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、それに対して税金が課されます。
税金の種類や税率は、どの手法で売却したかによって大きく異なります。特に2025年からは税制が変更される点もあり、注意が必要です。
ここでは、「株式譲渡」と「事業譲渡」のケースに分けて、かかる税金を解説します。
「株式譲渡」でかかる税金
オーナー経営者が個人として保有する株式を売却した場合、その売却益(譲渡所得)に対して、所得税と住民税が課されます。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
この譲渡所得に対して、合計20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が課されます。
【2025年からの税制改正に注意】
2025年1月からは「ミニマムタックス」制度が導入され、極めて高額な所得を得た個人に対する課税が強化されます。
具体的には、株式譲渡所得を含む所得の合計額が3.3億円を大幅に超えるような場合、実質的な税負担が最大で27.5%(所得税22.5%、住民税5%)程度まで上昇する可能性があります。
高額な売却が想定される場合は、税理士などの専門家と事前に相談することが極めて重要です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
「事業譲渡」でかかる税金
事業譲渡の場合、売却の主体は個人ではなく法人(会社)です。そのため、税金の計算はより複雑になります。
- 法人税:会社が事業を売却して得た利益に対して、法人税等が課されます。税率は会社の規模や所得によって異なりますが、実効税率は約30%〜34%です。
- 消費税:譲渡する資産のうち、建物や機械設備などの課税資産に対しては、消費税が課されます。土地は非課税です。この消費税は買い手が支払いますが、売り手である会社が国に納付する必要があります。
このように、売却手法によって納税者も税率も大きく異なるため、どの手法が自社にとって最適かを判断する際には、税務面からの検討が不可欠です。
会社売却で失敗しないための5つの重要ポイント

会社売却を後悔のない選択とするためには、押さえておくべきいくつかの重要なポイントがあります。
「こんなはずではなかった」と後悔しないために、以下の5つのポイントを常に意識してください。
- 最適な売却タイミングを逃さない
- 自社の強みを磨き、明確にアピールする
- 売却の目的と譲れない条件を明確にする
- 入念な準備と誠実な情報開示
- 信頼できる専門家をパートナーに選ぶ
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ポイント1:最適な売却タイミングを逃さない
会社を高く売るためには、タイミングが重要です。
業績が悪化してから売却を検討し始めると、買い手が見つかりにくくなったり、不利な条件を提示されたりするリスクが高まります。
自社の業績が良い時、そして業界全体が成長している時が絶好の売り時といえます。
経営者の健康状態や年齢だけでなく、市場の動向も見極め、機会を逃さないようにしましょう。
ポイント2:自社の強みを磨き、明確にアピールする
買い手は、自社の成長に貢献してくれる魅力的な会社を探しています。
「独自の技術力」「安定した顧客基盤」「優秀な人材」など、自社の強みは何かを客観的に分析し、磨き上げることが大切です。
企業概要書やトップ面談の場で、具体的なデータやエピソードを交えて明確にアピールできるよう準備しましょう。
自社の価値を正しく伝える努力が、より良い条件での売却につながります。
ポイント3:売却の目的と譲れない条件を明確にする
なぜ会社を売却するのか、その目的を明確にすることがすべての出発点です。
例えば、「創業者利益の最大化」が最優先なのか、「従業員の雇用維持」が絶対条件なのかによって、交渉の進め方や買い手選びの基準は大きく変わります。
売却価格はもちろん重要ですが、それ以外に何を重視するのか、譲れない条件は何かを事前に整理し、優先順位をつけておきましょう。
この軸がぶれてしまうと、交渉の途中で判断に迷い、結果的に不本意な契約を結んでしまうことになりかねません。
ポイント4:入念な準備と誠実な情報開示
M&Aの交渉では、信頼関係が何よりも大切です。
自社にとって不都合な情報(例えば、過去の訴訟リスクや簿外債務など)を隠していると、デューデリジェンスの段階で発覚し、信頼を失って破談になる可能性があります。
入念な準備を行い、誠実な情報開示を心がけることが、結果的に円滑な取引につながります。
ポイント5:信頼できる専門家をパートナーに選ぶ
会社売却の成否は、パートナーとなるM&A専門家の力量に大きく左右されます。
実績や専門性はもちろん、自社の業界に精通しているか、そして何より経営者の想いに寄り添ってくれる担当者かどうかを見極めることが重要です。
複数の専門家と面談し、心から信頼できるパートナーを選びましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
会社売却時の信頼できる相談相手の選び方

会社売却の成否は、パートナーとなる専門家の能力に左右されると言っても過言ではありません。
しかし、M&A仲介会社やコンサルティングファームは数多く存在し、どこに相談すれば良いか迷う経営者も多いでしょう。
ここでは、自社にとって最適なパートナーを見つけるための、5つの選び方のポイントを解説します。
専門性と実績の豊富さ
まず確認すべきは、M&Aに関する専門知識と実績の豊富さです。
これまでの成約件数や、どのような規模・業種の案件を手がけてきたかを確認しましょう。
特に、自社と同じ業界での実績が豊富であれば、業界特有の事情を理解したうえで、的確なアドバイスや買い手候補の紹介が期待できます。
公認会計士や弁護士などの有資格者が在籍しているかどうかも、専門性の高さを判断する一つの指標です。
自社の業界や規模との適合性
M&A仲介会社には、大企業中心のところもあれば、中小企業に特化したところもあります。
自社の規模に合ったサポートを提供してくれる会社を選ぶことが大切です。
また、全国に拠点を持つ会社であれば、地方の企業であっても最適な買い手を見つけ出す幅広いネットワークが期待できます。
料金体系の透明性と妥当性
アドバイザリー契約を締結する前に、料金体系について詳細な説明を受け、十分に理解することが重要です。料金体系は、主に以下のような項目で構成されます。
| 費用項目 | 概要 |
| 相談料 | 初回の相談時に発生する費用。無料の場合が多い。 |
| 着手金 | アドバイザリー契約時に支払う費用。成約しなくても返金されないことが多い。 |
| 中間金 | 基本合意書の締結時など、特定の段階で支払う費用。 |
| 成功報酬 | M&Aが成約した際に支払う費用。「レーマン方式」と呼ばれる、取引金額に応じて料率が変動する方法が一般的。 |
| 月額報酬 | 契約期間中、毎月発生する費用。リテイナーフィーとも呼ばれる。 |
これらの料金がいつ、どのような条件で発生するのか、書面で明確に提示してもらいましょう。料金体系が不透明であったり、説明が曖昧であったりする会社は避けるべきです。
担当者との相性と信頼関係
会社売却は、数ヶ月から1年以上にわたる長い道のりです。
その間、密に連携を取る担当者との相性は、精神的な負担を大きく左右します。
経営者の想いに寄り添い、どんな些細な不安にも親身に耳を傾けてくれるか。
複数の担当者と面談し、「この人になら任せられる」と心から思えるパートナーを見つけましょう。
厳格な情報管理体制とM&A後のサポート
M&Aの情報は、外部に漏れると従業員や取引先に動揺を与え、事業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、専門家が厳格な情報管理体制を敷いているかは、必ず確認すべきポイントです。
秘密保持契約の内容や、具体的な情報の取り扱い方法について確認しましょう。
また、クロージング(売却完了)後の引き継ぎや、経営者の引退後の資産運用など、M&A後のサポート体制が充実しているかも、長期的な視点でパートナーを選ぶうえでの判断材料となります。
| チェックポイント | 確認すべき内容 |
| 専門性と実績 | ・自社と同じ業界・規模のM&A実績が豊富か?
・成功事例だけでなく、どのようなノウハウを持っているか? |
| 業界・規模との適合性 | ・中小企業のM&Aに特化しているか?
・地方の案件にも対応できるネットワークがあるか? |
| 料金体系の透明性 | ・料金体系は明確で分かりやすいか?(例:完全成功報酬型)
・不必要な費用を請求されるリスクはないか? |
| 担当者との相性 | ・親身に話を聞き、何でも相談できるか?
・難しい専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれるか? |
| 情報管理とアフターサポート | ・秘密情報を厳格に管理する体制が整っているか?
・成約後の経営統合(PMI)までサポートしてくれるか? |
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
会社売却(M&A)の事例

実際に会社売却を経験した経営者は、どのような背景で決断し、どのような結果を得たのでしょうか。
ここでは、目的別に3つのM&A事例を紹介します。
事例1:【成長戦略としての事例】スタートアップの大型売却:KDDIによるソラコムの買収
IoTプラットフォームを提供するソラコムは、2017年に約200億円でKDDIに売却されました。創業からわずか2年半での大型M&Aです。
この決断は、ソラコムの経営基盤強化とIoT普及の加速、KDDIのIoT事業拡大という、両社の成長戦略が合致した結果です。
スタートアップが大手企業の傘下に入ることで、技術と経営資源を融合させ、事業成長を加速させた代表的な事例です。
参考:KDDI株式会社『株式会社ソラコムの子会社化について』
事例2:【異業種連携によるシナジー創出】新たな価値を創造するM&A:丸井織物によるミチ(ミチネイル)の事業買収
石川県の伝統的な織物メーカーである丸井織物が、ネイルチップのECサイト「ミチネイル」を運営する株式会社ミチから事業を譲り受けた事例です。
一見すると関連性の低い異業種の組み合わせですが、丸井織物は子会社を通じてデジタルマーケティングに強みを持っています。
一方、ミチはECサイト運営のノウハウを持っていましたが、少人数での運営に限界を感じていました。
このM&Aにより、伝統企業の経営基盤とスタートアップのデジタル技術が融合し、コスト削減や事業成長の加速といったシナジーが創出された事例です。
参考:丸井織物『「ミチネイル」を事業譲受 ーニュースリリース』
事例3:【事業の選択と集中】不採算事業の売却による経営再建:パナソニックのヘルスケア事業売却
パナソニックは事業ポートフォリオの見直しの一環として、ROIC(投下資本利益率)が低くシナジーが見込めないヘルスケア事業を2013年に米国投資ファンドKKRに売却しました。
売却後、同事業は独立し成長を遂げ、パナソニックは株式の一部を保持しつつ、経営資源をコア事業に集中させることで企業価値の向上を実現しました。
参考:Panasonic『パナソニック ヘルスケア株式会社の株式譲渡契約締結および共同持株会社設立に関するお知らせ』
会社売却に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、経営者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 赤字や債務超過でも会社は売却できますか?
- 可能です。
赤字であっても、独自の技術や特許、優れた顧客基盤、将来性のある事業などを保有していれば、買い手が見つかる可能性は十分にあります。
債務超過の場合でも、事業再生の一環としてM&Aが活用されるケースもあります。
重要なのは、自社の持つ潜在的な価値(強み)を正しく把握し、買い手側に的確にアピールすることです。
詳しくは、赤字企業の売却について解説した記事もございますので、そちらも併せてご参照ください。
関連記事:『赤字会社のM&Aは可能?売却できる理由や手法を徹底解説』
Q2. 従業員や取引先には、いつ、どのように伝えれば良いですか?
- 情報開示のタイミングは非常に重要であり、原則として最終契約の締結後です。
早すぎる情報開示は、従業員の動揺や取引先の不安を招き、交渉の妨げになる可能性があります。
M&Aの専門家と相談しながら、最適なタイミングと伝え方を慎重に計画する必要があります。
一般的には、最終契約を締結し、M&Aが確定した段階で、経営者から直接、丁寧に従業員や主要な取引先に説明します。
Q3. 売却後、社長(自分)はどうなりますか?すぐに引退できますか?
- ケースバイケースであり、交渉によって決まります。
円滑な事業の引き継ぎのため、売却後、数ヶ月から数年間は会長や顧問といった形で会社を残し、買い手企業をサポートする「キーマン条項」が盛り込まれることが一般的です。
すぐに引退したい場合は、その旨を交渉の初期段階で伝え、条件を調整する必要があります。
もちろん、買い手企業の傘下の元、譲渡企業の社長として経営を継続する選択肢もあります。
Q4. 相談したら、必ず売却しないといけませんか?
- いいえ、その必要は全くありません。
M&A仲介会社への相談は、あくまで選択肢を検討するための一歩です。
専門家と話をする中で、会社売却以外の道(例えば、親族外承継や事業の立て直し)が見つかることもあります。
M&Aフォースをはじめ、多くの仲介会社では無料相談を実施していますので、まずは気軽に話を聞いてみることから始めてはいかがでしょうか。
M&A仲介会社とは?FAとの違いや選び方・メリットを徹底解説
会社売却の正しい流れを理解し、未来への一歩を踏み出しましょう

会社売却は、決してネガティブな「終わり」ではありません。
それは、経営者自身の新たな人生の、そして会社と従業員の新たな未来を拓くためのポジティブな「始まり」です。
しかし、そのプロセスは複雑であり、成功させるには入念な準備と戦略的な視点、そして信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
この記事で得た知識をもとに、まずは自社の現状を客観的に見つめ直し、M&Aの専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
正しい知識を武器に、会社の未来、そしてご自身の未来のために、最善の一歩を踏み出しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










