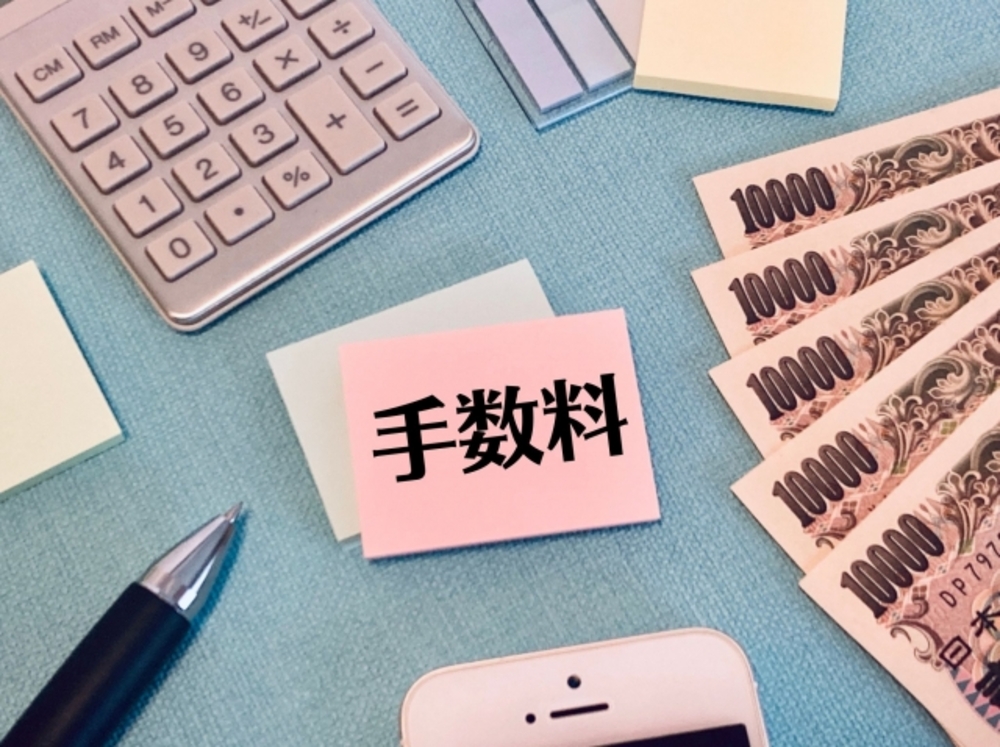株売却益の税率は変わる?2025年からの計算方法と節税策

会社の株式売却(M&A)や保有株式の利益確定を検討する際、税金はいくらかかるのかと気になる方も多いでしょう。売却によって得た利益には譲渡所得税が課され、最終的な手取り額に大きく影響します。
多くの方が株の利益にかかる税金は約20%と認識しているかもしれませんが、2025年の税制改正でミニマムタックスが導入され、高額な売却益を得る方にとっては税負担が変わる可能性があります。
この記事では、株売却益にかかる税金の基本的な仕組み、2025年以降の変更点、具体的な計算シミュレーション、さらにM&Aで活用できる節税のポイントまで、わかりやすく解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
株式売却益にかかる税金の基本

株式を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税や住民税などの税金が課せられます。
しかし、この税金の計算方法は、毎月の給与や事業所得とはまったく異なる特別なルールが適用されます。
まずは、その基本となる申告分離課税の仕組みや具体的な税率の内訳について、正しく理解しましょう。
給与所得とは別で計算される申告分離課税とは?
株式売却で得た利益は、申告分離課税という方式で税額が計算されます。
これは、給与所得や事業所得といった他の所得とは合算せず、株式売却の利益だけを独立させて税金を計算する仕組みです。
なぜなら、高額な役員報酬を得ている経営者が株式売却で大きな利益を得た場合、これらの所得を合算すると、非常に高い税率(累進課税)が適用されてしまうからです。
これでは、健全な投資や事業承継を阻害しかねません。
そこで、株式譲渡所得には他の所得と切り離した一定の税率を適用することで、所得金額の多寡にかかわらず公平な税負担となるよう設計されています。
関連:国税庁『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』
分離課税と総合課税の違い
日本の所得税の課税方式は、主に「申告分離課税」と「総合課税」の2種類に大別されます。
M&Aによる株式売却を考えるオーナー社長にとって、この違いを理解しておくことが重要です。
なぜなら、適用される課税方式によって最終的な手取り額が大きく変動するためです。以下の表で、両者の特徴を比較してみましょう。
| 課税方式 | 特徴 | 主な対象所得 | 税率の仕組み |
| 申告分離課税 | 他の所得と合算せず、その所得だけで独立して税額を計算する。 | 株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得 | 所得の種類ごとに定められた固定税率 |
| 総合課税 | 1年間のすべての対象所得を合計し、その総額に対して税額を計算する。 | 給与所得、事業所得、不動産所得 | 所得が多いほど税率が高くなる累進課税(5%~45%) |
もし、数億円の株式売却益が総合課税の対象となれば、税率45%が適用される可能性があります。しかし、実際には申告分離課税が適用されるため、税率は原則として約20%に抑えられます。
現行税率20.315%の内訳(所得税・住民税・復興特別所得税)
現在、株式売却益に対して課される税率は、合計で20.315%です。
この数字は、3種類の税金を合算したものです。それぞれの内訳を確認しておきましょう。
| 税金の種類 | 税率 | 概要 |
| 所得税 | 15% | 個人の所得に対して国が課す税金です。 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された税金です。所得税額の2.1%(15% × 0.021)が課され、2037年まで続きます。 |
| 住民税 | 5% | 都道府県や市区町村といった地方自治体に納める税金です。 |
| 合計 | 20.315% | – |
これら3つを合計した20.315%が、株式売却益(譲渡所得)全体に対してかかる実質的な税率となります。例えば1億円の利益が出た場合、税額は約2,031万円となります。
【2025年税制改正】富裕層の税率が変わるミニマムタックスとは

株の利益にかかる税金は約20%という認識は、2025年以降、すべての人に当てはまらなくなる可能性があります。
令和5年度税制改正により、高額な所得を得る富裕層を対象とした新たな税制度、通称「ミニマムタックス」が導入されるためです。
これは、数億円規模のM&Aを検討するオーナー社長の引退後の手取り額に直接的な影響を及ぼす、非常に重要な変更点です。
ミニマムタックスが導入された背景?1億円の壁問題とミニマムタックスの概要
ミニマムタックス導入の背景には、1億円の壁と呼ばれる社会的な課題が存在します。これは、年間の所得合計額が1億円を超えたあたりから、所得に占める税金の割合(所得税負担率)が逆に下がっていく現象です。
給与所得が中心の層は所得が増えるほど税率も上がる一方、所得が数十億円に達する富裕層は、所得の多くが株式売却益や配当などの金融所得になります。
この金融所得には一律約20%の分離課税が適用されるため、結果として所得全体に対する税負担率が低くなるのです。
この税率の逆転現象を是正し、課税の公平性を高める目的で導入されるのが、ミニマムタックス(正式名称:所得税の最低税率課税制度)です。
関連:国税庁『グローバル・ミニマム課税の概要等』
ミニマムタックスの対象となる人
ミニマムタックスは、すべての高所得者が対象になるわけではありません。対象となるのは、その年の課税所得が極めて高額な個人です。
具体的には、以下の計算式で算出された金額が、その年に納めるべき所得税額(調整等を考慮する前の金額)を上回る場合に適用されます。
追加で納める税額 = {(所得金額の合計)- 3億3,000万円} × 22.5% – 基準所得税額
この式がプラスになる場合、その差額分が追加で所得税として徴収されます。
簡単に言えば、M&Aによる株式売却などで一時的に所得が跳ね上がり、合計所得金額が数億円から数十億円規模になった場合に、この制度の対象となる可能性が出てきます。
特に売却額が10億円を超えるような大型のM&Aでは、この基準に該当するケースが多くなると予想されます。
ミニマムタックスがM&Aに与える影響
ミニマムタックスが適用されると、株式売却益に対する実質的な税負担率は、現行の20.315%から大きく上昇します。所得金額やその内訳によって変動しますが、所得が数十億円規模になると、実質的な税率が約27.5%に達する可能性も指摘されています。
例えば、30億円の譲渡所得があった場合、単純計算では約2億円もの追加納税が発生するケースも考えられます。これまで税金は約20%という前提で売却後の資金計画や引退後の生活設計を立てていたオーナー社長にとって、この変更は見過ごせません。
2025年以降にM&Aを実行する場合は、必ずこのミニマムタックスの影響を専門家と共に入念にシミュレーションし、売却戦略を立て直す必要があります。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
株売却益にかかる税金の計算方法

税金の基本構造と2025年の改正点を理解したところで、次に実際に手元に残る資金を把握するための具体的な計算方法を見ていきましょう。
計算は大きく2つのステップに分かれます。ご自身の会社の状況を当てはめながら、手順に沿って確認してみてください。
Step1:譲渡所得を算出する(譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用))
税金を計算する大元となるのが譲渡所得です。これは、単に株を売った金額そのものではなく、そこから必要経費を差し引いた儲けの部分を指します。計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 委託手数料など)
例えば、ある銘柄を200万円で売却したとします。
この株の購入代金(取得費)が120万円で、売却時の手数料(譲渡費用)が2,000円だった場合、譲渡所得は以下のようになります。
200万円 – (120万円 + 2,000円) = 79万8,000円
この79万8,000円が、税金計算の基礎となる金額です。
複数の銘柄を売買した場合は、それぞれの取引についてこの計算を行い、年間の合計額を算出します。
Step2:課税譲渡所得金額に税率を掛ける
Step1で儲けにあたる譲渡所得の金額が確定したら、その金額に税率を掛けて最終的な税額を算出します。
これは非常に簡単で、算出した譲渡所得に税率の20.315%を掛けるだけです。
税額 = 譲渡所得 × 20.315%
先ほどの例で計算してみましょう。
譲渡所得は79万8,000円でしたので、税額は以下の通りです。
79万8,000円 × 0.20315 = 16万2,113円 (1円未満は切り捨て)
この16万2,113円が、納めるべき税金の総額となります。
この2つのステップさえ押さえておけば、いつでもご自身で納税額を把握することができます。
【ケース別】計算シミュレーション(売却益1,000万円/1億円/5億円の場合)
ここでは、取得費と譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得(利益)が3つのパターンだった場合に、税額と最終的な手取り額がいくらになるのかをシミュレーションします。ご自身の状況に近いケースを参考に、具体的な金額のイメージをつかんでください。
※ミニマムタックスは考慮しない、現行税率(20.315%)での計算例です。
| 譲渡所得(利益) | 税額(譲渡所得 × 20.315%) | 手取り額(譲渡所得 – 税額) |
| 1,000万円 | 203万1,500円 | 796万8,500円 |
| 1億円 | 2,031万5,000円 | 7,968万5,000円 |
| 5億円 | 1億157万5,000円 | 3億9,842万5,000円 |
表を見ればわかる通り、売却益が増えるにつれて、納税額も数千万円から1億円を超える金額となります。5億円の利益が出た場合、約4億円が手元に残りますが、これはあくまで現行税率での計算です。
2025年以降は、この手取り額がさらに減少する可能性があることを念頭に置く必要があります。
M&A・株式売却で損しないための3つのポイント

M&Aによる株式売却では、売却金額だけでなく、税務戦略が最終的な手取り額を大きく左右します。高額な取引だからこそ、知っているか知らないかで数千万円単位の差が生まれることも少なくありません。
ここでは、オーナー社長が押さえておくべき、税務面に特化した3つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:取得費を証明する書類を準備する
税額計算において重要な要素のひとつが取得費です。
これは株式を取得するために要した費用で、譲渡価額から差し引けるため、取得費が大きいほど譲渡所得(課税対象の利益)が圧縮され、節税につながります。
しかし、この取得費を客観的に証明できなければ、税務署に認められません。
もし証明書類を紛失した場合、概算取得費として売却金額の5%を取得費とみなすルールがあります。
しかし、創業者オーナーの場合、実際の出資額(取得費)は売却額の5%よりはるかに低いことが多く、このルールを使うと本来より多くの税金を支払うことになります。
M&Aの検討を始めたら、まず以下の書類を探し、保全することを優先しましょう。
- 会社設立時の定款
- 株式引受証
- 出資の払い込みがわかる通帳のコピー
- 株主名簿
ポイント2:役員退職金の活用で所得を分散させる
M&Aの実行は、創業者オーナーが経営から退くタイミングでもあります。
この退職という事実を活用し、株式の売却対価の一部を役員退職金として受け取ることで、全体の税負担を軽減できる可能性があります。
株式売却益は譲渡所得ですが、役員退職金は退職所得として扱われ、税制上非常に優遇されています。
| 所得の種類 | 主な税制上のメリット |
| 譲渡所得 | ・分離課税(税率約20%) |
| 退職所得 | ・退職所得控除(勤続年数に応じた大きな非課税枠)
・控除後の金額をさらに2分の1にしてから課税 ・分離課税 |
例えば、5億円で株式を譲渡する代わりに、4億円の株式譲渡+1億円の役員退職金という形で受け取ることで、1億円の部分に優遇された税率が適用され、トータルの税額を抑えることができます。
ただし、不相当に高額な退職金は税務署に否認されるリスクもあるため、金額の設定には専門家との相談が不可欠です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
ポイント3:株式譲渡以外のM&Aスキームも検討する
オーナー社長が会社を売却する際、一般的な方法は株主である個人が保有株式を売却する株式譲渡です。しかし、会社の状況や買い手のニーズによっては、他のM&Aスキームを選択した方が税務上有利になるケースもあります。
各スキームの主な特徴は以下の通りです。
| スキーム | 概要 | 主な税金 | 特徴 |
| 株式譲渡 | 株主が保有する株式を買い手に売却する手法 | 株主個人に対し、譲渡所得税(所得税・住民税で約20%)が課税される | ・手続きが比較的シンプル
・オーナーへの課税が一度で済む |
| 事業譲渡 | 会社が事業の一部または全部を買い手に売却する手法 | 会社に対し、売却益に法人税(約30%)が課税される
オーナーへの利益還元時に追加で配当課税などが発生する |
・売却対象の事業や資産を選択できる
・繰越欠損金と利益を相殺できる場合がある |
| 合併・株式交換など | 会社の組織構造自体を再編する手法 | 組織再編税制の要件を満たせば、課税を将来に繰り延べできる可能性がある | ・税務や法務の要件が非常に複雑
・専門家との綿密な計画が不可欠 |
一般的に、非上場会社のオーナーが引退資金を得る目的では、税負担が一度で済む株式譲渡がシンプルで有利とされています。
しかし、例えば会社に多額の繰越欠損金がある場合は、事業譲渡で利益と相殺することで、法人税負担を軽減する戦略も考えられます。
どの手法が最適か、税理士やM&Aアドバイザーと多角的にシミュレーションすることが重要です。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
株売却益にかかる税金に関する注意点

税金の計算や節税策だけでなく、手続き面にもいくつか注意すべき点があります。
特にM&Aによる株式売却は金額が大きいため、手続きの遅れや誤りが思わぬペナルティにつながることもあります。
確実に手続きを進めるために、以下の3点は必ず押さえておきましょう。
非上場株式の売却は確定申告が必須
M&Aで売却するような非上場会社の株式は、証券会社を通じて売買する上場株式とは異なり、税金が自動で源泉徴収される仕組みがありません。
したがって、株式を売却して1円でも利益(譲渡所得)が出た場合には、売却した年の翌年に、必ず自分自身で確定申告を行い、税金を納付する義務があります。
この申告を忘れると、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課せられます。
M&Aが完了し、売却代金が入金されたら、翌年の確定申告の準備を始めることを忘れないでください。
税金の納付期限と方法(納付が遅れると延滞税が発生)
確定申告によって計算された所得税および復興特別所得税は、原則として確定申告の提出期限と同じ日までに納付する必要があります。
申告・納付期限:株式を売却した年の翌年3月15日
主な納付方法:
- 金融機関や税務署窓口での現金納付
- 指定した預金口座からの振替納税
- クレジットカード納付(別途手数料が必要)
- e-Taxを利用したダイレクト納付
納付が1日でも遅れると、その日数に応じて延滞税が発生します。延滞税の利率は比較的高いため、納税資金はあらかじめ確保し、期限内に必ず納付しましょう。
特に振替納税は、一度手続きをすれば指定日に自動で引き落とされるため、納付忘れを防ぐのに有効です。
住民税の納付は時期がずれる
所得税は翌年3月15日までに納付しますが、住民税はそれとは別のタイミングで納付することになります。
確定申告書を提出すると、その情報が税務署からお住まいの市区町村に共有されます。それに基づき市区町村が住民税額を計算し、翌年6月頃に納税通知書が自宅に送付されてきます。
納付は通常、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて行いますが、一括での納付も可能です。所得税の納税が終わったころに、数千万円規模の住民税の納付書が届くことも珍しくありません。
この支払いを想定せずに売却代金を使ってしまうと、資金繰りに窮する可能性があるため、あらかじめ住民税の納税分も別に取り分けておくなど、計画的な資金管理が不可欠です。
株式売却で利益が出た場合の確定申告

M&Aによる株式売却で利益を得た場合、確定申告は避けて通れない手続きです。
ここでは、申告の要否から具体的な手順、必要書類までをわかりやすく解説します。
手続き自体は税理士に依頼することが多いですが、オーナー自身も全体の流れを把握しておくことで、スムーズな進行につながります。
確定申告が必要なケース・不要なケース
確定申告の要不要は、主に利用している証券口座の種類で決まります。
以下の表でご自身の状況を確認してみましょう。
| 状況 | 確定申告の要不要 | 理由・補足 |
| 特定口座(源泉徴収あり)で利益が出た | 原則、不要 | 証券会社が税金の計算と納税を代行してくれるため。 |
| 一般口座で利益が出た | 必要 | 自分で年間の損益を計算し、申告・納税する必要があるため。 |
| 特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た | 必要 | 証券会社が年間取引報告書を作成してくれるが、申告と納税は自分で行う必要があるため。 |
| 損益通算や繰越控除を利用したい | 必要 | これらの制度は確定申告をすることが適用の条件となるため。 |
| 年間の利益が20万円以下の会社員 | 所得税は不要 | ただし、住民税の申告は別途必要。さまざまな条件があるため注意が必要。 |
確定申告の期間はいつからいつまで?
確定申告書を提出する期間は、法律で定められています。原則として、株式を売却した翌年の2月16日から3月15日までの1カ月間です。
この期間内に、必要な書類を揃えて管轄の税務署に提出しなければなりません。土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。
M&Aの取引は年末に行われることも多いため、申告準備の期間が意外と短いケースもあります。年が明けたら速やかに準備に取り掛かることをおすすめします。
申告に必要な書類と提出方法
非上場株式の譲渡所得を申告する際には、通常の確定申告書に加えて、専用の書類を添付する必要があります。
準備に時間がかかるものもあるため、事前に確認しておきましょう。主な必要書類は、以下の通りです。
- 確定申告書 第一表・第二表
- 確定申告書 第三表(分離課税用):譲渡所得など分離課税の所得を申告するための書類。
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書:売却した株式の情報、譲渡価額、取得費、譲渡費用などを詳細に記入する中心的な書類。
- 本人確認書類:マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証の写しなど。
- その他証明書類:株式譲渡契約書の写し、M&A仲介手数料の領収書など、譲渡価額や譲渡費用を証明する書類。
提出方法には、以下の3つがあります。
- e-Tax(電子申告):自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで提出できます。
- 郵送:管轄の税務署へ郵送します。
- 税務署へ持参:管轄の税務署の窓口へ直接提出します。
株売却益の税率計算が複雑なときは専門家への相談が安心

本記事では、株式売却益にかかる税金の仕組みから2025年の税制改正、具体的な計算方法、節税のポイントまでを解説しました。しかし、実際のM&Aにおける税務は、ここで解説した内容よりもはるかに複雑です。
特に、取得費の正確な算定、役員退職金の適正額、ミニマムタックスの適用シミュレーションなどは、高度な専門知識と経験が不可欠です。
オーナー社長個人の判断で進めてしまうと、思わぬ申告漏れや過大納税につながり、数百万円、数千万円単位で損をするリスクがあります。
会社の売却という、経営者人生の集大成ともいえる重要な決断で後悔しないためにも、必ずM&Aと税務に精通した税理士などの専門家へ早期に相談し、万全の態勢で臨みましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)