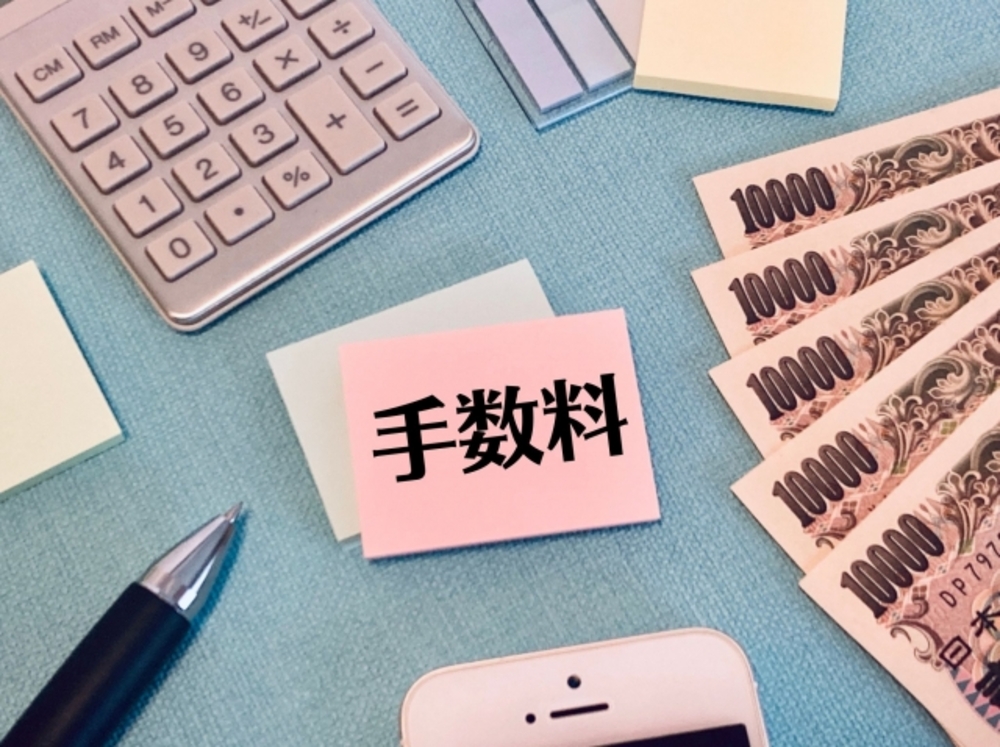事業譲渡と売却の違いとは?手続き・税金から最適な手法を解説

事業承継を検討する際には、事業譲渡や事業売却が主な選択肢となります。
しかし、この2つの手法は似ているようで、手続きの進め方から税金の計算、従業員の引き継ぎまで、多くの点で大きく異なります。この違いを正しく理解しないと、どちらが自社にとって有利な選択なのか判断するのは難しいでしょう。
そこで本記事では、事業譲渡と事業売却の根本的な違いを、手続きや税金の観点から分かりやすく解説します。
さらに、どのような企業がそれぞれの手法に適しているのかを具体例と共に紹介します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業譲渡と売却の基礎知識
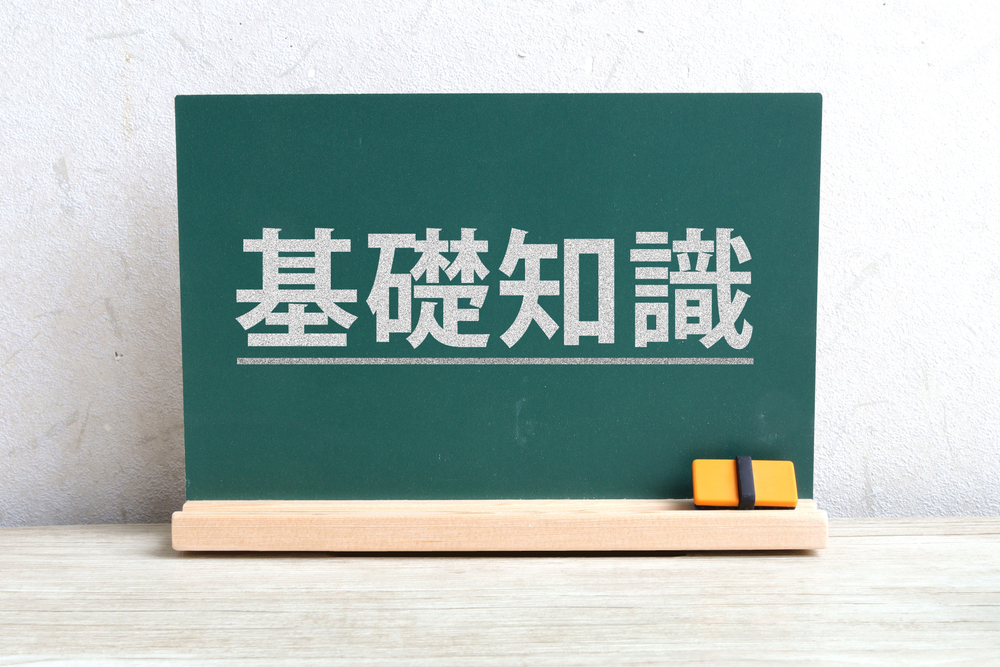
事業承継やM&Aを検討する上で、まず理解すべきなのが事業譲渡と事業売却の基本的な違いです。この2つは言葉が似ていますが、その内容はまったく異なります。
どちらの手法を選ぶかによって、手続きや税金などが大きく変わるため、それぞれの定義を正確に把握することが成功への第一歩となります。
事業譲渡とは?|事業の一部または全部を個別に譲渡する手法
事業譲渡とは、会社そのものではなく、会社が行っている事業の一部または全部を、他の会社に譲り渡すことを指します。会社という器は売り手の元に残り、その中身である事業だけを売買するイメージです。
譲渡する対象には、店舗や工場といった不動産、機械設備・在庫などの有形資産だけでなく、従業員との雇用契約、取引先との契約関係、ブランドのノウハウといった無形資産も含まれます。
事業譲渡の最大の特徴は、譲渡する資産や負債を個別に選べる点にあります。
例えば、複数の事業のうち、不採算部門だけを切り離して売却したい、特定の負債は引き継がず、優良な資産だけを譲渡したいといった柔軟な対応が可能です。
この特性から、事業譲渡は経営のスリム化を図る選択と集中の戦略としても活用されます。
事業売却とは?|会社の経営権を包括的に譲渡する手法
事業売却とは、会社の経営権そのものを、他の会社や個人に譲り渡すことを指します。中小企業のM&Aにおいては、これは会社の株式を譲渡することで行われるのが一般的です。そのため、実務上は株式譲渡とほぼ同義で使われます。
株式を譲渡することで、会社のオーナーが変わり、経営権が買い手に移転します。
事業売却の最大の特徴は、会社の資産や負債、権利関係が丸ごと引き継がれる点です。
事業譲渡のように個別の資産を選ぶことはできませんが、その代わりに、従業員との雇用契約や取引先との契約、事業に必要な許認可などを、原則としてそのまま引き継げます。
会社を一体として存続させたい場合や、後継者不在により会社全体を信頼できる第三者に託したい場合に最も適した手法と言えるでしょう。
事業譲渡と売却の決定的な4つの違い

続いて、事業譲渡と売却の決定的な違いを具体的に見ていきましょう。
ここでは、M&Aの手法を決定する上で特に重要となる、①譲渡対象・②手続き・③契約・許認可・④税金という4つの視点から、それぞれの違いを詳しく比較解説します。
| 比較ポイント | 事業譲渡 | 事業売却 |
| ① 譲渡対象 | 事業の一部または全部(資産・負債などを個別に選択) | 会社の株式(経営権) |
| ② 手続き | 個別承継(手続きが煩雑) | 包括承継(手続きが比較的簡便) |
| ③ 契約・許認可 | 原則、再契約・再取得が必要 | 原則、そのまま引き継がれる |
| ④ 税金(売り手) | 法人税・消費税 | 譲渡所得税(個人株主)・法人税(法人株主) |
違い①:譲渡対象
事業譲渡と売却の根本的な違いは、何を譲渡するのかといった対象です。
- 事業譲渡
事業譲渡の譲渡対象は事業そのものです。前述の通り、どの事業を、どの資産・負債を譲渡するのかを個別に選択できるのが最大の特徴です。これを個別承継と呼びます。
例えば、製造部門は手元に残し、収益性が低い販売部門だけを譲渡する、買い手が不要とする不動産は除外して契約するといった柔軟な対応が可能です。
これにより、売り手は会社を残したまま事業の整理や再編を行えます。 - 事業売却
譲渡対象は会社の株式です。株式を譲渡することで会社の経営権が移転するため、結果として会社の資産・負債・契約関係などすべてが丸ごと買い手に引き継がれます。これを包括承継と呼びます。
良い資産だけでなく、帳簿には現れない潜在的な債務(簿外債務)なども引き継がれるため、買い手側は慎重な調査(デューデリジェンス)が必要です。
違い②:手続きと承認プロセス
譲渡対象の違いは、手続きの複雑さにも大きく影響します。
- 事業譲渡
個別承継であるため、手続きが煩雑になる傾向があります。
譲渡する資産や負債を一つひとつ特定し、詳細なリストを作成しなければなりません。また、事業譲渡は会社の重要な財産を処分する行為にあたるため、原則として株主総会の特別決議(議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成)が必要です。
さらに、会社の債権者保護手続きが求められるケースもあり、全体的に時間と手間がかかります。 - 事業売却
包括承継であるため、手続きは比較的シンプルです。
基本的には、売り手である株主と買い手が株式譲渡契約を締結し、株主名簿を書き換えることで完了します。
株主個人の取引であるため、原則として株主総会の決議は不要です。そのため、事業譲渡に比べて迅速に手続きを進められるのが大きなメリットです。
ただし、ほとんどの中小企業の場合、株式に譲渡制限が付いていることが多く、取締役会または株主総会の承認が必要です。
違い③:契約・許認可の引き継ぎ
従業員や取引先との契約、事業に必要な許認可の扱いは、実務上重要なポイントです。
事業譲渡
会社という器が変わるため、原則としてすべての契約を改めて結び直す必要があります。
- 従業員:買い手企業へ転籍することになるため、個別に同意を得て、雇用契約を再締結する必要があります。
- 取引先:取引基本契約なども、買い手企業の名義で改めて契約を締結し直す必要があります。
- 許認可:建設業許可や宅地建物取引業免許といった事業に必要な許認可は、原則として買い手が新規に取得し直さなければなりません。
事業売却
会社のオーナーが変わるだけで、法人格(会社そのもの)はそのまま存続します。そのため、原則として契約や許認可はそのまま引き継がれます。
- 従業員:雇用主は会社のままなので、改めて同意を得たり再契約したりする必要はありません。
- 取引先:契約もそのまま有効です。
- 許認可:そのまま引き継がれるため、再取得の手間がかかりません。
これが事業売却の大きな利点ですが、取引先との契約書に経営権の移動を通知する義務などを定めた「チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項」が含まれていないか、事前に確認が必要です。
違い④:課税される税金の種類と負担
税金の違いは、手法選択における最も重要な判断材料の一つです。売り手と買い手、それぞれの税負担が大きく異なります。
| 事業譲渡 | 事業売却 | |
| 売り手 | 法人税: 譲渡益に対して課税
消費税: 課税資産(建物・機械など)の売却に対して課税 |
譲渡所得税: 譲渡益に対して課税(個人株主の場合、税率約20%)
法人税: 譲渡益に対して課税(法人株主の場合) ※消費税は非課税 |
| 買い手 | 消費税: 課税資産の購入に対して負担
不動産取得税: 不動産を取得した場合 登録免許税: 不動産登記など |
原則なし(みなし取得課税など例外あり) |
事業譲渡では売り手法人に法人税と消費税が課され、株式譲渡では売り手個人株主に譲渡所得税がかかります。
特に消費税の有無は、取引金額に大きな影響を与えるため注意が必要です。
【ケース別】事業譲渡と売却の選択基準

事業譲渡と売却の違いを踏まえたうえで、より具体的にどのような企業や状況が事業譲渡・事業売却にそれぞれ適しているのかを、代表的な3つのケースに分けて紹介します。
事業譲却が適している3つのケース
事業譲渡の事業を選んで譲渡できるという特性が最大限に活かされるのは、以下のようなケースです。
ケース1:不採算事業やノンコア事業だけを切り離したい
複数の事業を展開している企業が、特定の事業だけを整理したい場合に事業譲渡は最適です。例えば、主力事業に経営資源を集中させるため、関連性の薄い事業を売却したい、長年赤字が続いている部門を切り離し、会社全体の収益性を改善したいといった経営戦略を実現できます。
会社そのものは手放さずに経営を続けながら、事業ポートフォリオを再構築し、企業体質を強化したい場合に有効な手段です。
ケース2:後継者はいるが、一部の事業だけを整理したい
親族や従業員など、すでに事業を引き継ぐ後継者が決まっている場合にも事業譲渡は活用できます。会社のすべてを承継させるのではなく、後継者の負担を減らすために、将来性の見込めない事業は今のうちに整理しておきたい、専門性が高すぎて後継者には運営が難しい事業だけを、専門の会社に譲渡したいといった目的です。
これにより、後継者はより健全で運営しやすい状態で会社を引き継ぐことができ、円滑な世代交代をサポートします。
ケース3:特定の負債やリスクを切り離して譲渡したい
売り手企業に多額の借入金や、帳簿には現れない簿外債務や訴訟リスクなどの潜在的なリスクが存在する場合、買い手は会社を丸ごと引き受ける事業売却をためらうことがあります。
このような状況で、買い手が求める優良な事業や資産だけを切り出して譲渡するのが事業譲渡です。売り手にとっては事業を現金化でき、買い手にとっては不要なリスクを遮断できるため、双方にとってメリットのある取引が成立しやすくなります。
事業売却が適している3つのケース
事業売却の会社を丸ごと、スムーズに引き継げるという特性が活かされるのは、以下のようなケースです。
ケース1:後継者不在で、会社をそのままの形で残したい
経営者が高齢で引退を考えているものの、親族や社内に適任の後継者が見つからない場合に、事業売却は最も有力な選択肢となります。廃業を選べば従業員は職を失い、取引先にも迷惑がかかりますが、事業売却なら会社を信頼できる第三者に託すことが可能です。
これにより、従業員の雇用を守り、取引関係を維持し、長年築き上げてきた社名やブランドを後世に残せます。経営者自身も、創業者利益を確保し、引退後の生活資金に充てられます。
ケース2:許認可や重要な契約をスムーズに引き継ぎたい
建設業、運送業、不動産業など、事業運営に国や自治体の許認可が必要な業種では、事業売却が圧倒的に有利です。事業譲渡の場合は買い手が許認可を新規に取得し直す必要がありますが、事業売却なら法人格がそのままなので、許認可も自動的に引き継がれます。
また、多数の従業員や取引先との契約を個別に結び直す手間もかかりません。事業を一日も止めることなく、スムーズに経営を引き継ぎたい場合には、事業売却が最適な方法です。
ケース3:ブランドやノウハウなど無形資産の価値が高い
帳簿上の資産額はそれほど大きくなくても、長年の経営で培ったブランド力、独自の技術、優れたノウハウ、優良な顧客リストといった目に見えない価値(のれん)が高い企業は、事業売却が適しています。
これらの無形資産は、個別の事業だけを評価する事業譲渡よりも、会社全体を評価する事業売却の方が価値として認められやすく、結果としてより高い価格で売却できる可能性があります。会社の真の価値を正当に評価してもらい、譲渡対価を最大化したい場合に有効です。
事業譲渡・売却における企業価値(価格)の決め方

企業価値(価格)を算定するには、専門的な評価方法が用いられます。
最終的な譲渡価格は、買い手との交渉によって決まりますが、その交渉の土台となる企業価値評価には、大きく分けて3つのアプローチがあります。
どの方法が絶対的に正しいというわけではなく、会社の特性に応じて複数の方法を組み合わせて総合的に評価するのが一般的です。
| アプローチ | 考え方 | 特徴 | 主な評価方法 |
| コストアプローチ | 会社の純資産(資産-負債)に着目 | ・客観性が高い
・将来の収益性を反映しにくい |
簿価純資産法、時価純資産法 |
| インカムアプローチ | 会社が将来生み出すと期待される収益やキャッシュフローに着目 | ・会社の将来性を評価に反映できる
・事業計画の精度に依存する |
DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法 |
| マーケットアプローチ | 類似する上場企業や過去のM&A事例と比較 | ・市場の評価を反映できる
・類似企業や事例を見つけるのが難しい場合がある |
類似会社比較法(マルチプル法) |
コストアプローチ(純資産価額法など)
コストアプローチは、会社の貸借対照表(B/S)に記載されている純資産(総資産から総負債を差し引いた額)を基準に企業価値を評価する方法です。
特徴:
客観的な会計帳簿を基にするため、評価の根拠が明確でわかりやすいのが特徴です。特に、歴史のある中小企業や、不動産などの有形資産を多く保有する会社の評価に適しています。代表的な手法に簿価純資産法や、資産を時価で評価し直す時価純資産法があります。
注意点:
このアプローチは過去から現在までの蓄積を評価するため、将来の収益力やブランド、技術力といった目に見えない価値が価格に反映されにくいという側面があります。
インカムアプローチ(DCF法など)
インカムアプローチは、会社が将来にわたって生み出すと予測される収益(キャッシュフロー)を基準に企業価値を評価する方法です。つまり、この会社を買収すれば、将来どれくらいの利益を得られるかという収益力に着目した考え方です。
特徴:
将来の成長性や収益性を評価に織り込めるため、IT企業やスタートアップなど、現在は資産が少なくても将来の大きな成長が見込まれる企業の評価に適しています。代表的な手法として、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて計算するDCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法があります。
注意点:
評価の根拠が将来の事業計画になるため、その計画の精度によって評価額が大きく変動します。計画が楽観的すぎると過大評価に、悲観的すぎると過小評価になる可能性があり、客観性の担保が難しいという側面も持ち合わせています。
マーケットアプローチ(類似会社比較法など)
マーケットアプローチは、株式市場やM&A市場において、評価対象の会社と似たような業種・規模の会社が、どのくらいの価格で取引されているかを参考に企業価値を評価する方法です。
特徴:
市場での客観的な評価を基準にするため、説得力が高い評価方法と言えます。上場している類似企業の株価や、過去のM&A事例などを参考に、類似会社比較法(マルチプル法)といった手法が用いられます。
注意点:
中小企業の場合、比較対象となる類似の上場企業や、条件が近いM&Aの取引事例を見つけること自体が非常に難しいという大きな課題があります。そのため、他のアプローチと組み合わせて補助的に用いられることが多くなります。
譲渡と売却の違いを理解し、最良の選択へ

会社や事業の譲渡・売却は、経営者にとって非常に大きな決断です。
どちらの手法が最適かは、会社の状況、経営者の方が何を最も重視するかによって大きく異なります。
手続きの簡便さ、税負担の軽さ、従業員の雇用の維持、特定の事業の存続など、優先順位を明確にすることが、後悔のない選択をするための第一歩です。
今回ご紹介した知識を基に、まずは自社の状況を整理してみてください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)