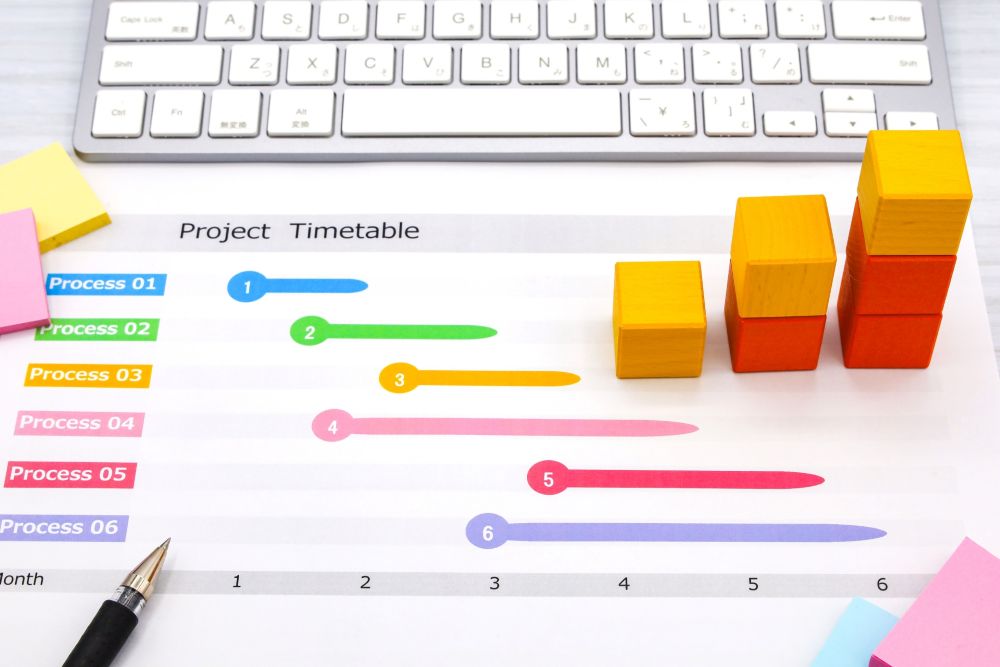【全9ステップ】M&Aのプロセスとは?相談からクロージングまでの流れを徹底解説
 M&Aプロセスとは、企業の合併・買収において相談から最終的な決済完了まで進める一連の手続きです。
M&Aプロセスとは、企業の合併・買収において相談から最終的な決済完了まで進める一連の手続きです。
後継者不在や事業拡大を検討する中小企業経営者にとって、正しいプロセスの理解は成功への第一歩となります。
本記事では、M&Aの全9ステップを具体的に解説し、円滑に進めるポイントや注意点もお伝えします。
M&Aによる事業承継や新規事業参入を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ステップ1:相談

M&Aの相談先には、M&A仲介会社(FA)、金融機関、商工会議所、弁護士、公認会計士、税理士などがあります。
特に専門性のあるM&A仲介会社は、クロージングまで一貫してサポートする体制が整っている点が強みです。
無料相談を活用し、実績や対応実例、料金体系を比較しながら、信頼できるパートナーを選定しましょう。
相談時には、自社の課題や希望条件、将来的なビジョンなどを整理し、専門家と建設的な対話を行うことが成功への第一歩です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aの目的を明確にする(事業承継、成長戦略など)
M&Aのプロセスを始める前に、なぜM&Aを行うのかという目的を明確にすることが重要です。
主な目的としては、以下のようなものが挙げられます。
| 目的の分類 | 具体的な目的の例 |
| 事業承継 | 後継者不在問題を解決し、従業員の雇用と事業を守りたい。 |
| 成長戦略 | 新規事業へ参入し、事業の多角化を図りたい。 |
| 同業他社を買収し、市場シェアを拡大したい。 | |
| 特定の技術やノウハウを獲得し、競争力を強化したい。 | |
| 創業者利益の獲得 | 会社を売却し、引退後の生活資金や新規事業の資金を得たい。 |
| 経営の安定化 | 大手企業の傘下に入り、経営基盤を安定させたい。 |
目的が曖昧なまま進めてしまうと、M&Aを行うこと自体が目的化してしまいかねません。
M&Aはあくまで目的を達成するための「手段」であるということを常に意識することが重要です。
専門家(M&A仲介会社・FA)へ相談するメリット
M&Aの目的が定まったら、次は専門家への相談を検討します。
M&Aには高度な法務・財務・税務の知識が必要であり、自社だけでプロセスを進めるのは現実的ではありません。
M&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)といった専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
| メリット | 具体的な内容 |
| 専門知識の活用 | 複雑な法務・税務手続きや企業価値評価を正確に行える。 |
| ネットワークの活用 | 専門家が持つ独自のネットワークから、最適な相手候補を見つけられる。 |
| 交渉の円滑化 | 相手方との交渉を代行し、客観的な立場で条件調整を進めてくれる。 |
| 時間の節約 | 煩雑な手続きや資料作成を任せることで、経営者は本業に集中できる。 |
| 情報管理の徹底 | 厳格な情報管理体制のもと、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられる。 |
無料相談で確認すべき事項と仲介会社の選び方
多くのM&A仲介会社が無料相談を実施しており、M&Aを具体的に進めるかどうか判断するための有効な機会です。無料相談では、自社の悩みや希望を率直に伝え、専門家からの客観的な意見を聞くことができます。
無料相談では、以下の点を確認しましょう。
| 確認項目 | チェックするべきポイント |
| 実績と専門性 | 自社の業種や規模に近いM&Aの成約実績は豊富か。 |
| 担当コンサルタントはどのような経験を持っているか。 | |
| 料金体系 | 料金はいつ、どのくらい発生するのか(着手金、中間金、成功報酬など)。 |
| 料金体系は明確で、納得できるものか。 | |
| サポート範囲 | 相手探しからPMI(経営統合)まで、どこまでサポートしてくれるのか。 |
| 相性 | 担当コンサルタントは信頼でき、何でも相談できる相手か。 |
信頼できる仲介会社を選ぶには、これらの質問に真摯かつ具体的に回答してくれるかを見極めることが大切です。また、特定の業種や事業規模に強みを持っているか、担当者との相性は良いかといった点も重要な選定基準となります。
信頼できる仲介会社の選び方や、FAとの違いなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。自社に最適な相談先選びの参考にしてください。
ステップ2:現状のヒアリング・ご提案

専門家への相談を経て、M&Aを本格的に検討する段階に進むと、次に行われるのが現状のヒアリングと具体的な提案です。
このステップでは、M&Aの専門家が会社の状況を深く理解し、最適なM&Aの形を模索します。会社の価値を正しく評価し、目的に沿った戦略を立てるための重要なプロセスです。
経営状況や事業内容に関するヒアリング
M&A仲介会社は、企業の価値を正しく評価し、最適な相手先を見つけるために、経営状況や事業内容について詳細なヒアリングを行います。これは、会社の健康診断のようなものであり、強みだけでなく、課題やリスクも正確に把握することが目的です。
具体的には、決算書や事業計画書などの資料を基に、以下のような項目について確認します。
- 事業内容:どのような製品やサービスを提供しているか、ビジネスモデル、業界での立ち位置など
- 財務状況:過去数年分の決算書を基にした収益性、資産状況、借入金の状況など
- 組織体制:役員構成、従業員数、組織図、キーパーソンとなる人材について
- 許認可・知的財産:事業に必要な許認可、保有する特許や商標など
これらの情報を誠実かつ正確に提供することで、より精度の高い企業価値評価や、ミスマッチの少ない相手企業の選定につながります。
M&Aの目的・希望条件の整理
ヒアリングと並行して、改めてM&Aの目的や希望条件を整理します。ステップ1で明確にした目的に加え、より具体的な条件を専門家と一緒に詰めていく作業です。
例えば、以下のような項目について希望を整理します。
| 項目 | 具体的な希望条件の例 |
| 希望売却価格 | 最低限確保したい金額、希望する金額 |
| 従業員の雇用 | 全員の雇用維持を絶対条件とするか |
| 取引先の維持 | 主要な取引先との関係を継続してほしいか |
| 売却後の経営関与 | 一定期間、引継ぎのために会社に残るか、すぐに退任したいか |
| 会社の屋号 | 思い入れのある社名を残したいか |
すべての希望が通るとは限りませんが、譲れない条件と、交渉の余地がある条件を明確に区別しておくことが、後の交渉をスムーズに進める上で重要です。
専門家はこれらの希望条件を踏まえ、最適なM&Aスキームや交渉戦略を検討します。
企業価値の簡易算定と最適なM&Aスキームの提案
ヒアリングした内容と希望条件を基に、M&Aの専門家は企業価値の簡易算定(バリュエーション)を行います。
これは、会社がいくらで売れるのかの目安を知るための重要なプロセスです。企業価値評価には、純資産を基準にする方法や、将来の収益性を基にする方法など、さまざまなアプローチがあります。
この簡易算定の結果と、オーナーの希望を踏まえて、最適なM&Aスキーム(手法)が提案されます。中小企業のM&Aでよく用いられるスキームは以下の通りです。
| M&Aスキームの例 | 特徴 |
| 株式譲渡 | 会社の経営権を包括的に譲渡する最も一般的な手法。手続きが比較的簡便。 |
| 事業譲渡 | 会社の一部または全部の事業を選択して譲渡する手法。不採算事業の切り離しなどに活用される。 |
| 会社分割 | 会社の一部または全部の事業を切り離し、新設または既存の会社に承継させる手法。 |
| 合併 | 複数の会社が1つの会社になる手法。シナジー効果を追求しやすい。 |
どのスキームを選択するかによって、税金や手続きが大きく異なるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に決定する必要があります。
ステップ3:ご契約

ヒアリングと提案内容に納得した場合、正式にM&A仲介会社との契約を締結します。契約段階では秘密保持と業務委託の2つの契約を結ぶのが一般的です。
特に料金体系については後のトラブルを避けるため、詳細まで確認しておくことが重要です。
秘密保持契約(NDA)の締結
M&Aプロセスでは企業の機密情報を多数開示するため、情報漏洩防止を目的とした秘密保持契約の締結が必要不可欠です。
秘密保持契約で保護される主な情報:
- 財務情報(売上・利益・資金繰り状況)
- 顧客情報(主要取引先・契約内容)
- 技術情報(特許・ノウハウ・開発計画)
- 人事情報(組織体制・人件費・労働条件)
- M&A検討事実そのもの
秘密保持契約には、情報の使用目的、開示範囲、保持期間、違反時の損害賠償などが明記されます。仲介会社だけでなく、その後のプロセスで関与するすべての関係者(買い手候補、専門家等)との間でも同様の契約締結が必要となります。
情報管理体制が整っていない仲介会社との契約は避け、セキュリティ対策についても事前に確認しましょう。
M&A提携仲介契約の締結と確認すべきポイント
秘密保持契約に続き、M&A仲介サービスの詳細を定めた提携仲介契約を締結します。この契約は、仲介会社が提供するサービスの範囲や役割、そして報酬について定めた重要な契約です。
契約を締結する際には、以下のポイントを必ず確認しましょう。
契約書で確認すべき主要項目:
| 項目 | 確認ポイント | 注意点 |
| 業務範囲 | 企業価値算定・マッチング・交渉支援の範囲 | 追加業務の費用発生条件 |
| 契約期間 | 専属契約期間・自動更新条項 | 途中解約の条件・違約金 |
| 報告義務 | 進捗報告の頻度・内容 | 重要事項の報告タイミング |
| 成約基準 | 成約の定義・成功報酬の発生条件 | 基本合意時点での報酬有無 |
| 免責事項 | 仲介会社の責任範囲・免責条件 | 損害発生時の責任分担 |
これらの内容を十分に理解し、納得した上で契約することが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。
料金体系(着手金・中間金・成功報酬)の確認
M&A仲介会社の料金体系は複雑で、後からトラブルとなるケースが散見されます。契約前に料金体系を詳細まで理解し、総費用を試算しておくことが重要です。
M&A仲介会社の主な料金体系は、以下のような料金があります。
| 料金の種類 | 発生タイミング | 概要 |
| 着手金 | 提携仲介契約時 | M&Aの成否に関わらず、業務に着手する際に支払う費用。無料の会社も多い。 |
| 中間金 | 基本合意契約の締結時 | M&Aの相手候補と基本的な条件で合意した際に支払う費用。成功報酬制も導入している場合、中間金がないケースもある。 |
| 成功報酬 | 最終契約の締結時 | M&Aが最終的に成立した際に支払う費用。譲渡価格などに応じて算出されることが多い(レーマン方式など)。 |
レーマン方式とは、取引金額に応じて一定の料率を掛けて算出する方法です。料金体系は仲介会社によって大きく異なるため、事前に詳細な説明を受け、総額でどのくらいの費用がかかるのかを把握しておくことが不可欠です。
ステップ4:企業概要書の作成

M&A提携仲介契約を締結し、本格的に相手探しを始める前に、自社の魅力を買い手候補に伝えるための資料を作成します。それが企業概要書(インフォメーション・メモランダム、IM)です。
この資料の出来栄えが、買い手候補の関心度や、その後の交渉に大きく影響を与えるため、非常に重要なステップとなります。
企業概要書とは
企業概要書とは、買い手候補がM&Aを検討する上で必要となる会社の情報を網羅的にまとめた、いわば会社の履歴書のようなものです。通常、M&A仲介会社が売り手企業から提供された情報やヒアリング内容を基に作成します。
この資料は、ノンネームシートで関心を示した買い手候補に対して、秘密保持契約を締結した上で開示されます。買い手は企業概要書を見て、M&Aの検討を本格的に進めるかどうかを判断するため、その内容は非常に重要です。
正確であることはもちろん、自社の魅力が最大限に伝わるように作成する必要があります。
企業概要書に記載する主な内容
企業概要書には、買い手候補が判断を下すために必要な情報が網羅的に記載されます。客観的なデータだけでなく、自社の強みや将来性といった定性的な魅力も伝えることが重要です。
具体的には、以下のような内容が含まれます。
| 記載項目のカテゴリ | 主な内容 |
| 会社概要 | 沿革、株主構成、役員構成、組織図、事業拠点など |
| 事業内容 | 製品・サービスの詳細、ビジネスモデル、市場での立ち位置、許認可など |
| 財務情報 | 過去数年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)、事業計画など |
| 定性情報 | 企業の強み・弱み、経営理念、企業文化、従業員の状況など |
| 譲渡条件 | 希望する譲渡価格、M&Aスキーム、その他希望条件など |
自社の強みや魅力を効果的に伝えるための分析
単に情報を羅列するだけでは、自社の魅力は十分に伝わりません。M&A仲介会社と協力し、自社の強みを客観的に分析し、買い手にとってどのようなメリットがあるのかを明確にすることが重要です。
例えば、高い技術力が強みであれば、それがどのように収益に繋がっているのか、将来どのような発展が見込まれるのかを具体的に示します。また、地域での高い知名度が強みであれば、それが安定した顧客基盤を形成している証拠であることをアピールします。
このように、強みを買い手のメリットに翻訳して伝えることで、企業価値を最大化できます。
企業価値評価の方法やポイントについて詳しく知りたい方は、下記の記事をあわせてご覧ください。
ステップ5:マッチング・トップ会談

企業概要書完成後、買い手候補の選定とアプローチを開始します。適切な候補企業の選定は M&A成功の鍵を握る重要なプロセスです。
仲介会社のネットワークを活用し、戦略的な相手先の発掘からトップ同士の面談まで、段階的にマッチングを進めていきます。
譲渡先候補企業のリストアップと選定(ロングリスト・ショートリスト)
買い手候補の選定は2段階のアプローチで進めます。まずは幅広い視点で候補企業をリストアップし(ロングリスト)、その後詳細な検討により優先順位を決定します(ショートリスト)。
ロングリスト作成の観点:
- 同業他社(水平統合)
- 関連業界(垂直統合)
- 投資ファンド
- 海外企業
- 異業種企業(多角化)
ロングリストでは通常50〜100社程度の候補企業を抽出し、各社の事業戦略や買収方針について調査します。公開情報や仲介会社の独自ネットワークを活用し、M&A検討の可能性を評価します。
ショートリストでは以下の評価基準により10〜20社程度に絞り込みます。
| 評価項目 | 重要度 | 評価基準 |
| 戦略的適合性 | 高 | 事業シナジーの創出可能性 |
| 財務力 | 高 | 買収資金の調達能力 |
| 企業文化 | 中 | 経営理念・風土の適合性 |
| 意思決定スピード | 中 | 買収検討のスピード感 |
| 地理的要因 | 低 | 事業拠点の近接性 |
選定過程では売り手企業の希望条件も重視し、価格面だけでなく従業員処遇や事業継続方針についても評価します。
ノンネームシートによる候補企業への打診
ショートリストに掲載された候補企業に対し、具体的なアプローチを開始します。
しかし、この段階ではまだ企業名が特定されないように、ノンネームシートと呼ばれる匿名の資料を用いて打診を行います。
ノンネームシートには、業種、事業エリア、売上規模、譲渡理由など、企業が特定されない範囲の情報が記載されています。候補企業がこのノンネームシートを見て関心を示した場合に限り、次のステップへと進みます。
トップ面談の目的と事前準備
候補企業から関心が示され、秘密保持契約(NDA)を締結した後、経営者同士が直接顔を合わせるトップ面談が設定されます。トップ面談は、数字や資料だけでは分からないお互いの経営理念や人柄、企業文化などを理解し、信頼関係を築くための重要な機会です。
面談に臨む前には、M&A仲介会社と協力して、相手企業の情報を十分に研究し、質問事項や伝えたいことを整理しておくことが成功の鍵となります。
トップ面談で確認すべき事項と注意点
トップ面談では、条件交渉ではなく、相互理解を深めることに主眼を置きます。確認すべき事項としては、以下のような点が挙げられます。
- 相手企業の経営理念や将来のビジョン
- M&Aを通じて何を実現したいのか
- 自社の従業員や事業をどのように扱ってくれるのか
- 経営者の人柄や価値観
注意点として、この場で安易に譲渡価格などの具体的な条件を約束しないことが重要です。あくまで、お互いが将来のパートナーとしてふさわしいかを見極める場であると認識しましょう。
ステップ6:基本合意契約締結

トップ面談で相互の意向が一致した場合、基本的な取引条件について合意する基本合意契約を締結します。法的拘束力は限定的ですが、その後の詳細交渉の基礎となる重要な契約です。
独占交渉権の設定により、買い手候補は安心してデューデリジェンスに臨めます。
基本合意書(LOI)の役割と法的拘束力の有無
基本合意書(LOI:Letter of Intent)は、M&A取引の基本条件について両当事者が合意したことを確認する文書です。最終契約締結に向けた中間地点として位置付けられ、その後の交渉の指針となります。
基本合意書の法的拘束力は、項目により異なります。
法的拘束力のある条項:
- 秘密保持義務の継続
- 独占交渉権の付与
- デューデリジェンスへの協力義務
- 誠実交渉義務
法的拘束力のない条項:
- 譲渡価格
- 譲渡対象(株式・事業の範囲)
- クロージング条件
- 取引実行スケジュール
- 基本合意書に盛り込まれる主要な条件(譲渡価格、スケジュール等)
価格等の基本条件は「現時点での合意」であり、デューデリジェンス結果により変更される可能性があります。ただし、著しい条件変更は信義則に反する場合もあるため、慎重な検討が必要です。
この区別を正しく理解し、誤解のないように記載されているか、契約書をじっくり確認しましょう。
独占交渉権の重要性と設定期間
買い手にとって、基本合意書で最も重要な条項の一つが独占交渉権です。これは、一定期間、売り手が他の候補とM&A交渉を行うことを禁止する権利です。
買い手候補は多額の費用をかけてデューデリジェンスを実施するため、その期間中は他の候補先との交渉を停止することを売り手に求めます。
独占交渉権は、買い手が安心してデューデリジェンスに臨むために不可欠な条項です。期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度で設定されます。
ステップ7:買収監査(デューデリジェンス)

基本合意契約締結後、買い手候補による本格的な企業調査(デューデリジェンス)が開始されます。財務・法務・税務・事業等の多角的な調査により、投資リスクを詳細に検証する重要なプロセスです。
売り手としては誠実な情報開示により、スムーズな調査進行と信頼関係の構築を図ります。
デューデリジェンスの目的と主な調査内容
デューデリジェンスの主な目的は、売り手企業の価値やリスクを正確に把握することです。
基本合意までの段階では開示されていなかった詳細な情報を調査し、買収対象として問題がないか、将来的なリスクが潜んでいないかなどを徹底的に洗い出します。
調査は多岐にわたり、それぞれの分野の専門家(弁護士、公認会計士など)が担当します。
| デューデリジェンスの種類 | 主な調査内容 |
| 財務DD | 収益性、財政状態の分析、簿外債務の有無、キャッシュフローの状況 |
| 法務DD | 契約関係、許認可、訴訟リスク、知的財産権、コンプライアンス体制 |
| 税務DD | 税務申告の適正性、過去の税務調査の状況、税務リスクの有無 |
| ビジネスDD | 事業の将来性、市場環境、競合優位性、顧客・取引先との関係 |
| 人事DD | 人員構成、労働条件、退職金制度、キーパーソンの存在、労務リスク |
| IT・システムDD | システムの現状、セキュリティ、システム統合の実現可能性とコスト |
各分野の専門家チームが並行して調査を実施し、全体で6〜8週間程度の期間を要します。調査結果は買い手候補の投資委員会等で検討され、最終的な買収判断が下されます。
売り手として準備・提出すべき資料一覧例
デューデリジェンスの効率的な進行には、売り手による適切な資料準備が不可欠です。要求資料は数百項目に及ぶため、事前に整理・準備しておくことが重要です。
事前に以下のような資料を整理しておくと、スムーズに対応できます。
- 財務関連:過去3〜5年分の決算書、試算表、勘定科目明細、固定資産台帳など
- 法務関連:商業登記簿謄本、定款、株主名簿、各種契約書(取引、賃貸借、リースなど)、許認可証
- 人事関連:従業員名簿、就業規則、給与規程、労働協約、退職金規程
- 事業関連:事業計画書、製品・サービス一覧、主要な取引先リスト
資料の準備が不十分だと、調査期間が長期化し、取引成立までに遅れが生じる可能性があります。M&A仲介会社や専門家と連携し、必要な資料を洗い出し、見落としや不足がないように体制を整えておくことが大切です。
マネジメントインタビューへの対応方法
デューデリジェンスでは資料調査に加え、経営陣や幹部社員へのインタビューも実施されます。数値では表現できない定性的な情報を収集し、事業の実態をより深く理解することが目的です。
対応する際は、M&A仲介会社と事前に打ち合わせを行い、想定される質問への回答を準備しておくことが重要です。質問に対しては、隠し事をせず、誠実かつ具体的に回答する姿勢が求められます。
不明瞭な回答や虚偽の説明は、買い手の不信感を招き、交渉決裂の原因となりかねません。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ステップ8:最終契約書の締結

デューデリジェンス完了後、調査結果を踏まえた最終的な取引条件の交渉と契約締結を行います。最終契約書は法的拘束力を持つ正式な契約であり、取引の詳細なルールを定める重要な文書です。
表明保証条項等の詳細な検討により、双方のリスクを適切に分担します。
デューデリジェンスの結果を踏まえた最終条件の交渉
デューデリジェンスで判明したリスクや課題に応じて、譲渡価格や表明保証等の最終条件を改めて協議します。
例えば、将来の訴訟リスクや財務上の問題が発見された場合は、価格減額や「証書差入」などの条件追加が求められる場合もあります。
この交渉は、売り手・買い手双方にとって最後の重要な調整局面であり、M&A仲介会社や弁護士、公認会計士などの専門家と連携し、冷静かつ戦略的に進めることが不可欠です。
最終契約書(DA)の内容確認と表明保証条項
最終契約書には、以下のような内容が詳細に規定されます。
- 譲渡価格および支払い方法
- 有価証券・資産の受け渡し方法・時期
- 表明保証(Representations & Warranties)
- 違約金や損害賠償、その他のペナルティ条項
- 契約成立後の手続きや双方の権利義務
特に表明保証条項は、経営陣が契約時にどのような状態を保証しているかを明記するもので、万が一内容に不備や違反があった場合の補償責任や取扱いが定められています。
この条項の範囲や緩和(エスクローや補償対象の限定など)についても十分に確認することが必要です。もし契約後に表明保証違反が発覚した場合、買い手は売り手に対して損害賠償を請求できます。
契約締結に向けた取締役会での承認
法人企業では通常、最終契約書の締結前に取締役会や株主総会での承認手続きが必要となります。この手続きの遅延はM&A成立の遅れに直結するため、事前に承認プロセスを確認し、スケジュールに遅れが生じないように留意してください。
特に上場企業など、会社の規模が大きい場合には、この手続きが法律や社内規程で義務付けられています。取締役会で承認が得られて初めて、代表者が契約書に署名・捺印し、正式に契約が締結されます。
ステップ9:クロージング(決済)

最終契約書の締結後、契約内容を履行してM&A取引を完了させる手続きをクロージングと呼びます。
具体的には、譲渡代金の決済と、株式や事業資産の引き渡しが行われます。クロージングの完了をもって、M&A取引が正式に完了です。
クロージングの定義と実行される手続き
クロージングは、事前に最終契約書で定められた条件に従い、売買当事者が実際に権利移転と代金支払いを履行する最終的な手続きです。
- 譲渡代金の受領:買い手から売り手へ対価が支払われます(支払い方法・タイミングは契約で規定)。
- 株式・資産の引き渡し:株式証券や事業の重要資産の移転が正式に行われます。
- 登記変更・許認可の書き換え:法務局での株主名簿変更登記や産業廃棄物業許可などの許認可の書き換え手続きが必要になります。
クロージングは通常1日で完了しますが、複雑な取引では数日に分けて実行する場合もあります。関係者が一堂に会し、手続きの順序や必要書類を事前に確認してから実行します。
譲渡代金の受領と株式・資産の引き渡し
クロージングの核心は譲渡代金の決済と株式・資産の引き渡しです。同日同時履行が原則ですが、実務上は買い手による代金振込確認後に株式等の引き渡しを行うケースが一般的です。
代金決済の流れ:
- 買い手による指定口座への振込実行
- 売り手による着金確認
- 株券・株主名簿等の引き渡し
- 対象会社による株主名簿の書換
- 取締役・監査役の退任・就任手続き
代金決済では大きな金額が動くため、事前に振込先口座の確認や着金方法について詳細に取り決めておきます。海外送金が必要な場合は、為替手続きや送金時間を考慮したスケジュール設定が重要です。
M&A成立後の登記変更と各種手続き
会社の所有・事業内容・役員等の変更は、法務局での登記や税務署への届出、許認可の書き換えなど、法的な手続きが不可欠です。例えば、以下の項目の手続きが必要です。
主な登記変更事項:
- 株主の変更(株主名簿記載事項の変更)
- 取締役・監査役の変更
- 資本金の変更(増資を伴う場合)
- 商号・目的の変更(必要に応じて)
- 本店移転(本社統合の場合)
各種官庁への届出:
- 税務署:異動届出書・青色申告承認申請書
- 都道府県・市町村:法人住民税異動届
- 労働基準監督署:労働保険関係成立届
- ハローワーク:雇用保険被保険者資格取得届
- 年金事務所:厚生年金保険新規適用届
手続きが漏れると事業継続に支障をきたすため、専門家と連携し、スムーズな移行を図ることが重要です。
従業員・取引先への正式発表
クロージング後、適切なタイミングで、従業員や主要な取引先、金融機関などに対して、M&Aが成立したことを正式に発表します。
特に従業員に対しては、丁寧な説明会を開き、M&Aの背景や目的、今後の処遇などについて説明し、不安を解消することが重要です。円滑な発表とコミュニケーションが、M&A後の事業運営をスムーズにする鍵となります。
M&A全体のプロセスは9つのステップで整理できますが、すべてのステップにおいて情報の正確性やスピード感、専門家との連携が欠かせません。
特に最後の買収監査以降は、契約条件や権利移転、社内外への説明など、法的・実務的な課題が集中します。そのため、専門家と一緒に十分な準備と丁寧な対応が、M&Aを円滑に進める秘訣です。
M&Aの流れ全体や成功のポイントについて俯瞰的・体系的に知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
M&Aプロセスを円滑に進める5つのポイント

M&Aはプロセスが複雑で、それぞれのステップで適切な対応が求められます。途中で混乱やトラブルが発生しないよう、下記のポイントを意識して進めることが非常に重要です。
ここでは、プロセス全体を通じて意識すべき5つのポイントを解説します。
専門家チームの効果的な活用
M&Aを成功に導くために、M&Aアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家チームを早い段階で組成し、それぞれの専門分野の知見を活用しましょう。
専門家とチームを組むことで、交渉や法務、税務、財務に関わる課題を的確に解決でき、リスクを最小限に抑えられます。
円滑な進行のためには、経営者と専門家が密に情報共有し、役割分担を明確にして連携を強化することが不可欠です。
適切なタイミングでの情報開示
M&Aプロセスでは段階的な情報開示により、情報漏洩リスクを管理しながら買い手候補の関心を高めましょう。開示タイミングと内容の最適化が、円滑な交渉につながります。
段階別情報開示の流れ:
- 第1段階:ノンネームシート(匿名情報)
- 第2段階:企業概要書(NDA締結後)
- 第3段階:詳細資料(基本合意後のDD)
- 第4段階:機密情報(最終契約直前)
各段階で開示する情報の範囲を事前に決定し、一貫性のある対応を心がけましょう。早期の過度な情報開示は競合他社への情報流出リスクを高める一方、情報不足は買い手候補の関心低下を招きます。
従業員・取引先とのコミュニケーション
M&Aの成功は、従業員や取引先といったステークホルダーの協力なくしてはあり得ません。特に、M&A後の経営統合(PMI)を円滑に進めるためには、従業員の理解と協力が不可欠です。
クロージング後の正式発表の際には、M&Aの目的や今後のビジョンを誠実に伝え、従業員の不安を払拭し、モチベーションを維持するための丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
リスク管理と問題解決のスピード
M&Aのプロセスでは、予期せぬ問題やトラブルが発生することが少なくありません。デューデリジェンスで新たなリスクが発覚したり、交渉が難航したりすることもあります。
重要なのは、問題が発生した際に迅速かつ的確に対応できる体制を整えておくことです。
経営トップの迅速な意思決定と、専門家チームとの連携により、問題を早期に解決することが、プロセス全体の遅延を防ぎます。
統合後のシナジー実現への準備
M&Aは、クロージング(契約成立)がゴールではありません。そこからが本当のスタートです。
M&Aによって期待されるシナジー効果(相乗効果)を最大化するためには、クロージング後の経営統合プロセス(PMI)が重要になります。
どのような組織体制にするのか、業務プロセスやITシステムをどう統合するのかといった計画を、交渉段階から並行して準備しておくことが、M&Aを真の成功に導く鍵となります。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aのプロセスにおける注意点

M&Aの各ステップにはそれぞれ特有の注意点があります。これらのポイントを把握し、適切に対処することで、M&Aの成功率を高めることができます。
以下では、M&Aのプロセスで注意すべき点を段階別に解説します。
【検討・交渉時】情報漏洩防止と秘密保持の徹底
M&Aを検討しているという情報が外部に漏洩すると、深刻な事態を招く可能性があります。
従業員に動揺が広がり優秀な人材が流出してしまったり、取引先が不安を感じて取引を縮小したりすることで、企業価値そのものが毀損されかねません。
対策として、M&Aに関わるメンバーを必要最小限に絞り、関係者全員と秘密保持契約(NDA)を締結することが基本です。
社内での会話や資料の管理にも細心の注意を払い、情報管理を徹底しましょう。
【デューデリジェンス時】不利な情報も誠実に開示する
デューデリジェンス(DD)の過程で、買い手からさまざまな資料の開示や質問を求められます。この時、自社にとって不利な情報(例えば、潜在的な訴訟リスクや偶発債務など)を意図的に隠蔽することは絶対にしてはいけません。
仮に隠したままM&Aが成立しても、後日発覚した際に表明保証違反として多額の損害賠償を請求される可能性があります。
何よりも、買い手との信頼関係が完全に崩壊し、その後の事業運営に大きな支障をきたします。不利な情報であっても誠実に開示し、その上で解決策を共に協議する姿勢が重要です。
【契約時】契約条件の不備による後続トラブル
M&Aの最終契約書は、非常に複雑で専門的な内容を含みます。契約内容の理解が不十分なまま署名してしまうと、後になって「こんなはずではなかった」というトラブルに発展する可能性があります。
特に、表明保証の範囲、補償の上限額や期間、役員の退職金など、金銭に関わる条項は慎重に確認しましょう。
必ず弁護士などの法務の専門家のレビューを受け、一つ一つの条項の意味を正確に理解し、自社にとって不利益な点がないかを確認することが不可欠です。
【成約後】PMIの失敗がM&Aの失敗に直結する
M&Aは、最終契約を締結し、クロージングが完了すれば終わりではありません。M&Aで期待されたシナジー効果(売上向上やコスト削減など)を実現できるかどうかは、その後の経営統合プロセス(PMI)にかかっています。
PMIの計画が不十分であったり、実行がうまくいかなかったりすると、組織内に混乱が生じ、従業員のモチベーションが低下します。
結果として、両社の強みが打ち消し合い、期待した効果が得られない失敗したM&Aになりかねません。契約成立はゴールではなく、新たなスタートラインであるという認識を持つことが重要です。
正しいプロセスの理解が、M&Aの第一歩

M&Aプロセスは一つひとつのステップが重要であり、それぞれをおろそかにせず、順序立てて進めることが成功への鍵となります。
中小企業経営者の皆様が後継者不在や成長戦略への課題を抱える中、正しいプロセスの理解と的確な準備が、安心してM&Aを進めるために欠かせません。スムーズかつ納得できるM&Aを目指すなら、専門性と経験を兼ね備えたプロのサポートが不可欠です。
M&Aの第一歩は、相談することから始まります。未来の事業承継や成長戦略に向けて、信頼できるパートナーとともに一歩を踏み出しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)