M&Aのスケジュールとは?作成手順と進め方・短縮する方法も解説
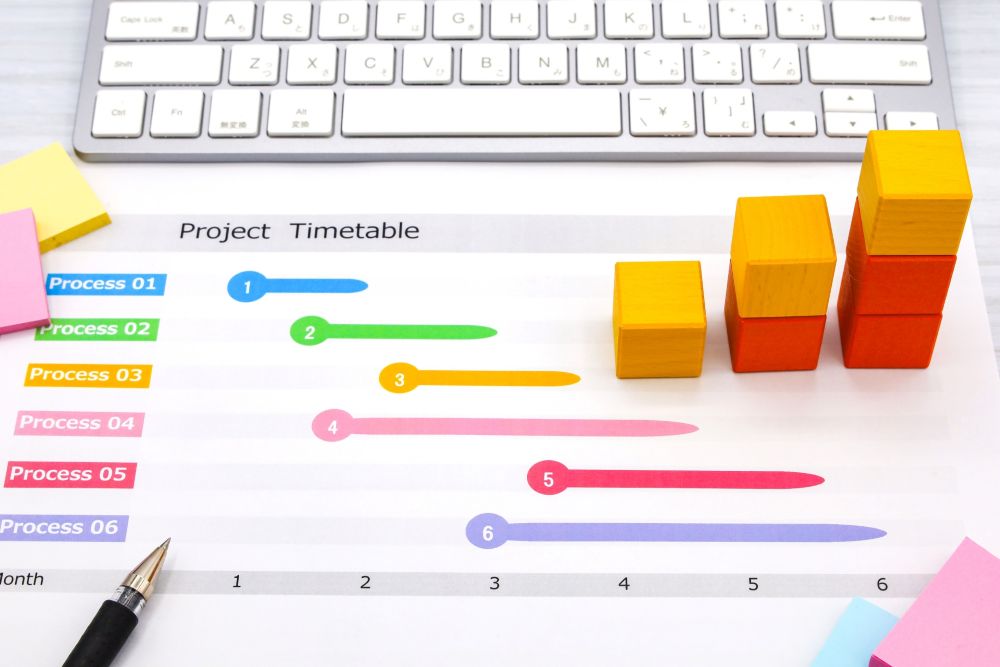
M&Aにおけるスケジュールの作成と管理は、交渉を成功に導く主要な要素の一つです。しかし「何から始めるべきか」「完了までどれくらいの期間がかかるのか」など、見通しがわからず不安な方も多いでしょう。
明確なM&Aスケジュールを立案し、的確に管理することでM&Aのプロセスを効率化でき、成果を高めることも可能です。
本記事では、M&Aの初期の相談から最終的なクロージングまでの全ステップの流れや、スケジュールが遅延する要因と対策、M&Aを短縮して成功確率を高める方法まで具体的に提示します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aスケジュールとは

M&Aスケジュールとは、M&Aの検討開始から経営統合までの一連のプロセスと、各工程にかかる期間を時系列で表した計画のことです。単なるタスクのリストではなく、プロジェクト全体の進捗を管理するために「誰が」「いつまでに」「何を」行うのかを明確にする羅針盤の役割を果たします。
M&A担当者にとってのM&Aスケジュールは、社内の関係部署や経営陣、さらには外部のM&A仲介会社や弁護士、公認会計士などの専門家と連携するための共通言語でもあります。補助金の申請期限や決算期といった、企業内外の重要な日程に合わせてM&Aを進める上でも、精緻なスケジュールを作成し管理することが不可欠です。
M&Aの全体的なスケジュールの流れ(スケジュール表)
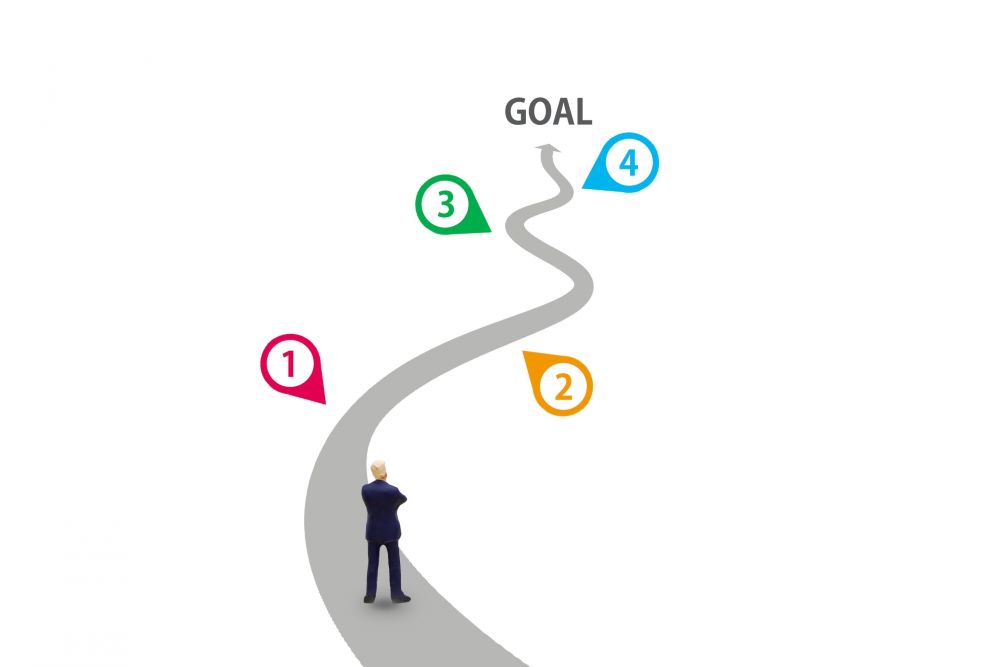 まずはM&Aスケジュールの全体的な流れを見ていきましょう。
まずはM&Aスケジュールの全体的な流れを見ていきましょう。
| ステップ | 主な内容 | 期間の目安 |
| ステップ1:相談 | M&A仲介会社などの専門家へ相談 | 1週間~1カ月 |
| ステップ2:現状のヒアリング・提案 | 企業情報のヒアリング、企業価値の簡易算定、M&A戦略の提案 | 2週間~1カ月 |
| ステップ3:契約 | M&A仲介会社などと提携仲介契約を締結 | 1週間~2週間 |
| ステップ4:企業概要書の作成 | 買い手候補に提示する詳細な企業資料の作成 | 1カ月~2カ月 |
| ステップ5:マッチング・トップ面談 | 買い手候補の選定、交渉、経営者同士の面談 | 2カ月~4カ月 |
| ステップ6:基本合意契約締結 | 譲渡価格やスケジュールなどの基本条件について合意 | 2週間~1カ月 |
| ステップ7:買収監査(デューデリジェンス) | 買い手による売り手企業の詳細な調査 | 1カ月~2カ月 |
| ステップ8:最終契約書の締結 | 最終的な条件交渉と、法的拘束力のある契約の締結 | 2週間~1カ月 |
| ステップ9:クロージング | 譲渡代金の決済、株券などの引き渡し、経営権の移転 | 1カ月程度 |
M&Aの流れを完全解説|検討から統合までの全プロセスと成功のポイント
ステップ1.相談
最初のステップは、信頼できる専門家(M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー)へ相談し、自社の現状や希望を伝えることです。
相談の段階では、M&Aを実行すべきかどうかも専門家と一緒に検討します。M&Aの目的を明確にすることで、その後のプロセスをスムーズに進められます。
無料相談を実施している会社もあるので、自社に合ったパートナーを見つけるためにも、複数の専門家の話を聞くと良いでしょう。
ステップ2.現状のヒアリング・提案
次に、M&Aの目的を具体的に設定します。同時に、目的の背景にある課題は何かを深掘りする重要なステップです。
- 後継者不在による事業承継
- 主力事業への経営資源集中
- 創業者利益の獲得
目的が明確になった段階で、M&Aの専門家が客観的な視点から、最適な戦略やスキーム(手法)を提案します。
ステップ3.契約
専門家の提案内容に合意できたら、正式に提携仲介契約を締結します。
仲介会社を選ぶ際には以下のポイントを確認しましょう。
- 自社の業界や規模でのM&A実績が豊富か、専門知識を持っているか
- 料金体系が明確化、着手金や中間金はないか
- 親身に相談に乗ってくれるか、コミュニケーションは円滑か
提携仲介契約書には、依頼する業務の範囲、手数料の体系、秘密保持義務といった項目が定められます。契約内容を十分に理解し、不明な点はすべて解消してから契約に臨むようにしてください。
ステップ4.企業概要書の作成
契約後、買い手候補企業に自社の情報を開示するための「企業概要書(インフォメーション・メモランダム)」を作成します。
買い手候補企業に提示する資料は、情報の開示レベルに応じて以下の2段階に分かれるのが一般的です。
| 資料の種類 | 特徴 |
| ノンネームシート | 企業名が特定されない範囲で、事業内容、エリア、売上規模などの概要をまとめた資料。初期の打診に使用します。 |
| 企業概要書(IM) | 秘密保持契約(NDA)締結後、より関心を示した候補企業にのみ開示する詳細資料。財務情報や組織図、事業の強みなどが含まれます。 |
上記2つの資料は、買い手に自社の魅力を的確に伝えるためのツールであるため、専門家と連携し、時間をかけて客観的かつ魅力的な内容で構成する必要があります。
ステップ5.マッチング・トップ面談
続いて、買い手候補企業を探し企業情報を提供するステップです。マッチングからトップ面談へは以下の流れで進めます。
- 仲介会社が自社の希望条件に合致する最適な候補先を選定
- 「ノンネームシート(企業名を伏せた企業の概要資料)」で相手企業に打診
- 候補企業が関心を示したら、秘密保持契約を締結した後「企業概要書(IM:売り手企業の詳細情報をまとめた資料)」を開示
- 「トップ面談」で双方の経営者同士がお互いの経営理念や将来のビジョンなどを共有し、相性やシナジーの可能性を確認
ステップ6.基本合意契約締結
トップ面談を経て、M&Aに前向きな意思を双方が確認できたら、「基本合意契約(LOI)」を締結します。
基本合意書とは、最終契約に向けた以下の基本的な条件についての合意を示す文書のことです。
- M&Aのスキーム(株式譲渡、事業譲渡など)
- 譲渡価格の目安
- 今後のスケジュール
- 独占交渉権の付与(一定期間、他の候補と交渉しない義務)
- 買収監査(デューデリジェンス)への協力義務
基本合意には独占交渉権などを除いて法的な拘束力はなく、本契約のたたき台のような位置づけです。
ステップ7.買収監査(デューデリジェンス)
基本合意契約後、買い手側は売り手企業の価値やリスクを詳細に調査する「買収監査(デューデリジェンス、DD)」を実施します。
デューデリジェンスとは、公認会計士や弁護士などの専門家がチームを組み、売り手企業の実態を以下の領域で詳細に調査し、潜在的なリスクを確認するプロセスのことです。
| DDの種類 | 主な調査内容 |
| 財務DD | 決算書の内容、収益性、資産・負債の実態など財務上のリスク |
| 法務DD | 定款、契約書、許認可、訴訟の有無など法的リスク |
| ビジネスDD | 事業の将来性、市場での競争力、組織体制、技術力などの評価 |
| その他 | ITシステム、人事、税務、環境など、必要に応じて実施 |
売り手側は調査に全面的に協力し、求められた資料を迅速に開示する義務があります。デューデリジェンスで問題が発見された場合は、取引価格などの契約条件が見直されることも少なくありません。
ステップ8.最終契約書の締結
デューデリジェンスの結果を踏まえ、双方が最終的な条件交渉を行い、譲渡価格やその他の条件について合意に至ったら「最終契約書(SPA:株式譲渡契約書など)」を締結します。
最終契約書は、M&Aに関するすべての取り決めを法的に確定させる重要な契約書です。法的拘束力を持ち、締結後は、原則として一方的な理由による契約破棄は認められないため、弁護士などと契約内容を慎重に確認の上、署名・捺印することが一般的です。
ステップ9.クロージング
最終契約書の締結後、契約内容を実行に移す手続きである「クロージング」が行われます。
具体的には、売り手から買い手へ株式や事業資産を引き渡し、買い手は売り手へ対価を支払う手続きです。スキームによる手続きの違いは以下の通りです。
| スキーム | 主なクロージング手続き |
| 株式譲渡 | ・譲渡代金の支払い
・株券の引き渡し ・株主名簿の書き換え |
| 事業譲渡 | ・譲渡代金の支払い
・事業資産(不動産、設備、知的財産など)の移転手続き ・従業員の転籍手続き |
これらの手続きがすべて完了した時点で、M&Aが正式に成立し、同時に、M&A後の統合プロセス(PMI)へと移行します。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aを短いスケジュールで実施するメリット

ここでは、M&Aのスケジュールを適切に管理し、短縮するメリットを解説します。
市場動向に左右されるリスクが軽減される
M&Aスケジュールを短縮するメリットとして、市場動向の変動によるリスクを軽減できることが挙げられます。
M&Aが長期化するほど、景気の動向、業界のトレンド、法規制の変更といった外部環境が変化するリスクが増します。M&Aの完了前に景気が後退すれば、見込んだシナジー効果が期待できなくなるおそれが生じ、買い手企業の買収意欲の減退を招きかねません。
迅速にM&Aを完結させることで、環境変化の不確実性と買い手の不安を最小限に抑えられます。
関係者への情報漏えいリスクが軽減される
M&Aのスケジュールの短縮は、情報漏えいリスクの低減にもつながります。
M&Aでは機密性の高い情報を多く扱うため、極秘に進められることが鉄則です。しかし交渉が長引くほど関わる人数や情報交換の頻度が増し、意図せず情報が外部に流出するリスクが高まります。
早い段階で従業員にM&A計画が漏れてしまうと、将来不安によるモチベーションの低下や、優秀な人材の離職を招きかねません。また、取引先が不安定な経営を懸念し、取引を縮小する可能性もあります。
プロセスを迅速に進行し情報漏えいリスクを抑制できれば、従業員や取引先との良好な関係を維持でき、経営の安定にもつながります。
M&Aの目的のフィジビリティを高められる
M&Aの目的の実現可能性(フィジビリティ)が高まることも、M&Aのスケジュールを短縮するメリットの一つです。
M&Aにおいては「新規事業へのスピーディーな参入」「特定の技術の獲得」など、タイミングがネックとなる目的が少なくありません。M&Aの交渉が長期化すれば、競合他社に先を越されたり市場の魅力が失われたりして、M&Aの目的が意味を成さなくなるおそれがあります。
計画通りにM&Aを完遂することで、事業戦略上の機会を逃すことなく、当初策定した戦略の実現性を高めることにもつながります。
M&Aスケジュールが長期化・遅延する要因

ここでは、M&Aのスケジュールが長期化・遅延する主な6つの要因を解説します。リスクを予測し、事前に対策を講じる上で役立ててください。
買い手探しが難航する
買い手探しの難航は、M&Aのスケジュールが遅延する要因の一つです。
財務状況や事業の将来性に懸念があると、買い手が投資に慎重になり、買い手探しが長引く傾向にあります。特に、以下のような状況では買い手探しに時間がかかることが一般的です。
- 事業内容が特定の分野に特化しすぎている
- 業績が不安定である
- 希望条件が市場相場と乖離している
M&Aが長期化するリスクを回避するためには、まず客観的な視点で自社の強みや課題を分析し、企業価値を正しく評価することから始めましょう。そして、現実的な希望条件を設定することが大切です。
幅広いネットワークを持つM&Aの専門家に相談し、より多くのアプローチ先を見つけることもおすすめします。
条件交渉が難航する
売り手と買い手の条件交渉が難航することも、スケジュールの長期化を招く大きな要因です。
M&Aで交渉すべき項目は、譲渡価格のほか従業員の雇用維持、役員の処遇、譲渡後の社名変更など多岐にわたります。いずれも双方にとって重要な経営判断であり、利害が対立しやすいことが一般的です。
たとえば、売り手が従業員の雇用継続を強く望む一方、買い手が事業の効率化のために人員整理を希望すれば、交渉は平行線をたどる可能性が高いため、お互いの立場を尊重しながら落としどころを探る姿勢が欠かせません。
交渉をスムーズに進めるためには、事前に「絶対に譲れない条件」と「譲歩できる条件」を明確にしておくことも必要です。
デューデリジェンスに想定外の時間がかかる
デューデリジェンス(買収監査)の過程で想定外の問題が発覚した場合も、M&Aのスケジュールの大幅な遅延が起こりやすい要因です。
デューデリジェンスの過程で以下のような問題が発見されると、社内で調査し対応策を検討する時間が追加でかかります。
- 多額の未払い残業代の存在
- 許認可の取得漏れや更新忘れ
- 過去の取引における契約違反
簿外債務や将来的な訴訟リスクは統合後の経営悪化の要因となるため、買い手側は慎重にならざるを得ません。可能な限り、売り手側でも事前に専門家による調査(セルサイド・デューデリジェンス)を実施し、問題を洗い出しておきましょう。
当局の規制審査に時間がかかる
企業の規模や業種によっては、当局による規制審査がスケジュールの遅延要因となることがあります。
一定の市場シェアを持つ企業同士がM&Aを行う場合、経営統合で市場の公正な競争を妨げるおそれがあるため、独占禁止法に基づき公正取引委員会による審査を受けます。この場合、審査に数カ月単位の期間がかかることも少なくありません。
また、海外企業とのM&Aや、特定の規制業種(放送、航空など)におけるM&Aでは、外為法やその他の法律に基づく届け出や審査が必要になるケースもあります。
自社のM&Aが審査対象となる可能性がある場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、必要となる手続きと期間を組み込んだスケジュールを立てることが重要です。
社内外の意思決定プロセスが遅れる
社内外の関係者における意思決定プロセスの遅れも、スケジュール遅延の一般的な原因です。
M&Aには関わる人が多く、それぞれの承認を得るのに時間がかかります。経営陣の間で意見がまとまらないケースや、複数の株主から同意を得るのに手間取るケースも少なくありません。
意思決定を円滑化するためには、M&Aの責任者や最終的な決定権者を明確にしておくことが不可欠です。また、経営陣や株主とは日頃から密にコミュニケーションを取り、M&Aの方針について事前にコンセンサスを形成しておくことで、プロセスの停滞を抑えられます。
書類や契約関連の準備が不足している
M&Aの各ステップで必要となる書類や契約関連の準備の不足も、手続きを滞らせる直接的な遅延の原因です。
M&Aでは、会社の基本情報を示す定款や登記簿謄本、過去数年分の決算書、重要な契約書、議事録など、膨大な資料の提出が必要です。しかし中小企業を中心に、社内で資料が整理されておらず、デューデリジェンスで要求された時にすぐに提示できない、といった事態が散見されます。
プロセスをスムーズに進めるためには、M&Aを検討し始めた段階から、専門家のアドバイスのもと必要書類のリストアップと整理を進めておくことが大切です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aスケジュールの立て方

M&Aの精緻なスケジュールを作成することで、プロジェクト全体が可視化され、関係者全員が共通の認識を持てます。
ここでは、計画倒れに終わらせない実用的なスケジュール表の作り方を解説します。
スケジュール表を作る手順
スケジュール表を作る手順は以下の通りです。
- 最終目標(クロージング日)を設定する
- 主要なフェーズとタスクを洗い出す
- 各タスクの所要期間を見積もる
- タスクの依存関係を整理する
- スケジュール表に落とし込む
まず、M&Aを完了させたい大まかな目標時期を定めたら、「準備」「基本合意締結」「デューデリジェンス」「最終契約」などの主要なフェーズと、行うべきタスクをすべてリストアップします。
次に「タスクAが終わらないとBへ進めない」といったタスク間の前後関係を明確にします。目標から逆算し、各タスクにかかる現実的な期間を見積もることがポイントです。
失敗しないスケジュール表作成のポイント
実行に移しやすいスケジュール表を作るには、単にタスクを並べるだけでなく、以下のポイントを押さえることが必要です。
- 予期せぬトラブルや遅延に備え、各工程に余裕(バッファ)を持たせる
- 経営陣、従業員、M&Aアドバイザーなど、関係者全員で共有し、認識を一致させる
- 計画通りに進んでいるか定期的にチェックし、必要に応じて柔軟にスケジュールを修正する
上記に留意したスケジュールは関係者が実行に移しやすく、形骸化しません。
M&Aのスケジュールを短縮する方法

M&Aのスケジュールは、工夫次第で短縮可能です。ここでは、計画性を維持しつつM&Aのプロセスを効率化し、スケジュールを短縮するための具体的な方法を解説します。
明確な期間を決めておく
M&Aのスケジュールを短縮するには、まず明確な目標期間を決めておくことが大前提です。
「半年後のクロージングを目指す」といった具体的なゴールを設定しましょう。最終的な期限を設定することで、ゴールから逆算して各ステップにかけられる時間が明確になるからです。
プロジェクトに関わる全員が共通の認識を持つことで、プロセスに集中でき緊張感を保てます。
明確な意思決定プロセスを確立する
明確な意思決定プロセスを確立することもスケジュール短縮の鍵です。
M&Aの交渉において意思決定のルールが曖昧では、その都度確認や調整に時間がかかり、プロセスが停滞してしまいます。事前に決定権者や「譲渡価格の○%までの減額交渉は担当役員の権限で即決する」といった具体的なルールを定めておきましょう。
M&Aプロジェクトを開始する前に、社内の決裁フローを整備し、誰が、いつ、どのように決定を下すのかを明確にしておくことで、迷いや手戻りを最小限に抑えられます。
条件の優先順位を整理しておく
交渉期間を短縮するために、M&Aで実現したい条件に優先順位を付けて整理しておくことも重要です。
M&A交渉において、自社の要望がすべて通るとは限りません。売り手・買い手のいずれも譲歩しなければ議論が平行線をたどり、交渉が難航することもありえます。M&Aにおいて重視する譲れない条件と、譲歩できる条件をあらかじめ決めておくことで、迅速かつ合理的な判断が可能です。
【条件の優先順位の例】
- 絶対に譲れない条件:従業員の雇用を3年間維持する
- 交渉次第で譲歩できる条件:希望譲渡価格(90%までなら許容)
- 優先度が低い条件:役員の退職金の額
必要な書類や資料は事前に準備する
交渉やデューデリジェンスで必要となる資料を早期に準備しておくことも、期間短縮につながるポイントです。
M&Aでは以下資料が必要であり、要求されてから探すと大幅なロスタイムが生じてしまいます。
- 会社関連:定款、登記簿謄本、株主名簿
- 財務関連:過去3〜5年分の決算書、試算表、勘定科目内訳書
- 契約関連:主要な取引先との契約書、リース契約書、不動産賃貸借契約書
- 人事関連:従業員名簿、就業規則、賃金規程
M&Aの専門家のアドバイスを受けながら、早い段階で必要書類のリストアップとデータ化を進めましょう。仮想データルーム(VDR)などを使って書類を整理しておくことで、効率的な情報提供が可能です。
プロセス全体をシミュレーションしておく
M&Aのプロセス全体をシミュレーションしておくことも、時間短縮の鍵です。
M&A専門家にも協力してもらい、「デューデリジェンスで簿外債務が見つかった」「相手から独占交渉期間の延長を求められた」といったM&Aにありがちなトラブルを想定し、ケーススタディを通じて対応策を準備しておくと理想的です。
日頃からトラブルの対応方針を検討しておくことで、問題発生時のタイムロスを最小限に抑えられます。
あらかじめPMI計画を立てておく
最終契約後に行うPMI(M&A後の統合プロセス)の計画を事前に検討しておくことも、M&A全体のスケジュール短縮に貢献します。
買い手は、買収後の統合がスムーズに進むかどうかを懸念しています。そのため、人事制度や業務システム、企業文化などに関する統合計画案を事前に示すことで、買い手に安心感を与えられ、買収の意思決定が早まる可能性があります。
PMIへの準備が整っていることを示せれば、売り手に対する買い手の信頼と評価が高まり、交渉自体を円滑に進めやすくなります。
M&Aのスケジュールをスムーズに進めるコツ
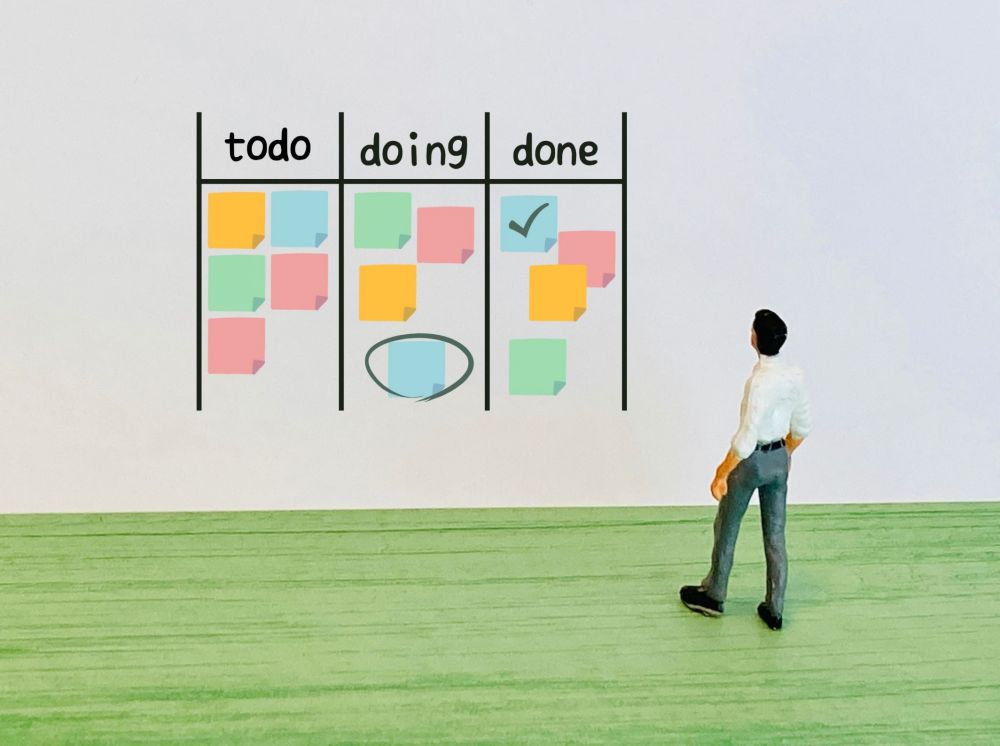
ここでは、スケジュールの遅延リスクを最小限に抑え、成功の確率を高めるための5つの重要なコツについて、具体的なアクションと共に解説します。
目的や方針がブレないよう留意する
M&Aのスムーズな進行には、M&Aの目的や方針がブレないように留意することが重要です。
交渉が長期化した場合は特に、当初の目的を見失ってしまうことが少なくありません。たとえば、「後継者問題の解決」が目的だったにもかかわらず、交渉の過程で価格交渉にこだわってしまうと、買い手候補との関係を悪化させ、M&A成立を妨げるおそれがあります。
方針のブレを回避するために、M&Aの目的を明文化し、プロジェクトチーム内で定期的に再確認する機会を設けることが大切です。判断に迷った時は当初の目的を基準としましょう。
チームのコミュニケーションを円滑化する
社内外のプロジェクトチーム内でコミュニケーションを円滑化することも、スケジュールをスムーズに進めるポイントです。
M&Aには、自社の担当者や経営陣のほか、M&A仲介会社、弁護士、公認会計士など多くの専門家が関わります。すべての関係者が常に最新の情報を共有できるよう、週に一度の定例ミーティングや、ビジネスチャットツールなどを取り入れることも大切です。
連携を密にすることで問題の早期発見と迅速な解決が可能になり、プロジェクトの停滞を防げます。
適切な情報開示を行う
買い手候補に対し、適切なタイミングで正確な情報開示を行うことも、双方の信頼関係を築き交渉をスムーズに進める秘訣です。
潜在的な訴訟リスクや簿外債務といった会社売却に不利になる情報についても、隠ぺいによってスケジュールが短縮されるわけではなく、かえって多くのリスクが生じるだけです。
むしろ早い段階から情報を適切に開示し、解決策を共に検討する姿勢を示すことで、買い手から誠実なパートナーとして評価され、円滑な交渉につながります。
工程管理ツールを活用する
M&Aスケジュールの管理には工程管理ツールを積極的に活用しましょう。M&Aのような複雑なプロジェクトにおいては、各タスクの担当者や期限、進捗状況をExcelなどで手動管理するには限界があるためです。
AsanaやTrelloといったプロジェクト管理ツールを使えば、誰がいつまでに何をするべきかを直感的に把握することが可能です。さらにガントチャート機能で全体の進捗状況を可視化すれば、遅延しているタスクをすぐに特定できます。
関係者全員がリアルタイムで状況を把握できれば、より正確かつ効率的なスケジュール管理が可能になり、担当者の管理負担軽減にもつながります。
早期にM&Aの専門家を起用する
M&Aを検討する早い段階で、信頼できるM&A専門家を起用することもスケジュールの短縮に貢献します。
M&Aには幅広い分野の専門的な知識と経験が必要となるため、社内だけで進めると各手続きに時間がかかる可能性が高いです。また、自己流で進めてしまうと、法務や税務上のリスクを見落としたり、不利な条件で契約してしまったりするリスクも否定できません。
しかし専門家に依頼すれば、相手探しや複雑な契約交渉、煩雑な手続きなど、あらゆる局面で的確にサポートしてくれるため、プロセス全体の進行がスムーズ化します。
M&Aの無料相談を実施しているM&A仲介会社もあるので、M&Aを検討し始めた段階で複数の専門家に相談し、その中から信頼できるパートナーを選びましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →まとめ|M&Aの成功は信頼できるパートナーとの計画的なスケジュール管理から

M&Aの成功には精緻なスケジュールの作成と十分な準備、プロセスの計画的な進行、管理が不可欠です。
各関係者のやるべきことが可視化され、M&Aをスムーズに進行できるスケジュールを作成するには、M&Aの全体像とタスクだけでなく、各ステップの注意点やリスクに対する正しい理解が欠かせません。
M&Aの計画段階から専門家のアドバイスを得ることで、関係者が容易に共有でき実行に移しやすいスケジュールの作成と、プロセスのスムーズな進行が可能です。
信頼できるパートナーを選び、M&Aを成功に導きましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










