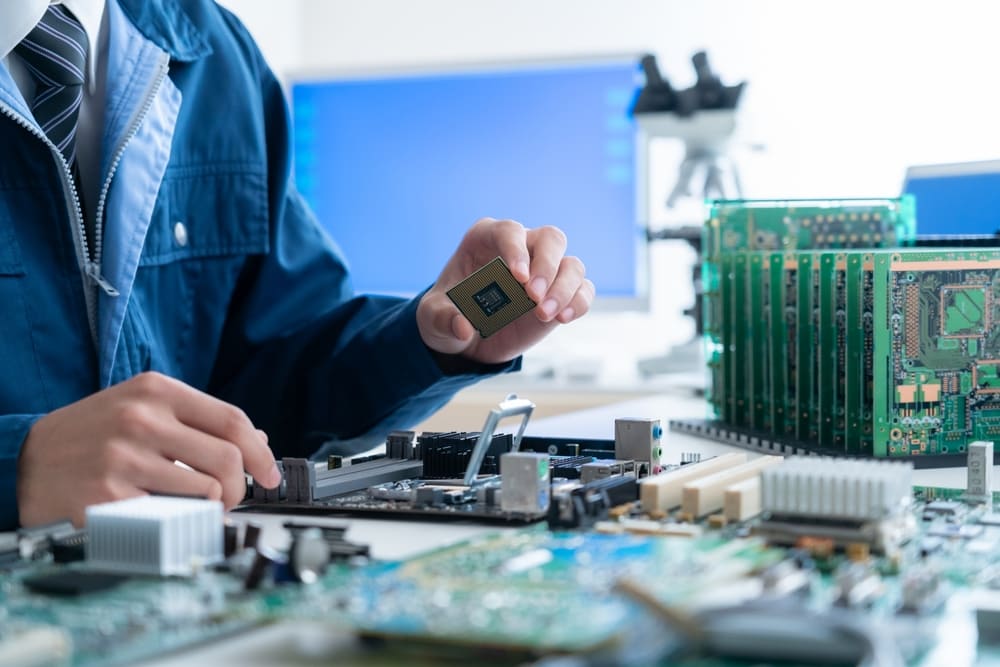不動産業界のM&Aを徹底解説!動向・メリット・事例紹介

不動産業界では近年、M&A(企業の合併・買収)が活発化しています。
とりわけ、不動産開発・販売・流通・管理などを手がける不動産関連会社では、事業承継や業界再編、成長戦略の一環としてM&Aを活用するケースが増加中です。
本記事では、不動産業界におけるM&Aの市場動向や、売り手・買い手双方にとってのメリット・デメリット、さらに実際の事例までを幅広く解説します。
不動産業界のM&Aについて基礎から理解したい方、実際にM&Aを検討している経営者・事業責任者の方は、ぜひ参考にしてください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
不動産業界の概要
不動産業界は、一般に「開発・販売」「流通(仲介)」「管理」「賃貸」など、いくつかの分野に分類されます。
- 開発・販売
土地の仕入れから造成、建物の建設・分譲までを手がける分野です。大規模な住宅地開発やマンション分譲を行うディベロッパーが代表的です。 - 流通(仲介)
不動産の売買や賃貸の仲介を行う分野です。個人向けの住宅仲介から、法人向けのオフィス・商業施設の仲介まで幅広く存在します。 - 管理
マンションやビル、賃貸住宅などの物件管理を行う分野です。入居者対応、建物メンテナンス、家賃回収などの業務を担います。 - 賃貸
自社で保有する不動産を賃貸し、安定的な賃料収入を得る事業モデルです。オフィスビルや商業施設、賃貸マンションなどが対象となります。
不動産業界の特徴は、固定資産を中心としたビジネスモデルであることです。
景気動向や金利水準の影響を受けやすい一方で、土地・建物という実物資産を扱うため、一定の資産価値を背景に安定的な収益を確保しやすいという側面もあります。
また、不動産業界は中小企業の占める割合が高く、地域密着型のビジネスモデルも多いため、オーナー経営者による事業承継問題が深刻化しやすい業界といえます。
このような背景から、近年ではM&Aによる事業継続や成長戦略の実現が注目を集めています。
不動産業界の市場動向

不動産業界は日本経済において重要な位置を占め、住宅、商業施設、オフィスビルの需要が経済の動向に直結しています。
しかし、人口減少や少子高齢化など、社会構造の変化が業界に影響を与えており、特に地方市場では課題が顕著です。
ここでは、不動産業界の現在の市場動向と今後の展望について解説します。
日本のGDPの約11%を占める重要産業
不動産業は、日本のGDPの約11%を占める重要な産業であり、日本経済全体に大きな影響を与えています。
不動産の開発、販売、賃貸、管理などの業務は、日本国内のあらゆる地域で展開されており、特に都市部では経済活動の中心となっています。
近年では、住宅の需要だけでなく、オフィスビルや商業施設の需要も拡大し、不動産市場は安定した成長を見せてきました。
しかし、今後は人口減少や少子高齢化という日本独特の社会問題が、不動産業界に対して新たな影響を与えると予測されています。
特に地方での人口減少は、住宅や商業施設の空室率を高め、今後の市場に変化を引き起こす可能性が高いと考えられます。
(参照:内閣府「2023年度国民経済計算」)
総合ディベロッパーの影響と中小企業の課題
日本の不動産業界では、総合ディベロッパーと呼ばれる大手企業が市場に大きな影響を与えています。
総合ディベロッパーとは、三井不動産、住友不動産、野村不動産など、土地の取得から開発、販売、管理までを一貫して行う大手企業のことです。
これらの企業は、規模の経済を活かし、強力な競争力を持っていて、大規模な開発プロジェクトを推進、展開しています。
その結果、特に地方の中小企業は、規模や資金力で大きな差をつけられ、競争が非常に厳しくなっています。
人口減少と高齢化による業界への影響
日本の人口減少と高齢化は、不動産業界に大きな影響を与えています。特に地方において空き家問題は深刻です。
一方、都市部では高齢者向けの住宅やサービスの需要が増加しており、ライフスタイルの変化に対応した新たな事業モデルが求められています。
また、テレワークやリモートワークの普及により、オフィス需要に変化が見られ、企業のオフィススペースに対する考え方も大きく変わりつつあります。
今後は、高齢者向けの住宅開発や、テレワークの普及に伴った新しいオフィス形態への対応など、柔軟な事業運営が不可欠になるでしょう。
建設業の現状とM&Aの動向|メリット・デメリットと事例を紹介
ビルメンテナンス業界のM&A徹底解説|売却メリット・事例・流れ・相談先など
不動産業界におけるM&Aの動向

近年、不動産業界におけるM&A(企業の合併・買収)が活発に行われています。その要因となっているのは、業界の構造変化や経済環境の影響などです。
特に、事業承継の問題や業界再編の必要性、資産の流動化や経営効率化を目指す動きがM&Aを促進している要因として挙げられます。
また、不動産業界は隣接する業種が豊富な点が特徴です。他業種とのシナジーが生まれやすく、事業の多角化や強化を図るためにM&Aが有効とされています。
不動産業界の隣接業種とのシナジー効果を期待
不動産業界は、単独ではなく、建設業、リフォーム業、施設管理業、さらにはITや金融サービスなどの隣接業種との連携が必要不可欠です。
これらの業界が手を組むことによって、各業務の効率化やコスト削減が期待できます。例えば、不動産開発業者が建設会社を買収することで、開発から施工、販売までを一貫して行える体制を築くことができます。
このように、異業種間でシナジーを生み出すM&Aは、事業運営の効率化や収益性の向上に繋がるため、非常に重要な戦略とされています。
事業承継問題と業界再編の加速
日本の不動産業界では、特に中小企業において事業承継問題が深刻化しています。
経営陣の高齢化が進む中で、後継者不足が大きな課題です。そこで、事業を継続するための手段としてM&Aが有効に活用されています。
また、業界全体では再編の動きが進行中で、大手企業と中小企業の競争が激化しています。これに対応するため、多くの企業が規模の拡大や事業の多角化を目指し、M&Aを積極的に取り入れています。
資産の流動化と経営効率化
不動産業界において、土地や不動産物件などは大きな経営資源です。
これらの資産を効率的に活用するために、M&Aが重要な手段となっています。
売却や提携を通じて、事業の効率化や資産の流動化を図る企業が増えており、規模の拡大によるコスト削減や事業運営の効率化も実現されています。
不動産業界でM&Aを実施するメリットとデメリット

不動産業界におけるM&Aは、事業の効率化や規模の拡大を目指す企業にとって非常に重要な戦略となっています。
しかし、M&Aには売り手側・買い手側それぞれにメリットとデメリットが存在します。
不動産業界におけるM&Aのメリットとデメリットを売り手側、買い手側に分けて詳しく見ていきましょう。
売り手側のメリット
M&Aの売り手側にもたらされるメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 事業承継の円滑化
後継者がいない場合でも、M&Aを通じて事業を第三者に譲渡することで、事業承継の問題を解決できます。 - 事業の成長機会の提供
買い手企業が持つ資金力やネットワークを活用することで、事業の成長や拡大が期待できます。 - 従業員の雇用継続
M&Aにより、従業員の雇用が守られる可能性が高く、従業員の生活が安定します。 - 事業の再編による効率化
事業の一部を譲渡することで、経営資源を集中させ、効率的な事業運営が可能となります。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
売り手側のデメリット
続いては、売り手側が考えておくべきM&Aのデメリットを紹介します。
- 企業文化の喪失
M&Aにより、企業の独自の文化や方針が変わる可能性があり、これに対する抵抗感が生じることがあります。 - 従業員の不安
M&A後の組織再編により、従業員の役割や待遇が変わる可能性があり、不安を感じる従業員が出ることがあります。 - 取引先との関係変化
M&Aにより、取引先との関係が変わる可能性があり、これにより取引条件の見直しや契約の再交渉が必要となることがあります。
買い手側のメリット
M&Aは買い手側にも大きなメリットがあります。4つのポイントを見ていきましょう。
- 事業の迅速な拡大
既存の事業基盤を活用することで、新規事業の立ち上げよりも迅速に市場に参入できます。 - シナジー効果の創出
異なる事業領域を統合することで、コスト削減や新たな収益源の創出が期待できます。 - 既存の顧客基盤の獲得
買収対象企業の顧客基盤を活用することで、新規顧客の獲得が容易になります。 - 専門知識や技術の取得
買収対象企業が持つ専門知識や技術を取り入れることで、自社の競争力を強化できます。
買い手側のデメリット
買い手側に考えられるデメリットは以下の通りです。
- 経営統合の難しさ
異なる企業文化や業務プロセスを統合することは難しく、時間と労力を要します。 - 予期しない負債の引き継ぎ
デューデリジェンスで見落とされた負債や契約上の問題が後に発覚する可能性があります。 - 従業員の抵抗
買収対象企業の従業員が新しい組織に対して抵抗感を示すことがあり、これに対する対応が必要です。 - ブランド価値の低下
買収により、既存のブランド価値が低下する可能性があり、ブランド戦略の見直しが求められます。
不動産業界のM&A価格相場と評価方法

不動産業界におけるM&Aの企業価値評価は、非常に複雑で多様です。
特に、不動産会社はさまざまな種類の資産を保有しており、収益物件や土地、建物の評価方法がそれぞれ異なります。
そのため、同じ業界内でも評価基準は一律ではなく、ケースごとに異なるアプローチが必要です。
ここでは、価格相場の特徴とその決定要因、代表的な評価方法などについて解説します。
価格相場の特徴
不動産業界におけるM&A価格相場には、明確な基準が存在しません。
価格は企業の保有資産の種類、規模、収益性によって大きく変動します。
特に中小企業においては、簡易的な計算式として「純資産額+営業利益2~5年分」を参考にするケースもあります。
しかし、不動産会社では、資産価値に差が大きいため、一般的な基準を適用するのが難しいのが現実です。
収益物件を保有している企業の場合、DCF法(ディスカウンテッドキャッシュフロー法)を用いて将来の収益を評価することが多く、この場合、評価額が高額になる傾向があります。
主要評価方法
不動産業界のM&Aにおける企業価値評価には、いくつかの評価方法が存在します。これらは企業の資産価値や将来の収益性を反映するもので、以下の主要な方法が用いられます。
- コストアプローチ
コストアプローチでは、企業が保有する資産の現状の価値を基に評価を行います。このアプローチには、いくつかの具体的な方法があります。
- 修正純資産法
企業の保有する資産(土地、建物など)を時価で評価し、その価値から負債を差し引いて企業価値を算出します。この方法は、特に土地や建物の時価評価を中心に行われます。ただし、未実現収益(たとえば、まだ賃貸契約が成立していない収益物件など)を反映しないため、売り手側にとっては不満が生じやすい方法です。 - 原価法
建物や施設の建築にかかるコストを基に評価します。減価償却を考慮し、元々の建設費用から減価償却分を引いた金額が企業価値として算出されます。土地の評価については、取引事例比較法(後述)と併用することが一般的です。
- インカムアプローチ
インカムアプローチは、企業が将来生み出すキャッシュフローを基に評価を行う方法です。特に収益物件を持つ企業に有効な方法です。
- DCF法(割引キャッシュフロー法)
将来のフリーキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り引いて企業価値を算出します。この方法では、企業の収益性や将来の収益計画が重要な要素となり、不動産賃貸収益や開発プロジェクトの収益性を反映することができます。 - 収益還元法
不動産のNOI(純営業収益)を利回りで割って価格を算定する方法です。収益物件や賃貸物件において広く利用されます。
- マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、実際の市場取引を基に評価を行う方法です。
- 類似会社比準法
同業他社の評価指標(PERやPBRなど)を基に企業価値を算出します。この方法は、不動産管理会社や仲介業者に適用されることが多いです。 - 取引事例比較法
類似の不動産物件の過去の取引価格を参考にして評価を行います。これにより、現在の市場価値を反映した評価が可能になります。
評価に影響する要素
不動産業界におけるM&A価格に影響を与える要素には、以下のようなものがあります。
- 保有資産の特性
収益物件の割合や立地条件、賃貸実績などが評価に影響を与えます。 - 事業ポートフォリオ
仲介業務、管理業務、開発業務などの収益バランスが評価に影響します。 - 簿外リスク
環境汚染や隠れた担保権、未払い費用など、目に見えないリスクが評価に影響を与えることがあります。 - スキームの選択
株式譲渡(資産包括承継)か事業譲渡(選択的承継)かにより、評価額が変動します。
不動産業界のM&Aにおける注意点

不動産業界のM&Aでは、特有のリスクや重要な注意点があります。譲渡方法や資産評価の選定に加え、スキーム選定やリスク管理に特に注意が必要です。
特に、実物資産を多く保有する不動産会社では、資産価値の算定が難しく、適切な評価を行わなければ後々トラブルに繋がる可能性があります。
この章では、M&Aを進める際に注意すべきポイントを詳しく解説します。
スキーム選定に注意を払う
不動産業界のM&Aでは、株式譲渡と事業譲渡の選択が重要です。株式譲渡は資産と負債を全て引き継ぎますが、リスクもそのまま引き継がれます。
一方、事業譲渡では特定の資産のみを選択できますが、手続きが複雑になることがあります。適切なスキームを選ぶことが成功のカギです。
資産評価の適切な方法を選ぶ
不動産業界のM&Aでは、DCF法や収益還元法などを用いて資産を評価します。
これらは収益性を重視した方法ですが、選定を誤ると企業価値が過大評価または過小評価され、後のトラブルにつながる可能性があります。適切な評価方法の選択が重要です。
簿外リスクへの対応を行う
不動産業界では、環境問題や未払いの税金、隠れた担保権などの簿外リスクが潜んでいます。これらを見逃すと、後に大きな問題を引き起こす可能性があります。
M&A前の徹底的なデューデリジェンスが必須です。
シナジー効果の過大評価に注意する
M&A後のシナジー効果に期待が高まる一方で、過度に評価することはリスクを伴います。
事業文化や運営の違いから、想定した効果が得られない場合もあります。シナジー実現の可能性を現実的に見極めることが大切です。
不動産業界のM&A事例紹介

実際に行われた不動産業界のM&A事例を2つ紹介します。それぞれの成功要因や学ぶべきポイントを探ってみましょう。
事業承継型M&Aの事例
APAMAN株式会社は、茨城県内で不動産賃貸仲介・管理事業を展開する株式会社マイハウスの株式を取得し、グループ子会社化しました。
マイハウスは、賃貸仲介店舗を3店舗展開し、管理戸数2,622戸を誇る地域密着型の不動産企業です。
APAMANグループは、賃貸仲介や物件管理に加え、AIやRPAを活用したクラウド技術も手がけており、今回のM&Aにより、これまで培ったテクノロジーと地域密着型事業を融合させ、さらなる事業拡大を目指しています。
(情報参照元:日本M&Aセンター M&Aマガジン「APAMAN(8889)、茨城県内において不動産事業を展開するマイハウスの株式取得」)
業界再編を目的としたM&Aの事例
大東建託株式会社は、賃貸管理業界のトップ企業の一つで、業界の再編を進める中で、積極的にM&Aを行っています。
特に、管理戸数の増加とシェア拡大を目指し、業界上位10社で管理戸数の合計が400万戸を突破し、市場シェアは約20%に達するなど、業界全体における影響力を強めています。
業界内の競争が激化する中、大東建託は規模の経済を追求し、M&Aを活用して事業を拡大しています。
特に、管理業務の効率化を目指し、複数の企業とのM&Aを通じて新たな収益源を確保しました。この戦略により、業界再編を加速させ、業界の主導的なポジションを確立しました。
また、大東建託はM&Aの一環として、株式会社アスコットに対して公開買付け(TOB)を実施し、アスコットを完全子会社化しています。この買収により、大東建託は賃貸管理市場での競争力を一層強化し、さらなる規模拡大を実現しました。
(情報参照元:日本M&Aセンター M&Aマガジン「大東建託、アスコットへTOB実施へ」)
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
不動産業界でM&Aを戦略的に活用しよう

不動産業界のM&Aは、競争の激化や市場の変動に対応するため、ますます重要な戦略となっています。
事業承継や業界再編を目的としたM&Aにより、企業は規模の拡大や業務効率化を実現可能です。
今後も、シナジー効果や成長の加速を目指して、積極的なM&A活動が続くことが予想されます。
売り手・買い手双方にとって、戦略的に活用することが成功の鍵となるでしょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)