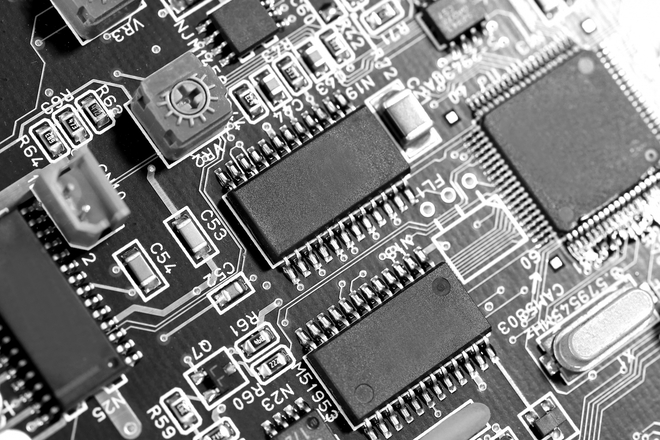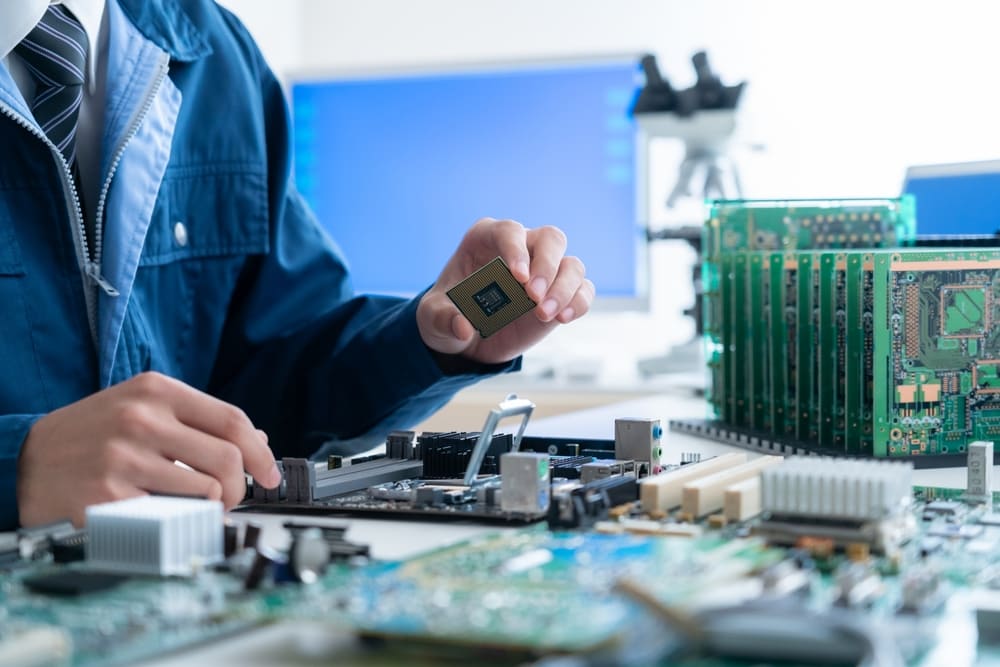食品製造業のM&A|事例でわかる価格相場と成功のポイント【2025年最新版】

後継者の不在や原材料の高騰、競争の激化など、さまざまな理由から事業の将来に悩みを抱える食品製造業の経営者の方は少なくありません。
事業の継続や廃業といった経営判断は、長年守ってきた伝統の味やブランド、そして従業員の生活にも関わるため、簡単には踏み出せないものです。
この記事では、食品製造業界におけるM&Aの動向や、業界特有のメリット・デメリットを解説するとともに、価格相場の決まり方、成功に向けたポイント、そして目的別に分類した最新の事例まで幅広く紹介します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
食品製造業界におけるM&Aの基礎知識

食品製造業界は、私たちの生活に欠かせない「食」を支える重要な産業ですが、近年は後継者不足やコスト高騰といった深刻な課題に直面しています。
こうした状況を打開する有効な経営戦略として、M&A(企業の合併・買収)が活発に行われています。
この章では、M&Aを検討する上でまず押さえておきたい、食品製造業界の定義や市場動向、そしてなぜ今M&Aが注目されているのかという基礎知識を解説します。
食品製造業とは
食品製造業とは、農畜産物や水産物といった原材料を仕入れ、工業的な規模で食料品や飲料を製造・加工し、その製品を販売して収益を得る産業です。
経済産業省の統計上は、パンや菓子、肉製品、調味料などを製造する食料品製造業と、清涼飲料や酒類などを製造する飲料・たばこ・飼料製造業に分類されますが、一般的にはこれらを総称して食品製造業界と呼ばれます。
この業界が取り扱う製品は非常に多岐にわたりますが、その製造形態は大きく2つに大別されます。
- 素材型:他の食品メーカー向けに、製品の原材料となる一次加工品(製粉、製糖など)を製造・提供する形態。
- 加工型:消費者が直接購入し、そのまま食べられる最終製品(パン、菓子、冷凍食品、惣菜、乳製品など)を製造・提供する形態。
食品製造業に従事する企業の大多数は、この「加工型」に属しており、私たちの食生活に最も身近な製品を生み出しています。
景気の変動を受けにくい安定した産業である一方、地域に根差した中小企業が多く、その土地ならではの伝統的な製法や味を守る地場産業としての側面も持ち合わせているのが大きな特徴です。
また、食品衛生法をはじめとする厳しい法規制のもとで事業運営を行う必要があり、消費者の安全・安心に対する高い意識が求められる業界でもあります。
中小企業M&Aとは?|動向や価格の決め方・事例をわかりやすく解説
食品製造業界の市場動向と課題
安定産業とされる食品製造業ですが、近年は厳しい経営環境に置かれています。
国内市場は人口減少や少子高齢化の影響で成熟期に入り、市場規模は横ばいから微減傾向で推移しています。
こうした状況下で、業界が直面している大きな課題は、以下の3つです。
原材料・エネルギーコストの高騰
世界的な需要増や天候不順、国際情勢の不安定化により、小麦や大豆、油脂といった原材料の価格が高騰しています。
さらに、電気代やガス代などのエネルギーコスト、包装資材や物流費も上昇し続けており、製造コスト全体を圧迫しています。しかし、価格競争が激しいため、コスト上昇分を製品価格へ十分に転嫁できず、収益性が悪化している企業は少なくありません。
慢性的な人手不足
日本の生産年齢人口の減少は、食品製造業にも深刻な影響を及ぼしています。特に地方の工場では労働力の確保が年々難しくなっており、生産ラインの維持や事業拡大の足かせとなっています。
熟練した技術を持つ職人の高齢化も進み、技術承継がうまくいかないという問題も顕在化しています。
深刻な後継者問題
中小企業が多い食品製造業界では、経営者の高齢化に伴う後継者不足が極めて深刻な課題です。親族や社内に適当な後継者が見つからず、優れた技術やブランド、黒字経営であるにもかかわらず、事業の継続を断念し廃業を選択せざるを得ないケースが増加しています。
業界特有の課題を解決するM&A
これまで述べたような業界特有の課題を解決する有効な手段として、M&Aが注目されています。M&Aは、単に会社を売買するだけでなく、事業の存続と成長を可能にする戦略的な選択肢です。
- コスト高への対策
大手企業の傘下に入ることで、原材料の共同仕入れや生産設備の共有によるスケールメリットが生まれ、コスト競争力を高められます。 - 人手不足・技術承継への対策
買い手企業の採用力や人材育成ノウハウを活用できるほか、他拠点の従業員との交流を通じて技術承継を進められます。 - 後継者問題の解決
M&Aによる第三者への事業承継は、後継者不在の問題を根本的に解決します。これにより、経営者は創業者利益を確保できるだけでなく、長年守ってきたブランドや伝統の味、そして大切な従業員の雇用を未来へつなぐことが可能です。
こうした背景から、近年は生産効率や販路拡大を目指す同業種間のM&Aに加え、新たな収益源を求めて外食産業や小売業などが食品製造業を買収する、異業種からのM&Aも活発化しています。
事業承継型M&Aとは?メリット・デメリット・成功のポイントを解説
食品製造業界におけるM&Aのメリット

M&Aは、企業を「売り手(譲渡企業)」と「買い手(譲受企業)」の双方に大きなメリットをもたらします。
ここでは、M&Aがもたらすメリットを売り手側と買い手側の視点から解説します。
売り手側のメリット
事業を譲渡する売り手にとって、M&Aは以下のような、事業承継や経営者個人の課題を解決する上で多くの具体的なメリットがあります。
- 後継者問題の解決と事業の存続
最大のメリットは、後継者問題を根本的に解決できる点です。親族や社内に適任者がいなくても、M&Aによって意欲ある第三者に事業を引き継げます。これにより、経営者は安心して引退できるだけでなく、自らが育てた会社・ブランド・伝統の味を未来へ存続させることが可能です。 - 従業員の雇用の維持
廃業すれば、従業員は職を失います。M&Aであれば、買い手企業に従業員の雇用を引き継いでもらうのが一般的です。従業員の生活を守れることはもちろん、買い手企業の傘下で待遇が改善されたり、新たなキャリアの機会が生まれたりする可能性もあります。 - 創業者利益の獲得と個人保証からの解放
M&Aで会社を譲渡することで、オーナー経営者は対価として「創業者利益」を金銭的対価として得られます。これは引退後の生活資金や、新たな挑戦の元手として活用できます。また、多くの中小企業経営者が抱える金融機関からの借入金に対する「個人保証」も、M&Aによって解消可能です。万が一の倒産リスクという重圧から解放される点は、精神的にも経済的にも大きなメリットです。 - 大手傘下での事業成長
自社単独では難しかった大規模な投資も、資金力のある買い手の傘下に入ることで実現可能です。例えば、老朽化した工場の刷新、HACCP対応の設備投資、新商品開発などが挙げられます。買い手の販売網やマーケティング力を活用し、ブランド価値の向上と事業のさらなる成長が期待できます。
| メリット項目 | 具体的な内容 |
| 後継者問題の解決 | 第三者への承継で、後継者不在でも事業を存続できる。 |
| 従業員の雇用維持 | 廃業による解雇を回避し、従業員の生活を守れる。 |
| 創業者利益の獲得 | 譲渡対価を得て、引退後の生活資金などに活用できる。 |
| 個人保証からの解放 | 会社の借入金に対する個人保証を解消し、経営リスクから解放される。 |
| 事業の成長加速 | 買い手の経営資源で設備投資や販路拡大が実現できる。 |
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
買い手側のメリット
事業を譲り受ける買い手にとって、M&Aは時間とコストを節約し、スピーディーに事業を拡大するための強力な手段です。
- 事業拡大にかかる時間の短縮
ゼロから工場を建て、人材を育て、販路を開拓するには数年単位の時間がかかります。M&Aであれば、すでに稼働している工場や熟練した従業員、既存の取引先といった事業基盤をすべて一括で手に入れられます。これは「時間を買う」とも言える、M&Aの最も大きなメリットです。 - 生産拠点・能力の確保
自社の生産能力が限界に達している場合や、新たなエリアに拠点を設けたい場合にM&Aは有効です。特にHACCPなどに対応した工場を獲得できれば、大きなアドバンテージになります。また、拠点を複数持つことで、災害時などのリスク分散にもつながります。 - 独自の技術・ブランドの獲得
食品製造業の競争力の源泉は、他社には真似のできない独自の製造技術にあります。M&Aは、こうした価値ある無形資産を獲得できる有効な手段です。また、地域で支持されるブランドを獲得すれば、製品ラインナップを強化し、新たな顧客層へアプローチできます。 - 優秀な人材と販売チャネルの獲得
人手不足が深刻化するなか、製造ノウハウを持つ工場長や熟練の職人を確保できることは大きなメリットです。また、売り手企業が築いた大手スーパーなどとの取引関係(販売チャネル)を引き継ぐことで、自社製品の販路を飛躍的に拡大させられます。
| メリット項目 | 具体的な内容 |
| 事業拡大のスピードアップ | 既存の事業基盤を一括で獲得し、「時間を買う」ことができる。 |
| 生産拠点・能力の確保 | HACCP対応工場などを獲得し、生産能力を増強。リスク分散にもつながる。 |
| 無形資産の獲得 | 独自の技術や確立されたブランドを獲得できる。 |
| 人材・販路の獲得 | 熟練の職人や専門人材を確保し、大手との取引関係を引き継げる。 |
食品製造業界におけるM&Aのデメリット
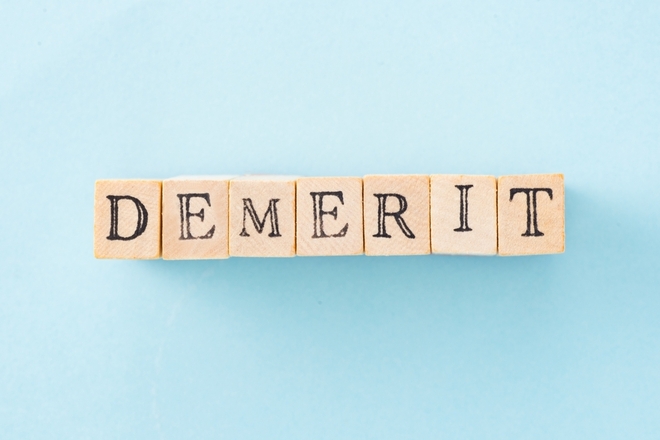
M&Aは多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットもあります。
ここからは、M&Aを検討する上で必ず理解しておくべきデメリットやリスクを、双方の立場から具体的に解説します。
売り手側のデメリット
会社を譲渡する売り手にとって、M&Aのプロセスは常に順風満帆とは限りません。交渉の過程やM&Aが成立した後に、想定外の事態に直面する可能性があります。
- 希望の条件で売却できるとは限らない
自社が持つブランドや技術に自信があっても、買い手側が同じように評価してくれるとは限りません。希望する売却価格や、従業員の雇用維持といった条件が受け入れられず、交渉が難航・決裂するケースは少なくありません。
理想の相手が見つかるまでには、長い時間がかかる可能性も覚悟しておく必要があります。 - 交渉中の情報漏洩による事業への影響
M&Aの交渉は極秘に進めるのが原則ですが、万が一情報が外部に漏れた場合、事業に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
意図せず従業員に知られた場合、不安からモチベーションが低下したり、優秀な人材が離職したりするかもしれません。
また、取引先や金融機関に不安を与え、取引の縮小や融資態度の硬化を招くリスクもあります。 - 経営権の喪失と孤独感
M&Aによって会社の経営権を完全に手放すため、オーナー経営者は長年心血を注いできた事業の意思決定に関われなくなります。
M&A後も役員として会社に残るケースもありますが、買い手企業の経営方針と自身の考えが合わず、疎外感や孤独感を覚えることもあります。 - 従業員の処遇が悪化する可能性
買い手企業との契約で雇用維持を約束したとしても、企業文化の違いや経営方針の変更により、従業員の労働環境や待遇が結果的に悪化してしまうリスクはゼロではありません。これにより、古くからの従業員が退職してしまい、守りたかったはずの組織が崩れてしまう可能性も考慮すべき点です。
| デメリット項目 | 具体的な内容 |
| 希望条件での売却難 | 希望価格や雇用維持などの条件が合わず、交渉が長期化・決裂する可能性がある。 |
| 情報漏洩のリスク | 交渉情報が漏れると、従業員の動揺や取引先の信用不安を招く恐れがある。 |
| 経営権の喪失 | 会社の意思決定に関われなくなり、経営方針の違いから疎外感を覚えることがある。 |
| 従業員の処遇問題 | 企業文化の違いなどから、M&A後に従業員の待遇が悪化し、離職につながるリスクがある。 |
買い手側のデメリット
事業を譲り受ける買い手は、売り手企業のすべてを引き継ぐからこそ、見えにくいリスクにも細心の注意を払う必要があります。
- 簿外債務や偶発債務の発覚
M&A後に、財務諸表に現れない簿外債務が発覚するリスクがあります。
食品製造業では特に、過去のずさんな品質管理に起因する大規模な製品リコールや、食中毒事故による損害賠償といった偶発債務が発生する可能性があります。
これは、買収価格を大きく上回る損失につながる恐れのある、最も警戒すべきリスクの一つです。 - 想定外の追加投資の必要性
事前の調査(デューデリジェンス)では見抜けなかった問題が、M&A後に明らかになることがあります。
例えば、生産設備の深刻な老朽化が発覚し、多額の修繕費や更新費用が必要になるケースです。
また、HACCPなどの衛生管理基準を満たすために、想定以上の大規模な工場改修が求められることもあります。 - キーパーソン(職人・工場長)の離職
M&Aによる経営方針の変更や企業文化の違いに反発し、製品の味や品質を支える核心的な人材(熟練の職人や工場長など)が退職してしまうリスクがあります。彼らが持つマニュアル化できない勘やコツが失われれば、製品の品質が維持できなくなり、ブランド価値が大きく損なわれることになります。 - 期待したシナジー効果が得られない
M&Aの目的であったはずのシナジー(相乗効果)が、計画通りに生まれないケースです。例えば、大企業の効率重視の文化と、売り手企業の職人気質の文化が衝突し、現場が混乱して生産性が低下することがあります。
また、販路は拡大したものの、生産体制が追いつかず、かえって顧客満足度を下げてしまうといった失敗も考えられます。
| デメリット項目 | 具体的な内容 |
| 簿外債務・偶発債務 | 過去の品質問題に起因するリコールなど、予期せぬ債務がM&A後に発覚するリスク。 |
| 想定外の追加投資 | 設備の老朽化やHACCP未対応など、事前の調査で見抜けなかった問題への対応費用。 |
| キーパーソンの離職 | 熟練の職人などが退職し、製品の味や品質といった競争力の源泉が失われるリスク。 |
| シナジー効果の不発 | 企業文化の衝突や現場の混乱により、期待した生産性向上や販路拡大が実現しない。 |
食品製造業界のM&A相場価格

M&Aの価格は、専門的な企業価値評価(バリュエーション)というプロセスを経て、個々の企業の状況に応じて算出されます。
ここでは、その価格が決まる基本的な考え方と、食品製造業において特に企業価値を高める要素について解説します。
企業価値評価の基本的な考え方
M&Aにおける価格は、企業の価値を客観的に評価する企業価値評価の結果をベースに、最終的には当事者間の交渉によって決定されます。
企業価値を算出するための代表的なアプローチには、以下の3つがあります。
- コストアプローチ
企業の保有する資産と負債を基準に価値を評価する方法です。代表的な手法に「時価純資産法」があり、これは帳簿上の資産・負債をすべて現在の価値(時価)に洗い直して、その差額(純資産)を企業価値とするものです。
客観性が高く、特に中小企業のM&Aでは、この時価純資産が価格交渉のベースとなることが多くあります。 - インカムアプローチ
企業の将来的な収益力に着目して価値を評価する方法です。「DCF法(Discounted Cash Flow法)」が代表的で、これは企業が将来生み出すと予測されるキャッシュフロー(現金)を、リスクなどを考慮した割引率で現在の価値に換算して算出します。
成長性が高い企業の価値を評価するのに適していますが、将来の事業計画の客観性が評価の精度を左右します。 - マーケットアプローチ
株式市場に上場している同業他社など、類似する企業の株価や財務指標を参考に価値を評価する方法です。「類似会社比較法(マルチプル法)」がよく用いられ、類似企業の株価が利益や純資産の何倍か(マルチプル)を算出し、自社の指標に掛け合わせて価値を類推します。
市場での評価が反映されるため客観性は高いですが、自社と完全に一致する類似企業を見つけるのが難しい場合があります。
実際には、これらの手法を一つだけ用いるのではなく、複数を組み合わせて多角的に企業価値を算出し、交渉の材料とするのが一般的です。
そして、算出された企業価値に、ブランド力や技術力といった目に見えない価値である「のれん(営業権)」が上乗せされ、最終的な売却価格が決定されます。
| 評価アプローチ | 特徴 | 代表的な手法 |
| コストアプローチ | 企業の純資産を基準に評価する。客観性が高い。 | 時価純資産法 |
| インカムアプローチ | 企業の将来の収益力を基準に評価する。成長性を反映しやすい。 | DCF法 |
| マーケットアプローチ | 類似する上場企業の市場評価を基準に評価する。 | 類似会社比較法 |
企業価値評価についてはこちらの記事も参考にしてください。
M&Aの企業価値評価とは?基本的な算出方法と売り手・買い手のポイントを解説【2025年最新】
食品製造業で企業価値を高める要素
では、具体的にどのような要素が、食品製造業の企業価値、特に「のれん」を高く評価させるのでしょうか。
買い手側が着目する主なポイントは以下の通りです。
- 高い収益性と将来性
単に売上規模が大きいだけでなく、利益率が高いことが重要です。価格競争に陥らず、安定して高い利益を生み出せるビジネスモデルは高く評価されます。また、健康志向や環境配慮、簡便化といった市場の成長トレンドに乗った商品を展開している場合、その将来性も企業価値に加味されます。 - ブランド力と独自性
「あのメーカーの〇〇」と消費者に指名買いされるような強力なブランド力や、長年愛されるロングセラー商品の存在は、非常に大きな価値となります。
また、他社が容易に真似できない独自の製造技術、特許なども、価格競争から脱却するための源泉として高く評価されます。 - 工場設備と品質管理体制
HACCPやFSSC22000、有機JASといった国際的な食品安全・品質認証を取得していることは、買い手にとってM&A後のリスク低減につながるため、大きなプラス要因です。また、設備の老朽化が進んでおらず、生産効率が高い工場は、買い手側が買収後に行う追加投資を抑えられるため、その分だけ企業価値が高まります。 - 強固で多様な販売チャネル
大手スーパー、コンビニ、有力な外食チェーン、生協など、安定的で多様な販路を持っていることは高く評価されます。特定の取引先に売上が過度に集中していると、その取引がなくなった場合のリスクが高いと見なされるため、販路が多様であるほど企業価値は安定します。 - 替えの効かない優秀な人材
製品の味や品質を支える熟練の職人、生産管理に長けた工場長、品質管理の専門家など、マニュアルだけでは代替できない優秀な人材の存在も評価対象です。これらのキーパーソンがM&A後も会社に残ってくれることは、事業の円滑な引き継ぎを望む買い手にとって重要な要素となります。
| 評価を高める要素 | 具体的なポイント |
| 収益性と将来性 | 高い利益率、市場の成長トレンドに合った商品展開。 |
| ブランド力と独自性 | 指名買いされるブランド力、ロングセラー商品、秘伝のレシピや特許技術。 |
| 工場設備と品質管理 | HACCPなどの国際認証の取得、老朽化していない高効率な生産設備。 |
| 販売チャネル | 大手スーパーやコンビニなど、安定的で多様な販路の確保。 |
| 人材 | 熟練の職人や工場長など、事業の核となるキーパーソンの存在。 |
食品製造業界のM&A成功のポイント

食品製造業界のM&Aを成功に導くためには、単に良い相手を見つけるだけでなく、事前の周到な準備と、専門的な視点に基づいた冷静な判断が不可欠です。
この章では、M&Aを成功させるために特に重要な3つのポイントを解説します。
M&Aの目的明確化と自社価値の整理
M&Aの検討を始める第一歩は、なぜM&Aを行うのかという目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、交渉の軸がぶれてしまい、最適な相手を選べません。
例えば、後継者不在の解決が目的なのか、大手傘下でブランドを全国に広げたいのか、創業者利益を確保して引退したいのかによって、探すべき相手企業の規模や文化、提示すべき条件は大きく異なります。
まずは自社の現状と将来像を冷静に見つめ、M&Aによって何を達成したいのかを言語化しましょう。
そして、次に重要なのが、自社の価値を客観的に整理することです。これは自社の強みは何かを棚卸しする作業です。
- ブランド・商品:地域での知名度、ロングセラー商品の有無、レシピの独自性
- 技術・設備:特許技術、独自の製造ノウハウ、HACCP対応工場の有無、設備の生産効率
- 販路・顧客:大手スーパーやコンビニとの取引実績、安定した顧客基盤
- 人材・組織:熟練した職人の存在、優秀な営業担当者、品質管理体制
これらの強みを客観的に整理しておくことで、交渉の場で自社の価値を的確にアピールでき、有利な条件を引き出すための材料となります。
事業シナジーを最大化する相手先の選定
M&Aの成功は、どれだけ大きなシナジー(相乗効果)を生み出せるかにかかっています。自社の強みを評価し、足りない部分を補完してくれる相手を見つけることが、M&Aを成功させる鍵です。
例えば、以下のような組み合わせが考えられます。
- 販路シナジー:優れた商品開発力を持つが販路が弱い自社が、全国に販売網を持つ企業と組む。
- 生産シナジー:稼働率に余裕のある自社工場が、生産能力の増強を求める企業と組む。
- コストシナジー:原材料の仕入れ量が少ない自社が、大量仕入れでコストを抑えている企業と組む。
- ブランドシナジー:若者向けの商品に強い自社が、中高年層に強いブランドを持つ企業と組む。
このように、具体的なシナジーのイメージを持つことが、最適な相手先を見極めるための重要な視点となります。
専門家と連携した業界特有リスクの洗い出し
M&Aのプロセスにおいて、最も専門性が求められるのが「デューデリジェンス(DD:買収監査)」です。これは、買い手側が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセスであり、最終的な契約条件を決定する上で極めて重要です。
売り手側も、デューデリジェンスに備えて自社の情報を整理しておく必要があります。
特に食品製造業では、以下のような業界特有のリスクを重点的にチェックされます。
- 品質・衛生管理:HACCPの運用状況、過去の食中毒や異物混入の履歴、アレルギー表示の正確性
- 設備・環境:工場の老朽化度合い、法規制(排水処理など)への対応状況
- 労務:従業員の労働時間管理、残業代の未払い、社会保険の加入状況
これらのリスクは、専門知識がなければ見抜くことが難しく、M&A後に大きな問題として表面化する可能性があります。
そのため、M&Aの検討段階から、M&Aアドバイザーや弁護士、会計士といった専門家と連携し、客観的な視点で自社のリスクを洗い出しておくことが、円滑な交渉とM&Aの成功に不可欠です。
【目的別】食品製造業界のM&A事例

M&Aは、企業の置かれた状況や目的によって、その戦略や相手選びが大きく異なります。
ここでは、食品製造業界で行われたM&Aを同業種間、異業種から、海外進出・事業承継という3つの目的に分類し、それぞれの代表的な事例を詳しく紹介します。
同業種間のM&A事例(業界再編・規模拡大)
同業種間のM&Aは、生産効率の向上や販路の共有、市場シェアの拡大といった直接的なシナジー効果を狙う、最も一般的な形態です。
山崎製パンによる神戸屋の包装パン事業取得
2022年、製パン業界最大手の山崎製パン株式会社は、業界大手の株式会社神戸屋から包装パン・デリカ食品等の製造販売事業を取得しました。
神戸屋は、ブランド価値の向上と経営資源の最適化を図るため、強みを持つフレッシュベーカリー(店内製造)事業とレストラン事業に経営を集中させることを決定しました。
一方、山崎製パンは、神戸屋の生産拠点と販売網を獲得することで、生産体制の効率化と供給体制の強化を目指しました。
国内市場が縮小するなか、大手同士が互いの強みを活かすために事業を選択・集中させた、業界再編を象徴するM&A事例です。
(情報引用元:山崎製パン株式会社 2022年8月26日付「株式会社神戸屋の包装パン事業等の譲受けに関するお知らせ」)
日清製粉による熊本製粉の子会社化
2022年、製粉業界トップの日清製粉株式会社は、九州を地盤とする熊本製粉株式会社の株式を追加取得し、子会社化しました。
熊本製粉は、九州産小麦の取扱いに強みを持ち、独自のブランド力と販売網を築いていました。
日清製粉は、このM&Aによって、これまで手薄だった九州エリアにおける事業基盤を強化するとともに、国産小麦の調達・供給体制を拡充する狙いがあります。
地域に根差した企業のブランド力と、大手企業の資本力・開発力を組み合わせ、地域経済の活性化と全国的な供給網の安定化を目指します。
(情報引用元:株式会社日清製粉グループ本社 2022年6月23日付 ニュースリリース「日清製粉株式会社による熊本製粉株式会社の株式取得に関するお知らせ」)
スターゼンと大商金山牧場の資本業務提携
2022年、食肉大手のスターゼン株式会社は、山形県で豚の生産から加工、販売までを一貫して手掛ける株式会社大商金山牧場と資本業務提携を締結しました。
スターゼンは、全国的な販売網を持つ食肉の加工・卸売(川中〜川下)に強みを持つ一方、大商金山牧場は、ブランド豚「米の娘ぶた」の生産(川上)に強みを持ちます。
この提携により、スターゼンは高品質な豚肉の安定的な調達先を確保し、大商金山牧場はスターゼンの販路を活用してブランド豚の販売を拡大します。
バリューチェーンの異なる段階に位置する企業同士が手を組むことで、生産から販売までの一貫体制を強化する「垂直統合型」のM&A事例です。
(情報引用元:株式会社 大商金山牧場 2022年4月14日付 「スターゼン株式会社との資本業務提携に関するお知らせ」)
いなば食品による焼津水産化学工業へのTOB(株式公開買付)
2024年、「CIAOちゅ〜る」などで知られるペットフード大手のいなば食品株式会社が、水産物由来の調味料や機能性素材を製造する焼津水産化学工業株式会社に対し、TOB(株式公開買付)を実施しました。
いなば食品は、ペットフード事業のさらなる成長に加え、焼津水産化学が持つカツオなどの水産物エキス抽出技術を活用し、人間向けの食品・健康食品事業を強化する狙いがあります。
一方、焼津水産化学も、いなば食品の資本力やグローバルな販売網を活用することで、研究開発や海外展開を加速させることを期待しました。
互いの事業領域を補完し、新たな成長を目指す戦略的なM&Aです。
(情報引用元:いなば食品株式会社 2024年3月27日付 リリース「焼津水産化学工業株式会社(証券コード:2812)株券に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ」)
このように、同業種間のM&Aでは、生産体制の強化や事業エリアの補完、お互いの強みを活かした事業の選択と集中といった、直接的な事業シナジーを追求するケースが多く見られます。
異業種からのM&A事例(新規参入・多角化)
食品製造業の安定性や将来性に着目し、新たな収益の柱を求めて異業種から参入する動きも活発です。既存事業とのシナジー効果を狙った戦略的なM&Aが目立ちます。
双日(総合商社)によるマリンフーズの完全子会社化
2022年、総合商社の双日株式会社は、水産加工品メーカーであるマリンフーズ株式会社を完全子会社化しました。
マリンフーズは、サーモンやエビなどを中心とした水産加工品を、量販店や外食産業向けに提供しています。
双日は、世界中に広がる自社の調達網を活用してマリンフーズに高品質な原料を安定供給するとともに、双日の持つ海外販売ネットワークを通じてマリンフーズ製品の海外展開を加速させる狙いです。
商社が持つ川上(調達)・川下(販売)の機能と、メーカーが持つ製造機能を垂直統合し、食のバリューチェーン全体を強化する事例です。
(情報引用元:双日株式会社 2022年2月9日付 ニュースルーム「双日、日本ハム子会社である水産食品加工会社の全株式を取得」)
ブロンコビリー(外食)による松屋栄食品本舗の子会社化
2022年、ステーキレストラン「ブロンコビリー」を展開する株式会社ブロンコビリーは、焼肉のタレやドレッシングなどを製造する松屋栄食品本舗を子会社化しました。
ブロンコビリーは、これまでも店舗で使用するソースやドレッシングの内製化を進めてきましたが、このM&Aにより、調味料の開発・製造能力をさらに強化しました。
自社店舗向けの製品供給を安定化させるとともに、松屋栄食品本舗が持つスーパーなどの小売店向け販路を活用し、外販事業を新たな収益の柱として育てることを目指しています。
外食企業が、自社の味の根幹を支える製造部門を内製化し、事業の多角化を図る動きです。
(情報引用元:株式会社ブロンコビリー 会社情報「ブロンコビリー早わかり」)
ファーマフーズ(バイオ)による明治薬品の子会社化
2021年、機能性素材の研究開発を行う株式会社ファーマフーズは、富山県の医薬品・健康食品メーカーである明治薬品株式会社を子会社化しました。
ファーマフーズは、独自の機能性素材(GABAなど)の研究開発力に強みを持つ一方、製品を製造するための大規模な工場を持っていませんでした。
このM&Aによって、明治薬品が持つGMP(医薬品製造基準)対応の工場と製造ノウハウを獲得し、自社素材を用いた製品の企画から製造、販売までを一気通貫で行う体制を構築しました。
研究開発型企業が、製造能力を持つ企業を買収することで、事業化のスピードを上げる戦略です。
(情報引用元:株式会社ファーマフーズ 2021年8月6日付 ニュースリリース「株式会社ファーマフーズグループへの参画についてのお知らせ」)
異業種からの参入では、買い手が持つ独自の機能(調達網、販売チャネル、研究開発力など)と、売り手の持つ製造基盤を組み合わせることで、新たな価値創造を目指す戦略的な動きが特徴的です。
クロスボーダーM&A事例(海外進出)
国内市場が成熟するなか、海外に成長機会を求めるクロスボーダーM&Aも、重要なトレンドとなっています。
キリンHDによる豪州Blackmores社(健康食品)の買収
2023年、キリンホールディングス株式会社は、オーストラリアの健康食品大手であるBlackmores Limited社を約1,700億円で買収しました。
キリンは、ビール事業で培った発酵・バイオテクノロジーを活かし、ヘルスサイエンス事業を新たな成長の柱と位置づけています。
このM&Aは、オセアニアや東南アジアで高いブランド力と広範な販売網を持つBlackmores社を獲得することで、ヘルスサイエンス事業のグローバル展開を一気に加速させるためのものです。
国内企業が、海外の有力ブランドと販路を獲得し、グローバル市場での競争力を高めるクロスボーダーM&Aの典型例です。
(情報引用元:キリンホールディングス株式会社 2023年9月22日付 ニュースルーム「ソーシャルボンド発行のお知らせ」)
森永乳業による米国の植物性食品メーカーの子会社化
2023年、森永乳業株式会社は、米国の植物由来食品メーカーであるTurtle Island Foods, SPCの株式を取得し、子会社化しました。
同社は、「Tofurky」ブランドで代替肉や植物性チーズなどを製造・販売し、米国の植物性食品市場で高い知名度を誇ります。
森永乳業は、世界的な健康志向の高まりを受けて急成長する植物性食品市場へ本格的に参入し、北米での事業基盤を確立することを目的としました。
このM&Aは、森永乳業が長年培ってきた発酵技術や製品開発力と、Tofurkyのブランド力・販売網を組み合わせることで、新たな成長ドライバーを確保するための戦略的な一手です。
乳製品という既存の枠を超え、サステナビリティや多様な食のニーズに応える姿勢を示す事例となっています。
(情報引用元:森永乳業株式会社 2023年2月10日付 ニュースリリース「米国 Turtle Island Foods, Holdings, Inc.の買収(子会社化)に関するお知らせ」)
これらの事例は、M&Aが海外への飛躍という企業の根幹に関わる経営課題を乗り越えるための強力なソリューションであることを示しています。
食品製造業界のM&Aで自社の可能性を最大化しよう

食品製造業界のM&Aは、単なる事業の売買にとどまらず、企業の存続、技術の承継、そして従業員の未来を左右する重要な経営判断です。
成功のためには、M&Aのメリット・デメリットから価格相場の仕組み、具体的な成功事例まで、多角的に理解しておく必要があります。
自社の強みを冷静に分析し、明確な目的を持って準備を進めることで、会社の可能性を最大限に引き出せます。
まずは自社の現状とM&Aの可能性を正しく知ることが、未来に向けた重要な第一歩となるでしょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)