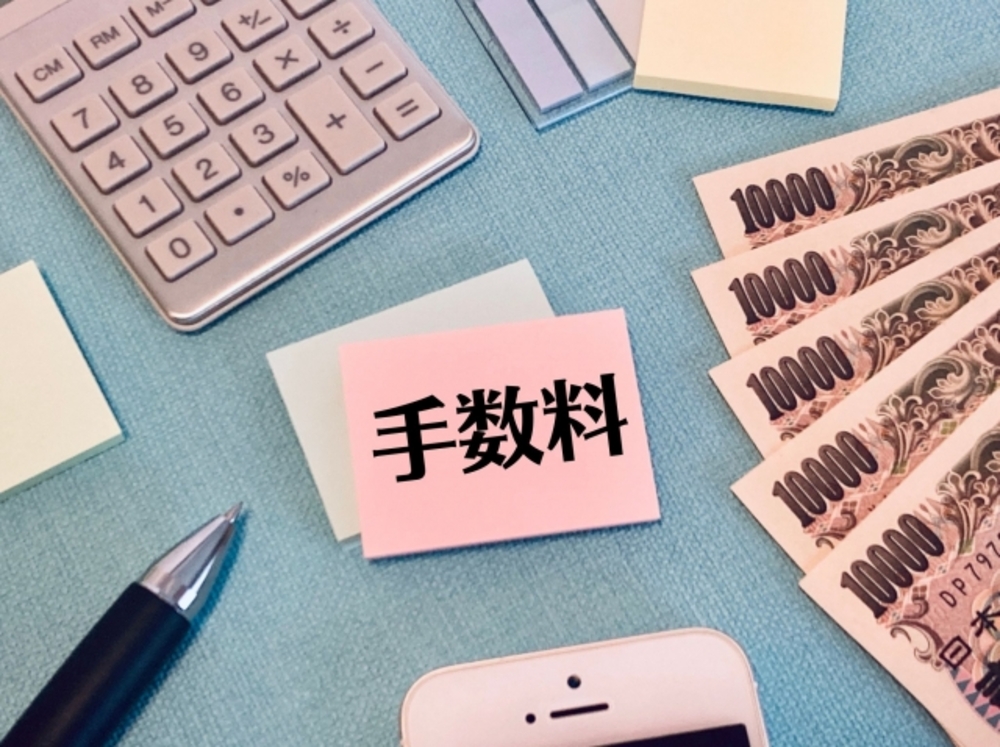M&Aにかかる費用の目安は?種類・算出基準から安くするコツまで徹底解説

事業承継や会社売却を検討するものの、M&Aにかかる費用の目安がわからず、一歩を踏み出せない経営者も多いのではないでしょうか。
M&Aの費用の目安と発生するタイミングを早期に把握することで、M&Aの適切な手順や選択すべきスキームがわかり、スムーズな進行が可能です。
本記事では、M&Aにかかる費用の種類と目安、成功報酬の算出基準、会計処理のポイントと費用を安く抑えるコツを解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aの費用とは?基本的な考え方と種類

M&Aを進める際にはさまざまな費用が発生します。
M&Aの計画段階で費用の全体像を把握し、適切な予算計画を立てM&Aをスムーズに進めましょう。
M&A費用の全体像
M&Aの主要な費用項目とその概要を以下にまとめました。
| 費用項目 | 支払者 | 概要 | 主な支払先 |
| 相談料 | 売り手・買い手 | M&Aの検討段階で仲介会社に相談する際の費用。近年は無料の場合が多い。 | M&A仲介会社 |
| 着手金 | 売り手・買い手 | 仲介会社と正式に契約を結ぶ際に支払う初期費用。M&Aが不成立でも返金されないことが多い。
※完全成功報酬制の会社は着手金が不要 |
M&A仲介会社 |
| 中間報酬 | 売り手・買い手 | 買い手候補との基本合意契約を締結した際などに支払う費用。
※完全成功報酬制の会社は中間報酬が不要 |
M&A仲介会社 |
| 月額料金(リテイナーフィー) | 売り手・買い手 | 契約期間中、毎月支払う顧問料のような費用。 | M&A仲介会社 |
| 成功報酬 | 売り手・買い手 | M&Aが最終的に成立した際に支払う最大の費用。 | M&A仲介会社 |
| デューデリジェンス費用 | 買い手(一部売り手負担) | 相手企業の価値やリスクを調査(DD)する専門家への報酬。 | 公認会計士、弁護士など |
| 弁護士・税理士報酬 | 売り手・買い手 | 契約書の作成や法務・税務に関するアドバイス、手続きを依頼する費用。 | 弁護士、税理士など |
| 買収資金・のれん代 | 買い手 | 会社や事業を買収するための対価。 | 売り手企業・株主 |
| 税金 | 売り手・買い手 | 株式譲渡や事業譲渡に伴って発生する法人税、所得税、消費税など。 | 税務署 |
| その他実費 | 売り手・買い手 | 登記費用、契約書の印紙代、交通費や通信費など。 | 法務局、各機関 |
次項からは売り手・買い手に分けて必要な費用を詳しく解説します。
譲渡側(売り手)にかかる費用
譲渡側がM&Aで負担する費用は、主に仲介会社への報酬と専門家への支払い、税金の3つに分類されます。
相談料
相談料は、M&A仲介会社に初めて相談する際に発生する費用です。企業の現状分析や簡単な企業価値評価に対する対価と位置付けられています。
現在では無料相談を実施している仲介会社が主流となっており、1時間程度の初回面談は費用がかからないケースがほとんどです。まずは気軽に相談し、M&Aの可能性や概算費用について情報収集することをおすすめします。
着手金
M&A仲介会社と正式にアドバイザリー契約を締結する際に支払う費用です。仲介会社が買い手候補を探すための資料作成やリストアップなどの活動に着手する準備金と位置づけられています。
着手金は0〜200万円の範囲で定められることが多く、着手金がかからない仲介会社もあります。M&Aが不成立の場合も着手金は返金されないことが一般的です。
中間報酬
中間報酬は、買い手候補との間で基本合意書を締結した段階で支払う費用です。成功報酬の一部前払いと位置づけられています。
中間報酬の相場は成功報酬の10〜20%程度で、着手金と同様、M&Aが最終的に成立しなくても返還されないことが通例です。中間報酬の金額は仲介会社によって異なり、中間報酬のかからない仲介会社もあるため、契約前に確認が必要です。
弁護士・税理士報酬
M&Aでは法務や税務に関する専門的な知識が不可欠であるため、弁護士や税理士といった専門家への報酬が発生します。
- 弁護士費用
M&A契約書(秘密保持契約書、基本合意書、最終契約書など)の作成やレビュー、法務デューデリジェンスの実施
契約書作成は5~数十万円程度が相場 - 税理士費用
M&A後の税務処理に関するアドバイス、税務申告、税務相談
専門家費用はM&Aの規模や複雑さ、依頼する業務内容によって異なります。M&A仲介会社によっては提携している専門家を紹介してもらえる場合もあるので、相談してみると良いでしょう。
デューデリジェンス関連費用
デューデリジェンス(DD)は、買い手が実施する対象企業の価値やリスクの詳細調査を指し、費用は基本的に買い手側が負担します。ただし、売り手側も必要な資料の準備や情報開示に際し、自社の顧問弁護士や会計士に対応を依頼する場合に費用が発生します。
費用は調査の範囲によっても異なりますが、小規模な取引で数十万~300万円程度、中規模で200万円から1,000万円程度が目安です。
月額料金(リテイナーフィー)
月額料金は、M&A仲介会社との契約期間中に毎月支払う固定費用です。仲介会社が継続的にサポートを提供するための費用として位置づけられます。
金額は仲介会社の規模やサービス内容によって異なり、月額料金を設定しない完全成功報酬制の会社もあります。
成功報酬
成功報酬は、M&A取引が最終的に成立し、クロージングが完了した時点で支払う費用です。譲渡価格に応じて金額が決まることが一般的で、M&A費用の中でも大きな割合を占めます。
多くの仲介会社では、取引金額に一定の料率を掛けて計算するレーマン方式と呼ばれる算出方法を採用しています。一般に金額が大きくなるほど料率は低くなりますが、成功報酬の算定基準によっても金額が異なるため、契約前に確認が必要です。
税金(法人税等)
M&Aで会社や事業を譲渡した際には、譲渡益に対して税金が課されます。
株式譲渡の場合、個人株主には譲渡益に対し約20%の所得税と住民税が課され、法人株主には法人税(実効税率約30%)が適用されます。事業譲渡の場合は、譲渡代金が法人税の課税対象となり、株主が配当や退職金として受け取る際に再度税金がかかる点に注意しましょう。
M&Aのスキームによる税務処理の違いは「M&Aの費用の会計処理と税務上の注意点」で解説します。
(情報参照元:
国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
財務省「法人税を知ろう」)
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
譲受側(買い手)にかかる費用
会社や事業を買収する譲受側(買い手)には、買収資金に加え、相手企業を調査する費用などがかかります。
相談料
買い手側の相談料も、売り手側と同様に無料としている仲介会社がほとんどです。多くの場合、M&A戦略の立案や譲渡案件の紹介など、初期段階の相談には費用負担が生じません。
着手金
売り手側と同様、仲介会社との契約時に着手金が発生します。
M&Aの成立・不成立にかかわらず返金されないことが一般的です。
近年は着手金不要のサービスが増えている一方で、買い手側のみ着手金を設定する仲介会社もあります。買い手の条件に合う譲渡案件を探す労力が大きいことが理由です。
中間報酬
基本合意締結時に支払う中間報酬は買い手側にも発生します。
基本合意後のデューデリジェンスなどで問題が発覚し、取引が中止になった場合でも中間報酬は基本的に返金されません。
デューデリジェンス費用
買い手側のデューデリジェンス(DD)費用は高額になりやすく、取引規模や調査の範囲によって金額が異なります。
小規模な取引であれば内容によって数十万~数百万円程度、大規模な取引では数千万円単位になることも少なくありません。また、法務や財務の他にビジネス、人事などのデューデリジェンスも実施する場合は追加の費用が必要です。
しかし潜在的なリスクを発見し、M&A後のトラブルを防ぐために欠かせない投資です。
成功報酬
成功報酬は取引金額に応じて料率が決まり、クロージング完了時に支払う報酬です。買い手側の成功報酬もレーマン方式で算出されるケースが一般的です。
M&A仲介会社を利用する場合、仲介会社が売り手・買い手の双方から成功報酬を受け取る両手取引が主流であるため、買い手側も売り手側とほぼ同額の成功報酬を負担することになります。
買収資金・のれん代
M&Aにおける買い手にとって最大の費用が、対象企業を買収するために支払う買収資金(のれん代含む)です。
- 買収資金:対象企業の株式や事業を買い取るために必要な資金。企業の評価額に基づいて決定される。
- のれん代:買収価額が被買収企業の純資産額を上回る場合に発生する差額。将来の超過収益力を期待して支払われる。
買収資金には対象企業の純資産以外に、買収した企業のブランド力、技術力、顧客基盤、ノウハウなど、貸借対照表に計上されていない無形資産の価値を表す「のれん代」が含まれることがあります。
買収資金は通常、自己資金や金融機関からの借り入れなどで調達しますが、のれん代はM&A後に償却処理されるため、買収後一定期間の財務状況に影響を与える可能性があります。
税金(登録免許税、消費税等)
M&Aの手法(スキーム)によっては、不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税、事業譲渡の場合は課税対象となる資産に対して消費税などが発生します。
登録免許税
所有権移転登記などの各種登記時に課される税金。資産種別で税率が異なる。
不動産取得税
不動産を取得したときにかかる都道府県税。税率は固定資産税評価額の3%から4%程度で、取得する不動産の価値が高いほど税負担も大きくなる。
かかる税金は取引スキームによっても異なり、株式譲渡では買い手側に原則税金はかかりません。
(情報参照元:
国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」
総務省「地方税制度|不動産取得税」)
M&Aの費用目安と相場感
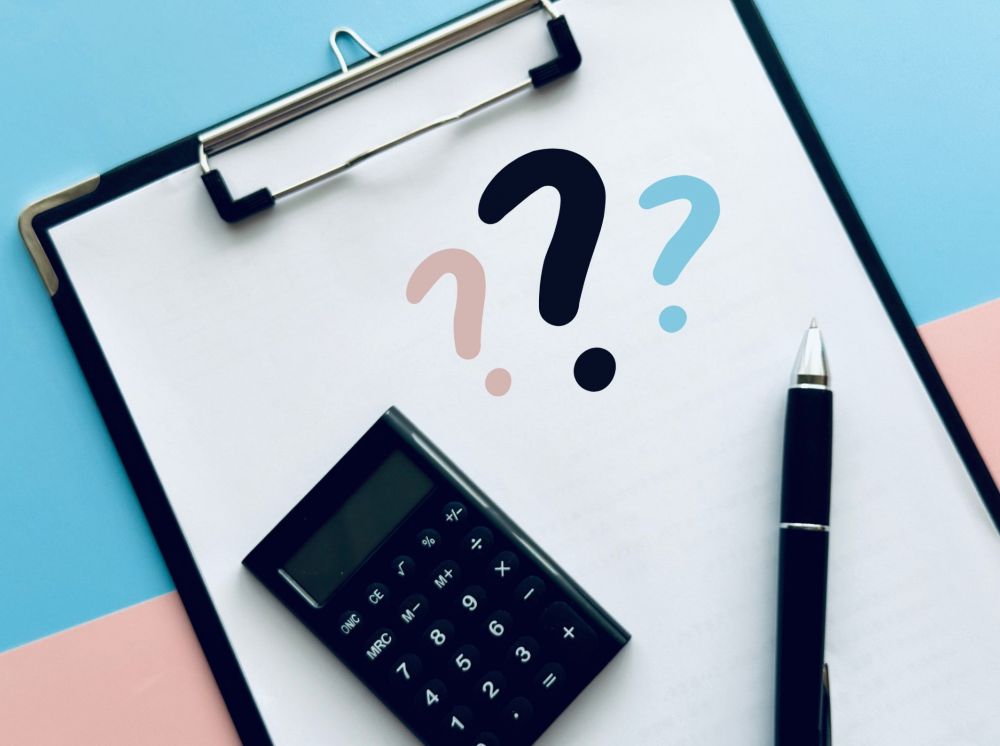
M&Aにかかる費用の相場は、案件の規模や業種、M&Aのスキームなどによって大きく変動します。
それぞれの特徴を押さえて適切に資金計画に組み込みましょう。
業種による相場の違い
業種によってM&A費用の相場は変わる傾向があります。企業価値の算定方法や取引の複雑さ、デューデリジェンスの工数が業種ごとに異なるためです。
例えば、IT企業や製造業のように技術的な側面が強く、知的財産や専門的な設備が多い業種の場合、技術デューデリジェンス(テクノロジーDD)や知的財産デューデリジェンス(IPDD)などの専門的な調査が必要となり、費用が高額になりやすい傾向にあります。
また、医療・介護業界では許認可の確認や法令遵守状況の調査が必須となり、法務デューデリジェンスの調査費用が高額になりがちです。
一方、飲食業やサービス業など、比較的事業構造がシンプルで財務や法務面でのリスク評価に特殊性のない業種では、デューデリジェンスの範囲が限定され、費用を抑えやすい傾向にあります。
M&A規模別の相場の違い
M&Aの規模(取引価格)が大きくなるほど、関連する費用も高額な傾向にあります。大規模なM&Aでは調査すべき事業拠点や子会社が多く、デューデリジェンスの範囲も広がるためです。
小規模なM&A(スモールM&A)の場合は、デューデリジェンスの範囲が限定的なケースが多く、弁護士や税理士への報酬も高額にはなりにくいでしょう。取引金額が数千万円から数億円程度であれば、仲介会社の手数料も比較的少額な傾向です。
一方、大規模なM&A(ミドルM&AやラージM&A)では、取引金額が数十億~数百億円に及ぶこともあります。必要に応じて複数の仲介会社やFA、多数の専門家チーム(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントなど)が携わるためです。
仲介会社の成功報酬についても、取引価格が大きければ成功報酬額も大きくなる傾向にあります。
海外・国内の費用の違い
海外企業が関わるクロスボーダーM&Aは、以下の理由で国内M&Aに比べて費用が高額になる傾向にあります。
- 専門家の数と質:現地の法律や税務、商慣習に精通した海外の弁護士や会計士
- コミュニケーションコスト:専門的な翻訳・通訳の費用や、時差による調整コスト
- 調査範囲の拡大:対象国の法規制や商慣習、政治的リスク
- その他の実費:関係者の渡航費や滞在費
海外の専門家に依頼する場合、先進国では日本と同等以上の費用が発生するほか、為替リスクも考慮に入れなければなりません。
M&A成功報酬を算出する方法と基準

M&A費用の中で大きな割合を占める成功報酬は、レーマン方式と呼ばれる算出基準を用いて計算されることが一般的です。
ここでは、レーマン方式によるM&A仲介報酬の算出方法と、取引金額の基準について解説します。
レーマン方式による算出方法
レーマン方式とは、M&Aの取引金額に応じて手数料率が段階的に変動する報酬体系です。
取引金額が大きくなるほど料率が下がる累進構造が特徴で、業界標準として広く採用されています。
一般的な料率テーブルは以下の通りです。
| 取引金額 | 手数料率 |
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
【計算例:取引金額が7億円の場合】
- 5億円以下の部分: 5億円 × 5% = 2,500万円
- 5億円超 7億円以下の部分: (7億円 – 5億円) × 4% = 800万円
- 合計成功報酬額: 2,500万円 + 800万円 = 3,300万円
取引金額全体に一律の料率を掛けるのではなく、金額を段階に分けて計算してから、合計して算出します。取引金額が5億円以下であれば一律5%で算出が可能です。
ただし、レーマン方式の料率や算出方法は、仲介会社によって若干異なる場合があります。また、取引金額によらず高品質なサービスを提供するために、レーマン方式を基本としながら最低報酬金額を設定している会社もあるので、事前に確認しましょう。
取引金額の算出基準
レーマン方式における成功報酬の算定基準には、主に以下の3つの方式があります。
| 算出基準 | 内容(ベースとなる金額) | 売り手への影響 |
| 株式価値(譲渡金額)基準 | 株主が実際に受け取る株式の対価(オーナー受取額)。 | – 計算がシンプルで納得感を得やすい。
– 負債が多くても手数料に影響せず、負担を抑えやすい。 |
| 企業価値基準 | 株式価値に、会社の有利子負債(借入金など)を加えた金額
(買い手が引き継ぐ実質的な経済価値)。 |
– 借入金などが多いほど手数料が高額になる。 |
| 移動総資産基準 | 株式価値に、負債の総額を加えた金額(対象企業の事業価値全体)。 | – 買掛金なども含めた負債総額が加算されるため、手数料がもっとも高額になりやすい。 |
どの基準を採用しているかによって、同じ取引でも成功報酬の金額は大きく異なる点に注意しましょう。
例えば、株式の売却価格が3億円、負債総額が2億円の会社の場合、株式価値基準では3億円を基準に算出しますが、移動総資産基準なら5億円が計算ベースとなり、成功報酬額も高額になります。
契約前には、どの算出基準が適用されるのか確認が必要です。
企業価値算定にかかる費用
M&Aの取引価格を決定する上で、自社の価値を客観的に評価するための企業価値評価(バリュエーション)が必要です。小規模な企業の場合、簡易的な企業価値算定であれば数十万円程度の費用で済むこともあります。
しかし、事業内容が複雑であったり、複数の事業部門を持っていたりする企業の場合、詳細な分析や複雑な算定手法が必要となり、費用が数百万円規模になることも少なくありません。
企業価値算定評価はM&A仲介会社のサービスに含まれることもあるので、依頼が可能か確認してみましょう。
M&A費用が高額になる要因

M&Aの費用は、以下のような要因によって想定よりも高額になることがあります。
- 着手金や中間報酬がかかる料金体系
着手金や中間報酬、リテイナーフィー(月額料金)は、交渉が長期化した場合に支払総額が大きくなる要因です。万が一破談になっても返金されず、そのまま損失になります。 - 成功報酬の算定基準が高額になるケース
成功報酬の計算基準が移動総資産基準や企業価値基準である場合、借入金や買掛金が多い会社は、譲渡金額のみを基準とする場合よりも成功報酬が高額な傾向です。 - デューデリジェンスのサポート費用が高額になる
売り手側の帳簿や資料に不備があったり、複雑な法的問題を抱えていたりすると、顧問弁護士や会計士に追加のサポート依頼が必要となり、費用が別途発生してしまいます。
特定の専門分野(法務、税務、会計、事業、ITなど)に特化した専門家を多く起用するほど費用が高額になりがちです。
次章で解説する費用を抑えるコツを実践することで、適正な費用でのM&A実現が可能です。
M&Aの費用を安く抑える4つのコツ

高額になりがちなM&A費用ですが、ここで紹介するポイントを押さえることで賢くコストを抑えられます。
完全成功報酬型の仲介会社を選ぶ
M&Aにかかる初期費用を抑えたい場合は、完全成功報酬型の仲介会社を選ぶことがおすすめです。
完全成功報酬型とは、M&Aが最終的に成立した場合にのみ成功報酬が発生し、相談料、着手金、中間報酬、月額料金(リテイナーフィー)などが無料、または低額に設定されている費用体系を指します。
M&Aが不成立に終わった場合は費用が発生しないため、完全成功報酬型はM&Aが初めての場合や、初期費用を抑えたい場合に適しています。
ただし、成功報酬の料率が高めに設定されている場合もあるため、複数の仲介会社を比較検討し、最終的な成功報酬額を事前にシミュレーションすることが大切です。
デューデリジェンスの範囲を絞る
デューデリジェンスは買い手にとって不可欠なプロセスですが、範囲を適切に絞ることで費用を大幅に削減できます。
まずは特に高いリスクが想定される分野や、買収後の事業統合に影響が大きい項目から優先的にDDを実施しましょう。IT企業なら知的財産権の確認、製造業なら設備の状態確認、サービス業なら人材の定着状況などがその一例です。
小規模な取引では、財務デューデリジェンスと基本的な法務デューデリジェンスのみに絞るといった方法も考えられます。ただし、重要なリスクを見逃さないよう、調査範囲は専門家と相談のうえ慎重に決定しましょう。
スキームを検討する
M&Aの手法(スキーム)によっても、税負担や手続きの費用が大きく異なります。
- 株式譲渡
手続きがシンプルで、登記費用などの実費を抑えやすい。個人株主の場合は税率も約20%と低め。 - 事業譲渡
特定の事業のみを譲渡したい場合に有効だが、資産ごとの名義変更が必要で手続き費用がかさみやすい。消費税も課税されるため税負担が大きくなる傾向。 - 会社分割や株式交換などの組織再編
一定の要件を満たせば税制上の優遇措置を受けられる。適格要件を満たす組織再編なら、課税を繰り延べられる点もメリット。
スキームの選択次第で大幅な節税も可能なため、専門家のアドバイスを得て事前にシミュレーションすると良いでしょう。ただし譲渡後の事業運営や従業員の処遇なども考慮に入れ、総合的な判断が必要です。
複数の仲介会社を比較する
M&A仲介会社を選ぶ際は、複数の会社を比較検討することが大切です。
仲介会社によって、費用体系(着手金の有無、中間報酬、成功報酬の料率や算出基準)、得意とする業種、M&Aの規模、サポート範囲、実績などが異なります。少なくとも2〜3社から見積もりを取得して比較検討することが不可欠です。
比較の際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 料金体系(完全成功報酬型か、着手金・中間報酬が必要か)
- 成功報酬の算定基準(譲渡金額ベースか、移動総資産ベースか)
- レーマン方式の料率と最低報酬額
- サービス範囲(企業価値算定、デューデリジェンスサポートの有無)
- 実績と専門性(自社の業種での成約実績)
- 担当者の専門性や業界知識
上記を総合的に比較し、もっともコストパフォーマンスが高く信頼できるパートナーを選びましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aの費用の会計処理と税務上の注意点
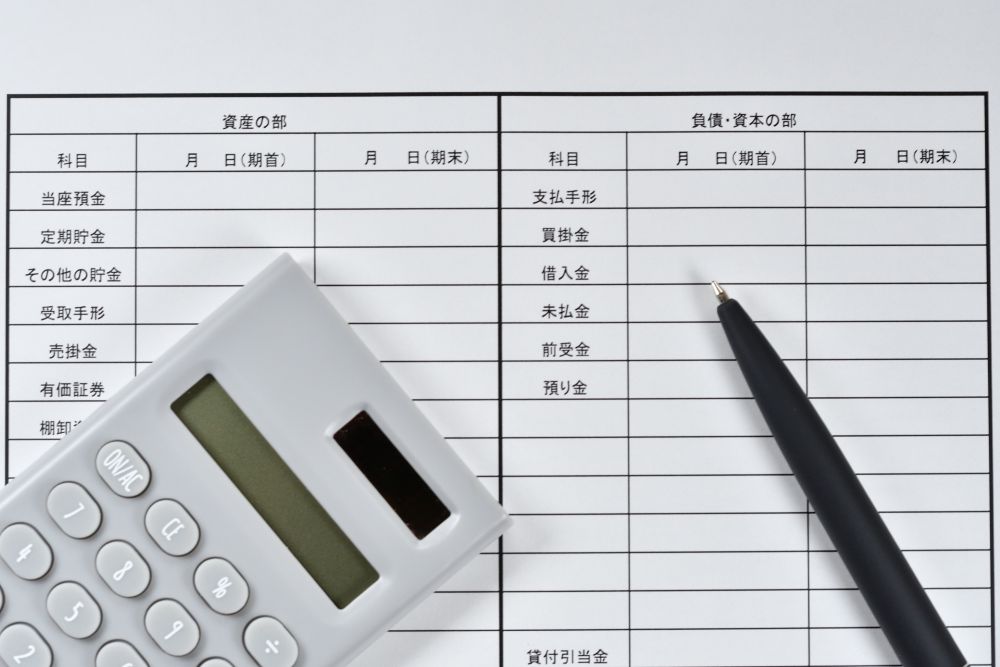
M&Aでは、選択したスキームによって会計処理と税務処理が異なります。ここでは、主要なスキームごとの会計処理と税務上の注意点について解説します。
株式譲渡の場合
株式譲渡は手続きがシンプルで、許認可の再取得も不要なため、中小企業のM&Aでもっとも多く選択されるスキームです。
【売り手側】
個人株主の場合、株式譲渡益は譲渡所得として確定申告が必要です。取得価額と譲渡価額の差額が課税対象となり、約20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
法人株主の場合は、譲渡益が法人の益金に算入され、法人税の対象となります。実効税率は約30%で、個人株主よりも重い税負担です。
【買い手側】
取得した株式は、投資有価証券として資産計上されます。買収価格が譲渡企業の純資産を上回る部分は、のれんとして無形固定資産に計上し、最長20年で償却します。
のれんの償却費は、損益計算書上で販売費および一般管理費として計上され、税務上も損金算入が可能です。ただし、のれんが過大と判断されると、減損処理が必要となることがあります。
(情報参照元:
国税庁「令和6年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた」「No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」
財務省「法人税を知ろう」
PwC Japan「のれんの償却と減損実務」)
株式交換の場合
株式交換は、買い手企業が譲渡企業の全株式を取得し、対価として買い手企業の株式を交付するスキームです。現金を支払わずに100%子会社化できるメリットがあります。
【買い手側】
M&A関連費用は、原則として「支払手数料」などの勘定科目で費用処理(損金算入)します。
取得した売り手企業の株式は「関係会社株式」として資産計上します。買収価額と純資産の差額はのれんとして計上し、20年以内で償却することが原則です。
【売り手側】
売り手企業の株主は、自身が保有していた売り手企業の株式と引き換えに買い手企業の株式を取得するため、原則として課税は発生しません。ただし非適格株式交換と判断された場合、株式譲渡と同様に課税が発生するため注意が必要です。
(情報参照元:国税庁「第4節 組織再編成」)
事業譲渡の場合
事業譲渡は、買い手企業が売り手企業の特定の事業部門や資産・負債を選んで承継するスキームです。企業の一部だけを売買したい場合や、特定の事業のみを切り離したい場合に用いられます。
【買い手側】
M&A仲介会社への成功報酬やデューデリジェンス費用などは、原則として「支払手数料」などの勘定科目で費用処理(損金算入)します。
譲り受けた資産や負債は、それぞれ適正な価額で計上します。のれんとして計上した部分は、20年以内で償却することが原則です。
【売り手側】
M&A仲介会社への報酬などは、譲渡費用として損金算入が可能です。
譲渡した資産の簿価と譲渡価額の差額が、譲渡益または譲渡損として損益計算書に計上されます。譲渡益は法人税の課税対象です。また、譲渡資産には消費税が課税されます(土地を除く)。
(情報参照元:国税庁「No.6105 課税の対象」「No.6201 非課税となる取引」)
合併の場合
合併は、複数の会社が統合して一つの会社になるスキームです。吸収合併と新設合併がありますが、実務上は吸収合併が大半を占めます。
【存続会社(買い手側)】
合併に関連して発生する仲介手数料や弁護士・税理士費用などは、原則として「支払手数料」などの勘定科目で費用処理(損金算入)します。
消滅会社から引き継いだ資産・負債は適正な価額で計上し、取得原価と純資産の差額は「のれん」として計上し、20年以内で償却することが原則です。
【消滅会社(売り手側)】
消滅会社のM&A関連費用も、原則として損金算入が可能です。適格合併と認められる場合、株主に対しては原則として課税が繰り延べられます。非適格合併の場合は株式の譲渡とみなされ、課税が発生します。
(情報参照元:e-Gov法令検索「法人税法第62条2」)
税務上の注意点
M&Aスキームによっては、適格要件を満たすかどうかで税務上の取り扱いが大きく異なる場合があります。
例えば、株式交換や合併、会社分割などでは、適格要件を満たすことで課税が繰り延べられる(非課税となる)メリットがあります。ただし事業の継続性、株式の保有割合、従業員の引き継ぎなどの要件のいずれか一つでも満たさない場合は課税が発生します。
不適切な税務処理をしてしまうと、後に多額の追徴課税を招くリスクがあるため、スキームを検討する段階から、M&Aに精通した専門家からアドバイスを受けるようにしてください。
(情報参照元:財務省「組織再編成に係る税制」)
M&A仲介会社の必要性と役割

M&A仲介会社は、専門家として売り手と買い手の間に入り、中立的な立場でM&Aの成立を支援する役割を担います。ここでは、M&A仲介会社の役割と活用するメリットについて解説します。
M&A仲介会社の業務内容
M&A仲介会社のサポートは多岐にわたります。
- M&A戦略の立案・相談
- 企業価値評価(バリュエーション)
- 買い手・売り手候補の探索と提案
- 交渉の場の設定と条件調整のサポート
- デューデリジェンスのサポート
- 各種契約書の作成支援
- M&A成立(クロージング)までの手続き全般の支援
M&A仲介会社が上記の専門的な業務を担うことで、経営者は本業に集中できます。
M&A仲介会社に依頼するメリット
専門家であるM&A仲介会社に依頼するメリットは以下の通りです。
- 最適な相手とのマッチング
独自のネットワークを持っているため、自社では見つけられない最適な候補先が見つかりやすい。 - M&Aプロセスの円滑化
法務や財務、税務の専門家が在籍しているため、行政手続きやデューデリジェンスをワンストップでスムーズに進められる。
売り手・買い手の思惑が一致しない場面でも、中立的な立場から合意形成へと導ける。 - 有利な条件での交渉
過去の事例や専門知識に基づき、客観的な立場で交渉を進めるため、より有利な条件での成約が期待できる。 - リスクの回避
専門的な視点から潜在的なリスクを洗い出せるため、デューデリジェンスや契約書作成において、将来のトラブルにつながる要素を排除できる。 - 時間と労力の削減
複雑な手続きや交渉を代行してくれるため、経営者は本業に集中できる。
M&Aは専門的な知識とノウハウが不可欠であり、経営者が本業の傍ら単独で進めることは困難でしょう。専門家であるM&A仲介会社が間に入ることで、手続きや交渉を滞りなく進められます。
M&A仲介会社に依頼する際の注意点
M&A仲介会社に依頼する際には注意すべき点もあります。
M&Aにおいては売り手の「高く売りたい」思惑と、買い手の「安く買いたい」思惑が相反する利益となることが一般的です。M&A仲介の多くは両手取引であるため、早期成約を見込める方法や再度取引が見込める買い手が優先されることもあります。
依頼者に最適でない条件を提案される可能性もあるため、仲介契約前に利益相反時の対応について確認しておくことが大切です。
また、契約書に専任条項がある場合は、契約期間中に他の仲介会社を利用できません。契約期間や解約条件が妥当か、契約前に確認してください。
M&A仲介会社の選び方
信頼できるM&A仲介会社を選ぶためには、以下の3つのポイントを比較検討しましょう。
- 費用体系の透明性
料金体系が明確でわかりやすいか、成功報酬の算出基準や追加費用の有無などを丁寧に説明してくれるか - 実績と専門性
自社の業種や規模に近いM&Aの成約実績が豊富か、担当コンサルタントが業界に精通しているか - サポート範囲
M&A成立後の統合プロセス(PMI)までサポートしてくれるか
着手金や中間金が不要な完全成功報酬制は、依頼者にとってわかりやすくリスクが低いといえます。
また、M&Aでシナジー効果を生み事業を成功に導くためには、円滑な事業の引き継ぎまで見据えたサポート体制がある会社を選ぶことも大切です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aの費用目安を把握し、信頼できる仲介会社を選ぼう

M&Aの費用は複雑で高額になりがちですが、事前に費用や税制の仕組みを正しく理解することで、適切な予算計画を立て、安心して手続きを進められます。
M&Aの費用について相談する際には、自社の業界に精通した信頼できるパートナー(M&A仲介会社)を選ぶことが大切です。手数料の仕組みを明確に開示してもらいましょう。
複数の会社を比較検討し、料金体系だけでなく実績や担当者との相性も見極めながら、納得のいくM&Aの実現を目指してください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)