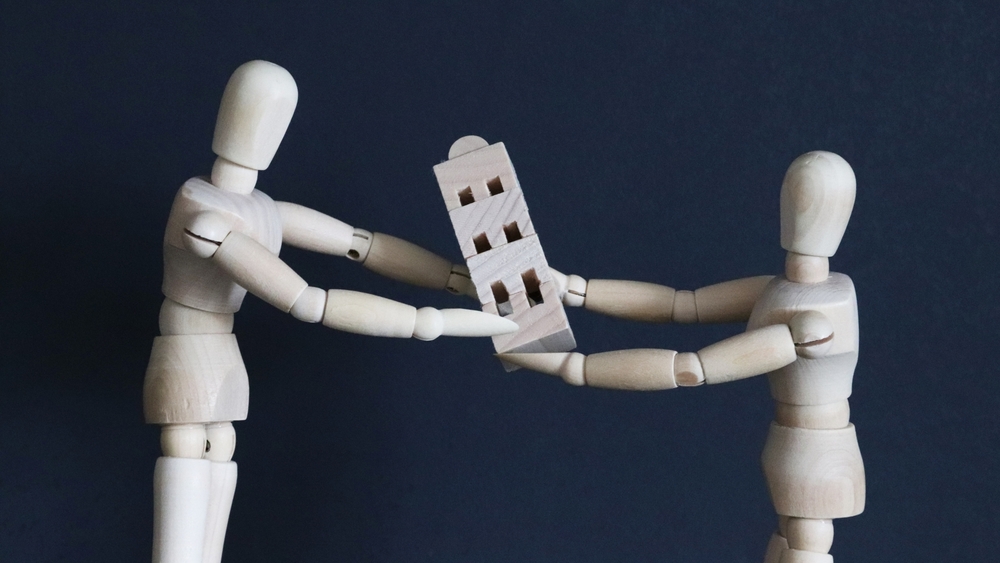会社売却が従業員に与える影響とは?メリット・デメリットから守る方法まで徹底解説

会社売却を検討する際、「雇用は継続されるのか」「待遇は悪くなるのか」「退職者が続出するのではないか」といった不安を抱える経営者の方は少なくありません。
実際、適切な対応を怠ると従業員の大量離職や労働紛争に発展するリスクがあります。
本記事では、会社売却が従業員に与える具体的な影響から、メリット・デメリット、トラブル防止策、従業員を守るための具体的方法まで、M&A専門家の視点から詳しく解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
会社が売却されるとはどのような状態?

会社売却が従業員に与える影響を正しく理解するためには、まず会社売却の仕組みと手法を把握しておく必要があります。
会社売却は、単に会社を手放すことではなく、会社の経営権を第三者に承継させるための経営判断です。
どの手法を選択するかによって、従業員の雇用契約の扱われ方が根本的に異なるため、その違いを明確に理解することが、従業員を守るための第一歩です。
会社売却の定義と主な手法

会社売却(M&A)とは、会社の経営権を第三者へ有償で譲渡(売却)する行為を指します。
後継者不在の問題を解決し、会社の存続と成長、そして従業員の雇用を守るための有効な手段として、近年多くの中小企業で活用されています。
主な手法として「株式譲渡」「事業譲渡」「合併・会社分割」の3つがあり、それぞれ従業員への影響が異なります。
株式譲渡
株式譲渡は、中小企業のM&Aにおいて多用される手法です。オーナー経営者が持つ株式を買い手に売却するだけで経営権が移るため、手続きが比較的シンプルです。
会社法人はそのまま存続し、株主が変わるだけなので、従業員が結んでいる雇用契約や会社が持つ許認可、取引先との契約なども原則としてそのまま維持されます。
従業員の雇用を維持したいと考える経営者にとって、基本となる選択肢です。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の特定の事業部門や工場、店舗などを選んで売却する手法です。
会社全体ではなく、資産や負債を個別に選んで売買契約を結びます。この手法では、従業員の雇用契約は自動的には引き継がれません。
従業員は一度、現在の会社を退職し、買い手企業と新たに雇用契約を結び直す転籍という形を取ります。
従業員一人ひとりの同意が必要になるため、交渉が複雑になりやすい点も特徴です。
合併・会社分割
合併は複数の会社が一体化する手法、会社分割は会社の一部を切り離して新しい会社や既存の会社に承継させる手法です。
これらは組織再編行為と呼ばれ、権利や義務は包括的に承継されます。そのため、従業員の雇用契約も原則としてそのまま引き継がれます。
ただし、手続きが非常に複雑であり、主に大企業同士のM&Aで用いられることが多く、中小企業のM&Aで選択されるケースは株式譲渡に比べて少ないです。
| 手法 | 概要 | 従業員の雇用契約への影響 |
| 株式譲渡 | 会社のオーナー(株主)が保有する株式を買い手企業に売却し、経営権を移転する手法。 | 会社自体は存続するため、雇用契約は原則としてそのまま買い手企業に引き継がれる。 |
| 事業譲渡 | 会社の事業の一部またはすべてを買い手企業に売却する手法。 | 雇用契約は自動的に引き継がれず、従業員は買い手企業と新たに雇用契約を結び直す必要がある。 |
| 合併・会社分割 | 複数の会社を一つに統合したり、会社の一部を切り出して別会社としたりする組織再編の手法。 | 権利義務が包括的に承継されるため、雇用契約は原則としてそのまま引き継がれる。 |
経営者が会社売却を決断する主な理由

長年手塩にかけて育ててきた会社の売却を決断するには、経営者としてさまざまな葛藤や想いがあります。なかでも中小企業の経営者がM&Aを決断する背景には、いくつかの共通した理由が存在します。
状況と照らし合わせることで、会社売却という選択肢をより客観的に捉えられるでしょう。会社売却の背景を理解することで、従業員への適切な説明と対応策を検討できます。
以下では経営者が売却を決断する主な4つの理由について詳しく解説します。
後継者不在
中小企業が会社売却を決断する理由が後継者不在です。親族内に適任者がいない、あるいは承継の意思がないケースや、社内に経営を任せられる有能な役員・従業員が見当たらないケースがこれに該当します。
経営者の高齢化が進むなか、事業の将来を案じ、会社の技術や従業員の雇用を守るために、外部の意欲ある企業に会社を託すという選択をする経営者が増えています。
これは、廃業を避け、会社を存続させる、そして従業員の雇用を守るための前向きな経営判断です。
経営者の高齢化・健康問題
経営者の高齢化も会社売却を検討する大きなきっかけです。経営には気力と体力が不可欠ですが、年齢と共に第一線で指揮を執り続けることが困難になる場合があります。
また、突然の病気や体調不良により、事業継続が難しくなるリスクも考えられます。「まだ元気なうちに、信頼できる相手に会社を譲り、従業員の将来に道筋をつけたい」という想いから、計画的にM&Aを進めるケースは少なくありません。
これは、経営者自身と家族、そして従業員を守るための責任ある決断といえます。
創業者利益の獲得
会社売却は、オーナー経営者がこれまで投下してきた資本と労力を回収し、引退後の生活資金となる創業者利益を確保する手段でもあります。
中小企業のオーナー経営者にとって、会社の株式は個人資産です。会社を高く評価してくれる買い手に株式を売却することで、まとまった資金を得られます。
経営者は安心して引退でき、充実したセカンドライフを実現できます。従業員の雇用を守ることと、経営者自身の人生設計を両立させるための現実的な選択肢です。
事業の将来性への不安と成長戦略
自社単独での成長に限界を感じたり、業界の先行きに不安を感じたりすることも、会社売却の動機です。例えば、大手企業との競争激化や技術革新への対応の遅れ、人材採用の困難さなどの課題が挙げられます。
このような状況で、より大きな経営基盤や販売網、開発力を持つ大手企業の傘下に入ることは、会社の新たな成長戦略となり得ます。
自社だけでは難しかった大規模な投資や海外展開が実現し、結果として事業が安定・成長し、従業員の雇用と未来を守ることにつながります。
会社売却が従業員に与える具体的な影響とは

ここからは、会社売却が従業員の雇用、給与、退職金といった労働条件に具体的にどのような影響をもたらすのかを詳しく見ていきましょう。
雇用契約の継続・再契約
まずは、雇用契約についてです。
前述の通り、これは会社売却の手法によって扱いが異なります。
| M&A手法 | 雇用契約の扱い | 従業員への影響 |
| 株式譲渡 | 会社の株主が変わるだけなので、雇用契約はそのまま買い手企業に引き継がれる。 | 従業員の手続きは不要。労働条件も原則として維持される。 |
| 事業譲渡 | 雇用契約は自動で引き継がれない。従業員は買い手企業と新たに雇用契約を結び直す必要がある。 | 従業員一人ひとりの同意(転籍の承諾)が必要。拒否した場合は元の会社に残るか、退職することになる。 |
従業員の雇用維持を優先に考えるのであれば、雇用契約がそのまま引き継がれる株式譲渡が適した手法といえます。事業譲渡を選択する場合は、従業員への丁寧な説明と、個別の同意を取り付けるプロセスが不可欠です。
労働条件(給与・役職・勤務地)の変更
株式譲渡の場合、雇用契約はそのまま引き継がれるため、給与や役職、勤務地といった労働条件も原則として維持されます。
しかし、これはあくまで原則です。M&A完了後、買い手企業の経営方針や人事制度に統合される過程で、労働条件が変更される可能性は十分にあります。
例えば、給与体系が買い手企業の基準に見直されたり、組織再編に伴って役職や部署が変更されたり、あるいは事業所の統廃合によって勤務地の変更を打診されたりするケースです。
経営者は、交渉段階で従業員の労働条件を可能な限り維持するよう、買い手企業と書面で合意しておくことが重要です。
退職金の扱いと再計算の可能性
従業員にとって、退職金の扱いはM&Aにおける大きな関心事の一つです。選択されるM&Aの手法によって、退職金の計算基礎となる勤続年数や支払い方法が異なります。
各手法による主な違いは、以下の表の通りです。
| M&Aの手法 | 勤続年数の扱い | 退職金の支払いタイミングと規程 |
| 株式譲渡 | 売却前の勤続年数が引き継がれる(通算される) | 将来の退職時に、通算した勤続年数に基づいて計算される。退職金規程も原則として維持される。 |
| 事業譲渡 | 勤続年数がリセットされる | 買い手企業への転籍時に、元の会社から支払われることがある。転籍後は買い手企業の規程が適用される。 |
株式譲渡の場合、会社の法人格はそのまま維持されるため、従業員の勤続年数も通算されるのが一般的です。
一方、事業譲渡では、従業員は一度元の会社を退職し、買い手企業に再雇用される形(転籍)をとるため、その時点で退職金が支払われ、勤続年数がリセットされる点に注意が必要です。
どちらの手法であっても、買い手企業の人事制度に統合される過程で、退職金制度そのものが見直される可能性があります。
これらの条件についても、M&Aの契約段階で明確にしておくことが、後のトラブルを防ぐために重要です。
企業文化や職場環境の変化
給与や制度といったハード面だけでなく、企業文化や仕事の進め方といったソフト面の変化も、従業員に大きな影響を与えます。
例えば、これまでトップダウンで迅速な意思決定がなされていた会社が大手企業の傘下に入ることで、稟議や報告といった手続きが重視されるようになるかもしれません。
また、評価制度やコミュニケーションの取り方、職場の雰囲気などが大きく変わることもあります。
こうした変化に馴染めず、ストレスを感じたり、仕事へのやりがいを失ったりする従業員が出てくる可能性も考慮しておく必要があります。
会社売却による従業員へのメリット

会社売却は、従業員にとって不安な側面ばかりではありません。むしろ、大手企業や成長意欲の高い企業の傘下に入ることで、従業員のキャリアや待遇にとって大きなプラスとなるケースも多くあります。
経営者は、これらのメリットを従業員に正しく伝えることでM&Aに対する前向きな理解を促すことができます。
待遇改善の可能性(給与アップ・福利厚生充実)
大手企業の傘下に入ることで、従業員の待遇が向上する可能性があります。これは、M&Aがもたらすわかりやすいメリットのひとつです。
例えば、以下のような待遇の向上が期待できます。
- 給与水準の向上:買い手企業の給与体系が適用され、基本給や賞与がアップするケースがあります。
- 福利厚生の充実:中小企業では導入が難しい、充実した福利厚生制度(住宅手当、家族手当、退職年金制度、資格取得支援、リゾート施設の利用など)が適用されるようになります。
これにより、従業員の生活が安定し、仕事へのモチベーション向上にもつながります。
キャリア成長機会の拡大
自社単独では提供できなかった、多様なキャリアパスが開かれることも大きなメリットです。買い手企業の大きな組織の中では、これまでの会社にはなかった新しいポストが生まれたり、本人の希望や適性に応じて他部署へ異動したりする機会が増えます。
また、買い手企業が海外拠点を持っている場合、海外勤務に挑戦できる可能性も出てきます。従業員はより広い視野で自身のキャリアを考えられるようになり、成長意欲の高い人材にとっては大きな魅力です。
自身のスキルや経験を新しい環境で試したいと考えている方にとっては、大きな機会となります。
経営安定化による雇用安定
後継者不在や業績不安を抱える会社にとって、M&Aは事業存続の危機を回避する手段です。
経営基盤が安定している企業の傘下に入ることで、会社の倒産リスクは大幅に低減します。これは、従業員にとって雇用の安定という安心材料になります。
目先の待遇だけでなく、「この会社で長く働き続けられる」という安心感が、従業員の定着と組織の安定につながります。
新しい技術・ノウハウの習得機会
買い手企業が持つ、自社にはない先進的な技術や生産管理手法、マーケティングノウハウなどを学ぶ機会が得られます。例えば、製造業であれば、より高度な生産技術や品質管理システムに触れることができます。
これにより、従業員は自身の専門スキルを向上させ、市場価値の高い人材へと成長することが可能です。
会社としても、新たな技術やノウハウを取り入れることで競争力が高まり、事業のさらなる発展が期待できます。
これは、従業員と会社の双方にとって大きな成長の機会となります。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
会社売却による従業員へのデメリット・リスク

会社売却には多くのメリットがある一方で、従業員にとって望ましくない結果をもたらす可能性もゼロではありません。
経営者は、これらのデメリットやリスクを直視し、交渉段階でいかに回避・軽減できるかが問われます。
労働条件の悪化リスク
メリットの裏返しとして、労働条件が悪化するリスクも存在します。買い手企業の人事制度に統合される過程で、自社の制度と比較して以下のような不利益な変更が生じる可能性があるためです。
- 給与の減少:成果主義の給与体系に移行し、従来の年功序列的な給与が保障されなくなる。
- 手当の削減:独自の手当(皆勤手当など)が廃止される。
- 労働時間の変更:勤務体系が変わり、残業が増えたり、休日の取得方法が変わったりする。
経営者は、M&Aの契約交渉において、主要な労働条件がM&A後も一定期間維持されるよう、重要条件として明確に盛り込む努力が求められます。
人員整理・配置転換のリスク
M&A後、経営の効率化を目的として組織再編が行われることがあります。その際に、買い手企業と機能が重複する管理部門(経理、総務など)を中心に、人員整理(リストラ)が行われるリスクは否定できません。
また、本人の希望とは異なる部署への配置転換や遠隔地への転勤を命じられる可能性もあります。
こうした事態を防ぐためにも経営者は交渉の場で従業員の雇用を維持することを強い姿勢で要求し、契約書に明記させることが重要です。
企業文化の変化による心理的負担
長年慣れ親しんだ企業文化や職場環境が大きく変わることは、従業員にとって大きなストレスとなり得ます。
例えば、家族的で風通しの良い社風だった会社が、M&Aを機に報告・連絡・相談が徹底され、管理体制の厳しい社風に変わった場合、窮屈さや疎外感を覚える従業員も出てくるでしょう。
こうした文化の摩擦(カルチャーギャップ)は、従業員のエンゲージメントを低下させる大きな要因です。
買い手企業がどのような文化を持つ会社なのかを事前に見極め、自社の従業員が適応できそうかを判断することも、経営者の重要な役割です。
モチベーション低下・離職率上昇
労働条件の悪化や人間関係の変化、将来への不安などが重なると、従業員の仕事に対するモチベーションは著しく低下します。
特に、会社の将来を担うと期待されている優秀な人材ほど、新しい環境に馴染めなかったり、自身のキャリアパスに疑問を感じたりして、早期に離職してしまうリスクが高まります。
キーパーソンの離職は、他の従業員の不安を煽り、離職の連鎖を引き起こしかねません。
従業員のモチベーションを維持し、離職を防ぐためには、経営者自らがM&Aの目的やメリットを誠実に説明し、従業員の不安に寄り添う姿勢が不可欠です。
会社売却で従業員とのトラブルを防ぐための5つの重要ポイント

会社売却を円滑に進めるためには、従業員の不安や不満を最小限に抑え、トラブルを未然に防ぐことが不可欠です。
従業員の動揺は、事業価値の低下やM&Aの破談に直結しかねません。
ここでは、経営者が従業員との無用な摩擦を避け、信頼関係を維持しながらM&Aを成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:情報開示のタイミングと方法を慎重に検討する
M&Aに関する情報をいつ、誰に、どのように伝えるかは、繊細な判断が求められる問題です。
情報開示が早すぎると、従業員の間に不安や憶測が広がり、通常業務に支障をきたしたり、取引先や金融機関に情報が漏れて交渉が不利になったりするリスクがあります。
一方で、開示が遅すぎると、従業員は「裏切られた」と感じ、経営者への不信感を抱くことになります。
一般的には、買い手企業と基本合意を締結し、M&Aの実現可能性が高まった段階で、まずは役員などの幹部社員に説明し、最終契約の締結・決済後に全従業員へ説明会を開くのが適切なタイミングとされています。
ポイント2:従業員の雇用維持を優先に交渉する
従業員が懸念するのは「自分の雇用がどうなるのか」という点です。経営者は、M&Aの交渉プロセスにおいて、従業員の雇用維持することを、買い手企業に求める重要課題として位置づけるべきです。
具体的には、最終契約書の中に「一定期間(例:M&A後2年間)は、人員整理を目的とした解雇を行わない」といった条項(雇用維持条項)を盛り込むよう強く交渉します。
この姿勢こそが、従業員を守るという経営者の強い意志を示すことになり、従業員の安心につながります。
ポイント3:キーパーソンとなる従業員の離職を防ぐ
会社の事業を支えるうえで、特定の技術やノウハウを持った従業員や、主要な取引先との信頼関係を築いている営業担当者など、他に替えのきかないキーパーソンがいます。
買い手企業も、こうしたキーパーソンが会社に残ることをM&Aの前提条件とすることがほとんどです。もしキーパーソンがM&Aをきっかけに離職してしまえば、会社の事業価値は大きく損なわれ、最悪の場合、M&A自体が破談になる恐れもあります。
これを防ぐため、経営者は事前にキーパーソンと個別に面談し、M&A後も会社に残ってもらえるよう誠実に説得するとともに、買い手企業に対しては、そのキーパーソンが納得するような待遇(昇給や役職の付与など)を用意するよう働きかける必要があります。
ポイント4:従業員への誠実な説明とコミュニケーションを徹底する
情報開示の際には、従業員説明会などの場を設け、経営者自身の言葉で、なぜ会社売却を決断したのか、従業員の雇用や待遇はどうなるのか、そしてこのM&Aが会社と従業員の未来にとってどのようなメリットがあるのかを誠心誠意説明することが重要です。
一方的な説明で終わらせず、従業員からの質問や不安の声を真摯に受け止め、丁寧に回答する質疑応答の時間を十分に確保しましょう。
従業員は、会社が自分たちのことを真剣に考えてくれていると感じられれば、変化を受け入れやすくなります。
説明会後も継続的にコミュニケーションを取り、従業員の不安に寄り添う姿勢を見せ続けることが信頼関係を維持するポイントです。
ポイント5:買い手企業による従業員のヒアリング(従業員面談)への準備
M&Aの最終段階では、買い手企業が会社のキーパーソンや主要な従業員と直接面談し、事業内容や組織文化、個人のキャリアプランなどをヒアリングする従業員面談が行われることがあります。
これは、従業員にとっては買い手企業を直接知る機会であると同時に、買い手にとってはM&A後のリスクを評価する重要なプロセスです。
経営者は、対象となる従業員に対し、面談の目的を事前に説明し、過度に緊張したり、不必要にネガティブな発言をしたりしないよう、準備をサポートする必要があります。
従業員が前向きな姿勢で面談に臨めるようケアすることが、M&Aの成功確率を高めます。
大切な従業員の雇用と未来を守るために経営者ができること

会社売却という大きな決断において、経営者の最後の使命は、これまで会社を支えてくれた従業員の雇用と未来を守り抜くことです。
それは、単に買い手を見つけることだけではありません。契約内容の細部にまで気を配り、M&A後の従業員の不安を取り除くための具体的なアクションを起こすことが求められます。
従業員の雇用条件を明記した契約を締結する
従業員を守るための確実な方法は、そのための条件を法的な拘束力を持つ最終契約書(株式譲渡契約書など)に明記することです。口約束だけでは効力がありません。
- 雇用維持条項:M&A後、一定期間は人員整理を目的とした解雇を行わないことを約束させる。
- 労働条件維持条項:給与、賞与、退職金などの主要な労働条件を、M&A後も一定期間は現状維持、または不利益に変更しないことを約束させる。
これらの条項を契約に盛り込むことで、買い手企業に対する明確なメッセージとなり、従業員の雇用と生活を守るための強力な後ろ盾となります。
従業員の不安を払拭するためのケアを行う
契約だけでなく、従業員の心理的なケアも経営者の重要な役割です。M&Aの発表後、従業員は大きな不安やストレスを抱えています。
経営者は、従業員一人ひとりの声に耳を傾けるための個別面談の機会を設けたり、相談窓口を設置したりするなど、不安を吐き出せる環境を整えましょう。
また、買い手企業の担当者と従業員が交流する場を設けるなどして、新しい親会社や職場環境に対する理解を深め、過度な不安を払拭する手助けをすることも有効です。
従業員が前向きな気持ちで新しいスタートを切れるよう、最後まで寄り添う姿勢が求められます。
買い手企業との間でPMI(統合プロセス)を円滑に進める
PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後に行われる経営方針、業務プロセス、企業文化などの統合プロセスを指します。このPMIが円滑に進むかどうかが、M&Aの成否を決めるといっても過言ではありません。
売り手企業の経営者は、契約が完了したら終わりではなく、このPMIの初期段階に積極的に関与し、自社の従業員と買い手企業との橋渡し役を担うことが重要です。
自社の強みや企業文化、従業員の特性などを買い手企業に丁寧に伝え、従業員が新しい体制にスムーズに適応できるよう支援することで、M&A後の混乱を最小限に抑え、シナジー効果の早期実現に貢献できます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
会社売却に関する相談先と選び方のポイント

会社売却は、経営者一人の力で進められるものではありません。
法律、税務、会計といった専門的な知識が不可欠であり、信頼できる専門家のサポートが成功の鍵を握ります。
しかし、相談先にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。自社の状況に合った相談先を見極めることが重要です。
ここでは、それぞれの相談先の特徴と選び方のポイントを解説します。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立ち、売り手・買い手双方の間に立ち、M&Aの交渉から成立までを仲介する専門家です。
豊富なネットワークを活かして、自社に最適な買い手候補を探し出し、交渉の仲介から契約書の作成支援、クロージングまで、M&Aの全プロセスをワンストップでサポートしてくれます。中にはご成約後のPMI(統合プロセス)までサポートする仲介会社も増えてきております。
中小企業のM&Aに関する実績が豊富で、従業員の処遇といったデリケートな問題にも精通しているため、初めてM&Aを行う経営者にとっては頼りになる相談先です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
金融機関(銀行・証券会社)
普段から付き合いのあるメインバンクや信託銀行、証券会社もM&Aの相談先です。
特に大手銀行や証券会社はM&A専門の部署を持っており、広範な顧客ネットワークを活かしたマッチングが期待できます。
自社の財務状況をよく理解してくれているという安心感がありますが、一方で、その金融機関の取引先の中から買い手を探す傾向があるため、最適な相手が見つかるとは限らない点も考慮が必要です。
事業引継ぎ支援センター
事業引継ぎ支援センターは、後継者不在に悩む中小企業の事業承継を支援するために国が設置した公的な相談窓口です。
全国47都道府県に設置されており、無料で相談に応じてくれます。中立的な立場でアドバイスを提供し、必要に応じて民間のM&A専門家を紹介してくれます。
まだM&Aを決断したわけではないが、まずは情報収集から始めたいという段階の経営者にとって、気軽に相談できる最初の窓口として適しています。
弁護士や公認会計士などの専門家
弁護士はM&A契約書の作成や法的なリスクチェック(法務デューデリジェンス)を、公認会計士や税理士は財務・税務面のリスク調査(財務デューデリジェンス)や株価算定、税務戦略の立案などを担当します。
彼らはM&Aプロセスの一部を専門的にサポートする役割を担います。顧問の弁護士や会計士に相談することも一つの手ですが、M&Aの実績が豊富かどうかは必ず確認する必要があります。
M&A仲介会社と連携して、これらの専門家がチームを組んで支援するケースが一般的です。
| 相談先 | 特徴 |
| M&A仲介会社 | M&Aの専門家。買い手候補の探索から交渉、契約まで一貫してサポートしてくれる。 |
| 金融機関(銀行・証券会社) | 豊富なネットワークを持ち、M&Aの相手先探しや資金調達の相談に乗ってくれる。 |
| 事業引継ぎ支援センター | 国が設置する公的機関。後継者不在の中小企業を中心に、無料で相談に応じてくれる。 |
| 弁護士や公認会計士などの専門家 | 契約書のリーガルチェックや、企業の価値算定(デューデリジェンス)など、専門分野でサポートしてくれる。 |
従業員と会社の未来へつなぐ会社売却を実現しよう

会社売却は、後継者不在の問題を解決し、会社を未来へつなぐための有効な経営戦略です。しかし、その過程では、これまで苦楽を共にしてきた従業員の生活やキャリアに大きな影響が及びます。
経営者にとって、会社売却の成功とは、単に高い価格で売却することだけではありません。従業員の雇用と未来を守り、彼らが新しい環境で安心して働き続けられる道筋をつけることこそが、経営者として使命です。
本記事で解説したポイント、なかでも従業員一人ひとりとの誠実なコミュニケーションを徹底し、信頼できる専門家と連携することで、すべての関係者にとって最善の結果をもたらすM&Aは実現できます。
従業員と共に築き上げてきた大切な会社を、次の成長ステージへと力強く引き継いでいきましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)