M&Aの種類を徹底解説|手法ごとのメリット・事例・選び方も紹介

M&Aは、企業の事業承継や成長戦略、資本強化を実現するための有効な手段です。しかし、M&Aには株式取得や事業譲渡、会社分割、合併、資本提携など多様な種類があり、目的や状況に応じて適切な手法を選ぶ必要があります。
本記事では、種類別にM&Aの手法の概要やメリット・デメリット、実際の事例、選び方のポイントなどをわかりやすく解説します。
適切な手法を理解し、将来の企業価値最大化につなげるための実務的な知識を身につけましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aとは

まずは、M&Aの意味や目的、市場動向など概要について見ていきましょう。
M&Aの意味と目的
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、会社の合併(Mergers)と買収(Acquisitions)を指す言葉です。会社や事業を買収・統合することで、短期間での事業拡大や経営資源の獲得を実現する経営戦略として活用されています。
M&Aの主な目的には以下のようなものがあります。
| 売り手企業側の目的 |
|
| 買い手企業側の目的 |
|
M&Aの市場動向
日本のM&A市場は近年、着実に拡大しています。レコフデータによると、2024年の日本企業のM&A件数は約4,700件で、前年比17.1%増となり、過去最多となりました。
特に、中小企業におけるM&Aは、経営者の高齢化や後継者不在の課題に対応する手段として注目されています。中小企業庁の調査によると、2025年には中小企業・小規模事業者の経営者のおよそ245万人が平均引退年齢である70歳を超えると予想しており、今後さらに事業承継ニーズが高まる見込みです。
政府は中小M&A市場改革プランやガイドライン改訂により、円滑なM&Aの実行やトラブル防止を支援しています。今後もM&A市場の重要性はさらに高まるでしょう。
(参考:中小企業庁|中小企業・小規模事業者における M&Aの現状と課題)
中小企業のM&Aの動向については、以下の記事で詳しく解説しています。
M&Aを検討する主な理由
企業がM&Aを検討する理由は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます。
- 事業承継の実現:後継者不在の問題を解決し、従業員の雇用と取引先との関係を維持しながら事業を継続
- 事業拡大・成長戦略:新規事業への参入や既存事業の強化を、自社で一から構築するより短期間で実現可能
- 経営の効率化:重複する機能の統合や規模の経済の実現により、コストを削減できる
- 選択と集中:不採算事業や非中核事業を売却し、中核事業に経営資源を集中させる
M&Aの分類
M&Aは、その範囲によって「狭義のM&A」と「広義のM&A」に分類されます。
狭義のM&A
狭義のM&Aとは、会社の支配権が移転する取引を指し、売り手企業の経営権が完全に、または実質的に買い手企業へ移転します。
具体的には、以下の手法が含まれます。
- 株式取得
- 事業譲渡
- 会社分割
- 合併
広義のM&A
広義のM&Aには、支配権の移転を伴わない企業間の協力関係も含まれます。
具体的には以下が該当します。
- 資本提携
- 業務提携
- 合弁会社設立
これらの手法では、各企業が独立性を保ちながら、特定の目的のために協力関係を構築します。完全な支配権の移転は伴いませんが、戦略的な協力関係を通じて相乗効果を生み出すことを目指しています。
狭義のM&A手法の種類

本章では、具体的な狭義のM&A手法の種類について詳しく解説します。
株式取得
株式取得とは、対象会社の株式を取得することで、その会社の経営権の獲得を指します。株式の過半数の取得で実質的な支配権を得られます。
株式取得を実現するための具体的な手法は、以下のとおりです。
- 株式譲渡
- 株式交換
- 株式移転
- 第三者割当増資
株式譲渡
株式譲渡は、既存の株主から株式を買い取ることで経営権を取得する手法で、手続きが比較的簡便であることが特徴です。
手続きの主な流れ:
- 株式譲渡契約の締結
- 株主名簿の名義書換
- 対価の支払い
株式譲渡では、対象会社の権利義務に影響が生じないため、契約関係の移転手続きや許認可の再取得は原則として不要です。
株式交換
株式交換は、対象会社の株主が保有する株式を、買い手企業の株式と交換する手法です。平成11年の商法改正で導入された制度で、100%親子会社関係を構築する際に活用されます。
手続きの主な流れ:
- 株式交換契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 株式交換の効力発生
株式交換では、対価として現金ではなく買い手企業の株式を交付するため、買い手企業の資金負担を抑えられることが大きなメリットです。ただし、売り手企業の株主は買い手企業の株主となるため、買い手企業の株主構成に影響を与える点に留意が必要です。
株式移転
株式移転は、既存の会社が発行済株式の全部を新たに設立する会社に取得させる手法です。株式交換と同様に100%親子会社関係を構築しますが、株式交換が既存会社を親会社とするのに対し、株式移転では新設会社が親会社となります。
手続きの主な流れ:
- 株式移転計画の作成
- 株主総会の特別決議
- 新会社の設立登記と株式移転の効力発生
株式移転は、新設共同持株会社を設立する際によく用いられます。複数の会社が対等な立場で統合する場合、既存のいずれかの会社を親会社とするのではなく、新設の持株会社の傘下に入ることで、対等性の保持が可能です。
第三者割当増資
第三者割当増資とは、対象会社が特定の第三者に新株を発行し、その第三者が出資する手法です。既存株式の譲渡ではなく、新株の発行により資本を増強します。
手続きの主な流れ:
- 取締役会決議(有利発行の場合は株主総会特別決議)
- 新株発行の通知
- 出資の履行
- 登記申請
第三者割当増資を用いた支配権の取得は、既存株主の持株比率を低下させるため、有利発行に該当する場合は株主総会の特別決議が必要です。
応用的な株式取得の手法(TOB・MBO・LBO)
株式取得には、通常の株式譲渡や第三者割当増資以外にも、特定の目的や状況に応じて用いられる次のような手法があります。
- TOB(Take Over Bid:株式公開買付):
TOBは、上場企業の株式を市場外で買い集める手法です。買い手企業が取得を希望する株式数や買付価格、買付期間などの条件を公表し、既存株主に対して直接株式の売却を呼びかけます。上場会社の株式を一定割合以上取得する場合には、TOBの実施が義務付けられています。 - MBO(Management Buyout:経営陣による買収):
MBOは、会社の経営陣が自ら資金を調達して自社株式を買い取り、経営権を握る手法です。オーナー経営者の事業承継や、非上場化(上場廃止)を目的とするケースもあります。外部資本の影響を受けずに経営の自由度を高めたい場合に選ばれます。 - LBO(Leveraged Buyout:レバレッジド・バイアウト):
LBOは、買収対象企業の資産や将来のキャッシュフローを担保にして資金を借り入れ、その資金で買収を行う手法です。投資ファンドなどが用いることが多く、少ない自己資金で大規模な買収を実現できる点が特徴です。
これらの手法は専門的なスキームが必要であり、主に上場企業や投資ファンドを対象とするM&Aで活用されます。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を他の会社に譲渡する手法です。事業譲渡では特定の事業や資産を選択して譲渡します。
手続きの主な流れ:
- 事業譲渡契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 対価の支払いと事業の移転
事業譲渡では、譲渡する資産・負債や契約を個別に特定する必要があります。このため、以下の手続きが必要となります。
- 不動産:所有権移転登記
- 債権:債権譲渡の通知または承諾
- 契約:相手方の同意を得て契約を承継
- 許認可:原則として再取得が必要
会社分割
会社分割とは、会社の事業に関する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる手法です。事業譲渡と類似していますが、会社分割では包括承継が認められる点が大きく異なります。
会社分割には、以下の2つの具体的な手法があります。
- 新設分割
- 吸収分割
新設分割
新設分割は、分割により新たに会社を設立し、その会社に権利義務を承継させる手法です。
手続きの主な流れ:
- 新設分割計画の作成
- 株主総会の特別決議
- 債権者保護手続き
- 新会社の設立登記と分割の効力発生
新設分割では、新設会社に権利義務が包括承継されるため、個別の資産移転手続きが不要です。ただし、労働契約の承継については労働契約承継法の適用を受け、一定の手続きが必要です。
吸収分割
吸収分割は、既存の会社に権利義務を承継させる手法です。新設分割が新会社を設立するのに対し、吸収分割では既存の会社が承継会社となります。
手続きの主な流れ:
- 吸収分割契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 債権者保護手続き
- 分割の効力発生
吸収分割も新設分割と同様に包括承継が認められるため、個別の資産移転手続きは原則として不要です。
合併
合併とは、複数の会社が1つの会社になる手法です。会社の法人格そのものが統合されるため、M&A手法の中でもっとも統合度が高い手法といえます。
合併を実現するための具体的な手法は、以下のとおりです。
- 吸収合併
- 新設合併
吸収合併
吸収合併は、存続会社が消滅会社の権利義務を承継し、消滅会社が解散する手法です。
手続きの主な流れ:
- 吸収合併契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 債権者保護手続き
- 合併の効力発生と消滅会社の解散登記
吸収合併では、消滅会社の権利義務が包括的に承継されるため、個別の承継手続きは不要です。許認可については、一定の要件を満たす場合に承継が認められるものもあります。
新設合併
新設合併は、複数の会社が解散し、新たに設立される会社に権利義務を承継させる手法です。
手続きの主な流れ:
- 新設合併契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 債権者保護手続き
- 新会社の設立登記と合併の効力発生
新設合併は、対等な立場での統合を印象づけられますが、手続きが煩雑で、許認可の再取得が必要となる場合が多いため、実務上は吸収合併が選択されることが多い傾向にあります。
広義のM&A手法の種類
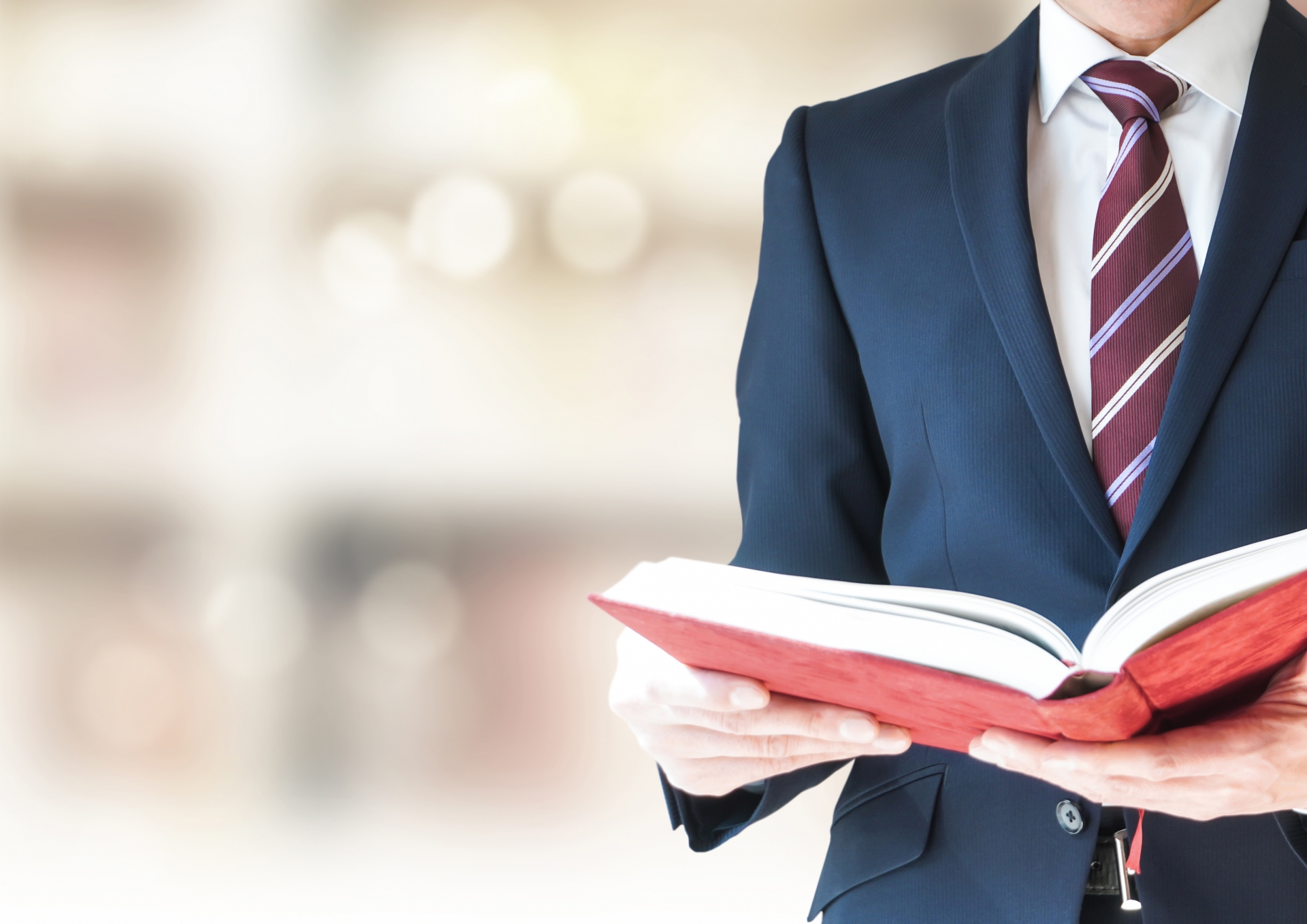
広義のM&Aには、株式取得や事業譲渡などの直接的な手法に加え、資本提携や業務提携、合弁会社の設立といった間接的な手法も含まれます。これらは、企業同士が資金や技術、人材を共有し、協力関係を構築することで、成長戦略や事業拡大を実現する手段として活用されます。
資本提携
資本提携とは、一方の会社が他方の会社の株式を取得し、資本関係を構築することで協力関係を強化する手法です。資本提携では、支配権の取得を目的としません。
資本提携では、株式の取得により以下の効果が生まれます。
- 提携関係の安定化
- 相手企業の経営への一定の関与
- 財務的な利益の享受
資本提携は、業務提携を強化する手段として活用されるケースが多いです。
業務提携
業務提携とは、特定の業務分野で協力関係を構築する手法です。契約に基づいて以下のような協力関係を築きます。
- 技術提携:技術やノウハウの相互利用
- 生産提携:生産設備や生産能力の相互利用
- 販売提携:販売網や販売ノウハウの相互利用
- 共同開発:新製品や新技術の共同研究開発
業務提携では、各社の独立性が保たれ、提携解消も比較的容易です。一方で、資本の裏付けがないため、提携関係が不安定になりやすい側面もあります。
合弁会社設立
合弁会社設立(ジョイントベンチャー)とは、複数の会社が共同で新会社を設立し、その会社を通じて特定の事業を展開する手法です。各社が出資して新会社を設立し、その新会社が事業活動を行います。
合弁会社設立には以下の形態があります。
- 均等出資型:各社が同じ出資比率で新会社を設立し、意思決定における対等性が保たれる。
- 主従型:一方の会社が過半数を出資し、経営の主導権を握る。
合弁会社設立は、互いの強みを活かして新規事業に参入する場合や、海外進出の際に現地企業と協力する場合などに活用されます。
種類別M&A手法のメリット・デメリット

本章では、主要なM&Aの手法ごとのメリット・デメリットを整理し、解説します。
株式取得
株式取得のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット
- 手続きの簡便性:
株式譲渡の場合、契約締結と株主名簿の書換で手続きが完了します。許認可の再取得や契約の巻き直しが原則として不要で、事業譲渡と比較して手続きが大幅に簡素化されます。 - 事業の一体性維持:
会社の法人格が維持されるため、従業員との雇用関係、取引先との契約関係、許認可などがそのまま継続します。事業の継続性が保たれ、取引先や従業員への影響を最小限に抑えられます。
デメリット
- 簿外債務のリスク:
簿外債務や偶発債務も引き継ぐリスクがあり、未払残業代や環境汚染に関する債務、訴訟リスクなど、貸借対照表に計上されていない債務が後日判明する可能性があります。 - デューデリジェンスの重要性:
簿外債務のリスクに対応するため、綿密なデューデリジェンスが必要です。 - 不要な資産・負債の承継:
事業に必要のない資産や負債も承継するため、選択的な承継ができません。 - のれんの税務上の扱い:
株式取得では、のれん(資産調整勘定)について、損金算入が認められません。
事業譲渡
事業譲渡のメリット・デメリットには、以下のような点が挙げられます。
メリット
- 柔軟な取引設計:
譲渡対象を柔軟に設計できるため、複数の事業のうち一部のみを譲渡する、特定の資産のみを譲渡するなど、目的に応じた取引が可能です。 - のれんの税務上の損金算入:
事業譲渡で生じるのれんは、税務上60カ月で均等償却され、損金算入が認められます。 - 競業避止義務:
事業譲渡を行った会社は、原則として20年間、同一の市町村および隣接市町村で同一の事業を行うことが禁止されるため買い手企業(譲受会社)にとっては、競合リスクを低減できます。
デメリット
- 手続きの煩雑さ:
資産・負債・契約を個別に移転する必要があるため、手続きが非常に煩雑です。不動産の移転登記、債権譲渡の通知、契約の巻き直しなど、多くの手続きを要します。 - 許認可の再取得:
許認可は原則として承継されないため、買い手企業が新たに許認可の取得が必要です。取得要件が厳しい業種では、事業譲渡が困難な場合があります。 - 取引先の同意:
債務の承継には取引先の同意が必要で、主要な取引先の同意が得られない場合、事業価値が大きく低下する可能性があります。 - 従業員の転籍手続き:
従業員の雇用契約は自動的には承継されないため、個別に転籍の同意を得る必要があります。 - 消費税の課税:
事業譲渡は消費税法上の資産の譲渡に該当し、消費税が課税されます。
会社分割
会社分割のメリット・デメリットは、次のとおりです。
メリット
- 包括承継による手続きの簡素化:
会社分割では権利義務が包括的に承継されるため、個別の資産移転手続きが不要です。事業譲渡と比較して、手続きを効率化できます。 - 許認可の承継:
一定の要件を満たす場合、許認可が承継される場合があります。 - 労働契約の承継:
会社分割に伴う労働契約の承継については労働契約承継法が適用され、一定の手続きを経ることで労働契約が承継されます。 - 対価の柔軟性:
対価として現金だけでなく、株式を交付することも可能で、買い手企業の資金負担を軽減できます。 - 組織再編税制の適用:
一定の要件を満たす会社分割は適格分割に該当し、税務上の繰越欠損金の引継ぎなどが認められます。
デメリット
- 法定手続きの複雑さ:
株主総会の特別決議、債権者保護手続き、官報公告など、法律上の手続きが必要で、完了まで数カ月かかる場合があります。 - 簿外債務のリスク:
包括承継であるため、簿外債務も承継される可能性があります。 - 労働契約承継法の手続き:
労働契約承継法に基づく手続き(労働者への通知、協議、異議申出への対応など)が必要であり、一定の時間とコストがかかります。
合併
合併のメリットとデメリットには、次のような点が挙げられます。
メリット
- 完全な統合:
法人格が統合されるため、強固な統合形態を実現でき、重複する機能の統廃合が可能です。 - 包括承継:
権利義務が包括的に承継されるため、個別の移転手続きが不要です。 - シナジー効果の最大化:
完全な統合により、規模の経済、範囲の経済などのシナジー効果を最大限に発揮できます。 - 組織再編税制の適用:
一定の要件を満たす合併は適格合併に該当し、税務上の繰越欠損金の引継ぎなどが認められます。
デメリット
- 手続きの煩雑さ:
株主総会の特別決議、債権者保護手続きなど、厳格な手続きが必要。完了までに半年以上かかる場合もあります。 - 許認可の取扱い:
業種によっては許認可の再取得が必要です。 - 企業文化の統合:
完全な統合であるため、企業文化や業務プロセスの統合が不可欠です。統合が不十分な場合、従業員の士気低下や人材流出のリスクが高まります。 - 反対株主の買取請求権:
合併に反対する株主は株式の買取を請求できるため、想定を上回るキャッシュアウトが発生する可能性があります。 - 統合コスト:
システム統合、業務プロセスの統一、人事制度の統合など、多額の統合コストが発生します。
資本提携
資本提携の、メリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット
- 独立性の維持:
支配権の移転を伴わないため、各社の独立性が保たれます。そのため、経営の自主性を維持しながら協力関係の構築が可能です。 - 提携関係の安定化:
株式の保有により、資本的なつながりが生まれ、業務提携よりも強固で安定した関係を構築できます。 - 段階的な統合:
まず資本提携から始め、事業の相性を確認したうえで、将来的により強固な統合(株式取得や合併)に進む段階的なアプローチが可能です。 - 財務的メリット:
配当収入や株式の値上がり益を享受できます。
デメリット
- 限定的な経営への関与:
支配権を持たないため、経営への関与は限定的です。 - 投資資金の回収リスク:
相手企業の業績が悪化した場合、投資資金の回収が困難となる可能性があります。 - 提携解消の困難さ:
株式を保有しているため、業務提携よりは解消が困難です。 - 少数株主としてのリスク:
相手企業の経営方針に影響を与えることが難しく、意図しない方向に経営が進むリスクがあります。
業務提携
業務提携には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 柔軟性:
資本関係を伴わないため、提携の開始も解消も比較的容易で、環境変化に応じた柔軟な対応が可能です。 - 低コスト:
資本の拠出が不要であり、初期投資を抑えて協力関係を構築できます。 - リスクの分散:
各社が独立性を保つため、相手企業の経営リスクを直接負いません。 - 補完関係の構築:
自社にない経営資源(技術、販売網、ノウハウなど)を、低コストで活用できます。
デメリット
- 関係の不安定性:
資本の裏付けがないため、相手企業の都合で一方的に解消される可能性があります。 - コミットメントの弱さ:
資本関係がないため、相手企業の提携に対するコミットメントが弱い場合は、期待したほどの協力が得られない可能性があります。 - 情報漏えいのリスク:
技術提携などでは、自社の重要な情報を相手企業に開示する必要があり、情報漏えいや技術流出のリスクに注意が必要です。 - 成果の不確実性:
各社の利害が完全には一致しないため、提携の成果が不確実です。
合弁会社設立
合弁会社設立のメリットは、以下のとおりです。
メリット
- リスクとコストの分担:
複数の会社で出資するため、リスクとコストを分担でき、単独では困難な大規模プロジェクトも実現可能です。 - 相互の強みの活用:
各社の強み(技術、販売網、ブランド、現地ノウハウなど)を結集し、単独では実現できない事業展開ができます。 - 独立した事業運営:
新会社が独立した法人として事業を運営するため、既存事業への影響を最小限に抑えられます。 - 段階的な投資:
まず合弁会社で事業を開始し、成功を確認してから本格的な投資を行う、段階的なアプローチが可能です。
デメリット
- 意思決定の複雑さ:
複数の会社が関与するため、意思決定に時間がかかる場合があります。特に均等出資の場合、重要事項の決定が難航する可能性があります。 - 利害の不一致:
出資会社間で配当政策や事業戦略などで意見が分かれた場合、経営が停滞する可能性があります。 - ノウハウの流出リスク:
合弁会社を通じて、自社の重要なノウハウが相手企業に流出する可能性があります。 - 撤退の困難さ:
合弁会社からの撤退には、相手企業との調整が必要で、簡単には撤退できない場合があります。
応用的な手法(TOB・MBO・LBO)
TOB、MBO、LBOの各メリット、デメリットは以下のとおりです。
| 手法 | メリット | デメリット |
| TOB |
|
|
| MBO |
|
|
| LBO |
|
|
M&Aの種類別事例

本章では、実際のM&Aの事例を手法ごとに解説します。
株式取得の事例
日本KFC株式会社の株式譲渡
2024年5月、三菱商事株式会社は、保有していた日本KFCホールディングス株式会社(ケンタッキーフライドチキン運営会社)の全株式を、カーライル・ファンド(投資ファンド)へ譲渡しました。
この取引は、三菱商事が進める事業ポートフォリオの見直しの一環として実施されたもので、カーライルによる買収後は、ブランド強化や店舗展開の拡大など、さらなる成長戦略の推進が期待されています。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 株式譲渡(持株の全株式を売却) |
| 売り手 | 三菱商事株式会社 |
| 買い手 | カーライル・ファンド(The Carlyle Group Inc.) |
| 目的 |
|
(参考:三菱商事株式会社│ニュースリリース)
事業譲渡の事例
花王株式会社による茶カテキン飲料「ヘルシア」の事業譲渡
2024年2月1日、花王株式会社は、自社が展開してきた茶カテキン飲料「ヘルシア」の事業を、キリンホールディングスのグループ会社であるキリンビバレッジ株式会社に譲渡する契約を締結しました。
この譲渡は、花王が自社の事業ポートフォリオを見直し、基盤事業への集中を図る戦略の一環です。
一方、キリングループにとっては、飲料・ヘルスケア領域の事業を強化し、「ヘルシア」のブランド価値をさらに発展させる機会として位置づけられています。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 事業譲渡(ブランド/製品の権利を他社へ移転) |
| 売り手(譲渡会社) | 花王株式会社 |
| 買い手(譲受会社) | キリンビバレッジ株式会社 |
| 目的 |
|
(参考:花王株式会社│プレスリリース)
会社分割の事例
ソフトバンクの「アニメ放題」事業の会社分割
2020年7月20日、ソフトバンク株式会社は、自社で運営していたアニメ専門コンテンツ配信サービス「アニメ放題」事業を、株式会社 U-NEXTに会社分割(吸収分割)により承継させることを決定しました。
この会社分割により、ソフトバンクはアニメ配信事業を切り出して運営体制をシフトし、U-NEXTは同事業を引き受けて運営を継続・強化する役割を担います。ソフトバンク側は、通信事業中心の経営体制に集中したいという戦略的意図を持っていました。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 吸収分割 |
| 分割元(分割会社) | ソフトバンク株式会社 |
| 承継先(承継会社) | 株式会社 U-NEXT |
| 対象事業 | アニメ専門コンテンツ配信サービス「アニメ放題」事業 |
| 目的 |
|
(参考:ソフトバンク株式会社│プレスリリース)
合併の事例
三菱HCキャピタル株式会社の合併
2020年9月24日、三菱UFJリース株式会社と日立キャピタル株式会社は、合併を通じた経営統合に向けた契約を締結しました。
この合併により、2021年4月1日を効力発生日として、三菱UFJリースを存続会社、日立キャピタルを消滅会社とする吸収合併方式で統合され、新会社「三菱HCキャピタル株式会社」が誕生しました。
本合併は、両社の事業領域や地域展開を補完し合いながら経営資源を統合することで、強固で持続的な経営基盤を構築し、リース事業の枠を超えた新たな価値の創出を目的としています。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 吸収合併 |
| 消滅会社 | 日立キャピタル株式会社 |
| 存続会社 | 三菱UFJリース株式会社 |
| 目的 | ビジネス領域の補完によるポートフォリオ分散、経営基盤の強化、新たな価値創造を通じた収益力向上 |
業務提携の事例
日本郵政と中国郵政の日中国際物流の強化に向けた業務提携
2010年11月、日本郵政株式会社と中国郵政集団公司は、日中間の国際物流ネットワークの強化を目的とした業務提携を発表しました。
この業務提携により、両社は国際物流ネットワークの強化を図り、Eコマース企業の国際展開を支援するとともに、日中間の物流効率の向上を目指しました。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 業務提携 |
| 提携企業 | 日本郵政株式会社、中国郵政集団公司 |
| 目的 | 日中間の国際物流ネットワーク強化、Eコマース事業支援、物流効率向上 |
(参考:日本郵便株式会社│プレスリリース)
合弁会社設立の事例
トヨタ自動車とパナソニックとの合弁会社設立
トヨタ自動車株式会社とパナソニック株式会社は、2020年4月1日に合弁会社「プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社」を設立しました。
本合弁会社は、トヨタとパナソニックがそれぞれの強みを活かし、電動車市場の拡大に対応することが目的です。これにより、両社は電池事業の競争力を強化し、他の自動車メーカーにも安定的に電池を供給する体制を構築しました。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 合弁会社設立 |
| 出資会社 | トヨタ自動車株式会社、パナソニック株式会社 |
| 目的 |
|
(参考:トヨタ自動車株式会社│ニュースリリース)
応用的な手法の事例
I-PEX株式会社によるMBO
電子部品メーカーのI-PEX株式会社は、2024年11月7日に、同社の普通株式に対する公開買付け(TOB)を実施し、非公開化を進める旨を発表しました。この取引は、創業家一族の資産管理会社であるDMC株式会社が設立した買収目的会社「UDON株式会社」によるもので、MBOに該当します。
このMBOは、創業家一族が中心となりTOBを通じてI-PEXの株式を取得し、非公開化した点が特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | MBO |
| 対象会社 | I-PEX株式会社 |
| 買収者 | UDON株式会社 |
| 目的 |
|
(参考:I-PEX株式会社│ニュースリリース)
M&Aの種類の選び方

M&Aの手法には数多くの種類があるため、適切に選ぶためのポイントを押さえる必要があります。
本章では以下の観点で、選び方のポイントを解説します。
- 目的別の選び方(事業承継/事業拡大/資本強化)
- 会社規模・業界特性による選び方
目的別の選び方(事業承継/事業拡大/資本強化)
実現したい目的によって、選択すべきM&Aの手法は異なります。
以下では、事業承継や事業拡大、資本強化といった目的別に、代表的な手法を紹介します。
<事業承継を目的とする場合>
事業承継を目的とする場合、一般的に選ばれるのが株式譲渡です。会社の法人格を維持したまま経営権を移転できるため、取引先や従業員への影響を最小限に抑えられます。
特に、中小企業の事業承継では、以下の理由から株式譲渡が選ばれます。
- 取引先との契約関係が継続
- 従業員の雇用が維持される
- 手続きが比較的簡便
以下の記事では、事業承継について詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
<事業拡大を目的とする場合>
新規事業への参入や既存事業の強化を目的とする場合、目的に応じて以下の手法を選択すると良いでしょう。
- 特定の事業のみを取得したい場合:
事業譲渡または会社分割の選択が有効です。必要な経営資源のみを取得でき、簿外債務のリスクを遮断できます。 - 会社全体を取得したい場合:
株式取得または合併によって実現が可能です。株式取得は手続きが比較的簡便であり、合併はより強固な統合を実現します。 - 段階的に関係を強化したい場合:
まず資本提携や業務提携から始め、事業の相性を確認したうえで、株式取得や合併に進むアプローチが有効です。
<資本強化を目的とする場合>
財務基盤の強化や戦略的パートナーの獲得を目的とする場合、資本提携や第三者割当増資が選択される場合があります。
資本提携では、出資を受ける会社が独立性を維持しながら、財務基盤を強化し、パートナー企業の経営資源を活用可能です。特に成長段階の企業が、大手企業から出資を受けるケースで活用されます。
一方、第三者割当増資は、新たに発行する株式を特定の第三者に引き受けてもらう手法で、資本提携と同様に資金調達と関係強化の双方を実現できる点が特徴です。
会社規模・業界特性による選び方
会社の規模や業界の特性によっても、有効なM&Aの手法が異なる場合があります。自社の状況に応じて、適切な手法を選択するようにしましょう。
<会社規模による選び方>
- 中小企業の場合:
主に株式譲渡が選択されます。手続きが簡便であり、許認可の承継が容易である点が理由です。 - 大企業・上場企業の場合:
合併や会社分割など、会社法に基づく組織再編手法が活用されます。また、上場企業の買収ではTOBが必要となる場合があります。
<業界特性による選び方>
- 許認可が重要な業種(建設業、医療、介護など):
許認可の承継が可能な手法の選択が重要です。株式譲渡であれば許認可は原則として維持されます。会社分割でも、一定の要件を満たせば許認可が承継される場合があります。一方、事業譲渡では原則として許認可の再取得が必要です。 - 労働集約型の業種:
従業員の雇用継続が重要な業種では、株式譲渡や会社分割が有効です。これらの手法では、労働契約が承継されるため、従業員の雇用が維持されます。事業譲渡の場合、個別に転籍の同意を得る必要があり、重要な人材の流出リスクがあります。 - 不動産を多く保有する業種:
不動産の移転には登録免許税や不動産取得税が課されます。事業譲渡では、不動産の移転により多額の税負担が発生する可能性があります。株式譲渡では、不動産の所有権は法人に帰属したまま維持されるため、税負担を抑えられます。 - IT・サービス業など無形資産が重要な業種:
無形資産(技術、ノウハウ、顧客リスト、ブランドなど)の承継が円滑に行える手法が有効です。株式譲渡や合併では、無形資産が包括的に承継されます。事業譲渡では、無形資産を個別に評価・移転する必要があり、手続きが複雑になる場合があります。
M&Aの契約の流れ

M&Aでは、交渉開始から最終契約締結まで、複数のステップを順を追って進めることが重要です。
本章では、以下の契約に関わる主要な手順をわかりやすく解説します。
- M&A交渉開始
- 秘密保持契約(NDA)
- 基本合意契約(LOI)
- デューデリジェンスの実施
1.M&A交渉開始
M&Aのプロセスは、買い手企業と売り手企業の最初のコンタクトから始まります。M&A仲介会社などを通じて紹介されるケースが多く見られます。
以下は、初期段階で紹介される主な情報です。
- 売り手企業の概要(事業内容、財務状況、従業員数など)
- 買い手企業の関心事項と買収目的
- 譲渡希望価格の目安
- M&Aのスケジュール感
この段階では、具体的な企業名は伏せられ、ノンネームシートと呼ばれる匿名の情報開示資料が用いられることが一般的です。
2.秘密保持契約(NDA)
双方が交渉継続の意思を持った場合、秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)を締結します。
NDAでは以下の事項を定めます。
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務の内容
- 秘密情報の使用目的の制限
- 情報の返還・廃棄義務
- 契約期間と有効期限
- 損害賠償条項
NDA締結後、売り手企業は買い手企業に対して、より詳細な情報を開示します。財務諸表や事業計画、主要な契約書、組織図などが提供され、買い手企業はこれらの情報を基に、本格的な検討を開始します。
3.基本合意契約(LOI)
双方の基本的な合意事項を確認するため、LOI(意向表明書)を締結します。LOIは、取引の基本条件や交渉の枠組みを文書で整理するためのもので、デューデリジェンス実施前に取り交わされるのが一般的です。
基本合意契約には、通常以下の内容が含まれます。
| 項目 | 詳細 |
| 取引の基本条件 |
|
| デューデリジェンスの実施 |
|
| 独占交渉権 |
|
基本合意契約の多くの条項は、法的拘束力を持たないものとされます。ただし、秘密保持義務や独占交渉権、費用負担などの条項は法的拘束力を持つように規定されることが一般的です。
4.デューデリジェンスの実施
デューデリジェンス(DD:Due Diligence)とは、買い手企業が売り手企業の実態を詳細に調査するプロセスです。専門家を起用して、以下の観点から調査を実施します。
| 項目 | 内容 |
| 財務デューデリジェンス |
|
| 法務デューデリジェンス |
|
| ビジネスデューデリジェンス |
|
| 税務デューデリジェンス |
|
デューデリジェンスの結果、重大なリスクが発見された場合、譲渡価格の減額交渉や、場合によっては交渉の中止もあり得ます。
5.最終契約(SPA・事業譲渡契約書など)
デューデリジェンスが完了し、最終的な条件について合意に達した後、最終契約を締結します。株式譲渡の場合は株式譲渡契約書(SPA)、事業譲渡の場合は事業譲渡契約書を締結します。
最終契約には、以下の重要条項が含まれます。
| 項目 | 内容 |
| 譲渡対象と譲渡価格 | 譲渡する株式または事業の範囲、最終的な譲渡価格、価格調整条項(クロージング時の純資産額に応じた調整) |
| 表明保証条項 | 売り手企業が財務状況・法的状況などについて、一定の事実が真実かつ正確であることを表明・保証する条項。違反があった場合、買い手企業は損害賠償請求が可能 |
| 前提条件 | 取引実行の前提となる条件(必要な許認可取得、第三者同意取得など) |
| 誓約条項 | クロージングまでの間、売り手企業が通常業務の範囲を超える行為(多額の借入、重要資産の処分など)を行わないことを約束 |
| 補償条項 | 表明保証違反や契約違反があった場合の損害賠償範囲、上限額、請求期間などを定める |
最終契約締結後、前提条件が充足されたことを確認し、クロージング(取引実行)を行います。
さらに詳しいM&Aの進め方については、以下の記事をご参照ください。
M&A契約における注意点

表明保証条項の重要性
表明保証条項は、M&A契約において重要な条項の一つです。売り手企業が、対象会社または対象事業に関する一定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証するものです。
表明保証の対象となる主な事項は次のとおりです。
<表明保証の対象となる主な事項>
- 財務諸表の正確性
- 簿外債務や偶発債務の不存在
- 重要な契約の有効性
- 訴訟・紛争の不存在
- 法令遵守
- 知的財産権の有効性と侵害の不存在
- 労務問題の不存在
- 環境問題の不存在
表明保証違反があった場合、買い手企業は売り手企業に対して損害賠償を請求できます。これにより、買い手企業は、デューデリジェンスで発見できなかったリスクから一定の保護を受けられます。
表明保証の範囲と内容は交渉事項であり、以下の点に留意が必要です。
| 表明保証条項の注意点 | 内容 |
| 表明保証の範囲 | 包括的な表明保証とするか、限定的な表明保証とするか |
| 損害賠償の上限額 | 譲渡価格の一定割合(例:50%)を上限とすることが多い |
| 免責金額 | 一定金額以下の損害は請求できないとする条項(少額クレームを排除) |
| 請求期間 | 表明保証違反に基づく損害賠償請求ができる期間 |
デューデリジェンスを十分に実施し、表明保証に依存しすぎないリスク管理が重要です。
価格調整条項・アーンアウト条項のリスク管理
M&A契約では、譲渡価格や対価の取り決めを明確にしておくことが大切です。特に、「価格調整条項」と「アーンアウト条項」は、価格や対価が変動する性質を持つため、契約上のリスクが生じやすい条項として注意が必要です。
<価格調整条項>
価格調整条項とは、クロージング時の純資産額や運転資本の額に応じて、譲渡価格を調整する条項です。
M&A契約締結からクロージングまでには一定の期間があり、その間に対象会社の財務状況が変動します。価格調整条項により、クロージング時の実際の財務状況を反映した公正な価格での取引が実現されます。
価格調整の方法:
- 基準となる純資産額または運転資本額を設定
- クロージング時の実際の価格を算定
- 差額に応じて譲渡価格を調整
価格調整においては、算定方法や対象項目について明確に定めることが重要です。あいまいな規定は、クロージング後の紛争の原因となります。
<アーンアウト条項>
アーンアウト条項とは、クロージング後の対象会社または対象事業の業績に応じて、追加的な対価を支払う条項です。
アーンアウトは、以下の場合に活用されます。
- 買い手企業と売り手企業の間で、事業の将来価値に関する評価が大きく異なる場合
- 売り手企業の経営陣がクロージング後も経営に関与し、業績向上へのインセンティブを与えたい場合
しかし、アーンアウト条項は、以下のリスクを伴うため注意が必要です。
| アーンアウトのリスク | 内容 |
| 業績指標の選定 | 何を業績指標とするか(売上高、営業利益、EBITDAなど)により、結果が大きく異なる |
| 業績の測定方法 | 会計基準の適用方法により、算定結果が変わる可能性がある |
| 経営方針の対立 | 買い手企業が短期的な利益を重視する一方、アーンアウトの対象者は長期的な業績向上を目指すなど、利害が対立する場合がある |
アーンアウト条項を設ける場合は、業績指標と測定方法を明確に定め、紛争を予防することが重要です。また、第三者による監査を義務付けるなど、透明性を確保する仕組みも有効です。
専門家に相談すべきタイミング
M&Aは専門的な知識を要するプロセスであり、適切なタイミングで専門家に相談することが重要です。
M&Aを検討し始めた段階で、M&A仲介会社などへの相談が推奨されます。
M&A仲介会社からは、以下のような支援を受けられます。
- 自社の状況に適したM&A手法の選定
- 想定される譲渡価格の目安の算定
- M&Aプロセスの全体像の把握
- 候補企業の探索
その他にも、密保持契約・基本合意契約の締結前やデューデリジェンス実施時、最終契約締結前には弁護士や税理士など、各分野の専門家との連携が必要です。
M&Aは企業の将来を左右する重要な意思決定です。専門家の知見を活用することで、リスクを抑え、成功確率を高められます。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aの種類を理解し適切な手法を選択しよう

M&Aには株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併など多様な手法があり、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持っています。
M&Aは企業の成長戦略や事業承継を実現する有効な手段ですが、その成功には適切な手法の選択と、専門的な知識に基づく慎重な進行が不可欠です。
M&A仲介会社などの専門家のサポートを受けることで、リスクを適切に管理し、円滑な取引の実現が可能になります。
自社の状況に最適なM&A手法を検討し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、M&Aを成功に導いてください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










