【飲食店M&A】事例から学ぶ売却・買収のすべて|相場・流れ・注意点を徹底解説

「自分の店を大きくしたい」「飲食店をはじめたいけど資金や経験がない」「事業承継の方法がわからない」飲食業界におけるこれらの課題は実は「飲食店M&A」で解決できることをご存知でしょうか?
飲食店の売却・買収を行うM&Aは、企業の成長戦略や事業承継の一手段として注目を集めています。しかし、成功するためには市場の動向を理解し、相場を把握し、メリット・デメリットを熟知することが必要です。
この記事では、大手から個人事業主までの実際のM&A事例から学び、飲食業界におけるM&Aの相場や動向、M&Aを実際に行う際の注意点などを徹底解説します。飲食店M&Aへの理解を深め、新たなスタートに向けての参考にしてください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
飲食店のM&A事例

ここでは、飲食店のM&Aの事例を、大手・中堅企業による買収事例と個人事業主レベルのM&A事例それぞれについて紹介します。これらの事例から、M&Aがどのように企業の成長や事業承継に貢献しているのかを見ていきましょう。
吉野家ホールディングスによる「キラメキノトリ」買収
牛丼チェーン「吉野家」やうどんチェーン「はなまるうどん」などを展開する吉野家ホールディングスは、2025年1月に、京都府を中心に鶏白湯ラーメンや台湾まぜそばを提供する人気ラーメン店「キラメキノトリ」(運営:キラメキノ未来株式会社)の全株式を取得し、完全子会社化しました。
このM&Aは、吉野家HDが進めるラーメン事業強化戦略の一環です。すでにグループ傘下に収めていたラーメンスープ・麺の開発製造会社「宝産業株式会社」との連携によるシナジー効果創出も目的としています。
吉野家HDの持つ国内外の経営資源や広範なネットワークを活用することで、「キラメキノトリ」ブランドの国内外でのさらなる成長拡大が期待されています。
この買収は、新たな収益の柱を育てたい吉野家HDと大手グループの支援を得て事業を拡大したいキラメキノ未来、双方にとって成長戦略に合致した事例と言えます。
参考:日本M&Aセンター『吉野家HD、京都のラーメン店「キラメキノトリ」を買収へ』
ラーメン業界のM&Aと現状の課題|事例や流れについて徹底解説
ゼンショーホールディングスによるSnowFox買収
「すき家」や「はま寿司」などを運営する外食大手のゼンショーホールディングスは、2023年9月、北米やイギリスを中心に約3,000店舗の寿司テイクアウト店や寿司の製造卸売事業を展開するSnowFox Topco Limitedの全株式を取得し、子会社化することを発表しました。
この買収は、ゼンショーHDが掲げる「人類社会の安定と発展に責任をおい、世界から飢餓と貧困を撲滅する」企業理念のもと、グローバル展開を加速させる戦略の一環です。
SnowFoxが持つ広範な海外ネットワークと、ゼンショーHDが持つメニュー開発力、食材調達網、物流システム、店舗運営ノウハウなどを組み合わせることで、大きなシナジー効果を生み出し、海外事業の成長をさらに強化することを目指しています。
このM&Aは、日本の大手外食企業が海外で成功している寿司事業会社を取り込むことで、グローバル市場における競争力を一気に高めようとする戦略的な動きであり、双方の強みを活かした成長が期待される事例です。
参考:ゼンショ―グループ『SnowFox Topco Limitedの株式取得(子会社化)に関するお知らせ』
木曽路による大将軍の買収
しゃぶしゃぶ・日本料理店「木曽路」などを全国展開する株式会社木曽路は、2020年11月に、千葉県を中心に焼肉店「大将軍」および「くいどん」を運営する株式会社大将軍の全株式を取得し、完全子会社化することを発表しました(株式譲渡実行は2021年1月)。
これは木曽路にとって初のM&A案件です。この買収の主な目的は、両社の強みを融合させることによる付加価値の高い商品・サービスの提供です。
また、木曽路の主力であるしゃぶしゃぶは冬期に売上が偏る一方、焼肉は夏期の売上が比較的高いため、グループ全体の業績の季節変動を平準化する狙いもありました。
さらに、すでに東海地区で展開していた自社ブランドの焼肉店「じゃんじゃん亭」と合わせ、焼肉部門の売上拡大と、大将軍の地盤である関東エリアへの本格展開も視野に入れています。
コロナ禍においても比較的堅調な焼肉業態を取り込むことで、業績の立て直しを図る戦略的な側面もありました。このM&Aは、異なる強みを持つ企業同士が連携し、シナジー効果と事業ポートフォリオの強化を目指した事例と言えます。
参考:日本M&Aセンター『木曽路、厳選和牛大将等の店舗を運営する大将軍の全株式取得、子会社化へ』
サンマルクホールディングスによるジーホールディングス買収
「ベーカリーレストランサンマルク」「サンマルクカフェ」などを展開するサンマルクホールディングスは、2024年10月、牛カツ定食業態「京都勝牛」やカフェ業態「NICK STOCK」を運営するジーホールディングス(GHD)を約112億円で買収しました。
この買収は、サンマルクグループのチェーン展開ノウハウを活かした新業態開発・育成するといった経営課題解決を目的としています。
買収後、インバウンド観光客の取り込みや海外進出の強化、グループ保有の商業施設情報や出店ノウハウの活用、DX支援、物流網の共有によるコスト削減など、多角的なシナジー効果が実現しています。
この事例は、異業態の企業同士によるM&Aによって、相互の強みを活かした事業拡大と収益性向上を達成した成功例と言えます。
参考:日本M&Aセンター『サンマルクホールディングス、牛カツ定食店など運営のジーホールディングスを買収』
JFLAホールディングスによる栄喜堂の買収
食品から酒類・飲料まで幅広い商品を扱う総合食品企業グループのJFLAホールディングスは、埼玉県入間郡三芳町に拠点を置く株式会社栄喜堂の全株式を取得し、完全子会社化しました。
栄喜堂は主に関東圏のレストランチェーンや量販店向けにパンや洋菓子の製造卸売業を展開しています。この買収により、JFLAホールディングスは生産事業の強化と既存ブランドを中心とした販売事業ポートフォリオの再構築を実現しました。
特に製販一体型モデルの強化に成功し、原材料調達から製造、販売までの一貫体制を確立することで、コスト削減と品質管理の向上を達成しています。
この事例は、食品製造業と外食産業の垂直統合によるシナジー効果を生み出した成功例として、飲食業界のM&A戦略において参考になるケースと言えます。
酒蔵M&Aの最新動向とは|法人経営者が知っておくべき売却メリット・流れ・事例など徹底解説
参考:日本M&Aセンター『JFLAホールディングス、栄喜堂の全株式取得、子会社化』
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
なぜ今、飲食店M&Aなのか? 飲食店のM&Aの動向

近年、飲食業界におけるM&A(合併・買収)が活発化しています。その背景には、業界特有の構造的な問題や外部環境の変化が複雑に絡み合っています。
ここでは、飲食店M&Aが注目される理由を深掘りし、その動向を解説します。
M&Aは事業承継の有効な手段
M&Aは、後継者不足や高齢化が進む飲食業界において、親族や従業員に後継者がいない場合でも事業を次世代につなげる有力な選択肢です。
従来の親族内承継や従業員承継が難しいケースでも、M&Aを活用すれば外部の第三者へ事業を引き継ぐことが可能となり、店舗のブランドや従業員、顧客基盤を維持しながら事業継続が図ることができます。
また、M&Aによって経営者は創業者利益を得て、新たな人生設計を描くこともできます。近年は小規模な個人経営飲食店でもM&Aによる事業承継が増加しており、事業承継・引継ぎ支援センターやM&A仲介会社などの公的・民間サービスも活用されています。
コロナ禍や経営低迷からの脱却
2020年以降のコロナ禍によって、多くの飲食店が売上減少や経営難に直面しました。このような厳しい経営環境の中、M&Aは経営再建や事業の立て直しを目指す店舗にとって重要な選択肢です。
特に、資金力や経営ノウハウを持つ企業による買収が進み、業績改善や新たな成長戦略を実現するケースが増加しています。
また、デリバリーやテイクアウト需要の拡大を背景に、これらの分野で強みを持つ店舗が買い手企業から注目され、戦略的なM&Aも活発化しています。
2024年以降は景気回復やインバウンド需要の高まりも追い風となり、飲食店M&Aの件数は増加傾向です。
飲食業界におけるオーナーの高齢化と後継者不足の深刻化
飲食業界では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な課題となっています。東京商工リサーチの「2024年「全国社長の年齢」調査」によると、経営者の平均年齢は62.77歳と過去最高を記録し、70代以上の経営者も32.7%に達しています。
さらに、飲食業界の人材不足は深刻で、帝国データバンクの人手不足に対する企業の動向調査では、正社員不足が56.9%、非正社員不足は77.3%と全業種平均を大きく上回っています。
このような状況下で、M&Aは後継者問題を解決し、長年培ってきた店舗のブランドや顧客、従業員を維持しながら事業を存続させる有効な手段として注目されています。
飲食店M&Aの相場とは?適正価格を知る方法

飲食店M&Aにおいて、適正な価格を知ることは、売り手・買い手双方にとって非常に重要です。相場を理解することで、双方が納得できる取引を実現し、M&A後の事業の成功につながります。
ここでは、M&A価格算出の計算方法と相場を左右する要因について解説します。
M&A価格算出の計算方法
飲食店M&Aにおける価格算出方法はいくつか存在しますが、代表的なものとして以下の方法が挙げられます。
| 算出方法 | 概要 | メリット | デメリット |
| コストアプローチ(純資産法) | 企業の純資産額をベースに企業価値を算定する方法です。貸借対照表に記載されている資産から負債を差し引いた金額を基に算出します。 | ・客観的な評価が可能
・計算が比較的容易 |
企業の将来性やブランド力などが反映されにくい |
| インカムアプローチ(収益還元法) | 企業の将来的な収益に着目し、その収益を現在価値に割り引いて企業価値を評価する方法です。 | 企業の将来性や成長性を評価に反映できる | ・将来の収益予測が難しい
・客観性に欠けてしまう |
| マーケットアプローチ(類似会社比較法) | 類似する上場企業の株価やM&A事例を参考に、対象企業の価値を評価する方法です。 | 市場の動向を反映した評価が可能 | 類似企業が見つからない場合や市場変動リスクの影響を受けやすい |
| 年買法 | 営業利益やEBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費を足したもの)の数年分を企業価値とする方法です。 | 簡易的に企業価値を算定できる | 詳細な分析には不向きで企業の特性が反映されにくい |
これらの算出方法を組み合わせて、より精緻な価格を算出します。M&Aの専門家は、これらの計算方法を駆使し、企業の状況に合わせて最適な評価を行います。
相場を左右する要因
飲食店のM&A相場は、さまざまな要因によって変動します。主な要因としては、以下のものが挙げられます。
- 立地条件:駅近や人通りの多い場所など、立地が良いほど売上が見込めるため、高評価につながる
- 店舗のブランド力・知名度:長年の実績や独自のブランド力がある店舗は、顧客基盤が安定しているため、高く評価されやすい
- 売上・利益:過去の売上実績や将来の収益予測は、M&A価格に大きく影響する
- 店舗の規模・内装:店舗の規模や内装の状態が良いほど、初期投資を抑えられるため、買い手にとって魅力がある
- 従業員の質:優秀な従業員が在籍していることは、M&A後のスムーズな運営につながるため、プラス評価になる
- 業界の動向:飲食業界全体のトレンドや競合店の状況も、M&A価格に影響を与える
- M&Aのタイミング:景気や市場の状況によって、M&Aの需要が変動し、相場も変動
これらの要因を総合的に考慮し、専門家による詳細な企業価値評価を行うことで、より適正なM&A価格を把握できます。M&Aを検討する際には、必ず専門家にご相談ください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
飲食店M&Aと居抜きとの違いとは?

飲食店を売却・買収する方法として、M&Aの他に「居抜き」といった手段があります。どちらも店舗を譲渡する点では共通していますが、その本質は大きく異なります。ここでは、居抜きとは何か、M&Aとはどう違うのかを解説します。
居抜きとは?
居抜きとは、既存の店舗の内装や設備、厨房機器などをそのままの状態で譲渡・売買することです。閉店する飲食店が、次の出店者に内装や設備を譲り渡すことで、出店者は初期投資を抑え、スムーズに開業できるメリットがあります。
一般的に、居抜きでの売却では、店舗の権利金や造作譲渡料が発生します。造作譲渡料は、内装や設備などの資産価値を評価して算出されますが、実際には、売り手と買い手の交渉によって決まることがほとんどです。
居抜き物件とM&Aとの違い
居抜き物件とM&Aの主な違いは、譲渡・売買の対象範囲にあります。居抜きはあくまで店舗の「箱」と「設備」の譲渡であるのに対し、M&Aは店舗の事業そのものを包括的に譲渡・売買します。
| 居抜き | M&A | |
| 譲渡対象 | 内装、設備などの有形固定資産 | 店舗の事業全体(顧客、従業員、ノウハウ、ブランドなど) |
| 手続き | 比較的簡易 | 専門的な知識が必要 |
| 費用 | M&Aに比べて安価 | 居抜きに比べて高額になる場合が多い |
| メリット | 初期費用を抑えられる | 事業の拡大、シナジー効果 |
| デメリット | 事業のノウハウは得られない | 従業員との関係構築が必要 |
具体的には、M&Aでは以下のようなものが譲渡対象に含まれます。
- 店舗の権利
- 内装、厨房設備
- 従業員
- 顧客リスト
- 仕入れルート
- メニュー
- ブランド
- ノウハウ
M&Aは、単なる店舗の譲渡ではなく、事業そのものを引き継ぐため、買い手は既存の顧客や従業員、ブランドなどを活用し、スムーズに事業を拡大できます。
一方、売り手は、事業を存続させることができ、従業員の雇用を守れます。また、M&Aでは、居抜きに比べて高額な売却益を得ることも可能です。
ただし、M&Aは、居抜きに比べて手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。また、従業員との関係構築や、旧オーナーが培ってきたつながりの維持など、買い手側の負担も大きくなる可能性があります。
そのため、店舗を閉店する際には、原状回復させる「スケルトン返し」や内装等の造作を譲渡する「居抜き」での売却が一般的でしたが、近年は「M&A」が注目を集めています。
売り手・買い手双方から見た飲食店M&Aのメリット・デメリット
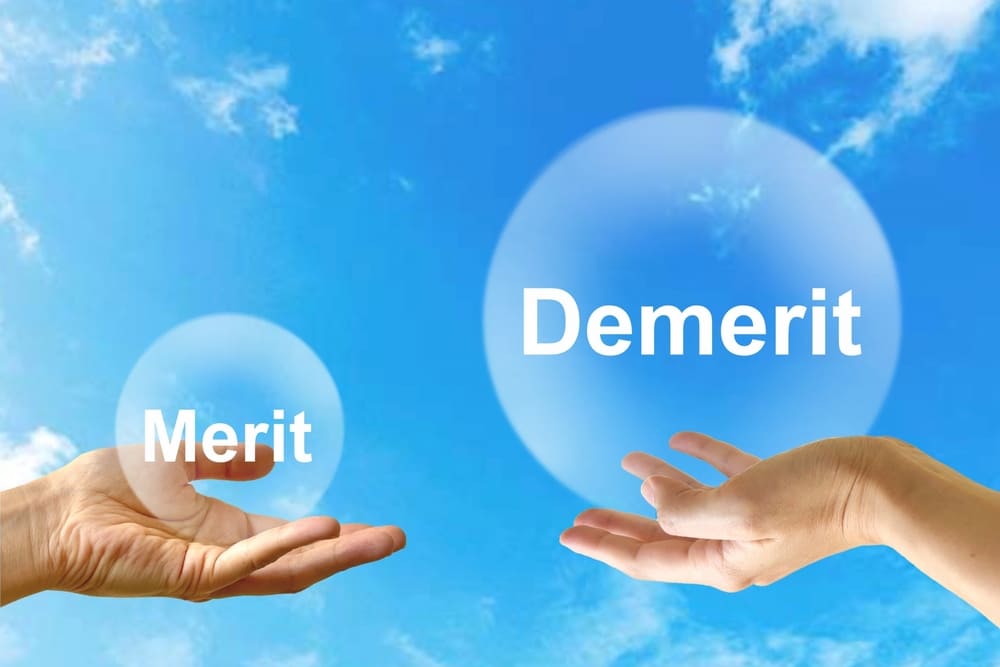
飲食店M&Aは、売り手と買い手の双方にとって、事業の拡大や再生、新たな展開の機会をもたらす可能性があります。しかし、その一方で、注意すべき点も存在します。
ここでは、それぞれの立場から見た飲食店M&Aのメリットとデメリットを詳しく解説します。
売り手のメリット
以下では、M&A(合併・買収)取引において、自社の株式や事業を譲渡する側の当事者である「売り手」側のメリットについて解説します。
売却益を得られる
飲食店をM&Aで売却する最大のメリットの一つは、まとまった「売却益」を得られることです。これは、単に店舗の資産価値だけでなく、長年かけて築き上げてきたブランド力や顧客基盤、将来性などが総合的に評価された結果です。
経営状態が良好であれば、いわゆる「創業者利益」として、これまでの努力が金銭的に報われることになります。得られた売却益は、引退後の安定した生活資金や新たな事業への挑戦資金など、オーナー経営者の次のライフプランを支える貴重な原資です。
売却価格は、純資産や利益を基にした計算方法や、企業の収益力などを考慮して算出されますが、最終的には買い手との交渉で決定されます。
顧客や従業員を守れる
後継者不足や経営不振から廃業を選ぶと、長年通ってくれた顧客との関係や共に店を支えてきた従業員の生活基盤は失われてしまいます。しかしM&Aであれば、事業は新たな経営者に引き継がれ、店舗の営業は継続されることが一般的です。
これにより、顧客は引き続き慣れ親しんだサービスを利用でき、従業員の雇用も多くの場合維持されます。大切な顧客と従業員双方の未来を守ることができる点は、M&Aの大きなメリットです。
原状回復費と解約予告家賃などコスト削減
飲食店を閉店する際には、原状回復工事費用と解約予告期間中の家賃支払いが大きな負担となります。
原状回復工事は坪あたり5〜10万円程度が一般的ですが、場合によっては20〜50万円かかる場合もあります。また、小規模店舗でも50坪程度の場合、50万円以上かかる可能性があります。
解約予告期間は通常1〜3ヶ月が一般的です。M&Aを活用することで、資産を有効に活用しつつ撤退することが可能で、廃業よりも経済効果が高い場合があります。
内装や設備の引き継ぎも可能ですが、具体的なコスト削減効果は契約内容や状況によって異なります。
売り手のデメリット
以下では、売り手側の飲食店M&Aのデメリットについて解説します。
資産価値を見極めることが難しい
飲食店の価値は、店舗設備のような「目に見える資産」だけでなく、ブランド力、秘伝のレシピ、常連客リスト、従業員のスキルといった「目に見えない価値(のれん)」も大きく影響します。
これらの無形資産を客観的に数値化し評価することは非常に難しく、売り手自身が適正な売却価格を見極められないケースが少なくありません。その結果、本来の価値よりも低い価格で売却してしまうリスクが生じます。
損をしないためには、M&Aの専門家に相談し、財務状況や将来性などを多角的に分析した企業価値評価(バリュエーション)を受けることが重要です。
属人化しているケースでは顧客が離れる可能性がある
飲食店の魅力がオーナーや特定の従業員の個性やスキルに強く依存している場合、M&A後に顧客離れが起こる可能性があります。
例えば、料理人の腕や接客スタッフの人柄が店の看板となっているケースでは、経営者の交代により店の雰囲気や提供価値が変わることで、常連客が離れてしまうリスクがあります。
このリスクを軽減するためには、事前に業務の標準化やマニュアル化を進め、個人の能力に依存しない店舗運営体制を構築することが重要です。
また、M&A後も一定期間は元オーナーや主要スタッフの継続勤務を条件とすることで、スムーズな事業承継を図れます。
株式譲渡に比べ手続きが複雑になる
事業譲渡は、株式譲渡と比較して手続きが複雑になる点がデメリットです。株式譲渡では会社全体を一括で移転できるのに対し、事業譲渡では資産や契約を個別に移転する必要があります。
店舗の設備や在庫、従業員の雇用契約、取引先との契約など、細かな調整が求められます。また、許認可の取得や名義変更といった法的な手続きも必要となり、これには時間とコストがかかる場合があります。
さらに、従業員や取引先との関係維持のために慎重な対応が求められることも、手続きの負担を増やす要因です。こうした複雑さを解消するためには、M&A仲介会社や弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。
買い手のメリット
以下では、他の企業やその事業部を買収する側の企業または個人を指す「買い手」側のM&Aにおけるメリットについて詳しく解説します。
飲食店経営の知識がなくても新規参入できる
M&Aを活用すれば、飲食業界の経験がなくても、すでに軌道に乗っている店舗をそのまま引き継ぐことが可能です。既存の設備、従業員、顧客基盤、仕入れルートなどの経営資源を一括で取得できるため、ゼロからの開業に比べてリスクを大幅に抑えられます。
特に2025年現在、飲食店M&Aの案件は増加傾向にあり、未経験者にとっても参入しやすい環境が整っています。
店舗運営のノウハウやマニュアルも引き継ぐことができるため、飲食店経営の知識を徐々に学びながら、安定した経営基盤の上でビジネスをスタートできる点が大きな魅力です。
設備や従業員、ブランドを引き継いで営業できる
飲食店M&Aでは、既存の設備や従業員、ブランドをそのまま引き継ぐことが可能です。これにより、新規開業に比べて初期投資を大幅に抑えられるだけでなく、既存の顧客基盤や評判を活用し、スムーズに事業を開始できます。
また、従業員の引き継ぎによって即戦力となる人材を確保できるため、人手不足のリスクも軽減されます。さらに、長年培われたブランドイメージやノウハウを活用することで、競争力のある経営が可能となり、早期の収益化が期待できる点も大きなメリットです。
仕入れや加工の合理化などのスケールメリットが期待できる
飲食店M&Aでは、複数店舗を統合することで、仕入れや加工の効率化が図れます。例えば、食材を大量に一括購入することで単価を抑えたり、共通の加工施設を利用することで物流コストを削減したりすることが可能です。
また、取引先との交渉力が向上し、より有利な条件で契約を結べるケースもあります。これらのスケールメリットにより、収益性の向上や競争力の強化が期待できるため、M&Aは成長戦略として非常に有効な手段となります。
多角的な事業展開でシナジー効果が期待できる
飲食店M&Aでは、多角的な事業展開を通じて複数の要素が組み合わさることで、単独で発揮する以上の成果や価値を生み出す「シナジー効果」を生むことが可能です。
例えば、異業種や異業態の店舗を買収することで、新たな顧客層を開拓したり、既存のノウハウを活用して新商品を開発などが期待できます。
また、観光業や農業など親和性の高い業種との連携により、送客シナジーや大量仕入れによるコスト削減も期待できます。これにより、事業の収益性向上や競争力強化が実現し、企業成長を加速させることが可能です。
買い手のデメリット
飲食店M&Aには多くのメリットがある一方で、買い手にとっていくつかのデメリットも存在します。以降では、買い手側のデメリットについて詳しく解説します。
コミュニケーションや相互理解など従業員との関係構築が必要
M&A後の最大の課題は、既存従業員との関係構築です。経営方針や企業文化の変化に対して、従業員は不安や抵抗感を抱きがちです。特に飲食業は人材が競争力の源泉となるため、スタッフの離職は事業価値を大きく損なう可能性があります。
買収後は、個別面談や定期的なミーティングを通じて従業員の声に耳を傾け、新しいビジョンを共有しながら信頼関係を構築することが重要です。また、優秀な人材を維持するためのインセンティブ制度や円滑な統合のための研修プログラムを導入することも効果的です。
旧オーナーが培ってきたつながりが希薄になる可能性がある
飲食店は地域社会との関係性が重要な業態です。特に長年営業している店舗では、旧オーナーが地域住民や常連客、取引先と築いてきた信頼関係が大きな無形資産となっています。
M&A後、これらの関係性は一朝一夕には引き継がれず、オーナー交代により常連客が離れたり、良好だった仕入れ条件が変更されたりするリスクがあります。
このリスクを軽減するには、旧オーナーからの丁寧な引継ぎ期間を設けることや地域イベントへの積極的な参加、常連客とのコミュニケーションを大切にするなど、地域との関係構築に意識的に取り組むことが重要です。
労務管理不備による買い手側の対応が必要な場合がある
買収対象の飲食店において、未払い残業代や社会保険料の未納など、労務管理上の問題が発覚するケースがあります。
デューデリジェンス(買収監査)をしっかりと行い、リスクを把握しておくことが重要です。万が一、問題が発覚した場合には、専門家と連携して適切に対応する必要があります。
| 飲食店M&Aのメリット・デメリット | ||
| 立場 | メリット | デメリット |
| 売り手 | ・売却益を得られる
・顧客や従業員を守れる ・原状回復費などのコスト削減 |
・資産価値を見極めるのが難しい
・属人化で顧客が離れる可能性 ・手続きが複雑 |
| 買い手 | ・未経験でも参入しやすい
・設備や従業員を引き継げる ・スケールメリット ・多角的な事業展開 |
・従業員との関係構築が必要
・旧オーナーとのつながりが希薄化 ・労務管理の問題 |
売り手・買い手側別に見る飲食店M&Aの流れ

飲食店M&Aは、売り手と買い手それぞれに特有のプロセスを経て進行します。ここでは、各々の視点からM&Aの流れを詳細に解説します。M&Aを成功させるためには、全体像を把握し、各ステップで適切な対応をすることが不可欠です。
売り手の流れ
飲食店を売却する際の流れは、以下のようになります。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 1. M&Aの目的明確化 | なぜM&Aを行うのか、目的を具体的に定める。
例:後継者不足の解消、事業の多角化、経営資源の集中など。 |
目的を明確にすることで、M&Aの方向性が定まり、その後のプロセスがスムーズに進みます。 |
| 2. 企業価値の評価 | 自社の財務状況、ブランド、顧客基盤などを評価し、企業価値を把握する。 | 正確な企業価値を知ることで、適切な売却価格を設定できます。専門家による評価も検討しましょう。 |
| 3. M&A仲介会社への相談・依頼 | M&Aの専門家である仲介会社に相談し、アドバイスを受ける。 | 仲介会社は、M&Aに関する知識や経験が豊富であり、適切な買い手探しや交渉をサポートしてくれます。 |
| 4. 買い手候補の選定 | 仲介会社のサポートのもと、自社の条件に合った買い手候補を選定する。 | 複数の候補を比較検討し、シナジー効果や企業文化の相性などを考慮して選びましょう。 |
| 5. 条件交渉 | 買い手候補と売却価格、条件などについて交渉を行う。 | 双方が納得できる条件を目指し、弁護士や公認会計士などの専門家と連携しながら進めましょう。 |
| 6. 基本合意書の締結 | 交渉がまとまったら、基本合意書を締結する。 | 基本合意書には、売却価格、スケジュール、秘密保持義務などが記載されます。 |
| 7. デューデリジェンスへの協力 | 買い手による詳細な企業調査(デューデリジェンス)に協力する。 | 必要な情報や資料を迅速かつ正確に提供することが重要です。 |
| 8. 最終契約の締結 | デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な売買契約を締結する。 | 契約内容をしっかりと確認し、不明な点は専門家に相談しましょう。 |
| 9. クロージング | 株式譲渡や事業譲渡の手続きを行い、M&Aを完了させる。 | クロージング後も、一定期間は買い手への協力や引継ぎを行うことが一般的です。 |
買い手の流れ
飲食店を買収する際の流れは、以下のようになります。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 1. M&A戦略の策定 | M&Aによってどのような目的を達成したいのか、具体的な戦略を立てる。
例:新規市場への参入、事業規模の拡大、競合他社の排除など。 |
明確な戦略を持つことで、M&Aの成功確率を高められます。 |
| 2. ターゲット企業の選定 | M&A戦略に合致するターゲット企業を選定する。 | 財務状況、ブランド、顧客基盤などを分析し、シナジー効果が期待できる企業を選びましょう。 |
| 3. 仲介会社への相談・依頼 | M&A仲介会社に相談し、ターゲット企業に関する情報を収集する。 | 仲介会社は、非公開情報を含む詳細な情報を提供してくれます。 |
| 4. 意向表明書の提出 | ターゲット企業に対して、買収意向を表明する意向表明書を提出する。 | 買収価格や条件などを提示し、交渉のテーブルにつくための意思表示を行います。 |
| 5. 条件交渉 | ターゲット企業と売却価格、条件などについて交渉を行う。 | 弁護士や会計士などの専門家と連携し、自社に有利な条件を目指しましょう。 |
| 6. 基本合意書の締結 | 交渉がまとまったら、基本合意書を締結する。 | 基本合意書には、独占交渉権やデューデリジェンスの実施などが盛り込まれます。 |
| 7. デューデリジェンスの実施 | ターゲット企業に対して、詳細な企業調査(デューデリジェンス)を実施する。 | 財務、法務、税務、労務など、多角的な視点からリスクを洗い出します。 |
| 8. 最終契約の締結 | デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な売買契約を締結する。 | 契約内容をしっかりと確認し、不明な点は専門家に相談しましょう。 |
| 9. クロージング | 株式譲渡や事業譲渡の手続きを行い、M&Aを完了させる。 | クロージング後も、PMI(Post Merger Integration)と呼ばれる統合プロセスが重要になります。 |
M&Aの流れは複雑であり、専門的な知識や経験が求められます。M&A仲介会社などの専門家を活用し、各ステップを慎重に進めることが成功への鍵となります。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
飲食店M&Aを成功させるためのポイントと注意点

飲食店M&Aは、売り手と買い手双方にとって大きな転機となります。成功のためには、単に取引を完了させるだけでなく、双方にとってメリットのある結果を目指す視点が不可欠です。
ここでは、M&Aを成功に導くために押さえておくべき重要なポイントと注意点を、売り手・買い手それぞれの立場から具体的に解説します。
売り手側が注意すべきこと
飲食店を売却する決断は、オーナーにとって大きな一歩です。しかし、焦りや準備不足から思わぬ失敗を招くケースも少なくありません。
大切な店舗を納得のいく形で譲渡し、円満なM&Aを実現するためには、売り手として押さえておくべき重要な注意点があります。
ここでは、後悔しないM&Aのために、特に意識すべき3つのポイントを解説します。
M&A後のビジョンを明確にすること
M&Aは、単なる事業の売却ではなく、新たなスタート地点です。売却後、どのような未来を描きたいのか、個人のキャリアプラン、セカンドライフ、新たな事業への挑戦など、具体的なビジョンを持つことが重要です。
ビジョンが明確であれば、M&Aの条件交渉や買い手とのコミュニケーションにおいて、主体的に行動できます。
どのような買い手に売却したいのかを具体的にイメージすること
企業規模、経営方針、従業員の待遇、ブランドイメージなど、理想の買い手像を具体的にイメージしましょう。譲渡後の従業員の雇用維持を重視するのか、事業のさらなる成長を期待するのかによって、選ぶべき買い手は異なります。
希望する買い手像を明確にすることで、M&A仲介会社との連携がスムーズになり、より良い条件での売却につながります。
店舗の状態把握や改善をすること
買い手は、店舗の現状を詳細に把握したいと考えています。売却前に、店舗の清掃、設備のメンテナンス、メニューの見直しなどを行い、可能な範囲で店舗の魅力を高めておきましょう。
また、過去の売上データ、顧客情報、従業員情報などを整理し、買い手に分かりやすく提示できるように準備しておくことが大切です。
買い手側が注意すべきこと
飲食店のM&Aは、事業拡大や新規参入を目指す買い手にとって大きなチャンスです。しかし、安易な判断は思わぬリスクを招きかねません。買収後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、事前に押さえておくべき重要な注意点があります。
ここでは、買収を成功に導くために、買い手として特に留意すべき3つのポイントを解説します。
ビジネスモデルや内装、設備など対象店舗を徹底的に調査すること
M&Aの対象となる飲食店について、ビジネスモデルの強みや弱み、内装や設備の状況、顧客層などを徹底的に調査しましょう。
売上データだけでなく、客単価、リピート率、時間帯別の集客状況など、詳細な情報を把握することで、買収後の経営戦略を立てやすくなります。
また、競合店の状況や市場のトレンドも考慮し、買収後の事業展開におけるリスクと機会を評価することが重要です。
デューデリジェンスをしっかり行うこと
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、買収対象となる企業の価値やリスクを詳細に調査することです。財務状況、法務、税務、労務など、多岐にわたる分野を専門家が調査し、潜在的なリスクを洗い出します。
デューデリジェンスをしっかり行うことで、買収後のトラブルを未然に防ぎ、適切な買収価格を決定できます。
スピード感ある判断し迅速に行動すること
M&Aの機会は、常に存在するとは限りません。魅力的な案件が現れた場合には、迅速な判断と行動が求められます。
ただし、焦って判断するのではなく、必要な情報を収集し、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討を進めることが大切です。
M&Aの交渉は、時間との勝負になることも多いため、社内の意思決定プロセスを迅速化し、スムーズに交渉を進められる体制を整えておくことが重要です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&Aは飲食店経営の新たな選択肢

飲食業界においては、中小企業や個人事業主にとっても、事業の成長や再生、そして事業承継を実現するための有効な選択肢です。
スマートフォンの普及やデリバリー需要の拡大を背景に、飲食業界ではM&Aが活発化しています。M&Aを活用することで、経営者は自身の築き上げてきた事業を次世代へとつなぎ、新たなステージへと進むことができます。
飲食業界におけるM&Aの可能性を理解し、自社の状況に合わせて検討することで、新たな成長の機会をつかみましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










