ビルメンテナンス業界のM&A徹底解説|売却メリット・事例・流れ・相談先など

ビルメンテナンス業界では、後継者不在や人手不足、競争激化などを背景に、M&Aによる事業承継や事業拡大を目指す動きが活発化しています。
しかし、M&Aは専門的な知識が必要であり、「何から始めればいいのか」「自社にとって最適な選択なのか」といった不安や疑問をお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ビルメンテナンス会社のM&Aを検討されている経営者に向けて、業界の最新動向やM&Aのメリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、成功に導くためのポイント、そして実際のM&A事例まで、網羅的に解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ビルメンテナンス業界の現状とM&Aを取り巻く環境

ビルメンテナンス業界は、建物の清掃や設備管理など、社会インフラを支える重要な役割を担っています。
近年では、人口減少や高齢化、都市部への人口集中といった社会構造の変化に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)や技術革新が活動的です。
こうした中、ビルメンテナンス業界全体の競争は激化し、利益率の低下や人材確保の難しさが課題となっています。これらの背景から、M&Aによって事業承継や経営基盤の強化を図る企業が増加しています。
市場規模と近年の推移
ビルメンテナンス業界の市場規模は安定的に成長を続けています。公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の調査によると、2023年の市場規模は4兆4,212億円に達しており、コロナ禍による一時的な停滞を乗り越え、回復基調です。
この成長の背景には、コロナ禍で先送りされていた新規案件の稼働開始や、ビル管理関連の改修工事等の受注増加があります。地域別に見ると、特に四国地方などの地方エリアで著しい成長が見られ、これらの地域での成長率の向上が業界全体の発展を牽引しています。
市場規模の拡大は、ビルメンテナンス会社のM&Aにおいても重要な要素です。安定した収益性を求める買い手企業にとって魅力的な投資対象となっています。
ビルメンテナンス業界が抱える課題
安定的な需要がある一方で、ビルメンテナンス業界は、以下のような多くの課題を抱えています。
- 人手不足の深刻化:少子高齢化の影響を受け、業界全体で人手不足が深刻化しています。特に、現場作業を担う人材の確保が難しくなっており、業務効率化や省人化が急務となっています。
- 従業員の高齢化:長年業界を支えてきたベテラン従業員の高齢化が進み、技術やノウハウの承継が課題となっています。若手人材の育成が追いつかず、技術力の低下が懸念されています。
- 競争激化:新規参入企業の増加や、価格競争の激化により、収益性の悪化が進んでいます。差別化戦略や高付加価値サービスの提供が求められています。
これらの課題を解決し、事業の継続や経営資源の統合による効率化を図る有効な手段の一つとして、M&Aが注目されています。
DX化や技術革新
近年、ビルメンテナンス業界では、DX化や技術革新の動きが加速しています。
- IoT技術の導入:センサーやネットワークを活用し、設備の稼働状況やエネルギー消費量などをリアルタイムで監視・分析することで、効率的なメンテナンスや省エネルギー化を実現しています。
- AI技術の活用:AIを活用し、過去のデータから故障予測や最適なメンテナンス時期を予測することで、予防保全の高度化やメンテナンスコストの削減を図っています。
- ロボット技術の活用:清掃ロボットや警備ロボットなどを導入し、省人化や業務効率化を進めています。
これらの技術革新は、ビルメンテナンス業界の生産性向上やサービス品質向上に大きく貢献する一方、導入コストや人材育成などの課題も存在します。
自社単独での対応が難しいこれらの課題を背景に、M&Aを通じて先進的な技術やノウハウを持つ企業を取り込み、自社の競争力を高めようとする動きも活発です。
特に、環境対応型サービスやスマート技術を持つ企業は、M&A市場で高い注目を集めています。
ビルメンテナンス業界におけるM&A動向

ビルメンテナンス業界では、近年M&Aが活発化しています。その背景には業界特有の事情があり、2025年現在も多くの企業がM&Aを戦略的な選択肢として重視しています。
ここでは、業界におけるM&A活発化の背景と、最新の特徴・傾向について見ていきましょう。
M&Aが活発化する背景
ビルメンテナンス業界でM&Aが活発化している背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
最大の要因の一つは、多くの中小企業が抱える後継者不在の問題です。経営者の高齢化が進む一方で、親族や社内に適切な後継者が見つからず、事業の継続が困難になるケースが増えています。こうした企業にとって、M&Aは事業と従業員の雇用を守るための有効な手段です。
また、人手不足や人件費の高騰もM&Aを後押しする要因です。M&Aによって人材を確保し、スケールメリットを追求することで、採用コストや労務管理の負担を軽減する狙いがあります。
さらに、異業種からの新規参入や、大手企業による事業エリア拡大、サービスラインナップの拡充を目的としたM&Aも見られます。ビルメンテナンス業は景気変動の影響を受けにくく、安定した収益を見込めるため、魅力的な投資対象と映る場合があるからです。
近年のM&Aの特徴と傾向
近年のビルメンテナンス業界におけるM&Aの特徴と傾向としては、以下の点が挙げられます。
| 近年のM&Aの特徴 | |
| 特徴 | 詳細 |
| 大手企業による中小企業の買収 | 大手企業が、事業エリアの拡大やサービスラインナップの拡充を目的として、中小企業を買収するケースが増加しています。 |
| 異業種からの参入 | 不動産会社や警備会社など、異業種からの参入が増えています。既存事業とのシナジー効果を期待する動きがあります。 |
| 海外展開を視野に入れたM&A | 海外市場への進出を目的としたM&Aも増加傾向にあります。 |
| 技術・ノウハウの獲得を目的としたM&A | 清掃ロボットやAIを活用した設備管理など、新たな技術やノウハウを持つ企業を買収するケースが見られます。 |
| 事業再生を目的としたM&A | 経営不振に陥った企業を、他の企業が買収し、事業再生を図るケースもあります。 |
M&Aの目的も多様化しており、事業承継だけでなく、成長戦略や事業再生など、さまざまな目的でM&Aが活用されています。
これらの動向を踏まえ、自社の状況や目的に合ったM&A戦略を検討することが重要です。
ビルメンテナンス業界のM&A徹底解説|売却メリット・事例・流れ・相談先など
ビルメンテナンス会社がM&Aを行うメリット【売り手】

ビルメンテナンス業界では、後継者不足や競争激化などの課題を抱える企業が少なくありません。M&Aは、これらの課題を解決し、更なる成長や安定を実現するための有効な手段となります。
ここでは、ビルメンテナンス会社がM&Aを行う際の売り手側のメリットについて詳しく解説します。
後継者問題の解決
中小企業にとって、後継者不足は深刻な問題です。特に、オーナー経営者が高齢化している場合、事業承継が喫緊の課題となります。
M&Aは、後継者不在の企業が第三者に事業を譲渡することで、事業の継続を可能にする有効な手段です。後継者問題を解決することで、長年培ってきた技術やノウハウ、顧客との信頼関係を次世代に引き継げます。
創業者利益の獲得と個人保証の解除
M&Aによる会社売却は、オーナー経営者にとって創業者利益を現金化する機会です。株式譲渡によって得た売却代金は、引退後の生活資金や新たな事業への投資などに活用できます。長年の努力が報われる瞬間であり、経営者としての大きな達成感にもつながります。
また、中小企業の経営者は、会社の借入金に対して個人保証を行っているケースが一般的です。M&Aが成立し、会社が買い手企業の傘下に入ることで、この個人保証や担保提供が解除される可能性が高まります。
経営者は個人的な財務リスクから解放され、精神的な負担も大きく軽減されます。
従業員の雇用維持
会社の売却を検討する際、経営者が最も懸念することの一つが従業員の雇用です。
廃業を選択すれば、従業員は職を失うことになります。しかし、M&Aによって事業が継続されれば、従業員の雇用も原則として買い手企業に引き継がれます。
M&Aは、従業員の生活を守り、彼らが安心して働き続けられる環境を提供するための有効な手段です。経営者は従業員に対する責任を果たせます。
大手傘下入りによる経営基盤の安定化・事業成長
M&Aによって大手企業や事業会社の傘下に入ることで、経営基盤が安定し、事業成長の機会が広がります。
大手企業の経営資源(資金、技術、ノウハウ、ブランド力など)を活用することで、自社だけでは難しかった事業拡大や新規事業への参入が可能です。
また、大手企業のネットワークを活用することで、新たな顧客の獲得や販路の拡大も期待できます。
経営からのリタイア・ハッピーリタイアの実現
M&Aは、経営者が経営の第一線から退き、新たな人生をスタートさせるための円滑な出口戦略です。
特に、後継者が見つからない場合や、自身の健康問題、あるいは新たな目標に挑戦したいと考えている経営者にとって、M&Aは魅力的な選択肢です。
事業を信頼できる相手に託し、従業員の雇用や取引先との関係も維持した上で、自身は創業者利益を得てリタイアする。
これは、多くの経営者が理想とする「ハッピーリタイア」(創業者利益によって経済的な安定を得て、事業や従業員を信頼できる相手に託し、心残りなく充実した第二の人生を送ること)の形と言えるでしょう。
M&Aを成功させることで、心残りなく経営から引退し、第二の人生を充実させることができます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ビルメンテナンス会社がM&Aを行うメリット【買い手】

ビルメンテナンス会社のM&Aは、買い手企業にとっても多くの戦略的メリットをもたらします。事業エリアの拡大や市場シェアの向上、優秀な人材や専門ノウハウの獲得、そして新規事業への参入など、M&Aは企業の成長を加速させる強力な手段です。
ここでは、買い手企業がビルメンテナンス会社のM&Aを通じて得られる主なメリットについて解説します。
事業エリアの拡大・市場シェアの向上
ビルメンテナンス会社を買収する買い手にとって、最も直接的なメリットの一つが事業エリアの拡大と市場シェアの向上です。
特に、自社がまだ進出していない地域で事業を展開している企業を買収することで、短期間で新たな市場への足がかりを築けます。また、同業他社を買収することで、既存エリアにおける顧客基盤や管理物件数を増やし、市場シェアを拡大できます。
地域内での競争優位性を高め、収益機会の増大につなげることが可能です。自社で一から新規開拓を行うよりも、時間とコストを大幅に節約できる点が大きな魅力です。
人材・ノウハウの獲得
ビルメンテナンス業界は労働集約型の産業であり、経験豊富で質の高い人材の確保が事業の成否を左右します。M&Aは、売り手企業が抱える熟練した技術者や営業担当者、管理スタッフなどをまとめて獲得できる有効な手段です。
特に専門性の高い分野や、採用が難しい職種の人材を確保できるメリットは大きいです。また、売り手企業が長年培ってきた独自の技術や業務ノウハウ、顧客との信頼関係なども引き継げます。
自社のサービス品質の向上や、対応可能な業務範囲の拡大が期待できます。
新規事業への参入・多角化
ビルメンテナンス事業は、清掃、設備管理、警備など多岐にわたるサービスを含んでいます。買い手企業が自社の既存事業と関連性の高いビルメンテナンス会社を買収することで、新規事業分野へ比較的スムーズに参入し、事業の多角化を図ることが可能です。
例えば、建設会社がビルメンテナンス会社を買収して竣工後の管理業務まで一貫して手がけられる体制を構築したり、不動産管理会社がサービスラインナップを拡充するために買収を行ったりするケースがあります。
新たな収益源を確保し、企業グループ全体の事業ポートフォリオを強化することが可能です。
スケールメリットによるコスト削減・効率化
複数のビルメンテナンス会社が統合することで、スケールメリットを活かしたコスト削減や業務効率化が期待できます。
例えば、資材や消耗品の一括大量購入による単価の引き下げ、管理部門の集約による間接コストの削減、重複する業務プロセスの見直しによる効率化などが挙げられます。
また、広範囲なエリアをカバーできるようになることで、人員配置の最適化や車両の効率的な運用も可能です。これらのコスト削減や効率化は、利益率の改善に直結し、企業の競争力強化に貢献します。
シナジー効果による企業価値向上
M&Aによる統合で期待される最も大きな効果の一つが、シナジー効果(相乗効果)の発現です。シナジー効果は、売り手企業と買い手企業がそれぞれの強みを持ち寄り、連携することで、単純な合計以上の価値を生み出すことです。
例えば、買い手企業の持つ営業力と売り手企業の持つ高い技術力を組み合わせることで、より広範な顧客層に高品質なサービスを提供できるようになる可能性があります。
また、両社の顧客基盤を相互に活用することで、クロスセルやアップセルの機会が生まれるでしょう。
これらのシナジー効果が実現すれば、企業全体の収益性や成長性が高まり、企業価値の向上につながります。
ビルメンテナンス会社がM&Aを行う際のデメリット【売り手】

M&Aは、ビルメンテナンス会社にとって大きな転換期となる可能性があります。しかし、成功ばかりではありません。売り手側には、いくつかのデメリットも存在します。
M&Aを検討する際には、これらのデメリットを十分に理解し、対策を講じることが重要です。
希望条件での売却が難しい可能性がある
M&Aでは、必ずしも売り手側の希望通りの条件で売却できるとは限りません。
買い手側の企業価値評価や交渉によって、売却価格やその他の条件が変動する可能性があります。特に、財務状況が良くない場合や、業界全体の景気が低迷している場合には、希望価格での売却は難しくなる傾向があります。
事前に自社の企業価値を正確に把握し、複数の買い手候補と交渉することで、より有利な条件での売却を目指すことが重要です。M&A仲介会社などの専門家を活用し、交渉を有利に進めるためのアドバイスを受けるのも有効な手段です。
従業員の処遇や企業文化の変化への懸念がある
M&A後、従業員の雇用条件や労働環境が変わる可能性があります。
例えば、給与や福利厚生の低下、異動や転勤、リストラなどの不安が生じ、従業員のモチベーション低下や離職につながるなどです。また、企業文化の違いから、従業員が新しい環境に馴染めず、組織全体のパフォーマンスが低下するリスクもあります。
M&A交渉の段階で、従業員の雇用維持や労働条件の維持について、買い手側と十分に協議することが重要です。また、M&A後には、従業員への丁寧な説明やコミュニケーションを行い、不安を解消し、新しい企業文化へのスムーズな移行を支援する必要があります。
従業員への配慮を怠ると、M&A後の事業運営に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。
情報漏洩のリスクがある
M&Aのプロセスでは、自社の財務情報や顧客情報など、機密性の高い情報を買い手側に開示する必要があります。情報管理体制が不十分な場合、これらの情報が外部に漏洩するリスクがあります。情報漏洩は、企業の信用を失墜させ、損害賠償請求につながる可能性がある重要な要素です。
そのため、M&Aの初期段階で、買い手側との間で秘密保持契約(NDA)を締結し、情報管理体制を強化することが重要です。また、開示する情報の範囲を必要最小限に絞り、情報へのアクセス権限を厳格に管理する必要があります。
M&A仲介会社など専門家を活用し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための対策を講じることが不可欠です。
M&A成立までの時間と労力がかかる
M&Aは、交渉、デューデリジェンス(企業価値精査)、契約締結など、多くのプロセスを経て成立します。これらのプロセスには、数カ月から数年単位の時間がかかることもあります。
M&Aをスムーズに進めるためには、早期から専門家(M&A仲介会社、弁護士、会計士など)に相談し、計画的に準備を進めることが重要です。
また、社内の担当者を明確にし、役割分担を行うことで、経営者の負担を軽減できます。M&Aは長期戦となることを覚悟し、根気強く取り組むことが成功への鍵となります。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ビルメンテナンス会社がM&Aを行う際のデメリット【買い手】
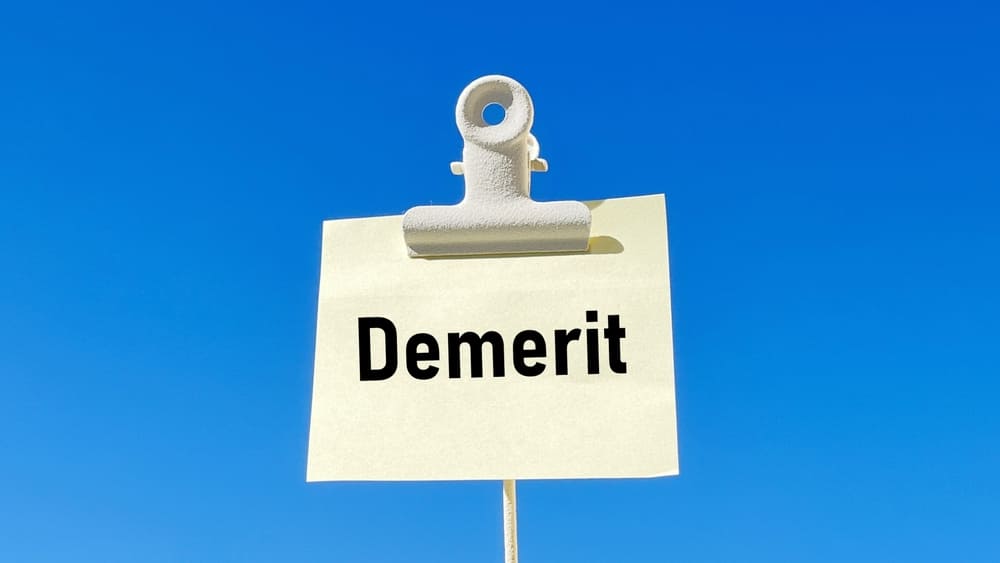
ビルメンテナンス会社のM&Aは、買い手企業にとっても大きなメリットが期待できる一方で、見過ごせないデメリットも存在します。M&Aを検討する際には、これらのリスクを十分に理解し、慎重な判断が求められます。
想定したシナジー効果が得られないリスクがある
M&Aの大きな目的の一つはシナジー効果の実現ですが、必ずしも期待通りに効果が現れるとは限りません。
例えば、両社の企業文化の違いから従業員のモチベーションが低下したり、業務プロセスの統合がスムーズに進まなかったりすることで、想定していたコスト削減や売上増加が達成できない場合があります。
また、市場環境の変化や競合の動向によって、M&A当時には見込めなかった新たな課題が発生することもあります。
シナジー効果を過度に期待するのではなく、現実的な目標設定と、達成に向けた具体的な計画の策定が重要です。
簿外債務や労務問題などの引き継ぎリスクがある
M&Aにおいて買い手企業が特に注意すべき点の一つが、売り手企業が抱える潜在的なリスクの引き継ぎです。財務諸表に現れない簿外債務や未払いの残業代、訴訟リスク、コンプライアンス違反など、買収後に問題が発覚するケースがあります。
これらの問題は、買収価格の算定やM&A後の経営に大きな影響を与える可能性があります。そのため、契約前のデューデリジェンス(企業調査)を徹底的に行い、潜在的なリスクを可能な限り洗い出すことが不可欠です。
発見されたリスクについては、契約条件に反映させるなどの対策を講じる必要があります。
買収後の統合プロセス(PMI)が困難
M&Aは、買収して終わりではありません。買収後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)が、M&Aの成否を大きく左右します。
PMIとは、両社の経営戦略、組織、システム、企業文化などを統合し、シナジー効果を最大化するための活動です。しかし、PMIは非常に複雑で、時間と労力を要するプロセスであり、両社の従業員の反発や協力不足、意思決定の遅延など、さまざまな困難が伴います。
PMIがうまくいかない場合、M&Aの効果は半減し、企業価値の低下につながることもあります。
高額な買収資金が必要となるケースがある
ビルメンテナンス会社のM&Aには、当然ながら買収資金が必要です。特に、優良な企業を買収しようとする場合、高額な買収資金が必要となるケースがあります。資金調達の方法によっては、金利負担が重くなり、経営を圧迫する可能性もあります。
また、買収資金を回収するために、過度なコスト削減や人員削減を行うと、従業員のモチベーション低下やサービス品質の低下を招き、長期的な企業価値を損なうことにもなりかねません。
ビルメンテナンス会社のM&A・売却の一般的な流れと手続き

ビルメンテナンス会社のM&Aや売却を進めるには、一定のプロセスと手続きが必要です。専門家への相談から始まり、相手企業との交渉、そして最終契約、さらにはその後の統合プロセスまで、段階を踏んで慎重に進めることが成功の鍵となります。
ここでは、M&Aの一般的な流れを4つの主要な段階に分けて解説します。
1.M&Aの検討・準備段階(専門家への相談、企業価値評価など)
M&Aを成功させるための第一歩は、自社の現状分析とM&A戦略の明確化です。なぜM&Aを行うのか、M&Aによって何を実現したいのか、目的を具体的に設定します。
この段階で、M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザーなどの専門家に相談し、アドバイスを求めることが一般的です。専門家は、M&Aの進め方や市場動向、想定されるリスクなどについて助言を提供してくれます。
また、自社の企業価値評価(バリュエーション)も重要な準備の一つです。企業価値評価は、売却価格の目安となるだけでなく、交渉戦略を立てる上でも不可欠な情報となります。
2.交渉段階(マッチング、トップ面談、基本合意)
準備が整ったら、次はM&Aの相手企業を探すマッチングの段階に入ります。M&A仲介会社などを通じて、自社の希望条件に合う候補企業を選定し、匿名で打診を行います。
関心を示した企業とは、秘密保持契約を締結した上で、より詳細な企業情報の交換を行いましょう。双方の経営者同士が直接会って経営方針やビジョンについて話し合うトップ面談は、M&Aの成否を左右する重要な機会です。
相互理解が深まり、M&Aの基本的な方向性について合意できれば、主要な条件(譲渡価格の範囲、スケジュール、独占交渉権など)を盛り込んだ基本合意書を締結します。
3.最終契約段階(デューデリジェンス、最終契約締結)
基本合意締結後、買い手企業は売り手企業に対してデューデリジェンス(買収監査)を実施します。デューデリジェンスでは、財務、法務、税務、事業、人事など、多角的な観点から売り手企業の実態を詳細に調査し、潜在的なリスクや問題点を洗い出しましょう。
デューデリジェンスの結果を踏まえて、最終的な譲渡条件について交渉が行われます。双方がすべての条件に合意すれば、法的拘束力のある最終契約書(株式譲渡契約書や事業譲渡契約書など)を締結します。
この契約書には、譲渡価格、支払方法、クロージングの前提条件、表明保証などが詳細に定められている契約書です。
4.クロージング・統合プロセス(PMI)
最終契約締結後、契約に定められた前提条件がすべて満たされたことを確認し、株式や事業の譲渡、対価の支払いが行われるクロージングを迎えます。クロージングをもって、M&Aの法的な手続きは完了です。
しかし、M&Aの真の成功は、その後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)にかかっています。
PMIでは、両社の経営方針のすり合わせ、組織体制の再編、業務プロセスの統合、情報システムの連携、企業文化の融合などを計画的に進めていく必要があります。
PMIを円滑に進めることが、M&Aで期待したシナジー効果を最大限に引き出すため重要な要素です。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ビルメンテナンス会社のM&Aを成功に導くポイント

ビルメンテナンス会社のM&Aを成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。早期からの準備や適切なアドバイザーの選定、自社の強みの明確化など、事前の取り組みがM&Aの成否を大きく左右する要因であるためです。
ここでは、M&Aを成功に導くための主要なポイントを解説します。
早期からの準備と企業価値向上策を実施すること
M&Aを成功させるためには、思い立ってすぐに動くのではなく、早期から周到な準備を進めることが重要です。まずは自社の経営状況や財務内容、強みや弱みを客観的に把握し、整理しておく必要があります。
その上で、日頃から帳簿書類の整備やコンプライアンス体制の構築など、社内管理体制を強化しておくことが望ましいです。また、企業価値を高めるための取り組みも重要です。
例えば、収益性の高い契約の獲得、業務効率の改善、従業員のスキルアップなどを継続的に行うことで、より有利な条件でのM&A実現につながります。M&Aを検討し始めた段階から、意識的に企業価値向上策を実施していくことが成功の鍵となります。
適切なM&Aアドバイザーや仲介会社を選定すること
M&Aは専門的な知識や経験が不可欠なため、信頼できるM&Aアドバイザーや仲介会社を選定することが極めて重要です。アドバイザーは、M&A戦略の立案から相手企業の探索、交渉、契約手続き、そしてPMIに至るまで、一連のプロセスをサポートしてくれます。
ビルメンテナンス業界のM&Aに精通しているか、自社の規模やニーズに合ったサービスを提供してくれるか、担当者との相性は良いかなど、複数の観点から慎重に選定する必要があります。
手数料体系も確認し、納得のいくパートナーを見つけることが、M&Aをスムーズに進めるための大きなポイントです。
自社の強みと希望条件を明確化すること
M&Aの交渉を有利に進めるためには、自社の強みを明確に把握し、それを効果的にアピールすることが重要です。
独自の技術力、特定の顧客層との強固な関係、優秀な人材、高い収益性など、他社にはない魅力を具体的に示すことで、買い手企業からの評価を高められます。
同時に、M&Aにおける自社の希望条件(売却価格、従業員の雇用維持、経営陣の処遇など)を優先順位も含めて明確にしておくことも大切です。交渉の軸がぶれることなく、納得のいく条件でのM&A成立を目指せます。
ただし、現実離れした条件に固執しすぎると、交渉が難航する可能性もあるため、柔軟な姿勢も必要です。
M&Aのタイミングを見極めること
M&Aを成功させるためには、適切なタイミングを見極めることも重要な要素です。自社の業績が良い時期や、業界全体が活況を呈している時期は、一般的に企業価値が高く評価されやすいため、売り手にとっては有利な条件で交渉を進められる可能性が高まります。
また、経営者の年齢や健康状態、後継者の有無なども、M&Aを検討するタイミングに影響を与えるでしょう。市場環境や自社の状況を総合的に判断し、最適なタイミングでM&Aを実行することが、より良い結果につながります。
専門家のアドバイスも参考にしながら、慎重に判断することが求められます。
従業員や取引先への丁寧な説明をすること
M&Aは、従業員や取引先にとっても大きな影響を与える出来事です。そのため、M&Aの公表タイミングや伝え方には細心の注意が必要です。
情報開示のタイミングは、一般的に最終契約締結後が良いとされていますが、状況に応じて専門家と相談しながら決定します。公表後は、従業員に対してM&Aの背景や目的、今後の処遇などについて、誠意をもって丁寧に説明し、不安を取り除く努力が不可欠です。
同様に、主要な取引先に対しても、今後の取引継続やサービス提供体制について説明し、理解と協力を得ることが重要です。関係者への丁寧なコミュニケーションが、M&A後の円滑な事業運営につながります。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
ビルメンテナンス会社のM&A事例紹介
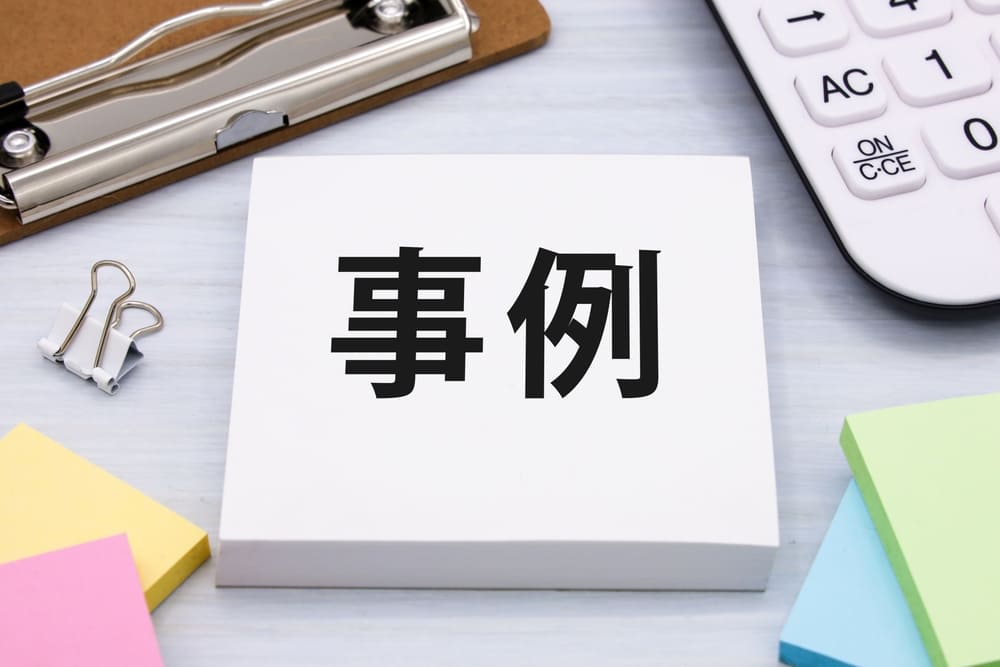
ビルメンテナンス業界におけるM&Aは、事業規模の拡大、技術・ノウハウの獲得、そして事業多角化など、さまざまな目的で行われています。ここでは、近年のM&A事例を3つのパターンに分けてご紹介します。
事例①同業他社によるM&A
ビルメンテナンス業界で最も一般的なM&Aの形態の一つが、同業他社による買収です。これは、事業エリアの拡大、管理物件数の増加による市場シェアの向上、あるいは特定分野の強化などを目的として行われます。
例えば、マンション管理を主力とする日本ハウズイング株式会社は、2021年12月に三井E&Sホールディングス株式会社からMESファシリティーズ株式会社の全株式を取得し子会社化しました。
MESファシリティーズは工場や産業施設の設備管理に強みを持っており、このM&Aにより日本ハウズイングは事業基盤の拡大と周辺事業の強化を図っています。
また、株式会社穴吹ハウジングサービスは、2020年11月に北海道で清掃事業などを展開する建衛工業株式会社を子会社化しました。これにより、穴吹ハウジングサービスは北海道エリアでの事業拡大を目指しています。
これらの事例のように、同業他社間のM&Aは、既存事業とのシナジー効果を発揮しやすい特徴があります。
事例②異業種によるビルメンテナンス会社進出へのM&A
近年では、異業種からビルメンテナンス業界へ参入するためにM&Aを活用するケースも見られます。
ビルメンテナンス事業は、定期的な契約に基づき安定した収益が見込めるストック型のビジネスモデルであるため、他業種の企業にとって魅力的な投資対象です。
2023年7月、出版業を中心に映画、ゲーム、アニメなど幅広いメディア事業を展開するKADOKAWAが、ビルメンテナンス事業を買収しました。
KADOKAWAは自社のビジネス領域を拡大し、多角化を図るためにこの買収を実施しました。
これにより、既存の出版業務とシナジーを生み出し、安定した収益基盤を築くとともに、関連業界への進出を果たすことを目指しています。
参考:株式会社KADOKAWA
事例③ビルメンテナンス会社から異業種へのM&A
ビルメンテナンス会社が、自社の事業ポートフォリオの多角化や新たな成長分野への進出を目指し、異業種の会社を買収するケースも存在します。
これは、既存のビルメンテナンス事業で培った顧客基盤やノウハウを活かしつつ、新たな収益の柱を確立することを目的としています。
例えば、イオンディライト株式会社は、総合ファシリティマネジメントサービス企業として国内外で事業を展開していますが、2024年には中国の連結子会社であった物流事業会社を売却しました。
参考:イオンディライト株式会社
これは、経営資源の選択と集中を進め、より成長が見込まれる分野や地域に注力するための戦略的な判断と言えます。このように、自社の強みを活かせる分野や、将来性のある市場へM&Aを通じて進出することは、企業が持続的に成長していくための一つの戦略です。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
ビルメンテナンス会社のM&Aに関する相談先

ビルメンテナンス会社のM&Aを検討し始めたものの、具体的にどこへ相談すれば良いのかわからないといった経営者の方も多いでしょう。M&Aは専門的な知識と経験が求められるため、適切な相談先を選ぶことが成功への第一歩となります。
ここでは、ビルメンテナンス会社のM&Aに関する主な相談先を紹介します。
M&A仲介会社・アドバイザリー
M&Aを専門に扱う仲介会社やアドバイザリーファームは、最も代表的な相談先です。
これらの専門家は、M&Aの戦略立案から相手企業の探索(マッチング)、交渉、デューデリジェンスのサポート、契約書の作成支援、そしてクロージングに至るまで、M&Aの全プロセスにわたって専門的なアドバイスと実務的な支援を提供します。
ビルメンテナンス業界に特化した実績や知見を持つ仲介会社であれば、業界特有の慣習や評価ポイントを理解しているため、よりスムーズなM&Aの実現が期待できます。
手数料体系は成功報酬型が一般的ですが、着手金や月額報酬が発生する場合もあるため、事前にしっかりと確認することが大切です。複数の会社から話を聞き、自社に合った信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
金融機関(銀行、証券会社)
取引のある銀行や証券会社などの金融機関も、M&Aに関する相談窓口を設けている場合があります。特に地方銀行や信用金庫は、地域の中小企業の事業承継問題に積極的に取り組んでおり、M&Aに関する情報提供やマッチング支援を行っています。
大手銀行や証券会社は、M&A専門の部署を持ち、より大規模な案件や複雑なスキームに対応できる体制が魅力です。金融機関に相談するメリットとしては、長年の取引関係に基づく信頼感や、M&Aに伴う資金調達の相談も併せて行える点などがメリットです。
ただし、必ずしもすべての金融機関がM&Aに精通しているわけではないため、実績や専門性を確認することが重要です。
公的機関(事業承継・引継ぎ支援センター)
中小企業の事業承継を支援するために、各都道府県に設置されている「事業承継・引継ぎ支援センター」も相談先の一つです。これらのセンターは、国が設置する公的な相談窓口であり、事業承継に関するさまざまな相談に無料で応じています。
後継者不在に悩む中小企業に対して、M&Aを含む事業引継ぎの選択肢や進め方についてアドバイスを行ったり、必要に応じて民間のM&A専門家を紹介したりするなどの支援を行っています。
特に、初めてM&Aを検討する企業や、何から手をつけて良いかわからないといった場合に、気軽に相談できる窓口として活用できる点が魅力です。ただし、センター自体が直接M&Aの仲介業務を行うわけではない点に留意が必要です。
| ビルメンテナンス会社のM&Aに関する相談先 | |||
| 相談先 | メリット | デメリット | おすすめの企業 |
| M&A仲介会社・アドバイザリー | 専門的な知識やノウハウが豊富
M&Aの全般的なプロセスをサポート |
費用がかかる | M&Aの経験がない企業
M&Aのプロセスをすべて任せたい企業 |
| 金融機関(銀行、証券会社) | 地域とのネットワークがある(銀行)
資金調達や企業価値評価に強い(証券会社) |
M&Aに関する専門的な知識やノウハウが不足している場合がある | M&Aの経験が豊富な企業
自社でM&Aのプロセスをある程度進められる企業 |
| 公的機関(事業承継・引継ぎ支援センター) | 無料で相談できる
中立的な立場で相談に乗ってくれる |
M&Aのサポート範囲が限定的 | 初めてM&Aを検討する企業
費用を抑えたい企業 |
M&Aの相談先を選ぶ際には、上記の情報を参考に、自社の状況や目的に合わせて最適な相談先を選びましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
ビルメンテナンスのM&Aで新たな未来を切り拓こう

ビルメンテナンス業界は後継者問題、人手不足、競争激化という課題に加え、DX化や新たなニーズの発生といった変化の渦中にあります。
このような環境下で、M&Aは事業承継の有力な手段であり、企業が持続的成長と新たな未来を拓くための戦略的な選択肢です。
売り手には創業者利益の獲得や従業員の雇用維持、事業の安定化などが、買い手には事業エリア拡大や人材獲得、新規事業への参入などのメリットが期待できます。
デメリットやリスクもありますが、専門家と慎重に進めることで克服は可能です。
自社の現状と将来ビジョンを深く見据え、M&Aを真剣に検討することが重要です。
よくある質問

ビルメンテナンス業界のM&Aに関するよくある質問をまとめました。
Q1.ビルメンテナンス会社を売却する際、企業価値評価において有利に働く強みはありますか?
ビルメンテナンス会社のM&Aでは、安定収益を示す長期契約が重視され、とりわけ官公庁や大手企業との取引は信用力の面で有利です。
複数の優良顧客を持つことはリスク分散にもつながります。
さらに、清掃・警備・設備管理など特定分野での専門性やノウハウ、資格保有者やISO認証、省エネ・DX対応といった付加価値も企業価値を高める要素とされています。
Q2.中小規模のビルメンテナンス会社がM&Aによって大手グループの一員となる場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
大手グループに加わることで、ブランド力や信用力が高まり、大規模案件の受注チャンスが拡大します。
また、資材調達の効率化によるコスト削減に加え、最新の清掃ロボットや管理システムの導入、人材採用・定着における強化も期待できます。
大手の経営基盤を背景に法令遵守や安全管理のレベル向上が図れる点も、中小規模の企業では得にくいメリットといえるでしょう。
Q3.M&Aにより顧客との契約関係を承継する際に注意すべき点は何ですか?また、契約が打ち切られるリスクはないのでしょうか?
契約には経営権の移動を制限する『チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項』が含まれている場合があり、M&A時に取引先の事前承諾を求められることがあります。
条項がなくても、取引先が信用面の不安から契約を見直すケースはあり得ます。
特に主要顧客には、事前に契約内容の精査と丁寧な説明が不可欠です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










