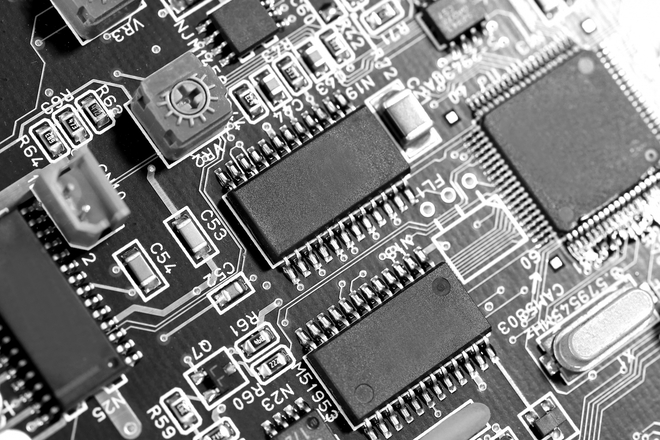自動車整備M&Aを成功させるポイント|事例と相場・相談先を解説

自動車整備業でM&Aや売却を検討しているものの、「何から始めればいいのか」「本当に自社を売却できるのか」と、踏み切れずにいる経営者は少なくありません。
しかし、業界再編が進む現在、自社で長年培ってきた独自の技術や顧客との信頼関係は、事業拡大を目指す他の企業にとって、獲得したい価値あるものとして映る可能性があります。
本記事では、自動車整備業界におけるM&Aの最新動向から、具体的な手続きの流れ、売却価格の相場、信頼できる相談先まで、成功の鍵となるポイントを事例を交えて解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
自動車整備業界の概要

自動車整備業界は、日本の自動車社会を支える基幹産業として私たちの生活に欠かせないインフラを支えている業種の一つです。日本自動車整備振興会連合会によると、業界全体の市場規模は約6兆2,561億円(2023年度実績)にものぼります。
主な事業内容は車検を中心とした「点検整備」、エンジンやブレーキを修理する「分解整備」、事故による損傷を修復する「板金塗装」などです。事業所の業態には分解整備を行う「認証工場」と、車検まで完結できる「指定工場」とがあります。
全国にはディーラー・自家(自社保有車両の整備業)を含む約9.2万もの整備事業場があり、その約8割が従業員10名未満の小規模な事業者で占められていることもこの業界の特徴です。自動車整備業界は地域に根差した中小企業が中心となり、国民の安全なカーライフを支えているのです。
中小企業M&Aとは?|動向や価格の決め方・事例をわかりやすく解説
(情報参照元:日本自動車整備振興会連合会「令和6年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について 」)
(情報参照元:国土交通省「自動車整備分野における人材確保に係る取組」)
自動車整備業界の現状と背景

ここでは、自動車整備業界の現状と、社会・経済的背景を解説します。
背景1.深刻化する後継者不在と経営者の高齢化
自動車整備業界では、深刻化する後継者不在と経営者の高齢化が大きな課題です。帝国データバンクが2024年に発表した調査結果によると、経営者が60歳以上の事業者が全体の57.0%を占め、後継者不在率は59.7%(2023年)にも及ぶことが明らかになりました。
さらに、多くの経営者が高齢で事業を譲りたいと考えても、親族や従業員の中に適任者が見つからないケースが増加しています。高い技術力や長年築いた優良な顧客基盤を持っていても、後継者がいないために廃業せざるをえない事業者も少なくありません。
(情報参照元:帝国データバンク「『自動車整備事業者』の倒産、休廃業・解散動向」)
背景2.EV・ADAS化などの技術革新の波
EV(電気自動車)やADAS(先進運転支援システム)化などの技術革新の波も、自動車整備業の経営に多大な影響を与えています。
近年の自動車整備には、従来のエンジン整備とは異なる専門知識や技術が求められるようになりました。特に、電子制御装置搭載車の整備に「特定整備認証」が必要とされたことで、事業者は設備や人材教育に対する新たな投資を迫られています。
技術革新に対応できなければ、新しい車種の入庫を断らざるをえず、仕事が先細りになることが予想されます。しかし個人経営や小規模な事業者にとっては、技術投資の負担が重く、事業継続を断念するケースもあるようです。
背景3.激化する人材獲得競争と熟練整備士の確保
激化する人材獲得競争と熟練整備士の確保も、業界に共通する深刻な課題です。
若者の車離れなどを背景に、自動車整備士の担い手は減少傾向にあり、新規人材採用は年々難しくなっています。2022年度の自動車整備士の有効求人倍率は5.02倍であり、2011年度の4倍以上にまで上昇している状況です。
その一方で、長年現場を支えてきた熟練整備士が高齢で引退するケースが増え、技術の継承が困難になっています。
人材不足により受注できる仕事の量が制限される中、採用コストや人件費が上昇していることも、小規模事業者の経営を圧迫する大きな要因です。
(情報参照元:帝国データバンク「『自動車整備事業者』の倒産、休廃業・解散動向」)
自動車整備業のM&A動向

先述した現状を受け、近年自動車整備業界では以下のような動機でM&Aが選択されるケースが増えています。
- 売り手側の動機:後継者問題の解決
- 買い手側の動機:商圏の拡大、サービス対応範囲の拡大
売り手側では経営者の高齢化に伴い、従業員の雇用と技術を守りつつ、自身も安心して引退できる手段としてM&Aを検討する企業が増えています。
一方、買い手側ではM&Aによって自社の商圏外に基盤を持つ企業を取得し、サービス提供エリアを拡大するケースが増加の傾向です。
また、中古車販売店や運送会社、リース会社といった周辺業種の企業が、提供サービス範囲を広げるために自動車整備工場を買収し、顧客の囲い込みを図る動きも目立っています。
自動車整備業界では売り手と買い手双方にM&Aのニーズが高く、小規模な地場企業であっても、独自の強みがあれば買い手が見つかりやすい傾向にあります。特に、優秀な整備士や「特定整備認証」を持つ事業者は、買い手から見て魅力的な存在です。
自動車整備業M&Aのメリット・デメリット
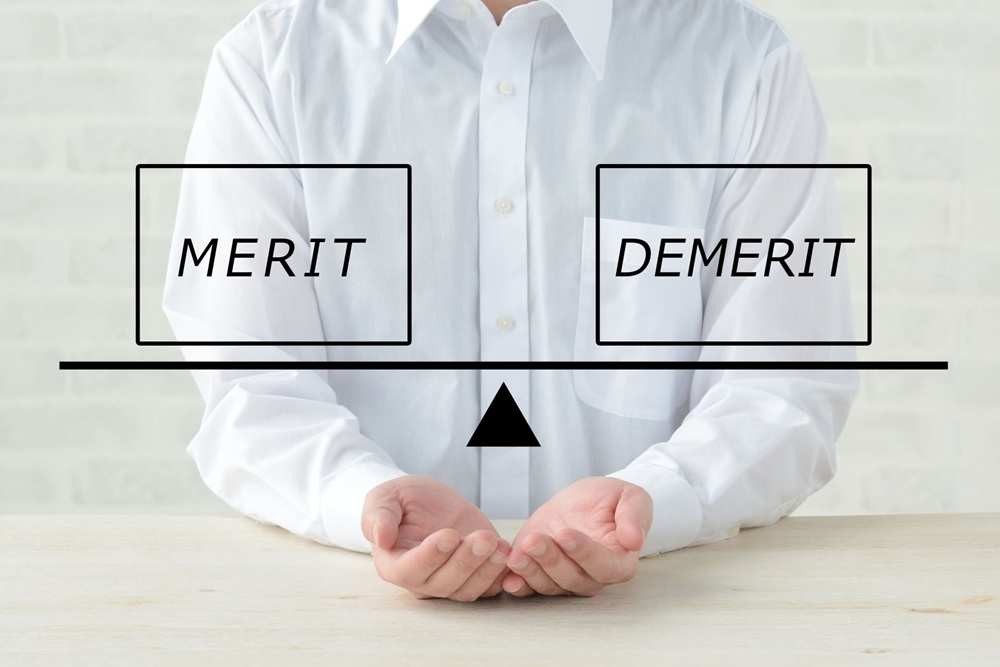 M&Aはさまざまな課題解決が期待できる一方で、慎重に検討すべき点もあります。
M&Aはさまざまな課題解決が期待できる一方で、慎重に検討すべき点もあります。
ここでは、自動車整備業界におけるM&Aのメリットとデメリット、注意点を解説します。
自動車整備業M&Aのメリット
自動車整備業におけるM&Aの最大の利点は、後継者不在問題を解決できる点です。親族や従業員に適切な後継者がいなくても、M&Aによって第三者に事業を承継できるため、長年築き上げてきた会社や技術を存続させられます。
廃業すれば従業員も職を失いますが、M&Aであれば従業員の雇用も維持できる可能性が高いです。また、会社を売却して創業者利益を確保できるため、経営者自身の引退後の生活設計も立てやすくなります。
さらに、資金力のある企業の傘下に入れば経営基盤が安定し、最新の設備を導入したり、新たな人材を確保しやすくなるなど、事業のさらなる発展も期待できます。
自動車整備業M&Aのデメリット
自動車整備業のM&Aにはデメリットや注意すべき点もあります。
M&Aでは、必ずしも希望する条件で売却できるとは限りません。自社の価値が想定より低く評価されるケースや、買い手が見つからないケースも想定する必要があります。
また、買い手企業の経営方針が従来と大きく異なる場合、M&A成立後に従業員の反発や退職を招くリスクもあります。同様に、長年の取引先との関係性が変化し、取引が縮小または停止される可能性もゼロではありません。
特にM&Aの交渉中に情報が外部に漏れてしまうと、従業員や取引先に過剰な不安を抱かせる原因となります。M&Aのリスクを適切に管理するためには、信頼できる専門家と連携し手続きを進めることが肝心です。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
自動車整備業M&Aにおける準備から成約までの6ステップ

自動車整備業のM&Aは、相談から最終契約まで半年から1年以上かかる長期のプロジェクトであり、プロセスの全体像を把握し、各段階で何をすべきか明確にしておく必要があります。
ここでは、M&Aのプロセスを6つのステップに分けて解説します。
- M&A仲介会社への相談と準備
- 買い手候補の選定(マッチング)
- 経営者同士のトップ面談
- 基本合意契約(MOU)の締結
- デューデリジェンス(買収監査)の実施
- 最終契約の締結と引き継ぎ(PMI)
ステップ1.M&A仲介会社への相談と準備
M&Aを成功させる最初のステップは、信頼できるM&A仲介会社に相談することです。
M&Aには多方面にわたる専門知識が必要なため、専門家による支援が欠かせません。自社の経営状況や課題、M&Aで実現したい成果について、早い段階から正確に伝えておくことで、適切な企業評価と最適なマッチングにつながります。
相談と並行して、自社の強みや弱みを客観的に分析し、決算書や試算表などの財務資料を整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。仲介会社と契約を結ぶ際には、情報漏洩を防ぐために秘密保持契約(NDA)を締結します。
ステップ2.買い手候補の選定(マッチング)
次のステップは買い手候補企業の選定です。
M&A仲介会社がリストアップしてくれた買い手候補に対し、「ノンネームシート(譲渡企業名を特定されない範囲で企業情報をまとめた資料)」を提示します。
そして関心を示した企業に対しては、秘密保持契約を締結したうえで、より詳細な企業情報(企業概要書:IM)を開示する流れです。
マッチングの精度がM&Aの成否を左右するため、交渉を進める相手を選定する際にはM&A仲介会社のアドバイスのもと、自社の事業とのシナジー効果や企業文化の親和性などを検討する必要があります。
ステップ3.経営者同士のトップ面談
次のステップでは、書類ではわからない経営者の人柄や経営理念、将来のビジョンなどを共有するために、経営者同士が直接対面する「トップ面談」が行われます。
売り手にとっては、自社の歴史や強み、従業員への想いを直接伝えることで、買い手側に理解を深めてもらう場となります。一方、買い手側は買収後の経営が円滑に進むか、また自社の文化と相性が良いかなどを判断することが一般的です。
トップ面談を通じてお互いが信頼関係を築き、双方がM&Aに対して前向きな合意を形成できることが理想的です。
ステップ4.基本合意契約(MOU)の締結
トップ面談でお互いの意思が固まったら、M&Aの基本的な条件をまとめた「基本合意契約(MOU)」を締結します。この契約には、現時点での譲渡価格の目安、M&Aのスケジュール、今後の交渉の進め方などが盛り込まれます。
基本合意契約では、譲渡価格など一部の項目には法的な拘束力を持たせません。ただし買い手に「独占交渉権」が付与され、基本合意締結後は売り手に他の買い手候補との交渉が認められなくなります。
ステップ5.デューデリジェンス(買収監査)の実施
基本合意契約の締結後、買い手側によって「デューデリジェンス(DD)」が実施されます。
デューデリジェンスとは、売り手企業の財務状況や法務上のリスク、事業内容などを詳細に調査する「買収監査」のことです。
買い手側はM&Aによって売り手の資産と潜在リスクの両方を負うことになるため、調査は弁護士や公認会計士などの専門家がチームを組み、数週間から2カ月程度かけて行われることが一般的です。
売り手側には、要求された資料を迅速・正確に開示するなどの協力が求められます。
ステップ6.最終契約の締結と引き継ぎ(PMI)
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終的な条件交渉を行い、双方が合意に至ると「最終契約書(SPA)」が締結され、M&Aが正式に成立します。
契約書には、最終的な譲渡価格、従業員の処遇、引き継ぎのスケジュールなどが詳細に定められ、各項目が法的拘束力を持つ点が基本合意との相違点です。
契約締結後は、M&A後の統合プロセス「PMI(Post Merger Integration)」が始まります。PMIは、買い手と売り手の経営方針や業務プロセス、企業文化などをすり合わせ、M&Aによるシナジー効果を最大化するための取り組みです。
M&AはPMIがスムーズに進み、期待したシナジーが得られて初めて成功と呼べるのです。
PMI(ポストマージャーインテグレーション)の重要性 – 株式会社M&Aフォース
自動車整備業M&Aにおける相場・売却価格の決まり方

自動車整備業のM&A売却価格には決まった相場はなく、通常は各社の状況に適した専門的な手法で評価し、最終的には買い手との交渉によって決まります。
まず、企業価値を評価する基本的な考え方と、自動車整備業ならではの評価ポイントを理解しておきましょう。
企業価値評価における3つの基本的手法
企業の売却価格を算出する際には、まず客観的な企業価値評価(バリュエーション)が行われます。評価の際のアプローチは以下の3種類に分類されますが、実際には複数のアプローチ手法を組み合わせて、多角的に企業価値を評価することが一般的です。
【コストアプローチ】
貸借対照表の純資産額を基準に企業価値を評価するアプローチです。
会社の資産から負債を差し引いた純資産をベースにするため、計算が比較的シンプルで客観性が高いのが特徴です。
中小企業のM&Aではコストアプローチを採用することが一般的です。
【マーケットアプローチ】
評価する会社と事業内容が類似する上場企業や、過去のM&A事例などと比較して価値を算出する方法です。
市場での取引価格を参照するため、客観的な評価手法といえますが、事業の特殊性によっては、自社と類似性の高い企業を見つけにくいケースがあります。
【インカムアプローチ】
会社が将来生み出すと予測される収益(キャッシュフロー)を基に企業価値を評価する方法です。
企業の将来性や収益力を評価に反映できるため、成長性の高い企業の評価に適しています。
M&Aの企業価値評価とは?基本的な算出方法と売り手・買い手のポイントを解説【2025年最新】
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
自動車整備業独自の評価ポイント
一般的な企業価値評価に加えて、自動車整備業者としての独自の強みが評価され、売却価格に上乗せされることがあります。財務諸表には表れない「のれん代」と呼ばれるものです。
業界特有の主な評価ポイントには以下のものがあります。
| 評価されるポイント | 具体例 |
| 認証・指定工場の許認可 |
|
| 優秀な整備士と組織力 |
|
| 安定した顧客基盤 |
|
| 優良な立地と設備 |
|
| 独自の技術やノウハウ |
|
自動車整備業界(中小企業)のM&A事例

ここでは、M&Aの具体的なイメージをつかめるよう、中小企業のM&A事例を5つ紹介します。
和寒自動車工業 × 北のふるさと事業承継支援ファンド(株式譲渡による完全子会社化)
北海道の地域密着型の自動車整備業者である和寒自動車工業に対し、地域企業の事業承継を支援する「北のふるさと事業承継支援ファンド」が全株式を取得し、完全子会社化した事例です。
後継者が株式を買い取れるまでの間、同ファンドが一時的に株式を保有することで、事業運営の継続を図る仕組みです。
親族以外への事業承継を検討している地方の中小企業にとって、この事例は地域企業向けの公的ファンドがM&Aの有力な選択肢となり得ることを示唆しています。
| 実施日 | 2021年8月20日 |
| 譲渡企業 | 有限会社和寒自動車工業(北海道) |
| 譲受企業 | 北のふるさと事業承継支援ファンド(北海道) |
| スキーム | 株式譲渡 |
(情報参照元:北海道中小企業総合支援センター「『北のふるさと事業承継支援ファンド』投資先の決定について」)
福丸自動車工業 × 西和物流(異業種の資本業務提携)
大阪府で民間車検工場を営む福丸自動車工業が、関西圏を中心に物流業を営む西和物流と資本業務提携を結んだ事例です。
福丸自動車工業は小規模ながら、大型特殊車両にも対応できる民間車検工場としての高い技術力を有しています。この提携により、福丸自動車工業は経営基盤を強化でき、西和物流は自社車両の整備を内製化することで、大きなシナジー効果を実現しています。
| 実施日 | 2021年8月17日 |
| 譲渡企業 | 福丸自動車工業株式会社(兵庫県) |
| 譲受企業 | 西和物流株式会社(奈良県) |
| スキーム | 資本業務提携 |
(情報参照元:西和物流株式会社「福丸自動車工業との資本提携について」)
デルオート × SPK(株式譲渡による完全子会社化)
トランスミッションの修理やリビルト品(再生部品)の提供に強みを持つデルオートが、自動車部品の企画・販売を手がけるSPKの完全子会社となった事例です。
SPKは、リビルトニーズに応えるラインナップの強化を検討しており、デルオートが持つ高いリビルトの技術力がSPKの事業拡大戦略の要件と一致したことで、株式取得を決定しました。
このM&Aによって、デルオートはSPKの持つ広い販売網を獲得し、SPKは顧客へのサービス提供範囲の拡大に成功しています。
| 実施日 | 2021年12月22日 |
| 譲渡企業 | 株式会社デルオート(神奈川県) |
| 譲受企業 | SPK株式会社(大阪府) |
| スキーム | 株式譲渡 |
(情報参照元:SPK株式会社「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 」)
高森自動車整備工業 × オートバックスセブン(株式譲渡による完全子会社化)
三重県で地域に密着した自動車整備事業を展開していた高森自動車整備工業が、カー用品最大手のオートバックスセブンの完全子会社となった事例です。
オートバックスセブンは、EVや先進運転支援システム(ADAS)などの次世代技術に対応できる整備ネットワークの構築を重要戦略に掲げていました。そこで地域に根付いた高森自動車整備工業の整備工場網の獲得に乗り出したのです。
このM&Aで、高森自動車整備工業は大手資本による安定した経営を実現し、オートバックスセブンは整備ネットワークの拡大と新たな顧客層の獲得に成功しています。
| 実施日 | 2020年4月1日 |
| 譲渡企業 | 高森自動車整備工業株式会社(三重県) |
| 譲受企業 | 株式会社オートバックスセブン(東京都) |
| スキーム | 株式譲渡 |
(情報参照元:株式会社オートバックスセブン「高森自動車整備工業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」)
旭自動車工業 × ONE&PEACE(資本業務提携)
新潟市で約60年の歴史を持つ旭自動車工業が、同地域で中古車の買取・販売を手がけるONE&PEACEと資本業務提携を結んだ事例です。
旭自動車工業は、指定工場としての高い整備技術力と、地域に根ざした顧客対応力が強みであり、一方のONE&PEACEは県内に複数の販売網を持っていることが強みです。
旭自動車工業の整備技術とONE&PEACEの販売力を掛け合わせることで、両社は販売からアフターフォローまで一貫したサービスを実現しました。
| 実施日 | 2021年6月 |
| 譲渡企業 | 旭自動車工業株式会社(北海道) |
| 譲受企業 | 株式会社ONE&PEACE(新潟県) |
| スキーム | 資本業務提携 |
(情報参照元:株式会社ONE&PEACE「旭自動車工業株式会社との資本業務提携のお知らせ」)
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
自動車整備業のM&Aを成功させるポイント
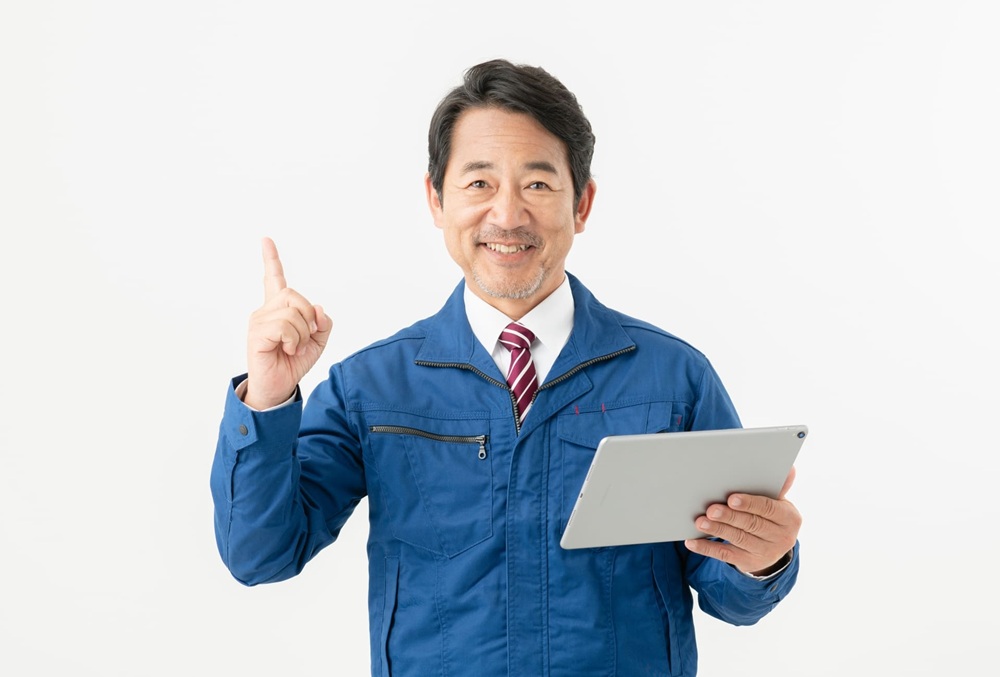
自動車整備業のM&Aを成功に導くためには、押さえておくべきポイントがあります。これから紹介する5つのポイントに留意し、納得のいく形で会社を次世代へ引き継ぎましょう。
情報開示のタイミングに留意する
M&Aの仮定においては、情報開示のタイミングに留意する必要があります。
M&Aを検討している事実は、最終契約が締結されるまで従業員や取引先には伝えないことが原則です。早い段階で情報が漏洩すると、経営不安の憶測を呼び、従業員のモチベーション低下や離職につながる恐れがあります。
また、取引先や金融機関との関係性が悪化し、M&A交渉の妨げになる可能性も否定できません。
不確定な情報で関係者を混乱させないためにも、M&Aの専門家と相談のうえ、慎重に情報開示のタイミングを見計らうことが大切です。
財務の透明性を確保する
買い手から信頼を得るためには、会社の財務状況を正確かつ透明性の高い状態で開示することが不可欠です。
デューデリジェンスで帳簿に記載のない負債(簿外債務)や、経営者個人の支出と思われる不明瞭な会計などが判明すると、自社の信頼性が損なわれ、売却価格が大幅に引き下げられたり、交渉自体が破談になったりすることもあります。
日頃から税理士と連携し明瞭な会計処理を心がけましょう。
得られるシナジー効果を明確にする
両社が提携することで生まれる相乗効果(シナジー)を具体的に示すことができれば、M&Aの成功確率は高まります。買い手は、M&Aによって自社の事業がさらに成長することを期待しているからです。
「指定工場の資格×広い販売網=車検の受注アップ」のように、両社の強みを掛け合わせることで生まれるメリットを明確に伝えましょう。
自社の強みや企業価値を適正に評価する
納得の行く条件でM&Aを成立させるためには、自社の強みを客観的に把握し、価値を正しく評価することが不可欠です。
売却価格は財務データだけでなく、数字に表れない「のれん代(無形資産)」も加味して算出されます。長年培った地域住民からの厚い信頼や特定分野の技術力、年代のバランスの良い人材構成といった強みも、買い手に高く評価される企業価値の一例です。
自社の強みを整理し、説得力のある形でアピールすることが、より良い条件での売却につながります。
M&Aの専門家に相談する
自動車整備業のM&Aを成功させるには、経験豊富な専門家のサポートを得ることがもっとも近道です。
M&Aの手続きには法務や税務、会計といった多岐にわたる専門知識が求められるため、経営者一人で進めることは現実的ではありません。
M&A仲介会社などの専門家は、幅広いネットワークを活かした買い手候補の選定から、適正な企業価値の算定、条件交渉、契約書の作成まで一貫して支援してくれます。
特に、自動車整備業界に精通する専門家であれば、企業独自の価値を正しく評価でき、シナジーを生むマッチングの実現が期待できます。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →自動車整備業M&Aの相談先

M&Aの相談先の選定は企業の将来を左右する重要な選択です。
ここでは、主な相談先を5つ紹介します。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択しましょう。
税理士や会計事務所
日頃から会社の経営状況を相談している顧問税理士や会計事務所は、最も身近な相談先の一つです。自社の財務状況を深く理解しているため、M&Aの進め方について財務的な観点から的確なアドバイスが期待できます。
ただし、税務や会計の専門性は高くても、すべての税理士がM&Aに精通しているとは限りません。M&Aの相手探しや交渉は得意としていない可能性もあるので、財務面でのセカンドオピニオンや、M&A専門家への橋渡し役として活用することが推奨されます。
地元の金融機関
メインバンクとして付き合いのある地元の銀行や信用金庫も、相談しやすい専門機関の一つです。
地域経済に精通する金融機関では、取引先企業の中から買い手候補を紹介してもらえる可能性があります。また、M&Aに必要な資金の調達方法について相談に乗ってもらえる点もメリットです。
一方で、金融機関のM&A部門が担当するのは大規模な案件が中心で、中小企業のM&Aについては提携する仲介会社を紹介するケースが多い傾向にあります。
また、買い手も同じ金融機関の顧客である場合に、依頼者である売り手の利益より、将来にわたって取引先となる買い手の利益が優先される(利益相反)可能性がある点にも注意が必要です。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業の事業承継を支援するために、国が全国47都道府県48カ所に設置している公的な相談窓口です。原則無料で利用でき、中立的な立場で相談に乗ってくれる点がメリットです。
センターの専門家からアドバイスを受けられるほか、「後継者人材バンク」という仕組みを通じて譲渡先を探すことも可能です。ただし、センター自体が直接M&Aの仲介を行うわけではないため、相手方との条件交渉や質問事項のやり取りには対応していません。
民間のM&A仲介会社や士業などの専門家へ橋渡しすることが事業承継・引継ぎ支援センターの主な役割です。
(情報参照元:「東京都事業承継・引継ぎ支援センター」)
FA(ファイナンシャルアドバイザー)
FA(ファイナンシャルアドバイザー)は、売り手か買い手いずれかと契約し、依頼主の利益を最大化するために動く専門家です。
M&A仲介会社が中立的な立場を取るのに対し、FAは依頼者の利益を優先して交渉を進めてくれる点が両者の違いです。 売り手の専属アドバイザーであれば、少しでも良い条件で売却できるよう、交渉戦略の立案から実行まで尽力してくれます。
ただし、相手方もFAを立てている場合には、交渉が複雑化したり決裂したりする可能性がある点がデメリットです。そのため、友好的なM&Aを実施したい場合には、FA以外へ依頼することが推奨されます。
FAは一般に株主への配慮が必要な大手上場企業同士や、クロスボーダーM&A(海外企業とのM&A)で多く利用される手法です。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立って中立的な立場で交渉をまとめる会社です。M&Aに特化した豊富なM&Aの専門知識や経験、交渉ノウハウを持ち、独自のネットワークを活かして幅広い候補先からもっとも条件に見合う相手を探してくれます。
相談から相手探し、交渉、契約書の作成まで、M&Aの全プロセスを一貫してサポートしてもらえることが最大のメリットです。相手先との交渉や複雑な手続きに伴走してくれるので、中小企業にとってはもっとも相談しやすい依頼先といえるでしょう。
M&A仲介会社とは?FAとの違いや選び方・メリットを徹底解説
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →自動車整備業のM&Aに仲介会社を使うメリット

最後に、自動車整備業のM&Aに仲介会社を使うメリットを3つ紹介します。
M&Aに特化した専門的なアドバイスを得られる
M&A仲介会社に依頼するメリットの一つは、M&Aに特化した専門的なアドバイスを得られる点です。
M&Aのプロセスには、適正な企業価値の算定や法務・税務に関する高度な知識が求められますが、すべてにワンストップで対応できる仲介会社なら安心して業務を託せます。
さらに、豊富なM&Aサポート経験をもとに、売却価格や従業員の処遇といった条件交渉を有利に進めるための戦略的なアドバイスも期待できます。
自動車整備業界に精通した仲介会社であれば許認可や熟練整備士の技術力といった、財務諸表に表れない自社の強みも適正に評価してくれるでしょう。
幅広く買い手候補から納得いく企業を探せる
幅広い買い手候補から納得のいく企業を探せることも、M&A仲介会社ならではのメリットです。
自社の将来を託すのにふさわしい相手を、経営者個人の人脈だけで見つけることは困難です。一方、全国規模のネットワークやデータベースを持つM&A仲介会社であれば、同業他社やシナジー効果を見込める異業種企業まで、多様な候補先をリストアップできます。
依頼者は複数の候補を比較検討できるため、その中から自社の企業文化を理解し、従業員の雇用を守ってくれる最良のパートナーと出会える可能性が高まります。
交渉や調整、手続きまで一貫して任せられる
交渉や調整、手続きまで一貫して任せられる点もM&A仲介会社のメリットです。
M&Aの交渉には精神的な負担を伴う場面も少なくありませんが、仲介会社が間に立つことで、相手方に直接伝えにくい希望条件なども、客観的かつ的確に伝えられます。
また、基本合意契約や最終契約といった書類の作成、デューデリジェンスへの対応など、煩雑で専門的な手続きも全面的にサポートしてもらえるため、経営者はM&Aの重要な意思決定に専念できます。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →自動車整備業のM&A成功には、早めの準備と信頼できるパートナー選びを
 自動車整備業界は、後継者不足や競争激化、EV化などにより大きな転換期を迎えています。見通しの立ちにくい環境の中、長年築いてきた会社と従業員の雇用を次世代へつなぐ、有効な事業承継の手段がM&Aです。
自動車整備業界は、後継者不足や競争激化、EV化などにより大きな転換期を迎えています。見通しの立ちにくい環境の中、長年築いてきた会社と従業員の雇用を次世代へつなぐ、有効な事業承継の手段がM&Aです。
M&Aの成功には、自社の強みを客観的に評価し、早期に準備に着手することが欠かせません。複雑な交渉や手続きを一貫してサポートしてくれて、信頼できるパートナーを選ぶことが成功への近道です。
最良のパートナーとタッグを組んで大切な事業を納得のいく形で承継し、最大限のシナジー効果を実現しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)