食品卸業界M&A完全ガイド|動向と事例・相場・注意点を解説

近年、食品卸業界では後継者不在や激化する価格競争、物流コスト上昇を背景に、M&Aによる業界再編が加速しています。
M&Aは自社の事業承継や事業拡大の有効な切り札にもなり得ます。しかし「雇用や取引を維持できるのか」「本当に自社を売却できるのか」と、M&A実施に踏み切れずにいる経営者も多いのではないでしょうか。
本記事では、M&Aの最新動向から売却相場、具体的なM&A事例と実施の流れを網羅的に解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
食品卸業界の現状

食品卸売業はメーカーと小売業の間に位置し、生産者と消費者をつなぐ食品流通の中核を担う業種です。しかし、その経営環境は年々厳しさを増しており、多くの企業が変革を迫られている状況です。まずは、業界の全体像を把握していきましょう。
食品卸業界の定義
食品卸売業とは、食品メーカーなどから商品を仕入れ、小売業者や飲食店、ホテル、病院などに販売(卸売り)する事業を指します。日本標準産業分類における「農畜産物・水産物卸売業」と「食料・飲料卸売業」がこれに該当します。
メーカーから直接仕入れる「一次卸」、一次卸から仕入れる「二次卸」など、多層構造の産業形態が特徴です。
| 階層 | 役割 | 主なプレイヤーの例 |
| 一次卸 | メーカーから直接商品を仕入れ、二次卸や大規模小売チェーンに販売します。 | 国分グループ本社、三菱食品、日本アクセスなど |
| 二次卸 | 一次卸から商品を仕入れ、地域の中小小売店や飲食店に販売します。 | 地域の専門卸、地方卸売市場の仲卸など |
| 地方卸 | 特定地域に特化し、地元の特産品などを扱います。 | 各都道府県の地場卸など |
現在の食品卸売業の業態は、単なる中間流通業者にとどまらず、商流と物流の効率化を推進する重要な役割も担っています。
たとえば、スケールメリットを活かして複数メーカーの物流を一括で代行したり、豊富な市場情報を基に小売業者に品揃えのアドバイスをしたりする企業も少なくありません。小売業者の決済業務を代行することもあり、メーカー・小売業者双方の負担軽減にも貢献しています。
このように、小売店の代理機能や物流機能、情報提供や経営支援など、多様な機能を提供しているのが現在の食品卸業界です。
【飲食店M&A】事例から学ぶ売却・買収のすべて|相場・流れ・注意点を徹底解説
業界の市場規模
経済産業省の「商業動態統計」によると、2024年度の食品卸業界の市場規模(年間販売額)は合計で約111.2兆円に達し、現在も拡大傾向にあります。
- 農畜産物・水産物卸売業: 約44.6兆円(対前年度比約8.6%増)
- 食料・飲料卸売業: 約66.7兆円(対前年度比約3.5%増)
ただし、販売額の上昇にはメーカーによる商品価格の値上げが影響しており、市場全体が好調であるとは一概には言えません。大手企業による寡占化が進む中で、多くの中小卸売業者は厳しい価格競争やコスト増加に直面しているのが実情です。
特別な許認可が不要で参入障壁が低いことから、大手メーカーや小売業など異業種からの参入が進み、販売額ベースでの市場規模は今後も拡大すると予測されます。一方で、人口減少による国内市場の縮小が予想される中、海外市場への進出を図る動きも見られる現状です。
食品卸業界の課題

多くの食品卸企業が、共通の課題を抱えています。これらの課題が、M&Aを検討する直接的な動機となるケースが少なくありません。
| 課題カテゴリ | 具体的な内容 | 経営への影響 |
| 事業承継 | 経営者が高齢化したが、親族や社内に適切な後継者が不在 | 優れた事業内容であっても廃業せざるを得ないリスクが増大 |
| 競争環境 | 大手による寡占化が進んだことによる厳しい価格競争 | 利益率が低下し、独自の強みを打ち出すことが困難に |
| コスト構造 | 燃料費高騰による物流コストや人件費が増加の一途 | 収益性を直接圧迫し、価格への転嫁も困難 |
| 流通構造 | 大手小売業者が卸を通さず直接メーカーと取引する「中抜き」の増加 | 卸売業の介在価値が問われ、取引が減少する可能性 |
後継者不足と事業承継問題
中小企業において、後継者不足による事業承継問題は年々深刻化しており、食品卸業界においても例外ではありません。
特に家族経営の企業では、経営者が高齢になっても後継者が見つからないケースが少なくありません。経営者が引退を考えても事業の承継者がいなければ、長年かけて築いた会社を清算せざるを得なくなり、廃業を選択するケースが増加傾向にあります。
大手による寡占化と価格競争の激化
大手企業による寡占化や、それに伴う価格競争の激化も、食品卸業界の経営を圧迫する要因です。
2011年頃から本格化した業界再編により、日本アクセスや三菱食品といった大手企業が市場シェアを拡大する傾向が顕著となりました。
これらの大手企業は「規模の経済」を活かし、低価格での供給や幅広い品揃えを実現しています。その一方で、中小の卸売業者は厳しい価格競争にさらされ、利益の確保が困難な状況です。
また、一部の大手小売業者がメーカーや元卸業者から直接仕入れる「中抜き」によって流通経路を短縮化する動きもあり、価格競争をさらに激化させています。
物流コストの上昇と利益率の低下
トラックドライバー不足や燃料価格の高騰による物流コストの上昇は、近年の業界環境を象徴する課題です。食品卸売業はもともと原価率が高く、薄利多売になりやすいビジネスモデルのため、物流コストの上昇は経営を直接圧迫する要因となっています。
M&Aによって物流網を統合・効率化し、コスト削減を図る動きも見られますが、資金力の乏しい中小企業にとって、その実行は容易ではないのが実情です。在庫管理にかかるコストも軽視できない問題といえるでしょう。
食品卸業界におけるM&A動向

食品卸業界が抱える課題を背景に、M&Aによる業界再編が加速しています。M&Aのパターンは、主に以下の3つに分類されます。
- 同業種同士のM&A
- 隣接業種による買収
- 後継者問題の解消
同業種同士のM&A
食品卸業界で特に多く見られるM&Aは、同業種間で行われるものです。この業界では規模の経済が働きやすく、事業規模が大きくなるほど一つの商品あたりの配送コストや管理コストの削減につながります。
そのため、取扱商品の拡充や配送エリアの拡大を通じて経営基盤を強化し、競争力を高めることを目的としたM&Aが活発に行われる傾向にあります。
隣接業種による買収
食品メーカーや物流会社など、隣接する業種の企業が食品卸売業者を買収するケースも増加しています。
メーカーが食品卸売業者とM&Aを実施すれば販売チャネルの確保につながり、物流会社にとっては事業領域の拡大にもつながります。サプライチェーン全体の効率化といったシナジー効果も期待できることから、隣接業種とのM&Aを選択する企業は増加の傾向です。
食品製造業のM&A|事例でわかる価格相場と成功のポイント【2025年最新版】
後継者問題の解消
後継者が見つからない中小の食品卸売業者が、事業承継を目的として会社を売却するケースも少なくありません。
廃業すれば従業員の解雇は避けられませんが、M&Aを実施すれば従業員の雇用や取引先との関係を維持しつつ、事業を存続させられます。
後継者問題は今後ますます深刻化すると予測されており、その解決策としてM&Aへの期待が高まっています。
食品卸業界におけるM&Aのメリット

M&Aは、会社を売却する「売り手」と買収する「買い手」、双方にメリットをもたらします。それぞれの立場から見た主なメリットを整理しました。
| 売り手(譲渡側)のメリット | 買い手(譲受側)のメリット | |
| 経営課題 | 長年の後継者問題を解決できる | 新規事業や未進出エリアへ迅速に参入できる |
| 財務 | 創業者利益を獲得し、借入金の個人保証からも解放される | 事業規模の拡大により、仕入れや物流のコストを削減できる |
| 事業 | 大手の傘下に入ることで、経営基盤が安定する | 新たな販路や顧客基盤、ブランドを獲得できる |
| 人材 | 大切な従業員の雇用を維持できる | 経験豊富な人材や業界のノウハウを一括で獲得できる |
| その他 | 地域社会に必要な事業を存続させ、社会貢献につながる | 既存事業との相乗効果(シナジー)を創出できる |
売り手のメリット
売り手にとっての最大のメリットは、後継者不在という経営課題を解消し、築き上げた事業を次世代へ承継できる点です。
さらに従業員の雇用や取引先との関係も維持できるため、関係者全員にとって良い結果となる可能性を秘めています。大手企業の傘下に入れば経営基盤が安定し、従業員の処遇改善や新規事業投資も可能になるでしょう。
経営者自身にとっては、会社の売却で得た対価を引退後の生活資金に充てられ、さらに金融機関の個人保証からも解放されることが大きなメリットです。
買い手のメリット
買い手にとっての最大のメリットは、新規の事業基盤や商材、ブランドやノウハウ、経験豊富な人材を一度に獲得できる点です。
売り手企業の事業を引き継げば、ゼロから新規事業を立ち上げて未開拓のエリアに進出したり、人材を育成したりする時間とコスト、手間を大幅に削減できます。
さらに、既存事業と買収した事業を組み合わせることで、新たな価値を生み出すシナジー効果も期待できます。事業規模が拡大すれば、物流や仕入れの効率化が進み、コスト削減も見込めるでしょう。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
食品卸業界におけるM&Aのデメリット
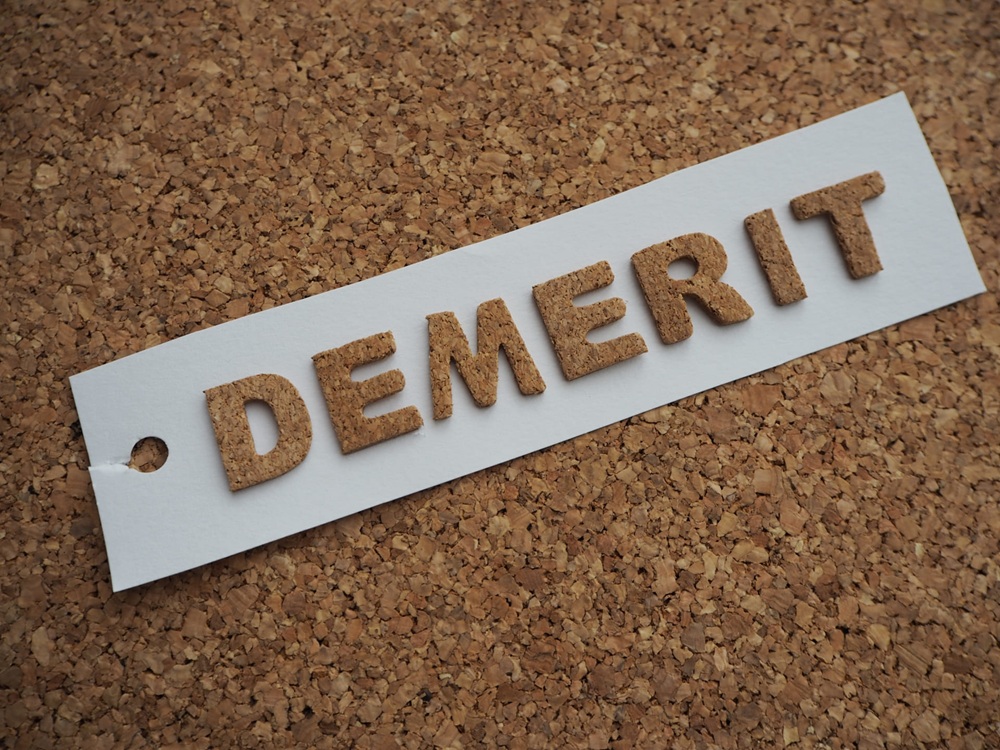
多くのメリットがある一方で、M&Aには注意すべきデメリットやリスクも存在します。事前にリスクを理解し、対策を講じることがM&Aを成功させる鍵です。
| 対象 | デメリット・リスク | 主な対策 |
| 売り手 | 希望する価格や条件で売却できるとは限らない | 企業価値を高める努力を重ね、業界動向を見極めて最適な時期に売却 |
| 売り手 | M&Aの情報が漏洩し、従業員や取引先が動揺する可能性がある | 秘密保持契約を締結し、情報開示は慎重に段階的に行う |
| 買い手 | 帳簿に記載のない債務(簿外債務)を引き継いでしまうリスクがある | 弁護士や会計士によるデューデリジェンス(買収監査)を徹底する |
| 買い手 | M&A後の統合プロセス(PMI)が計画通りに進まない可能性がある | 事前に入念な統合計画を立て、丁寧なコミュニケーションを心がける |
| 双方 | 両社の企業文化が異なり、従業員間の対立や離職につながるリスクがある | トップ面談などを通じて、お互いの価値観や文化を深く理解し合う |
売り手のデメリット
売り手にとってのM&Aのデメリットの一つは、必ずしも希望通りの価格や条件で売却できるとは限らない点です。交渉の過程で相手企業の要件に適合させる必要が生じたり、財務状況によっては買い手が見つからなかったりする可能性も考えられます。
オーナー経営者の場合には、M&A後に経営の自由度が低下し、従来通りの裁量を発揮できない可能性もあるでしょう。
もう一つのデメリットは、M&Aの情報が社内外に漏洩した場合、従業員や取引先に動揺を与えるおそれがある点です。M&Aが原因でキーパーソンが離職したり取引が打ち切られたりすれば、企業価値の減損にもつながりかねないため、情報管理には細心の注意が必要です。
買い手のデメリット
買い手側にとってM&Aの最大のリスクは、買収した会社に想定外の問題が隠されている可能性があることです。「簿外債務」と呼ばれる、帳簿には記載されていない借金や将来発生しうる損害賠償などが見つかった場合、事業統合後に経営が悪化する恐れがあります。
また、M&A後の統合プロセス(PMI)が円滑に進まず、期待したシナジー効果を得られない可能性も否定できません。特に、M&Aが原因で売り手側の優秀な人材が流出してしまった場合、事業計画の見直しが必要になることもあるでしょう。
入念な統合計画を立て、売り手と密なコミュニケーションを図ることが必須です。
食品卸業界M&Aの売却相場と価格算定方法
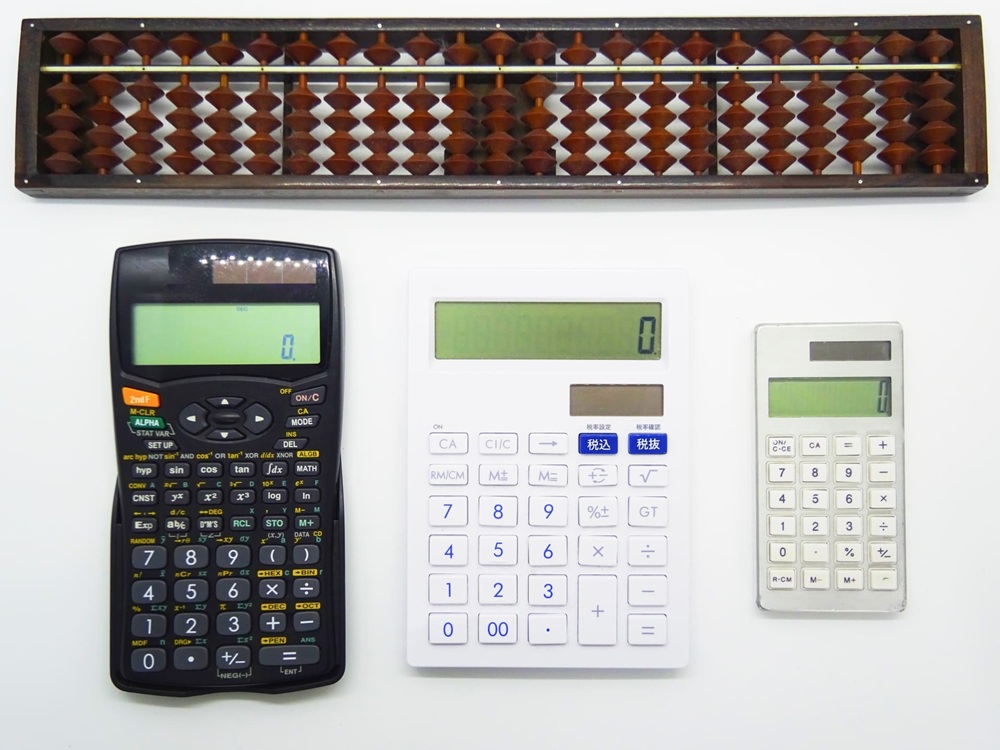
自社がいくらで売れるのかは、経営者にとって最大の関心事の一つでしょう。M&Aにおける会社の価格(企業価値)は、さまざまな方法を組み合わせて算出されます。ここでは代表的な算定方法を紹介します。
時価純資産+営業利益から算出する方法
一つ目は「年買法(年倍法) 」と呼ばれる算出法です。比較的シンプルな計算方法として中小企業のM&Aで広く用いられています。
会社の純資産(資産から負債を引いた額)を現在の価値で評価し直した「時価純資産」に、数年分の営業利益を加えて企業価値を算出します。
企業価値 = 時価純資産 + 直近年度の営業利益 × 3~5年分
営業利益の何年分を上乗せするか(倍率)は、会社の将来性や業界動向によって変動しますが、おおむね3~5年が目安です。
バリュエーションに基づき算出する方法
もう一つの算出方法は、専門的なアプローチで会社の価値を評価する「バリュエーション」です。
バリュエーションには主に以下の3つのアプローチがあり、これらを組み合わせて総合的に企業価値を判断するのが一般的です。
| 評価アプローチ | 概要 | メリット | デメリット |
| コストアプローチ | 会社の純資産価値に着目(時価純資産法など) | 客観性が高く、算出が比較的容易 | 会社の将来の収益性を直接反映できない |
| マーケットアプローチ | 類似する上場企業の株価やM&A事例に着目(類似会社比較法など) | 市場での評価を反映でき、客観性も高い | 比較対象として適切な類似企業が見つからない場合がある |
| インカムアプローチ | 会社が将来生み出すキャッシュフローに着目(DCF法など) | 事業計画などの将来性を価格に反映できる | 将来予測の精度に結果が大きく左右される |
これらの評価額を基準としながらも、最終的な売却価格は買い手との交渉によって決定されます。独自の販路やブランド力、優秀な人材といった、財務諸表には表れない「無形の資産」も価格を左右する重要な要素となります。
M&Aの企業価値評価とは?基本的な算出方法と売り手・買い手のポイントを解説【2025年最新】
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
食品卸業界におけるM&Aの注意点と対策

M&Aを成功に導くために、契約締結前後の各プロセスで注意すべき点を、売り手と買い手それぞれの立場で解説します。
売り手の注意点
売り手は、ただ待っているだけでは好条件でのM&Aは実現しません。最適な相手を見つけるためには、主体的に以下のアクションを起こすことが必要です。
M&Aの目的を明確にする
まず、なぜM&Aを行うのか、目的を明確にすることから始める必要があります。「後継者問題の解決」「事業のさらなる成長」「従業員の雇用維持」など、目的によって優先すべき条件や選択すべき相手は変わってくるためです。
目的が不明確なまま見切り発車すると、交渉の軸がブレて不要な工程やコストが発生したり、相手企業との摩擦が生じたりするおそれがあります。
M&Aを検討する段階から、得たい成果と利益について明確な目標を立てておきましょう。
自社の強みを明確にする
希望の条件で事業を売却するためには、自社の強みや魅力を明確にし、買い手に対して効果的にアピールしなくてはなりません。
自社の強みは企業価値に上乗せされる「無形資産」として評価され、より良い条件を引き出す交渉材料となります。
一例として「特定の地域での高いシェア」「独自の仕入れルート」「長年の取引先との強い信頼関係」などが挙げられます。強みを整理し客観的な資料としてまとめておきましょう。
早期から計画的に準備を進める
戦略立案などのM&Aの準備は、早期から計画的に進めることが必要です。
M&Aは、検討を開始してから成立するまで1年以上かかることも珍しくありません。引退する予定の時期から逆算するなど、余裕を持ったスケジュールで計画的に進めることで、M&Aに成功する確率を高められます。
また、財務状況が悪化してからでは売却価格が低く抑えられ、M&Aの成功率も下がってしまうため、会社の業績が良いタイミングで準備を始めるのが理想的です。
M&A専門家にサポートを依頼する
売り手企業は早い段階でM&A専門家にサポートを依頼することも大切です。
M&Aには、法務や税務、会計といった高度な専門知識が不可欠なため、社内に専門の担当者がいない場合に、経営者がすべてを抱え込むのは現実的ではありません。早い段階で経験豊富なM&A仲介会社などの専門家に相談することが、スムーズで安全な取引につながります。
また、企業価値を適正に評価するためのサポートも受けられるため、希望に近い条件で売却できる可能性も高まります。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →買い手の注意点
買い手は、M&Aによって予期せぬリスクを抱え込まないよう、以下のポイントに留意して買収対象の企業を多角的に分析し、将来性を冷静に見極める必要があります。
業界特有のルールを把握する
業界や売り手企業特有のルールがあるか、事前のリサーチやヒアリングを通じて調査し、ある場合はその内容を把握することも重要です。
食品卸業界には歴史の長い企業が多く、長年の商慣習や地域特有のルールが存在する場合があります。こうした暗黙のルールを理解せずに事業を引き継ぐと、取引先や従業員との関係が悪化してM&Aに失敗したり、期待するシナジーを得られなかったりする可能性があります。
特に異業種から参入する場合は、財務諸表に表れない文化的背景や商習慣への理解が不可欠です。
徹底したデューデリジェンスでリスクを洗い出す
企業の買収前には、デューデリジェンス(買収監査)を徹底し、リスクを洗い出すことが不可欠です。
簿外債務や未払い残業代といった隠れたリスクを見逃して契約に至ると、M&A後に訴訟問題に発展したり、事業収益が悪化したりする恐れがあります。最終契約を結ぶ前に、財務や法務、事業内容などを専門家が調査し、潜在リスクをクリアにしましょう。
調査結果によっては、契約条件の見直しや交渉の中止も視野に入れる必要があります。
取引の継続や特約の有無をチェックする
売り手企業の取引状況や特約の有無をチェックすることも必要です。
食品卸業界においては、代表者個人の信頼関係に依存する取引も少なくありません。売り手企業の主要な取引の前提が経営者への信頼にある場合、M&Aで経営者が変わると取引の継続を断られる可能性があるため、取引の継続可能性を把握しておく必要があります。
また、契約に一定期間の最低購入数量などを定めた特約がある場合、柔軟な取引が制限され、想定外の固定費支出が発生する可能性があります。契約内容を確認し、特約がある場合は自社で対応できる内容かどうか精査することが重要です。
食品卸業界M&Aの事例

近年、食品卸業界ではM&Aが活発に行われています。ここでは、近年の代表的な事例をいくつか紹介します。
事例1【同業種M&A】マルイチ産商 × ダイニチ(養殖事業強化)
2024年、水産物に強みを持つ食品卸のマルイチ産商が、養殖事業を手がけるダイニチを子会社化しました。
マルイチ産商は、従来の集荷・販売中心のビジネスから、より利益率の高い生産事業への本格的な進出を計画していました。そこで優れた養殖技術と数々の認証、国内外の販路を持つダイニチをグループに迎え入れることにしたのです。
このM&Aによりマルイチ産商は川上(生産)から川下(販売)までを一貫して手がける体制を強化し、商品の安定供給と品質向上を目指します。
- 実施時期: 2024年9月(株式譲渡契約締結)
- 買い手: 株式会社マルイチ産商(長野県)
- 売り手: 株式会社ダイニチ(愛媛県)
- スキーム: 株式譲渡
(情報参照元:株式会社ダイニチ「株主の変更予定に関するお知らせ」)
事例2【異業種M&A】オーウイル × 海鮮(水産分野への進出)
2024年3月、食品原料専門商社のオーウイルが、水産物の輸入加工・販売を行う海鮮の全株式を取得し子会社化しました。
オーウィルは食品原材料の販売・輸出入、アイスクリームの製造販売を行い、海鮮は魚介類の卸売、魚卵の輸入・加工販売事業を展開しています。
オーウイルは、既存事業とは異なる水産分野へ進出することで、事業ポートフォリオを多角化し成長機会を拡大する狙いです。このM&Aにより、両社は新たな営業機会の創出や顧客への提供価値向上を目指しています。
- 実施時期: 2024年3月(株式譲渡契約締結)
- 買い手: オーウイル株式会社(東京都)
- 売り手: 株式会社海鮮(東京都)
- スキーム: 株式譲渡
(情報参照元:日経会社情報「株式会社海鮮の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」)
事例3【規模拡大M&A】ヤマエグループHD × トップ卵(商品仕入れ強化)
2023年12月、九州を地盤とするヤマエグループホールディングスが、鶏卵事業を行うトップ卵を子会社化しました。
ヤマエグループホールディングスは食品や不動産関連の卸売業、製造業などのグループ企業を擁しており、一方のトップ卵は養鶏・畜産部門での豊富な生産実績を持っています。
ヤマエグループは中期経営計画でM&A戦略を掲げ、事業の多角化を推進しています。そこで最新設備や品質管理に優れたGPセンターを持つトップ卵をグループに迎え入れ、商品仕入れ力の強化と、双方の販売網を活かした事業拡大を狙っています。
- 実施時期: 2023年12月(取締役会決議)
- 買い手: ヤマエグループホールディングス株式会社(福岡県)
- 売り手: トップ卵株式会社(福岡県)
- スキーム: 株式譲渡
(情報参照元:ヤマエグループホールディングス「トップ卵株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」)
事例4【同業種M&A】トーカン×山給(販路拡大・流通体制強化)
2021年4月、愛知県で業務用食品卸を展開するトーカンが、東海エリアで給食市場に強みを持つ山給の全株式を取得し、山給とその子会社ヒカリを子会社化しました。
トーカンを傘下に持つセントラルフォレストグループは、長期戦略で比較的手薄な給食・惣菜市場への参入を推進しています。このM&Aによって両社は販路の強化を図り、企業価値のさらなる向上を目指しています。
- 実施時期: 2021年4月
- 買い手: 株式会社トーカン(愛知県)
- 売り手: 三給株式会社(愛知県)
- スキーム: 株式譲渡
(情報出典元:セントラルフォレストグループ株式会社「三給株式会社の株式取得に関する株式譲渡契約書締結についてのお知らせ」)
事例5【同業種M&A】トーホー×関東食品(物流・商品供給網の効率化)
業務用食品卸大手のトーホーは、2016年に関東食品を持分法適用関連会社としていました。その後、2019年に出資比率を引き上げて子会社化しています。
関東食品は群馬県・埼玉県で学校・病院給食を中心とした業務用食品卸を展開しており、トーホーはこの子会社化を通じて、グループ内の事業シナジーと関東エリアにおけるさらなるシェア拡大を目指しています。
- 実施時期: 2019年3月(子会社化)
- 買い手: 株式会社トーホー(兵庫県)
- 売り手: 関東食品株式会社(群馬県)
- スキーム: 株式の追加取得
(情報参照元:株式会社トーホー「持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)に関するお知らせ」)
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
食品卸業界のM&Aの流れ
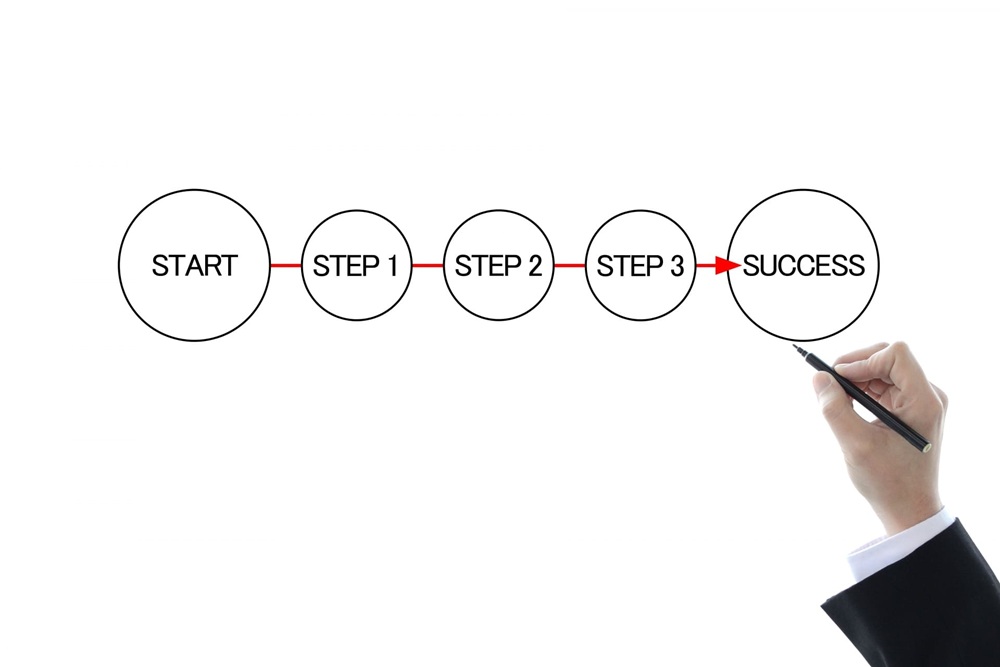
最後に、食品卸業界でM&Aを実際に進める場合のプロセスを解説します。
| ステップ | 主な活動内容 | 期間の目安 |
| 1. 戦略策定・プランニング | M&Aの目的や希望条件を明確にし、自社の強みや課題を分析します。 | 1カ月〜 |
| 2. 専門家への相談 | M&A仲介会社やアドバイザーを選定し、契約を締結します。 | 1カ月〜 |
| 3. 相手企業の選定 | 候補となる企業をリストアップし、社名を伏せた状態で打診します。 | 2~6カ月 |
| 4. トップ面談 | 経営者同士が直接会い、経営理念や将来のビジョンなどを確認し合います。 | 1~2カ月 |
| 5. 基本合意書の締結 | 譲渡価格や今後のスケジュールなど、基本的な条件について合意します。 | 1カ月 |
| 6. 買い手側のデューデリジェンス | 買い手が、売り手企業の財務・法務などのリスクを詳細に調査します。 | 1~2カ月 |
| 7. 最終契約書の締結 | 調査結果を踏まえ、最終的な条件を確定し、契約を締結します。 | 1カ月 |
| 8. クロージング実行 | 株式や事業の引き渡しと、売却代金の決済を実行します。 | 契約締結後ただちに |
| 9. PMI(統合プロセス) | 買収後、両社の経営方針や業務、企業文化などを統合するプロセスです。 | 6カ月〜数年 |
1.戦略策定・プランニング
最初のステップは、M&Aの戦略策定とプランニングです。
まず、M&Aによって何を達成したいのか、目的を明確にすることから始めます。その上で、譲れない条件と譲歩できる条件を整理しておくと、その後のプロセスをスムーズに進められます。
社内でM&Aの条件を絞ることが困難な場合は、プランニングの段階でM&Aの専門家に相談することも検討しましょう。専門家の視点から、現実的な戦略策定のアドバイスが得られます。
2.専門家への相談
M&Aの方向性が固まったら、M&Aの専門家に相談するステップに移ります。
自社で定めた目的や条件を伝え、要件に合致する相手企業の選定を依頼します。パートナー(専門家)選びはM&Aの成否を左右するため、食品卸業界に詳しく、実績が豊富な仲介会社を選ぶことが重要です。
仲介会社によって料金体系(着手金の有無など)やサポート内容は異なるため、相談の際にはしっかり確認しましょう。
M&Aにおけるレーマン方式とは? – 株式会社M&Aフォース
3.相手企業の選定
続いて、M&Aの相手企業を選定します。
まず、M&A専門家が売り手の希望条件に合う買い手候補をリストアップしてくれます。そして初期段階では、売り手企業の社名を伏せた「ノンネームシート」と呼ばれる資料を用いて相手企業に打診します。
相手企業が関心を示した場合に、秘密保持契約を締結した上で詳細な企業情報を開示するのが一般的な流れです。
4.トップ面談
相手先からM&Aを前向きに検討したい旨の意向表明を受けたら、経営者同士のトップ面談を実施します。
トップ面談は、会社の未来を託すにふさわしい相手かどうかを判断する重要な場です。条件交渉だけでなく、お互いの経営理念や価値観、従業員への想いなどを共有し、信頼関係を築ける相手かを見極めることが求められます。
5.基本合意書の締結
トップ面談でお互いの意思が固まったら、基本合意書を締結します。
基本合意書とは、M&Aを本格的に検討することを売り手・買い手双方が合意するもので、現時点での譲渡価格の目安や今後のスケジュール、独占交渉権などが盛り込まれます。
主要な合意事項に対する法的な拘束力はありませんが、独占交渉権や秘密保持義務などには法的拘束力を持たせることが一般的です。
ただし、M&Aの協議を進める過程で、基本合意で定めたスキームや売却価格、契約条件が変更されるケースもあります。
6.買い手側のデューデリジェンス
基本合意後、買い手は売り手企業の詳細な調査(デューデリジェンス)を実施します。
デューデリジェンスとは、公認会計士や弁護士などの専門家が、売り手企業の財務状況や法務リスクなどを徹底的にチェックするプロセスのことです。M&Aスキームによっては、買い手企業が売り手のリスクをすべて負うことになるので、入念な調査が不可欠です。
売り手企業には、この調査に対して誠実に対応し、要求された資料を迅速に提示する姿勢が求められます。
7.最終契約書の締結
デューデリジェンスで経営上の大きな問題がなければ、最終的な条件交渉を経て、株式譲渡契約や事業譲渡契約といった最終契約を締結します。
最終契約書は法的な拘束力を持つ、M&Aの最終的な合意文書であるため、契約締結後は原則として一方的な契約破棄は認められません。
クロージング実行
最終契約の締結後、契約で定められた日に、株式や資産の引き渡しと売却代金の支払いを実行します(クロージング)。
クロージングは通常、「売り手がクロージングの前提条件を満たしている」と確認された後に実行されることが一般的です。このクロージングをもってM&Aの取引は完了し、経営権が正式に買い手に移転します。
PMI(統合プロセス)
クロージング後、PMI(Post Merger Integration:統合プロセス)が始まります。
PMIとは、両社の経営や業務、文化をすり合わせて統合するプロセスのことで、M&Aの目的であるシナジー効果を最大化するための一連の活動です。このPMIが円滑に進み、期待したシナジー効果が発揮されて初めて、そのM&Aは成功したと評価されます。
クロージング実行後も専門家のサポートを得ながら、確実に成果へと結び付けましょう。
PMI(ポストマージャーインテグレーション)の重要性 – 株式会社M&Aフォース
食品卸業界M&Aは適切な準備とパートナー選びが成功の鍵

食品卸業界を取り巻く経営環境は、今後も厳しさを増すと予測されます。先行きが不透明な環境下で、後継者問題を解決し、事業の持続的成長を実現するために、M&Aは極めて有効な経営戦略の一つといえるでしょう。
ただし、適切な相手先企業を見つけ、自社の企業価値や潜在的なリスクを正しく評価・提示するには、高度な専門知識と経験が不可欠です。
自社の現状を正確に把握し、将来の可能性を広げるためにも、M&Aを検討する早い段階から信頼できる専門家へ相談することが成功の鍵となります。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










