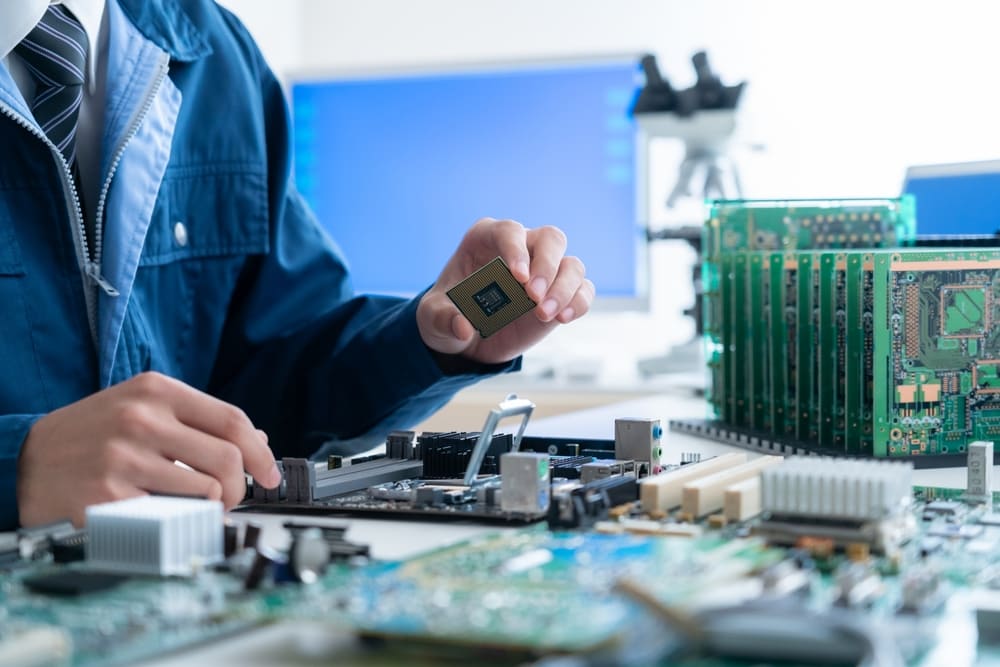【2025年最新】学習塾のM&Aを徹底解説|動向・事例から成功のコツまで

学習塾のM&Aは、後継者問題を抱える経営者の事業承継や、企業の成長戦略を実現するための有力な手段です。
特に少子化や競争激化といった課題に直面する学習塾業界において、M&Aは事業の存続と発展を両立させるための極めて重要な経営判断といえます。
しかし、M&Aを具体的に検討する上では、売却価格の相場観、メリットだけでなく潜在的なリスクといった、専門的な知識が不可欠です。
本記事では、学習塾のM&Aが活発化する背景と最新動向から、売り手・買い手双方のメリット・デメリット、そしてM&Aを成功に導くための重要なコツを解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
学習塾業界の現状とM&A動向
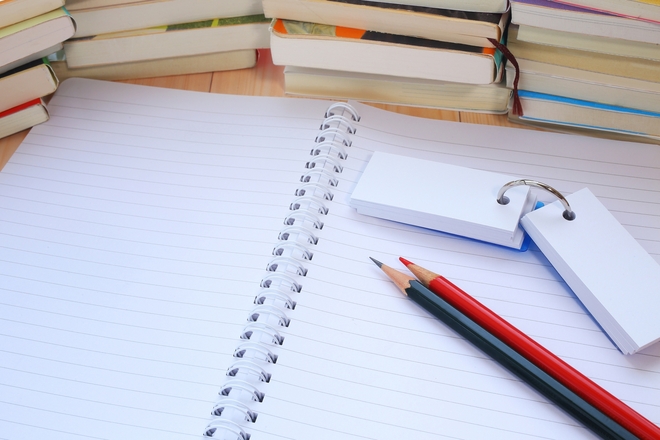
学習塾業界は少子化や競争激化で厳しい状況が続いています。
そのため、後継者不足や経営基盤強化を目的に、M&Aが注目され活発化しています。
ここでは、客観的なデータと共に、M&Aがなぜ今、有効な経営戦略として注目されているのかを解説します。
学習塾業界の現状と課題
学習塾業界は、少子化の進行や学習指導要領の改訂、ICT教育の普及など、大きな変化に直面しています。
国内の子どもの数が減少していることにより、生徒数の確保が難しくなり、各塾間での競争は激化しています。
また、保護者の教育ニーズが多様化し、英語教育やプログラミング、探究学習など、従来の学習指導だけでは生徒を集めることが困難な状況です。
さらに、オンライン学習サービスや個別指導塾の台頭により、従来型の集団指導塾は競争力を失いつつあります。
その結果、経営の安定化や収益力の向上に苦しむ学習塾が増加し、事業承継やM&Aを選択肢とする経営者が増えています。
| 学習塾業界が抱える主な経営課題 | 具体的な内容 |
| 少子化の影響 | 生徒数の絶対数が減少し、地域によっては生徒獲得競争が激化している。 |
| 大手塾との競争 | 豊富な資金力やブランド力を持つ大手塾の進出により、差別化が難しくなっている。 |
| 人材確保・育成 | 質の高い講師の採用が難しく、人件費も上昇傾向にある。 |
| デジタル化への対応 | オンライン授業やICT教材の導入など、新たな投資とノウハウが求められる。 |
学習塾でM&Aが活発化する背景
学習塾業界でM&Aが活発化している背景には、以下のような要因があります。
- 後継者不在問題:特に地方の学習塾では、経営者の高齢化に伴い、後継者が見つからず廃業せざるを得ないケースが増えています。M&Aは、事業を継続させる有効な手段です。
- 市場の成熟と競争激化:学習塾市場は成熟期に入り、新規参入や競合との競争が激しくなっています。経営資源の集中や業界再編の一環として、M&Aによる規模拡大やシェア拡大を図る動きが活発です。
- デジタルシフトの加速:オンライン教育やICTの導入が加速し、投資負担が重くのしかかる中、資本力や技術力を持つ企業との統合を目指すケースが増えています。
このように、事業承継問題の解決や経営基盤の強化を目的として、多くの学習塾がM&Aを検討・実行する状況が生まれています。
学習塾M&Aの最新トレンド
近年、教育業界ではデジタル化やオンライン学習の普及が急速に進んでおり、生徒や保護者の学習ニーズも多様化しています。
しかし、質の高いオンライン授業の提供やICT教材の導入には多額の設備投資と専門知識が必要です。
そのため、M&Aによって大手企業の傘下に入ることで、こうした最新の教育システムを活用し、生徒の満足度を高めるという選択肢が現実的なものとなっています。
最近の学習塾M&Aには、以下のようなトレンドが見られます。
- 大手同士の統合:業界大手の塾同士が統合し、全国展開を強化する動きが進んでいます。これにより、ブランド力や営業力を高め、競争優位性を確保しています。
- 異業種からの参入:教育業界に新規参入した異業種企業(IT企業、人材会社など)が、学習塾の買収を通じて教育市場に参入する事例が増えています。特にオンライン教育やAI教材との連携が期待されています。
- 地域密着型塾の買収:地元で一定のブランド力を持つ小規模塾が、エリア拡大や多店舗展開を狙う中堅・大手塾に買収されるケースも増加しています。
- 人材確保やノウハウ共有を目的としたM&A:単なる事業譲渡だけでなく、指導ノウハウや教育システムの共有、人材交流を通じた成長戦略の一環としてM&Aが活用されるようになっています。
これらの動きは、今後も加速すると予想され、学習塾業界におけるM&Aはますます一般的な経営戦略の一つとなっていくでしょう。
学習塾M&Aのメリット

M&Aと聞くと、単に会社を売却するというイメージが先行しがちですが、実際には経営者、従業員、そして生徒にとっても多くのメリットをもたらす可能性があります。
ここでは、特に塾を譲渡する売り手の視点から、M&Aがもたらす具体的な利点について詳しく見ていきましょう。
売り手のメリット
売り手にとって、M&Aは事業の存続と経済的な利益を両立できる有効な選択肢です。
まず、学習塾業界は少子化や競争激化により、単独での経営が厳しくなるケースも少なくありません。
そんな中でM&Aを活用することで、信頼できる買い手に事業を引き継ぐことができ、従業員や生徒、保護者への影響を最小限に抑えながら、安定的な事業継続が実現します。
また、M&Aによってまとまった売却益を得ることができ、これまで築き上げた事業の価値をしっかりと回収できる点も大きな魅力です。
後継者不在の問題解決や、自身のリタイアメント資金の確保といった個人的な目標も同時に叶えることができます。
さらに、自力での成長が難しい場合でも、M&Aを通じて大手企業や異業種の企業が経営基盤を引き継ぐことで、塾のブランドやノウハウが継続的に活かされる可能性が高まります。
| 売り手の主なメリット | 詳細 |
| 後継者問題の解決 | 親族や社内に適任者がいなくても、意欲と能力のある第三者に事業を託せる。 |
| 創業者利益の獲得 | 事業を現金化し、ハッピーリタイアメントや新規事業への投資が可能になる。 |
| 従業員の雇用維持 | 廃業とは異なり、従業員の雇用を守り、生活の基盤を維持できる可能性が高い。 |
| 生徒への教育継続 | 生徒たちが慣れ親しんだ環境で学び続けられるよう、教育サービスを存続できる。 |
| 個人保証の解除 | 経営者が個人で負っていた金融機関からの借入金などの連帯保証を解消できる。 |
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
買い手のメリット
学習塾業界でのM&Aは、買い手にとっても大きなメリットがあります。
特に、既存の教育ノウハウやブランド力、立地・生徒基盤を短期間で獲得できる点は、新規参入や事業拡大を目指す企業にとって非常に魅力的です。
ゼロから学習塾を立ち上げるには、施設投資や人材採用、ブランド構築など多大なコストと時間がかかりますが、M&Aならそれらを一括して取得でき、スピーディな事業拡大が可能です。
また、すでに運営実績のある塾を承継することで、集客面や売上の安定性も期待できます。
さらに、他業種から教育事業に参入する場合でも、M&Aを活用すればノウハウや人材をそのまま引き継げるため、リスクを抑えながらスムーズに新分野への展開が図れます。
競争が激化する学習塾市場においては、既存資源を活かすM&A戦略が、買い手の成長を加速させる有効な手段です。
| 買い手の主なメリット | 詳細 |
| 事業拡大のスピード向上 | 既存の施設・人材・生徒基盤を取得でき、短期間で多店舗展開や売上拡大が実現できる。 |
| 新規参入のリスク軽減 | 未経験の教育業界でも、既存のノウハウ・運営体制を引き継ぐことで、失敗リスクを抑えられる。 |
| ブランド・顧客基盤獲得 | 地域でのブランド力や既存の生徒・保護者との関係性をそのまま活かせる。 |
| 売上・収益の即時確保 | スタート時点から一定の売上や利益が見込めるため、収益化までの時間を短縮できる。 |
| 人材・ノウハウの獲得 | 教育業界に精通した講師やスタッフ、蓄積された運営ノウハウを引き継ぐことができる。 |
学習塾M&Aのデメリットと注意点

学習塾M&Aには多くのメリットがある一方で、売り手・買い手それぞれが把握しておくべきデメリットや注意点も存在します。
M&Aを円滑に進め、成功させるためには、こうしたリスクへの正しい理解が欠かせません。
売り手のデメリット
学習塾M&Aにおいて、売り手が注意すべき最大のデメリットは、譲渡後に経営方針や運営体制が変わることで、従業員や生徒、保護者に混乱が生じるリスクです。特に指導方法やカリキュラム、教室運営方針が大きく変わる場合、これまで積み重ねてきた塾の文化や良さが失われてしまう可能性があります。
その結果、講師やスタッフのモチベーションが低下し、離職につながるだけでなく、生徒離れや保護者からの不満も招く恐れがあります。M&Aは事業の引き継ぎだけでなく、「これまでの想い」も共有してもらえる買い手を選ぶことが重要です。
また、売却に伴う創業者利益には税金が課される点も見逃せません。
個人事業主が事業を売却した場合、利益には所得税や住民税などが課されます。
一方、会社のオーナーが株式を売却した場合は、その譲渡益に対して課される所得税や住民税などの税率が異なる仕組みになっています。
そのため、事前に税金の試算をしておかないと、手元に残る資金が想定より少なくなるリスクもあります。
さらに、売却後に過去の未払い債務や法的リスクが発覚した場合、売り手にも責任が及ぶことがあります。こうした事態を防ぐためには、事前の情報開示とデューデリジェンスへの誠実な対応が不可欠です。
| 売り手の主なデメリット | 詳細 |
| 経営方針の変更リスク | 譲渡後に教育方針や運営体制が変わり、従業員や生徒に悪影響が出る可能性がある |
| 講師・従業員の離職 | 経営方針変更に伴い、従業員の離職やモチベーション低下が起こる可能性 |
| 税金負担 | 売却益に対する税金が発生し、手元資金が目減りするリスク |
| 法的リスク | 未払い債務や契約問題が売却後に発覚し、責任を問われる可能性 |
買い手のデメリット
買い手側にとっての最大のリスクは、統合(PMI:Post Merger Integration)の難しさです。
異なる企業文化や教育方針を持つ塾を統合する際には、従業員の反発や業務の混乱、想定外のコストが発生することが少なくありません。
特に、従業員の雇用条件が変更される場合、待遇悪化への不満から優秀な講師が離職してしまうリスクがあり、M&A後1年以内の離職率が高まる傾向も指摘されています。
人材の流出は、教育サービスの質の低下や生徒離れにつながり、事業価値を損なう可能性も否定できません。
また、財務状況や生徒数の見込みが不正確だった場合、買収後に思わぬ損失や経営不振に直面するリスクもあります。
こうしたリスクを回避するためには、専門家のサポートを受けつつ、徹底したデューデリジェンスと、綿密な統合計画を策定することが不可欠です。
| 買い手の主なデメリット | 詳細 |
| 統合(PMI)の難しさ | 経営統合がスムーズに進まないと、業務混乱や従業員の反発が生じる |
| 従業員の離職リスク | 雇用条件の変更などにより、講師やスタッフの離職が発生する可能性 |
| 想定外の債務・業績悪化 | 財務や生徒数の不確実性により、予想外の損失を抱えるリスク |
学習塾M&Aの売却相場と企業価値評価

学習塾のM&Aを検討する際に、多くの経営者が気になるのは「いくらで売却できるのか」という点ではないでしょうか。
適切な価格で取引を成立させるためには、M&Aの相場や企業価値の算出方法を理解することが不可欠です。
【2025年最新】M&Aの企業価値評価とは?売り手・買い手の視点でわかりやすく解説
M&A価格の算出方法
学習塾のM&Aにおける売却価格は、主に「時価純資産法」「DCF法」「類似業種比較法」という3つの方法で算出されます。
それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
時価純資産法(アセットアプローチ)
時価純資産法は、企業の貸借対照表をもとに、資産と負債を時価に修正し、その差額(純資産)に数年分の営業利益を加えて企業価値を算出する方法です。
学習塾のような中小企業では、最も一般的な算出方法とされており、過去の実績をベースに安定的な価値評価ができます。
【計算式】
時価純資産 + 営業利益 × 3〜5年分
※ 営業利益の代わりに、経常利益や税引後利益が用いられる場合もあります。
DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法/インカムアプローチ)
DCF法は、将来のキャッシュフロー(利益の源泉)を現在価値に割り引いて企業価値を評価する手法です。将来的な収益性や成長性を重視する場合に有効です。
ただし、売り手が作成する事業計画に大きく左右されるため、算出結果には一定の主観が入ることも留意しておきましょう。
【計算式】
フリーキャッシュフロー ÷(1+割引率)¹ +
フリーキャッシュフロー ÷(1+割引率)² + ……
類似業種比較法(マーケットアプローチ)
類似業種比較法は、株式市場に上場している同業他社の株価や財務指標をもとに、学習塾の企業価値を推計する方法です。
非上場企業であっても、市場での相場感や業界の成長性を反映させた企業評価が可能となります。
【計算式】
類似企業の株式時価総額 ÷ 類似企業の指標(売上高・営業利益など)=係数
対象企業の同指標 × 係数 = 企業価値
3つの算出方法はそれぞれ強みと弱みが異なるため、複数の手法を併用しながら適切な企業価値を見極めることが、納得できるM&Aの成立につながります。
企業価値を高める主な要素
高値で売却するためには、企業価値を高める要素を意識して経営することが重要です。
学習塾の場合、以下のようなポイントが評価されやすくなります。
- 安定した生徒数と継続率
安定的に生徒を確保し、退塾率を低く抑えている学習塾は、収益基盤が安定していると評価され、買い手から高く評価されます。 - 優秀な講師陣の確保と定着率
講師の質は、学習塾の評判や成果に直結します。離職率が低く、教育力の高い講師を抱えていることは大きな価値となります。 - 立地やブランド力
好立地にある校舎や、地域での知名度・評判が高い場合は、集客面で大きな強みとなり、プラス評価につながります。 - オンライン対応・IT活用
近年ではオンライン授業や学習管理システムの導入も評価ポイントです。ITを活用した柔軟な経営体制は、成長性の面でも買い手に魅力的に映ります。
これらの要素は短期間で整備できるものではないため、将来的なM&Aを見据えて、日頃から意識的に改善・強化しておくことが大切です。
学習塾M&Aの手法とプロセス
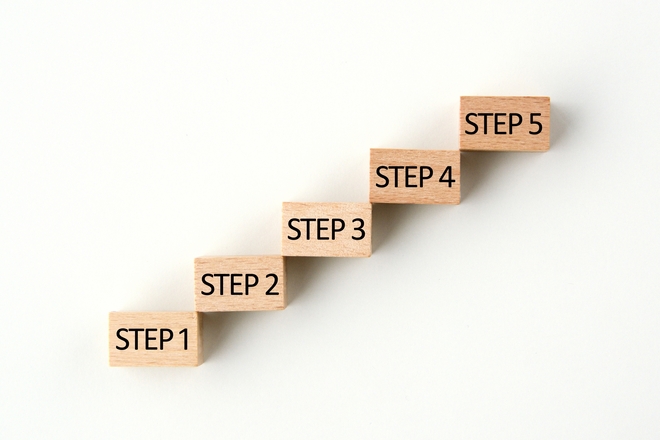
M&Aにはいくつかの手法があり、それぞれメリット・デメリットや税務上の扱いが異なります。
また、実際にM&Aを進める際の基本的な流れを理解しておくことで、スムーズな進行と失敗リスクの軽減につながります。
M&Aの主な手法(株式譲渡・事業譲渡)
学習塾のM&Aで主に用いられるのは「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つの手法です。
| M&A手法 | 概要 | メリット | デメリット |
| 株式譲渡 | 会社の株式を売買することで、経営権を買い手に移転させる手法。会社を丸ごと譲渡するイメージ。 | ・手続きが比較的簡便。
・従業員の雇用契約や許認可などをそのまま引き継げる。 ・会社は存続するため、事業への影響が少ない。 |
・不要な資産や簿外債務も引き継がれるリスクがある。
・会社のすべての株式を買い取るため、多額の資金が必要になる場合がある。 |
| 事業譲渡 | 会社の事業の一部または全部を買い手に譲渡する手法。特定の教室や部門だけを売却することも可能。 | ・譲渡したい事業だけを選んで売却できる。
・買い手は不要な資産や負債を引き継ぐリスクがない。 ・売り手は会社を残し、他の事業を継続できる。 |
・資産や契約、従業員を個別に移転させる必要があり、手続きが煩雑。
・従業員の再契約が必要となり、同意が得られない場合がある。 ・消費税の課税対象となる。 |
どちらの手法を選ぶかは、譲渡の目的やスキーム、リスク管理の観点から慎重に判断する必要があります。
M&Aの基本的な流れと期間
学習塾のM&Aは、以下のようなステップで進んでいきます。
- M&Aの検討・準備:譲渡目的の明確化、自社の強み・弱みの分析。
- 専門家への相談:M&A仲介会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)を選定し、契約。
- 譲渡先の選定(マッチング):仲介会社を通じて候補先企業を探し、交渉相手を絞り込む。
- トップ面談・基本合意:経営者同士で面談し、理念やビジョンを確認。譲渡価格や条件の基本的な合意(基本合意書の締結)。
- デューデリジェンス(買収監査):買い手が、売り手企業の財務や法務、事業内容などを詳細に調査する。
- 最終条件交渉:デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格や条件を交渉する。
- 最終契約の締結:株式譲渡契約書や事業譲渡契約書を締結する。
- クロージング:譲渡代金の決済や株式の名義変更などを行い、M&Aを完了させる。
一般的に、学習塾のM&Aは初期相談から成約まで半年〜1年程度を要することが多いです。規模や条件によってはさらに長期化する場合もあるため、余裕を持ったスケジュール管理を行いましょう。
また、各ステップで専門的な知識が必要となるため、早い段階でM&A仲介会社などの専門家に相談することが成功の鍵となります。
学習塾M&Aの相談先と選び方

学習塾のM&Aを成功させるためには、適切な相談先を選ぶことが極めて重要です。
M&Aは専門性が高く、自社だけで進めるのは困難なため、信頼できる専門家の支援を受けることが欠かせません。
ここでは、どのような相談先があるのか、そしてどうやって最適なパートナーを選べば良いのかを解説します。
M&A仲介会社の役割と活用方法
M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立ち、中立的な立場でM&Aの成立をサポートする専門家です。
その役割は多岐にわたりますが、主に以下のような役割を担います。
- 企業価値評価:客観的な視点で企業価値を算定します。
- 候補先企業の探索(マッチング):独自のネットワークを活かし、最適な譲渡先候補を探します。
- 交渉のサポート:相手方との面談に同席し、価格や条件の交渉を円滑に進めます。
- 各種手続きの支援:契約書の作成支援など、複雑な手続きをサポートします。
特に学習塾業界に詳しい仲介会社を選べば、業界特有の課題や商習慣を踏まえた的確なアドバイスが得られ、交渉もスムーズに進みやすくなります。
また、豊富な案件情報を持つため、より良いマッチングの可能性も広がります。
良い相談先の選び方と注意点
M&A仲介会社を選ぶ際は、以下のポイントを意識しましょう。
| 良い相談先を選ぶためのチェックポイント | 理由 |
| 学習塾業界への専門性・実績 | 業界特有の慣行や価値評価のポイントを理解しているため、より的確なアドバイスが期待できる。 |
| 中小企業のM&Aに特化しているか | 大企業とは異なる中小企業特有の課題(後継者問題、個人保証など)に精通している。 |
| 担当コンサルタントとの相性 | 長期間にわたるプロセスを共に進めるため、信頼関係を築けるかどうかが重要。 |
| 料金体系の明確さ | 「完全成功報酬制」か「着手金」が必要かなど、料金体系を事前に確認し、納得できるか。 |
| 秘密保持の徹底 | 情報漏洩は事業価値を大きく損なうため、秘密保持体制がしっかりしているかを確認する。 |
また、複数の仲介会社に相談し、比較検討することもおすすめです。信頼できるパートナーと出会うことで、M&Aの成功可能性は大きく高まります。
学習塾のM&A事例

近年、学習塾業界ではさまざまな形態のM&Aが実施されています。
ここでは、代表的なパターンを3つに分類し、実際の事例を紹介します。
大手学習塾同士のM&A事例
学習塾業界では、大手同士のM&Aが進んでおり、事業規模の拡大や新たな教育分野への進出を目指す動きが活発です。
ここでは、代表的なM&A事例を詳しく紹介します。
増進会ホールディングスによる栄光ホールディングスの買収
2015年、通信教育「Z会」で知られる増進会ホールディングスは、学習塾「栄光ゼミナール」を運営する栄光ホールディングスを約137億円で買収し、完全子会社化しました。
栄光ゼミナールは、関東を中心に多数の教室を展開し、小中高生向けの指導に強みを持つ大手学習塾です。
増進会ホールディングスは、通信教育と対面指導の両輪を活かし、幅広い顧客層に対応できる体制構築を目指してこのM&Aを実施しました。
これにより、教室ネットワーク拡大とデジタル教材開発の相乗効果を生み出し、教育業界内での競争力を高める結果となっています。
(情報引用元:株式会社増進会出版社「【増進会出版社】栄光ホールディングス株式会社に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」)
この事例は、同業間でのM&Aを通じて教育ノウハウの獲得、市場エリア拡大、シナジー効果の獲得を目指した典型的なパターンに該当します。
異業種によるM&A事例
学習塾業界では、教育関連企業だけでなく、異業種からのM&Aも増加傾向にあります。
少子化や教育ニーズの多様化を背景に、新たな事業領域を開拓したい企業や、既存事業とシナジーを生み出したい企業が、学習塾への参入を進めています。
ここでは、そうした異業種による代表的なM&Aの具体例を見ていきましょう。
ベネッセホールディングスによるミネルヴァインテリジェンスの買収
2014年、株式会社ベネッセホールディングスは、子ども向け英会話教室を首都圏、関西圏を中心に約400教室展開するミネルヴァインテリジェンスを買収しました。
英語教育ニーズの高まりを背景に、ベネッセは既存の学習塾事業とのシナジー効果を見込んで異業種である英会話スクールの買収に踏み切りました。
このM&Aにより、英語教育市場への参入強化や教育サービスの幅を広げることに成功し、多様な学習ニーズに応える体制を整えています。
(情報引用元:株式会社ベネッセホールディングス「株式会社ミネルヴァインテリジェンスの株式取得に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」)
ヒューリックによるリソー教育の子会社化
2024年、不動産業界大手のヒューリックは、学習塾「TOMAS(トーマス)」を展開する株式会社リソー教育を子会社化しました。
買収額は最大で約160億円にのぼり、教育業界への本格参入を目的としたM&Aとして注目されました。
この買収は、少子化が進む中でも安定した需要が見込まれる教育市場に新たな成長の柱を求めたものです。
リソー教育は、個別指導のTOMASブランドで一定の市場シェアと高いブランド力を有しており、ヒューリックにとっては、教育事業への参入だけでなく、既存の不動産資産や経営ノウハウと組み合わせた新たなビジネス展開が期待されています。
(情報引用元:株式会社リソー教育「ヒューリック株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び親会社の異動に関するお知らせ」)
このように、異業種によるM&Aは、既存の教育業界に新たな視点やリソースをもたらし、学習塾の新しい可能性を切り開く手段となっています。
地域密着型塾のM&A事例
地域密着型の学習塾は、生徒や保護者との信頼関係を強みとし、安定した経営を続けている一方、後継者不在や経営資源の限界に直面することも少なくありません。
M&Aは、そうした課題を解決し、さらなる発展につなげる手段となっています。
ここでは、地域密着型塾における代表的なM&A事例をご紹介します。
英進館による田中学習会の買収
2021年、福岡県の大手進学塾「英進館」は、広島県を中心に学習塾「田中学習会」を展開する株式会社ビーシー・イングスの株式を取得し、事業を引き継ぎました。
ビーシー・イングスは、1985年の創業以来、広島・岡山・大阪・四国地域で93校を展開し、約13,000人の生徒を抱える地域密着型の進学塾です。
しかし、経営の永続性や上場準備の難しさから、同じ教育業界で理念を共有できる英進館をパートナーに選びました。
このM&Aにより、両社は教育を通じて人間性を育むという共通の価値観を基盤に、事業の拡大と運営の強化を図っています。
社名や教室名、事業方針は変更せず、地域で築いてきたブランドや信頼を守りながら、新たな成長を目指す形となりました。
(情報引用元:株式会社ビーシー・イングス「株式会社ビーシー・イングスの筆頭株主変更について」)
地域密着型塾のM&Aは、このように「地元の信頼」と「新たな成長機会」の両立を実現する選択肢として、今後も増えていくと考えられます。
学習塾M&Aを成功させるコツ

学習塾のM&Aは、適切に進めれば大きな成果が得られる一方で、進め方を誤ると失敗リスクも伴います。
ここでは、学習塾M&Aを成功させるための5つの重要なポイントを解説します。
M&Aの目的と戦略の明確化
なぜM&Aをするのか、その目的を明確にすることがすべての出発点です。
「後継者がいないから」「引退したいから」といった理由だけでなく、「従業員の雇用を守りたい」「生徒の教育環境をより良くしたい」といったポジティブな目的を整理しましょう。
そして、自社の強み(例:地域での高い評判、特定の受験科目での高い合格率など)を客観的に分析し、言語化しておくことが、交渉を有利に進めるための武器となります。
シナジー効果の冷静な分析
買収によって得られるシナジー効果(相乗効果)を過大評価しないことも重要です。
生徒数の増加・人材の確保・コスト削減・新規エリア進出など、具体的な効果を客観的に分析し、実現可能性を見極めましょう。
冷静な分析が、無理のない成長計画につながります。
徹底したデューデリジェンスの実施
M&A前には、対象企業の財務状況や法的リスク、講師やスタッフの雇用状況、生徒数や業績の推移など、徹底したデューデリジェンス(精査)が必要です。
デューデリジェンス(買収監査)は主に買い手側が行う調査ですが、売り手側も誠実に対応することが信頼関係の構築につながります。
自社の財務状況や法務関連の資料を整理し、質問に対して正確に回答できるよう準備しておきましょう。
後から簿外債務などの問題が発覚すると、交渉決裂や損害賠償につながりかねません。
関係者への丁寧なコミュニケーション
M&Aは、従業員や生徒、保護者にとって大きな不安を伴う出来事です。
情報管理を徹底し、適切なタイミングで、誠意をもって説明することが極めて重要です。
特に、長年連れ添った従業員に対しては、M&Aの目的や今後のビジョン、雇用条件の維持などを丁寧に伝え、理解と協力を得ることが円満な統合の鍵となります。
PMI(M&A後の統合)の計画的な実行
M&Aは契約成立で終わりではなく、むしろ統合後の運営が成否を左右します。
ブランドの統合や人事制度の整備、業務プロセスの統一など、PMI(Post Merger Integration:統合プロセス)を計画的に行うことで、M&Aによる効果を最大化できます。
売り手としても、スムーズな引き継ぎができるよう、業務のマニュアル化や主要な取引先・顧客リストの整理など、事前にできる準備を進めておくことが重要です。
買い手側と協力し、組織文化の融合や人事制度のすり合わせなどを計画的に行いましょう。
学習塾M&Aで理想の事業承継・売却を実現しよう

少子化や競争激化が進む学習塾業界では、M&Aが事業の存続と発展を両立する有力な選択肢となっています。
理念や教育サービスを残しつつ、次世代へスムーズにバトンを渡せるのが大きな魅力です。
一方で、M&Aは大きな経営判断であり、価格や条件だけでなく、誰に引き継ぐかや従業員や生徒の未来を見据えることが大切です。
正しい知識と専門家のサポートを活用し、理想の事業承継を実現しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)