M&Aの成功率は2〜4割?|成功率を高める5つのポイントを解説

多数の企業がM&Aを通じた成長戦略を検討する一方で、期待した成果を得られないケースも少なくありません。
「自社のM&Aは本当に成功するのか」「そもそもM&Aの成功率はどのくらいなのか」と不安を抱え、実行に踏み切れない経営者も多いのではないでしょうか。
本記事では、M&Aの成功率が低い要因と成功率を高める5つのポイントを具体的に解説します。
適切な準備と戦略により、M&Aの成功率は大幅に向上します。自社のM&A戦略を見直し、確実な成功へとつなげましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&A成功率とは

M&Aの成功率を理解するためには、まず「成功」の定義を明確にする必要があります。本章では、M&A成功の基準と日本における実際の成功率について詳しく解説します。
- M&A成功の定義
- 日本におけるM&Aの成功率は2〜4割
それぞれ詳しく見ていきましょう。
M&A成功の定義
M&Aの成功は、買収後に当初の目標を達成したかどうかで判断されます。一般的には買収後の目標達成率が80%を超えた場合に「成功」とされています。
目標とは、具体的に売上高や利益率の向上、市場シェアの拡大、新規事業への参入など、設定した数値が挙げられます。
また、社員の定着率や企業文化の融合度も成功の重要な要素です。
ただし、企業によって成功の基準は異なり、財務的な成果だけでなく、技術獲得や人材確保を主目的とする場合もあります。
M&A実施前に明確な成功基準を設定し、その達成度を定期的に検証する体制を整えておきましょう。
日本におけるM&Aの成功率は2〜4割
日本企業のM&A成功率は、各種調査によると2〜4割程度にとどまっています。
この数値は欧米企業と比較しても同程度であり、M&Aの難しさは世界共通の課題です。
成功率が低い背景には、異なる企業文化の統合の困難さや、複雑な経営統合プロセスへの対応の難しさがあります。特に中小企業では、M&A後の統合作業に必要なリソースや専門知識が不足しがちです。
一方で、M&A仲介会社の増加により支援体制が充実し、企業間でのM&Aに関する知見の共有も進んでいます。
また、事業拡大や海外進出といった前向きな目的によるM&Aも増加しており、成功率の向上には、事前準備と統合後のフォロー体制が極めて重要です。
M&Aの成功率が低くなる要因
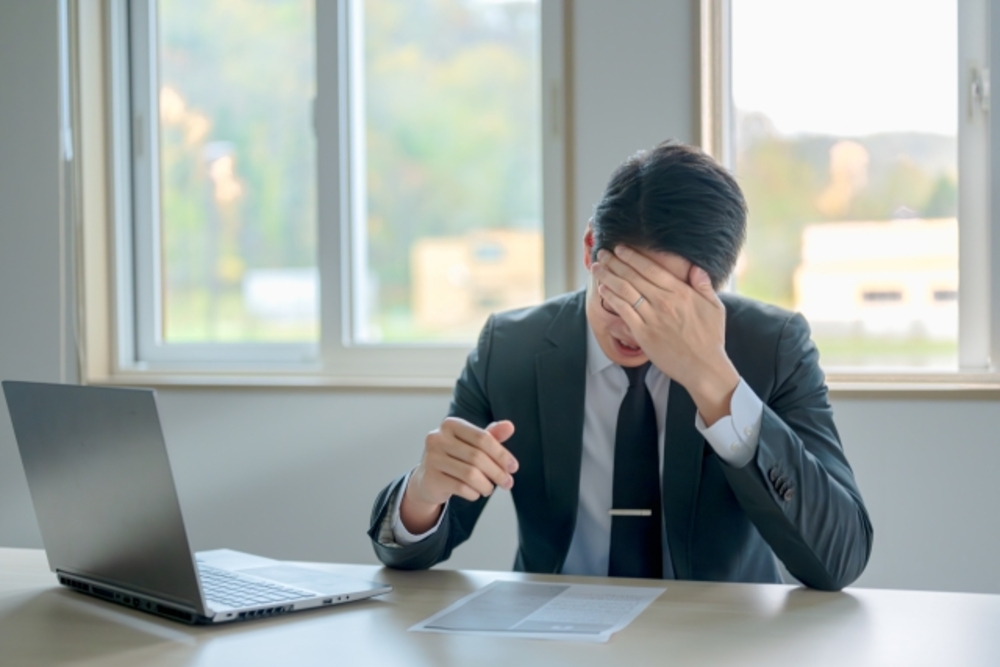
M&Aの成功率が2〜4割にとどまる背景には、複数の要因が存在します。
本章では、失敗につながる5つの主要因について詳しく分析します。
- デューデリジェンスの不足
- 企業価値の過大評価
- PMIの失敗
- シナジー効果の欠如
- 経営戦略の不足
各要因について具体的に解説します。
デューデリジェンスの不足
デューデリジェンスの不十分な実施は、M&A失敗の最大要因の一つです。
財務面の調査に偏り、法務、労務、環境などの重要リスクを見逃すケースが多く見られます。特に簿外債務や潜在的な訴訟リスク、重要な取引先との契約条件などの見落としは、買収後に深刻な問題を引き起こします。
また、企業文化や組織体制、ITシステムの互換性など、非財務面の調査も重要です。
時間的制約から調査を省略したり、専門家を活用せずに自社のみで実施したりすると、重大なリスクを見逃す可能性が高まります。
包括的なデューデリジェンスの実施は、M&A成功の必須条件です。
企業価値の過大評価
買収価格の設定において、対象企業の過大評価は、M&A後の収益性を大きく損なう要因です。
競合他社との入札競争や、感情的な判断により、適正価格を大幅に超える金額で買収するケースが後を絶ちません。特に将来のシナジー効果を過度に期待し、その効果を買収価格に織り込みすぎる傾向があります。
また、市場環境の変化や業績予測の不確実性を十分に考慮せず、楽観的な事業計画に基づいた価格設定も問題です。
適正な企業価値の評価には、複数の評価手法を併用し、保守的なシナリオも含めた分析が不可欠です。
PMIの失敗
PMI(Post Merger Integration)の失敗は、M&A後の統合段階で多く発生する問題です。統合計画の不備や実行体制の不足により、想定していた統合効果が実現できないケースが多数報告されています。
特に、両社の業務プロセスやITシステムの統合、人事制度の一元化などでつまずくことが多く見られます。また、統合スピードの誤算も大きな要因です。急速な統合は現場の混乱を招き、逆に統合が遅すぎると機会損失が発生します。
さらに、キーパーソンの離職や社員のモチベーション低下も、PMI失敗の典型的な症状です。PMIを成功させるには、詳細な統合計画と柔軟な実行体制が必要です。
シナジー効果の欠如
期待したシナジー効果が実現しないことも、M&A失敗の要因です。
売上シナジーやコストシナジーの過大な見積もりにより、投資回収が困難になるケースが頻発しています。特に、顧客基盤の共有や販売チャネルの相互活用において、実際には想定どおりの効果が得られないことが多く見られます。
また、重複部門の統合によるコスト削減も、実際には統合コストが予想以上にかかり、期待した削減効果が得られないケースがあります。
シナジー効果の実現には、具体的な実行計画と継続的なモニタリングが不可欠です。抽象的な期待値ではなく、実現可能な具体的施策に基づいた効果測定が重要です。
経営戦略の不足
明確な経営戦略なしに実施されるM&Aは、高い確率で失敗に終わります。
M&Aありきで案件を進め、自社の中長期戦略との整合性を十分に検討しないケースもあります。特に、事業の多角化を目的としたM&Aで、自社の主力事業の強みとの関連性が薄い企業を買収する場合、統合後の経営が困難になりがちです。
また、買収後のビジョンや成長シナリオが不明確なまま進めると、統合後の方向性が定まらず、組織全体が混乱します。
成功するM&Aには、自社の強みを活かし、明確な成長戦略に基づいた案件選定と実行計画が必要です。
M&Aの成功率を高める5つのポイント

M&Aの成功率を向上させるためには、戦略的なアプローチと綿密な準備が不可欠です。
本章では、成功率を高める5つの重要ポイントを解説します。
- M&Aの目的と戦略の明確化
- デューデリジェンスの徹底
- 計画的なPMIの実施
- 良好な関係構築
- 専門家への相談
各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
M&Aの目的と戦略の明確化
M&A成功の第一歩は、明確な目的設定と戦略立案です。
市場シェアの拡大、新技術の獲得、事業領域の拡張など、目標を具体的な数値に落とし込むことが重要です。
また、自社の強みとM&A対象企業の特性を詳細に分析し、統合後のビジネスモデルを明確に描く必要があります。
戦略策定では、3〜5年後の具体的な事業計画を作成し、各段階での達成指標を設定します。さらに、複数のシナリオを想定し、市場環境の変化にも対応できる柔軟な戦略準備が重要です。
経営陣全体で戦略を共有し、組織全体が同じ方向を向いて進める体制構築も成功の鍵です。
デューデリジェンスの徹底
包括的なデューデリジェンスの実施は、M&Aリスクを最小化する最も効果的な方法です。
財務・税務調査に加え、法務、労務、環境、IT、知的財産など、多角的な視点から対象企業を精査します。特に重要なのは、ビジネスデューデリジェンスです。
市場動向、競合状況、顧客基盤の安定性、サプライチェーンの健全性などを詳細に調査します。
また、企業文化や組織風土の調査も欠かせません。両社の価値観や意思決定プロセスの違いを事前に把握し、統合計画への反映が重要です。
専門家チームを編成し、十分な時間をかけた調査により、買収後の想定外リスクを大幅に削減できます。
計画的なPMIの実施
PMIの成功は、M&A全体の成否を左右する重要な要素です。
買収合意前からPMI計画の策定を開始し、Day1(統合初日)から100日間の詳細なアクションプランを準備します。
統合推進室を設置し、各部門から選抜されたメンバーで構成される専任チームの作成が有効です。重要なのは、優先順位の明確化です。
まず安定的な事業継続を確保し、次に短期的な統合効果を実現し、最後に中長期的な成長基盤を構築します。
また、定期的な進捗モニタリングと柔軟な計画修正も欠かせません。社員への継続的なコミュニケーションを通じて、不安を解消し、統合への協力を得るよう努めましょう。
良好な関係構築
M&A成功には、買い手と売り手の信頼関係構築が不可欠です。
交渉段階から誠実な対応を心がけ、相互の利益を追求する姿勢が重要です。特に売り手企業の経営陣や社員との関係構築は、統合後の円滑な事業運営に直結します。
買収後も、売り手企業の優れた点を尊重し、両社の良い部分を組み合わせる姿勢が大切です。
また、優秀な人材の流出を防ぐため、適切なインセンティブ設計と明確なキャリアパスの提示も必要です。
定期的な対話の機会を設け、統合に関する不安や課題を早期に把握し、解決する体制を整え、良好な関係を維持しましょう。
専門家への相談
M&Aの複雑なプロセスを成功に導くには、各分野の専門家の支援が欠かせません。
M&Aアドバイザー、弁護士、会計士、税理士など、それぞれの専門領域で豊富な経験を持つプロフェッショナルの知見を活用することが重要です。
特に初めてM&Aに取り組む企業では、経験豊富なアドバイザーの支援により、成功率が大幅に向上します。専門家の選定では、業界知識や実績だけでなく、自社との相性も重要な要素です。
また、案件の規模や複雑さに応じて、適切な支援体制の構築が大切です。コスト面での負担はありますが、失敗リスクの低減効果を考慮すれば、十分に投資価値のある選択といえます。
正しいアプローチでM&Aの成功を確実にしよう

M&Aの成功率は一般的に2〜4割と低い水準にありますが、適切な準備と戦略的なアプローチにより、成功率の向上は可能です。
本記事で解説した5つのポイントを意識し、M&Aの成功率を高めましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










