事業売却とは?会社売却との違いからメリット・手続き・税金まで徹底解説

事業売却とは、会社が運営する事業の一部または全部を、他の会社に売却するM&Aの手法です。経営権を手元に残したまま、ノンコア事業を整理して主力事業に集中したり、後継者問題を解決したりできるため、有効な経営戦略として注目されています。
その選択肢として事業売却を検討する中で、「会社売却とは何が違うのだろう?」「自社にとってはどちらが最適なのか判断できない」といった疑問やお悩みをお持ちの経営者は少なくありません。
事業売却は、会社全体ではなく特定の事業のみを売却するM&Aの手法です。経営権を手元に残したまま、資金調達や事業の再編が可能なため、有効な経営戦略となり得ます。
会社売却との違いと、売り手・買い手双方のメリット・デメリット、手続きの流れ、税金の問題まで網羅的に解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業売却とは?会社の事業の一部を売買するM&A手法

事業売却とは、会社が運営する複数の事業のうち、一部または全部を第三者に売却するM&A(企業の合併・買収)の手法の一つです。
法律上は「事業譲渡」と呼ばれ、会社そのものの経営権を売却するのではなく、特定の事業に関連する資産や人材、ノウハウなどを切り離して譲渡する点が特徴です。
売り手企業は会社を存続させたまま、事業の選択と集中を進められます。
事業売却と会社売却・事業譲渡の違い
事業売却を検討する際、多くの方が混同しやすいのが「会社売却」と「事業譲渡」です。それぞれの違いを正確に理解することが、最適な経営判断の第一歩となります。
まず、大きな枠組みとしてM&A(会社の合併・買収)があり、その具体的な手法として事業譲渡や株式譲渡などが存在します。
- 事業譲渡: 会社の事業の一部または全部を売却する手法。
- 株式譲渡: 会社の株式を売却し、経営権を買い手に移転させる手法。
世間一般で会社売却という場合、会社の経営権が動く後者の株式譲渡を指すことが多いため、この記事でもその慣例に従い、事業の一部を売る行為を事業売却、会社全体を売る行為を株式譲渡として比較し、解説を進めます。
【株式譲渡(会社全体の売却)との違い】
事業売却と株式譲渡の最も大きな違いは、売買の対象と、それに伴う経営権の行方です。
| 比較項目 | 事業売却 | 株式譲渡 |
| 売買の対象 | 事業に関する資産・負債 | 会社の株式 |
| 経営権 | 売り手企業に残る | 買い手企業に移る |
| 債務の引継ぎ | 個別に合意した範囲のみ | 原則すべて引き継ぐ |
| 手続き | 煩雑(資産・契約の個別移転) | 比較的シンプル(株主の変更) |
事業売却は、会社の事業という資産を売る取引であるのに対し、株式譲渡は会社の所有権そのものである株式を売る取引です。
そのため、事業売却では会社の経営権は売り手の手元に残りますが、株式譲渡では経営権が買い手に完全に移転します。ノンコア事業だけを整理したい場合や、会社そのものは手放したくない場合には、事業売却が適した選択肢です。
【事業譲渡との違い】
事業売却と事業譲渡は、ほぼ同じ意味で使われます。
厳密には、事業譲渡が会社法で定められた法律上の正式名称であり、事業売却はM&Aの実務などで使われる一般的な呼称です。
本記事では、イメージしやすい事業売却という言葉で統一して解説を進めます。
事業売却が選択される主な目的
企業が事業売却を行う背景には、主に以下のような目的があります。
- 選択と集中(ノンコア事業の整理)
会社全体の成長を加速させるため、収益性が低いノンコア事業や、本業とのシナジーが薄い事業を売却するケースです。売却によって得た資金や人材といった経営資源を、成長が見込まれる主力事業に再投資することで、企業価値の最大化を目指します。 - 資金調達(財務改善・新規事業投資)
特定の事業を売却することで、まとまった資金を確保する目的です。金融機関からの融資に頼らず、この資金を元手に借入金を返済して財務体質を改善したり、将来性のある新規事業への投資を行ったりします。 - 後継者問題の解決(事業承継)
後継者が見つからず、会社全体の事業承継が難しい場合でも、特定の事業だけなら引き受け手が見つかることがあります。事業売却によって事業と従業員の雇用を存続させ、経営者は残った事業に専念する、あるいは会社を清算するといった選択が可能です。
これは、事業の一部だけでも存続させたいと考える経営者にとって、有力な選択肢の一つです。
【売り手・買い手別】事業売却のメリット

事業売却は、売り手と買い手の双方にとって多くのメリットをもたらす可能性があります。それぞれの立場から見た主な利点を理解することで、交渉を有利に進めるためのヒントが得られます。
ここでは、特に中小企業の経営者の方が知っておくべきメリットに焦点を当てて解説します。
【売り手側】事業売却のメリット
売り手にとって、事業売却は単なる資金調達手段にとどまらず、会社の未来を再設計するための戦略的な一手です。経営権を維持したまま、会社の課題を解決できる点が大きな魅力です。
- 会社の経営権を維持できる
会社売却(株式譲渡)が会社の所有権そのものを手放すのに対し、事業売却は特定の事業のみを切り離すため、会社の経営権は手元に残り続けます。 創業した会社への思い入れが強い経営者や、主力事業は今後も自分で育てていきたいと考える経営者にとって、これは最大のメリットと言えるでしょう。 - 主力事業へ経営資源を集中できる
売り手企業にとって経営資源を効率的に使う「選択と集中」を実現できる点も大きなメリットです。伸び悩んでいる事業や、本業との関連性が薄い事業を売却することで、そこに投下していた人材・資金・時間といった貴重な経営資源を解放できます。そして、その資源を成長著しい主力事業や新規事業に再投資することで、企業全体の競争力を高め、持続的な成長を目指すことが可能です。 - 売却益でまとまった資金を確保できる
事業売却によって、譲渡対価としてまとまった現金を得られます。この資金の使い道は多様で、借入金を返済して財務基盤を強化する、新たな設備投資を行う、研究開発費に充てるなど、会社の次なる成長戦略のための原資として活用できます。 - 事業と従業員の雇用を存続させられる
後継者不足や市場の変化により、事業の継続が困難になるケースは少なくありません。そうした場合、廃業という選択肢を取ると、長年培ってきた技術やノウハウが失われ、従業員も職を失ってしまいます。事業売却であれば、その事業の価値を評価してくれる他社に引き継いでもらうことで、事業そのものと、そこで働く従業員の雇用も守れます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
【買い手側】事業売却のメリット
買い手にとって事業売却は、リスクを限定しながらスピーディーに事業を拡大できる効率的な手法です。必要なものだけを取得できるため、無駄のない投資ができます。
- 必要な事業・資産だけをピンポイントで買収できる
新規事業への参入を検討している場合、ゼロから人材を採用し、設備を整え、ノウハウを蓄積するには膨大な時間とコストがかかります。
事業売却を活用すれば、すでに軌道に乗っている事業を、必要な資産や人材ごとまとめて手に入れられます。これにより、事業立ち上げにかかる時間を大幅に短縮し、迅速な市場参入を実現できます。 - 簿外債務を引き継ぐリスクを回避できる
会社を丸ごと買収する株式譲渡では、貸借対照表に記載されていない簿外債務や、将来発生するかもしれない偶発債務まで引き継いでしまうリスクが常に伴います。
しかし、事業売却では、契約によって引き継ぐ資産と負債の範囲を明確に特定します。そのため、売り手企業の潜在的なリスクから切り離された、健全な事業だけを譲り受けることが可能です。これは買い手にとって非常に大きな安心材料です。 - のれん償却による節税効果が期待できる
事業売却では、買収価格が譲り受ける資産の時価を上回った場合、その差額がのれん(営業権)として資産計上されます。こののれんは、会計上、一定期間(通常5年)にわたって償却でき、税務上も損金として算入することが認められています。 結果として、課税所得が圧縮され、法人税の負担を軽減する効果が期待できます。
【売り手・買い手別】事業売却で注意すべきデメリット
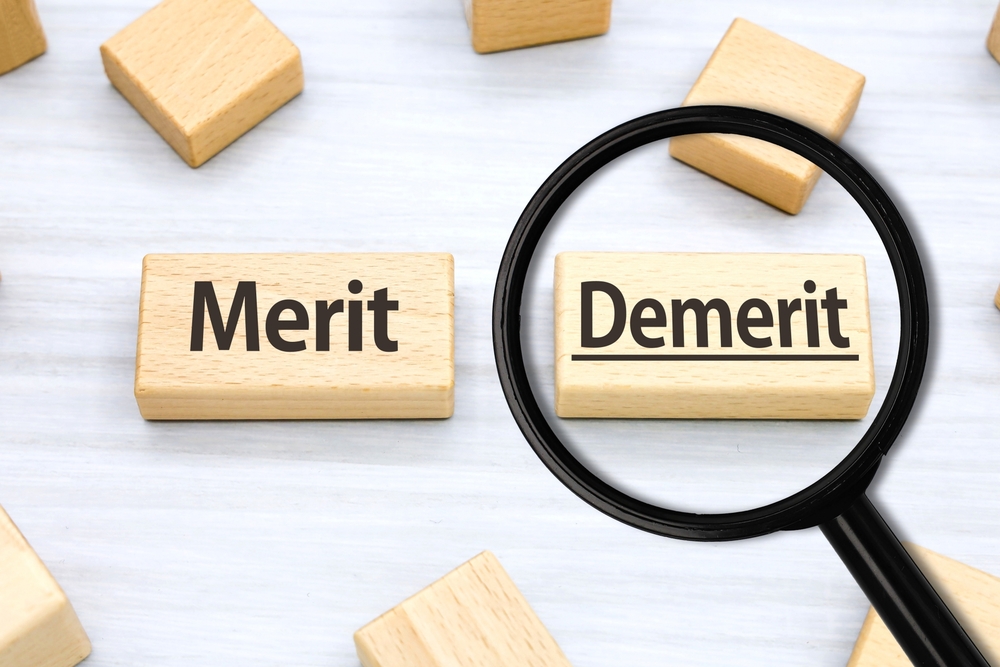
事業売却には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。特に手続きの煩雑さや税務面での注意点は、事前にしっかりと把握しておく必要があります。
失敗を避けるためにも、以下のポイントを必ず確認してください。
【売り手側】事業売却のデメリット
売り手側が直面する可能性のあるデメリットは、主に行政手続きと税金に関するものです。
これらは専門家の助けを借りることで、負担を軽減できる場合があります。
- 会社売却(株式譲渡)に比べて税負担が重くなる可能性がある
事業売却によって得た利益(譲渡益)には、法人税(実効税率約30%)が課税されます。一方、会社売却(株式譲渡)の場合、オーナー経営者が個人として株式を譲渡するため、譲渡益にかかる税金は所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて約20%です。
売却の規模や利益額にもよりますが、一般的に事業売却は会社売却よりも税率が高くなる傾向にあります。
そのため、どちらの手法が自社にとって税務上有利なのか、専門家である税理士などに相談し、慎重にシミュレーションを行うことが不可欠です。 - 手続きが煩雑で、完了までに時間を要する
事業売却は、売却対象となる資産や負債、契約などを一つひとつ個別に移転させる手続きが必要です。例えば、不動産があれば所有権移転登記、従業員がいれば雇用契約の再締結、取引先との契約があれば契約の承継手続きなど、多岐にわたる煩雑な作業が発生します。
これに対し、株式譲渡は株主が変わるだけなので、手続きは比較的シンプルです。事業売却は、クロージング(取引の完了)までに多くの時間と労力がかかることを覚悟しておく必要があります。 - 競業避止義務が課される
会社法では、特約がない限り、事業を譲渡した会社は同一の市町村および隣接市町村において、譲渡日から20年間、同一の事業を行ってはならないと定められています(競業避止義務)。これは、買い手側の利益を保護するための規定です。
例えば、地域に根差した飲食店事業を売却した後に、すぐ隣で同じような飲食店を開業することは原則としてできません。
この期間や範囲は当事者間の合意で変更可能ですが、売り手にとっては事業活動の制約となるため、契約内容を十分に確認する必要があります。
【買い手側】事業売却のデメリット
買い手側のデメリットは、主に許認可の再取得や従業員の引き継ぎに関するものです。事業をスムーズに開始するために、事前の計画が重要です。
- 事業に必要な許認可の再取得が必要
事業運営に必要な許認可(例えば、建設業許可や飲食店営業許可など)は、売り手企業(法人)に対して与えられているため、事業売却によって自動的に買い手企業に引き継がれることはありません。
そのため、買い手企業は自社の名義で、必要な許認可を改めて行政庁に申請し、取得し直す必要があります。許認可の種類によっては取得までに数ヶ月かかる場合もあり、その間の事業運営に支障が出ないよう、スケジュールを逆算して計画的に手続きを進めなければなりません。 - 従業員や取引先との契約を個別に結び直す必要がある
従業員の雇用契約や取引先との基本契約なども、自動的には承継されません。そのため、買い手企業は、対象事業の従業員一人ひとりと個別に雇用契約を締結し直す必要があります。同様に、重要な取引先とも契約を再度結び直すか、契約上の地位の移転について個別の同意を得なければなりません。
この過程で、キーパーソンとなる従業員が退職してしまったり、重要な取引先が離れてしまったりするリスクも考慮する必要があります。 - 課税資産の取得に消費税がかかる
事業売却において、買い手が譲り受ける資産のうち、土地を除く有形資産(建物、機械など)や無形資産(のれんなど)は消費税の課税対象となります。そのため、買い手は売買代金とは別に、消費税を支払う必要があります。
この消費税は、原則として仕入税額控除によって後から還付されますが、一時的に多額の資金を立て替える必要があるため、キャッシュフローに影響を与えます。買収資金を準備する際には、この消費税分も考慮に入れた資金計画が重要です。
事業売却の価格はどう決まる?価値算定方法(バリュエーション)と相場

事業売却を検討する経営者にとって、自分の事業はいくらで売れるのかは最大の関心事です。売却価格は、客観的な企業価値評価(バリュエーション)を基に、最終的には買い手との交渉によって決定されます。
ここでは、その基礎となる価値の算出方法について解説します。
主な事業価値の算出方法(バリュエーション)
事業の価値を客観的に評価する手法(バリュエーション)には、主に3つのアプローチがあります。実際には、どれか一つの手法だけを用いるのではなく、複数の手法を組み合わせて多角的に価値を算出し、妥当な価格レンジを探っていくのが一般的です。
| 評価アプローチ | 主な算定方法 | 考え方 |
| インカム・アプローチ | DCF法 | 事業が将来生み出すキャッシュフロー(現金収益)を予測し、それを現在の価値に割り引いて評価する方法。 |
| マーケット・アプローチ | マルチプル法 | 類似する上場企業の株価やM&A事例などを参考に、特定の財務指標(利益や純資産など)の何倍かで評価する方法。 |
| コスト・アプローチ | 時価純資産法 | 事業が保有する資産の時価から、負債の時価を差し引いて評価する方法。 |
これらの評価は専門知識を要するため、M&Aの専門家である仲介会社や公認会計士に依頼することをおすすめします。
事業売却の価格相場と最終価格の決まり方
「この業種なら、売上高の〇倍が相場」といった話を耳にすることがあるかもしれませんが、株式市場のように明確な相場は事業売却には存在しません。一つひとつの事業が持つ特性や状況が異なるため、価格は個別具体的に決まります。
【価格相場に影響を与える要因】
バリュエーションによる理論値はあくまでスタートラインです。そこから、以下のようなさまざまな要因が加味され、価格は変動します。
- 収益性と将来性: 安定した利益を生み出しており、今後も市場の成長が見込まれる事業は高く評価されます。
- 独自の強み(競争優位性): 特許技術、独自のノウハウ、強固なブランド、優良な顧客基盤など、他社が容易に模倣できない強みは、価格を大きく押し上げる要因です。
- 買い手とのシナジー効果: 買い手企業がその事業を取り込むことで、どれだけの相乗効果(売上の拡大、コストの削減など)が生まれるかは非常に重要です。大きなシナジーが見込まれる場合、買い手は理論価値よりも高い価格を提示するインセンティブが働きます。
- 潜在的なリスク: 特定の取引先に売上を大きく依存している、法規制の変更による影響を受けやすい、といったリスク要因は、価格交渉においてマイナスに働く可能性があります。
最終的な売却価格は、バリュエーションによる理論価格を基準に、これらの個別要因を反映させた上で、売り手と買い手の交渉によって決定されます。
特に、買い手がどれだけ大きなシナジー効果を見出しているかは、価格を大きく左右する最大のポイントです。つまり、自社の事業価値を最も高く評価してくれる最適な買い手を見つけることが、高値での売却に直結します。
事業を高値で売却するために押さえておくべきポイント

事業を少しでも高く売却するためには、事前の準備が重要です。
買い手にとって魅力的で、リスクの少ない事業であることを示すことが、価格交渉を有利に進める鍵となります。
ポイント1:事業の収益性と将来性を向上させる
買い手が最も重視するのは、その事業が将来にわたって安定的に利益を生み出せるか、という点です。M&Aの交渉を始める前から、事業の収益性を高める努力をしておくことが不可欠です。
- コスト構造の見直し: 不要な経費を削減し、利益率を改善します。
- 売上の安定化: 特定の顧客に依存している場合は、取引先を分散させ、安定した収益基盤を構築します。サブスクリプションモデルなど、継続的な収益が見込めるビジネスモデルは高く評価される傾向にあります。
- 成長戦略の明確化: 今後の市場動向を踏まえ、どのような成長戦略を描いているのかを具体的に示せるように準備します。明確な成長ストーリーは、買い手にとって大きな魅力となります。
日頃から事業の磨き上げを行うことが、いざという時の高値売却につながります。
ポイント2:自社の強みを客観的に整理し、アピール材料を用意する
自社の事業が持つ独自の強みは何かを客観的に分析し、それを買い手に分かりやすく伝えられるように準備しておくことが重要です。貸借対照表などの財務諸表に現れない無形の価値こそが、価格交渉における強力な武器となります。
- 技術・ノウハウ:
特許技術や独自の製造プロセス、長年蓄積された専門的なノウハウなど。 - ブランド・顧客基盤:
業界内での高い知名度、顧客からの厚い信頼、優良な顧客リストや強固な販売網。 - 人材・組織文化:
優秀なエンジニアチームや営業部隊、代替の難しいキーパーソンの存在、従業員のモチベーションが高い組織文化など。
これらの強みを客観的なデータや実績とともに資料にまとめ、買い手が「その価値を手に入れるためなら、多少高くても買いたい」と思えるようなアピール材料を用意しましょう。
ポイント3:最適なタイミングと売却先を見極める
事業を最も高く評価してくれる相手に、最も良いタイミングで売却することも極めて重要です。
- タイミングの見極め:
事業の業績が好調で、市場全体が成長トレンドにある時が、最も高く評価されやすいタイミングです。業績が悪化してから慌てて売却しようとすると、買い手から足元を見られ、不利な条件での交渉になりがちです。「もう少し自社で頑張れる」という余力があるうちに検討を始めるのが理想と言えます。 - 最適な売却先の選定:
自社の事業と最も大きなシナジー効果(相乗効果)を生み出せる買い手を見つけることが、高値売却の最大の秘訣です。例えば、自社の技術を欲している企業、自社の販売網を活用できる企業など、買い手候補を広くリストアップし、それぞれの企業が自社の事業をどのように評価するかを予測することが重要です。
これらの見極めには専門的な知見が必要となるため、M&Aの専門家と協力しながら戦略的に進めることが成功の確率を高めます。
知っておきたい事業売却にかかる税金と専門家への費用
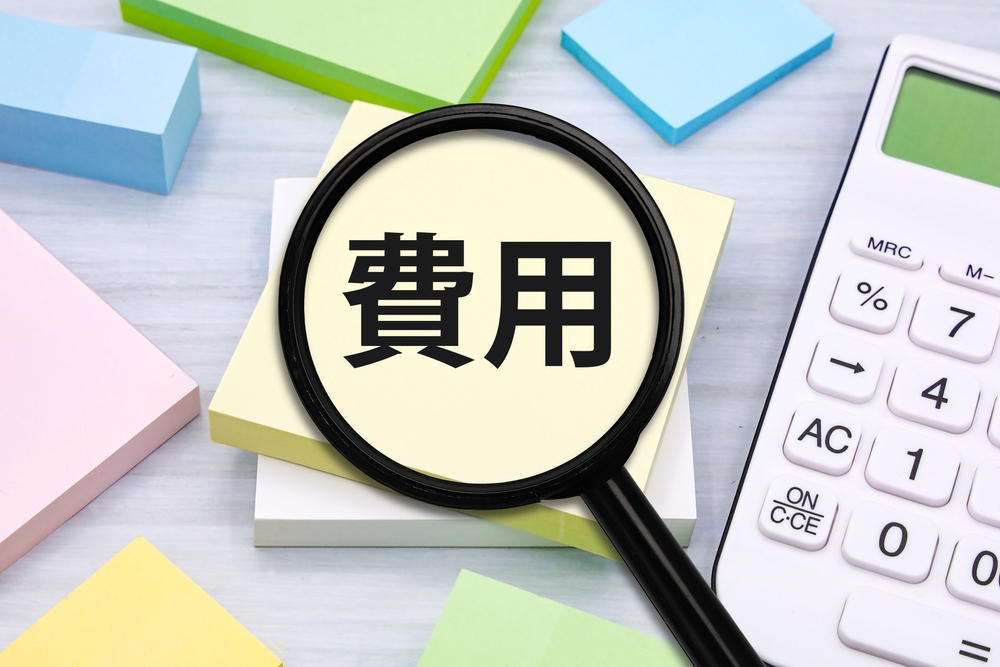
事業売却には、売却益に対する税金や、手続きをサポートしてくれる専門家への手数料が発生します。最終的な手取り額を正確に把握するため、これらのコストについてもしっかりと理解しておきましょう。
事業売却で発生する税金
事業売却では、売り手側と買い手側の双方に、それぞれ異なる種類の税金が発生します。
ここでは、それぞれの立場においてどのような税金がかかるのかを具体的に解説します。
【売り手側】にかかる税金の種類
売り手企業が事業を売却して得た利益(譲渡益)に対しては、法人税等(法人税・地方法人税・法人住民税・事業税)が課税されます。
譲渡益は、以下の計算式で算出されます。
譲渡益 = 事業の売却価格 - 譲渡資産の簿価
例えば、簿価1億円の事業を3億円で売却した場合、差額の2億円が譲渡益です。この2億円が、その年度の他の事業の損益と合算された上で、法人税等の課税対象となります。
法人税等の実効税率は企業の規模や所在地によって異なりますが、およそ30%程度と見積もっておくと良いでしょう。
前述の例では、単純計算で2億円 × 30% = 6,000万円程度の税負担が発生する可能性があると理解しておく必要があります。
【買い手側】にかかる税金の種類
買い手側には、主に消費税がかかります。事業譲渡において譲渡される資産のうち、土地や有価証券などを除く「課税資産」が消費税の対象です。
具体的には、以下のようなものが課税資産に該当します。
- 建物、機械装置、車両などの有形固定資産
- 特許権や商標権などの無形固定資産
- 棚卸資産(在庫)
- のれん(営業権)
買い手は、事業の売却価格のうち、これらの課税資産に対応する部分に対して消費税(10%)を上乗せして売り手に支払う必要があります。
この消費税は、買い手側で仕入税額控除の対象となるため、原則として後日還付されますが、取引時点では一時的に多額の資金が必要となる点に注意が必要です。
また、事業用不動産を譲り受ける場合には、別途不動産取得税や登録免許税も発生します。
M&A専門家に支払う手数料(仲介手数料など)
事業売却は非常に専門的なプロセスであるため、M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)といった専門家のサポートを受けるのが一般的です。
その際に発生する手数料は、主に成功報酬として支払われます。
成功報酬はレーマン方式と呼ばれる計算方法で算出されることが多く、取引金額に応じて一定の料率が適用されます。
| 取引金額 | 成功報酬料率(一般的な例) |
| 5億円以下の部分 | 5.0% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4.0% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3.0% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 2.0% |
| 100億円超の部分 | 1.0% |
その他、相談料や着手金、中間金が必要な場合もありますので、契約前に料金体系をよく確認することが重要です。
事業売却の進め方|相談から完了までの全ステップを解説
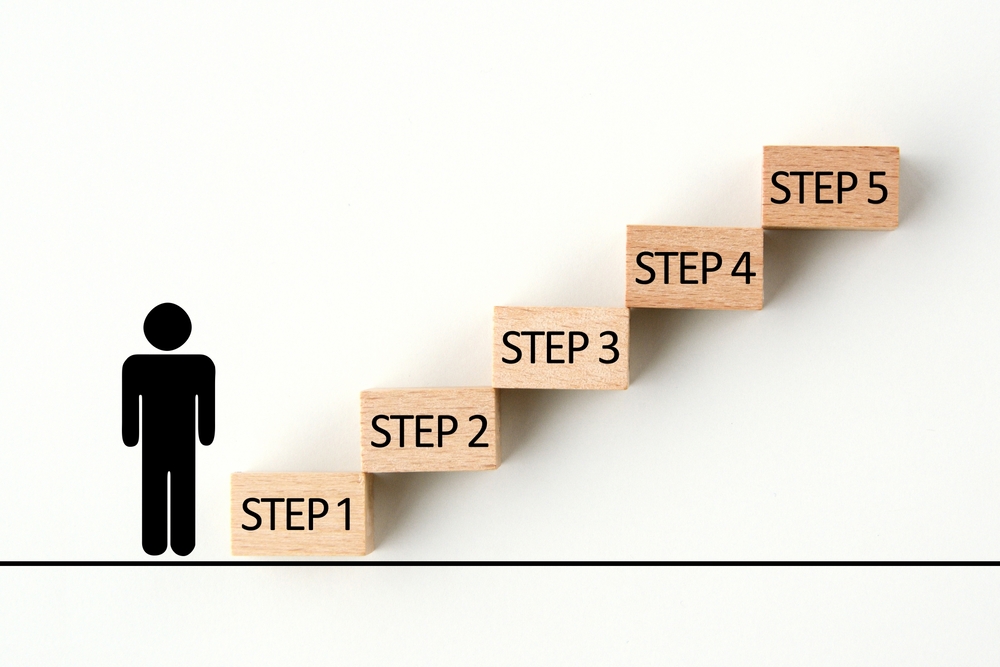
事業売却は、思い立ってすぐにできるものではありません。専門家への相談から最終的な引き渡しまで、通常は半年から1年以上かかる長期的なプロジェクトです。
ここでは、一般的な事業売却のプロセスを6つのステップに分けて解説します。
ステップ1:M&A専門家への相談と売却戦略の策定
事業売却を考え始めたら、まず最初に行うべきは、信頼できるM&Aの専門家(M&A仲介会社、FA、事業承継・引継ぎ支援センターなど)に相談することです。事業売却は秘密保持が極めて重要であり、かつ高度な専門知識が不可欠です。
この段階で専門家と共有すべき内容は以下の通りです。
- 売却を検討する背景や目的
- 対象事業の概要や財務状況
- 売却希望価格や時期などの条件
専門家は、これらの情報をもとに、事業売却の実現可能性や想定される売却価格(バリュエーション)、最適な進め方について客観的なアドバイスを提供してくれます。
ここでの相談を通じて、信頼できるパートナーを見つけることが、プロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
ステップ2:買い手候補の選定と交渉
専門家と正式に契約を結んだ後、具体的な買い手候補を探すプロセスに入りましょう。
専門家は、独自のネットワークやデータベースを活用し、売却対象事業と最も高いシナジー効果が期待できる買い手候補をリストアップします。
この際、売り手企業の社名が特定されないように、ノンネームシートと呼ばれる匿名の企業概要書を用いて、買い手候補に打診を行います。
関心を示した買い手候補とは秘密保持契約(NDA)を締結した上で、より詳細な情報(IM:インフォメーション・メモランダム)を開示し、トップ面談などを通じて、双方の経営方針やビジョン・条件などをすり合わせていくことが重要です。
ステップ3:基本合意契約の締結
複数の買い手候補との交渉を経て、最も条件の良い1社に候補を絞り込み、基本合意契約(MOU)を締結します。
基本合意契約は、現時点での双方の合意事項(譲渡対象、譲渡価格、今後のスケジュールなど)を確認し、認識のズレを防ぐために交わされるものです。この契約には、通常は独占交渉権が付与され、売り手は一定期間、他の候補と交渉することができなくなります。
ただし、この段階での合意内容は最終的なものではなく、法的な拘束力を持たない事項がほとんどです。
ステップ4:デューデリジェンス(買収監査)の実施
基本合意契約を締結した後、買い手側によるデューデリジェンス(DD)が実施されます。これは、買い手が弁護士や公認会計士などの専門家を起用し、売り手企業の事業内容や財務状況、法務面などに問題がないかを詳細に調査するプロセスです。
売り手側は、この調査に全面的に協力し、要求された資料を迅速に提出する必要があります。DDで事前に開示されていなかった重大な問題(簿外債務や訴訟リスクなど)が発見された場合、売却価格の減額や、最悪の場合は交渉決裂に至る可能性もあります。
ステップ5:最終契約の締結と各種決議
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な条件交渉が行われます。双方がすべての条件に合意すれば、法的な拘束力を持つ事業譲渡契約書を締結します。
また、事業売却は会社の重要な経営判断であるため、売り手・買い手双方の会社で取締役会の承認が必要です。
さらに、売り手企業は原則として、株主の3分の2以上の賛成を得る株主総会の特別決議を経なければなりません。
ステップ6:クロージング(事業の引継ぎと対価の決済)
事業譲渡契約書で定められたクロージング日に、事業に関連する資産や権利、契約、従業員などを買い手企業へ引き継ぐ手続きを行います。同時に、買い手から売り手へ、合意した譲渡対価が支払われます。
これをもって、事業売却のすべてのプロセスが完了です。
事業売却を成功させるなら、信頼できる専門家への相談が不可欠

事業売却は、会社全体の経営権を手放すことなく、ノンコア事業の整理や財務改善、事業承継といった経営課題を解決するための極めて有効な戦略的選択肢です。
一方で、そのプロセスは複雑であり、慎重な準備と専門的な知見が求められます。
もし事業売却を少しでも検討されているなら、まずは一度、M&Aの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。自社の状況を客観的に見つめ直し、事業売却を含むさまざまな選択肢の中から、会社の未来にとって最善の一手を見つけるための、大きな一歩となるはずです。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










