【一覧表あり】M&Aの手法を徹底解説|主要な手法の特徴と選び方

M&Aには株式譲渡や事業譲渡、合併、会社分割など多くの手法があり、企業の目的や規模によって適切な方法はさまざまです。
本記事では、M&Aの各手法の特徴やメリット・デメリットをわかりやすく整理しています。さらに、最も選ばれている手法や手法別の事例、適切な手法を選ぶためのポイントまで詳しく解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aの手法とは
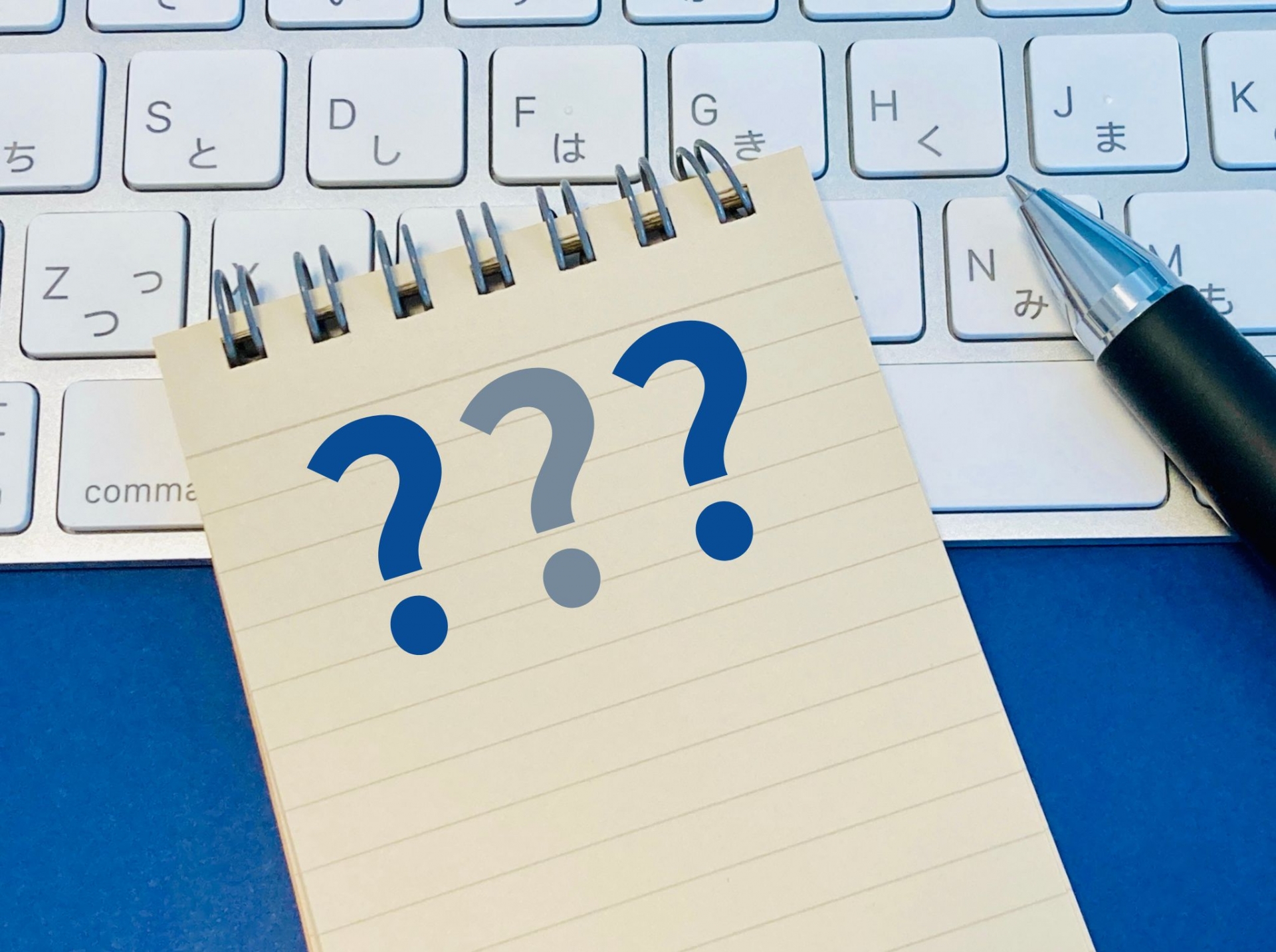
M&Aの手法を理解するために、まずはM&Aそのものの意味と目的、形態を把握することが重要です。
M&Aの意味と目的
M&Aとは、英語の「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の頭文字を取った言葉です。合併や買収の総称であり、2つ以上の会社が1つになったり、ある会社が他の会社を買い取ったりすることを指します。
M&Aは、後継者不足に悩む企業の事業承継だけでなく、事業の拡大、新規市場への参入、技術力の獲得など、さまざまな経営課題を解決する目的で活用できます。
M&Aの形態
M&Aは、その目的や支配権の移転度合いによって、大きく「買収」「合併」「提携」の3つの形態に分類されます。
買収
買収は、ある会社が他の会社の株式や事業を取得し、経営権を握る手法です。
売り手企業の独立性は維持される場合もあれば、完全な子会社となる場合もあります。対象とする範囲や取得方法によって、会社全体の経営権を取得する株式取得や、特定の事業部門のみを取得する事業譲渡など、さまざまな手法があります。
合併
合併は、複数の会社が法的に一つの会社に統合される手法です。
合併に参加した会社のうち、1社だけが存続し、他の会社は消滅する吸収合併が一般的です。すべての会社が消滅し、新たに設立した会社に事業を引き継ぐ新設合併という形態もあります。
提携(広義のM&A)
提携は、経営権の移転を伴わず、複数の会社が協力関係を築く手法です。
互いに株式を持ち合う資本提携や、共同で事業を行う業務提携などがあります。
厳密なM&A(狭義のM&A)には含まれないこともありますが、企業間の連携を強化する戦略として、広い意味でM&Aの一環と捉えられています。
M&Aの手法一覧
M&Aには、これまで説明した形態の中に、さらに具体的な手法が存在します。それぞれの手法は、目的、手続きの複雑さ、税務への影響などが大きく異なります。
まずは全体像を把握するために、主要な手法の特徴を一覧表で確認しましょう。
| 買収
|
株式取得
|
株式譲渡 | 会社の株式を第三者に売却することで、経営権や所有権を移転する |
| 株式交換 | 買い手企業が売り手企業の全株式を取得する対価として、自社の株式を売り手企業の株主に交付する | ||
| 株式移転 | 1つまたは複数の株式会社が、その発行済株式のすべてを新たに設立する会社に取得させる | ||
| 第三者割当増資 | 会社が新たに株式を発行し、それを特定の第三者が引き受ける | ||
| 事業譲渡 | 会社の一部または全部の事業を売買する | ||
| 会社分割
|
新設分割 | 特定の事業を切り離し、別会社に承継させる | |
| 吸収分割 | 既存会社の一部事業を、他の既存会社に承継させる | ||
| 合併 | 吸収合併 | 1つの会社が他の会社を吸収し、吸収された会社は消滅する | |
| 新設合併 | すべての会社が消滅し、新設会社に事業を承継する | ||
| 提携 | 資本提携 | 一方が他方の株式を取得するか、互いに株式を持ち合う | |
| 業務提携 | 資本の移動を伴わず、企業が共同で事業活動を行う | ||
| 合弁会社設立 | 複数の会社が共同で出資し、新しい会社を設立する | ||
買収によるM&A手法

買収は、会社の経営権や特定の事業の取得を目的としたM&A手法です。
買い手企業は必要な経営資源を迅速に獲得でき、売り手企業は事業の継続や創業者利益の確保といったメリットを得られます。
ここでは、代表的な買収手法である「株式取得」「事業譲渡」「会社分割」について詳しく解説します。
株式取得
株式取得は、売り手企業の株式を買い手企業が取得することで、経営権を支配する手法です。
過半数(50%超)の株式を取得すれば、取締役の選任など普通決議を単独で可決でき、実質的な経営権を獲得できます。
| メリット | デメリット |
| – 会社を丸ごと引き継ぐため、許認可や契約関係の再手続きが不要な場合が多い | – 売り手企業の負債(簿外債務含む)もすべて引き継ぐリスクがある |
| – 事業譲渡に比べて手続きが比較的シンプルで、迅速に進められる | – 会社全体を取得するため、不要な事業や資産も引き継ぐことになる |
| – 売り手企業の法人格が維持されるため、従業員や取引先への影響が少ない | – 多額の資金が必要になる |
株式取得の具体的な手法には、以下のようなものがあります。
- 株式譲渡
- 株式交換
- 株式移転
- 第三者割当増資
- 応用的な株式取得の手法(TOB・MBO・LBO)
株式譲渡
株式譲渡は、既存の株主(主にオーナー経営者)が保有する株式を、買い手企業に売却することで経営権を移転する手法です。
売却後は、買い手企業が対象会社の株主となり、会社の権利義務や契約関係はそのまま引き継がれます。
手続きが比較的簡易で、取引コストも低いことがメリットです。
株式交換
株式交換は、買い手企業が売り手企業の全株式を取得する対価として、自社の株式を売り手企業の株主に交付する手法です。
この取引により、売り手企業は買い手企業の100%子会社となります。
対価が自社株式であるため、多額の現金を用意せずにグループ再編や買収を実現できる点が大きなメリットです。
株式移転
株式移転は、1つまたは複数の株式会社が、その発行済株式のすべてを新たに設立する会社(親会社)に取得させる手法です。
株式移転により、既存の会社は新設会社の完全子会社となり、法人格は存続したままグループ経営や持株会社(ホールディングス)体制を構築する際に活用されます。
複数社の株式移転により、すべての参加会社を新設会社の傘下に置くことも可能です。
第三者割当増資
第三者割当増資は、会社が新たに株式を発行し、それを特定の第三者(通常は提携先や投資家)が引き受けることで資金を調達する手法です。
売り手企業は新株発行によって事業資金を得られ、買い手企業は出資を通じて経営への関与や持分を確保します。
主に、業務提携や資本提携を強化する目的で使われます。
応用的な株式取得の手法(TOB・MBO・LBO)
株式取得の中には、上場企業や投資ファンドによる買収など、より大規模なM&Aで活用される手法もあります。
- TOB(株式公開買付): 上場企業の株式を、証券取引所を通さずに株主から直接買い集める手法です。
- MBO(経営陣買収): 会社の経営陣が、株主から自社の株式を買い取り、経営権を取得する手法です。
- LBO(レバレッジド・バイアウト):買い手企業が、売り手企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に資金を調達して買収する手法です。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を、他の会社に売却する手法で、工場や店舗、従業員、ブランド、取引先といった事業を取引の対象とします。
| メリット | デメリット |
| – 必要な事業や資産だけを選択して承継できる | – 資産や契約を個別に移転する必要があり、手続きが非常に煩雑 |
| – 簿外債務など、予期せぬ負債を引き継ぐリスクを回避できる | – 従業員の再雇用契約や取引先との契約再締結が必要になる |
| – 売り手企業は不採算事業を切り離し、主力事業に集中できる | – 事業に必要な許認可を、買い手企業が新たに取得し直さなければならない |
| – 売り手企業は会社を存続させたまま、事業を整理できる | – 譲渡対象の資産に消費税が課されるなど、税負担が大きくなる場合がある |
会社分割
会社分割は、会社が営む事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に包括的に承継させる組織再編の手法です。事業譲渡が個別の資産や契約を移転するのに対し、会社分割は事業を一体として承継する点が大きな違いです。
| メリット | デメリット |
| – 事業を包括的に承継するため、事業譲渡より手続きが簡便な場合がある | – 不要な資産や負債も一体として引き継ぐ可能性がある |
| – 不採算事業の切り離しなど、柔軟な組織再編が可能 | – 手続きが会社法で厳密に定められており、債権者保護手続きなどが必要 |
| – 対価を株式にできるため、買い手企業は多額の現金を用意する必要がない | – 従業員の労働条件など、複雑な調整が必要になる場合がある |
会社分割の具体的な手法は、次のとおりです。
- 新設分割
- 吸収分割
新設分割
新設分割は、既存会社の一部事業を切り出し、新たに設立する会社に承継させる手法です。例えば、複数の事業を持つ企業が特定の事業を独立させ、子会社化する場合などに用いられます。
この手法により、事業ごとの経営資源の集中やグループ再編、新規事業の独立が実現可能です。
吸収分割
吸収分割は、既存会社の一部事業を、他の既存会社に承継させる手法です。
グループ企業内での事業再編や、他社への事業売却の際に活用されます。切り出した事業の権利義務は承継会社に包括的に移転し、分割元会社は存続します。
この手法を用いることで、事業ごとに経営資源を集中させたり、戦略的な事業の継承・統合を効率的に行ったりできます。
合併によるM&A手法

合併は、複数の会社が法的に統合され、一つの法人格になるM&A手法です。
これにより、経営資源の集約、組織の効率化、市場シェアの拡大といった強力なシナジー効果が期待できます。
ただし、異なる組織文化を持つ企業同士が一つになるため、統合プロセス(PMI)には細心の注意が必要です。
| メリット | デメリット |
| – 組織が完全に一つになるため、迅速な意思決定が可能になる | – 異なる人事制度や企業文化の統合に時間とコストがかかる |
| – 重複する部門を統合することで、コスト削減効果が期待できる | – 統合プロセスがうまくいかない場合、従業員のモチベーション低下や離職につながる恐れがある |
| – 企業の規模や信用力が向上し、ブランドイメージの強化につながる | – 株主総会の特別決議や債権者保護手続きなど、法的な手続きが複雑で時間がかかる |
合併の具体的な手法は、次の2つです。
- 吸収合併
- 新設合併
吸収合併
吸収合併は、合併する会社のうち1社のみが存続会社として残り、他の会社(消滅会社)の権利義務すべてを承継して消滅させる手法です。
日本のM&Aにおける合併では、手続きの煩雑さが少ないため、ほとんどの場合この吸収合併が選択されます。
新設合併
新設合併は、合併するすべての会社が解散・消滅し、同時に新しく設立する会社にすべての権利義務を承継させる手法です。
すべての当事会社が対等な立場で統合できるというメリットがあります。しかし、許認可の再取得や上場企業の場合は再上場申請が必要となるなど、手続きが非常に複雑なため、実務で用いられるケースは一般的ではありません。
提携による広義のM&A手法
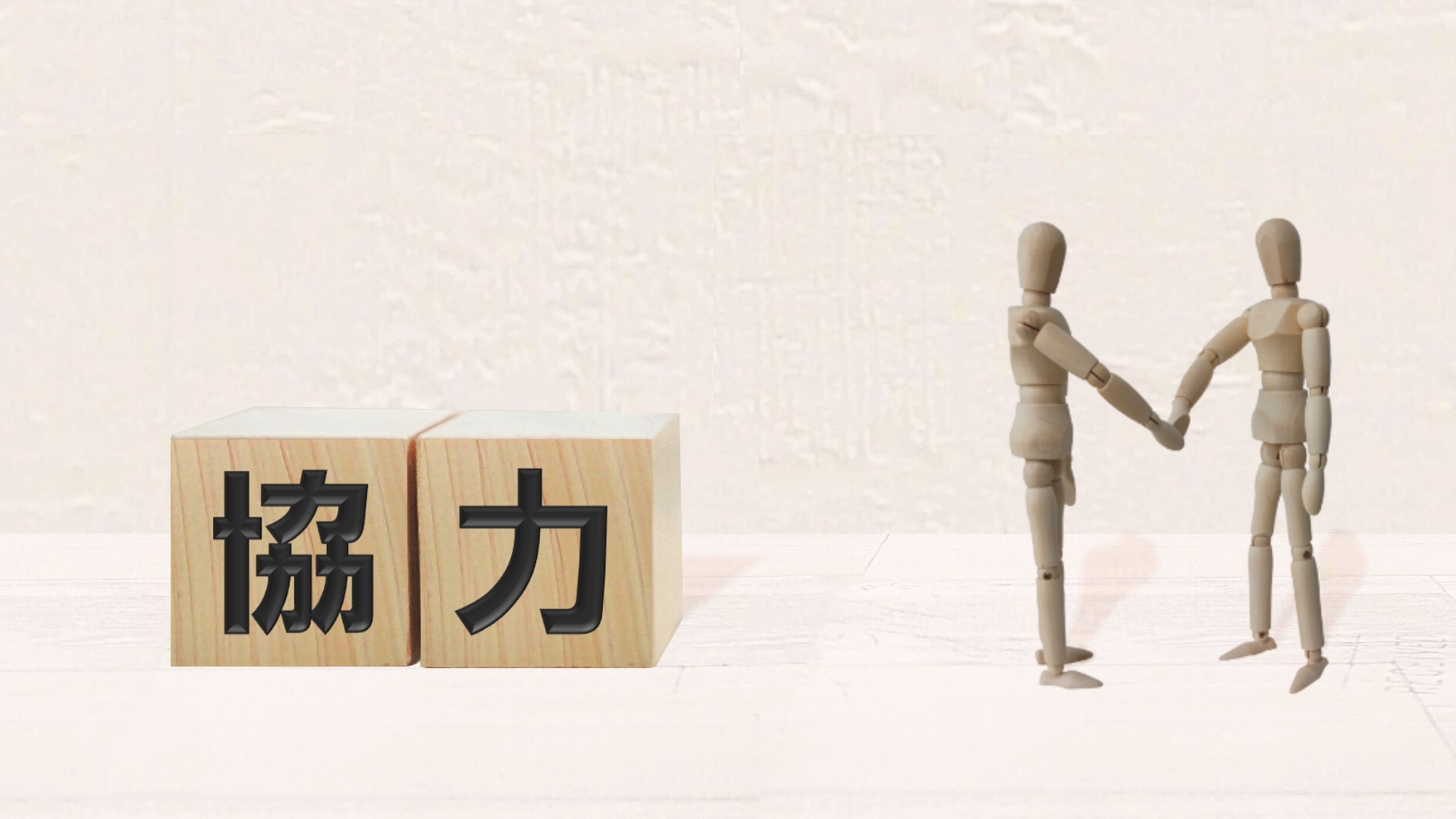
経営権の移転を伴わずに、企業間の協力関係を構築・強化する手法も、広い意味でM&Aの一環と捉えられます。買収や合併に比べてリスクを抑えながら、お互いの強みを活かした事業展開が可能です。
以下のような手法が、広義のM&A手法として挙げられます。
- 資本提携
- 業務提携
- 合弁会社設立
資本提携
資本提携は、一方の会社が他方の会社の株式を取得したり、互いに株式を持ち合ったりすることで、資本関係を伴う協力関係を築く手法です。
株式の保有比率を低く抑えることで、互いの経営の独立性を維持しながら、通常の業務提携よりも強固な関係を構築できます。
| メリット | デメリット |
| – 経営の独立性を保ちつつ、長期的な協力関係を築ける | – 提携関係の解消が難しい場合がある |
| – 資金調達や技術供与など、相互の経営資源を活用できる | – 相手企業の経営不振が自社の株価に影響する可能性がある |
業務提携
業務提携は、資本の移動を伴わず、企業が共同で事業活動を行う手法です。
技術開発、生産、販売など、特定の分野で協力し、互いのノウハウや販路、ブランド力を活用してシナジー効果を狙います。
契約に基づいて行われるため、比較的柔軟に関係を構築・解消できます。
| メリット | デメリット |
| – 低リスクかつ迅速に他社の経営資源を活用できる | – 協力関係が弱く、期待した成果が得られないことがある |
| – 契約内容を自由に設計でき、柔軟な協力が可能 | – 自社の技術やノウハウが流出するリスクがある |
合弁会社設立
合弁会社設立(ジョイント・ベンチャー)は、複数の会社が共同で出資し、新しい会社を設立する手法です。
新規事業への進出や海外展開など、単独ではリスクが高いプロジェクトに取り組む際に活用できます。
各社の強みを持ち寄ることで、リスクを分散しながら事業の成功確率を高められます。
| メリット | デメリット |
| – リスクやコストを参加企業で分担できる | – 参加企業間の意見対立により、意思決定が遅れる可能性がある |
| – 各社の技術やノウハウを融合し、高いシナジーを期待できる | – 運営方針や利益配分を巡ってトラブルになることがある |
最も選ばれているM&A手法とその理由

多様なM&A手法の中で、特に中小企業のM&Aにおいて最も多く採用されているのは株式譲渡です。
中小企業庁のデータによると、M&A支援機関が関与した案件のうち、譲渡側・譲受側ともに7割以上が株式譲渡を選択しています。
| M&Aの手法 | 譲渡側の割合 | 譲受側の割合 |
| 株式譲渡 | 71.3% | 73% |
| 事業譲渡 | 23.8% | 22.4% |
| その他 | 5% | 4.8% |
株式譲渡が中小企業のM&Aにおいて最も選ばれている理由として、以下の点が挙げられます。
- 手続きの簡便さ:
株式譲渡は、株主が保有する株式を売買するだけで経営権が移転するため、事業譲渡や合併に比べて手続きがシンプルです。許認可や契約関係も原則としてそのまま引き継がれるため、事業への影響を最小限に抑えられます。 - オーナーへの対価:
会社の株式を売却することで、創業者であるオーナー経営者は直接的に売却対価を受け取れます。これにより、引退後の生活資金や新たな事業への投資資金を確保できます。
適切なM&A手法の選び方とポイント

自社にとって最適なM&A手法を選択することは、M&Aの成功を左右する極めて重要なプロセスです。
本章で解説するポイントを総合的に検討し、慎重に判断しましょう。
目的・対象を明確にする
まず、「何のためにM&Aを行うのか」「何を譲渡・譲受したいのか」の明確化が重要です。
以下の項目で、自社がM&Aを実施する目的と対象を確認しましょう。
| 検討事項 | 詳細 |
| 売却の範囲 | 会社そのものを引き継いでほしい場合は「株式譲渡」、特定の事業だけを売却したい場合は「事業譲渡」や「会社分割」が候補 |
| 経営への関与度 | 経営権を完全に移転させたいのか、協力関係を築きたいのかによって、「買収・合併」か「提携」かという大きな方向性が決まる |
税金・費用を確認する
M&Aの手法によって、課される税金の種類や発生する費用が大きく異なります。
例えば、事業譲渡では譲渡対象の資産に消費税がかかりますが、株式譲渡ではかかりません。また、合併や会社分割では、税制上の要件を満たす適格組織再編に該当するか否かで、税負担が大きく変わります。
初期段階で専門家と共に税務シミュレーションを行い、コストを比較検討することが重要です。
どのような手続きが必要か把握する
M&Aを検討する際は、まず各手法にどのような手続きが必要かを把握することが重要です。手法ごとに会社法などで定められた手続きがあり、所要時間や会社にかかる負担が異なるため、事前に次のような点を確認しておく必要があります。
- 手続きの複雑さと期間:
株式譲渡は比較的シンプルで短期間で進められるケースが多い一方、合併や会社分割では株主総会の特別決議や債権者保護手続きが必要になることがあり、数カ月から1年以上かかる場合もあります。 - 許認可の引継ぎ:
建設業や飲食業など、許認可が必要な事業では、手法によっては許認可を再取得しなければならないこともあり、事業が一時的に停止するリスクを考慮する必要があります。
ステークホルダーへの影響を考慮する
M&Aは、従業員や取引先、金融機関など、多くの関係者(ステークホルダー)に影響を与えます。
そのため、従業員の雇用契約をどう引き継ぐか、取引先との関係をどう維持するかなど、手法ごとの影響を事前に分析し、丁寧なコミュニケーションプランを準備しておくことが、M&A後の円滑な事業運営につながります。
専門家に相談する
M&Aの手法選択には、法務、税務、会計など高度な専門知識が求められるため、自社だけで最適な判断を下すのは非常に困難です。そのため、M&Aを検討し始めた段階で、専門家に相談することが重要です。
M&A仲介会社などの専門家は、豊富な経験と知識に基づき、企業の状況や目的に合わせた最適なスキームを提案してくれます。客観的なアドバイスを受けながら検討を進めるようにしましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
手法別M&A事例
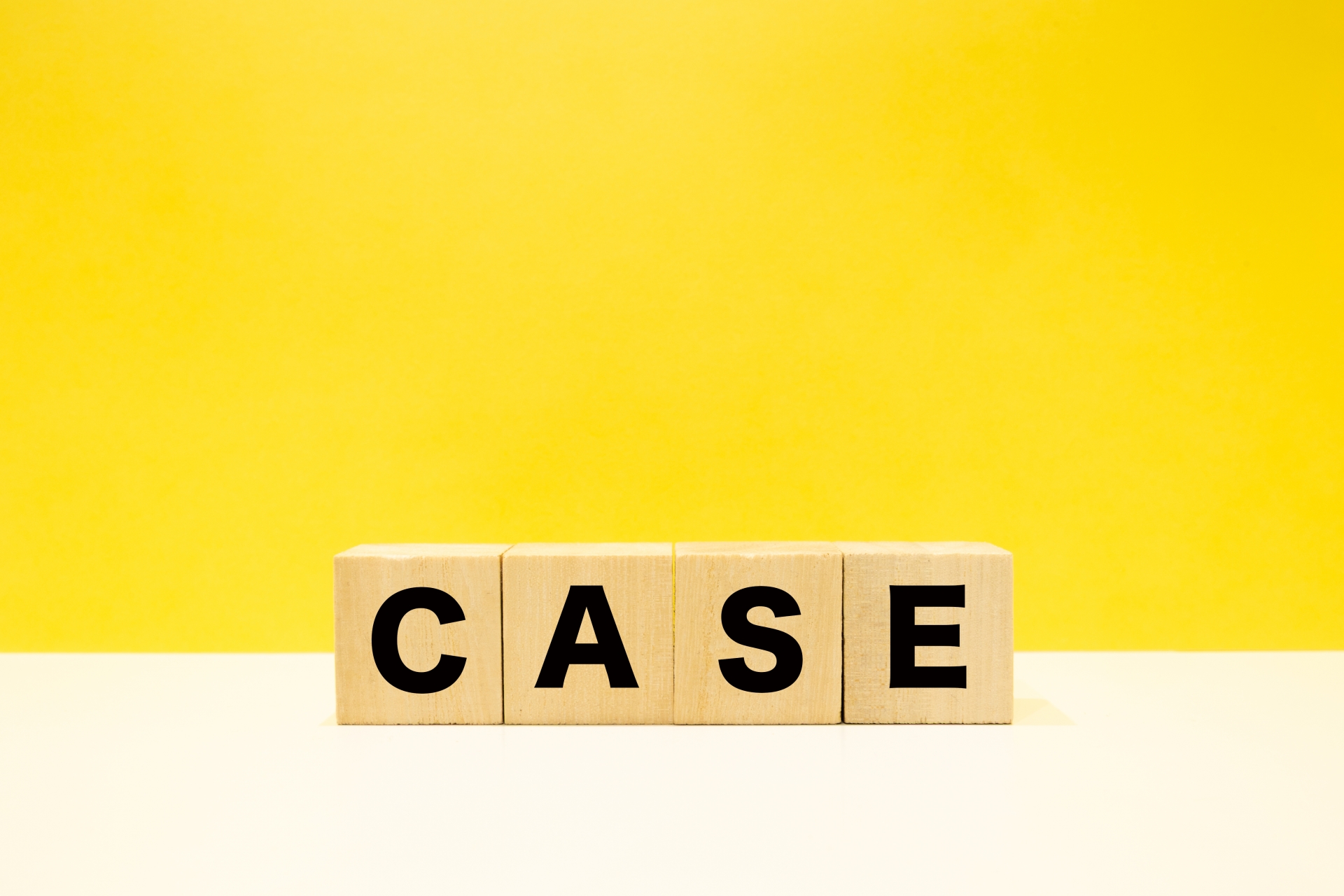
本章では、実際に行われたM&Aの事例を手法別に紹介します。
どのような目的で各手法が選択されたのか、具体的なイメージをつかみましょう。
株式取得による事例
(事例)KDDIによるローソンのTOB(株式公開買付)
2024年、KDDIはコンビニ大手のローソンに対し、TOB(株式公開買付)を実施し、株式の50%を取得しました。これによりKDDIはローソンの経営権の一部を取得し、三菱商事と共同で経営する方針を発表しました。
このTOBでは、双方の顧客基盤や店舗網を活用した新サービス創出が目的とされています。
| 事例概要 | 内容 |
| 手法 | 株式取得(TOB:株式公開買付) |
| 売り手 | ローソン株式会社(既存株主) |
| 買い手 | KDDI株式会社(三菱商事と共同で経営) |
| 取得割合 | 株式の50% |
| 目的 | – 通信事業とコンビニ事業の異業種連携
– 両社の顧客基盤・店舗網を活用した新サービス創出 |
(参考:株式会社ローソン|プレスリリース)
事業譲渡による事例
(事例)ブログウォッチャーによるコロプラ「おでかけ研究所」の事業譲受
2021年6月、コロプラは位置情報分析コンサルティングサービス「おでかけ研究所」事業を、ブログウォッチャーに事業譲渡しました。
コロプラはゲームやVR、投資事業など幅広く展開する一方、ブログウォッチャーはユーザープロファイルや行動分析を活用したソリューション事業を手がけています。
両社は以前から「おでかけ研究所」事業で協力関係があり、今回の事業譲渡により、事業の持続的な成長と価値向上を目指しています。
| 事例概要 | 内容 |
| 手法 | 事業譲渡 |
| 売り手(譲渡会社) | コロプラ株式会社 |
| 買い手(譲受会社) | 株式会社ブログウォッチャー |
| 譲渡対象 | 「おでかけ研究所」事業(位置情報分析コンサルティングサービス) |
| 目的 | – 事業の持続的な成長
– 事業価値の向上 |
会社分割による事例
(事例)楽天による楽天カードの吸収分割
2023年8月10日、楽天グループ株式会社は、グループ内のフィンテック事業の再編を目的として、以下の2つの組織再編を発表しました:
- 会社分割(簡易吸収分割):楽天グループが運営する「楽天ペイ(オンライン決済)事業」と「楽天ポイント(オンライン)事業」を、連結子会社である楽天ペイメント株式会社に承継させました。
- 株式交付:楽天グループが保有する楽天ペイメント株式会社の全株式(楽天ペイメントの発行済株式総数の95.28%)を、連結子会社である楽天カード株式会社に移管しました。
| 事例概要 | 内容 |
| 手法 | 吸収分割(簡易吸収分割) |
| 分割元 | 楽天グループ株式会社 |
| 承継先 | 楽天ペイメント株式会社、楽天カード株式会社 |
| 目的 | -フィンテック事業の再編と一元化 -キャッシュレス決済サービスの競争力強化 |
(出典:楽天グループ株式会社│プレスリリース)
合併による事例
(事例)ファミリーマートとユニーグループ・ホールディングスの吸収合併
2016年、ファミリーマートは、サークルKサンクスを運営するユニーグループ・ホールディングスを吸収合併しました。
コンビニ業界の競争が激化する中、経営資源を統合して店舗網や商品開発力を強化し、業界内での地位確立を目的とした大型合併でした。
| 事例概要 | 内容 |
| 手法 | 吸収合併 |
| 消滅会社 | ユニーグループ・ホールディングス(サークルKサンクス運営) |
| 存続会社 | ファミリーマート株式会社 |
| 目的 | – 経営資源の統合による店舗網の強化
– 商品開発力の向上 |
提携による事例
(事例)トヨタ自動車とスズキの資本提携
2019年、トヨタ自動車とスズキは、自動運転などの次世代技術分野で協力関係を強化するため、資本提携に合意しました。
両社の独立性を尊重しながら、それぞれの得意分野(トヨタの電動化技術、スズキの小型車開発)を活かし、長期的な視点で協力していくことを目的としています。
| 項目 | 内容 |
| 手法 | 資本提携 |
| 出資側 | トヨタ自動車株式会社 |
| 出資を受ける側 | スズキ株式会社 |
| 対象・内容 | 次世代技術の協力を目的とした資本関係の構築 |
| 目的 | – 自動運転などの次世代技術分野で協力関係を強化
– 両社の得意分野を活かした長期的な事業協力 – 独立性を維持しつつ戦略的連携を推進 |
(出典:トヨタ自動車株式会社│ニュースリリース)
自社にとって最適なM&A手法を見極めよう

本記事では、M&Aの主要な手法である「買収」「合併」「提携」と、それに含まれる具体的な手法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説しました。
中小企業のM&Aでは手続きが簡便な「株式譲渡」が主流ですが、必ずしもそれが唯一の正解ではありません。
自社の事業内容、M&Aの目的、従業員や取引先への影響、そして税務上の観点などを多角的に検討し、適切な手法の選択がM&A成功の鍵です。
M&Aは専門知識が必要な複雑な手続きが伴います。
判断に迷う場合は、自己判断で進めるのではなく、M&A仲介会社などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受け、リスクを抑えつつ、円滑にM&Aを実現しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










