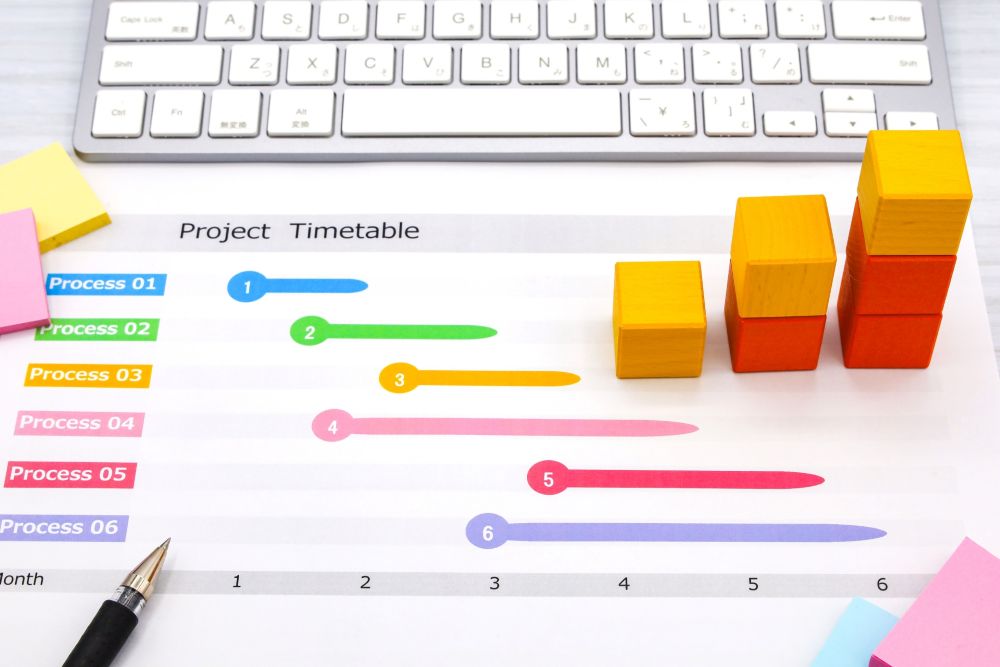M&Aの流れを完全解説|検討から統合までの全プロセスと成功のポイント

M&Aを成功させるには、複雑な流れを正しく理解することが不可欠です。しかし、M&Aは準備から成立まで半年から1年以上を要する長期のプロセスであり、各段階で専門的な判断が求められるため、「何から始め、どう進めるべきか」と悩む経営者の方は少なくありません。
本記事では、M&Aの全体像を明確にするために、基本となる9つのステップを3つのフェーズに分けて徹底解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aプロセスの全体像と基本の9ステップ

本章では、検討の開始から最終的な決済が完了するまでのM&Aの基本的な9つのステップを解説します。
ステップ1.相談
M&Aの検討段階で、まず信頼できる専門家と相談しながらM&Aの目的を明確化します。
【M&Aの主な目的の例】
- 後継者問題を解決したい
- 従業員の雇用や取引先との関係を維持したい
- 創業者利益を確保したい
- 大手企業の傘下に入り、事業をさらに成長させたい
目的が明確であれば、買い手探しや相手企業との交渉において強気の姿勢を貫きやすくなります。
ただし、自社だけでM&Aの要件を客観的に整理することは大変困難です。経営者自身の思い入れが判断を鈍らせたり、自社の本当の価値や潜在的なリスクを見落としたりする可能性があるためです。
M&A仲介会社などの専門家は、客観的な視点から自社の強み・弱みを分析し、M&A戦略立案をサポートしてくれるため、M&Aの検討段階からの相談を推奨します。
ステップ2.現状のヒアリング・ご提案
次のステップでは、専門家が会社の財務状況や事業内容、M&Aの目的をヒアリングし、具体的な戦略を提案します。
より精度の高い提案を受けるには、ヒアリング時の正確な情報提供が欠かせません。ただし不適切な情報管理によりM&Aの検討が外部に漏洩すると、M&Aの進行に支障が生じる恐れがあります。
そのため、M&A仲介会社に自社の財務諸表や事業計画などの重要な機密情報を共有する前に、「秘密保持契約(NDA)」を締結することが一般的です。情報漏洩の懸念なく自社の現状を伝えられれば、より現実に即した的確なM&A戦略の提案が受けられます。
M&A仲介会社とは?FAとの違いや選び方・メリットを徹底解説
ステップ3.契約
M&Aの支援を正式に依頼する専門家を決め、「アドバイザリー契約」を締結します。
アドバイザリー契約書には、専門家が提供するサービスの範囲や報酬、手数料の体系、秘密保持、契約期間、解除条件などが明記されているので、内容を十分に理解し、納得した上で契約することが大切です。
特にM&A仲介の報酬には着手金や相談料、中間金、月額料金、成果報酬などがあり、仲介会社によっても体系が異なるため、自社に適した方法を選ぶ必要があります。
ステップ4.企業概要書の作成
買い手候補に自社の魅力を伝えて交渉の土台を築くため、「企業概要書」の作成と「企業価値評価(バリュエーション)」を行います。
企業概要書(インフォメーション・メモランダム)は、買い手がM&Aを検討する際の重要な判断材料の一つです。
自社の魅力を客観的なデータや根拠と共に示すことで、自社に関心を持つ買い手候補が見つかる可能性が高まり、希望に近い価格で売却交渉を進めやすくなります。そのため、専門家と連携し、以下の内容を盛り込んだ魅力的な企業概要書を作成することが大切です。
- 事業内容とビジネスモデル
- 財務状況(過去数年分の推移)
- 組織体制と従業員に関する情報
- 他社にはない独自の強み(技術、ブランド、顧客基盤など)
- 事業の将来性や成長戦略
同時に、交渉の基準となる自社の価値を算定する「企業価値評価」を実施します。評価のアプローチは専門家と相談のうえ、以下の3種類から自社の状況に最も適した方法を選択します。
| 評価アプローチ | 主な考慮要素 | 概要 |
| コストアプローチ | 純資産 | 会社の貸借対照表(B/S)上の資産から負債を差し引いた価値を基準に算出する。 |
| インカムアプローチ | 将来の収益力 | 会社が将来生み出すと予測されるキャッシュフローを基に価値を算出する。 |
| マーケットアプローチ | 市場での類似取引 | 上場している同業他社や、過去の類似M&A事例などを参考に価値を算出する。 |
M&Aの企業価値評価とは?基本的な算出方法と売り手・買い手のポイントを解説【2025年最新】
ステップ5.マッチング・トップ面談
次のステップでは買い手候補を探し、関心を示した企業の経営者と「トップ面談」を行います。
まず、M&A仲介会社が、社名を伏せて業種・エリア・事業規模・譲渡理由などを記載した「ノンネームシート」で買い手候補へ打診します。ノンネームシートであれば情報漏洩のリスクを抑えつつ、広く関心を持つ企業を探すことが可能です。
そして関心を示した企業とはNDAを締結したうえで、詳細な企業概要書を開示し、双方の意向が合えば経営者同士のトップ面談へと進みます。
トップ面談は、譲渡価格などの条件だけでなく、経営理念やビジョン、企業文化といった目に見えない価値観の相性も確認する重要な機会です。
トップ面談の際にお互いの相性を慎重に見極めないと、仮にM&Aが成立しても後の統合プロセス(PMI)で組織が融合せず、シナジー効果を得られない可能性がある点に留意しましょう。
ステップ6.基本合意契約締結
トップ面談を経て、M&Aの基本的な条件について大筋で合意でき、双方のM&Aに対する意思が固まった段階で、現時点での合意事項を書面にまとめた「基本合意書(LOI)」を締結します。
独占交渉権や秘密保持義務といった一部の条項を除き、基本合意契約に法的拘束力はありません。最終的な調整の余地は残しつつ、M&A実施の意思と今後のスケジュールを確認することが主な目的です。
ただし、上場企業の場合、基本合意契約締結時点で株主や投資家にM&A情報を開示する必要があるため、心理的な拘束力はあるといえます。
ステップ7.買収監査(デューデリジェンス)
基本合意書を締結したら、買い手が売り手企業の価値とリスクを詳細に調査する「デューデリジェンス(DD)」を実施します。
買い手は、財務・法務・人事・事業など多角的な視点から、基本合意書で合意した内容に相違がないか、開示されていない重大なリスクが隠れていないかを、1〜2カ月かけて徹底的に調査します。
もし、貸借対照表に記載されていない簿外債務(未払残業代、退職給付引当金など)や、将来の訴訟につながる法務上の問題が買収後に発覚すれば、買い手は想定外の損失を被り、経営計画が頓挫する恐れがあります。
買い手が売り手の負債やリスクもすべて引き継ぐM&Aにおいて、デューデリジェンスは最終判断を下すために欠かせないプロセスです。売り手は、要求された資料を正確かつ迅速に開示し、調査に協力する姿勢を示さなければなりません。
ステップ8.最終契約書の締結
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終的な条件交渉を行い、法的な拘束力を持つ「最終契約書(DA)」を締結します。
この際にデューデリジェンスで判明したリスクを、最終的な譲渡価格や取引条件に反映させます。具体的には、発見されたリスク分を価格から減額する、あるいは売り手がクロージング(最終決済)までに問題を解決することを契約の前提条件とするといった調整です。
最終契約書には、M&Aの実行を法的に約束するさまざまな条項が盛り込まれますが、特に「表明保証」は重要性の高い条項です。表明保証とは、売り手が買い手に対して「開示した財務や法務に関する情報が真実かつ正確である」ことを保証する条項です。
もし契約後に表明保証の内容に違反する事実が発覚した場合、売り手は契約に定めた範囲内で買い手に対し損害賠償責任を負う可能性があります。そのため、特に表明保証の範囲については弁護士を交えて慎重に確認し、合意形成を進めることが必要です。
M&Aの相場は利益の何倍?価格算定方法から高値売却の5つのコツまで徹底解説
ステップ9.クロージング(決済)
最終契約書で定められた内容を実行し、M&Aを完了させる手続きが「クロージング」です。
クロージング日当日に、売り手による株式や事業資産の譲渡と、買い手による譲渡対価の支払いを同時に実行します。この手続きをもってM&Aは法的に完了し、会社の経営権が買い手へ正式に移転します。
最終契約の締結からクロージングまでは、1カ月程度の期間を設けることが一般的です。ただし、事業に必要な許認可の再取得や、独占禁止法に基づく公正取引委員会への届出が必要な場合や、スキームによっては半年から1年以上を要するケースも少なくありません。
クロージングの実行には、契約書で定められた「クロージングの前提条件」をすべて満たす必要があります。準備不足から前提条件を満たせない場合、契約が解除されたり、相手方から不利な条件変更を要求されたりするリスクが生じます。
そのため、必要な手続きを洗い出した上で、余裕を持ったスケジュールで臨むことが重要です。
e-Gov法令検索「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条2項」
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aクロージング後~PMIの流れ

M&Aは、法的な契約が完了した時点で終わりではありません。M&Aで期待するシナジー(相乗効果)を創出し、最終目的を達成できるかどうかは、クロージング後の「PMI(Post Merger Integration:経営統合プロセス)」の成否にかかっています。
PMIとは、M&A(合併・買収)後の統合プロセスを指す言葉です。クロージング後からPMIへの主な流れは以下の通りです。
| プロセス | 詳細 |
| 1.財務諸表の確定と対価調整 | 期首からクロージング時点までの財務諸表を確定させ、最終的な譲渡価格の調整を行う。 |
| 2.各種移転手続き | 買収対象企業の資産(不動産など)や権利(契約関係)を法的に買い手へ移転する。 |
| 3.許認可の再申請・届出 | 事業に必要な許認可の再申請や届出を行う。業種やM&Aスキームによって要否が異なる。 |
| 4.PMI(経営統合)の実行 | 短期的な統合計画を実行しつつ、中長期的な計画を策定・推進する。 |
クロージング後、まずは財務・法務上の手続きを完了させます。同時に、経営理念のすり合わせから、業務プロセスの標準化、人事評価制度やITシステムの統合まで、多岐にわたるPMIをスタートします。
PMIが計画通りに進まないと、組織文化の対立による生産性の低下を招き、期待したシナジーが得られない恐れがあります。
M&Aの成果を出すためには、クロージング前からPMIの入念な計画を立て、M&A実行後も継続的に進捗をモニタリングしながら、課題を解決していくプロセスが不可欠です。
PMI(ポストマージャーインテグレーション)の重要性 – 株式会社M&Aフォース
M&Aの主要な契約書と必要書類一覧
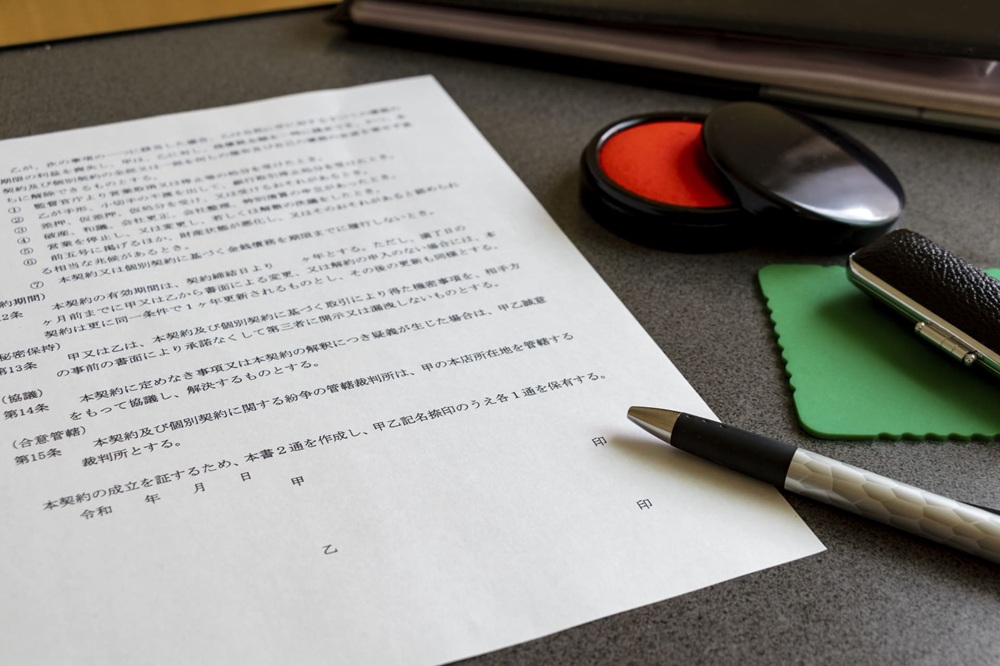
M&Aを円滑かつ安全に進めるためには、各プロセスで適切な契約書を締結し、自社の権利と利益を守ることが不可欠です。ここでは、M&Aで特に重要となる5つの契約書について、締結のタイミングと目的を解説します。
秘密保持契約書
M&Aの検討を開始する際、最初に締結するのが秘密保持契約書です。M&Aを検討している事実そのものが極めて重要な秘密情報であり、外部への漏洩は深刻な経営リスクに直結します。
情報漏洩が起きると、従業員の動揺による離職や、取引先の不安による取引解消を招きかねないため、相手方に対して法的な守秘義務を課し、情報漏洩リスクを抑制する役割を持ちます。
【主な記載事項】
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務の範囲
- 目的外使用の禁止
- 情報の返還・破棄義務
- 契約違反時の損害賠償
アドバイザリー契約書
M&A仲介会社などの専門家へ正式に支援を依頼する際の業務委託契約です。
M&Aサポートの契約形態や業務内容は、提供元の会社や業態によって異なります。契約の金額も高額なため、契約内容を正しく提示・確認せずに契約を締結すると、後に大きなトラブルにつながりかねません。
依頼者が納得して契約できるよう、業務内容や報酬の詳細について書面で明確に示すことが大切です。
【主な記載事項】
- 委託する業務の具体的な範囲
- 報酬体系(着手金、中間金、成功報酬など)と支払時期
- 秘密保持義務
- 契約期間と解除条件
意向表明書(LOI)
買い手が売り手に対し、M&Aへの意欲と現時点での希望条件を伝えるための書類です。通常、トップ面談後に買い手から提示されます。
この書類に法的な拘束力は原則ありませんが、その後の基本合意に向けた交渉の土台となる重要な文書です。売り手は、意向表明書の内容から買い手の本気度や条件を評価し、交渉を進めるかどうかを判断します。
【主な記載事項】
- M&Aの目的とスキーム
- 希望する譲渡価格の範囲とその算定根拠
- M&A後の経営方針や従業員の処遇に関する考え
- 今後のスケジュール案
- デューデリジェンスの実施範囲
基本合意書
デューデリジェンスの前に、現時点での基本的な合意事項を書面で確認する契約です。
基本合意の際には、買い手に一定期間、他の候補者と交渉しないことを約束させる「独占交渉権」を付与することが一般的です。デューデリジェンスの負担が生じる買い手にとって、独占交渉権は安心して調査に臨むための前提条件となります。
譲渡価格などの主要な条件については、今後最終的な調整が生じることから、基本合意書に法的な拘束力は生じません。
【主な記載事項】
- M&Aの手法(株式譲渡、事業譲渡など)
- 譲渡価格の目安
- デューデリジェンスの実施期間と協力義務
- 独占交渉権の付与
- 有効期間
最終譲渡契約書
M&Aのすべての取引条件を法的に確定させる契約書です。M&Aのスキームに応じて「株式譲渡契約書」や「事業譲渡契約書」とも呼ばれます。
最終譲渡契約書には法的拘束力があるため、違反した場合には、契約内容に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。
そのため、特に表明保証や補償・賠償の対象範囲については、弁護士などの専門家を交えて記載する内容を慎重に精査することが必要です。
【主な記載事項】
- 最終的な譲渡対象と譲渡価格
- クロージングの前提条件
- 表明保証
- 当事者の誓約事項
- 補償・賠償に関する条項
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
中小企業のM&Aを成功に導く6つのポイント

これまでのプロセスを踏まえ、特に中小企業の経営者がM&Aを成功させるために押さえておくべき重要なポイントを6つに絞って解説します。
目的と譲れない条件を明確にする
M&Aの交渉を始める前に、自社にとっての「成功の定義」と「絶対に譲れない条件」を明確に言語化しておく必要があります。
M&Aのプロセスでは、価格、スケジュール、従業員の処遇など、数多くの決断を迫られます。判断の拠り所となる「目的」が曖昧だと、目先の金額や条件に流され経営判断を誤ることにもなりかねません。
たとえば、譲渡価格の高さを追求した結果、長年会社に貢献した従業員の雇用が守られなかったり、築き上げてきた取引先との関係が断絶されたりするケースは少なくありません。
M&Aの初期段階で、「従業員の雇用は維持する」「地域経済へ貢献し続けるため工場は閉鎖しない」といった具体的な条件を定めておくことで、交渉の軸がぶれずに済みます。
情報管理を徹底する
M&Aを検討している事実が外部に漏れることは、交渉の成否や事業そのものに深刻なダメージを与えるため、情報管理の徹底はM&A成功の必須条件です。
万が一、M&Aの情報が漏洩した場合、以下のリスクが生じます。
- 従業員の動揺と人材流出:自身の処遇に不安を感じた優秀な従業員が、会社から離れてしまう恐れがあります。
- 取引先の離反:M&A後の関係性に不安を抱いた取引先が、取引を縮小・停止する可能性があります。
- 買い手からの不信感:情報管理がずさんと捉えられ、交渉の足元を見られたり、デューデリジェンスがより厳格になったりします。
社内でM&Aの検討に関わるメンバーは必要最小限に絞り、専門家とは速やかに秘密保持契約を締結するなど、情報の取り扱いには細心の注意を払わなくてはなりません。
デューデリジェンスに時間をかける
買い手によるデューデリジェンス(買収監査)には、時間をかけて誠実に対応しましょう。このプロセスは、買い手との信頼関係を築き、最終契約を有利に進めるための重要な機会だからです。
デューデリジェンスは、買い手が売り手企業の潜在的なリスクを洗い出すための調査です。自社のネガティブな情報を意図的に隠ぺいすると、買い手の不信感を招き、大幅な価格引き下げや交渉決裂につながりかねません。
むしろ交渉に不利になりそうな情報であっても、自社の課題や弱みを正直に開示した上で、改善策を提示するほうが買い手からの信頼を得やすくなります。
また、デューデリジェンスで発覚した問題を解決しないまま最終契約を結ぶと、後に「表明保証違反」で売り手が損害賠償責任を負うリスクもあります。自社を守るためにも専門家と連携し、迅速かつ正確な情報開示に努める姿勢が重要です。
PMIの重要性を理解する
M&Aの真の成功は、契約締結後に行われるPMI(Post Merger Integration)が円滑に進んで初めて達成されます。売り手としても、PMIの成功に協力する姿勢が不可欠です。
異なる文化や業務プロセスを持つ組織の統合には、想定以上の困難を伴うことが一般的です。PMIが失敗すれば、従業員のモチベーション低下や主要人材の離反、顧客離れなどを招き、期待したシナジー効果を得られなくなります。
このPMIを成功させるには、売り手側も買い手任せにせず、積極的な協力が不可欠です。
- 主要な従業員(キーパーソン)に対し、M&Aの背景や目的を丁寧に説明し、統合への協力を促す。
- 業務内容やノウハウが円滑に引き継がれるよう、詳細な引継ぎ資料を作成する。
- 買い手の経営陣と従業員との間で、円滑なコミュニケーションの橋渡し役を担う。
こうした協力的な姿勢がM&A後の事業成長を後押しし、結果的に双方にとって良い結果をもたらします。
M&A完了後の事業展開を見据える
相手企業を選ぶ際には、譲渡価格だけでなく統合後の事業展開を見据え、「自社の事業を最も成長させてくれるのは誰か」という視点で選ぶことが重要です。M&Aは単なる会社売却ではなく、自社が新たな成長ステージに進むための手段だからです。
譲渡後の事業がどのように展開されていくのか、ビジョンを買い手と共有できていれば、従業員や取引先も将来に不安を抱くことなく、新しい体制を前向きに受け入れられます。
たとえば「自社の持つ技術力と、買い手の持つ販売網を組み合わせることで、どのようなシナジーが生まれるのか」など、トップ面談の段階から具体的な事業展開について深く議論し、ビジョンを共有できる相手が、最善のパートナーといえます。
信頼できるM&A仲介会社をパートナーに選ぶ
M&Aの成否は伴走する専門家の質に大きく左右されるため、自社にとって最適なパートナーを慎重に選ぶプロセスが重要です。
M&A仲介会社を選ぶ際には専門知識や経験だけでなく、自社との相性も考慮しなければなりません。依頼を検討している仲介会社を以下のポイントでチェックしましょう。
| チェックポイント | 詳細 |
| 実績と専門性 | 自社の業界や事業規模に近いM&Aの実績が豊富か。 |
| 料金体系の透明性 | 着手金や中間金の有無、成功報酬の算定基準が明確で、納得できるか。 |
| 担当者との相性 | 親身に話を聞き、誠実な対応をしてくれるか。自社の状況を深く理解しようと努めているか。 |
| メリットとデメリットの説明 | M&Aのメリットだけでなく、潜在的なリスクやデメリットについても正直に説明してくれるか。 |
複数の会社を比較検討し、統合後まで責任を持って自社に寄り添ってくれるパートナーを選ぶことが、M&A成功への最も確実な近道です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aに成功するための仲介会社の選び方

M&Aの成否は、伴走するM&A仲介会社の質に大きく左右されます。ここでは、後悔しない会社選びのための4つの視点を解説します。
自社の業界や規模に特化した実績と専門性があるか
自社の業界や事業規模に特化した支援実績が豊富なM&A仲介会社を選ぶことが、交渉を有利に進める上で極めて重要です。
M&Aにおける企業価値評価やリスク判断は、業界特有の商慣習、規制、将来性などに大きく左右されます。たとえば、建設業であれば「経営事項審査」、IT業界であれば「技術者の定着率」が企業価値を大きく変動させる要因です。
業界に精通していない仲介会社では、企業の専門的な価値を正しく評価できず、不当に安い価格で売却してしまうリスクがあります。
一方、特定の業界に強みを持つ仲介会社であれば、業界内の有力な買い手候補との独自ネットワークも期待でき、より良い条件でのマッチングが実現しやすくなります。仲介会社のWebサイトで、自社と同業種・同規模の企業のM&A成約実績を確認しましょう。
料金体系は明確か
契約前に料金体系の全体像を正確に把握し、特に「着手金」や「中間金」の有無を必ず確認しましょう。
M&A仲介会社の報酬体系は、以下のいずれか、または組み合わせです。
| 報酬体系 | 支払いタイミング |
| 着手金 | 業務委託契約時 |
| 中間金 | 基本合意時 |
| 月額報酬(リテイナーフィー) | 業務委託契約時~M&A成立までの毎月 |
| 成功報酬 | M&A成立時(売買金額の1~5%など) |
M&A仲介会社の料金体系はさまざまで、たとえばM&Aの成否にかかわらず相談開始時に「着手金」、基本合意時に「中間金」といった費用が発生する会社の場合、万が一M&Aが不成立に終わった場合でも返金されないため、売り手にとっては金銭的リスクにもなります。
一方で、M&Aが成立するまで一切費用がかからない「完全成功報酬制」の場合は、売り手が初期費用を抑え、M&Aが不成立に終わった場合のリスクを回避できるため、安心して相談を進めやすいでしょう。
M&Aにおけるレーマン方式とは? – 株式会社M&Aフォース
手厚いサポート体制があるか
M&Aの初期相談から契約後のPMIまで、法務・税務などを含めて一貫してサポートしてくれる体制が整っているかも確認しましょう。
M&Aは法務、税務、労務など多岐にわたる専門知識が求められるプロセスです。仲介会社に弁護士、公認会計士、税理士などとの連携体制が整っていない場合、問題が発生するたびに自社で専門家を探さねばならず、時間のロスが交渉停滞の要因にもなりかねません。
交渉をスムーズに進めるためにも、社内に専門家を抱えている、あるいは強固な提携ネットワークを持つ仲介会社を選ぶことが大切です。複雑な問題にも迅速かつワンストップで対応できるため、経営者は精神的な負担が軽減され本業に集中できます。
担当コンサルタントは信頼できるか
会社の看板だけでなく、実際に交渉の最前線に立つ「担当コンサルタント」個人の資質を厳しく見極めることが、M&Aの成否を分けます。
数カ月から1年以上に及ぶ長期プロジェクトのM&Aにおいて、担当コンサルタントは会社の機密情報を共有し、困難な交渉を共に乗り越えるパートナーであり続けます。担当者との相性が悪かったり技量に問題があったりすると、経営判断に支障が生じる恐れがあります。
自社の未来を託せる人物かどうかを判断するために、以下の点を確認しましょう。
- リスクの説明:M&Aのメリットだけでなく、潜在的なデメリットやリスクについても包み隠さず説明してくれるか。
- 傾聴力と理解力:自社の歴史や事業への想いを真摯に聞き、深く理解しようと努めているか。
- 客観的な視点:経営者の意見を尊重しつつも、言うべきことは客観的な視点から臆せず伝えてくれるか。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&Aは専門家のサポートを受けて進めよう
 M&Aプロセスの流れは大変複雑であり、判断を誤れば期待するシナジーを得られなくなるリスクもはらんでいます。
M&Aプロセスの流れは大変複雑であり、判断を誤れば期待するシナジーを得られなくなるリスクもはらんでいます。
M&Aを成功させるためには、プロセスを一貫して伴走してくれて、あらゆるリスクに共に向き合ってくれる専門家をパートナーに選ぶことが大切です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)