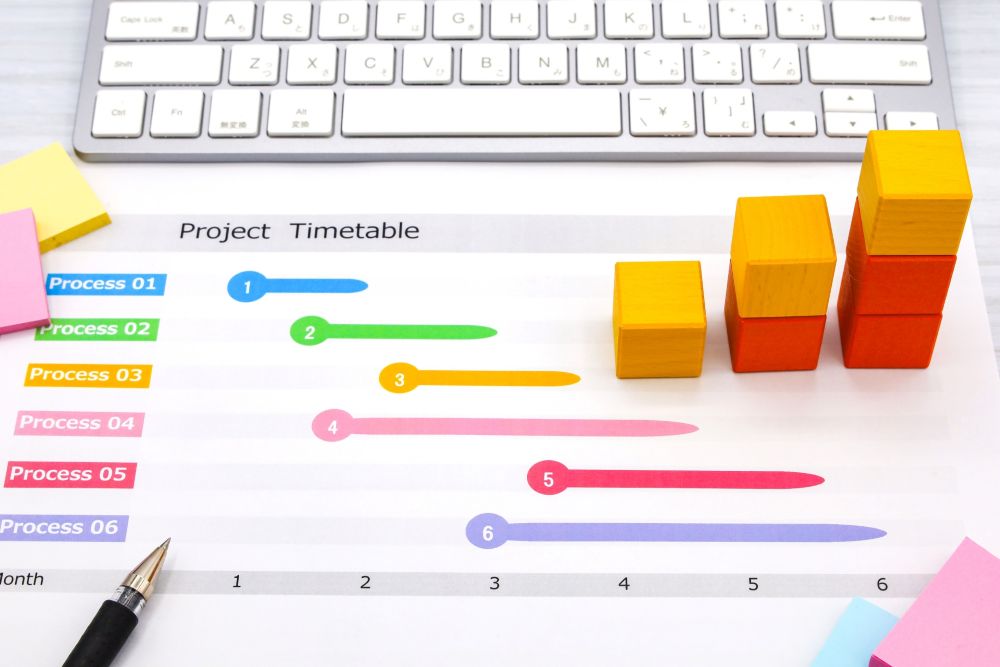会社売却にかかる手数料とは?費用相場と抑えるポイントを徹底解説

会社売却を検討するうえで、手数料の負担は大きな懸念事項の一つです。
実際、M&Aの仲介手数料が高額になるケースは少なくありません。手数料の相場や誰が支払うのかがわからず、会社売却に踏み切れない経営者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社売却にかかる手数料の種類や費用相場、成功報酬の計算方法、費用を抑えるポイントをわかりやすく解説します。明確な手数料体系をもつ仲介会社の選び方も紹介するので、会社売却時の費用軽減にお役立てください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
会社売却の手数料とは

会社売却の手数料とは、M&A仲介会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)をはじめとする専門家へ支払う報酬のことです。
譲受先企業探しから条件交渉、契約締結まで、専門家はM&Aの複雑なプロセスを包括的にサポートしてくれます。その対価として発生するのが相談料や着手金、成功報酬などの手数料です。
ただしどの手数料がどのタイミングで発生するかは、依頼する仲介会社や契約内容、売り手か買い手かによって異なります。納得できる会社売却を実現するためには、手数料の仕組みを正しく知ることが不可欠です。
会社売却で発生する手数料の種類と相場一覧

ここでは、会社売却にかかる代表的な6つの手数料と、それぞれの費用相場を解説します。
| 手数料の種類 | 概要と発生タイミング | 概算相場 |
| 1. 相談料 | 正式な依頼前の初期相談時に発生する費用 | 無料〜1万円/時間 |
| 2. 着手金 | 仲介会社との業務委託契約時に支払う初期費用 | 50万〜200万円
※無料の仲介会社もある |
| 3. 中間報酬(中間金) | 買い手候補との基本合意契約(MOU)締結時に発生する費用 | 成功報酬の10〜20%
※無料の仲介会社もある |
| 4. デューデリジェンス費用 | 買い手が実施する企業調査(財務・法務など)の費用 | 50万円〜300万円
※調査範囲に応じて変動 |
| 5. 成功報酬 | M&Aが最終的に成約した際に支払う最も大きな費用 | レーマン方式を導入している仲介会社の場合、取引金額の1~5%
※最低報酬額を設定している仲介会社もある |
| 6. リテイナーフィー | 契約期間中、毎月発生する月額の顧問料 | 30万円〜100万円/月 |
1. 相談料
相談料は、M&A仲介会社に会社売却の検討を初めて相談する際に発生する費用です。企業の概要に対する簡易的な企業価値評価や、売却の進め方に関するアドバイスに対して支払います。
しかし、近年では業界内競争により相談料を無料とする会社が増えています。費用を気にかけず専門家のアドバイスを得られるため、まずは複数の会社に相談し、自社の状況を客観的に把握することから始めましょう。
2. 着手金
着手金とは、M&A仲介会社と正式に業務委託契約を結ぶ際に支払う費用のことです。M&A仲介会社が本格的な支援業務を始めるための準備金として位置づけられます。
着手金の支払いを確認すると、仲介会社は売却先の候補リスト作成や、企業の魅力をまとめた候補企業への提案資料作成などに着手します。
相場は50万円〜200万円程度ですが、M&Aが成立しなかった場合でも返金されない点に注意が必要です。なお完全成功報酬制を導入している仲介会社では、着手金はかかりません。
3. 中間報酬(中間金)
中間報酬は、買い手候補企業と基本的な条件について合意し、「基本合意契約」を締結した際に発生する手数料です。M&Aプロセスの一定の進捗への対価と位置付けられ、成功報酬の一部の前払いと解釈されています。
相場は、最終的な成功報酬額の10%〜20%程度、もしくは100万円〜200万円といった固定額で設定されることが一般的です。ただし完全成功報酬制を導入している仲介会社では、中間報酬はかかりません。
中間報酬についても、最終的にM&Aが破談になった場合に返金されないことが多いので、どのような条件で中間報酬が発生するのか、契約前に確認しましょう。
4. デューデリジェンス(DD)費用
デューデリジェンス(DD)費用は、買い手企業が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査する際にかかる費用です。企業の内部情報を精査する財務・税務・法務などの専門家に対して支払われます。
通常、デューデリジェンス費用は買い手側が負担することが一般的です。ただし、売り手側も資料の準備や質問への回答のために、自社の顧問弁護士や会計士にサポートを依頼する費用がかかるケースがあります。
5. 成功報酬
成功報酬は、M&Aの契約が最終的に成立した時点で仲介会社へ支払う手数料です。M&Aを成功に導いた対価であり、会社売却にかかる手数料の中でもっとも大きな割合を占めます。
成功報酬の計算には、取引金額が大きくなるほど料率が低くなる「レーマン方式」という、業界標準の計算式が用いられることが一般的です。
また、案件の規模にかかわらず質の高いサービスを提供するために、最低報酬額を設定している会社もあります。
6. リテイナーフィー(月額で発生する費用)
リテイナーフィーとは、M&A仲介会社と契約している期間中、毎月定額で支払う費用のことです。継続的な情報提供やアドバイス、譲受先企業の探索活動などに対する顧問料のように位置づけられています。
着手金や中間金が無料の代わりにリテイナーフィーが設定されるケースもあれば、近年ではリテイナーフィーを無料とする仲介会社も少なくありません。相場は月額30万円〜200万円程度ですが、M&Aのプロセスが長期化するほど負担が大きくなり、企業の規模や依頼する業務内容によっても変動します。
契約前には、月額費用の有無とリテイナーフィーに含まれるサポート内容、また想定される契約期間の目安などを確認しておくと安心です。
会社売却の手数料が高くなるケース

会社売却の手数料は、依頼する仲介会社や会社の状況、契約内容によって異なります。ここでは、手数料が高額になりやすい3つのケースを解説します。
支払う手数料の種類が多い
支払う手数料の種類が多いほど、最終的な支払い総額が高くなる傾向にあります。
報酬体系はM&A仲介会社によって異なり、完全成功報酬の会社がある一方で、成功報酬のほかに着手金や中間報酬、月々のリテイナーフィーなどが必要な会社もあります。完全成功報酬型であれば着手金や中間報酬がかからず、費用を抑えられることが一般的です。
着手金とリテイナーフィーはM&Aが不成立の場合でも返金されず、中間報酬も返金されないことが大半である点にも留意しなければなりません。
デューデリジェンスで多くのサポートが必要になる
デューデリジェンス(DD)で多くのサポートが必要になると、売り手側の費用負担が増えることがあります。
一例として、買い手側の調査範囲が広かったり、多くの回答が必要になったりして、売り手側が自社の顧問弁護士や会計士にサポートを依頼するようなケースです。特に、会計帳簿の未整備や、法務上の潜在的な問題が発覚したケースでは、対応に多くのサポートが必要となり、別途費用がかかります。
日頃の管理体制が行き届かない企業や資料が整理されていない企業は、デューデリジェンス対応の工数と費用が増える傾向にあるため注意が必要です。
成功報酬の算定基準が高い
成功報酬の算定基準が高額なことも、支払う手数料が膨れ上がる大きな要因です。
会社売却の最大の手数料である成功報酬は、計算の基礎となる取引金額(報酬算定基準)の定義が仲介会社によって異なります。
たとえば、株式価値1億円、負債2億円の会社の場合、負債を含めない基準(株式価値)なら1億円をベースに手数料を計算しますが、負債を含める基準(移動総資産)の場合は3億円が手数料計算のベースとなります。
手数料率を掛ける取引金額に負債を含めるか、含めないかなど、報酬を算出するベースによって手数料に大きな開きが生じるため、契約前の確認を怠らないよう留意しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →会社売却手数料(成功報酬)の計算方法とシミュレーション

M&Aの成功報酬は「レーマン方式」で算出されることが一般的です。レーマン方式とは、M&Aの取引金額に応じて、手数料率が段階的に低くなる計算方法です。ここでは、レーマン方式で成功報酬を算出する方法を解説します。
レーマン方式の計算式と手数料率
レーマン方式は取引金額が大きくなるほど、適用される料率が下がる累進構造が特徴で、案件の規模に応じた公平な報酬設定が可能です。
一般的に、レーマン方式では以下の料率テーブルが用いられます。
| 取引金額 | 手数料率 |
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
取引金額全体に単一の料率を掛けるのではなく、金額を段階に分け、それぞれに料率を適用してから合計する点がポイントです。
売却価格別の計算例
それでは、上記の料率テーブルを使って、具体的な計算例を見ていきましょう。
ケース1:売却価格が4億円の場合
売却価格が4億円の場合、全額が5億円以下の段階に含まれるため、手数料率は一律5%です。
- 計算式:4億円 × 5% = 2,000万円
売却価格4億円に対する成功報酬額は2,000万円となります。
ケース2:売却価格が15億円の場合
売却価格が15億円の場合、金額を3つの段階に分けて計算し、最後に合計します。
- 5億円以下の部分:5億円 × 5% = 2,500万円
- 5億円超 10億円以下の部分:(10億円 – 5億円) × 4% = 2,000万円
- 10億円超 15億円以下の部分:(15億円 – 10億円) × 3% = 1,500万円
- 合計成功報酬額:2,500万円 + 2,000万円 + 1,500万円 = 6,000万円
このケースでは、成功報酬の総額は6,000万円となります。
レーマン方式の4つの報酬算定基準
レーマン方式で計算する際の取引金額(報酬算定基準)には、主に以下の4種類があります。
| 算定基準 | 内容(ベースとなる金額) | 売り手への影響 |
| 株式価値基準 | 株主が受け取る純粋な売却金額(オーナー受取額) | -計算方法がシンプルでわかりやすい
-手数料を抑えやすい |
| 企業価値基準 | 株式価値に、会社の有利子負債(借入金など)を加えた金額 | -負債が多いほど手数料が高額になる |
| 移動総資産基準 | 株式価値に、負債の総額を加えた金額 | -算入する負債総額が大きく手数料がもっとも高額になりやすい |
| オーナー受取額基準 | 売却により最終的にオーナー(株主)が実際に受け取る金額 | -負債が多い場合の手数料負担が抑えられる
-自社株すべてを個人オーナーが所有する企業に適している -受取額の定義が曖昧になりやすい |
どの基準を採用するかは仲介会社によって異なります。算定基準によって手数料額が数千万円単位で変わることもあるため、契約前には、どの算定基準が適用されるのか確認しましょう。
会社売却にかかる手数料を抑える7つのポイント

会社売却の手数料は高額になりがちですが、ここでは、手数料を抑えるための具体的な7つの方法をご紹介します。
1.複数の仲介会社から見積もりを取る
会社売却の手数料を抑えるためには、複数の仲介会社から見積もりを取り、比較検討することが基本です。
M&A仲介会社の手数料には法律の定めがなく、料金体系や料率は会社ごとに異なります。同じ売却価格であっても、成功報酬の料率や最低報酬額の違いによって、支払う手数料の総額は数百万円以上変わることもあるため、最低3社程度は話を聞き、見積もりを取得することがおすすめです。
各社の料金体系を比較することで、相場観が分かり価格交渉の材料にもなります。手数料の総額だけでなく、料金体系の内訳や費用が発生するタイミングも確認しましょう。
2.成功報酬制の仲介会社を選ぶ
着手金や中間金が不要の成功報酬制の会社を選ぶことで、初期費用や途中で発生する費用を抑えられます。
完全成功報酬制の会社を選べば、M&Aが成立した場合しか手数料が発生しないため、万が一売却に至らない場合には金銭的な負担の回避が可能です。
ただし、成功報酬率が他社より高めに設定されていないか、成功報酬以外に本当に費用が発生しないかについては、確認が必要です。
3.成功報酬の算定基準を確認する
手数料の料金体系を確認する際には、成功報酬の算定基準もチェックし、負担の少ない方法を選択しましょう。
成功報酬の算定基準は仲介会社によって異なる場合があります。どの基準(株式価値、企業価値など)が採用されているか、アドバイザリー契約書で確認してから契約することが大切です。
可能であれば、自社にとってより有利な基準で計算してもらえるよう、交渉することも一つの手です。仲介会社によっては、案件の規模に応じて手数料の相談に乗ってくれる場合があるので、掛け合ってみましょう。
4.最低報酬額を確認する
成功報酬の「最低報酬額」も忘れずに確認しましょう。
最低報酬額とは、レーマン方式で計算した成功報酬額が一定の金額に満たない場合に適用される、最低限の手数料のことです。
小規模なM&Aの場合、レーマン方式で計算した金額より最低報酬額の方が高くなることがあります。 たとえば、売却価格が4,000万円で料率が5%の場合、計算上の成功報酬は200万円です。しかし、仲介会社の最低報酬額が500万円に設定されていると、差額の300万円を余分に支払うことになり、負担が大きくなりがちです。
小規模な会社の売却を検討している場合は、最低報酬額が低く設定されているか、設定されていない仲介会社を選ぶことで、手数料の負担を大幅に削減できる可能性があります。事前に最低報酬額を確認し、高すぎる場合は交渉の余地がないか検討しましょう。
5.デューデリジェンスの調査範囲を絞る
買い手と交渉しデューデリジェンスの調査範囲を絞ることで、売り手の費用負担を軽減できる場合があります。
デューデリジェンスの調査範囲が広範な場合は、売り手側の対応負担が増える傾向にあります。売り手側には要求された資料を準備したり、質問に回答したりする義務があり、弁護士や会計士にサポートを依頼する費用が別途発生するためです。
不要な調査を削減しM&Aプロセスが迅速化されることは、買い手にとってもメリットです。不要な調査項目を削れないか、買い手側と協議することをおすすめします。
6.公的機関やマッチングサイトを活用する
手数料を抑えたい場合は、公的機関やM&Aマッチングサイトを活用することも一つの手です。
たとえば、全国の「事業承継・引継ぎ支援センター」では、専門家への相談や限定的なマッチング支援を無料で受けられるため、特に比較的小規模な会社売却の場合には有効な選択肢になり得ます。
また、近年増えているオンラインのM&Aマッチングサイトは、仲介会社よりも手数料が安価な傾向にあり、中には無料で利用できるサイトもあります。ただし、安価なサービスは交渉や契約手続きを当事者間で進める必要があるなど、十分なサポートを受けられない可能性もあり、別途専門家への依頼が必要な場合がある点に留意しましょう。
7.国や自治体の補助金を活用する
国や自治体が設けている補助金制度を活用し、手数料負担を軽減する方法もあります。
国は中小企業の事業承継を支援するため、M&Aにかかる経費の一部を補助する「事業承継・M&A補助金」などの制度を設けています。補助金の「専門家活用枠」を利用すれば、M&A支援機関に登録された専門家に支払う着手金や成功報酬、デューデリジェンス費用などの一部について、補助を受けることも可能です。
ただし、申請には自社の売却が補助要件に当てはまる必要があります。補助率や上限額、申請要件は公募回ごとに変わるため、利用を検討する際は中小企業庁の公式サイトで最新の情報をチェックしてください。
会社売却の手数料は誰が支払う?売り手・買い手の分担方法

会社売却の手数料を売り手と買い手のどちらが支払うのかは、M&Aの取引形態によって異なります。ここでは、仲介会社との取引方法による手数料負担の違いと、手数料の会計・税務処理について解説します。
「両手取引」「片手取引」による負担の違い
M&Aの仲介形態には、主に「両手取引」と「片手取引」の2種類があり、それぞれ手数料の支払い方が異なります。
【両手取引】
1社のM&A仲介会社が、売り手と買い手の両方の間に入って交渉を仲立ちする、日本の中小企業M&Aで主流の取引形態です。
売り手と買い手の双方が同一の仲介会社へ手数料を支払うことが一般的です。
【片手取引】
売り手と買い手が、それぞれ別の仲介会社(アドバイザー)を立てる取引形態です。
売り手と買い手はそれぞれ自社が依頼した仲介会社のみに手数料を支払います。
「両手取引」のメリット・デメリット
両手取引は、M&Aのプロセスを円滑に進めやすい反面、利益相反のリスクを指摘されることもあります。
【メリット】
- 仲介会社が持つネットワーク内で相手先が見つかりやすい
- 仲介会社が売り手と買い手の情報を一元管理するため、意思疎通がスムーズになり交渉が早く進みやすい
- 仲介会社が中立的な立場で両社の間に入り、意見を調整してくれるため、交渉がまとまりやすい
【デメリット】
- 仲介会社は双方から手数料を得るため、依頼者の利益を最大化するより取引の成立を優先させる可能性がある
- 手数料を高く取れる買い手が優先される可能性がある
両手取引を選択する際は、仲介会社が自社の立場を理解し、誠実に対応してくれるか見極めることが重要です。
「片手取引」のメリット・デメリット
片手取引は、自社の利益を追求しやすい反面、交渉が難航するリスクもあります。
【メリット】
- 売り手の利益を最大限に代弁してくれる(売却価格の引き上げや有利な契約条件の獲得など)
- 利益相反のリスクがない
【デメリット】
- 売り手側と買い手側の仲介会社が、それぞれ自社の依頼者の利益を主張し合うため交渉が複雑化し、時間がかかることがある
- 専門性の高い交渉を担う仲介会社やFAへの手数料は、両手取引より割高に設定される傾向にある
会社売却時の手数料の会計・税務処理
会社売却時に支払った仲介手数料は、会計上は費用として計上し、税務上は株式の売却益からの控除が可能です。
会計上、支払った手数料は「支払手数料」などの勘定科目を用いて、営業外費用または特別損失として処理します。費用として計上することで、その期の利益を圧縮する効果があります。
税務上では、手数料は株式を譲渡するために直接かかった費用(譲渡費用)と見なされます。法人税は、株式の売却代金から「株式の取得費」と「譲渡費用(手数料)」を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。手数料を費用として計上できるため、課税対象となる所得が減り、節税が可能です。
具体的な会計・税務処理は、会社の状況や契約内容によって異なるため、必ず顧問税理士などの専門家に相談してください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →「M&Aガイドライン」改定が会社売却時の手数料に及ぼす影響

近年、中小企業庁が「中小M&Aガイドライン」を改定したことで、会社売却時の手数料に対する透明性が高まりつつあります。ここでは、M&Aガイドライン改定の概要と、改定が会社売却の手数料に及ぼす影響について解説します。
2023年中小企業庁によるガイドライン改定の概要
中小企業庁は2023年9月、中小企業のM&Aを円滑に進め、売り手と買い手の双方を保護する目的で「中小M&Aガイドライン」を策定・改定しています。
ガイドライン改定の背景には、M&A専門業者の急増に伴い、手数料体系の不透明さや、依頼者にとって不利な契約内容に関するトラブルが増加したことがあります。
改定では、M&A支援機関が遵守すべき行動指針が示され、利益相反のリスクや手数料体系について、依頼者へ事前に詳しく説明することが求められるようになりました。結果として、売り手は契約前に複数の仲介会社を比較検討しやすくなり、十分な情報を得て不利な契約を締結するリスクが軽減されると考えられます。
M&A支援機関登録における手数料体系開示の義務化
ガイドラインの改定に伴い、「M&A支援機関登録制度」に登録する仲介会社は、自社の手数料体系を公表することが義務付けられました。
M&A支援機関として登録を受けるには、自社のWebサイトなどで、成功報酬の計算方法(レーマン方式の料率など)や最低報酬額、着手金や中間金の有無といった詳細な料金体系を公表しなければなりません。
売り手は、支援機関のWebサイトを確認するだけで、各社の手数料を手軽に比較できるようになったのです。
会社売却を依頼する会社を選ぶ際の3つのポイント

M&Aの成功は、パートナーとなる仲介会社選びで大半が決まるといっても過言ではありません。最後に、会社売却を依頼する会社選びの特に重要なポイントを解説します。
1. 同業種・同規模の成約実績が豊富か
依頼を検討している仲介会社が、自社と同じ業種や同程度の規模のM&Aをどのくらい成功させているか、実績を確認しましょう。
業界特有のビジネスモデルや商慣習、適正な企業価値の評価方法を深く理解している仲介会社は、より良い買い手候補を見つけ出し、有利な条件で交渉を進めてくれる可能性が高いです。たとえば、IT業界に強みを持つ仲介会社と、製造業や建設業を専門とする会社では、保有する買い手企業のネットワークや評価のノウハウがまったく異なります。
仲介会社のWebサイトで公開されている成約事例をチェックしたり、無料相談の場で具体的な実績について直接質問したりして、自社業界に対する理解度を確かめることが、満足のいく会社売却への近道です。
2. 手数料体系の透明性が高いか
手数料体系の透明性が高い仲介会社を選ぶことは、予期せぬトラブルを避けるために絶対に欠かせません。
料金の計算方法や費用が発生するタイミングが曖昧なまま契約してしまうと、後から想定外の高額な費用を請求されるリスクがあります。「中小M&Aガイドライン」の改定を受けて、多くの支援機関はWebサイトで料金体系を公開しています。成功報酬の算定基準(株式価値か、負債を含む移動総資産か)、最低報酬額の有無と金額、着手金や中間金の扱いについて契約書で確認してください。
料金体系が明確で、追加費用が発生する可能性などについて、丁寧に説明してくれる会社を選びましょう。
3. 「M&A支援機関」に登録されているか
安心して依頼できる仲介会社かを見極める基準として、中小企業庁が2021年度に創設した「M&A支援機関登録制度」に登録されているかを確認することも一つの方法です。
この制度に登録されている事業者は、「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言しているため、一定の信頼性が担保されていると判断できます。
また、先述の「事業承継・M&A補助金」を利用する要件として、登録機関に支払う手数料のみが補助対象とされています。登録機関は中小企業庁の「登録支援機関データベース」で検索できるため、パートナー選びの一つの基準として、登録の有無を確認してみましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →会社売却の手数料を正しく理解し、納得のいくM&Aを実現しよう
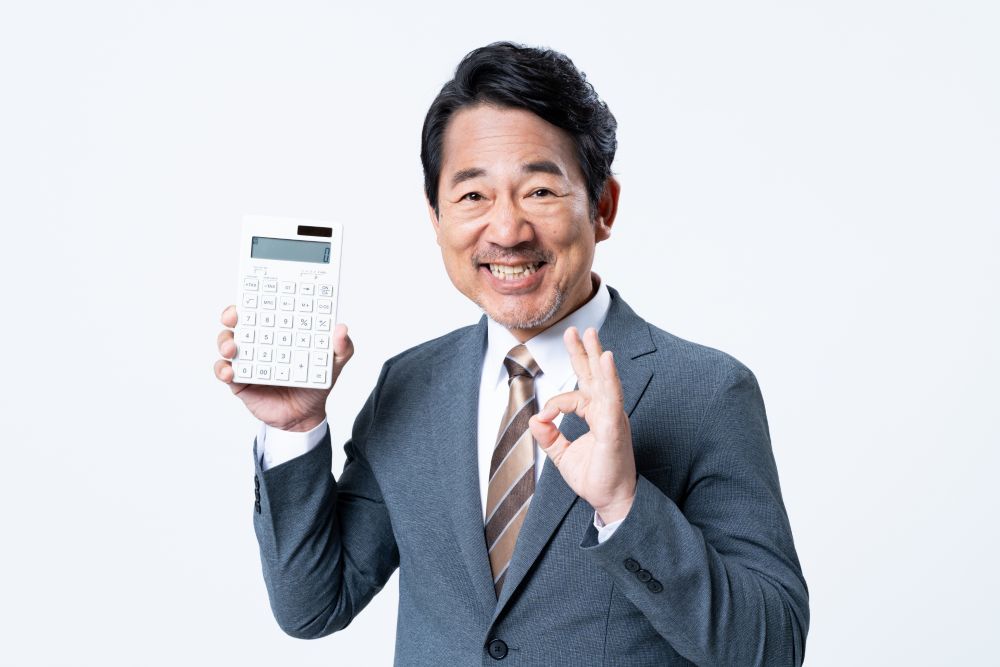
会社売却を成功させるには、手数料の仕組みを正しく理解し、自社に合った料金体系の仲介会社を選ぶことが不可欠です。
手数料には成功報酬のほか、着手金や中間金など複数の種類があり、その計算方法も仲介会社によって異なります。特に成功報酬は、算定基準や最低報酬額によって支払う金額が大きく変わるため、契約前の確認が重要です。
納得できる会社売却を実現するために、手数料体系の透明性が高く、信頼できる「M&A支援機関」登録機関へサポートを依頼することをおすすめします。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)