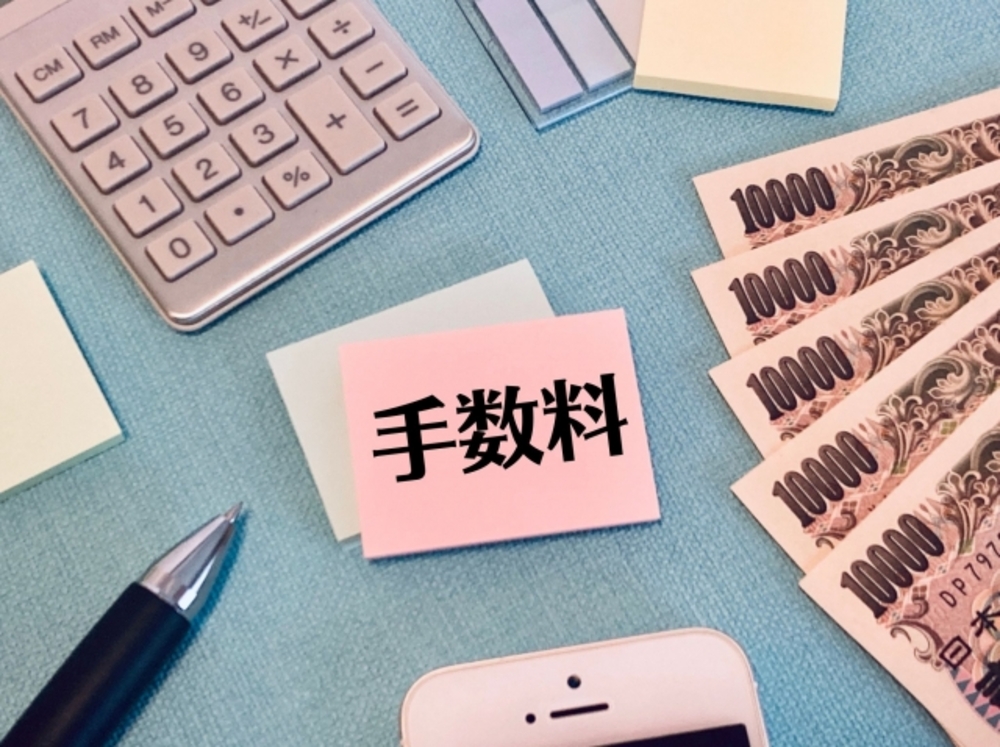M&Aの期間はどれくらい?成約までの流れと成功のポイントを徹底解説

M&Aの期間は数カ月とも1年以上とも言われますが、状況によって異なります。「いつから準備を始めれば良いかわからない」「短期間で、スムーズに引継ぎまで終えたい」と、スケジュール感を知りたい経営者も多いのではないでしょうか。
本記事では、M&Aの相談からクロージングまでの全ステップと、それぞれに必要な期間の目安をタイムラインに沿って解説します。M&Aをスムーズに進めるための準備や、期間が長引く要因も紹介するので、効率的なM&Aの進行にお役立てください。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aに必要な期間の全体像

M&Aを検討する上で、全体のスケジュール感を押さえておく必要があります。まず、M&Aプロセス全体にかかる平均的な期間を見ていきましょう。
M&A全体の平均期間は6カ月~1年
一般的な中小企業のM&Aでは、専門家への相談から最終的な契約締結(クロージング)まで、およそ6カ月〜1年が目安です。
ただし、これはあくまで平均的な期間です。
相手企業との交渉がスムーズに進んだり、事前の準備が万全だったりすれば短期間で完了することもある反面、複雑な課題が見つかった場合には1年以上かかるケースも少なくありません。まずは6カ月〜1年を一つの基準として捉えておくと良いでしょう。
(情報参照元:日本総研「中小企業によるM&Aの現状と課題─その定着に関する考察」)
企業規模によるM&A期間の違い
M&Aにかかる期間は、企業の規模によっても大きく異なります。
利害関係者が比較的少なく、経営者のトップダウンで意思決定しやすい中小企業は、プロセスが迅速に進む傾向があります。手続きが比較的簡素なため短期間で進めやすいといえます。
一方、株主や部門が多く、法規制などの手続きが複雑になる大企業間のM&Aでは、1年〜2年以上を要することも珍しくありません。関係者が多く、法規制や組織統合が複雑なため長期化する傾向があります。
本記事では、主に従業員数100名以下の中小企業M&Aを念頭に解説を進めます。
M&Aの全工程と期間を9つのステップで徹底解説

M&Aのプロセスは、相談からクロージングまで複数のステップで構成されています。ここでは、M&Aの主要なステップと、それぞれの目安期間を解説します。
| ステップ | 期間の目安 |
| ステップ1:準備 | 1週間~1カ月 |
| ステップ2:現状のヒアリング・提案 | 2週間~1カ月 |
| ステップ3:契約 | 1週間~2週間 |
| ステップ4:企業概要書の作成 | 1カ月~2カ月 |
| ステップ5:マッチング・トップ面談 | 2カ月~4カ月 |
| ステップ6:基本合意契約締結 | 2週間~1カ月 |
| ステップ7:デューデリジェンス | 1カ月~2カ月 |
| ステップ8:最終契約書の締結 | 2週間~1カ月 |
| ステップ9:クロージング | 1カ月程度 |
ステップ1.相談(1週間~1カ月)
M&Aの検討を開始したら、M&A仲介会社などの専門家へ相談しましょう。
専門家にM&Aの目的や希望条件、企業の概況などを伝えたら、なぜM&Aを行うのか、目的を明確に言語化することが重要です。
- 後継者問題の解決
- 創業者利益の確保
- 事業のさらなる成長
目的の明確化によって交渉の軸がぶれなくなり、後の意思決定が迅速化します。
同時に、自社の強みや課題を洗いだし、専門家に客観的な視点から分析してもらうことも必要です。専門家は、相談内容に基づいてM&Aの可能性や進め方をアドバイスしてくれます。
無料相談を受け付けているM&A仲介会社も多いので、積極的に活用しましょう。
ステップ2.現状のヒアリング・提案(2週間~1カ月)
続いて、M&A仲介会社との間で秘密保持契約(NDA)を結び、自社の財務状況や事業内容、組織体制など、詳細な情報を提供します。
M&A仲介会社は企業情報をもとに、M&Aの最適なスキームや企業価値の評価、想定される買い手候補のタイプなどを提案してくれます。
疑問点や不安な点は、ヒアリングの時点で解消しておきましょう。専門家の提案を通じてM&A全体のやるべきことと道筋が見えてきます。
ステップ3.契約(1週間~2週間)
M&Aの支援を正式に依頼する専門家を決め、提携仲介契約を締結します。
提携仲介契約書には、仲介会社が提供するサービスの範囲や報酬、手数料の体系、契約期間、秘密保持、解除条件などが記載されています。内容を十分に理解した上で契約することが重要です。
特にM&A仲介の報酬体系は会社によって異なるため、自社に適した報酬体系を取っているか契約前に確認しましょう。
契約締結後は、本格的なM&A活動がスタートします。
ステップ4.企業概要書の作成(1カ月~2カ月)
M&A仲介会社が、譲受先候補企業へ提示するための企業概要書(IM:インフォメーションメモランダム)を作成します。
企業概要書とは、事業内容や財務状況、強み、M&Aの目的などが詳細にまとめられている書類のことで、買い手企業がM&Aを検討する際の重要な判断材料の一つです。
魅力的かつ正確な企業概要書を作成することで、マッチングの可能性が高まるため、M&A仲介会社の協力を得ながら自社の強みを明確に記載することがポイントです。
同じタイミングで、譲渡価格の基準となる企業価値評価を実施します。
ステップ5.マッチング・トップ面談(2カ月~4カ月)
企業概要書が完成したら、M&A仲介会社は買い手候補企業への打診を開始し、マッチングを進めます。
興味を示す企業が現れたら、まず匿名で企業情報(ノンネームシート)を開示し、関心を示したら秘密保持契約を締結した上で詳細な企業情報を開示する流れです。
その後、売り手企業の経営者と買い手企業の経営者が直接会うトップ面談へと進みます。トップ面談では、双方の経営方針やM&Aの目的、将来のビジョンを話し合い、事業シナジーや企業文化の相性を確認します。
ステップ6.基本合意契約締結(2週間~1カ月)
トップ面談を経て、M&Aの基本的な条件について大筋で合意できたら、現時点での合意事項を書面にまとめた「基本合意書(LOI)」を締結します。
基本合意書には買収価格の目安やM&Aスキーム、今後のスケジュールなどが盛り込まれています。後のデューデリジェンスや最終交渉に向けた双方の意思確認と、スケジュールの共有が目的のため、独占交渉権や秘密保持義務といった一部の条項を除き法的拘束力はありません。
ステップ7.デューデリジェンス(1カ月~2カ月)
基本合意契約の締結後、買い手企業は売り手企業に対してデューデリジェンス(DD)を実施します。
デューデリジェンスは、買い手企業が売り手企業の事業や財務、法務、税務、人事などあらゆる側面を詳細に調査するプロセスです。多角的な視点から、開示されていない重大なリスク(簿外債務や訴訟リスクなど)の有無を徹底的に調査します。
売り手側には、要求された資料や情報の迅速かつ正確な提供が求められます。DDで新たなリスクが発覚した場合は、譲渡価格の減額などの調整が行われることもあるため、慎重かつ誠実な対応が不可欠です。
ステップ8.最終契約書の締結(2週間~1カ月)
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格や取引条件の交渉を行うステップです。
双方がすべての条件に合意したら、最終契約書(SPA:株式譲渡契約書など)を締結します。最終契約書とは、買収価格、M&Aの実行日、表明保証、補償条項など、M&Aに関するすべての条件が詳細に記載された、法的な拘束力を持つ契約書です。
最終契約書はM&Aの取引内容を法的に確定させる重要な書類であるため、弁護士などの専門家を交えて慎重に内容の精査が必要です。
ステップ9.クロージング(1カ月程度)
最終契約書の締結後は、M&Aの実行日に向けて最終的な手続き(クロージング)を進めます。
クロージング当日は、株式の譲渡や代金の決済、役員の変更登記など、M&Aの実行に必要な法務・税務上の手続きを完了させます。株式譲渡と決済は同時に実行することが原則です。
クロージングの手続きをもってM&Aは法的に完了し、会社の経営権が買い手へと正式に移転します。
M&Aの期間を左右する5つの要因

M&Aの平均的な期間は6カ月〜1年ですが、実際にはさまざまな条件により変動します。ここでは、M&Aの期間に影響を与える主な5つの要因を解説します。
M&Aが長期化するリスクを事前に予測し、対策を講じましょう。
買い手・売り手の条件交渉
買い手と売り手の条件交渉は、M&A期間を決定するもっとも大きな要因の一つです。
譲渡価格や従業員の処遇、債務の引継ぎ方法といった条件交渉は難航するケースが少なくありません。特に、創業オーナーにとっては会社への思い入れも強く、価格面で折り合いがつきにくい傾向にあります。
また、長年会社を支えてくれた従業員の雇用維持や役員の処遇なども、交渉が難航しやすいポイントです。
M&Aを長期化させないためには、感情的な対立を避け、客観的なデータに基づいて交渉を進めることが重要です。
デューデリジェンスでの問題発覚の有無
デューデリジェンスの過程で、事前に開示されていなかった問題が発覚した場合、交渉は一時中断され、期間が大幅に長引く可能性があります。
具体的には、簿外債務や偶発債務、環境問題、係争中の訴訟、将来の訴訟に発展しかねない法務上のリスクなどです。新たな問題に対する追加調査や対応策の検討、譲渡価格の再交渉などが必要となり、スケジュールに遅れが生じる原因となります。
独占禁止法など法規制への対応
企業の規模や業種によっては、M&Aの実行に際して行政機関への届出や許認可が必要になる場合があります。
特に、市場シェアの高い企業同士のM&Aや、特定の業界における大型M&Aでは、独占禁止法に基づく公正取引委員会の審査が必要となるケースもある点に留意しなければなりません。審査には通常30日間、二次審査に進むとさらに数カ月かかります。
上記の他に、金融業では金融庁への認可申請、通信業では総務省への届出など、業界特有の手続きが生じることもあります。自社のM&Aにどのような法規制が関わるのか、事前に専門家へ確認しておくことが不可欠です。
(情報参照元:公正取引委員会「企業結合審査ガイドブック」)
(情報参照元:e-Gov法令検索「金融機関の合併及び転換に関する法律」)
(情報参照元:総務省「届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者とは (電気通信事業法施行規則第3条第1項)」)
利害関係者の合意形成
利害関係者との合意形成も、M&Aに時間がかかる大きな要因です。
M&Aには従業員や株主、取引先、金融機関など、多くの利害関係者が関係しています。すべての利害関係者からM&Aへの合意を得るためには、丁寧な説明と入念な調整が必要となり、特に複数の株主がいる場合、全員の合意を得るまでに時間がかかることがあります。
また、主要な取引先や金融機関への説明と理解を得るまでのプロセスにも、多くの時間が割かれることが一般的です。
関係者間で丁寧なコミュニケーションを重ねることが、M&Aを円滑に進めるポイントです。
事前準備の有無
売り手企業の事前準備の有無によっても、M&Aの期間が大きく左右されます。
特に、デューデリジェンスにおいては法務や財務、従業員の雇用関連、知的財産権など、膨大な資料が必要です。必要な資料や情報が整理されていないと各ステップで手戻りが発生し、大幅な時間のロスにつながります。
M&Aの検討を始めた段階から準備を計画的に進められるかどうかが、全体の期間を左右するといっても過言ではありません。次項で解説する方法で入念に準備を進めましょう。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
M&Aをスムーズに進行するための5つの準備の心得

M&Aの期間が長引くこともある一方で、事前の準備次第ではプロセスをスムーズに進めることも可能です。
ここでは、M&Aを成功に導くために経営者が押さえておくべき準備の心得を解説します。
承継の予定時期から逆算して準備する
M&Aを検討する際は、事業承継を完了させたい時期や、事業の成長戦略における目標達成時期から逆算して準備を始めることが重要です。
例えば、3年後に引退する目標であれば、遅くとも1年半〜2年前には準備に着手し、企業価値を高める施策を講じたり、資料整理に着手したりする必要があります。
ゴールが明確であれば、各ステップで何をすべきか、いつまでに終えるべきかが明確になり、着実にプロセスを進められます。
準備が整い次第着手する
M&Aは市場環境や競合他社の動向に左右されるため、準備が整い次第、会社の経営状態が良いうちに着手することが重要です。
業績が悪化してから慌てて売却を検討しても、買い手が見つかりにくく、不利な条件で譲渡せざるを得ない可能性があります。後継者問題などで将来的にM&Aを視野に入れているのであれば、自社の価値が高いタイミングで準備を開始するほうが賢明です。
準備を通じてM&A仲介会社と綿密な情報交換をすれば、最適なタイミングを逃さずにM&Aを進められるでしょう。
M&Aの目的と相手像を明確にする
M&Aを成功させるには、なぜM&Aを行うのか、どのような相手企業を求めているのかを明確にすることが不可欠です。
会社を売却する目的によって、買い手企業に求める要件も異なります。従業員の雇用を守ってくれる会社なのか、自社の技術を発展させてくれる会社なのかといった具体的な買い手企業像があれば、候補先を絞り込みやすくなり、マッチングの期間を短縮できます。
目的と買い手企業に求めるものが明確であれば、交渉時の判断で迷うことも少なくなるでしょう。
デューデリジェンスに備え、資料を整理・データ化しておく
デューデリジェンスでは、過去数年分の決算書、法人税申告書、株主名簿、重要な契約書など、膨大な資料の提出を求められます。事前に必要書類を整理し、データ化しておくことで、デューデリジェンス期間の大幅な短縮が可能です。
近年は、機密情報をオンライン上で安全に情報を共有できるデータルーム(VDR)などもあるので、活用すると良いでしょう。DDにおける情報開示もスムーズになり、買い手との信頼関係構築につながります。
意思決定のプロセスを確立する
M&Aのプロセスでは、価格交渉から契約内容の確認まで、専門的かつ重要な判断を次々と下す必要があります。誰が、何を基準に、いつまでに決定するのか、以下の内容について社内の意思決定プロセスを確立しておくことが重要です。
- 最終決定者と決定権限の範囲
- 重要事項の協議・承認フロー
- 外部専門家の意見聴取方法
- 緊急時の連絡体制と意思決定手順
特に株主が複数いる場合は、事前にM&Aの方針について合意形成を図っておくことで、土壇場での混乱を防ぎ、スムーズな進行が可能になります。
M&A成立までの期間を効率化する3つのポイント

M&Aの複雑なプロセスを効率的に進めることは容易ではありません。
ここでは、M&Aを効率的に進め、成立までの期間を短縮するために意識すべき3つのポイントを解説します。
譲れない条件と譲歩できる条件に優先順位をつける
M&A交渉を効率化するためには、譲れない条件と譲歩できる条件を明確にし、優先順位をつけることが重要です。
例えば、従業員の雇用維持は譲れないが、譲渡価格についてはある程度の幅を持たせるなどが挙げられます。交渉では最優先条件の確保に集中し、その他の条件については柔軟に対応しましょう。
メリハリの効いた交渉により、双方が納得できる条件での早期成約が期待できます。買い手からの提案に対しても迅速に判断でき、交渉期間の短縮が可能です。
M&Aスケジュールをシミュレーションしておく
M&Aの検討段階で、詳細なスケジュールをシミュレーションしておくことも期間効率化には不可欠です。各ステップにかかる期間や、発生しうるタスクを洗い出し、現実的な全体像を把握しておきましょう。
例えば、デューデリジェンスの準備にどのくらいの時間がかかるのか、買い手候補との交渉にはどれくらいの期間を見込むべきかなど、具体的に想定しておくことが大切です。
「M&Aの全工程と期間を9つのステップで徹底解説」で紹介したスケジュールをシミュレーションし、途中で発生しうる遅延要因を事前に予測し、対策を準備しておきましょう。
スケジュールを可視化できれば、全体の進行状況を把握でき、M&Aプロセスの効率化につながります。
信頼できるM&A専門家(仲介会社)に早期から相談する
M&Aをスムーズかつ効率的に進めるためには、豊富なサポート実績があり信頼できるM&A専門家を選び、早期から相談することが重要です。
買い手候補探しやマッチング、企業価値評価、デューデリジェンスの調整、契約書作成など、すべてを自社のみで取り組むと膨大な時間がかかることが予想されます。しかしM&Aの豊富な知識と経験を持つ専門家であれば、複雑なプロセスをスムーズかつ効率的に進行できます。
早期に専門家に相談することで、M&Aの目的達成に向けた無駄のない動きが可能になり、時間のロスを削減しながらM&Aの実現が可能です。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&A成功のためにやるべきこと

M&Aのスムーズな進行は、早期に準備に着手できるかどうかにかかっています。
まず、M&Aの目的を明確にし、共に目的を達成するパートナーの要件を明確にすることが大切です。自社の強みや将来性を客観的に評価し、買い手企業に魅力的に伝えるための準備も早期に進める必要があります。
また、日頃から財務状況や法務関係の資料を整理整頓しておくことも大切です。デューデリジェンスに余裕を持って臨めれば、買い手企業からの信頼が高まりスムーズな合意形成が期待できます。
最後に、M&A後の事業統合(PMI)まで見据えた計画を早期に立てることも大切です。M&A後の組織文化の融合や、従業員のモチベーション維持策なども事前に検討しておくことで、統合後のシナジー最大化にもつながります。
計画段階から専門家と連携し、上記を着実に実行していくことがスムーズなM&A実現の鍵です。少しでも不明点や不安な点があるときは、専門家へ積極的に相談し、都度疑問を解消しましょう。
M&Aの期間を正しく理解し、計画的な事業承継・成長戦略を

M&Aの平均期間は企業規模や交渉の進捗など、さまざまな要因に左右されます。
M&Aの期間を短縮するには、目的を明確化した上で、承継時期から逆算し計画的に準備を進めることが不可欠です。計画段階から専門家のサポートを得ることで目標が明確になり、M&Aの準備と各工程をスムーズに進められます。
信頼できるM&A専門家への早期相談が、M&A期間の効率化と成功につながります。専門家のサポートを得ながら計画的に準備を進め、M&Aによる事業承継や成長戦略を実現しましょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)