事業譲渡とM&Aの違いとは?株式譲渡と比較してメリット・手続き・税金を徹底解説
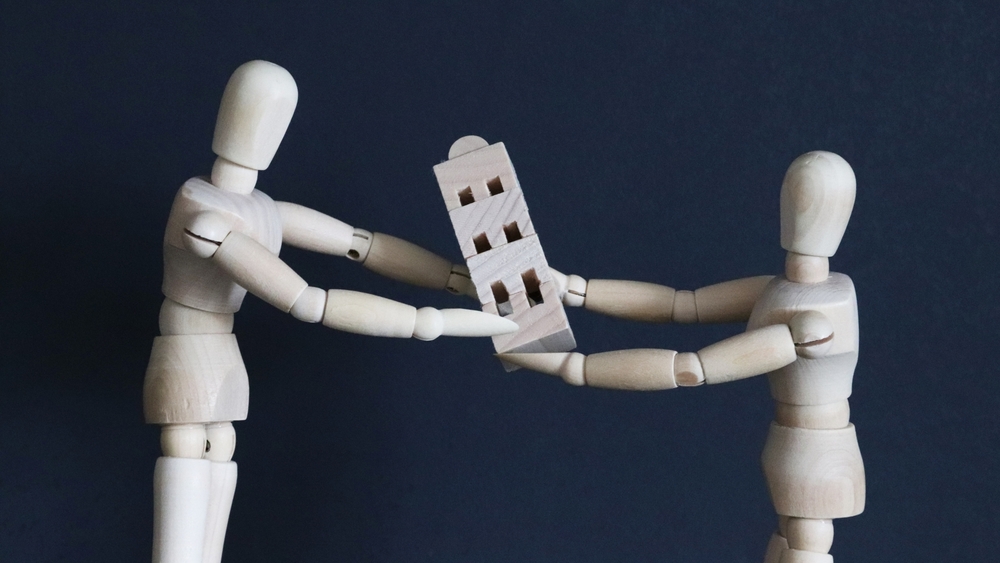
M&Aによる会社の売却や事業の整理を検討する中で、「事業譲渡とM&A(株式譲渡)は何が違うのだろうか?」「自社にとっては、どちらの手法が最適なのかわからない」といった疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。
M&Aは会社の合併・買収の総称であり、事業譲渡はその中の一つの手法です。そして、多くの場合M&Aとの違いで比較されるのは、最も代表的なM&A手法である株式譲渡を指します。
この記事では、M&Aの専門知識がない方でも理解できるよう、事業譲渡と株式譲渡の根本的な違いを以下の7つの観点から徹底的に比較・解説します。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
事業譲渡とは?M&Aにおける位置付けと基本を解説

企業の成長戦略や事業承継を考える上で、M&Aや事業譲渡という言葉を耳にする機会は多いでしょう。しかし、これらの言葉が具体的に何を指し、両者がどのような関係にあるのかを正確に理解されている方は意外と少ないかもしれません。
ここでは、まずM&Aと事業譲渡の基本的な定義と、両者の関係性を明確に解説します。
事業譲渡の定義:特定の事業を選んで売買するM&A手法
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、他の会社に売却(譲渡)するM&Aの一手法です。
最大のポイントは、会社の経営権(株式)を丸ごと売買するのではなく、特定の事業に関連する資産や負債・人材・契約などを個別に選択して取引する点にあります。
例えば、複数の飲食店を経営する会社が、特定の1店舗だけを売却するケースが典型的な事業譲渡です。この場合、売買の対象となるのは、その店舗の不動産・厨房設備・従業員との雇用契約・仕入先との取引契約、そしてブランド(のれん)など、事業を運営するために必要な要素一式となります。
譲渡する側(売り手)は、不採算事業を切り離して主力事業に集中したり、会社は手元に残したまま事業整理を行ったりできます。一方、譲受する側(買い手)は、必要な事業だけを選んで取得できるため、帳簿に載らない簿外債務などの潜在的なリスクを引き継ぐ心配が少ないというメリットがあります。
なお、以前は営業譲渡という言葉が使われていましたが、2006年の会社法施行により、現在は法律上、事業譲渡という名称に統一されています。
M&Aの定義:企業の成長戦略を実現する合併・買収の総称
一方、M&Aとは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略称で、企業の合併や買収を総称する言葉です。
単に会社を売買するだけでなく、複数の会社が一つになったり(合併)、他社の事業を取り込んだり(買収)することで、自社の成長戦略や経営課題の解決を目指す、広範な経営戦略の選択肢を指します。
M&Aの目的は多岐にわたります。
- 後継者不在による事業承継
- 新規事業への参入による事業拡大
- 既存事業とのシナジー効果(相乗効果)の創出
- 不採算事業の売却による経営資源の集中
- スケールメリットによる競争力の強化
このように、M&Aは企業のさまざまな課題を解決し、成長を加速させるための目的や戦略そのものを指す言葉です。
そして、その目的を達成するための具体的な手段の一つとして、前述した事業譲渡や、後ほど詳しく比較する株式譲渡・会社分割といったさまざまな手法が存在します。
つまり、M&Aと事業譲渡の関係は、戦略(目的)と戦術(手段)の関係と捉えるとわかりやすいでしょう。M&Aという大きな目的を達成するために、どの手法を選ぶべきかを検討していくことになります。
事業譲渡のメリット・デメリットを売り手・買い手別に解説
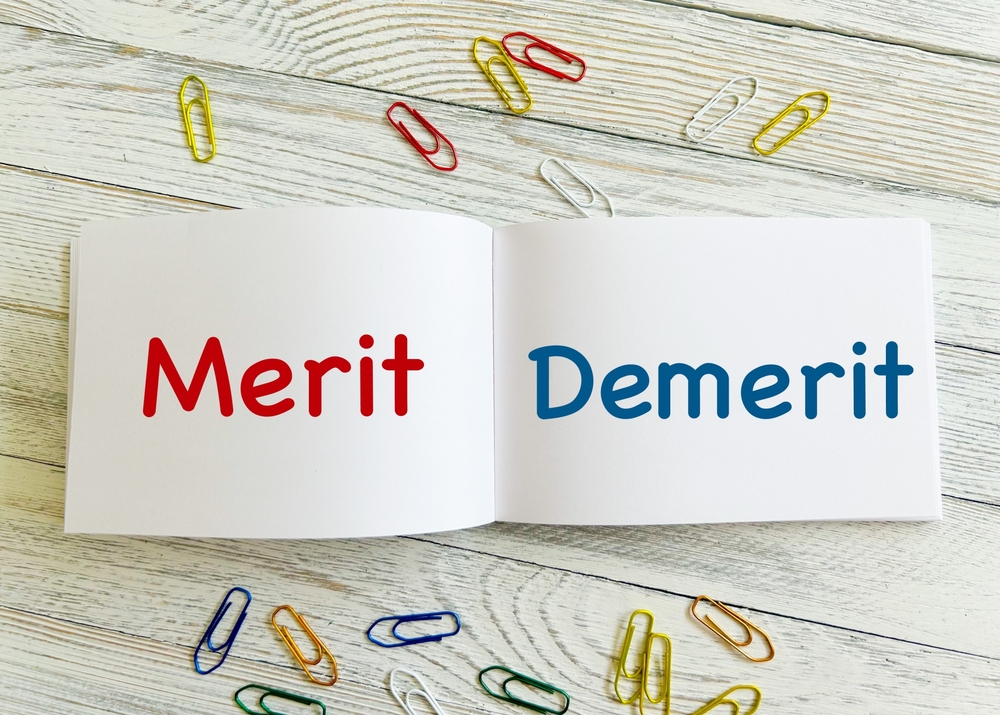
事業譲渡が自社にとって最適な手法かどうかを判断するためには、そのメリットとデメリットを正確に理解しておくことが不可欠です。
事業譲渡は、資産や契約を個別に移転するという特性上、売り手(譲渡側)と買い手(譲受側)の双方に、他のM&A手法にはない独自のメリットとデメリットをもたらします。
ここからは、それぞれの立場から見た事業譲渡のメリットとデメリットを詳しく解説します。
売り手のメリット・デメリット
事業を譲渡する側の企業にとって、事業譲渡は経営の自由度を高める有効な選択肢となり得ますが、手続き面での注意点も存在します。
メリット
- 特定の事業のみを売却できる:
最大のメリットは、会社の一部の事業だけを切り出して売却できる点です。これにより、不採算事業は手放し、成長が見込める主力事業に経営資源を集中させるといった選択と集中が可能になります。 - 会社(法人格)を存続させられる:
事業を売却しても会社そのものは手元に残るため、経営権を維持したまま事業の再構築が図れます。譲渡で得た資金を元手に新たな事業を始めることも可能です。 - 特定の資産を手元に残せる:
例えば、本社ビルや思い入れのある不動産など、事業には直接関係しない、あるいは手元に残しておきたい資産を譲渡対象から外すことができます。 - 譲渡益を有効活用できる:
事業譲渡によって得た売却益は、会社の資産となります。これを残った事業の設備投資資金に充てたり、借入金の返済に回したりと、会社の財務状況の改善に直接役立てることができます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。
デメリット
- 手続きが非常に煩雑:
資産や負債を個別に移転するため、不動産の登記移転、従業員一人ひとりからの転籍同意の取得、取引先との契約の再締結など、膨大な事務手続きが発生し、多くの時間と労力がかかります。 - 譲渡益に法人税が課される:
事業譲渡によって得た利益(譲渡益)には、法人税が課されます。これは、個人の株主が株式を売却した際の譲渡所得税(約20%)と比較して、税率が高くなるケースがあります。 - 競業避止義務を負う:
会社法により、売り手企業は原則として、同一の市区町村および隣接市区町村において、譲渡した事業と同一の事業を20年間行えません(当事者の合意により期間の変更や排除は可能)。
買い手のメリット・デメリット
事業を譲受する側の企業にとって、事業譲渡はリスクを限定できる魅力的な手法ですが、その反面、承継に手間がかかるという側面もあります。
メリット
- 必要な事業や資産だけを取得できる:
自社の事業戦略に必要な資産(技術、人材、顧客リストなど)だけを選んで買収できます。不要な資産を引き継ぐ必要がないため、効率的な投資が可能です。 - 簿外債務などを引き継ぐリスクがない:
買い手にとって最大のメリットがこれです。事業譲渡では、契約で定めた資産・負債のみを引き継ぐため、帳簿に記載されていない債務(簿外債務)や将来発生するかもしれない偶発債務を引き継いでしまうリスクを完全に遮断できます。 - 「のれん」の償却による節税効果:
買収価格が、譲り受けた資産の時価を上回る場合、その差額は「のれん(営業権)」として資産計上されます。この「のれん」は、会計上、一定期間で費用として償却することができ、税務上の損金にも算入できるため、法人税の節税効果が期待できます。
デメリット
- 手続きが煩雑で許認可の再取得が必要:
売り手と同様に、個別の資産移転手続きが必要です。特に、事業に必要な許認可(建設業許可、飲食店営業許可など)は自動的に引き継がれず、買い手が新たに取得し直さなければならないため、事業開始までに時間がかかる場合があります。 - 譲渡資産に消費税が課される:
土地を除く、建物や機械設備といった課税資産の譲渡に対しては、消費税が課されます。買い手は消費税分も上乗せして支払う必要があるため、買収資金が想定より高額になる可能性があります(支払った消費税は、原則として後で控除できます)。 - 従業員や取引先が離反するリスク:
従業員の転籍や取引先との契約は、自動的には引き継がれません。個別に再契約を結ぶ過程で、キーパーソンとなる従業員が退職してしまったり、重要な取引先が契約を継続してくれなかったりするリスクがあります。
事業譲渡と他のM&A手法の違い【スキーム・特徴】
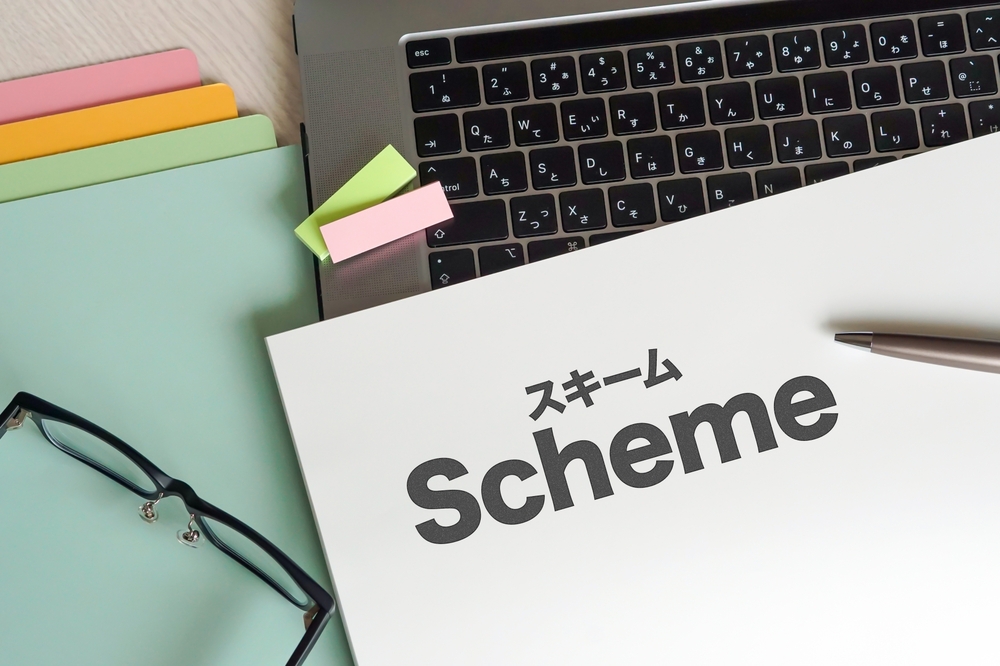
M&Aには、その目的や状況に応じてさまざまな手法(スキーム)が存在します。事業譲渡はあくまでその中の一つの選択肢に過ぎません。
自社にとって最適な手法を選ぶためには、まずM&Aの全体像を把握し、各手法がどのような取引形態で、どのような特徴を持っているのかを理解することが重要です。
この章では、まず代表的なM&A手法を一覧で示し、事業譲渡と特に比較検討されることが多い株式譲渡・会社分割、さらにその他の手法との違いを解説します。
M&Aの代表的な手法一覧と比較表
M&Aの手法は多岐にわたりますが、特に中小企業のM&Aでよく用いられるのは株式譲渡と事業譲渡です。
まずは、それぞれの特徴を比較表で確認し、全体像をつかみましょう。
| 項目 | 事業譲渡 | 株式譲渡 | 会社分割 |
| 取引対象 | 事業に関連する資産・負債(個別選択) | 会社の株式(経営権) | 事業部門全体 |
| 取引の当事者 | 売り手企業と買い手企業 | 売り手企業の株主と買い手企業 | 分割する企業と承継する企業 |
| 債務の承継 | 契約で定めた債務のみ | すべての債務(簿外債務含む)を承継 | 包括的に承継 |
| 手続きの煩雑さ | 煩雑(個別同意や名義変更が必要) | 比較的簡便 | 煩雑 |
| 許認可の扱い | 原則、再取得が必要 | 原則、引き継がれる | 原則、引き継がれる |
| 主な税金(売り手) | 法人税・消費税 | 譲渡所得税(個人株主の場合 約20%) | – |
事業譲渡のスキームと特徴
改めて事業譲渡のスキームを確認すると、会社が主体となり、特定の事業を対価(主に現金)と引き換えに売買する取引です。
ポイントは、資産や契約などを個別に移転させる点にあります。会社という器はそのままに、中身である事業の一部を出し入れするイメージです。
そのため、不要な資産や簿外債務を引き継ぐリスクがない反面、手続きが非常に煩雑になるという特徴があります。
株式譲渡のスキームと特徴
株式譲渡は、中小企業のM&Aで最も多く用いられる手法です。これは、株主が主体となり、保有する株式を対価(主に現金)と引き換えに売買する取引です。会社のオーナー経営者が、自身の持つ株式を買い手に売却することで、会社の経営権そのものを譲渡します。
事業譲渡との最大の違いは、会社を丸ごと(包括的に)承継する点です。
会社という器ごと所有者が変わるイメージで、従業員との雇用契約や取引先との契約、許認可などは原則としてそのまま引き継がれます。
そのため手続きは比較的シンプルですが、買い手は不要な資産や簿外債務も引き継いでしまうリスクを負います。
会社分割のスキームと特徴
会社分割は、事業譲渡とよく似ていますが、法律上の位置づけが異なります。これは、会社が主体となり、特定の事業を切り出して、既存の会社または新設する会社に承継させる組織再編行為です。
事業譲渡が個別の資産を売買する取引行為であるのに対し、会社分割は会社法で定められた組織再編行為であり、権利義務が包括的に承継される点が大きな違いです。
そのため、従業員の同意や取引先の再契約は原則不要で、事業譲渡よりもスムーズに事業を移転できます。対価は現金だけでなく、承継会社の株式とすることも可能です。主にグループ企業内での事業整理や、組織再編を目的として活用されます。
その他の手法(合併・株式交換など)のスキームと特徴
M&Aには他にも複数の会社を一つにする合併や、子会社化を目的とした株式交換などがあります。
| 手法 | 概要 | 特徴 |
| 合併 | 複数の会社が法的に一つの会社になる | 組織を完全に一体化でき、高いシナジー効果が期待できる |
| 株式交換 | ある会社が他の会社の発行済株式のすべてを取得し、完全親子会社の関係を築く | 対価として自社の株式を交付できるため、買収資金が不要な場合がある |
これらの手法は、事業の一部だけを売買したいという事業譲渡の目的とは異なり、主に大企業同士のM&Aで用いられることが多く、より複雑な手続きと法務・税務の知識が求められます。
事業譲渡と他のM&A手法の違い【手続き・流れ】

M&Aの手法を選択する上で、スキームや特徴と並んで重要な判断材料となるのが、手続きの煩雑さと必要な期間です。手法によって、クリアすべき法的な要件や、関係者から取得すべき同意の種類が大きく異なります。
ここでは、事業譲渡・株式譲渡・会社分割のそれぞれについて、一般的な手続きの流れを解説し、その違いを解説します。
事業譲渡の手続き・流れ
事業譲渡は、資産や契約を個別に移転するため、数あるM&A手法の中でも特に手続きが複雑です。一般的に、交渉開始から最終的な譲渡完了までには6カ月〜1年以上の期間を要し、従業員や取引先の数が多いほど長期化する傾向にあります。
- 取締役会での決議と契約締結
譲渡範囲を定めた事業譲渡契約を締結します。この契約書には、どの資産・負債・契約を移転するのかを詳細に記載する必要があり、作成には法務の専門知識が不可欠です。 - デューデリジェンス(DD)の実施
買い手による買収監査が行われます。事業譲渡のDDでは、譲渡対象となる資産の実在性、所有権の確認、許認可の有効性、キーパーソンとなる従業員のスキルや処遇などが特に重要な調査対象となります。 - 株主総会の特別決議
事業譲渡は会社の経営に重大な影響を与えるため、原則として株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。 - 従業員からの転籍同意の取得
事業譲渡における最重要プロセスの一つです。譲渡対象事業の従業員は、自動的に買い手企業に移るわけではありません。売り手企業との雇用契約を一度合意退職し、買い手企業と新たに雇用契約を結ぶ必要があります。そのためには、説明会や個別面談を通じて、処遇や労働条件を丁寧に説明し、一人ひとりから転籍同意書を取得しなければなりません。 - 取引先との契約再締結
事業に関する賃貸借契約や取引基本契約なども、従業員と同様に自動では引き継がれません。契約の相手方である取引先から個別に同意を得て、契約を巻き直す必要があります。 - 各種名義変更と許認可の再取得
不動産の所有権移転登記、事業に必要な許認可(建設業許可など)の買い手による再取得など、行政手続きも多数発生します。
株式譲渡の手続き・流れ
株式譲渡は株主間の取引が基本となるため、事業譲渡に比べて手続きがシンプルです。一般的には3カ月〜6カ月程度で、迅速に進められるのが特徴です。
- 譲渡承認請求と取締役会での承認
譲渡制限株式の場合、会社に対して譲渡の承認を求め、取締役会で決議します。 - デューデリジェンス(DD)の実施
株式譲渡のDDでは、会社を丸ごと引き継ぐため、簿外債務、偶発債務、過去の税務リスク、法務上の問題(訴訟リスクなど)といった隠れたリスクの発見が最大の焦点となります。 - 株式譲渡契約の締結
売り手株主と買い手が契約を締結します。ここでは、発見されたリスクに対する売り手の保証(表明保証)条項などが重要な交渉ポイントになります。 - クロージング(決済と株主名簿の書換)
譲渡代金の決済と、会社の株主名簿を新しい株主の名前に書き換えることで、手続きは完了します。資産の個別移転や契約の巻き直しは発生しません。
会社分割の手続き・流れ
会社分割は組織再編行為であり、債権者保護手続きが特徴です。所要期間は株式譲渡と同様、3カ月〜6カ月程度が目安となりますが、債権者保護手続きに最低1カ月を要します。
- 分割契約の締結と事前開示
分割内容を定めた契約書等を作成し、株主や債権者が閲覧できるよう本店に備え置きます。 - 債権者保護手続き
官報での公告と、個別の催告(通知)を行い、債権者が1カ月以上の期間内に異議を述べられる機会を設ける必要があります。 - 株主総会の特別決議
原則として、株主総会の特別決議が必要です。 - 効力発生と登記申請
効力発生日に事業に関する権利義務は包括的に承継され、登記を行うことで手続きが完了します。従業員の同意や契約の巻き直しは原則不要です。
事業譲渡と他のM&A手法の違い【会計処理】

M&Aの手法によって、企業の財務諸表に与える影響、つまり会計上の処理方法は大きく異なります。特に、資産や負債をどのように帳簿に記録し、発生したのれんをどう扱うかは、M&A後の経営戦略にも関わる重要なポイントです。
この章では、各手法における会計処理の違いを、具体的な仕訳例を交えながらわかりやすく解説します。
事業譲渡の会計処理
事業譲渡は、特定の資産・負債を個別に売買するため、仕訳も個別の勘定科目ごとに行います。
売り手側の仕訳
売り手は、譲渡する資産・負債を帳簿から消し、受け取った対価を計上します。その差額が譲渡損益となります。
(例)簿価3,000万円の事業(資産5,000万円、負債2,000万円)を現金6,000万円で譲渡した場合
| 借方 | 貸方 |
| 現金 6,000万円
負債 2,000万円 |
資産 5,000万円
事業譲渡益 3,000万円 |
買い手側の仕訳
買い手は、譲り受けた資産・負債を時価で計上します。支払った対価が受け入れた純資産の時価を上回る場合、その差額が「のれん」となります。
(例)時価4,000万円の事業(資産6,000万円、負債2,000万円)を現金6,000万円で譲り受けた場合
| 借方 | 貸方 |
| 資産 6,000万円 のれん 2,000万円 |
負債 2,000万円 現金 6,000万円 |
この後、買い手企業は計上したのれんを、設定した年数(20年以内)で規則的に償却(費用化)していきます。
株式譲渡の会計処理
株式譲渡は株主間の取引ですが、買い手企業にとっては子会社への投資となるため、会計処理が発生します。
売り手側が個人株主の場合、この取引は個人の資産の売買となるため、会社の会計処理は発生せず、株主個人が確定申告を行います。
一方、買い手企業は、取得した株式を子会社株式や関連会社株式といった投資有価証券として資産計上します。
(例)A社の株式を現金1億円で取得した場合
| 借方 | 貸方 |
| 子会社株式 1億円 | 現金 1億円 |
この時点では、買い手企業の個別財務諸表にのれんは計上されません。ただし、連結財務諸表を作成する際には、投資額と子会社の純資産の差額がのれんとして計上されます。
会社分割の会計処理
会社分割の会計処理は、当事者間の支配関係によって処理が異なります。
グループ内再編など、分割後も支配関係が継続する場合は共通支配下の取引とみなされ、資産・負債は簿価で引き継がれます。会計上の損益は発生しません。
これに対し、支配関係のない第三者への会社分割などの場合は、資産・負債は時価で評価され、買い手側ではのれんが計上されることがあります。
事業譲渡と他のM&A手法の違い【税金】

どのM&A手法を選択するかによって、誰が、いつ、どのような税金を納めるのかが大きく変わってきます。
税金は最終的な手取り額に直結するため、手法ごとの課税関係を正確に理解しておくことは極めて重要です。
事業譲渡でかかる税金
事業譲渡では、売り手と買い手の双方に異なる種類の税金が発生します。
- 売り手側にかかる税金:法人税
事業の譲渡によって生じた利益(譲渡益)に対して、法人税が課されます。譲渡益は「譲渡価格 - 譲渡資産の簿価純資産額」で計算され、他の事業の損益と合算された上で、法人実効税率(約30%〜34%)が適用されます。 - 買い手側にかかる税金:消費税・不動産取得税など
- 消費税: 譲り受ける資産のうち、課税資産に対して10%の消費税がかかります。土地や有価証券は非課税ですが、建物、機械設備、のれん(営業権)などは課税対象です。
- 不動産取得税・登録免許税: 事業用不動産(土地・建物)を取得した場合に課税されます。
株式譲渡でかかる税金
株式譲渡は、主に売り手である株主に税金がかかります。
- 売り手側にかかる税金:譲渡所得税または法人税
誰が株主かによって税金が変わります。- 個人株主の場合: 株式の売却益(譲渡所得)に対して、所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)、住民税(5%)を合わせて合計20.315%の税率が適用されます。これは他の所得とは合算しない申告分離課税です。
- 法人株主の場合: 売却益は他の利益と合算され、法人税の課税対象となります。
- 節税のポイント:役員退職金の活用
オーナー経営者が株式譲渡で会社を手放す際、譲渡所得の一部を役員退職金として受け取ることで、全体の税負担を軽減できる可能性があります。
役員退職金は、税制上の優遇措置(退職所得控除・分離課税・1/2課税)が大きく、譲渡所得(税率約20%)よりも低い税率となるケースが多いためです。
ただし、不相当に高額な退職金は税務上否認されるリスクがあるため、専門家との相談が不可欠です。
会社分割でかかる税金
会社分割の税務は、法人税法に定められた税制適格要件を満たすかどうかが最大のポイントです。
100%の支配関係があるグループ内での分割など、一定の要件を満たす税制適格分割に該当する場合、資産・負債が簿価で引き継がれたものとされ、分割時点での課税は発生しません(課税の繰り延べ)。
一方、要件を満たさない税制非適格分割の場合は、資産・負債が時価で譲渡されたものとみなされ、譲渡損益に対して法人税が課税されます。基本的には事業譲渡と同様の課税関係となります。
事業譲渡によるM&Aが向いている3つのケース

これまで解説してきたように、M&Aにはさまざまな手法があり、それぞれに一長一短があります。自社にとって最適な手法を選択するためには、これらの特徴を理解した上で、目的や優先事項を明確にすることが重要です。
ここでは、特に事業譲渡によるM&Aが向いている代表的な3つのケースについて、具体的な状況を交えながら解説します。
ケース1:不採算事業などを整理し、主力事業に集中したい
企業が成長する過程で、複数の事業を手がけることは珍しくありません。しかし、時代の変化とともに、一部の事業が不採算部門となったり、企業のコア事業との関連性が薄れたりすることがあります。
このような状況で、赤字の事業を切り離し、経営資源を成長分野である主力事業に集中させたいと考える場合、事業譲渡は最も適した手法です。
株式譲渡では会社全体を売却することになるため、好調な主力事業まで手放さなくてはなりません。一方、事業譲渡であれば、対象となる事業だけを選択して売却できるため、会社を存続させたまま、事業ポートフォリオの再構築(選択と集中)を実現できます。売却で得た資金を主力事業の成長投資に充てることで、企業全体の収益性を大きく改善させることも可能です。
ケース2:会社や特定の資産は手元に残したい
後継者はいないが、先代から受け継いだ会社そのものをなくしたくはない、事業は売却したいが、本社ビルや工場など、思い入れのある不動産は手放したくないといったニーズを持つ経営者の方も少なくありません。
このような、会社(法人格)や特定の資産を自身の管理下に残したいと考える場合も、事業譲渡が有効です。
事業譲渡は、あくまで事業のみを売買する取引です。売却後も会社は存続し、譲渡対象から外した資産はそのまま保有し続けることができます。これにより、会社の歴史や伝統を守りつつ、事業だけを意欲のある第三者に引き継いでもらう、という選択が可能になります。また、残した会社で不動産賃貸業など、新たなビジネスを始めることもできます。
ケース3:【買い手視点】簿外債務などの潜在的リスクを避けたい
これは主に買い手側の視点になりますが、M&Aにおいて最も警戒すべきリスクの一つが「簿外債務(帳簿に載っていない債務)」の存在です。例えば、未払いの残業代や、将来発生する可能性のある訴訟リスク、税務上の問題などがこれにあたります。
株式譲渡では、会社を丸ごと引き継ぐため、こうした隠れたリスクもすべて承継してしまいます。デューデリジェンス(買収監査)で徹底的に調査しますが、すべてのリスクを100%発見できる保証はありません。
買い手として、こうした潜在的なリスクを完全に遮断したいと考える場合、事業譲渡は非常に魅力的な手法です。
事業譲渡では、譲渡対象となる資産や負債を契約書で明確に特定します。契約書に記載されていない債務については、原則として引き継ぐ義務がありません。このリスクの遮断効果は、買い手が安心してM&Aを進める上で大きなメリットとなります。
事業譲渡を成功に導くための3つの重要ポイント

事業譲渡は、正しく進めれば非常に有効な経営戦略ですが、そのプロセスには多くの落とし穴が存在します。
ここでは、事業譲渡を成功させるために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
ポイント1:譲渡範囲の明確化と適正な企業価値評価
事業譲渡の交渉は、「何を売り、何を買うのか」という譲渡範囲の特定から始まります。
- 譲渡範囲の明確化:
建物や機械といった有形資産だけでなく、従業員や取引先との契約、ノウハウやブランドといった無形資産まで、譲渡するものをリストアップし、契約書に詳細に記載する必要があります。ここが曖昧だと、後々のトラブルの原因となります。 - 適正な企業価値評価(バリュエーション):
譲渡する事業がいくらの価値を持つのかを客観的に算定することが、交渉の土台となります。事業価値の評価には、将来の収益性から価値を算出するDCF法や、類似する上場企業の株価から価値を類推する類似会社比較法など、専門的な手法が用いられます。
適正な価格で売買するためにも、専門家による客観的な価値評価は不可欠です。
ポイント2:従業員・取引先への適切な情報開示
事業譲渡において、最もデリケートかつ重要なのが、従業員や取引先との関係の引き継ぎです。
- 従業員への対応:
M&Aの情報は、最終契約が締結されるまで秘密裏に進めるのが基本です。しかし、譲渡が決定した後は、従業員の不安を払拭するための丁寧なコミュニケーションが不可欠です。情報開示のタイミングを慎重に見極め、経営者自らの言葉で、譲渡の背景、目的、そして従業員の雇用が守られることを誠実に伝える必要があります。特に、キーパーソンとなる人材の流出を防ぐためのインセンティブ(リテンションプラン)も有効です。 - 取引先への対応:
重要な取引先には、従業員と同様に、適切なタイミングで情報開示を行い、今後の取引関係が円滑に継続されることを説明し、安心感を与えることが重要です。サプライチェーンの要となる取引先など、事業の根幹に関わる相手には、買い手企業の担当者も同席の上で説明を行うなどの配慮が求められます。
ポイント3:M&A専門家との連携と役割分担
事業譲渡は、法務・税務・会計・労務など、多岐にわたる専門知識を必要とする複雑なプロジェクトです。経営者が本業の傍ら、これらすべてを一人で進めるのは現実的ではありません。
M&A専門家は、豊富な経験とネットワークを活かして、最適な相手企業を探し出し、複雑な交渉を有利に進め、煩雑な手続きをミスなく遂行するための強力なパートナーとなります。
専門家の種類と役割
- M&A仲介会社/FA: 相手探しから交渉、クロージングまで、M&Aプロセス全体をサポートします。
- 弁護士: 契約書の作成やレビュー、法的なリスクの洗い出しなど、法務面をサポートします。
- 公認会計士/税理士: 企業価値評価、デューデリジェンス、税務戦略の立案など、財務・税務面をサポートします。
自社の状況やM&Aの規模に応じて、これらの専門家と適切に連携することが、事業譲渡を成功に導くための最短ルートと言えるでしょう。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
事業譲渡のM&A事例

理論や手法を理解した上で、実際に行われたM&Aの事例に触れることは、事業譲渡への理解をさらに深める上で非常に有効です。
ここでは、近年公表された事業譲渡の中から、目的や背景が異なる3つの代表的な事例をご紹介します。
これらの事例を通じて、企業がどのような経営課題を解決するために事業譲渡という手法を選択したのか、その戦略的な意図を読み解いていきましょう。
事例1:コクヨによるフェローズジャパンからの一部事業譲渡
- 譲渡企業: フェローズジャパン株式会社
- 譲受企業: コクヨ株式会社
- 対象事業: シュレッダーやラミネーターなどの開発・販売事業
- 譲渡日: 2023年12月12日
オフィス用品大手のコクヨは、オフィス向け通販事業のさらなる強化を目的として、シュレッダーなどで高いブランド力を持つフェローズジャパンの関連事業を譲り受けました。
この事例は、買い手であるコクヨが自社の既存事業とのシナジー効果を狙い、特定の商品群に関する事業だけをピンポイントで取得した典型的なケースです。
フェローズジャパン側にとっては、当該事業を強力な販売網を持つコクヨに託すことで、事業のさらなる成長が期待できます。
自社の強みを活かせる領域に経営資源を集中させる「選択と集中」の戦略の一環として、事業譲渡が活用された好例と言えるでしょう。
(情報引用元:コクヨ株式会社「Fellowesブランド製品の販売を開始します」)
事例2:小田急グループによるベーカリー事業「HOKUO」の譲渡
- 譲渡企業: 株式会社北欧トーキョー(小田急グループ)
- 譲受企業: 株式会社ドンク(「ドンク」「ミニワン」などを展開)
- 対象事業: ベーカリー「HOKUO」の店舗運営事業
- 譲渡日:2021年12月21日
小田急電鉄の完全子会社である北欧トーキョーは、長年首都圏で展開してきたベーカリーHOKUOの事業を、同業大手のドンクに譲渡しました。
小田急グループは、経営資源を本業である鉄道事業や不動産事業に集中させることを目的としていました。
一方、ドンクにとっては、首都圏の駅前という好立地にある店舗網を一挙に獲得できるという大きなメリットがありました。
この事例は、非中核事業(ノンコア事業)を切り離して本業に集中したい売り手と、事業エリアを拡大したい買い手のニーズが合致し、事業譲渡という形でWin-Winの関係が成立したケースです。
(情報引用元:小田急電鉄株式会社「㈱北欧トーキョーにおける㈱ドンクへの一部事業譲渡、小田急電鉄㈱と㈱ドンクの業務提携に関するお知らせ」)
事例3:富士通ゼネラルによる半導体関連事業の譲渡
- 譲渡企業: 株式会社富士通ゼネラル(連結子会社の富士通ゼネラルエレクトロニクス)
- 譲受企業: L&T Semiconductor Technologies Limited(インド)
- 対象事業: パワーモジュール事業
- 譲渡予定日: 2025年6月23日
空調機などを主力事業とする富士通ゼネラルは、連結子会社が手がけるパワーモジュール(半導体)事業を、インドの半導体企業であるL&T Semiconductor Technologies Limited(LTSCT)へ譲渡することを決定しました。
この事業譲渡は、富士通ゼネラルグループが事業基盤の強化を目指す中で、電子デバイス事業のポートフォリオを見直す「選択と集中」戦略の一環として位置づけられています。自社の経営資源を、より成長が見込める主力事業へ集中させることが主な目的です。
一方、譲受側であるインドのLTSCTにとっては、富士通ゼネラルグループが長年培ってきたパワーモジュール事業の技術やノウハウを獲得することで、自社の製品開発力や市場競争力を強化する狙いがあります。
この事例は、企業が自社のコアコンピタンス(中核的な強み)を見極め、ノンコア事業をその分野でさらなる成長が見込める他社へ譲渡するという、典型的な戦略的事業譲渡です。また、日本企業からインド企業への事業譲渡という、国境を越えたクロスボーダーM&Aの事例としても注目されます。
(情報引用元:株式会社富士通ゼネラル「連結子会社における一部事業の譲渡および特別利益の計上のお知らせ」)
事業譲渡とM&A各手法との違いを理解し、自社の目的に合った選択を

事業譲渡は、M&Aにおける数ある手法の中でも、会社全体の経営権を手放すことなく、ノンコア事業の整理や主力事業への経営資源集中といった経営課題を柔軟に解決するための、極めて有効な戦略的選択肢です。
しかし、この記事で見てきたように、株式譲渡や会社分割など他のM&A手法にもそれぞれ独自のメリット・デメリットが存在し、どの手法が自社に最適かを見極めるには、慎重な検討と専門的な知見が不可欠です。
もし事業譲渡を含むM&Aを少しでも検討されているなら、まずは一度、M&Aの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
専門家は、各手法の違いを深く理解した上で貴社の状況を客観的に分析し、事業譲渡が本当に最善の選択肢なのか、あるいは他の手法がより適しているのかを判断するための、最適なパートナーとなるはずです。
M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。
M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。
専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。
M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。




-2-1-scaled.png)










